90年代前半:ハードの進化でストーリーが体験と分化
『現代ゲーム全史』では、1990年〜2005年の15年を《仮想現実の時代》と区分している。中川氏は、1980年代まではテクノロジーが人々の理想や夢に向かって発展していったのに対して、1990年以降になると「現実そのものがテクノロジーによって変容させられていく時代に入っていく」と語っている。
1990年代前半には、コンシューマゲーム機がファミコンからスーパーファミコンへと進化することで、より詳細なキャラクター表現が可能になった。それに伴い、『ときめきメモリアル』のような恋愛ゲームに代表される、感情移入できるキャラクター表現とゲームとの結びつきが、日本ゲームの大きな特徴の1つになっていった。

(中川氏pdf 8ページ目 1990年代前半より)
中川氏:
遠藤さんご自身は、この時代にはどんなゲームを作られていたのですか?
遠藤氏:
『ファミリーサーキット』【※】を作っていましたね。『ファミリーサーキット』は自分で遊ぶのもおもしろくて。コンピュータの性能が上がるとまた作りたいなぁと思って、(連作しない自分では)珍しく何作も作っていますね。ファミコンで2作、スーファミで1作、それからPCエンジンでも作っているんですけど、それらすべてのプログラムと走行ルーチンを、自分で書いています。このあたりまでは、プログラマーとしてもやっていた時代ですね。
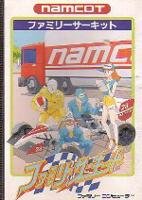
(画像はAmazonより)
※ファミリーサーキット
F1やル・マンなどのカーレースをモチーフにした、トップビューのレーシングゲーム。ギヤ比やハンドリングなど、マシンのセッティングをプレイヤー自身で細かく設定できる。1988年にファミコンで『ファミリーサーキット』が発売されたのに続き、1991年に『ファミリーサーキット’91』とPCエンジンの『ワールドサーキット』、1994年にスーパーファミコンで『スーパーファミリーサーキット』が発売された。
中川氏:
この時代になってくると、物語そのものを直接的に描けるようになってきましたから、遠藤さんとしてはナラティブをどう進めるといったことは考えましたか?
遠藤氏:
今で言うところのデジタルコミックみたいなものにもトライしています。あとはエンディングが変わるマルチエンディングじゃなくて、途中の過程がまるごと変わってしまうマルチストーリーにトライしてみたくて。組み合わせによって48種類のストーリーができて【※】、1回のプレイを1時間ぐらいにして、何回も遊んでもらおうと思ったんだけど、1回エンディングを見ちゃうともう1回はプレイしてくれないっていうのがよくわかりましたね。
でも逆に、48種類のストーリーがあるってことにものすごく惹かれて、すべてを見てやるってプレイしてくれた人も多くて、そういう意味では乖離していきましたね。ナラティブが好きな人と、そうでない人がいるんだなって。
※48種類のストーリーができて
1994年に発売されたスーパーファミコン用アドベンチャーゲーム『ザ・ブルークリスタルロッド』のこと。ブルークリスタルロッドを奪還してドルアーガの塔から脱出した主人公ギルが、天界へと向かう道程によって、ストーリーが全48種類に変化する。
中川氏:
ちょうどこの時期に、ナラティブが好きな人と、ストーリーに寄っていかない体験の創発性が好きな人に分化していったんじゃないかと思うんです。その象徴が、チュンソフトが作った2つのシリーズ、つまり『弟切草』【※1】に始まるサウンドノベルと、『不思議のダンジョン』【※2】だったんじゃないかと。『ドラクエ』にあった両者のミックス感が、それぞれの方向へと分化していったんじゃないかと思うんです。
※1 弟切草
1992年にチュンソフトより発売されたゲームソフト。サウンドノベルというジャンルを初めて確立した作品とされる。また、「バイオ」以前のコンシューマーにおける、ホラーゲームの先駆的作品の一つでもある。
※2 不思議のダンジョン
スパイク・チュンソフトおよび同社の前身であるチュンソフトが開発、もしくはタイトル使用許諾をしたローグライクゲームのタイトルに使われるフレーズ。1993年に発売された『トルネコの大冒険 不思議のダンジョン』が、「不思議のダンジョン」を冠した最初の作品となった。
遠藤氏:
そうですね。あとはこの時期に、『ストリートファイターII』をはじめとする対戦格闘ゲームも出てきて。デジタルゲームは基本的に、1人遊びであるというところに存在価値があったんだけど、ここに来て2人対戦というそれ以前のゲームに戻っている。対戦というのは原始的なおもしろさでもあるので、そちらの方向もこれ以後ずっと残るんですね。
中川氏:
1人遊びと多人数遊びの間を揺れ動きながら、ゲーム史が進んできている。
遠藤氏:
そうですね。技術がそれを可能にするところもあって。たとえばチーム戦みたいなもの、今のMOBA【※】みたいなものは、ネット環境も整っていて、CPUパワーも十分にあるっていう技術のバックアップがあって、初めて実現できるものですから。
※MOBA マルチプレイ・オンライン・バトル・アリーナの頭文字を取った略称。リアルタイムストラテジー(RTS)から派生したジャンルで、個々のキャラクターを操作する複数のプレイヤーがチームを組んで、2チームでオンライン対戦を繰り広げる。
 |
90年代後半:ゲーム業界に異業種の参入を誘発したプレステ
1990年代後半には、プレイステーションをはじめとする3Dポリゴン表示を駆使するゲーム機が主流となり、ゲームの表現に大きな変化が起こっている。また同時に、CD-ROMメディアが主流となることでコンテンツの流通形態も変化し、クリエイターがより小リスクでいろいろなものを作れる時代になったほか、異業種のクリエイターも参入しやすくなった。

(中川氏pdf 9ページ目 1990年代後半より)
遠藤氏:
(CD-ROMという大容量メディアが出てきたことで)アクションにこだわっている任天堂と、マス媒体で勝負しようというソニーのあいだで乖離が起こったんですね。初代プレイステーションにはモーションJPEGという機能が入っていて、ムービーを上手く使えたんです。それもあって、当時のパソコンゲームを作っていた人たちもPSに来たし、CGを作っていた人たちもPSに来た。
中川氏:
異業種の参入メディアだったんですよね、プレイステーションは。遠藤さんがもともと演劇や映像でやられていたような感性を持った人たちが、ここでより多く入ってくることができた。その一方で任天堂は、ニンテンドー64の『ゼルダの伝説』みたいに、3Dを使ったアクションを追求していて。3Dを操作していく上では、それまでの2Dとはまったく違うインターフェースが必要になるわけじゃないですか。今の標準となる基盤が、この時代に築かれた。
遠藤氏:
この時期に、アーケードで『ダンスダンスレボリューション』(以下、『DDR』)が登場していますけど、ここではその後につながる、まったく新しい文化が生まれているんです。つまり“魅せる”楽しみと、人のプレイを“見る”楽しみですよね。『DDR』は僕も練習しましたね。後ろを向いたまま踏めるようになるまでは練習しました。しかも(1Pと2Pを)両方使いながらやるっていう。なぜそんなことをやるのかというと、カッコイイからですけど(笑)。
中川氏:
アーケード空間の使い方が変わったのがこの時期ですよね。プリクラや『電車でGO!』が出てきたのもこの時期だし。コンシューマがプレイステーションの登場で変化するのに呼応して、アーケードもカジュアル化や劇場化が進んでいく。
遠藤氏:
あとはインターフェースですよね。そのゲーム固有のインターフェースが作れるというところに、(アーケードの価値を)持っていくわけです。

(Image by JeffTheGamrWIKI. Licensed under the terms of the cc-by-4.0.)
ここで中沢新一が乱入! 『ポケモン』に衝撃を受けた理由
中川氏:
それからこの時代で忘れてはいけないのは、こういう3Dの時代とかがやってきている一方で、『ポケットモンスター』が出てきていることです。『赤・緑』の発売が1996年ですから、初代PSの2年後ですよ。

(画像はポケットモンスターオフィシャルサイトより)
遠藤氏:
当時は『ポケモン』というタイトルが流行っていることを、ゲーム業界の関係者はぜんぜん知らなかったんですよ。子どもたちの口コミだけでしかなくて。ホントに『ポケモン』のおかげで日本の携帯ゲーム機は伸びていったし、これがなければゲームボーイというハードはたぶん死んでいたでしょうね。
中川氏:
僕は1974年生まれのファミコン世代なんですけど、この時は大学生になっていたので、『ポケモン』はまったく視野に入っていなかったですね。それまでは僕のようなファミコン世代が、ゲームの市場をずっと引っ張ってきたんだけど、『ポケモン』が登場したことで、ファミコン世代ではない新世代が初めて大きなパワーを発揮しだした。
そんなふうに、僕らファミコン世代には視野に入っていなかった『ポケモン』のインパクトを、その当時に正しく評価することのできた方が、人類学者の中沢新一先生なんです。
ここで、客席に座っていた中沢新一氏が、中川氏に誘われて登壇することに。『ポケモン』の話題に入る前に、中沢氏がゲームに関心を持つきっかけともなった、遠藤氏の『ゼビウス』についての話題から語り始めた。

中沢新一氏(以下、中沢氏):
『ゼビウス』が登場してきた時は、本当に衝撃だったんですよ。
遠藤氏:
『ゼビウス』の当時はまだ、「子どもの遊びにいい大人が」って言われていた時代でしたから。あの当時に「ゲームは素晴らしいものだ」と、中沢先生のような権威のある学者さんが言ってくれたおかげで、僕らはすごくラクになったんです。
中沢氏:
じつは僕は最初、『ゼビウス』を知らなかったんですよ。細野晴臣さん【※】が「スゴいものがあるんだ」って言って、喫茶店に連れて行かれて。そこで初めて『ゼビウス』に出会って、すごく衝撃を受けたんですね。
※細野晴臣
1980年代前半に一大ブームを巻き起こしたテクノポップバンド、イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)の元メンバー。その後も音楽活動だけに留まらず、俳優や文筆など幅広い活躍を続けている。YMOの活動時からビデオゲームに関心が深く、1984年に同氏がプロデュースした『VIDEO GAME MUSIC』は、『ゼビウス』をはじめとするナムコ(当時)のゲーム音楽を収録した、日本初のゲームミュージック・サウンドトラックアルバムである。
遠藤氏:
細野さんがまた、『ゼビウス』が上手かったんですよね。
中沢氏:
「これが武道館だよ」とか言いながら。
遠藤氏:
アンドアジェネシスのことを、細野さんは“武道館”って呼ぶんです(笑)。
中沢氏:
それから細野さんと一緒に、『ゼビウス』にハマりにハマったんですね。この『ゼビウス』みたいなゲームの世界は、表現の中でもそれまでに語られていなかった領域を作っているし、語られたことのない物語の喚起性を持っている。これをどうやって言葉にすればいいのかというのが、僕にとってすごく挑戦だったんですね。それで『ゼビウス』論を書いて。タイトルがちょっとしゃれてたでしょ。
中川氏:
「ゲームフリークはバグと戯れる」。
中沢氏:
あれは細野さんの言葉だったんですけど。
それから時が流れて。僕は小学館の『コロコロコミック』の編集者と友達だったんですけど、「中沢さん、これ知ってますか?」って見せてもらったのが、『ポケモン』だったんですね。その時はまだ、人気が爆発はしていなかったんですよ。小学生の間では大人気だけど、世間はそれを知らなかったんです。
「これを知らないと小学生文化は語れませんよ」って、『コロコロコミック』の編集者に言われて。僕は小学生文化を語るつもりは、ぜんぜんなかったんですけど(笑)。でもそれですぐ、『ポケモン』を買いに走って、やってみたらめちゃくちゃハマったんですよ。
そのハマってる最中に、大学のゼミの学生を連れて、野外レクチャーで多摩川に行ったんですね。そうしたら小学生が、網でザリガニかなんかを捕りながら、片手でゲームボーイを扱ってるんです。『ポケモン』を野外に持ってきて、片手でザリガニを捕りながら、もう一方の手ではゲームの中でニョロモとかを捕まえているんですよ。
そのゲームと現実との行ったり来たりを、小学生がものすごく楽しんでやっているというのに、僕はものすごく衝撃を受けて。これは今に、現実とバーチャルっていうのかな、この2つの世界の入れ子状態というか、はめ込みみたいなことが起こってきて、現実の構造自体が変わってくるんだろうなと、その時に思ったんですね。
中川氏:
まさに今、『ポケモンGO』で出現する風景みたいなものが、原点の『ポケモン』の時点で、しかもそのようにプリミティブな形で実現していたと。
中沢氏:
そうです。そんなわけで僕は今、『ポケモンGO』もたいへんおもしろく遊びました。ただ、ロールプレイングの要素とARの要素が上手く結合するには、まだちょっと時間がかかるなと思っています。まだ未発達ですけど、これからどんどんと変わっていくと思います。
僕自身は、『ポケモンGO』でまた『ポケモン』に火がついちゃって、今は『サン・ムーン』に夢中なんですよ(笑)。

(画像は『Pokémon GO』の公式サイトより)
遠藤氏:
それは日本人として、いい傾向です。日本人は通常の『ポケモン』でも十分に楽しめるんですけど、海外の方は(ゲーム画面を見ても)それと現実とのリンケージがないんですね。ARで「ここにいるよ」っていう状態を実際に見せてあげないと、興奮できないんです。なので『ポケモンGO』でそれを実際に見せてあげると、海外ではあんなに殺到するんですよ。
中沢氏:
日本人は仮想現実と現実の間に、敷居がそんなにないですから。だから僕はむしろ、ゲームボーイを持ちながらザリガニを捕っていた子どもたちの、あの中から何かが出てくるという予感が、いまだにしているんですよね。
サプライズ出演の短い時間ではあったが、さすがに『ポケモン』の真価をいち早く見抜いた人物だけあって、中沢氏の言葉は非常に奥行きのあるものだった。また、最新タイトルである『ポケモンGO』や『サン・ムーン』をプレイしているというだけに、中沢氏による新たなゲーム論の登場にも期待したいところだ。
 |


































