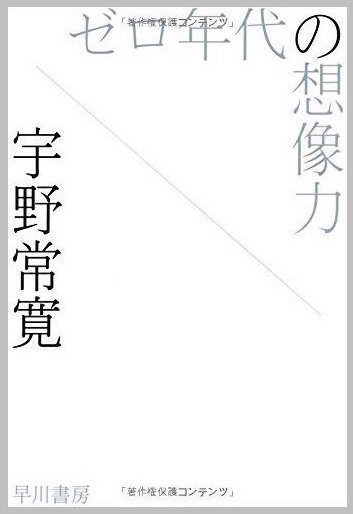ゲーム批評史<2000年代後半>:コンテンツそのものの批評から、現象としてのゲーム批評に
――だんだん読者の記憶に新しい時代に入ってきたところですが……では、2000年代に入ってオンラインゲームが出てきて、古典的な意味での批評モデルが通用しなくなったときに、ゲーム語りはどうなっていったのでしょうか。
中川氏:
僕が『現代ゲーム全史』を執筆する直接のきっかけになったのは、2010年に出版された批評誌『PLANETS VOL.07』の「ゲーム批評の三角形(トライフォース)」という特集なんですが、その三角形とはアーキテクチャ、コンテンツ、コミュニケーションなんです。

この特集をやることになった背景としては、濱野智史さん【※1】が『アーキテクチャの生態系』を出版して、情報環境批評のある種のスタンダードを打ち出したということが、大きかったんです。その一方で、基本的にはゲームを対象にしていない宇野常寛さん【※2】の『ゼロ年代の想像力』があり、こちらは文芸批評的なスタイルのコンテンツ論ですよね。
社会学者・アイドルプロデューサー。2008年に発表した『アーキテクチャの生態系』で、さまざまなネットサービスをアーキテクチャの観点から社会的に分析し、高い注目を集めた。またアイドルに対する論評も、積極的に行っている。
画像は『アーキテクチャの生態系: 情報環境はいかに設計されてきたか(文庫版)』(2015・筑摩書房)
評論家。2008年に発表した『ゼロ年代の想像力』で、文学やアニメからテレビドラマまで、ゼロ年代に生まれた物語の想像力を幅広く論じて、一躍脚光を浴びた。ラジオやテレビでも活躍中。
画像は『ゼロ年代の想像力(文庫版)』(2011・早川書房)
――それは、どういう特徴を持っていたのでしょうか?
中川氏:
そもそも現代では、古典的な文芸批評の方法としてよくあるように、作品を通じて表現される作家の内面の問題を社会全体の問題として押し広げて論ずるには、コンテンツ分野全体が小さなジャンルごとに島宇宙化し、あまりにも個別的なものになりすぎてしまっているんです。
例えば、かつてであれば、国民国家の比喩なり縮図なりとして私小説を読むといったことがそこそこ説得力を持ちえたけれども、たとえばライトノベルの世界で同じ深読みの仕方をしようとするのはナンセンスですよね。
――それはまあ、そうですよね。
中川氏:
宇野さんは様々なサブカルチャー分野を横断して膨大なサンプルを集めながら共通の時代的動向を炙り出すことで、コンテンツ論が陥りつつあった限界を突破しようとした。対して、ITシステムを語ることが社会を語ることと近しいという点に注目したのが、濱野さんのアーキテクチャ論です。
このコンテンツ論とアーキテクチャ論が両輪となって、ゼロ年代批評というものが推進されてきた時に、ゲームはその両者が渾然一体となっていることが、改めて見えてきた。そこから『現代ゲーム全史』につながる新たなゲームの批評の語り口みたいなものが見いだせたわけです。
そして『PLANETS VOL.07』の「ゲーム批評の三角形(トライフォース) 」ではもう1つ、コミュニケーション批評という語り口がありました。
――たしかに『モンスターハンター』のようなゲームは、従来までの批評ではなくて、コミュニケーション批評でしか語ることのできないものですよね。
中川氏:
PSPの『モンスターハンターポータブル』のブームでは、携帯型ゲーム機の進歩によって協力型のマルチプレイアクションが日常世界に持ち出せるようになったんです。そのときに、小さなコミュニティにおけるコミュニケーションツールとしての性格に焦点が当たり、のちのソーシャルゲームへの流れを決定づける潮流になりました。
そのような作品に対しては、コミュニケーション環境のテクノロジーが作り出す社会のあり方そのものがおもしろいという、ちょっと引いた形での語りしかできなかったわけです。

画像はプレイステーション オフィシャルサイトより
――RPGがストーリードリブンのゲームだとしたら、『モンハン』はコミュニケーションドリブンのゲームですからね。ただ、そういう意味では、ソーシャルゲームはどうですか。盛んに語られていると思うのですが、その中心を占めているのはビジネス批評が中心ですよね。
中川氏:
ビジネスモデル批評というのは、アーキテクチャ批評の延長線上ではあるんですけど、それはつまり権力論です。どのようにして人を動かすのかという。
ゲームとしては正直さほどの深みもないし、ましてや掘り下げる意味のある作家性や物語性などは皆無なんだけど、コンテンツに没入させるのではなく身体的なインターフェース設計で中毒性を生んだり、射倖性を喚起して課金させるための人間工学的なシステムとしては、すごくよくできている。
だからソーシャルゲームの登場において、“遊び”が“実用”に呑み込まれていったとも言えるんですよ。いかにユーザーを楽しませるかではなくて、いかに利益を効率よく回収するかのサプライヤー側のノウハウが、より重視されるという意味において。
――実際、ソーシャルゲームというのは名前に反して、もともとはソーシャルな要素を入れることでゲームが遊ばれるはずだったのに、まさに「人間工学」を突き詰める中で、フレンド登録をはじめとするソーシャルな要素が全部なくなりましたよね。
中川氏:
そう、「ソーシャル」の名に反して、むしろSNSの普及で過剰になった人間同士の関わりの煩わしさを自動的なゲームシステムに置き換えている感じがあるわけですね。
だって、最初は『怪盗ロワイヤル』みたいにPvP要素がウリだったんですよ。でも、それでギスギスするのもイヤだから、カードバトル型になった【※】『探検ドリランド』のあたりで、協力だけにしようとなった。さらにスマホ時代の『パズル&ドラゴンズ』とかになると、強いプレイヤーからレベルの高いキャラを1人借りてくるだけでしかなくなってしまった(笑)。
※当初、ドリランドは現在とは全く違う、穴を掘り進める別のゲームだった。
――一方で、ソーシャルゲームの流行と並行して、動画サイトでは『マインクラフト』やホラーゲームの実況で、ゲームについての語り自体がコンテンツになってしまうという現象が起きました。
中川氏:
ゲーム実況に関しては、最初のほうに話した『ゲームセンターあらし』的なものだと思うんですよ。
ゲーム体験を物語化する『ゲームセンターあらし』が、コンテンツ批評に取って代わられていったのがパッケージゲームの時代だったのに対して、ゲームがパッケージングから解放された2000年代後半からは、ちょうど逆向きの変化が起こったという。
――ああ、なるほど。1対1の方に閉じ続けていたゲームというメディアが、ゲーム実況で再びみんなと盛り上がりを共有するものになった感じはありますね。その結果が、まさに“あらし”のように、プレイヤーのゲームの楽しみ方そのものが、コンテンツになる流れであった、と。
中川氏:
ただ、個別的に実況者がそのクラスタの中だけで盛り上がっていく流れができると、それを社会に対して意味のある形で語っていくには、そういうことが起こりうるアーキテクチャ環境とか状況そのものを解説する以外にないですよね。
――それはネットである以上、仕方ないというか……。では、これからのゲーム批評は、コンテンツそのものの批評から、現象の批評になっていくと?
中川氏:
そうならざるを得ないですよね。もちろん、コンテンツ批評が成り立つゲーム作品も、たくさんありますよ。
例えば、買い切り型のダウンロード販売で流通するパソコンやコンシューマー機向けのインディーズゲームなどは、昔ながらの作家性の強い作品として1つのシェアをなしていると思います。でもそれは、広く一般に向けたものというよりは、あくまでニッチなゲーム愛好者のためのものですよね。
――基本は嗜好性がハッキリしたニッチ分野で文脈遊びをしている作品が多くて、批評が扱うタイプの作家性とはむしろ真逆の作品が多い印象ですよね。では、洋ゲーのAAAタイトルはどうでしょう? ピクサーやマーベルが映画において最先端の映像表現に誰よりも意欲的に挑戦したり、物語でグローバル社会の課題に誠実に向き合っているようなことは、AAAタイトルでも起きていると思うんですが。
中川氏:
洋ゲーのAAAタイトルは基本的に、規格化された3Dエンジンによってリアルタイムに進行する現実そのものに近い体験性を志向し続けていますよね。
『コール オブ デューティ』のようなFPSにせよ、『グランド・セフト・オート』のようなオープンワールド型のクライムアクションにせよ、あるいは『アンチャーテッド』とか『ラスト・オブ・アス』のようなストーリー主導型のアクションアドベンチャーにせよ、一緒だと思います。
その結果、各シリーズとも2D時代には見た目的にもゲームシステム的にも別物だったけど、シリーズが進むにつれて、どれも似たような操作系のインターフェースとフォトリアリスティックな画面構成になっていってるという流れがあって、それが日本のゲームのファンには食指が動きにくい部分になっているという印象です。

画像はプレイステーションオフィシャルサイトより
――ただ、その辺は日本のゲーム語りが、ゲームシステムの新規性から語り始めるのに慣れすぎているのもある気がするんです。だって、最近の洋ゲーのAAAタイトルって、基本的には同じゲームシステムの中で、あくまで“ストーリー”や“体験のあり方”で勝負をしているわけじゃないですか。これって、いわば映画などに近いコンテンツのありようですよね。
中川氏:
はい。そこは3Dのゲームエンジンという形で、だからこそゲームシステムの標準フォーマット化に成功しているわけですね。あたかもスクリーンというフォーマットが自明化している「映画」のように。ゆえに、日本では2000年代初頭に途絶えてしまった“ 映画的”ゲームの系譜が生きていて、それぞれのタイトルの中でどんな体験ができるかという、純粋にコンテンツの中身こそを作品のアイデンティティとして語れる環境が整っている。
したがって、洋ゲーのAAAタイトルこそ、むしろ旧フォーマットのゲーム批評で語られるべきなのかもしれませんね。
――そういう意味では、少し前になりますが、徳岡正肇さんの『S.T.A.L.K.E.R.』についての批評がありましたよね。チェルノブイリのすぐ横であのゲームが作られた意味を語っていて、まさに正統派のコンテンツ批評として成立していると思います。
中川氏:
なるほど、これは素晴らしいですね。コンテンツメディアとしてのゲームの表現特性は、「(擬似)体験をもって(他者の)体験を伝える」ということだと思うんですが、日本のゲームでは1990年代後半から2000年代初頭にかけて桝田省治さんや芝村裕吏さんが『俺の屍を越えてゆけ』や『高機動幻想ガンパレード・マーチ』で追求していた可能性が、旧ソ連圏を含む欧米圏にあっては、きわめてダイレクトなかたちで発展しているさまが分かりました。
三次元空間に生きる現実の人間の身体構造の共通性に即して体験同士を変換することで、こうした地域固有のローカリティに即したリアリスティックな主題も文字や映像を超えた次元で伝えられるという可能性を感じます。意欲あるユーザーに対しては。
ただ、やっぱりこうした濃密なゲーム体験を紐解いていくような批評は、自分でも書きたいし粛々と浸透してほしいと思う反面、現在の日本で現実的に受け止めてもらうのは厳しかろうなという気もします。
なにせ1本あたりのプレイ時間に膨大な時間がかかるから共通体験になりにくいし、無制約な行動の自由度とか暴力をめぐる主題が前面化しがちなフォーマット性とかも、やはり欧米的なコンテクストに根ざしたものだと思いますから。
なので異文化研究としての意味は大きいと思いますが、文化の垣根を超えてよりグローバルな世界の動向とリンクするのは、もっと別のタイプのゲームなのではないかなという気がします。
 |