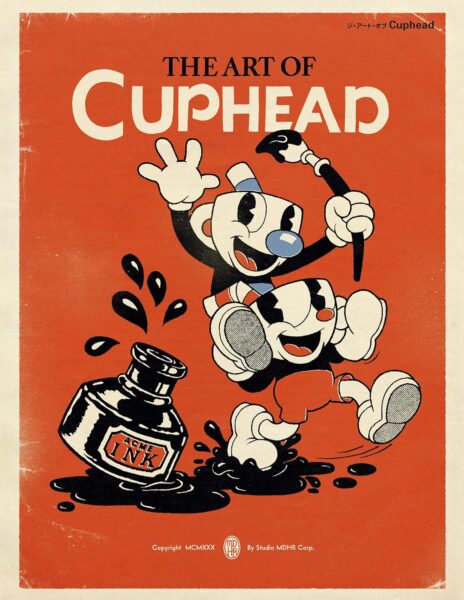2017年2月にコーエーテクモウェーブから発表された多機能VR筐体「VR センス」は、近年盛り上がりを見せるVRマシンの中でも、際だってユニークな存在だ。

歴史シミュレーションゲームで知られるコーエーテクモが独自のVRマシンを、しかもアミューズメント向けの筐体をリリースするというのも驚きだが、我々が特に興味を抱いたのは、本機の開発経緯だ。
このVR センスはなんと、コーエーテクモホールディングスの代表取締役会長である襟川恵子氏が、自ら開発を指揮しているとのこと。
コーエーテクモのゲーム開発といえば、コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)で、シブサワ・コウの名前でも広く知られている襟川陽一氏のイメージが強い。だが実際には、陽一氏の妻でもある恵子氏が、そのパワフルな個性でコーエーテクモグループの経営面を推進し、陽一氏のゲーム開発を強固に支えている。
信長から乙女ゲームまで… シブサワ・コウとその妻が語るコーエー立志伝 「世界初ばかりだとユーザーに怒られた(笑)」
※電ファミでは以前、襟川夫妻が同席するインタビューで、お二人の軌跡を伺った。その際、恵子氏の強い信念が、世界で初めて「女性向けゲーム」のジャンルを切り開いたという事実を知ることができた。
そんな襟川恵子氏が今なぜ、VR筐体の開発を自ら指揮しているのだろうか? しかもVR センスの発表会で恵子氏自身が語ったところによると、本機の開発にあたっては夫の陽一氏をはじめ、コーエーテクモの役員たちが反対するなか、恵子氏はそれを押し切ってプロジェクトを推進したのだという。恵子氏はVRとこの筐体に、どんな未来を見ているのだろうか?
そこで今回は、襟川恵子氏がVRに対してどのような情熱を持って取り組んでいるのか、直接伺ってみることにした……のだが、恵子氏の語る話題はVRだけに留まらず、e-Sportsから世界平和まで、非常に多岐に渡るものとなった。
前回のインタビューがコーエーテクモのこれまでの歩みを明らかにするものだとすれば、今回は現在進行形で進んでいる、襟川恵子氏の野望を語ってもらったものだと言えるだろう。
聞き手/TAITAI、伊藤誠之介
文/伊藤誠之介
カメラ/増田雄介
「今すぐVRをやるべきだと思ったんです」
――今回は、襟川さんがVRにすごく力を入れられていると伺って、ぜひその理由をお聞きしたかったんです。技術者ではない襟川さんが、自ら開発を指揮されるほどVRに情熱を持って取り組まれているのは、いったいなぜなのでしょうか?
襟川恵子氏(以下、襟川氏):
2016年の4月ぐらいでしょうか、たまたまVRのお話を伺ったんです。そうしたら他のゲームメーカーのみなさんが、かなり研究してらっしゃるじゃないですか。セガさんもバンダイナムコさんも、何年間も研究されていて。

私は今から20年ぐらい前に、コンピュータグラフィックスのSIGGRAPH(シーグラフ)【※1】でVRを見て、その時にこれはぜひやりたいと思っていたんです。そして3年ぐらい前でしたか、スマホに箱をくっつけてVRの世界を体験できるというもの【※2】を見て、感動しました。
だから直感的に、今すぐVRをやるべきだと思ったんです。なぜならテクモはかつてゲームの筐体も制作していて、今年は設立50周年を迎えた節目ですから。

(画像はAmazonより)
※1 SIGGRAPH
アメリカに本部を置くACM (Association for Computing Machinery) が主催する、コンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術の国際会議。技術論文やソフトウェアの発表だけでなく、ゲームや映画のCGムービーなども多数出展されている。
――とはいえコーエーテクモさんも、2015年9月の東京ゲームショウでは、PlayStation VR用の技術デモを発表されていますよね?
襟川氏:
はい。当社もSIEさんがVRを発売されるので、『真・三國無双7 VR Demo』【※1】を作っていました。それと『DEAD OR ALIVE Xtreme 3』【※2】ね(笑)。
※1 真・三國無双7 VR Demo(画像左)……「真・三國無双」シリーズより、『真・三國無双7』ベースに製作された、VRで戦場の臨場感を体感できるデモコンテンツ。2015年の東京ゲームショウにて公開された。
※2 DEAD OR ALIVE Xtreme 3(画像右)……2016年にコーエーテクモゲームスより発売された、PlayStation 4・PlayStation Vita用バカンスゲーム。PS4版では、「やわらかエンジン2.0」が搭載されることで、日焼けのあと、水着の着崩れ、水に塗れた肌などが、よりリアルに描写される。
当社は、昔から新しいものにチャレンジしていました。PCゲームに色々なジャンルの音楽を入れたり、ボーカルソングを入れたり。ネットワークゲームも他社さんがまだ参入していない頃から、社内LANを通して研究していました。
海外にはすでにOculus Rift(オキュラス・リフト)があって、これからPlayStation VRも台数が出てくれば、そのうちに必ずハードは安くなって、普及するはずだと。そうなる前に、VRに参入しなければと思ったんです。競争が激しくなってから始めると、コスト増になってしまいますから。
――その時点で襟川さんとしては、これからVRが普及するという自信を持っていたわけですか?
襟川氏:
確固たる自信なんかありませんよ。直感ですね。以前にネオロマンス【※1】を始めた時も、「女性のゲーマーなんかいないのに、よくそんな市場もないところから始めましたよね」と、御社の佐藤(辰男)前会長【※2】に言われました。

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※1 ネオロマンス
「ネオロマンスゲーム」は、コーエーテクモが開発する女性向け恋愛ゲームのシリーズ名。襟川恵子氏が自ら開発を指揮して1994年に誕生した、世界初の女性向け恋愛ゲーム『アンジェリーク』が、その第1作となっている。「ネオロマンスゲーム」誕生の経緯については、前回のインタビューで襟川氏自身が詳しく語っている。
でも、世の中の半分は女性だし、自分たちが市場を創ればよいと考えていました。だからVR センスも、ネオロマンスを作った時と同じような感覚ですね。VRを見た時に自分が面白いなと思えば、その発展系としてのビジネスが見えてきますから。
※2 佐藤(辰男)前会長
カドカワ取締役相談役、学校法人角川ドワンゴ学園理事長。『コンプティーク』編集長などを経て、1992年にメディアワークス(現アスキー・メディアワークス)を設立。2015年6月より2017年6月まで、KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ)の代表取締役会長を務めた。襟川陽一・恵子夫妻との交流は長く、前回のインタビューにも同席している。
――ちなみに、襟川さんご自身が本格的なVRを実際に体験されたのは、いつ頃だったのでしょうか?
襟川氏:
初めて触ったのは、2016年6月のE3【※1】ですね。SIEさんのブースで3タイトルと、カプコンさんが『バイオハザード7 レジデントイービル』【※2】をPlayStation VRで作っているというので、遊ばせていただいたんです。

(画像はCAPCOM公式サイトより)
館の上り下りにはしごを使うようになっていて、自分の手でつかまりながら降りていくのですが、画面にはCGの手が出てきてあたかも自分の手であるように錯覚できます。着地すると急にゾンビが覆いかぶさってきて、「ギャー!」って、もう、かぶっているヘッドセットを取って投げ捨てました(笑)。「これはスゴい!」と思いましたね。
 |
※1 E3
Electronic Entertainment Expo.の略称。毎年5月中旬から6月中旬ころ数日間アメリカで開催される、世界最大のコンピューターゲーム関連の見本市。
役員たちから一斉に反対された
――襟川さんがVRに将来性を感じているのはよくわかりましたが、VR センスの開発を襟川さんご自身が指揮されているのは、なぜなんでしょうか?
襟川氏:
経営会議の時に「VRをぜひやってみたい」と言ったら、役員たちから一斉に反対されたんです。「どこもうまく上手くいってない」、「まだビジネスが確立されていない」と。
昨今、“働き方改革”【※】というものが現れていますが、社長の襟川(陽一氏)は遵法精神が高いですから、即取り組みました。その結果、社員が残業をしづらい環境となってしまった。そうした会社の勤務体制を変革中でしたので、わけのわからない仕事なんかやっている場合ではないと考えたんでしょう。

(Photo by Getty Images)
というわけで、社長の襟川(陽一氏)は私の部下でありながら「VRをやるのなら、コーエーテクモゲームスの人間は使うな」と言うんです。
でもね、そんなことを言われると、逆に「よーし、絶対なんとかする」と思うんですよね(笑)。
コーエーテクモグループの中には、パチンコ・パチスロの開発や、アミューズメント施設の運営を行っている、コーエーテクモウェーブという会社があるんです。ここならコーエーテクモゲームスじゃないわけですから、VRの開発ができると。コーエーテクモゲームスと違い、社員の残業時間を調べたらほとんど残業をしない社員が何人もいました。
――なるほど、子会社とはいえ別の会社ですからね(笑)。
襟川氏:
そこで(コーエーテクモウェーブ代表取締役)社長の阪口(一芳氏)に、「2〜3人VR センスの仕事を割り振りたい」と言いましてね。彼らのほうもまだ若いし、新しいことなので面白いと思ったんじゃないですか。いい調子で乗ってきてくれました。
しかもゲームだけを作るのではなくて、ハードも一緒に作らないといけませんから。昔一緒に仕事をしたことのある社員で、ソフトもハードもできる人が技術支援部にいたんです。この人も引っ張り込んで、たった3〜4人で作り始めたんですよ。
五感を刺激するVRで楽しさ倍増
――VR センスでもう1つ興味があったのは、ハードのことなんです。VRに本格的に取り組むにあたって、PlayStation VRやOculus Riftといった既存のハードでソフトを開発するだけではなく、なぜ専用の筐体まで作ろうと思われたのですか?
襟川氏:
VRというのは、この世にあるまじき世界を体験するものじゃないですか。でも視覚だけでは、要素が足りないと思ったんです。
映像だけが突出しても、今までにない感動を味わえますが、それは視覚だけの体験です。VRも視覚だけじゃなくて、あらゆる感覚の仕掛けがあったほうがより没入感が出る、と考えました。

あれだけ衝撃的な映像を見られるのなら、香りも欲しいし、空気も感じたい。南の島にいるのなら、そよ風とともに花の香りがふわっと来てほしい。視覚だけじゃなくて、五感全部を刺激するようなものができたら楽しさも倍増するだろうと、確信していました。
VRをやろうと思ってから、いろいろとチェックしてみたんですけれど、椅子が動くとか、風を感じるとか、そういうものはありましたけど、五感全部に訴えるというものはなかったのです。
――たしかに、そうした個々の要素を1つ、2つと採り入れているものはありますが、それら全ての要素をまとめて、汎用の筐体に備えているものはまだないと思います。でも他にないからといって、ハードを自分たちで作ろうという発想は、なかなか出てこないと思うんです。
襟川氏:
さっきお話しした、技術支援部にいた社員と、昔よくハードを作っていました。任天堂さんのスーパーファミコンに向けて英語ソフト【※】を作ろうとしたら、肝心の声が出せないじゃないですか。そこで、赤外線を飛ばしてレコーダーと連動させれば声を出せると思いましてね。

自分で回路は組めませんが、社外の方で、すごく優秀な技術者の方と昔仕事をしていて、その方にハードは協力してもらいました。
どういう仕組みかお話ししたら、向こうはだいたい様子がわかるんですよね。「私が作る椅子は前後左右に動くだけじゃなくて、もっと臨場感を出すために、角を上げたりするような動きもしたい」と言うと、彼はすぐわかるんです。
そういう椅子の部分だとか、上から物が落ちてくるだとか、あとは香りとか。本当に何もないところから考えるのは楽しいです。誰も作ったことがないものですし、技術者も社内で一人しか使えない。しょうがないので、ソフトも外部の方にもお願いしました。だって、ゲームスの人間は誰も使うなと言われていますから(笑)。