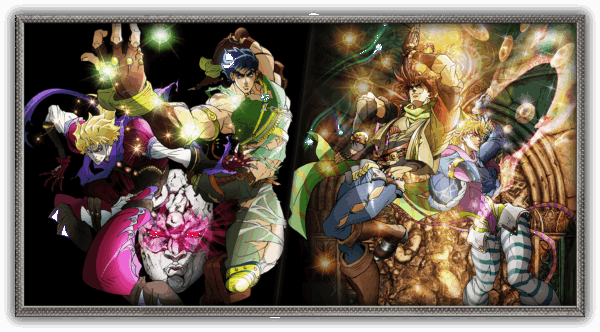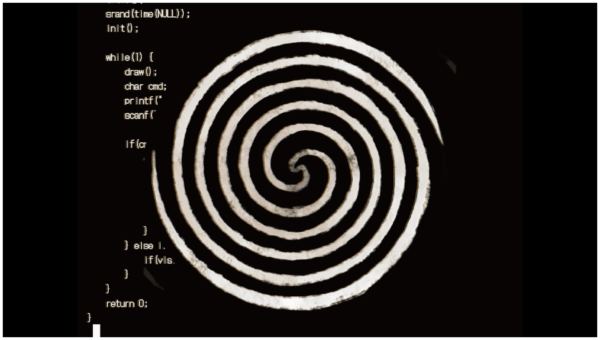『ドラクエ』はいかにして誕生したか
――ところで、いまエニックスの話が出ましたけど、後の『ドラクエ』に繋がるような人間関係はどこから生まれたんですか?
鳥嶋氏:
ちょうど最初のパソコンゲームの特集で、売上につながらなくて困っていたときに、千田さん(※)という人が持ち込み企画を持ってきたの。会ってみたら、100万円を優勝賞金にしたゲームソフトのコンテストをやると言うんだね。
でも、どうもその会社はついこの間まで公営住宅の申し込みの代行業をやっていたらしいんだよ。それがパソコンソフトの問屋卸業に乗り出した頃の、エニックスだった。
※千田幸信
1950年生まれ。スクウェア・エニックス取締役。
エニックスの設立に参画し、同社の常務、専務、副社長を歴任。エニックス時代に堀井雄二から『ドラゴンクエスト』の提案を受け、開発・製作のGOサインを出した人物と知られる。『ドラゴンクエスト』から『ドラゴンクエストVII』まで同シリーズのプロデューサーを担当し、以降もエグゼクティブプロデューサーとしてその名を連ねている。
――ぜんぜん違う業種じゃないですか。
佐藤氏:
そもそも、ゲーム業界自体が今までなかったんだからね。当時は転業組が多かったんです。
鳥嶋氏:
そうそう。
不動産業界でライバルが増えてしまって、とにかく新しいことをやらなきゃいけなくなったから、「なんか儲かるらしいぞ」とパソコンに乗り出したというね。しかし、新宿の雑居ビルでソフトの卸を始めたはいいけど、そこで肝心の売るソフトがないことに、はたと千田さんは困った(笑)。それで彼が思いついたのが、コンテストで作品を募集することだったんだね。
佐藤氏:
それがあの「ゲーム・ホビープログラムコンテスト」でしょ。一位が『森田将棋』の森田さんで、2位が後のスパイクチュンソフトの中村光一さん、佳作に堀井雄二さんが入賞したという。振り返ればむちゃくちゃタイムリーな企画でした。新しい才能が発見されるのを待ってた感じだったね。
――あの伝説の……でも、それがまさかこんなデタラメな経緯で始まっていたとは(笑)。
鳥嶋氏:
でもさ、当時の千田さんはなけなしの100万円を優勝賞金にして、各出版社に協賛をお願いして回っていたんだよ。僕のところに持ち込まれたときには、既にNHKが協賛してたと思う。でも、僕からしたら、パソコン特集の次の展開を考えなきゃいけない時期だったから、もう渡りに船。その場で「ジャンプの独占で協賛をやるから、他の雑誌には一切持ち込まないでくれ」と千田さんに言ったの。
――え、あのコンテストはジャンプが独占で協賛していたんですか。
佐藤氏:
しかも、そうしたら中村光一さんが『ドアドア』を送ってきちゃったわけでしょう。
鳥嶋氏:
あれほどの天才が送ってくるのは想定外だったんだけどね。まあ、僕のところに持ってきた時点で、森田さんは既に仕込みで入っていたけれども。
佐藤氏:
ん? ……となると、もしかして堀井さんが『ラブマッチテニス』(※)を応募したのは鳥嶋さんの仕込みですか?
 |
※『ラブマッチテニス』
堀井雄二氏が「ゲーム・ホビープログラムコンテスト」に応募し、同コンテストの入選プログラム賞を獲得したテニスゲーム。なお、堀井氏は本作を独学で製作したとのこと。
鳥嶋氏:
違うよ(笑)! あれは勝手に応募してたの。
だって、当時の僕はコンテストのゲーム紹介の特集記事を、彼をライターに指名して作ってたんだから。なのに気づいたら本人が佳作で入ってるんだよ。当時は「堀井さん、なんだよそれ!?」だよ。
――カオスですね(笑)。それにしても、エニックスとジャンプの関係がこんな時期からあったとは驚きます。ゲーム業界参入の瞬間から相当に深く関わっていたんですね。
鳥嶋氏:
まあ、そこはジャンプ編集部というよりは、千田さんと僕の信頼関係でやっていたところはあるけどね。
ともかく、そのコンテストで中村光一という天才少年と堀井さんがゲームクリエイターとして世に登場して、二人とも一気にゲームクリエイターとして頭角を現していったわけだよ。
――そうして飛ぶ鳥を落とす勢いだった二人がタッグを組んだところから、ドラゴンクエストが始まった……でも、そこに鳥嶋さんがどう関わったのかはあまり表に出ていないですよね。
鳥嶋氏:
とりあえず先に、中村さんと堀井さんが組むことだけは決まったの。それで当時、僕らの間で流行ってた、『ウィザードリィ』とか『ウルティマ』みたいなRPGを作りたいという話になったんだよね。
でもさ、さっきも言ったけど、『ウィザードリィ』は世界観や戦闘は面白いけど、フィールドやダンジョンは単調で気が滅入る。逆に『ウルティマ』は戦闘は面白くないけど、フィールドやダンジョンは面白いんだよね。それは一緒に徹夜して遊んでた堀井さんも同じ意見だった。それで、僕が「じゃあ、いいとこ取りでやるんでしょ」と確認したら、彼らも「そのつもりです」と言う――そうしたら、僕は編集として動くだけだよね。
実は当時、ジャンプのゲーム特集は、また危うい状況になっていたの。ファミ通のようなゲーム雑誌が攻略情報のための解析部隊を抱えだしていて、僕らのやり方ではもう太刀打ち出来なくなっていた。そこで僕が考えたのは、もうゲームを作るインサイダーになってしまい、その過程を子供たちに誌面で見せていくという手法ね。
――テレビのバラエティ番組なんかがそういうリアリティショーを行うのは今となっては珍しくないですが、それを週刊誌で、しかもゲーム開発で80年代初頭に行っていたというのは驚いてしまいますね……。
鳥嶋氏:
ただ、誌面づくりにはフックが必要じゃない。その一つとして鳥山明さんにキャラ絵を描いてもらったら、それだけで目につくと考えた。それで、鳥山さんに『ドラクエ』のデザインを頼んだの。
――あれ? ということは、鳥山さんを『ドラクエ』のキャラデザに入れたのは、あくまでも雑誌編集者として誌面でのアイキャッチを強めたかったから、ということですか。
鳥嶋氏:
そういうことだね。我ながらよく気の利く雑誌編集者だったと思うよ(笑)。
ただ、僕はそういう企画の頭の部分では関わったけど、以降は関わってないからね。もちろん、開発の途中で撮影するときにスタッフと一緒に顔を出したりはしたけど、もうそこはビシッと一線を引かなきゃいけない。
――でも、鳥嶋さんが中に入って監修することも出来たわけですよね。
鳥嶋氏:
いや、違う。
編集者はそこに線を引いておかないとグダグダになってしまうんですよ。僕はあくまでも雑誌編集者として関わっていたわけで、大事なのはジャンプという雑誌の“読者目線”でいかに記事を作るかなんだね。
そのためには、知った方がいいことと知らない方がいいことがある。中に入ると、つい作り手の目線に立ってしまうでしょ。優れた編集者というのは、どこで線引きをするかを的確に判断できなきゃいけないんです。
――あくまでも誌面の盛り上げの一環というスタンスは崩さなかったわけですね。あと……これはお伺いしてよいことかわからないのですが、『ドラクエ』にはジャンプ編集部と金銭的な契約があったのでしょうか。
鳥嶋氏:
ハッキリ言っておくね。それは全くない。
さっきも言ったけど、僕は編集部の現場でずっと働いてきて、会社の上の方の人間は信用できないと思ったし、好きじゃなかった。だから、いかに集英社を『ドラクエ』に噛ませないかを考えて、集英社を抜く形でエニックスとの契約に持ち込んだんです。
――ええっ!?
佐藤氏:
じゃあ、鳥嶋さんの主張次第では、エニックスが集英社を入れることをOKした可能性があったということ?
鳥嶋氏:
それは大いにあり得たよね。
あのね、もし間に集英社が入っていたら、『ドラクエ』は今みたいに上手く行ってないですよ。それに、鳥山さんの取り分も減るじゃない。当時、鳥山さんにもそのことは丁寧に説明したけど、まあ彼は覚えていないだろうね(笑)。
ただ、代わりにジャンプの巻頭で『ドラクエ』の特集はやったからね。『ドラクエ』の解説本だって集英社で出したでしょ。その辺の約束はエニックスとやっていて、基本的には攻略本は出していたし、集英社にしっかりと本の儲けが転がり込むような組み方をしていたからね。
――それにしても、エニックスとここまで強固な協力関係にあったというのは驚きました。
佐藤氏:
でも、エニックスがゲームだけじゃなくて、漫画雑誌にまで出ていく瞬間があったわけでしょう。鳥嶋さんはどうしたんですか?
鳥嶋氏:
そりゃ「んー」とは思ったけど、まぁ千田さんがやりたいんならどうぞって感じだったよね。
 |
『クロノ・トリガー』は鳥山明のイラストから作った
――その後、ジャンプは『ドラクエ』だけじゃなくて『FF』とも組んでいきましたよね。
鳥嶋氏:
最初に坂口博信(※)と会ったのは『FFIII』のときだったかな。
Vジャンプを立ち上げようとしていた時期に、後に『遊☆戯☆王』の初代カードプロデューサーになる下村聡さん(※※)という人が紹介してくれたんだよ。当時、『FF』は若い人の間で人気になりだしていたけど、全く付き合いがなかったからね。
※坂口博信
1962年生まれ。「ファイナルファンタジー」シリーズを手がけたゲームクリエイターとして知られるが、脚本家・映画監督としても活躍。2001年にゲーム制作会社のミストウォーカーを立ち上げ、現在は同社の代表取締役社長を務める。
※※下村 聡
2011年に“世界で最も販売枚数の多いトレーディングカードゲーム”としてギネス・ワールド・レコーズ社に認定された『遊☆戯☆王』の初代カードプロデューサー。作中に登場するシモン・ムーランというキャラクターの名前は下村氏が由来となっている。
ただ、そのときに坂口が「『FFⅣ』をジャンプで特集してくれ」と持ってきたのは、申し訳ないけど見送ることにした。
僕らのゲームページの方針というのは、単にゲームを見せるというものじゃなかったからね。最初からちゃんと組んで、編集部がキッチリとモノを言える体制にする代わりに誌面に大きく出す。そうしてマーチャンダイジング的な展開まで組んで、大きな流れにしていく。ジャンプでやるからには、そうでないといけないと思っていたんです
――ただ、以前に坂口博信さんにインタビューしたとき、断られるついでに鳥嶋さんにもの凄いダメ出しを食らったと聞いて……(笑)。
鳥嶋氏:
ああ、あったね(笑)。
やっぱり、『FF』はあまりにバランスが悪いんだよ。ドラマは魅力的なのに、ダンジョンが妙に難しかったり、台詞がどうしようもなくクドかったり、とにかく独りよがりな部分が多くて「惜しいなあ」と思っていたんだね。
だから、僕は坂口がやってくるなり初対面で、いかに『FF』がダメかという話を滔々としたの。
――いきなり会議室に呼ばれるなり「敵役に魅力がない」なんて説教されて、坂口さんは「奮起した」と言ってました。
鳥嶋氏:
僕があとで聞いたら、「ものすごく腹が立った」と言ってたけどね(笑)。「呼ばれたから来てみたら、いきなり文句を言われて、何だそりゃ!?」って。
ただ、僕としてはそのくらい坂口と『FF』を語りたかったんです。なぜなら、本気で『FF』を『ドラクエ』と並び立つもう一本にしたかったから。そうなればゲーム業界がどれだけ活性化することか。考えただけでも、ワクワクするじゃない。
――ライバルの存在こそが盛り上げていく。まさにジャンプの発想ですね。
鳥嶋氏:
業界を盛り上げる上で、ライバルの存在というのは重要なんですよ。で、ついでに『FF』もジャンプが扱うようになるわけ(笑)。
佐藤氏:
それにしても、その二つがいまや合併しちゃってるんだよねえ。
鳥嶋氏:
あれは今のゲーム業界をつまらなくした元凶の一つでしょう。やっぱりスクウェアとエニックスは合併するべきではなかったと僕は思ってますね。
――その後、坂口さんとの関係はどうなったのですか?
鳥嶋氏:
不思議なことに気がつけば週一回、飲みに行くようになったんだよ。しかも、坂口の方から誘ってきていたと思う。
佐藤氏:
カチンと来ていたのに(笑)。
――坂口さん、さすがですね。
鳥嶋氏:
いやあ、アイツ、単にMなんじゃないの(笑)?
その後も坂口が『FFⅣ』をジャンプ編集部にプレゼンしに来たら、編集部の連中に「何だ、『ドラクエ』じゃないのか」と立ち去られたという“事件”があって、坂口は深く傷ついていたからね(笑)。結局、『FFIV』もジャンプ誌面では取り上げなかったな。
――ひどい(笑)。
鳥嶋氏:
ただ、『Ⅴ』からは『ドラクエ』のようにタイアップで始めてみたんですよ。
ところが……全くウケないんだね。やっぱり、『ドラクエ』は鳥山さんの絵があるから、それだけでキャッチーだったんですよ。
――まさに、鳥山さんを絡ませた判断は大当たりだったという話だと思いますが、でも当時のFFって、いまも語り継がれる天野喜孝さんの絵だったわけですよね。
鳥嶋氏:
でも、ジャンプではウケなかった。結果『FFV』の売上は前作の2.5倍になったんだけど、最初誌面での人気はもうボロボロ。それで、坂口と話して「このままじゃダメだね」となったの。
そこで僕たちはゲームに映画のスチールの考え方を持ち込んだんだよ。
要するに、始まったばかりで何も出来ていないものを中途半端に見せても仕方ないじゃない。だから、いきなりキービジュアルを作りこんでしまうわけ。「このシーンはこうだ!」というビジュアルを先に見せた上で、後からゲームを作り込んでいく。これが現在に至るゲームの記事の出し方の始まりですよ。
――なんと……。
佐藤氏:
そのキービジュアルというのは、ゲームの画面のことだよね?
 |
鳥嶋氏:
先にボス戦の構図だとか、決めのシーンの絵を仕上げた上で、そこに向けて作っていくんだよ。これを徹底的にやったのが、少し先の話になってしまうけど『クロノ・トリガー』ね。先に鳥山明さんが各シーンの絵を描いて、それに合わせる形でスクウェアがゲーム画面を作って、ゲームはそれを縫うように作っていった。
――そんなやり方で製作されていたとは……。鳥山さんの『クロノ・トリガー』の絵は、今もファンの間で「神がかっている」と語り継がれるものですが、むしろあの絵をインスピレーションにゲームがつくられていたのですか。
鳥嶋氏:
たぶん、もう今の鳥山さんに、あの絵は描けないと思う。彼の才能が全盛期にあったときに、まずは思うままに描いてもらったんだね。
――それって、もはやゲームデザインみたいな話から組み立てていく発想とは、真逆の場所からゲームが作られていますよね。ゲームの反響から先に設計しているというか……。
佐藤氏:
というか、もっと言ってしまうと、当時のジャンプの誌面の中でいかにウケるかという発想からゲームが作られていたということだよね。
鳥嶋氏:
もちろん。でもさ、そもそもタイムテーブルで言うと、発売まで半年くらい誌面を持たせなきゃいけないわけで、期待感を煽るのは必要になるわけでしょう。
佐藤氏:
でも、当時のゲームクリエイターに、そういう発想は難しかっただろうね。「キャッチーに作っていく」とか「ウリの要素をただ足すだけでなくて抜き出していく」みたいな、プロデューサー的なセンスはあまりなかったと思いますよ。
鳥嶋氏:
うん。でも、出版業界の編集者にとっては、「キャッチーな絵で売る」とか「パッケージでどう目を止まらせるか」みたいな考え方は当たり前のことだから。
――そもそも昔のゲームクリエイターって、いわゆる“コンピューターオタク”上がりの、マイナーな世界で活動されていた方が多かったですしね。
鳥嶋氏:
そういう部分については、やっぱり編集者のポジションの人間がダメ出しをしないといけなかったんですよ。
――以前に坂口さんにインタビューしたとき、確かに鳥嶋さんに言われた瞬間はカッとなったけど、家に帰って考えたら「いや、これは正しいぞ」と思えてきたと言ってました。
鳥嶋氏:
結局、クリエイターは自分が作ったものに対する思い入れや愛着があるんですよ。それに、「これは仲間と一緒に作ったものだから」とかつい思っちゃうしね。
でも、僕たち編集の仕事は、読者目線で「そういうクリエイターのエゴをいかに断ち切るか」にあるんです。全ては読者にとって、面白いか面白くないかだけ。だから、勝負は最初にパッと見た瞬間に決まる。キャッチーかキャッチーじゃないか――まずはそれなんですよ。
 |