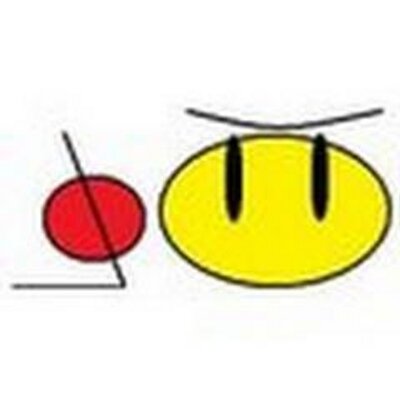カオスだった『ムジュラ』の開発体制
藤澤氏:
もう一つ今日はお伺いしたいことがあって、それは任天堂のものづくりの体制なんですよ。
例えば、今日のために準備してきた資料を読むと、『時のオカリナ』はディレクターが複数いる環境で開発されているという話があって、「そんなこと可能なのか?」と思いまして。
青沼氏:
まあ、『ムジュラの仮面』までは複数人いましたね。その後は、さすがにディレクターは一人になっていきましたけど、今でもあまり守備範囲を「ここからここまで」とは、決めませんね。どうも僕らは「自分はこの枠の中をやれ」って言われると、その枠超えたくなるんですよね。そうでないと最初に全部やりたくなってしまう(笑)。
藤澤氏:
超えるための枠が必要というのもあるでしょうね。
青沼氏:
『時のオカリナ』のときも、僕は色んなデモムービーを設計して、最終的にはフィールドにも手を出しました。次の『ムジュラの仮面』では、最初はダンジョン設計を継続してやる予定だったんですが、色々とあって僕がディレクターをやることになって、一人では不安だったので、オカリナで3Dディレクターをやっていた小泉歓晃【※】を呼んだんです。そうしたら小泉は、「じゃあ、俺のやりたいことをやらせてくれ」というわけです。そこで考えたのがあの「三日間システム」でした。
※小泉歓晃(よしあき)
任天堂 企画制作本部副本部長。『時のオカリナ』ではキャラクターデザインとともに3Dのシステムをディレクション。話題となっている『ムジュラの仮面』では青沼氏とともにディレクターを務め、ゲームの中心街であるクロックタウンを担当。同作の独自性に大きく寄与している。

(画像は3DS版公式サイトより)
藤澤氏:
実は、僕は『ムジュラの仮面』が一番好きなんです。特に、後半にあった「めおとの面」が手に入るところ【※】が、全ての「ゼルダ」含めても一番好きなシーンなんですよ。
ちょうどプレイしたのが、『ドラクエ7』の仕事が一段落して、ゲームにおける面白い物語表現とはなんだろうと悩んでいた時期だったんです。「ゲームにしかできない物語表現がある」というのはよく聞く話ですが、その答えを掴めていなかった自分は、やや懐疑的だったんです。そんなものは、本当にあるのだろうか、と。
ですが、あの「めおとの面」のストーリーで、破滅していく世界の中で、許婚がやって来るのを待つ女性の横でリンクが付き添って待っているシーンを見て、「ああ、これはゲームならではの感動だ」と、感銘を受けたんです。
※「めおとの面」が手に入るところ
『ムジュラの仮面』に登場するシーン。“めおとの面”は、3日間にわたるサブイベント“アンジュとカーフェイ”のクリアで入手できるアイテム。世界の破滅の元凶となるスタルキッドの魔法により子ども化し、さらにある事情で失踪した町長の息子カーフェイと、姿を隠した婚約者の気持ちに不安を覚えるアンジュの仲を、リンクが再び取り持つことでイベントは進んでいく。
青沼氏:
あれは『時のオカリナ』が終わったあとに、スタッフの結婚式に小泉と参列しているときに、「そういえばゲームの中で結婚式ってやってないよね」と話したのがきっかけですね。
藤澤氏:
そういう流れだったんですか。確かに、ちょっと『卒業』っぽいですよね。待っている人と迎えに来る人という。
僕があのシーンで印象的だったのは、それが「ゲームならではの不安」だったことです。色々な手続きを踏んで、あとはクエストをクリアするためには、待つしかない。あの「本当にこれで正しかったのかな」と思いながら待つ感じが、「あの人は来ないんじゃないか」と旦那様を待っているキャラと重なったというか。
青沼氏:
あのシーンは自分たちの世代から出てくる結婚のエピソードの王道を入れつつ、最後の日にギリギリそうなることで、劇的な瞬間を感じて欲しかったんですね。で、待たせる辺りは、意図してやってます。ギリギリまで引っ張っていってね。
藤澤氏:
僕はいいように転がされてましたね(笑)。あと、『ムジュラの仮面』ってNPCが非常に特徴的ですよね。チンクルとかも、すごく挑戦的です。
青沼氏:
『時のオカリナ』で作ったNPCを全て使おうと思ったんです。で、そいつがちょっと変な感じに皆変わってる。まあ、『時のオカリナ』のパロディみたいなものですね。ちょっとおどろおどろしい世界で、ダンジョンもすごく難易度が高いんです。あれは『時のオカリナ』を遊んだファンに向けた挑戦状なんですね。
――CMからして、チャレンジャブルでしたよね【※】。
※『ムジュラ』のCM
世界を破滅させる凶悪な月の接近シーンや不気味な面の数々を映し、「あなたはまだ月のこわさを知らない」、「あなたはまだ仮面のこわさを知らない」などの煽り文句で、ダークな世界を表現した。
青沼氏:
『時のオカリナ』を死に物ぐるいで作ったあとに今度は一年で制作しましたから、もう半分頭がおかしくなってるんです。「『時のオカリナ』で免疫があるんだから、難しいのをガーッて作ったらええねん」というノリが原動力になった作品ですよね。いやあ、よくゴールに到達できたなって思いますもん。
藤澤氏:
カオスな状況で作ったものが後で評価される、というのは割とあるパターンですね(笑)。
でも、そのノリが伝わってるのかわからないですけど、僕と同年代の「ゼルダ」好きの中では、『ムジュラの仮面』が一番好きだと言う人は多いですよ。あのリニアじゃない攻めたゲームデザインが、後のゲームに与えた影響は大きいように思います。
青沼氏:
濃いユーザーの方に限って『ムジュラの仮面』が好きだと言われるので、ちょっと複雑な心境でもあるんです。正直なところ、あの時代にあの規模のゲームを作るから、許されたんでしょうね。今アレを作れって言われても作れないですよ。
 |
それに、そういうカオスな環境に行きすぎると地に足がついていない作品になっていく、と僕は思ってます。今回の『ゼルダ』も、確かに大変な状況でしたけど、昔のように仕事に追われて私生活がおろそかになるようなことにはなっていません。やはり生活の中で、しっかりと今の時代の空気を吸い込みながら毎日作っていかないと、共感してもらえるような作品を継続的に生み出すことはできない気がしています。
300人で遊んだものづくりの体制
――もう少し任天堂の開発スタイルに踏み込んでみたいです。例えば、昔のゲーム開発者の人に聞くと、「規模が小さかった頃は、みんなで全体を見渡しながら細かいところまでこだわれて……」と、昔を懐かしむ声を聞くことが多いんです。分業が苦手というのは、21世紀に入って開発が大規模化したときに、日本のゲーム産業に起きた問題としてよく語られるのですが、任天堂はどうなんだろう、と思うんです。
藤澤氏:
不思議ですよね。『スプラトゥーン』みたいな作品が、今でも任天堂から生まれてくるんですよ。さっきの複数人ディレクターの体制もそうですが、外部でその謎を疑問に思ってる人は多いと思うんです。
――例えば、今回の『ゼルダ』はどうだったのですか?
青沼氏:
今回について言えば、そもそも細かい部分での挙動がおかしいことが、このゲームの面白さを半減させることに繋がらないというのが一つありました。だから、バグを“あら探し”しては潰して調整するというよりは、この世界の中で「どこにモンスターが発生するか」という分布図なんかの大づかみのバランスを最終的にしっくり来るまで直し続けた感じですよね。そこは目線がこれまでとは違いましたよね。
ただ、それを担当している人はさすがにいっぱいいっぱいになりながらやるわけですよ。気になって聞いてみると、どうも別のバランスが考慮されたときに、当初考慮された分布が効力をなくしているようなことが起きるんです。それって、やっぱり連絡ミスが原因なんですね。
――ああ、やっぱり任天堂でも大規模開発での連絡ミスは起きてくるんですね。
青沼氏:
ただ、そういうのが起きるのは、これだけ広いモノをつくってる以上は仕方ないんです。大事なのはそこで「ヤァー!」って直せることなんです。そのときに、開発者がちゃんとゲームを触っていたら、的確にどう直せばいいかわかるんです。
 |
だから、今回一番重視したのは、とにかく徹底して全員で遊ぶことでしたね。4年間の間に、10回ぐらいみんなで遊ぶっていう時間を入れたんじゃないかな。
藤澤氏:
それって全員で……ですか。
青沼氏:
ええ。まあ、開発当初は1日くらいで終わってましたけど、最後の方なんて1週間くらい遊ばないと全部見れませんから。そこでつい省力化したくなるんですけど、ダメです。もう絶対にみんなで最後まで遊ぶ。これを徹底しました。
――あの……なんかサラリとムチャクチャな話を聞いている気がするのですが、開発者みんなって何人ですか?
青沼氏:
えーっと、プログラマもデザイナーもサウンドも、とにかく全員ですから最後の方は300人規模でプレイしてました。
一同:
(笑)
――ええと、300人で1週間って人月単位で計算すると、とんでもない額ですよ。しかも、それが何回もある……!?
藤澤氏:
「ドラクエ」でも、マイルストーンを切って、丸一日かけて全員で遊ぶ日を作って、意見を募ったりはしましたけど、1週間は長い……あまりに長いですよ。
 |
青沼氏:
さすがに300人規模は本当に最後の頃でしたけどね。もちろん、僕もプロデューサーなので、開発費用を考えれば、そこはなんとか短くしたいと思うんですけど、現場のスタッフが「ダメです」と言ってくるわけですよ。だから僕もキッチリ1週間、遊びます。するとやっぱり何が問題点なのかが見えてくるんですね。
結局、このゲームは各々の考えで作っているものですから、それをみんなでプレイして全体像を見渡して評価するのがいいんです。そうすると、「何を作れていて、何ができていないのか」が全員分かるんです。
だって、責任者が言葉で自分の考えを末端まで伝えるのなんて、本当に難しいですよ。だけど、みんなが遊んでいれば、「あそこさー」「ですよねー」で会話できる。そのことで逆にこの広い世界を作り込む時間的なコストは劇的に下げられていると思いますよ。
――そうケロリと言われてしまうと、「そうですか」となってしまうのですが(笑)。でも、1週間で300人にただゲームを遊ぶ稼働をさせて「時間を省略できた」と言い切れる会社が日本に、いや世界中にどれだけあるのかと思いますね……。
藤澤氏:
そもそも日本のメーカーがなかなかオープンワールドを作れずにいた理由は、開発手法がガラリと変わってしまうからだと思うんです。日々熱心に仕様をまとめたWikiを更新し続けたり、連絡をきちんとやるというやり方になっていて、慣れた手法を棄て去るという割り切りがなかなかできなかったんです。北米の企業は、こういう分業のマネジメントがしっかりと機能するようなのですが。
ところが、どうも任天堂はここをあまり苦労せずに乗り越えてしまった印象がありますね。
――ホントですね。現代のゲーム開発のこの問題に対して、今日の任天堂の『ゼルダ』チームのような回答は初めて見ました。つまり、300人になっても全員でプレイして、「あれあれ」「そうそう」の日本人らしい会話をしながら、みんなで細やかに作り続ければいいだけじゃないか、と(笑)。
どうやってオープンワールドに対応したのか
藤澤氏:
もう一つすごいと思うのは、今回の『ゼルダ』がオープンワールドの文法にしっかりと乗れていることですね。
日本の開発者は、良くも悪くも「プレイヤーにこういう体験をさせるために、こういう手順を踏んでもらいましょう」というロジックから入りがちなんです。でも、オープンワールドで開発者が作るものは、その世界を成り立たせる「摂理」であって、プレイヤーの体験については決めない。そこは「皆さんが決めてください」と任せてしまう方向に、発想を転換しなければいけない。
さっきから青沼さんが仰っている内容は、まさにこの発想の転換そのものなんですが、これは容易ではなかったはずです。特に任天堂さんのような歴史のある会社は、方法論に少なからずこだわりがあるだろうと思うんですが……。
青沼氏:
当然、僕たちも大変でしたよ。最初はもう、チームが崩壊するんじゃないかと心配するくらいに、色々なところで意見が毎日戦わされてましたから。
なにしろ、ずっと「ゼルダ」を一緒に作ってきたプログラマたちが、「これは自分たちが評価できるものじゃない」とハッキリ言ってきたんです。Havokを使うことも、当初は「こんな作り方で面白い『ゼルダ』は絶対に作れない」と言われました。
藤澤氏:
そういうことが、必ず起きますよね。しかも、技術論の問題ではなくて、むしろ慣れ親しんできた方法論に対して、人の心を変えていく大変さだと思うんですよ。

(※画像はWii U版です。ドラゴンクエストX 公式プロモーションサイトより)
実は、僕も『10』でオンライン化に挑戦したときに、同じような体験をしているんです。僕らの場合には、「オンラインゲームとはこうあるべき」と「ドラクエとはこうあるべき」という2大派閥があって、やっぱり意見がぶつかりあったんですね。
――MMO【※】もある種、オープンワールドのような発想が大事になるジャンルですよね。
※MMO
正しくはMMORPGと表わす。Massively Multiplayer Online Role Playing Game(大規模多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム)の略。運営会社の設置したサーバー内に展開する世界に数百~数千のプレイヤーが同時接続し、オンラインで同期して楽しむタイプのロールプレイングゲーム。代表例に、藤澤氏の手がけた『ドラゴンクエストX』シリーズや、『World of Warcraft』、『ファイナルファンタジーXI』や『XIV』などがある。
藤澤氏:
『10』の時は、「今回のプロジェクトの目的は、とにかく『ドラクエ』を作ることだ」と明言しました。ただ、それはあくまでもスローガンであって、それがすべてだったわけではないんですが、やはりそういう交通整理は必要でした。青沼さんの場合はどうでしたか?
青沼氏:
うーん。整理なんて、僕には出来なかったです。だから、時間による解決ですかね。4年かかれば、さすがにみんな「なるほど……これしかないわ」となりました(笑)。
一同:
(笑)
藤澤氏:
それもよく分かる気がします。時間で解決するしかないことがあるのも、事実ですよね。
――でも、青沼さんご自身は、不安はなかったんですか?
青沼氏:
いやいや、不安だらけですよ。
僕はやっぱりイイ歳なんで、たまに若い人とのズレを感じる瞬間は出てくるんです。そういうときは、大抵昔から自分が引きずっているやり方にこだわっているときですね。だから柔軟性を持って世の中を見たいと思っているし、それが出来なくなったら現場から立ち去るときだろうと思ってます。
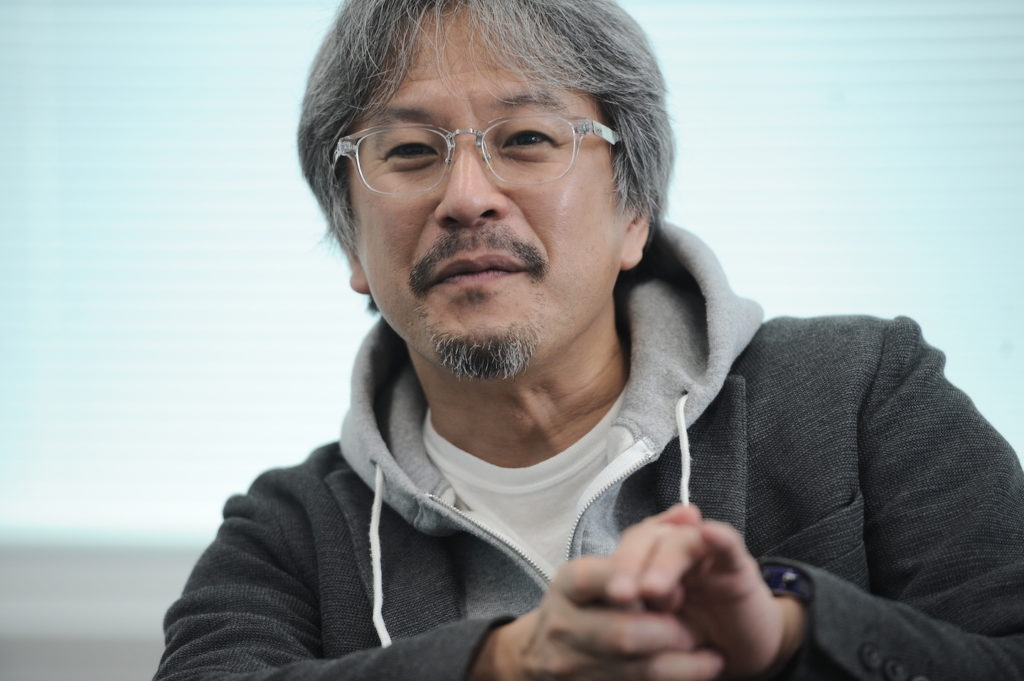 |
ただ、やっぱり、そういう価値観を持つ人ばかりではないですよ。だから、そこは時間をかけるしかなかった。だけど、変わらなければ作る意味がないと覚悟していたし、時間がかかってでも全然違う『ゼルダ』にしたいと決めていたんです。
……なんて言いつつ、本当はコンパクトな人員で試す予定だったけど、気がつけばスタッフが300人になっちゃったんで、もう後に引けず「完成させたるわい!」と覚悟した、という真相もあるんですけどね(笑)。
「同じタイトルを続けること」への回答は……?
――さて、随分と色々なお話を聞かせていただいて、そろそろ時間が来てしまったのですが……。
青沼氏:
ちょっと待った!
一番最初の「同じタイトルをずっと続けるのか」について、まだ結論が出てないですよ。藤澤さんが何か良いものを得たぞという感覚がないと、僕も申し訳ないです(笑)。
――う、確かに。藤澤さん、どうでしょうか?
藤澤氏:
いえいえ。僕は楽しくて、その問題を考えるのを忘れてしまっていました。
一同:
(笑)
藤澤氏:
ただ、一つ気になったのですが、いまは宮本さんはどういう関わり方なのですか。「こういうのをやりたい」という人が二人いると、プロジェクトは迷走しがちだと思うんですが。
 |
青沼氏:
基本的には、任せてもらっています。僕が考えることについても、「間違いもあるけれど、上手くやればちゃんとなるんだろう」くらいの感じで、一歩引いて見てくれていると思います。ただ、そこは宮本ですから、いわゆる「ちゃぶ台返し」みたいなことは今でもありますよ。
藤澤氏:
そうなんですか。
青沼氏:
ただ、昔はゲームの完成間際にバーンってひっくり返して、「えーっ! それやったら半年延びますよ!」というのを平気でやってのけてましたが、最近は序盤の重要なところでバランスや完成の見通しについてジャッジを早めに入れてくるようになりました。ひっくり返しも小さめです。それどころか、今回の『ブレス オブ ザ ワイルド』では、宮本は全然ちゃぶ台をひっくり返してませんからね。
ただ、実際に遊んでくれて、「なかなか面白いじゃないか」という顔はしてました。
藤澤氏:
「顔」をしていた(笑)。
青沼氏:
絶対に現場で「イイじゃん」とか言ってくれませんからね! 岩田が存命の頃は、彼の口から「宮本さん、今回の面白いって言ってましたよ」って聞かされて、「えっ!? そんなの俺、何も聞いてないよ!」みたいな話ばかりでしたから。
藤澤氏:
ああ、人づてで聞くやつですよね(笑)。僕も堀井さんから直接ほめられたことって、ほとんどないんですけど、知り合いから「よくやってるって言ってたよ」みたいなことを伝えてもらったりしましたね。
青沼氏:
まあ、そういうもんなんでしょうね。僕自身もほめられちゃうと、そこで安心して終わってしまう気もするんで、それでいいんですけども。
藤澤氏:
そうかもしれないですね。
ただ、僕は堀井さんと、師匠と弟子としか言いようがない関係だったのですが、堀井さんも積極的に「我が技を教える」というスタンスでやる方ではないので、いわゆる一子相伝みたいな厳しい空気はなかったんです。堀井さんの手伝いをする中で、気づくと一通りのことは見たな、という感じですね。
「宮本茂を『神だ』なんて思ってない」
青沼氏:
でも、それを聞くと、宮本と僕の関係というのは、所詮は「上司と部下」なんだなとは思いますね。そこが結局、僕がずっと「ゼルダ」を続けちゃっている理由かも知れないですよ。
藤澤氏:
ああ、確かにそうかもしれないですね。堀井さんの場合はフリーランスですからね。そこは大きいと思います。
青沼氏:
だって、僕は「宮本さんってすごい人だな」と思いながら、「いつかは超えたい」って、心の中で思ってますからね。
――おおおお。
青沼氏:
だって、僕は同じ社屋の中で仕事をしてるんですよ。特に海外ではゲーム開発者としての宮本を神のように言う人もいるみたいですけど、僕は神だなんて全然思ってません。だから、「宮本茂をいつかは超えてやる」と思ってます。まあ、まだ全然超えられてないんですけどね。でも、そんなに遠い存在ではない。近くにはいるんです。だから、追い続けてしまっているんだと思います。
 |
藤澤氏:
そういう意味で言うと、僕と堀井さんはもう少し距離感があったかもしれないですね。
もちろん、一緒に仕事をしているときは、立場がどうであろうと、作品のために必要なことならば徹底的に戦ってきたんですよ。でも、離れてみて堀井さんが成し遂げてきたことを振り返ってみると……自分はそこに行けるような人間じゃないな、とつくづく思ってしまうんです。「超えたい」と思ったことは、たぶん僕はないですね。
青沼氏:
なるほど……。
――堀井さんを見る目は、離れてみて変わりましたか?
藤澤氏:
そうですね。
離れてみて、あれだけ一生懸命にやった「ドラゴンクエスト」が、自分がいなくても活発に動き続けている姿を見るんです。そのときに、「これは誰の功績なんだろう」と考えると、やっぱり堀井さんが、みんなを道案内する旗を振っているからなのは間違いないんです。それは、やっぱり堀井さんにしかできないことだし、改めて尊敬の念は深まっていますね。
青沼氏:
でも、藤澤さんはもうやめられて、自分のタイトルを作ってるわけですよね。
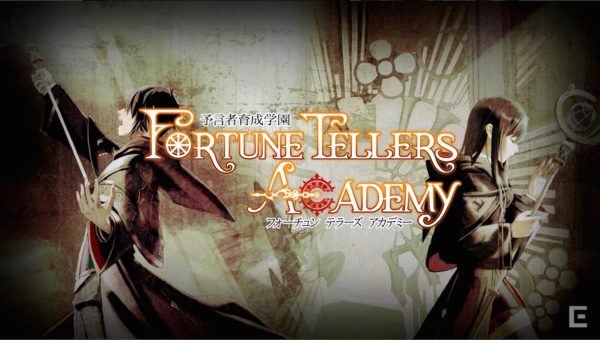
(画像は『予言者育成学園 Fortune Tellers Academy』プロモーション映像より)
僕も、「ゼルダ」から離れることは、一度やらなきゃなと思うときはあるんです。ただ、その代わり新しいIPをつくるという話になると、「そんなすぐに出てきません!」ってなっちゃって、こうしている部分もあるんですよ。
藤澤氏:
まあ、なかなか新しいIPというのは、口で言うほど簡単ではないな、と痛感する日々ですけども(笑)。
青沼氏:
ちなみに、最初にも話したように、僕は一度やめようと思ったんです。
それを宮本に説得されて、『トワイライトプリンセス』でプロデューサーという立場で復帰したんですね。そしたら、開発の途中で自分が入る必要が出てきたのもあったのですが、それ以上に色々とゲームを面白くする材料が揃っていることに気づいちゃったんです。そうしたら、「これを俺がまとめたら面白くなるぞ」と思って、つい自分でまたディレクターをやりたくなっちゃったんですね(笑)。
――ははは(笑)。
 |
シリーズのバトンを受け継いでいくこと
青沼氏:
何が言いたいかというと、僕も一度やめましたけど……結局、戻りましたからね(笑)。でも、戻ってきたら新しい何かがあるかもしれないですし、アリなんじゃないですか。
藤澤氏:
そうですか(笑)。
青沼氏:
まあ僕なんて宮本から、いまだに「お前……相変わらず素人やな!」って言われるし、そんなもんですよ。
藤澤氏:
それ、たぶん宮本さんは誰にでも言ってるんじゃないかと思います(笑)。
いや、もちろん僕は「ドラクエ」を出て行くときに、まだまだ「ドラクエ」でやりたいこともあったし、そこに後悔があるのも知っていたんですよ。でも、その後悔を怖れていたら、別のことをやらなかった後悔が生まれるのも知っていたから、そこは覚悟してやめたんです。
ただ、今日のお話で、青沼さんが今に至るまでずっと「ゼルダ」を作られてきて、中心メンバーとしてチームのあり方を変えながら新しいものづくりに励んでいる姿を見て、ちょっと「うらやましいな」と思ってしまったのも事実です。
青沼氏:
でも、「ドラクエ」が今も続いているのは、藤澤さんがそこでシリーズの中継をしてきたからじゃないんですか?
藤澤氏:
そうだったらいいなとは思っていますけど(笑)。
ただ、堀井さんにディレクターを任されたときから、僕は「ドラゴンクエスト」という仕事場で若い人たちが活躍できるようにして、循環させなければいけないと考えてきました。
 |
「ドラクエ」は任されたものでしかなくて、その立場に拘って残り続けることはしたくなかったんです。だから、いま若い人たちが「ドラクエ」で活躍している現状に対して、「ああ、これでよかったんだ」と思っているのも事実なんです。
――すごく藤澤さんらしい言葉ですね。
青沼氏:
うわあ、僕もバトンを渡さないといけないなあ!
一同:
(爆笑)
青沼氏:
あ、でも、僕は渡せる人間を「自分の手で見つけたい」と思っています。もうね、誰かから「こいつに渡せ!」とは言われたくない(笑)!
藤澤氏:
その気持ちも、わかります。
だから、そういう意味でいうと、「ドラゴンクエスト」は稼働中の『10』も、今作ってる『11』も、自分と一緒にやってきた仲間たちが中心に動かしてくれてるんですよ。それは僕にとっては、本当に嬉しいことなんです。
――最後にもう一度、改めてお聞きします。今回の対談を経て、藤澤さんの求めていた答えは見つかりましたか?
藤澤氏:
今日は本当に勉強になったし、刺激にもなりました。正直、自分がこの先やるべきことは、自分でも分かっているつもりだし、それをきちんとやるだけです。今日は、そのことを改めて確認させてもらった、という感じです。
青沼氏:
僕も、今日、藤澤さんとお話できて、いろいろ今まで気が付かなかった事に気づけたところがあって、本当によかったと思っています。今度、機会があればぜひ飲みにでもいきましょう!(了)
 |
宮本茂と堀井雄二、ゼルダとドラクエ。「天才」から人気シリーズを継承して、それぞれの道を歩む藤澤氏と青沼氏――その姿は、読者の目にどう映っただろうか?
二人の「師」に向き合う姿は、とても対照的だ。藤澤氏は「堀井雄二にはかなわない」と認め、ドラクエのバトンを次世代の開発者へ無事に渡せたことを誇りにする。一方で青沼氏は「宮本茂を超えてやる」と息巻きながらシリーズを作り続け、ついには今作で新しいステージへとゼルダを引き上げてみせた。少なくとも筆者には、そのどちらもが正しいように思えるし、そのどちらもが同じくらいに「清々しい」ものに映る。
二人がこれから生み出す新作ゲームが、本当に楽しみになる対談だった。
 |
そして今回の取材では、ヴェールに包まれた任天堂のゲーム開発現場が垣間見えたのも見逃せない。とはいえ聞いてみれば、やっていることは実にシンプル。つまり、自分たちに合ったやり方で、丁寧に着実に物作りをしていく――そんな当たり前の話の実践に尽きていたように思う。
とはいえオープンワールドのゲームを開発するに当たって、2Dゲームでプロトタイプ開発をしたり、300人での通しプレイを課したりするのは、やはり尋常ではない。これを当たり前のようにケロリと言うあたりには、任天堂という会社の底知れぬ“凄み”を感じざるを得ない。
だが、その一方で、こういう話を聞いて「さすが任天堂!」と、ただ驚いていてよいのだろうか……とも思う。とくにゲーム開発が大規模化するなかで、より効率的な開発体制や分業システムの必要性が叫ばれて久しい。もちろん、モノを作る効率性はとても大事だとは思う。しかし、である。そこを突き詰めるだけで、本当に日本のメーカーが世界で勝てるのか? とも思うのだ。
そもそもフォーディズム【※】のような分業の労働システムが、アメリカという国籍も学歴も違う人々が暮らす「多民族国家」で発展した手法であることを考えれば、日本という同質性の高い国(同じ言語、人種)では、やはりその特性にあったやり方があるように思えてならない。今回の「300人通しプレイ」のエピソードなどは、そうした課題に対する実に大胆な回答だったのではないだろうか?
その意味で、なんとも日本人らしいやり方で昨今のAAAタイトルの「定番」に切り込んでみせた新作ゼルダの成否は興味深い。それはゲームに限らず、今後否応なしにグローバル市場の戦いに巻き込まれていく、日本のコンテンツ産業の未来を占うものなのではないだろうか。
※フォーディズム
1910年代にヘンリー・フォードが車の大量生産・販売を行うために開発した生産システム。科学的管理法を応用したもので、作業工程を分解して分業を行うなどの手法を労働の場に持ち込んだ。
「ゲームの企画書」関連記事:
掃除のおばちゃんにプレイさせて『バーチャファイター』開発。時代を先取りした鈴木裕のゲーム開発哲学 【鈴木裕氏×『鉄拳』原田勝弘氏】
伝説の漫画編集者マシリトはゲーム業界でも偉人だった! 鳥嶋和彦が語る「DQ」「FF」「クロノ・トリガー」誕生秘話
ホラゲにゲームデザインの常識は通用しない!? Jホラーゲームの第一人者『零』×『SIREN』開発者が語り合うホラーの摩訶不思議(柴田誠×外山圭一郎)
(c)2017 Nintendo