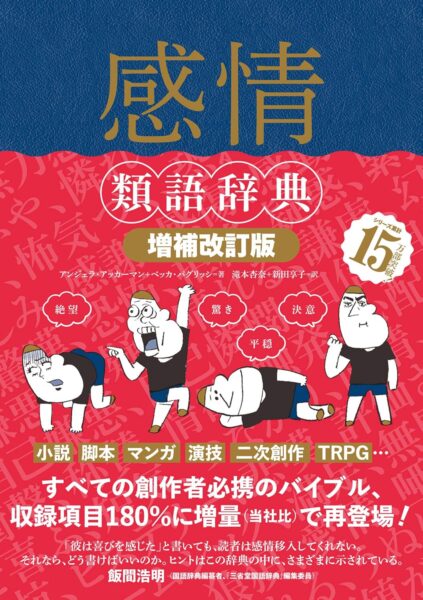8月17日、No More Robotsは『Papers, Please』に影響を受けたポストブレグジットマネージメントゲーム『Not Tonight』をSteamにてリリースした。開発はイギリスのインディゲームデベロッパーPanicBarn。
ブレグジットとは2016年に国民投票が実施されたイギリスのEU離脱のことで、作中では同件でディストピアと化したifのイギリスを皮肉たっぷりに描いている。
『Papers, Please』の主人公はパスポートの確認を行う入国管理官だったが、本作の主人公はバウンサーとしてバーやクラブの入口でIDやチケットの確認の仕事に従事する。
バウンサーというと暴れる客を取り押さえる用心棒のような仕事をイメージする人も多いと思うが、実際のバウンサーの仕事はもう少しだけ穏便なようだ。
プレイヤーは上司から与えられた確認事項に沿って、IDやチケットを確認するパズルゲームを進めていく。チェックする書類やチケットのUIと、行列に並んで主人公の仕事を待つ人々の様子は、『Papers, Please』を知る人なら見慣れた風景かもしれない。

ゲームの舞台は架空の極右政党であるAlbion Firstが政権を取ったイギリスとなる。Albionとはブリテン島の古い呼び名であり、そこからイギリス人の呼び名のひとつとなった。つまり、イギリス人のための政党ということだ。
主人公はそんなブレグジット後の混乱の中で生きる移民のひとりとして政府から割り当てられた仕事をこなす。架空の共産主義国を描いた『Papers, Please』では職業選択の自由はなかったが、『Not Tonight』が描くブレグジット後の移民にも職業選択の自由はない。

ゲームの冒頭でプレイヤーはAlbion Firstの政権発足1周年を祝う英国歴史博物館(Museum of British History)でのセレモニーでチケット確認の仕事を行う。
なお、英国歴史博物館は架空の博物館だ。このシーンはチュートリアルも兼ねており、客の持つチケットの日付とスタンプを確認して問題がなければ場内へ案内する。
しかし、幾人かを案内した後、大きな爆発音とともに博物館が大破する。何が起きたかを理解する前にそこから視点は過去へとさかのぼり、政権が発足した2018年1月1日へと戻る。プレイヤーは、この大事件へと至る1年間の英国での生活を追体験することになる。
『Not Tonight』の序盤の難易度は『Papers, Please』に比べれば難しくない。IDの確認はパスポートに比べれば簡単で、ミスした時のペナルティもあまり手痛いものではない。毎日の食費や光熱費のことを考える必要もなく、ひとり身なので家族のことを考える必要もない。
悠々自適とは言えないが、明日こそ寒さや食糧難で死ぬかもしれないというような差し迫った恐怖は感じない。『Papers, Please』が難しくて挫折した人でもきっと楽しくプレイできるだろう。
 |
しかし本作はイギリスがEUから離脱することを決めたブレグジットの後を描いたゲームであり、ブレクジットに至る原因のひとつと言われる移民問題、ひいては移民の弾圧を作中で描いている。
低賃金で働く移民はイギリス人から仕事を奪い、さらに治安の悪化の原因だとしてもともと住む人々からの規制を求める声は少なくない。ブレグジットやその後の選挙でも大きな争点のひとつとなった。
今後イギリスがEUから離脱した後、イギリス国内の移民がどうなるか正確に予想するのは難しい。しかし、少なくとも移民の受け入れは今より規制されるだろうという意見は根強い。
現実のブレグジットは非常に複雑で繊細な問題であり、その原因やこの先どうなるかもいまだ完全な結論は出ておらず、本稿はそれを議論するものではない。よってブレグジットを風刺する『Not Tonight』の世界がどうなっているかを一度振り返るだけにとどめておきたい。
上記の通り『Not Tonight』は極右政党が政権を取った後のイギリスだ。現実とは違い変化は急激で大きい。移民は強制収容所のようなアパートに押し込められ、強制送還をちらつかせた方法で職業を押し付けられる。
主人公のひび割れたスマートフォンには政府が移民の職業を管理するためのアプリがインストールされ、後に移民としての社会的地位や信用を表示する「BillR」と呼ばれるアプリも登場する。さらに、アパートには「人種差別廃止官(Integration Officer)」が定期的に政府から派遣されてくる。

ここまでくると度の過ぎたブラックジョークでほとんどコメディのようだと言えるが、このような状況がやってくる可能性を完全に否定することはできない。たとえばイギリスでは2008年から、職業や言語能力によって移民を分類するポイント制システムが導入されている。
『Papers, Please』が描いた共産主義の世界はある種のノスタルジーが漂う前世紀の遺物としての側面が強く、朝令暮改の政府の方針や度重なるテロリズムの脅威もどこか遠くの世界のファンタジーのように見えた。
しかし、国は違うとはいえ同じ時代を生きる人々が抱く不安を生々しく描く『Not Tonight』の世界には、単純にジョークだと笑い飛ばすことができない薄ら寒さがある。
文/古嶋 誉幸