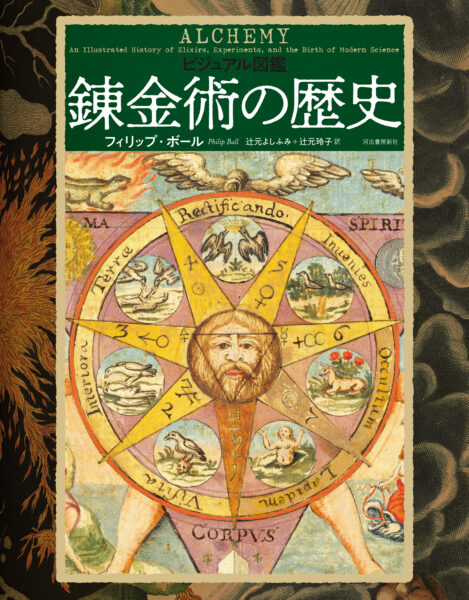『全裸監督』は日本で、そして世界でなぜヒットしたのか
梅田氏:
プロモーション的にそこまで届いていない理由としては単純に、接触頻度の問題もあると思うんです。
だって『全裸監督』なんか、めちゃくちゃたくさんテレビCMをやっていたじゃないですか。その上、芸人さんがバラエティ番組で話題にしたり、モノマネしたりして。
たちばな氏:
はい。
梅田氏:
『全裸監督』の宣伝でお聞きしたいのは、主人公がブリーフ一丁の格好でカメラを持っている、あの画ですよ。すごくエッジが利いていて、普通の人が見たらギョッとするはずなんですけど、あれがお茶の間に大量に流れたわけで。
たちばな氏:
そうですね。
梅田氏:
そういう宣伝をすごい規模で並べていくことで、『全裸監督』はマスを獲得していったわけですよね。あれにはどんな計画があったんですか?
 |
たちばな氏:
Netflixの広告は、かなりたくさんのバリエーションを作っているので、それは結果論だと思います。Netflixがスゴイのはの、宣伝チームが完全に別働隊なところなんですよ。
梅田氏:
あっ、そうなんだ。
たちばな氏:
TVドラマの場合、基本的にはそのドラマのプロデューサーが全体を統括しているんです。でも映画の場合は、制作側と配給会社が分かれていて、配給側が宣伝に責任を持っている場合が多いじゃないですか。Netflixは、そのテレビっぽいところと映画っぽいところの両方を持っていると感じました。
しかもNetflixは、マーケティング部門がムチャクチャ優秀だと思います。海外の広告クリエイティブチームがポスターとかを作っているし、ネット上で展開する画像もターゲットとか趣味嗜好に合わせて種類もたくさん作って、しかもセンスが良い。さらに、その広告をどのタイミングでどう出していくか、どうやって見せていくかみたいなこともプロの人たちが計画していて、そこにはしっかりテクノロジーの力が効いているという。
これは僕の想像も含まれますけど、当然いろんなパターンの広告を試して、その中でいちばん反応が良いものというか、見る人にとっていちばん刺さるものを、アルゴリズムで出しているんだと思うんです。
逆に、特定のジャンルやサムネイル画像に嫌悪感を抱くような人には、それに類したものがレコメンドに出なくなるとか、常に最適化されていると聞きますよね。
梅田氏:
あっ、その中で「いける」というものを、地上波のCMで流したんだ。そういうことか。
──『全裸監督』って、日本でウケるのはまだ理解できるんです。テレビではできないことをやる感じだとか、ギョッとする感じとか。でも一方で、海外でもけっこうウケているじゃないですか。いったい海外ではどういうふうに受け入れられているのか、まったく想像もつかないんですが、実際どういう感じなんでしょう?
たちばな氏:
そこに対して、明確な答えはないんですが……。ただ、僕が企画を提案する段階で、「日本固有の、ローカルでありながらグローバルに届くもの」ってなんだろう? と考えたときに、いくつか方向性があるなと思っていました。
 |
まずひとつは、いわゆるアニメ的なIPで、たとえば『ONE PIECE』を実写化します、みたいな方向。で、そのほかにいくつか違う方向を探していったときに、「エロ」という世界があったんですね。
日本って、本音と建前というか、「表」と「裏」が違うことが多いじゃないですか。みんな表ではすごく真面目そうなんだけど、その裏側ではすごいムッツリだったり。アダルトビデオについては、日本は世界の中で圧倒的なんですよ。本数もジャンルも多い。しかもそれがコンビニにも置かれているなんて、外国人からすると信じられないわけですよ。
それはフェミニズム的なことを含めて日本の意識がすごく低いということで、誇れることでは全くないと思いますけど、結果的には世界から見て、そういう人間の「根源的な興味」というか、日本の裏側である「エロ」に対する興味がものすごくあった、ということですかね。
──そういう意味では、日本の僕らが海外のスラム街の物語を見るとか、ギャングの生活を見るみたいな、ドキュメンタリー的なものに近い受け取られ方いうことですか?
たちばな氏:
まさにそこだと思います。海外ドラマでは『ブレイキング・バッド』【※1】や『ナルコス』【※2】のようなヒット作もNetflixにはありますし。
だから、エロで興味を引くということではなく、そういう題材だからこそ描ける人間の本質や、そういう「生(なま)」な感じをどう出せるかというのは、プロダクションとしてはすごくこだわった部分ですね。
※1 『ブレイキング・バッド』
2008年〜2013年にアメリカで放送されたTVドラマ。ガンで余命数年と診断された化学教師が、麻薬ビジネスに乗り出したことで、自らの人生を大きく変えていく。海外で高い人気と評価を獲得しており、スピンオフドラマ『ベター・コール・ソウル』が現在も放送されている。
※2 『ナルコス』
Netflixで2015年から配信が開始されたオリジナルドラマシリーズ。コロンビアの麻薬カルテルとアメリカの麻薬取締捜査官たちとの対決が、実話を元に映像化されている。2018年のシーズン4からは、メキシコの麻薬カルテルを題材にした『ナルコス:メキシコ編』がスタートしている。
梅田氏:
単純にメチャクチャ面白かったですもん。
たちばな氏:
ありがとうございます。
梅田氏:
主演の山田孝之さんが「本当に素晴らしい現場だった」と言っていますよね。それは「みんなにとって快適な環境を作ろう」だとか、何か意識した部分があったんですか?
たちばな氏:
うーん……それはわりと当たり前のことというか、そんなにすごく特別だったわけじゃないと思います。
でも何かあったとすれば、これも結果論になりますけど、「今までないものを作りたい」と思っている人が集まった、というのはある気がします。
 |
『デスカムトゥルー』の「次」が出た時のために、この体験を蓄積させたい
梅田氏:
接触機会の増やし方としていろいろな方法がある中で、プロモーションにかけられるお金があまりない。そのへんが『デスカム』が『全裸監督』とは違うところかもしれないね。
僕は『デスカム』を体験してくれた人を、これからもどんどん増やしていきたいし、この対談からも増やしてもらおうと思っているし。そうやって蓄積していくことはすごく大事かな、と思うんですよ。
もし次につながっていくなら、そのときはすでに知っている人たちから、「『デスカム』の次が出たらしいよ」と言いやすいだろうなと。
たちばな氏:
そうですね。
梅田氏:
YouTuberの「水溜まりボンド」さんとコラボしたり、いろいろとチャレンジはしているんです。そこからふだんはぜんぜんゲームを遊ばないような、すごくカジュアルにYouTubeを見ている人たちが興味を持ってくれたりもしているんですけどね。
でも、どれかひとつが爆発的なヒットにつながるかというと、そうじゃないんですよね。その理由としては、新しさが伝えづらい、ミステリーであるから伝えづらい、というのがあるのかもしれない。
だけど「蓄積していく」ことはできる。いろんなチャレンジをしながら蓄積していって、それをいろんな意味で次につなげる。今はそれができればと思っています。
たちばな氏:
水溜まりボンドさんを起用したりと「もっと若い人向けに」という発想があったと思うんですが、そのカジュアル感というか、ライトさはどのくらいを想定してたんですか?
梅田氏:
難しいですよね、そのあたりのライトさの加減というのは難しいですよね。それこそ「ヒカキンに出てもらおう」みたいな話もあったんですよ。その流れから、水溜りボンドさんにプロモーションを手伝ってもらうことになったんですが。
まぁでもヒカキンに出てもらったとして、そのシナリオを小高さんに書いてもらうのも難しいですよね(笑)。
 |
小高氏:
(笑)
梅田氏:
でもキャストというのも、パイの広げ方のひとつの手法でしかないですよね。たとえば『カメラを止めるな!』なんかは、キャストを誰も知らなかったわけで。それでもあんなにヒットしたわけですから。
たちばな氏:
もっと話題のある、アイドルグループみたいなキャストで固めるといった方向に振り切るやり方も、もちろんありますよね。だけどそれでいいのかどうかというのは考えどころですよね。
たとえば「本当に芝居が上手い演劇役者を集めて面白いことをやろう」みたいなことを思っていても、それだけではなかなか計算が立たない。そういうところをバランス良くやるのが、まさにプロデュースワークなんだろうなと思います。
梅田氏:
なるほどね。
日本のゲームクリエイターには、ストーリーを作る世界的な才能がある
──たちばなさんがゲーム業界に関心を持ち始めたのは、どういったところからですか?
たちばな氏:
実写側というか映像側の業界にいる人間として、「ライブ」と「インタラクティブ」という2つのキーワードが、今の映像業界にはあまりにもないぞと感じたんです。時代のうねりみたいなものに対してものすごくクラシカルになってるけど、大丈夫なの? と。
そんな問題意識から、それこそ「マーダーミステリー」や「人狼ゲーム」みたいなものも含めて、自分なりにいろいろ探っていくようになったんです。もともと舞台が好きだったので、最初は「人狼」から入り始めましたね。
小高氏:
『人狼TLPT(人狼 ザ・ライブプレイングシアター)』【※】ですか?

(画像は人狼TLPTとは | 人狼 ザ・ライブプレイングシアターより)
たちばな氏:
そうです。『人狼TLPT』を見たり、ゲームクリエイター人狼会に行ったりして「めっちゃ面白いやん!」と思って。それとリアル脱出ゲームや、マーダーミステリーですね。そういったものをやっていく流れで、ゲーム業界のいろんな方々とお会いすることになったんです。
──ということはゲームといっても、そういったライブ感覚のあるゲームを中心に?
たちばな氏:
そうですね。僕は「一億総クリエイター」というか、これからはもっと個人がストーリーを発信する時代になっていくし、ストーリー自体も個人的になっていくと考えているんです。
 |
ちょっと長くなっちゃうんで端折った話になりますけど、動画はYouTubeなどで民主化されているんですけど、映画はまだ民主化されていないんですよ。それを「どうやって民主化するか」というのを、この間、大友啓史監督や東宝の山田兼司プロデューサーと、3人で話したりしたんです。
音楽やマンガの世界はすでに民主化されているというか、プラットフォームができていて。ゲームも一応、民主化されていますよね?
小高氏:
最近はインディーゲームを流通する場所が増えてきたり、どんどんそうなってますね。
たちばな氏:
それはスゴイなと思って。さらに言うとマーダーミステリーとかも、むしろアマチュアの人たちが市場を作りだしている感じがあるじゃないですか。ああいうものをプロ側はどう見ているんだろうか、みたいなことにすごく興味があって、いろんな人に話を聞いたりしているんです。
そういう民主化が進んでいくと、良くも悪くも玉石混交になって、プロも引きずり下ろされる可能性があるわけですよね。でも僕は、結果としてそれが産業を成長させるというか、良いものが生まれるきっかけになると思っているんです。
でも、映画ではそれがまだないんですよ。この民主化をどうやって作ろうか、ということのためにも、ゲーム業界はとても参考になると思っています。
──民主化とはちょっと違うかもしれないですけど、ゲーム業界の場合は5年おきぐらいの間隔でプラットフォームが変わったりして、シャッフルが起きるんですよ。
たちばな氏:
あぁ、なるほど! ゲーム機の世代交代ですね。
──そのシャッフルが起きるタイミングで、若い人が台頭してくるような流動性がありますね。その点はは映画業界とは違うかもしれないですね。
小高氏:
とはいっても、コンシューマゲームはこの先もう、トップダウンしかなくなるでしょうね。これから先は、AAA(トリプルエー)しか戦えなくなってきちゃうので。
 |
たちばな氏:
それは1個1個のタイトルが、大きく張っていくがゆえに、ということですよね?
小高氏:
基本的にはそっちになっていますね。
たちばな氏:
才能のあるクリエイターがインディーゲーム業界からピックアップされたりとか、せめてそういう仕組みがあればいいんでしょうけど。
小高氏:
そこは完全に分断されちゃいましたね。
たちばな氏:
トップダウンとボトムアップがくっつくかどうかが、すごく重要なんです。そこがくっつかないと、上のほうが膠着化していくので。
小高氏:
ゲームはこれから、もっと工業製品に近い感じになっていくんじゃないですかね。AIで作ることもより増えてくるだろうと思うし。
たちばな氏:
そうですか。その話は面白いな(笑)。
小高氏:
ゲームはこの先、『サイバーパンク2077』【※】みたいなバケモノばっかりですよ。戦おうという気すら失くしますよ(笑)。任天堂以外は日本の出る幕がだんだんなくなってくるなぁって感じますね。
僕はもう「ゲームじゃなくてもいいじゃん」って思っているところがあって。「ゲームとは?」みたいなことって、むしろユーザーのほうがすごくこだわってるという感じがしますね。

(画像は『Cyberpunk 2077』公式サイトより)
たちばな氏:
僕は、日本のゲームクリエイターの世界観を作る、ストーリーを作る才能は本当に高いと思っています。日本の漫画家もそうなんですけど、ゲームクリエイターも漫画家と同じぐらい、その才能があると思っているんです。
だから小高さんみたいな人が、海外TVで言うところの「ショーランナー」【※1】という、クレジットで「created by」と出てくるような役割をやったほうがいいと思っていて。それこそJ・J・エイブラムス【※2】みたいな立ち位置ですよね。
※1 ショーランナー
アメリカやカナダのTVドラマで、実際の現場で制作の指揮を行う総責任者のことを指す用語。
※2 J・J・エイブラムス
『ミッション:インポッシブル3』『スター・トレック イントゥ・ダークネス』『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』などで知られる映画監督。『エイリアス』『LOST』など、多数のTVシリーズでも製作総指揮を担当している。
 |
──たちばなさんみたいに、映像系の人でここまでゲームに寄った話ができる人に、僕はあんまり出会ったことがないですね(笑)。ゲーム好きかどうかというよりも、ゲームに固有の特性みたいな話に踏み込んでくる人は、なかなかいないかと思います。個々のタイトルのファンです、みたいな人はけっこういると思うんですが。
小高氏:
そうですね。
たちばな氏:
かもしれないですね。ゲーム好きな人もいるとは思いますけど。
小高氏:
映像業界にいる人たちは「オレたちがトップだ」と思っているから、コンプレックスがないんじゃないですか。ゲーム業界の人間なんて、「ちっくしょおー!」みたいなのしかないから、「あっちを喰ってやるぜ!」という気概を見せるんですけど(笑)。
映像業界の人はあんまりこっちを理解しようと思わないというか。「へぇ〜、がんばりたまえ」みたいな(笑)。勝手なイメージですけどね。
たちばな氏:
たしかに映像業界の人って、あまり外の世界に出ないんですよ。だから僕は意図的に外に出て、外の人たちと話すことで自分の価値を上げられないかと頑張っています。
ゲーム業界の人たちは本当に楽しくて話があうというか、たとえば僕は「感動とは何か」とか考えるのが好きなんですけど、映像業界の人でそういうことを考える人って、あまりいないんです。いないわけじゃないけど、自分が面白いと思うストーリーを作る方に意識がいくというか。
でもゲーム業界の人たちは、そういうところまで考えて体験を作っているから、その過程でいろんなことを言語化する能力がメチャクチャ高い。だから話していて、すごく楽しいんですよね。
小高氏:
でも、映像業界の人たちが気づかないうちに、こう、後ろから呑み込んでやろうと思ったのに、たちばなさんのように「ハッ!」と気づく人がいると、逆に困るんですよね(笑)。
 |
アクションゲームを操作しながら、感動して「泣く」ことはできるのか?
たちばな氏:
どんでん返しといったミステリー的な「満足」と、ラブストーリー的な「感動」は、作り方がまた大きく違うところだと思うんです。その点で『デスカムトゥルー』は、本当に良いバランスになっていたなと。
小高氏:
ミステリーにこだわりすぎてしまうと、それはそれでどうしてもクイズ大会になっちゃって、感情が乗らなくなってしまうんです。
たちばな氏:
あぁ、なるほど。
小高氏:
それは『デスカム』の前に僕が作っていた、『ダンガンロンパ』ですごく気をつけていたことなんです。事件がただの謎解きになっちゃったら、キャラが立たなくてつまんなくなるな、と思って。
 |
僕がいちばん好きなミステリーは、東野圭吾の『容疑者Xの献身』なんですよ。「なぜこういう殺人を犯したのか?」とか、動機が全部、ちゃんとドラマになっていて。
トリックのすごさで言えば、もっと優れたものはたくさんあるんですけど、僕としてはそれよりも、ドラマとしての魅力を出したいな、と思っています。そういう意味では、ミステリーは「風味」であっても、きっと通じるだろうなと。
それに『デスカム』の場合は、キャストの人数もかなり限られていたので、この人数でガチのミステリーを作るのは不可能に近いということもありましたね。
普通のミステリーとして作ると、単純に「ハウダニット」、つまりどうやって殺したのかを解いていくゲームになっちゃう。ハウダニットだとパズルになっちゃって面白くないし、かといって「フーダニット(犯人探し)」は人数が少なすぎてできない。
だとしたらミステリーは「風味」にして、その代わりにドラマを乗っけないとダメかなと。だから繰り返し言っているとおり、道が決まっていたといえば決まっていましたね。

(画像はAmazon.co.jp: 容疑者Xの献身 | Prime Videoより)
たちばな氏:
映画的な感動と、ゲーム的なインタラクティブ要素が、ぶつかり合うところはなかったですか?
小高氏:
それは僕が「ゲームで物語を紡ぐ」というのをずっとやってきているので、そんなにぶつかることはなかったですね。
あと、実写は初めてですけど、アニメやマンガの話も書いていることもあって、「流れていく物語」と「自分で押して進んでく物語」の両方を、どっちもなんとなく分かっているので。
なんていうのかな、「ゲームでやる場合はこういう話だよね」、「これはアニメ向きの話だな」と、最初からそういう区分けをしちゃってるんです。ゲームに向いていない物語を、ゲームに無理やり入れようとはしないので、そこで「ぶつかる」ということはないですね。
たちばな氏:
これは僕の個人的な感覚なんですけど、さっき言った「感動」って、どちらかというと「我を忘れていないとできないもの」じゃないか、と思っているんです。
その場合、僕の仮説では「コントローラでゲームを動かしているときって、感動はできないんじゃないか?」というのがあるんですよ。
 |
たとえば、ゲームの操作が中心になる「ゲームパート」と、ちょっと感動的な「ムービーパート」に分かれていて、それを上手く組み合わせることが、ひとつの解になるのかなとか。
そうすると、単なる映画よりも面白いものができる可能性はすごくあるな、と思っているんです。でもそれがあまり行ったり来たりしすぎても、ちょっと違うのかな、とか。
小高氏:
そうですね、ゲームと言っても幅が広いので。たしかにガチのアクションをやってる間は泣けないですね(笑)。
もしそういうことができたら、逆に面白いなとは思いますけど。「泣きながらやるアクション」みたいなものも、作ってみたい気はするし(笑)。
一同:
(爆笑)
たちばな氏:
それはスゴイ! そこに「没入」と「体験」の違いがある気がするんです。
「没入」は僕の感覚では、さっき言ったように「我を忘れないとできない」ことで、対して「体験」は「今、自分が体験している」ことを意識することもできるという違いがあると思っているんです。だから、もし「泣きながら戦う」ことができたら、本当にすごいと思います。
小高氏:
ゲームって、何十時間もやったりするじゃないですか。そうすると、どんどん手癖になってくるというか、操作しているという感じよりも、自転車に乗っているような感じになってくる感じがありますよね。
たちばな氏:
なるほど。
小高氏:
最初は操作にすごく気を遣うけど、途中からはぜんぜん気にしなくなる。ゲームを進めていった後半の方で、そういう状態になったら泣けるかなとは思います。
 |
たちばな氏:
たしかに、それはありますね。そのへんをどうやって感動にまで至らせるのか、というのが僕の問題意識なんです。意識がずっと働いていると、無意識まで届かず、なかなか感動までいけないんじゃないか、と。
『デスカムトゥルー』は僕の体感として、後半になるにつれて、選択肢の意味がだんだん少なくなっていく感じがしたんですよ。でも、むしろそれが良かった。
最初のほうにいろんな謎があって、可能性がどんどん膨らんでいるところから、あるところを過ぎると今度は「こうだ」と絞り込まれていくようになる。
そうなると選択を悩むというよりは、自分の意志を込めて「もちろんこっちでしょ!」と選ぶアクションになっていく。その「体験設計」の具合が、本当に素晴らしかったと思うんです。
小高氏:
そうですね。選択肢を選んだ割合を集計したら、みんなけっこう同じルートを通っているだろうな、というのはあります。だから、そこは「風味」で十分なのかなっていう気もしますね。
たちばな氏:
2回目に遊んだ時に、最後のほうの選択肢で、1回目に選ばなかったほうを選んだら、「うーん、それじゃないなぁ」みたいに、あっさり戻されたりもしましたね(笑)。
小高氏:
そこは推理のトコだから、正解は1つしかねぇよ、みたいな。
梅田氏:
たしかに。
小高氏:
まぁ僕としては、「ボタンを押す」だけでゲームだと思っているので。それで十分かなと。
たちばな氏:
なるほど。
 |
インタラクティブになることで、物語に介入できる「ライブ感」を得られる
梅田氏:
たちばなさんは映像サイドから見て、「感動」ということにすごくこだわっているじゃないですか。
たちばな氏:
はい。
梅田氏:
その「感動」は映像だけでもできるものだし、もしその仮説が正しければ、むしろ映像のほうが近道かもしれない、ということもあり得るわけですよね。だけど今、たちばなさん自身はゲームというかインタラクティブ性も、かなり気にしていますよね。それはなぜですか?
たちばな氏:
そこは僕自身も、ずっと考えているところです。だから、求めているのはもしかしたら「インタラクティブ」よりも、「ライブ」のほうが近いかもしれないですね。
梅田氏:
あぁ、ライブ体験。
 |
たちばな氏:
どちらかというと、「ライブ体験的な臨場感を作りたい」というのが、僕の求めていることなんだと思います。ストーリー的な多様性だとか、マルチエンディングに対しての興味とかもあるんですけど、どちらかというとライブ感覚だとか、ライブ体験的なものへの興味と言った方が本質的かもしれません。
──ライブというのは、「今、流行ってるよね」みたいなライブ感ではなく、リアルタイム性を感じるという意味ですか?
たちばな氏:
そうですね。
小高氏:
それは、僕もけっこう近いなと思うところがあって。ユーザーが介入してインタラクティブでやるからこそ、「今この瞬間に物語を紡いでいる」ようなライブ感が出てくるんじゃないかと。
コール・アンド・レスポンスみたいな感触が出るのが、インタラクティブのドラマのいいところなのかな、という気がするんです。だからいっそ、介入の手段はべつに地デジTVのdボタンでもいいのかなと。そんなふうにちょっと介入するだけでも、リアルタイム感が出てくると思うんです。
たちばな氏:
これは僕の職業病的なことかもしれないんですけど、普通のドラマを見ると、明らかに撮影されて編集されて、ある程度の工程を経て出てきているということが、分かるわけじゃないですか。
ともすると「この役者さんは最近、こういうニュースに出ていたな」とか、そういった余談みたいな情報も乗っかってきてしまうわけで。そういうものを取り除いて、もっと強烈にストーリーを体験したい、ストーリーに没入したい、という欲求があるんです。
あとは、僕はもともと舞台がすごく好きなので、役者さんの「生(なま)」のパワーがより届くにはどうすればいいのか、みたいな思いもあります。
事前にいただいた今日のテーマメモに、「作り手はなぜ、ワンカット長回しみたいなものが好きなのか」と書いてあって、すごく面白い質問だなあと思ったんですけど(笑)。でもそれを考えてみた時に、やっぱり「お祭り感」みたいなものを求めているところもあるのかなと。
──ワンカット長回しみたいなチャレンジによって、作り手側が「お祭り感」を味わうことを求めている、ということですか?
たちばな氏:
はい。情報としてのストーリーは変わらないんだけど、自分の中に押し寄せてくる熱量がそのお祭り感でかさ上げされる感じを、僕はすごく求めていて。それを表すのに「臨場感」という言葉がいいのか、それとも「ライブ感」がいいのかは分からないんですけど。
 |
──例えが適切かどうか分からないですけど、僕はもともと、ドワンゴという会社にいたんですけど、そこでよく議論になった話で「1カ月かけて100万回再生される動画」と、「1時間のあいだに同時接続10万人の動画」はどちらに価値がある? というのがあるんです。
僕としては、同時接続10万人のほうが、圧倒的に価値があると思っているんです。なぜなら、そっちのほうが熱量があって面白いから。でもビジネス的に考えると、1カ月で100万人を集めるほうが良かったりもするんです。同時に10万人を集めるのは、1カ月かけて100万人に集めるよりも難しくて、ビジネス的に割に合わないので。
でも1年後を振り返って「あれはスゴかったよね」と伝説的に語られるようになるのはどちらか。と言うと、明らかに同時接続10万人の方の動画なんですよ。
でも、今はネット社会がより進んできたことによって、「ワッ!」と集まるタイミングも増えた一方で、集団がかなりバラけてしまった感じもしています。
昔は『ジャンプ』の発売日だとかアニメの放送時間だとか、1週間に1回みんなで同時に集まる瞬間が、機能的に提供されていたんですけど、今はそれが電子書籍だ、動画配信だと、バラバラのタイミングになっていますよね。
そのために、昔は100万人が同時にワッ! と集まっていたような話題でも、いまは1万人が100個のコンテンツについてそれぞれ話している、みたいな状況になっている。そのせいで、熱量みたいなものが希釈されちゃっている傾向にあるんじゃないかと。
小高氏:
そうですね。
たちばな氏:
その問題はすごくありますよね。YouTuberでいうと「あさぎーにょ」さんという方がいるんですが、2つすごく面白い配信をしていたんです。ひとつは、それこそループしちゃうよっていう、繰り返しちゃうみたいな配信で、もうひとつは生配信的なことをやったんですよ。
小高氏:
あっ、そっちの生配信のほうは見てないですね。
たちばな氏:
そっちはあらかじめ作った映像を出しつつ、生で配信もしてコメントも拾うというものでした。両方とも素晴らしかったんだけど、特に後者の生配信でやった動画はもう発明的だなと思って。でも、そっちは生でなければ意味がないから、もう見られないんですよ。
──そうですね。
たちばな氏:
だから結果的には、1つめのループする配信はどんどん拡散されていった一方で、生配信のほうは同時接続で3万人ぐらいが観ていたんですが、それはそれでスゴイんだけど、それ以上伸びなかったところがあるんです。個人的にはなんか悔しい気がしたというか、もちろん両立するのがいちばんいいんでしょうけど、ライブなほうがビジネス的な理由で選択されない方向に進んでいくのは認めたくないなって。
 |