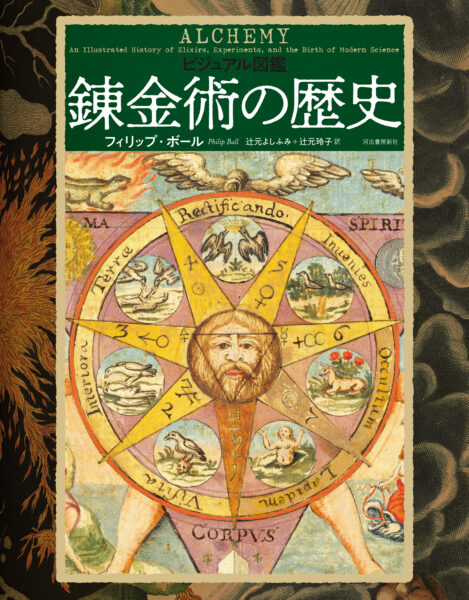主人公がプレイヤーの「1.5歩」先を歩くことで、物語を誘導できる
──『デスカム』は最初の導入が面白いですよね。プレイヤーの情報と、主人公の情報が一致している状態から始まるじゃないですか。どちらも何も分からない。ああいう見せ方は、すごくゲーム的だなぁと思います。
 |
たちばな氏:
そうですね。
小高氏:
最初に警察官が来るじゃないですか。その次にまた警察官が来る。あそこまでの展開は、自分でもめちゃめちゃゲーム的だなと思います。
最初に長々と、主人公はこういうヤツで、こういう状態でというのを説明せずに、できるだけすぐに、最短距離で選択肢が出てくる。そこまではシナリオというよりはチュートリアルであって、ゲームのレベルデザイン的な感じで作られているからでしょうね。
たちばな氏:
ゲームってやっぱり「主人公になれる」というのが、スゴイことだなと思うんです。でも『デスカム』はどうだったかな? と思い返してみると、主人公になっている体験は半々ぐらいなのかなと。
──『デスカム』は一人称に寄っているようで寄っていないというか、なんだか絶妙なバランスですよね。カメラは三人称視点なんだけど、モノローグが入って、選択肢を選ぶときは一人称視点になるという、すごく不思議な作りで。
小高氏:
時にはしゃべり出し、時には自分で動かす、というその主人公の置き方がゲームっぽいのかもしれないですね。
──主人公とプレイヤーをどこまで一体化させたかったんですか? 完全に一体化するといいうよりは、一歩引かせていた気もするんです。
小高氏:
カラキマコトという人物がいる、これがベースにはなっています。そこにときどき、プレイヤーがカラキマコトにシンクロできるような余地を入れた、みたいな感じですかね。
 |
──ということは完全にシンクロさせようとはしていない?
小高氏:
そうですね。
──それはなぜなんですか?
小高氏:
なんていうか、主人公がプレイヤーの「1.5歩ぐらい前」を歩いているのがいちばん気持ちいいなと、思っているんです。主人公とプレイヤーが足並みを揃えちゃうと、けっこう退屈なヤツになっちゃうなと思うので。
感情の線もそうですよね。「ここで泣くんだ」とか、「こいつはここで怒るんだ」とか、それが1.5歩ぐらい離れていると、感覚的にいちばん気持ちいいな、と。そこを横並びにしちゃうと、ちょっとつまんないなぁと思うんです。
──でもそれはアドベンチャーゲームの文法からすると、ちょっと異質な感じがしますね。 普通のアドベンチャーゲームはもうちょっと主人公と一体化させようとしている気がします。
小高氏:
モノによりますかね。それこそギャルゲーなんかは一体化していますけど、『逆転裁判』【※1】や『探偵 神宮寺三郎』とかは、ちょっと違いますよね。ああいうのはもうちょっとキャラが立っていて、まさに1.5歩先を歩いている感じですよね。

(画像はCAPCOM:逆転裁判123 成歩堂セレクション 公式サイトより)

(画像はNintendo Switch|ダウンロード購入|探偵 神宮寺三郎 プリズム・オブ・アイズ 〜ふた色の少女〜より)
──たしかに。
たちばな氏:
確かに。さっきもちょっと言いましたが、『デスカム』の後半は「この選択肢はもはやこっちでしょう」という感じを味わいましたね。主人公にそう誘導させられているのか、自分が自発的にそう思ったのかは客観的には分からないんですけど、その塩梅が良かった感じはしていますね。
小高氏:
もしかしたら、僕がもともとミステリーをやっていたから、そういう作りにしているのかもしれないです。
さっき挙げた『神宮寺』や『逆裁』って、基本的に謎解きゲームじゃないですか。だから、もしプレイヤーと成歩堂君が同じ目線に立っちゃうと、謎解きが分かんなくなっちゃうかもしれないんですよ。成歩堂君がプレイヤーをちょっと引っ張ってあげて、それで成功して「やったね!」と肩を組んでくれるぐらいが、ミステリーとしていちばん気持ちいいというか。
 |
成歩堂君が引っ張ってくれるんだけど、プレイヤーがいかにも自分で解いたかのように物語が進んで、「オレたちは一心同体」みたいな気持ちにさせてくれる。これが2歩離れちゃうと、一心同体感がなくなるし、横並びだと2人とも「分かんないね」って話になっちゃうので(笑)。
たちばな氏:
そうなんですよ! 『デスカム』も本郷さんの役が後半、だんだん成長してきて「いい男」になってきている感じがあるじゃないですか。そのあたりから主人公が、ちょうど自分の半歩前ぐらいをいく感じになっていて。
──たしかに。だんだんと頼れる感じになっていきますよね。
たちばな氏:
「こうなってほしい」という、ちょうど半歩先を行ってくれていて、しかもそれを表現するような選択肢が出てくるので、「そうだ、行けー!」みたいな感じになるんです。
いろいろ迷って選択するというよりは、ちょうど半歩先を歩いている相手を、熱を持って応援するみたいな感じで。その感じが本当に素晴らしかったんですよ。
小高氏:
アドベンチャーゲームでもやっぱり2種類ありますね。分岐系のゲームを作る人はたぶん、もっといくらでも分岐できるようにするんでしょうけど、僕はもともと一本道のゲームを作っているので、僕自身の中でも明確に「こっちが正解ですから」というのがあるんです。
それを主人公にも与えちゃっているというか、そういう作りにはしちゃってますね。もっとフワッと分岐する作り方も、できるっちゃできるとは思うんですけど。
「ボタンを押す」だけでも、それはゲームだ
小高氏:
これが分岐系のゲームだと、最後まで「あなたが選びなさい」みたいな感じに特化するんでしょうけど。
たちばな氏:
だからその半歩先感が、僕が言っている「没入感」みたいなものとつながっているんですかね。いろんな可能性がありすぎると逆に、そういう没入感が得られないというか。
 |
梅田氏:
あぁ、そうですね。
小高氏:
そういう意味ではやっぱり、「『バンダースナッチ』があったから」というのがあるかもしれないです。『バンダースナッチ』はどちらかというと分岐系のゲームというか、「お好きにどうぞ」みたいな感じだけど。
それだと僕は突き放されているように感じちゃって、ガッとのめり込めなかったんです。だからそうじゃなくて、自分の得意な「一本道だけど選択肢があるもの」に持っていこうと思った、というのはあるかもしれないですね。
──「一本道だけど選択肢があるもの」というと、選択肢の意味がないような気もするんですが、なぜそれが有効になるんですか?
小高氏:
うーん……そうですね。ちょっと感覚的なところが強いので、答えになっているのか分かりませんが。
僕はページ送りをするだけでも、それだけでゲームになると思ってるんです。たとえば、このタイミングでこのセリフのページ送りをさせる、とか。
──なるほど、ページ送りしたときに効果音が鳴ったりとかもですか。
小高氏:
そうですね。あとは『ダンガンロンパ』のシチュエーションでもありましたけど、自分とずっと仲の良かった人間がすでに犯人だと分かっているんだけど、それを「プレイヤー自身の手で、あえて犯人として選択させる」とか。
本当は選択したくないんだけど、こいつを犯人と言わないとゲームが進まない。その「本当は選択したくない、でも選択しないといけない」という気持ちになるだけでもゲームだと思うんです。だから「選択肢=迷うこと」ではないですね。
梅田氏:
「答えはこれだ」と分かっているけど、「それを選びたくない」という感情があるだけでもゲームになるということですよね。
 |
小高氏:
そうですね。逆に、「どうしてもこれを選びたい」というのもゲームです。
たちばな氏:
「いけー!」って、プラス1個、自分のパワーを送るみたいな感情ですよね。
小高氏:
そうですね。応援するとか、「いいね」する、みたいな(笑)。
──アドベンチャーゲームの歴史は古いですけど、昔のゲームのほうが、主人公とプレイヤーが一致しているんですよね。
小高氏:
そうですね。
──ただそれだと、難しいしマニアックなんです。でも、最近ヒットしたアドベンチャーゲームって、『ダンガンロンパ』もそうですし、『逆転裁判』もそうですけど、従来のアドベンチャーゲームをあまり好きじゃない人に受け入れられたところがあって。それはなぜだろう? という疑問があったんです。
今の小高さんのお話を聞いて、主人公が半歩前をリードして引っ張ってくれるという「受け身でも遊べる感じ」が、もしかしたらひとつのキーだったのかなと思いました。
だからたちばなさんもおっしゃられているように、インタラクティブな映像も「選ぶ」とか「分岐する」とかよりはむしろ、物語を引っ張っていってくれる主人公に対して「ボタンを押す」ことで乗っかれるとか、そういった方向のほうが相性がいいのかな、とは思いますね。
たちばな氏:
そうですね。僕もそういうところはすごく感じました。
 |
でも昨日、ゲームに詳しい友人に小高さんの話を聞いたんですけど、「エモさまっしぐらな人ではない」みたいに言われて(笑)。
一同:
(笑)
たちばな氏:
そのときは「あぁ、そうなんだ」と思ったからこそ、今のお話を聞いて余計にスゴいなと思いました。もちろん、もっとバリバリにゲーム脳で、みたいな作り方もあるとは思うんですけど。
梅田氏:
「没入感」という意味だと、小高さんも先におっしゃってましたけど、選択肢が複雑になって「これで合っていたのか?」みたいになって、没入感を削ってしまうことはあるでしょうね。
小高氏:
そう、それは最近の『ライフ イズ ストレンジ2』や『Detroit』の頃から、すごく思うようになって。もう選択肢を選んだ瞬間に「あっちのほうを選び直したい」って、すげぇ気になっちゃって(笑)。難しいですね、それが面白いところでもあるし、それでいいのかとも思うし。
映画ではなくTVドラマのスタッフが、日本オリジナルのNetflix作品を作るべきだ
──たちばなさんからのたくさんご質問をいただいたので、逆に小高さんのほうから、何か聞いてみたいことや相談したいことはありますか?
小高氏:
そうですね……どうすればライトユーザーに届くんですか? ライトユーザーってどこにいるんですか? どこにいて何を見ているんですか?(笑)
たちばな氏:
どこにいるんですかね。でも、確実に分散していますよね。
小高氏:
もうテレビにいるだけじゃないですよね。
たちばな氏:
それで言うと、僕にはゲームという世界の人口がよく分からないんですけど、少なくはないはずですよね?
──ゲームは広く捉えたら、メチャクチャ多いと思いますよ。
たちばな氏:
そうですよね。だから十分じゃないかって思うんですけど、一方でそれ以上に届けるとなると、あとはテレビ的なところと、ネット的なところですよね。
それが地上波のテレビを見ている人たちと、NetflixやAbemaを見ている人たち、みたいになるんですかね。
 |
小高氏:
やっぱり映画館に行くのとNetflixで見るのとでは、見る側の気持ちは違うものなんですか?
たちばな氏:
僕個人でいうと、映画館の最大の良さは大画面でも音量でもなく、“集中度”だと思うんです。上演中は見ることに集中できる空間にいられるというか。
小高氏:
『カメラを止めるな!』が、まさにそれを使ってましたもんね。自宅のテレビだったら、前半のクオリティが低いところで、見るのを止めちゃうわけじゃないですか。
たちばな氏:
このあいだ大友啓史監督と対談した時に、映画館の話になったんです。今、映画館がヤバいという時に、映画とは何なのかをもう少し考えて、「映画」と呼んでいるもの全部をもし守れないとしたら、何を守りたいのか、何を残したいのかを考えるべきなんじゃないかと。
もう映画作品自体は、ウィンドウがどこであろうと構わなくなっているので、べつに映画館じゃなくても観られるわけです。
でも、結局みんなが行き着くのは、映画館での「体験」なんですよね。それはすごく分かります。だから僕としては、単純に両立してほしいなと思うところです。
小高氏:
映画監督が映画っぽい作品を、Netflixオリジナルで作るというケースのあるじゃないですか。でも僕の中では、配信サービスの作品はどっちかというと、テレビ的な作りなのかなと。
さっきもたちばなさんがおっしゃっていたように、映画って「逃げられない」じゃないですか。その一方でテレビの場合は、「ツカミ」がないとダメなんです。
そう考えると、Netflixってやっぱりテレビなんじゃないかな、という気がしていたんですけど、実際どうですか? テレビの作りをやるのか、それとも映画っぽく作っちゃっていいのか、それともどっちもアリなのか。
たちばな氏:
そこは超面白くて、難しいところなんです。簡単に言うと、コンテンツ的にはテレビ的なものなんだけど、今実際に作っているのは、映画の人たちなんですよ。それは映画のクオリティがほしいから、という理由なんですけど、僕はテレビの制作会社が作ったほうが良いと思っているんです。
本当は、連続ドラマの名プロデューサー、名ディレクターみたいな人が、Netflixで面白いものを作って世界に出すほうがいいはずなんですよ。10時間のドラマを作るときのチームとしてのタフさ、みたいなことも含めて。
そういったことに関して、経験値的に言っても、テレビドラマを作っているチームは、ポテンシャルがすごくあると思うんです。
 |
小高氏:
イッキ見できる連ドラ、というのが、Netflixとかのいちばん強いところなんじゃないかなって気がするんですよね。
たちばな氏:
ホント、そうなんですよ。
小高氏:
昔の日本のテレビドラマだと「とりあえずヒキを作っておけ」みたいな作り方がよくありましたよね。『キン肉マン』のゆでたまご先生的な発想で(笑)。1時間放送の最後のほうで、急に誰かが死にかけたり。この間の『あなたの番です』【※】なんかは、まさにそれですよね。
※『あなたの番です』
2019年4月〜9月に日本テレビ系で放送されたミステリードラマで、原案・企画を秋元康氏が担当。前半となる第1章のラストから、衝撃の展開が第2章に持ち越されるなど、クリフハンガー的な展開が話題を呼んだ。
たちばな氏:
そうですね。
小高氏:
あの「連続でイッキ見できる」という特性は、むしろ今は韓国ドラマとかのほうが上手く使えているんですか?
たちばな氏:
どっちかと言うと、イッキ見という文化が世界で主流だったことが不思議というか。
連続ドラマの世界で言うと、「反応を見ながら変えられる」というのが、1週間ごとに放送している良さとしてよく言われていますね。でも実際には、大して変わらないんですよ。
梅田氏:
そりゃそうでしょうね(笑)。
小高氏:
間に合わないですよ、普通に考えて(笑)。
たちばな氏:
そうなんです。でも韓国ドラマでは実際に変えているみたいで。『愛の不時着』【※】は超好評だったから、北朝鮮からの脱出を2話分延ばした、とかいう話があるんです。
現実的な話をすると、いちばん大きいのは、役者さんがプロモーションに出てもらえることですね。毎週撮影して追っかけで出していると、そこで役者さんのスケジュールが押さえられているので。
逆に映画でいちばん大変なのはそういうプロモーションなんです。撮影が終わった1年後に公開されるとして、そこにもう一回、役者さんのスケジュールとやる気を持ってきてプロモーションするのは、すごく難しいんですよね。

(画像は愛の不時着 | Netflix (ネットフリックス) 公式サイトより)
──なるほど。
たちばな氏:
役者さんによっては、撮影の時とは髪型が変わっていたりもするし(笑)。
連続ドラマの場合はそこが一致しているから、プロモーションがやりやすいんです。放送時期にバラエティ番組とかに宣伝で出るとかも計画しやすいし。あと今は出演者のSNSとか個人のメディアが重要だから、リアルタイムで撮影していると役者さんが自分たちのSNSで「撮影現場でこんなことが」とか臨場感のある情報をアップしてくれて、そういう意味でもPRがしやすいんです。これが結構大きくて。
梅田氏:
なるほどね。それはそうだ。
たちばな氏:
イッキ見という形だと、それを削らなきゃいけないから、そこの短所は大きいんじゃないかなぁと、僕は思っていたんですけどね。
リアリティショーが流行する理由は、フィクションを超えたライブ感にある
──ぜんぜん関係ない話になっちゃうんですが、いま「リアリティショー」が全世界的に流行ってるじゃないですか。あれはなぜなんですか?
たちばな氏:
なぜなんでしょうね。「すごく象徴的だな」と思ったのは、まだ『テラスハウス』がやっていたときの話ですけど、日本のNetflixの人気ベスト10に韓国ドラマが2つ、3つ、アニメが5つ。あとの残り2つぐらいがリアリティショーだったんですよ。
『テラスハウス』と、あともう1個、アメリカでスゴイのがあったんですよ。『ザ・ジレンマ』【※】っていうリゾート地で男女10人ぐらいが一緒になり、はたして禁欲の1カ月を過ごせるか、みたいな番組が(笑)。
 |
日本のドラマは1個も入らず、アニメと韓国ドラマとリアリティショーだったという。そしてリアリティショーが強いのはやはり「ライブ感」が理由だとは思いますね。予測のつかなさとか、功罪も含めてSNSで伝播していく感じとか。そういうものを含めたライブさなんでしょうかね。
※『ザ・ジレンマ』
Netflixで配信中のリアリティショー『ザ・ジレンマ:もうガマンできない?!』のこと。海辺の楽園で共同生活を送る独身男女が、1カ月間禁欲生活を送らなければ賞金10万ドルを手にできないという内容。
──Abemaなどでも似たようなリアリティショーをやっていて、それなりにヒットしているんですよね。そうすると内容の如何を問わず、リアリティショー自体がひとつのフォーマットとして優れているんだな、というのは感じるんです。
では、そのフォーマットたる所以はどこにあるんだろう、何がそのフォーマットの軸の要素なんだろうというのが、すごく気になっているんです。たとえば、脚本の作り方がぜんぜん違うのか、それともTwitterでその演者がしゃべったりすることなのか。
たちばな氏:
ドラマ業界でよく話されるテーマのひとつに「ラブストーリーが作られなくなった」というのがあるんです。今は月9ですらラブストーリーを作らなくなった時代と言われていて。
ひとつは、「大きな物語」がもう成立しないということ。みんなでお茶の間に集まって、ひとつの物語を共有することがもうなくて、個々の「小さな物語」に細分化している、という話がまずありますよね。
それに加えて、時代を代表する2大スターの「この人とこの人のラブストーリー」にみんなで乗っかる感じではなくなって、スターの人気も分散化している。そういったいくつかの理由からラブストーリーが作られなくなって、代わりに群像劇的なドラマがすごく多くなっている。
海外ドラマはさらにそういう傾向が強くなっていますね。「映画スターが出ない」という状況下で企画を打たなければならないし、長く作る前提なので、プロットラインがいくつもある。そういう理由からではあるんですが、一方で時代的な価値観の多様化とかも相まって、それぞれの視聴者が各々の「共感できる人を選ぶ」という感じで見やすいんじゃないかと思います。
梅田氏:
なるほどね。
 |
小高氏:
フィクションって、見ている人からしたらやっぱり疲れますよね。フィクションである以上は、フリもあるからオチもある。だから、ちゃんと理解しながら進んでいかなくちゃいけないので。
でもリアリティショーはフィクションじゃないから、なんでもアリじゃないですか。でも恋愛が入っていたり、ケンカが入っていたりするから、バラエティ感覚で見られるフィクション、みたいな感じなんですかね。
たちばな氏:
それはあると思います。たしかにラブストーリー的な要素もあるんだけど、今、小高さんの話を聞いて思ったのは、「対立」のリアリティがやっぱり大きいのかなと。だからこそ炎上とかもしてしまうわけですけど。
リアリティショーってやっぱり、「対立」がワクワクするわけですよ。フィクションだと予定調和というか「演じてるんでしょ」となるんだけど、リアリティショーではそうじゃない。生々しくぶつかっている感じに、ワイドショー的にドキドキできるという部分はありますよね。
──その理屈でいうと、格闘技とかももっと流行りそうなものですが、どうなんでしょう?
梅田氏:
総合格闘技が流行ったのは、よりリアルを求めるという意味でそういうところかもしれないですね。
小高氏:
それもやっぱりプロレスという「フィクション」を楽しめなくて、単純にその瞬間、その瞬間の刺激を求めているというか。
梅田氏:
そうですね、その瞬間の瞬発力みたいなものはたしかに、フィクションの壁を通さないリアルのほうがありますよね。
 |
たちばな氏:
フィクションだとどうしてもね、ウソっぽくなっちゃうっていうのはあるので。それをどう打破できるかということが、僕のテーマとしてはいちばん大きいですね。
──たちばなさんは、最近で完全フィクションで感動できたものってありますか?
たちばな氏:
完全フィクションというのは、映画的なものですか?
──実話ベースではなくフィクションベースのもので、すごく感動できたものって、いま何があるのかなとふと思いまして。自分でもちょっと考えたんですけど、あんまり思いつかなかったんですよ。
たちばな氏:
ゲーム的なものでいうと、この間マーダーミステリーで号泣したんですよ。フィクションだと……フィクションは意図的にあんまり見てないっていうのもあるんですけど、まぁでも『愛の不時着』か(笑)。
『愛の不時着』はね、これも語りだすと長いんですけど、今まで言ったことを吹っ飛ばしちゃうんですよ。「これでいいじゃん」っていう(笑)。
一同:
(笑)
たちばな氏:
もうコテコテで。でもノックダウンされちゃう。
梅田氏:
僕が最近感動した完全フィクションは『梨泰院クラス』【※】ですよ(笑)。

(画像は梨泰院クラス | Netflix (ネットフリックス) 公式サイトより)
たちばな氏:
でしょ? いやもう、そうなんですよ。
梅田氏:
何かあります? 最近の作品で感動したもの。
小高氏:
いやぁ……映画館に行けなくなっちゃいましたからね。 絶対量が少なくなっちゃって。
梅田氏:
あぁ、そうですよね。
『デスカム』がヒットしなければ、日本では「インタラクティブムービー」はもう無理だ
小高氏:
どうすればライトユーザーにプレイされるのか。結論:「答えは出なかった」。
一同:
(笑)
たちばな氏:
あぁ、そうか。ライトユーザーの話でしたね。
小高氏:
Netflixを見てる人たちって、ライトユーザーなんですか? けっこうみんな見ているので、コアまではいかないと思うんですよ。
たちばな氏:
そんなにみんなが見ている印象ってあります?
 |
小高氏:
まぁ、僕の周りの界隈はみんな見てますね(笑)。
──今、Netflixの会員数はどのぐらいなんですか?
たちばな氏:
数字は出してないんじゃないでしょうか。僕もぜんぜん知らないです。
──1年ぐらい前の時点でざっくり300万人みたいな話は、聞いたことがありますね。
小高氏:
日本だけで? やっぱり多いなぁ。
──だから今は500万〜600万ぐらいなのかなぁ、と勝手に想像しているんですが。
たちばな氏:
1年前で300万だったら、少なくとも500万は突破していると思いますね。
──でも1年前は「まだまだだね」というぐらいの感じでしたよね。動画配信サービスの規模で言えば、国民の全体のシェアから考えたら300万人ってまだまだの大きさじゃないですか。
小高氏:
NetflixやAbemaを見ている人は、テレビやYouTubeを見ている人よりも、やっぱり意識が高いと思うんですよ。ということは、NetflixやAbemaで『デスカム』のCMをやればいいんですかね?
──意識が高いというと、具体的にはどういう人たちに届けたいんでしょう?
小高氏:
たぶん、テレビを受け身で見ている人は、そのまま動かないと思うんですよね。AbemaやNetflixだと自分から積極的に見ている気がするから、もうちょっと効果があるのかなと。
だって、迎え打つ気が満々のような感じがするじゃないですか。「面白いのをよこせ!」って(笑)。
梅田氏:
Netflixの中でCMはやってないから、やっぱり『デスカム』自体をNetflixに載せるしかないかな、って気はしますけど。
 |
──『デスカム』の実績をある種のテコにして、それこそNetflixで、1本につき1時間ぐらいで体験できる、いろんなシチュエーションのアドベンチャーシリーズをやるとか。
そんなふうに世界に向けて、日本のゲームクリエイターが映像に対してこういうことをやるよ、というのを打ち出すぐらいのほうがいいかもしれないですね。
梅田氏:
Netflixから巨額のお金をもらって、ゲーム側は「自由にやらせてくれ」って言うとか。
──映像に対してインタラクティブなことができるようになる「仕組みそのもの」は、たぶんこれから、なんかいろんなところで実装されていくとは思うんです。
だから今後、それだけでジャンル化するぐらいになってほしいんですよね。Netflix 2.0みたいな次世代サービスが出てきたときには、そういうアドベンチャー機能が強化されていて、もう一大ジャンルになっているような。
たちばな氏:
そうですね。でも僕としては、その立ち上がりはボトムアップだと思っています。そういうものの傑作が生まれるのは、テレビ的なところよりはインディーズじゃないかという気がしていて。
結局、マスっぽいものはやっぱり「そつがない」というか。そこで出さなきゃいけない結果とか、そこのルールみたいなものにアジャストさせていく間に、どんどん「良さ」が失われていくというか。でも、可能性自体はすごくある気がしているんだよなぁ……。
小高氏:
『デスカム』は本当にインディー的なつくりで、報酬も現物出資でやってたりするんですよ。みんな売れた分の何パーセントみたいな感じで、やっていて、じつは僕もお金はまだもらっていないんです。
 |
この形はゲームだとなかなかないですよね。
──それもスゴイ話ですね。
小高氏:
『デスカム』はそこまでして、本当にせめぎ合いの中でやっているんです。
梅田氏:
そう(笑)。みんなギリギリで。
小高氏:
そういう意味では『デスカム』が、いちばんギリギリでビジネスで成立するラインだと思うんですよ。これが上手くいかなかったら、たぶんどんなものをやっても上手くいかねえなって。
これよりもっとお金をかけてやったところで、絶対に上手くいかないし。これより小さくなっても上手くいかないし。
たちばな氏:
なるほど。ヤバイ!(笑)
小高氏:
まぁ宣伝という意味では、まだまだ弱いところはあったかもしれないですけど。
──『デスカム』が前例のない「挑戦である」ということは、僕らとしても、もっと伝えていかないといけないですね。さっき言われていたように、小高さんたちがある種の持ち出しに近い形でやっているとか、いわゆる「受け身」の仕事でやってるわけじゃないよ、というのはもっとアピールしたほうがいいなと。
小高氏:
そういう意味では、これが失敗するようでは「インタラクティブムービー」というものは、日本ではもう無理な気がします。それで海外でバカみたいに流行って、それが日本に入ってきて、ようやく日本もやろうかなみたいな感じになるという(笑)。
──そのときに「なぜ日本ではできなかったのか」みたいな話になるんですよ。いやいや、やってたから!(笑)
小高氏:
そういう羽目になるぞ、という(笑)。
──でも、本当にそうですよ。インタラクティブムービーとかインタラクティブドラマって、今、日本が世界に先手を取れるジャンルのひとつだと思うので。
たちばな氏:
僕も本当にそう思いますね。(了)
 |
インタラクティブな映画という試みは、映像業界とゲーム業界の双方で、かなり古くから試みられてきたジャンルだ。レーザーディスクやCD-ROMといった、ランダムアクセスが可能なメディアの登場した1980〜1990年代には、いくつものタイトルが発売されたし、DVDのマルチアングル機能やチャプター機能を使ったゲームもリリースされている。だがそれらは、「映画」と呼ぶには画面のサイズや解像度が乏しく、「ゲーム」と呼ぶには操作の快適性が乏しかった。
『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』や『デスカムトゥルー』を実際にプレイしてみると、2020年の今になってようやく、真にインタラクティブな映画と呼べるだけの技術を実現できていることが実感できる。だが一方で現在は、人物を含めたあらゆる存在が、本物以上のリアリティを持ったCGでゲーム内の空間に表現できる時代になっている。だからこそ、実写映像を使ったゲームを制作する際には、今回の鼎談で何度も話題に出たとおり、「実写である意味」を問われることになるだろう。
映画をはじめとする映像作品と、ゲームの双方を同じように愛してやまない筆者としては、たちばな氏の言うように、将来的に「すべてがゲームになる」のかどうかは分からない。だが映画には映画の良さが、ゲームにはゲームの良さがあるように、その2つを融合させたジャンルの良さというのも必ずあるはずだ。ゲームの持つドライブ感と、映画の持つ感情移入の双方を持ち合わせている『デスカムトゥルー』は、その可能性を確かに感じさせてくれている。
だからこそ、2020年に『デスカムトゥルー』が改めて切り拓いたチャレンジは、これから先も続けられていくべきものではないだろうか。
【この記事を面白い!と思った方へ】
電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。
頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応
※クレジットカードにのみ対応
【あわせて読みたい】
なにが「映画」を「ゲーム」たらしめるのか。『Death Come True』が映画の禁じ手を打ち破って表現した「ゲーム的な映画」という新感覚の正体とはそれはアドベンチャーゲームの開発を経験したクリエイターだからこそできる、新しい表現といえるかもしれない。我々は映画がゲームになる瞬間を、本作で目撃するだろう。