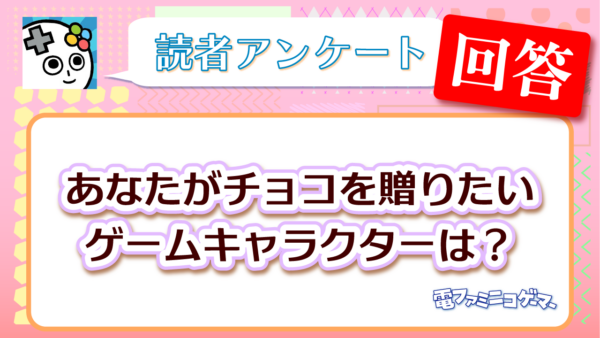『プロセカ』のおかげで、KAITOやMEIKOのボイスに改めて労力をかけることができた
──バーチャル・シンガーの表現についてお聞きします。これまでだとライブのMCでちょっとしゃべるみたいなものはあったかもしれないですけど、『プロセカ』のように長いセリフを、しかもドラマとして説得力のある形で話すというのは、かなりのチャレンジだったと思いますが?
佐々木氏:
そういった試みをやっていかなきゃ、となったのはけっこう昔のことなんです。それこそミクがファミリーマートさんのキャンペーンをしていた(※注:2012年~2015年)後期から始まっていて。その頃は「ミクでアニメをやりませんか?」「ドラマをやりませんか?」「ラジオに出てもらえませんか?」という要望があって。当時は無茶だと思っていたんですけど、同時に需要もあるんだろうなと思ってました。
それでもミクは「初音ミクシンフォニー」というイベントの中でそこそこしゃべったりしていたんですけど、MEIKOやKAITOは非常に難しくて。
そんななかで『プロセカ』の企画が出てきて、この企画を成立させるために、KAITOとMEIKOにもきっちりと取り組んで、人も手もかけることができたんです。それはセガさんと近藤さんのご提案の中で理由をつけて、社内に通せたところなので。普通だったらそこに、これほどの労力をかけることは難しかったですから。なので『プロジェクトセカイ』は、僕らにとってもすごく捻くれた勝負のプロジェクトというか、ゲリラと言うか……振り返ったらちょっと寒気が(笑)。
 |
小菅氏:
クリプトンのみなさんには、本当にいろいろと動いてもらっていますから。ここまで制作していただいているのは、他の作品ではできないなと思います。
近藤氏:
ボイスもちょっとずつ進化していて。いちばん最初に作ってもらったものと今とでは、声の自然さもぜんぜん違っていますね。もしかしたら今後、音声を差し替える部分もあるかもしれないですけど。
佐々木氏:
もともとはクリエイターさんがボイスや発声を作り込んで、多種多様な歌があるという文化なので、こういうふうに我々が「やってますよ」と言うのも珍しいんですけどね。我々には我々の試みがあるし、作家さんには作家さんの試みがあるし、両方とも受け入れられる世界になったなと。これが10年前なら大炎上だったと思いますけど(苦笑)。
 |
──しかも単にキャラクターがしゃべるだけではなくて、セカイごとに性格付けも違うじゃないですか。以前のインタビューで話題に出た「アッパーなミクさん」だとか。そのあたりはどのように試行錯誤されたのでしょうか?
佐々木氏:
Colorful Paletteさんのほうで表現したい世界観の中にいる多種多様なミクのイメージが、ドラマにおじゃまさせてもらうというか、次元の違う存在として雰囲気を出していくというところでチューニングしていったら、自然とそういうふうになっていった感じですね。ニュアンスやテイストというのはどちらかというと、現場の若いスタッフさんが「ここなんじゃないか」というところに、制作のおじさんが合わせていくスタイルなので(笑)。
小菅氏:
「ミクがセカイごとに違う」と言われて、最初は「それを3Dで全部作るんですよね?」と思いました(笑)。「マジか!? でもやろう」と。
バーチャル・シンガーたちが、ストーリーの中でちゃんと役割を持っている
 |
──『プロセカ』の物語は、まず最初に5つのユニットごとのメインストーリーとバーチャル・シンガーたちのストーリーがあって、そこにイベントストーリーという形で、新しい物語が追加されていく形ですよね。その中で各ユニットのイベントストーリーに関しては、メインストーリーから続く少し先を描く形で進んでいると思うのですが、それだけではなくて学校や街を舞台にして、ユニットを超えたキャラクターの交流みたいなものも、少しずつ描かれています。それは今後どういう方向になっていくのでしょうか?
近藤氏:
基本的にはユニットごとのストーリーがあって、それを軸にして進んでいく形です。ストーリーに関しては、キャラクターたちの成長を描いていくというのが根底にあるので。だとすると、彼ら彼女らが壁に当たった時に、その壁を越えるために自分自身でいろいろと考えるかもしれないし、誰かの一言からの気づきがあるかもしれないし。その中でバーチャル・シンガー、つまりミクさんたちの言葉からの気づきがいちばん多いと思うんですけど。
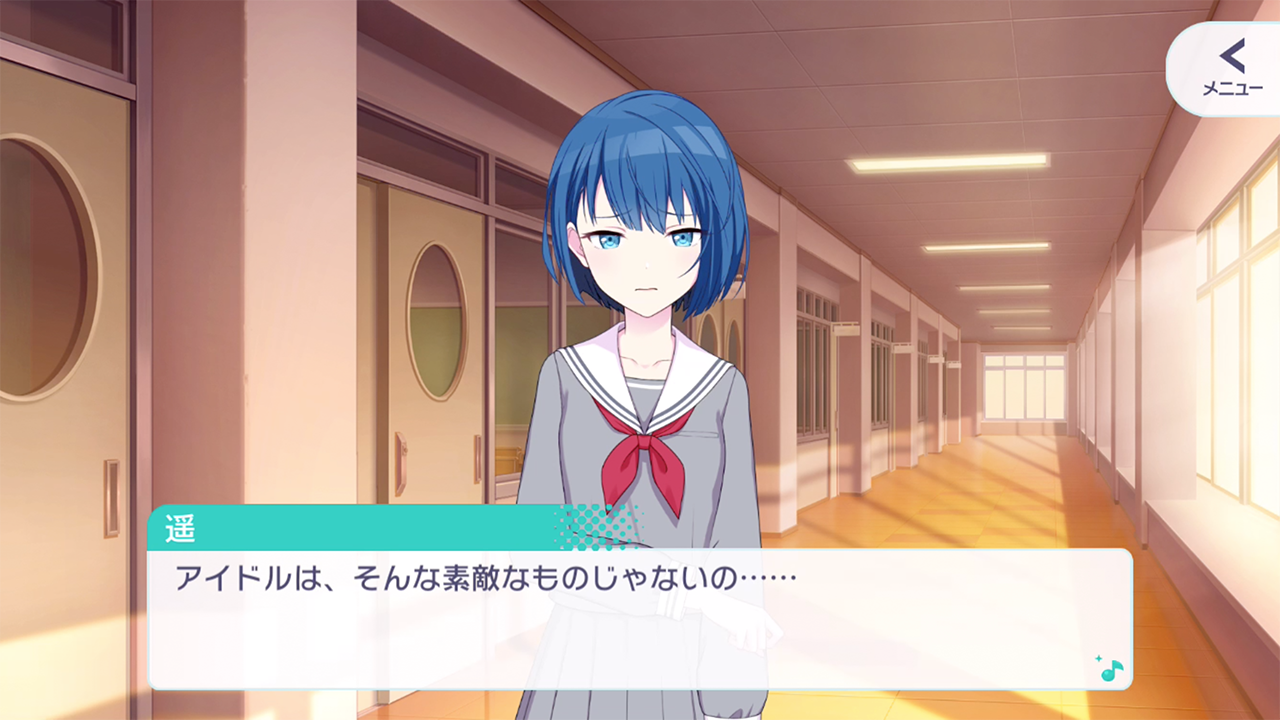 |
でも普通に考えると、すごく閉鎖的なコミュニティの中だけで、そういうものがあるわけではないじゃないですか。バイト先の先輩から言われるかもしれないし、学校の友達から言われるかもしれない。ユニット混合のイベントはそのあたりを開放して、各々のキャラクターが他のユニットのキャラクターと触れあって、それぞれが自分たちのユニットに持ち帰っていくという考え方ですね。今後もそういった形で続いていくと思いますし、だから最終的にはおそらく、全員のキャラクターが知り合いになるかもしれません。
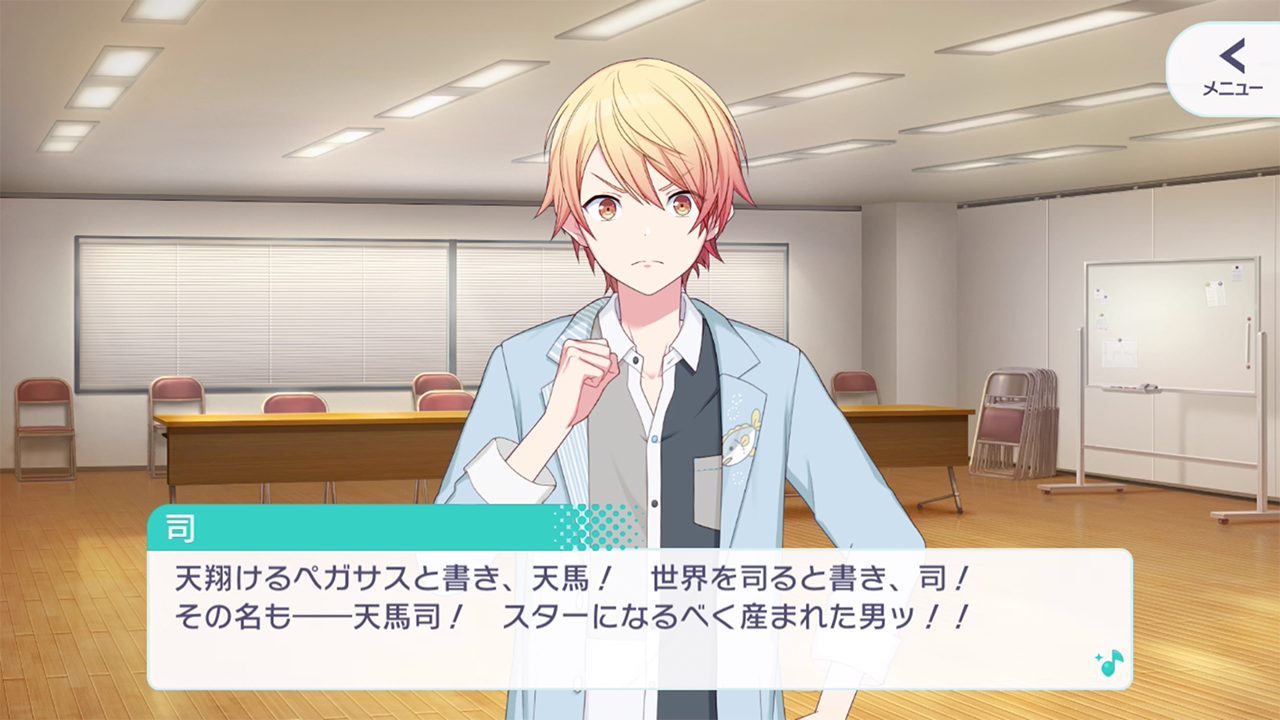 |
──ゲームをプレイすることによってだんだんと、あの20人のキャラクターたちが生活しているシブヤの街、みたいなものが見えてくるのが、すごく魅力的だなと思うんです。キャラクターごとのサイドストーリーに、意外な人間関係が隠れていたりとか。
近藤氏:
そうですね。サイドストーリーも含めると、どこにどのキャラクターが出てくるのか、けっこうサプライズなところもあったりするので。
──個人的な感想になっちゃうんですけど、この半年間のイベントの中だと、自分は体育祭のストーリー(「走れ!体育祭!~実行委員は大忙し~」)が好きなんです。あそこまで性格が真逆なキャラクター同士だと、むしろ仲良くなるんだ、みたいな。
 |
近藤氏:
えむとまふゆですか。あの2人を仲良くなったと言っていいのかはアレですけど(笑)。でも、そういう関係性も面白いなと思います。
──あと、ミクさんが普通に体育祭の応援に出てくるというのも楽しくて。
近藤氏:
バーチャル・シンガーたちが現実世界に出てくる頻度は、ちょっとずつ上がっている気がしますね。
佐々木氏:
これまではミクがすごく人気で、他のキャラクターはミクほどの人気はないよね、と協業先からも思われやすかった中で、『プロセカ』の中ではMEIKOの出番をすごく気づかってくれていたり、レンやKAITOにこんなに需要があったんだ、みたいなバズり方をしてくださったりするので。クリプトン的には今までMEIKOやKAITOにあまり手をかけられていなかったところもあったので、「報われたね、良かったね」と草葉の陰から見ています(笑)。
──MEIKOに関しては、『プロセカ』のプレイヤーの間で「MEIKO姉さん」という敬称が、普通に通用するようになりましたよね。
佐々木氏:
役割の中でちゃんとポジションを持たせてもらっているのが、ほんとハッピーだなと思いますね。
──リン・レンはある意味、すごく分かりやすい弟や妹のポジションだと思うんですけど、考えてみればMEIKOやKAITOは、かなり不思議なポジションですよね。
近藤氏:
ウチの実家の母親や姉や姪も『プロセカ』をやっているんですけど、みんなKAITOが好きなんですよ。「お兄さんっぽくて安心感がある」と。バーチャル・シンガーと人間という括りじゃなくて、普通にいちキャラクターとして「KAITOいいよね」と言っているのを聞くと、「垣根がないんだなぁ」って思いますね。
佐々木氏:
ミクは「可愛いアンドロイド」というお手本がSFの中であったと思うんですけど、その可愛いアンドロイドよりも前に出ていた旧型のお兄さんが、「包容力がある」と受けとめられるのって、斬新だなぁと思いますよね(笑)。
 |
──それはやっぱりユーザーさんとの相互関係の中で、キャラクターが育っていっていると考えていいのでしょうか?
近藤氏:
そうですね。僕らとしては、必要最低限のキャラクター付けはさせていただいている部分があって。とはいえバーチャル・シンガーに関しては、それは本当に必要最低限に留めているので。それをどう受けとめて、どう楽しんでいただくかというのは、ユーザーの皆様に委ねているところではあります。さっきの関係性のところも含めてですけど。
人間とバーチャル・シンガーが共に歌う際のチューニングは、今でもフィーリングです
 |
──次は楽曲についてお聞きします。この半年間で過去の名曲だけでなく、有名クリエイターによる書き下ろしの新曲が次々に登場して驚いたのですが、これはもともとそういう想定だったのでしょうか?
近藤氏:
そうです。オリジナル曲を一定ペースで追加し続けることが、絶対に必要だと思っていたので。ボカロ界隈のクリエイターの方々に、コンスタントにオリジナル曲を書き下ろしていただいて実装していくというのは、本当にいちばん最初から要件として入っていました。そのためにいろいろな苦労があり、今も佐々木さんにはそういう交渉をお願いしているんですけど、とにかくそれは最初からの意図ですね。
──しかもクリエイターの方々が、各ユニットのキャラクターやストーリーに即した楽曲を作られていて。それがオリジナルの新曲として出てくるのは、ゲームをプレイしている側として、すごくインパクトがあります。
 |
近藤氏:
それは僕らというよりも、クリエイターさんの側でかなり汲み取ってくださっている部分が大きいですね。僕らからはそこまで細かいオーダーをしていないんですよ。
こういうコンテンツを作る時に、けっこう細かく指定する場合もあると思うんですけど、ボカロのクリエイターさんはご自身の持ち味だとか、独自の世界観が強くあると思っているので。どちらかというと僕らが気をつけているのは、「今回はこういうテーマの曲だから、こういったクリエイターさんに書いてもらいたい」という部分ですかね。そうすればクリエイターさんの持ち味もおそらく活きるし、いいんじゃないかと。そこから先は、必要最低限のキーワードとイメージみたいなものをお渡しして。そうすると、すごく汲み取って書いてくださって、歌詞や曲調も合わせてくださっているということだと思います。
 |
佐々木氏:
いちばん最初の頃は、『プロジェクトセカイ』というゲームで、声優さんが歌ってミクもいてという、今までのボカロ曲にはない謎ロケーションみたいなものについて、作家さんもかなり戸惑われていたと思います。純粋に「この企画、コケるんじゃないか?」と推察された方もいると思いますし。ユーザーさんにも過去の名曲になればなるほど、その名曲をゲーム側の趣向や都合で料理する、みたいな見られ方もしていたと思うので。
ただ、GigaさんやDECO*27さん、Mitchie Mさんらが『プロジェクトセカイ』の第1波のオリジナル曲を出されると、他のクリエイターさんはそれを分析されて、「客層はこうで、この曲のこの要素がこう伸びているんじゃないか」だとか、そのへんの肌感を、みなさんお持ちだなと。そこからはすごく早くて、イラストレーターさん含めクリエイターさん同士で、いい意味で「この人がこう来るなら自分はこうする」みたいな感じになって。だから今では、「このユニットの曲を書きたい」とおっしゃってくれることも増えましたね。
 |
小菅氏:
実際にゲームを遊んでくださって、シナリオも読み込まれている方がすごく増えましたから。
近藤氏:
最初の頃は「一緒に歌うって、どういうこと?」といった質問をたくさんいただきましたね。声優とバーチャル・シンガーが一緒に歌うとどういう音や雰囲気になるのか、と。
小菅氏:
まず「一緒に歌えるの?」という不安もありましたから。
 |
──そこに関してクリプトンさんとしては、人間とバーチャル・シンガーが一緒に歌っても大丈夫だという自信があったのですか?
佐々木氏:
大丈夫かどうかと言う自信は、正直そんなにあったわけではないですけど。ただ、安室奈美恵さんやBUMP OF CHICKENさんとミクとのセッションだったり、ボカロPさんだとピノキオピーさんがボカロと一緒に歌うのを模索されている流れの中で、一緒に歌うことで良くも悪くも目立って、アイデアも際立って、それがすごくチャレンジングというか、ひとつの壁を乗り越えようとしているように感じてはいました。まぁ、今回は全部がチャレンジだったので、ここもチャレンジしていいかなと(笑)。
近藤氏:
僕としては、いちばんのチャレンジがそこだったんですよ。そこに関してはけっこうギリギリまで答えが見えていなくて。最初に公開した「スイートマジック」が完成したのが本当にギリギリの時だったんですけど。
佐々木氏:
ああ、その話はヤバいヤバい(笑)。本当に公開の数日前でした。
 |
近藤氏:
それまでは完成音源がなくてイメージが沸かない中で、佐々木さんが連れてこられたサウンドチームのエンジニアの方々がすごくがんばってくださって、実際いい音になって。
人間とバーチャル・シンガーが一緒に歌うのは、普通にやるとたぶん成立しなくて、裏でかなりスゴイ処理をしているんですよ。その結果、僕らが聴いても違和感なくまとまっているという。
小菅氏:
そこに関しては明確なレギュレーションがあるわけではなくて。僕らもいまだに佐々木さんに見てもらいながら、曲ごとにバランスを取っているんです。
 |
佐々木氏:
最終的にはフィーリングのお話だったりするので。それこそColorful Paletteの若いスタッフの子に、SlackのDMで作った音源を聴いてもらって「しっくりきますか? きませんか?」みたいな尺度で確認させてもらって(笑)。
我々みたいな制作と、リアルタイムに楽しく聴いてくださっている方とでは、押さえているポイントがみんな違っていて。反響でも賛否両論、今でも当然いろいろあったりする中で、やっぱり若い人たちに聴いてもらいつつ、長く聴けるものがモアベターですから。バーチャル・シンガーが人間っぽくなることがゴールでもないですし、そこのさじ加減って本当にフィーリングだなぁと。
でも最終的に、『プロセカ』全体がそういう…いい意味で未完成なフィーリングになりましたよね。
近藤氏:
そうですよね。
 |
──僕なんかはむしろ、最初から違和感なく聴いていて。アナザーボーカルでバーチャル・シンガーだけの歌声にしたり、過去の名曲を遡ってオリジナルのボカロバージョンを動画で聴いたりすることで初めて、人間とバーチャル・シンガーが一緒に歌っていたことを意識するというか。
近藤氏:
バーチャル・シンガーと人間が一緒に歌える事が成立するからこれをやろう、ではなくて、もうちょっと違うところからスタートしているんです。人間とバーチャル・シンガーが共存する世界で、「じゃあどう共存するの?」という話になって。僕はいまだに覚えているんですけど、小菅さんたちと話している時に「一緒に歌うしかない」という結論になって、じゃあ佐々木さんにもそう言いにいくしかないと。
 |
小菅氏:
けっこう最初の頃から「一緒に歌うしかない」という話になったんですけど、さすがにトライするものが大きすぎて、しばらく寝かせたんです(笑)。いよいよとなった時に、佐々木さんに対して、これはもう相談からですよね。「本当にそんなことできるんですか」というところからのスタートでしたね。
佐々木氏:
ウチは逆に、最初から一緒に歌う方向でいきたいなと思ってはいたんですけど、それを言い出しても責任を取れないので、告白されるのを待つ、みたいな(笑)。そうしたら「来た来た」と(笑)。
近藤氏:
その結果、「無理かも」ということを一個一個成し遂げていって。本当に奇跡みたいなものですね。
佐々木氏:
でもユーザーの方から見ても、声優さんたちとバーチャル・シンガーたちが一緒に歩み寄ろうと努力している雰囲気が伝わって、応援したいなと思ってもらったり、「みんなで仲良く」とか「お互いに理解し合いながら」というのを感じ取ってもらえたんじゃないかと思います。言葉にしちゃうと説教臭いものになってしまうところを、試みとして声や音で示せたというか、伝わるものがあったんだろうなと。それは、とても音楽っぽいなと思いますね。楽器と楽器が認め合いながら重なっていく感じですね。
新しい音楽を発見する上で、『プロセカ』がひとつの橋渡しになれている
 |
──以前のインタビューで「『プロジェクトセカイ』がボカロの音楽が盛り上がっていくきっかけになれば」とおっしゃっていましたが、この半年間で、そうしたきっかけになれたという実感はありますか?
近藤氏:
あるかないかで言うと、少しはあるのかな……とは思います。『プロセカ』にはずっと最近の曲を入れているわけではなくて、ひと昔前の有名な曲も入っていますし、ある程度再生数はあるんだけどちょっとマイナーな曲も入っていたりするんですけど。新しい音楽を見つける上で、『プロジェクトセカイ』がひとつの橋渡しになってくれているというのは、少しずつ実感できていますね。
たとえば、『ミルククラウン・オン・ソーネチカ』という曲が僕は好きなんですけど、『プロセカ』収録曲の中ではそんなにすごく有名なわけでもなくて。でも『プロセカ』に入ることが発表されると、Twitterのトレンドに入ったんですよね。それで楽曲のもともとのファンの方にも喜んでもらえましたし、本家の曲のYouTubeのコメント欄を見ると「この曲を知ることができて良かったです」みたいな新しい書き込みがあったりして。そういう感じで、貢献できることもあったのかなと。
ただ、今の状況が100点満点だとはぜんぜん思っていないですし、何かを作るきっかけになってくれればいいなというのが最終的にあるので、そこに関してはまだまだ、できていることとできていないことがあるかなと思いますね。
 |
佐々木氏:
このあたりってニワトリタマゴの関係で。『プロジェクトセカイ』の素晴らしさと、ネットのクリエイティブのそもそもの素晴らしさと両方あって、それが調和しているからだと思うんです。
言葉にするとチープになるんですが、ボカロPさんだとかイラストレーターさんだとか、クリエイターさんの中に共鳴する感じ…共感覚というか、言葉にならない何かをものすごく広い範囲に伝播させる力を持っている方々がたくさんいらして。そういった方々に対して、プロジェクト側がいい形で「共振器」になれていて、『プロセカ』の物語に彼らの曲がドラマティックにはめ込まれることによって、非常に広い範囲に素早くお届けできる、みたいな。結果論ですけど、そういうハーモニーみたいなものが少しできていて。
こうなるためのニーズもあったし、底力もあったし、結局これを生んだのはリスナーひとりひとりの念というか。ネットのクリエイティブって、決められたルールはない思うんですけど、雰囲気を乱すことはしたくなかったんですよね。そこの微妙なバランスは、すごく難易度が高かったですが、近藤さんがもともとボカロPとして活動されていたりとか、セガさんはセガさんで『DIVA』の頃からCGの表現を蓄積されていたりとか、それぞれ生き様の中で準備してきたんですよね。
そういう想いが一点に集まりつつ、ドミノ倒し的にバーッと広がっていったのかなと。
 |
近藤氏:
針を100本並べて、そこに糸を順番に通していくような、そんな感じですね。何かがハマったからというよりは、そういう繊細なものをひとつずつ解決していくことで、全体が上手くハマっていってくれたというか。
──僕らとしては、全部じゃないにしても90本ぐらいにはすでに糸が通った状態で見ているので、最初からすごく綺麗に作られているように見えたんですけど、実際の作業はそうではなかったということですか?
近藤氏:
いえもう、ぜんぜん。最初の2年ぐらいは本当に、みんな大変だったんですよ。
佐々木氏:
今、近藤さんがおっしゃっているハードルって、内部的にはけっこう高くて。セガさんもそのへんは一番大変というか。
小菅氏:
その針もまっすぐ並んでいるわけじゃないですからね(笑)。あっちこっち向いているところを通していく、みたいな。でも結果的にお客さんの手に届くところには、しっかりとしたものをお届けできたので、良かったと思います。
『プロセカ』のe-Sports大会は、「RAGE」史上2番目の同時視聴者数を記録
──『プロセカ』はゲームそのものだけじゃなくて、ゲームをどう見せていくかの部分の戦略も、すごく考えられている印象があります。ゲーム中の3DMVを、YouTubeで順次公開したりだとか、受け手の側が求めていることを、きちんと理解されている感じで提供されているので。
近藤氏:
僕の考え方としては、根本的には良いプロダクトがないと絶対にダメなので、まずは良いプロダクトを作ることがいちばん最初に来るんですけど。
先ほど、マーケティングが強い、みたいなことを佐々木さんが言われていたんですけど、僕としては本当に良いものを「これは良いよね」とちゃんと思ってもらえるように見せることも大事だと思っているだけなんです。『プロジェクトセカイ』は業界的にも、プロモーションが上手くいっていると言われることが多いんですけど、基本的にはまず良いプロダクトを作って、その上で『プロセカ』であれば『プロセカ』にしかない良いところをメンバーが理解して、それをしっかりと伝えていくことが大事で。
『プロセカ』なら、たとえば初音ミクさんたちバーチャル・シンガーがいることだったり、好きだったボカロ曲に3DMVがついてリズムゲームで遊べることだったり、難易度「MASTER」っていう本当にめちゃくちゃ難しい難易度があるということだったり、そういったものを、それを魅力的に感じる人にしっかりと伝えていく。その中で、難易度「MASTER」は音ゲーマーの方々にすごく刺さるものだというところまでは比較的簡単にわかるんですけど、そこから先、どう伝えたらいいかはクリエイティブ勝負というかアイデア勝負で。そこで「社築(やしろきずく)【※】さんを超えろ!」みたいな企画が生まれてくるわけですけど。
なので、ユーザーさんやお客さんやコアなファンの方々がそもそも何を求めているのか、その人たちに本当に喜んでもらえるような要素はなんだろうか、というのをまず突き詰めて考えて、それをプロダクトに落とし込むところが、上手くいっている理由の8割ぐらいなんです。プロモーションは正直、それをどういうふうにみんなに伝えていこうか、という残り2割の感じですね。
※社築(やしろきずく)
にじさんじ所属のVTuber。音ゲーについての造詣が深く、プロリーグの監督も務めている。『プロジェクトセカイ』ではリリース前からプロモーションに参加している。
小菅氏:
今、例に出た難易度「MASTER」に関しても、最初はそこの部分を見せていたら「難しすぎる」みたいな声が出てきたので、もっと遊びやすい部分を見せていったりだとか、そういうこともしていましたね。
 |
──難易度の話が出てきた流れでお聞きしますが、まさか『プロセカ』が「RAGE プロジェクトセカイ 2020 Winter」として、e-Sportsにまで進出するとは思っていませんでした。
近藤氏:
あれは正直、あんなに好評になるとは思っていなかったんですよ。ただ、チームに「チャレンジはしよう」「チャレンジはしたほうがいいよね」という価値観が大前提にあるので、音ゲーの大会を賞金付きでやってみるというのも、まぁいいんじゃないかというぐらいの温度感だったんです。そうしたらかなり盛り上がって。
サイバーエージェントグループが関わっているe-Sports大会「RAGE」のイベントのひとつとしてやったんですけど、それが「RAGE」でも歴代2位ぐらいの同時視聴者数になったんです。
──しかもその大会の決勝曲としてサプライズ発表されたのが「千本桜」で。そういうところまで上手くできていたなと。
近藤氏:
同じことをずっとやっていても絶対に飽きられますし、何か新しいことをやり続けないといけないので。「RAGE」にしても、好評だったからといって第2回をそのままやるのでは意味がないので。じゃあ、より面白くするにはどうやるか。でもそれも、当たり前のことを言ってるだけですけど。
僕は、世界的に大ヒットしているゲームとかもよくやるんですけど、そういうゲームってじつはけっこうゴリゴリにアップデートして内容を変えてくるんですよ。環境も変わるしUIも変わるしで、その時は戸惑うんですけど、結果として面白くなっていて。10年前のそのゲームを見ると古く感じるんですけど、今のそのゲームを見てもぜんぜん古く感じない。途中で一気に変わったわけじゃなくて、ちょっとずつ進化しながら今に至っているんです。そういう体験がベースにあるので、やっぱり変えていかないとダメだよな、という気持ちが根底にありますね。
「セカイ」を大きく広げていきたいが、薄まってしまわないようにしたい
 |
近藤氏:
ソーシャルゲームとかスマートフォンゲームの寿命は何年、みたいな話がありますけど。僕はもっといきたいというか、海外のゲームだとそもそも、寿命みたいな話がなかったりもするので、それは目指していくべきだと思います。結果としてそこまで上手くいくかはともかくとして、姿勢としてはそれをやっていかないとという気持ちで、今も開発を続けています。
佐々木氏:
採り上げたいボカロ曲だとか、参加いただきたいクリエイターさんが際限なくいらっしゃるので、そういう考え方がベースになってきますよね。
近藤氏:
そうですね。ずっと進化し続けていきたいとは思っていますし、ユーザーのみなさんが「こういうものがほしい」というものは順次検討していきます。でもそれだけではなくて、「こういうものが来るとは思っていなかったけど、それはすごく嬉しい」というものを仕込むことに、僕らは一種の責任感を感じていたりもしますから。むしろそれがないとダメだなと思っているので。
ユーザーのみなさんへは、ワクワクしてもらったぶんだけ良いものを提供できればと思っています。ハーフアニバーサリーと言わず、1周年、2周年、3周年と続けられるだけの良いコンテンツにできるよう、引き続きがんばりますのでよろしくお願いします。
佐々木氏:
こういう風に、長く続けていきたいなと思うんですよ。で、自分達に出来る地道な努力を続けていきたいなと思うのはサウンド面のテクニカルさだったり、ミクとMEIKOの差を埋めることだったりするのですが、皆さんの評価を見ながら改善していくしか無いので、今はコツコツ続けていきたいなと思っています。
3DCGのほうも、このプロジェクトが注目されればされるほど、どうやっていこうかというのがさらに難しくなっていくので。そこはセガさんも大変だなぁと。どうですか?
小菅氏:
3Dに関してはとにかく、さっきお話ししたように表現を上げていこうとしていますし、そうすればストーリー性を持ったものも、もっといろいろと作れるようになると思います。そこから楽曲のほうもさらに展開が広がるでしょうし。
私としては『プロジェクトセカイ』をより「広げたい」と、より「届けたい」の二軸で動いていて。「広げたい」はグッズであったりとか、他のメディアへの展開とかですね。場合によってはリアルライブみたいなこともできたらいいなと思っていますし。
──『プロセカ』はタイアップやコラボも、いろいろと考えられますよね。
小菅氏:
そうですね。『プロセカ』というタイトル単位だけではなくて、ユニットごとのコラボもすでに動いています。
──それこそ男女混合ユニットもいるので、いろんな切り口ができると思いますし。
小菅氏:
作りやすいですね。佐々木さんもさっき言っていましたけど、『プロセカ』はいろいろな土壌に広げられる「器」になっているので。今後はいろんなところにお出かけしていくと思います。
もうひとつの「届けたい」としては、今は日本で楽しまれているコンテンツですけど、できればもっと世界に出ていって楽しまれるコンテンツになれたら、もっといろんなことができるんじゃないかと。
──現状で、海外でのサービスの予定は?
小菅氏:
まだ検討している段階ですが、海外を見据えた動きをしていきたいと思っています。YouTubeのコメントでも外国の言葉をけっこう見かけているので、いろんなところから注目されているというのは実感しています。日本だけではなくて、もっと多くの人に遊んでもらえるような動きを、これから取り組んでいきたいと思っています。
佐々木氏:
今、夢はいろいろ広がっている最中だと思うんですけど、その中でヘンに薄まってしまわないように注意しながら、ファンのみなさんとコミュニケーションを取って広げていけたらいいなと思っています。
近藤氏:
いろんなやりたいことは無限にあるんですけど、クオリティは落としたくないですよね。やりたいことを良いクオリティでやれるように、がんばっていますので。
──どうもありがとうございました。(了)
 |
鼎談の中にもあるように、『プロジェクトセカイ』はゲームの中でオリジナルキャラクターが繰り広げている物語とボカロ曲が結びつくことで、ボカロ文化やネット音楽の「器」、つまりプラットフォームとして機能し始めている。それは今後、ゲームの人気が拡大していくことで、『プロセカ』がかつてのニコニコ動画が果たしていたような役割を、今後担っていく可能性をも秘めているのかもしれない。
ハーフアニバーサリーを迎えた『プロセカ』は、今後も新たな試みが用意されているという。ゲームをすでにプレイしている人はもちろんのこと、まだ触れたことがないという人も、この機会にぜひチャレンジしてみてほしい。