100年の歴史で最大の経営危機に直面して、ソフトウェア開発の大半をリセット
谷氏:
僕は2000年に社長になったんですけど、そこからソフトウェア開発の業績はずーっと苦しいですね。そこはほかの部署が埋めてくれてなんとか維持されているという事情はあるんですけど。当時は、社員にも本当に迷惑をかけたなって思うんですけど、でもね、どうしようもなかったんです。
 |
そうこうしているうちに、2008年8月のリーマンショックとなってしまう。2009年のお正月に銀行さんが来てですね、「社長、今年は御社も大鉈を振るわなければいけないかもしれませんね」って言うんです。正月の挨拶で、ですよ。「なんじゃそりゃ」って思うじゃないですか。
去年の年末にはボーナスも出てるし、秋には社員旅行も行っているし。ちゃんとやってきている会社なのに、世の中でリーマンショック、リーマンショックと言い始めたことによって「もしかしたら」みたいなことを銀行が言うなんて、「どうかしてんじゃねぇの?」って思ったぐらい、奇妙な話だったんです。ところがね。不思議なことに、その直後から変なことが起きたんですよ。
じつは2009年は、ウチのフラッグシップタイトルである『シュヴァルツシルト』と『パワードール』で勝負しようと決めていたんです。その年の決算である6月に『シュヴァルツシルト』を出して、その手前に『パワードール』を出すっていう。これはもう、初めての「社長命令」ぐらいのつもりでやってきました。
これまでの反省として、開発が作りたいものを作って、それを営業が渡されて売ってくるというのには無理があると。何を作るのか、あるいはどんなものができあがってくるのかを、開発と営業とで密に情報交換しながら、考えてやっていこう、と提案してきた時期なんですね。それで、ウチのフラッグシップタイトルふたつを作ろうと話を進めていた。
それまでの時代、僕が『パワードール』の新作を作ってくれ、と言っても、「もう戦争なんか起きねえよ」ってスタッフから一蹴されちゃう。嘘みたいでしょ?
 |
──そうですね(苦笑)。
谷氏:
でもホントに一蹴されて、「ハハハハッ」って笑われて終わり。それ以上なんにも言えなくなっちゃう。
とはいえ「こういう時期だから」と粘ったら、「いきなり『パワードール』の『7』だ『8』だというのはいまのメンバー的にもすぐにはやれないので、昔の『1』を最近のプラットフォームで遊べるようにしよう」と、リマスター版を出すことは応じてくれて。それで『パワードール 1』を3月までに出すって約束してくれたんです。

3月に出すってことは、マーケティング的には1月にはある程度盛り上がりができていて、受注活動が完了している時期なんですね。でも、そのときに流通さんから送られてきた発注書の数字は僕らのイメージしていたものよりも1ケタ少ないんですよ。……「なんじゃこりゃ!」って。まじで冷や汗が出ましたよ。
「これは参ったぞ」と本気で思って。こんな状態で、じゃあ新作の『シュヴァルツシルト』はどのくらい売れるの? となってくるわけですよね。
で、ちょうどそのタイミングぐらいか、ちょっと手前ぐらいで、開発から『シュヴァルツ』のアルファのアルファみたいなものができたって、営業スタッフに渡されて。それをみんなテストプレイしたんだけど、もう忘れもしない。「なんじゃこりゃ!」ですよ。もちろん悪い意味で。
 |
僕にしてみたら『シュヴァルツシルト』は、自分が入社したてのときに生まれたタイトルですから、思い入れもあります。「今度の『シュヴァルツシルト』はこうなる!」とプランニングの初期段階にも一緒に加わって、遊び方の模擬プレイを会議テーブルの上でやったりしたんです。それで「あぁ、今度の『シュヴァルツシルト』はおもしろくなりそうだなぁ」って、僕は判子を押したわけです。
そうして上がってきたものが、ぜんぜんルールが違う。制作途中に社長判断でお蔵入りにした企画は、この最後の『シュヴァルツシルト』だけじゃないですかね。このときは営業担当も全員が、「これを出したら『シュヴァルツシルト』のブランドが地に落ちる」って言ってましたから。
そこで開発担当者に「これはどういうこと?」って聞いたら、「いろいろと考えてみたんだけど、うまく集約できなかったのでルールを変えた」と言われたんですね。いやいや、ちょっと待ってよ。「変えた」じゃねぇだろう。なんでそれを社長が知らねぇんだよと。
──普通の会社ではありえない状況ですね。
谷氏:
そう、ありえない。自分は社長として、事前に説明された内容に対して「了解」して開発費を投じる決定をしているわけですよ。「それが大事なルールの変更を知らないってどういうこと?」って、僕はそのときにものすごく大きな問題として捉えたんです。自由気ままに作りたいものを作らせてきた結果が、社長に何も言わずに大事なことを変えて、先に進めていくような風土になってしまった。これはいくらなんでも容認できない。
 |
世の中は、リーマンショックでガタガタきていて、直前の受注は1ケタ少ないんですから。「これはもうだめだ」って思って。じつはこのときに全社員を集めて、経営状態をみんなの前で発表して、工画堂始まって以来の希望退職を募りました。これはもう工画堂の歴史に残る、史上最大の「負のイベント」でしたね。
──本当に大鉈を振るうことになったんですね。
谷氏:
そうなんです。工画堂にはBtoBをやっているグラフィックデザイン事業があって。それとは別に、BtoCをやっているソフトウェア事業があって。決算書を見ると、何が原因で悪くなってきているのかはわかっている。だから端的に言うと、この危機を乗り越えるために、ソフト部門は解散。
ソフトウェア開発部の歴史を一歩ずつ積み上げてきてくれたスタッフの方々に対しては本当に「感謝」しかありませんでしたが、手段としてはこれしか無かった。心の中では、泣いて馬謖を斬るという想いでした。
でも、このときに解散して「ゼロ」にしてしまうと、あとから掛け算をしてもゼロなんですよ。じゃあどうするべきなのか、と思ったときに、世の中で本当に何もかもがダメになっちゃったのか、ちゃんとお金が動いていることはないのか、というのをみんなで話し合ったんです。
そうしたら、それは「萌え」とか「ギャルゲー」とか「アキバ系」とか、そういうキーワードだと。そのど真ん中が「くろねこさんちーむ」と「くまさんちーむ」だったので、「じゃあ、そのふたつだけ残して後はリセットしよう」と言ったのが、そのときの方針です。
 |
その時点ですでに「くまさんちーむ」は工画堂から独立して運営されていました。ちなみに先代の鬼羅が、そちらの会社の社長を務めていて。なので、外にいる「くまさんちーむ」と社内にいる「くろねこさんちーむ」。このふたつだけを残して、ゼロではなくて1とか2だけ残して、なんとかやっていこうと。
そのリーマンショックのときのリセットが、工画堂のこれまでの歴史の中でいちばん大きな負の出来事です。けれども、それをしたことで100年の歴史を持つ工画堂は間違いなく生き延びられたし、ソフトもいまにつなげることができた。少なくとも僕はそう思っています。あのときの風土をそのまま引きずっていたら、もう絶対に会社全部がダメになっていたと思うので。
マーケティング感覚のズレが、経営危機を生んだ
──開発チームがそういう状態であっても、結果そのものは出るわけじゃないですか。「売れていない」ということに対する、彼らのリアクションはどうだったんですか?
北川氏:
僕自身、チームを見るようになって、すごく感じることなんですけど。開発している現場の子たちが、売り上げとか制作費とかをどのぐらい事細かに知っておくべきかというのは、けっこう議論がわかれると思うんです。それを知っておいてコスト感を持っていないとモノなんか作れない、という考え方がひとつ。でももう一方で、費用を知ってしまうと企画が小っちゃくなってしまう、という考え方もあって。
──たしかに。
北川氏:
先代の部長だった人は、これを作るのにどのぐらいお金がかかるんですよ、あなたたちが1年働いたらこのぐらいかかるんですよ、というのをおそらく現場に教えなかったんです。その代わり、「君たちがやれる“ベスト”を作ってくれれば、それで会社が儲かるんだから大丈夫だ」っていう進め方をしていたのではないかと思うのです。
それによってコスト感が失われたというのは、プラスもありマイナスもありだと思うんです。けれどもまたそれとは別に、“マーケティング感覚”もズレてきちゃったんでしょうね。「自分たちが作りたいもの」と「世の中が求めているもの」が、ちぐはぐになってき、マーケットから離れていっちゃった。そこが大問題だったのかなというふうには感じます。
そのやり方が悪かったのかどうかは、僕も先代の部長から仕事を教えられた人間なので、一概に判断はできないです。あとは、いま僕が同じ立場になると、彼の考えていたことも少しは理解できるように感じるので。ただ、やっぱり「あのときこうすればよかった」という答えは、まだうまく導き出せないですね。
谷氏:
いま、北川のマーケットの話を聞いていて思ったんですけど、当社はパソコンゲームの開発チームとコンシューマゲームの開発チームに分かれていたんですよ。当時の市場を冷静に見たらどちらのチームも「いまはもうPS3とかコンシューマ中心でやらなきゃダメだ」って、なっていたはずなんです。
 |
ところが、「パソコンでこれが売れてるんだから、いいじゃねえか」って、あまり聞く耳を持ってくれなかった。自分の作りやすいところから離れようとしない、ということですね。「挑戦」できなくなってしまった、ということかな。パソコンゲーム市場はそれ以降、壊滅的な状況になっていきますので、そういう考え方が結果的に、ダメになっていった背景にはあるだろうなとは思いますね。
北川氏:
「くろねこさんちーむ」の鳥越とか、そのあとにウチでいくつも作品を出した「しまりすさんちーむ」とか、フワフワしているようでいて、きちんと“マーケティング感覚”があるんです。「こういうのがウケている」って。
 |
谷氏:
だって鳥越なんか、通勤途中にたまに会っても、僕が近くに寄っても気がつかないで、ずーっとゲームをやっているんですから。
──入り込んでる(笑)。
谷氏:
もう本当に、いつでもゲームをやっている。でも“マーケティング感覚”って、そういうところから培われるものだと思うんです。
カードゲームの依頼から生まれたイラスト制作事業が、工画堂の新たな柱に
──ソフトウェア事業を大幅に縮小せざるを得なくなった一方で、それと入れ替わるようにして、工画堂スタジオの新しい事業の柱となったのが、イラストの制作事業ですよね。これはどのようにして手がけられるようになったのですか?
谷氏:
本当に、偶然のご縁なんです。2002年にXboxが登場したじゃないですか。そのときにマイクロソフトに対して、参入の交渉をしていたんです。まぁ、端的に言っちゃうと「移植するから開発費支援をしてくださいよ」なんですけど(笑)。それは結果的にダメだったんですが……。
 |
その際に窓口だった方から、日本の子ども向けにカードゲームを普及させるというお話をご紹介いただきまして。その新企画のイラストを工画堂にお願いしたいと。
ウチはグラフィックデザインの会社ですから、そういった2Dの成果物を作るのは、もういちばん親和性のある仕事です。しかもその成果物が、男児向け玩具ですからね。なので、社内でタカラトミーさんとかの仕事をやっている部隊の担当者を捕まえて、「今日、こういういい仕事の話があったんだよ」と持っていきました。そうしたら「そんな3カ月で100枚だ、200枚だなんて、いったい誰が描くんですか。やれるわけないじゃないですか!」と言われてしまって(笑)。
──たしかに(笑)。
谷氏:
それで、涙を吞んでいったんはお断りしたんです。ところが後日「いろいろ考えたんだけど、あの仕事は工画堂でやらなきゃダメだよ」とクライアントさんが言ってくれたんですよ。普通はあり得ないじゃないですか、そんなのって!
そこで社内の同じ担当者を捕まえて、「ここまで言ってくれているんだよ!」と説得したら、担当者も「わかった」と言ってくれて。当然、やり方がわからないわけですから、暗中模索ですよ。イラストレーターの人たちをどうやって探したらいいのかもわからない。でも少しずつ進めていって、時間はかかりましたけれども、ようやく第1弾ができあがりました。それが『デュエル・マスターズ』です。

「ああ、こういうふうになるんだね」って言いながら、第2弾の作業に移って。第2弾の制作が終わったら、今度は第3弾の制作がスタートする。そんなふうに繰り返していくうちに、だんだんと軌道に乗ってきました。「『デュエル・マスターズ』のイラストの制作を、工画堂がやっているんだよ」とようやく言えるようになったのは、カードが発売になってしばらくしてからですね。
で、こんな素晴らしいものができたなら、営業ツールにしたいじゃないですか。僕はそもそも営業ですからね。それでいろんな会社に実績紹介をしました。そしたら、似たような仕事が取れたんですよ。
──さすがですね(笑)。
谷氏:
それが、『ディメンション・ゼロ』(『D-0』)という新しいカードゲームです。ただ、うちではすでに『デュエル・マスターズ』をやっていて、同じカテゴリーの競合商品になり得るタイトルを、同じ人たちがやるのは「ちょっといくらなんでも」と考えまして。
──それをどう解決されたのですか?
谷氏:
当時、工画堂のグラフィックデザイン部門は阿佐ヶ谷に、ソフトウェア開発部はお隣りの高円寺にありました。当時はまだリーマンショックよりも前でしたけど、高円寺のとあるチームで作って販売していたゲームタイトルが非常に不調で。「当分、オリジナル開発はさせられないぞ」というタイミングで、ちょうど『ディメンション・ゼロ』のお仕事が取れたんですよ。
そこで、高円寺のそのチームを中心に置いて『ディメンション・ゼロ』をやっていこうと。そうすれば『デュエル』の阿佐ヶ谷部隊、『D-ZERO』の高円寺部隊ということで、場所もスタッフもすべてにおいて線引きができている。それでいて、イラスト制作のノウハウは社内で共有できるはずだと。
──なるほど。
谷氏:
なので、こちらはご縁を大事にしただけだったんですけれども、それがいまにつながっていい仕事になった、ということなんです。ただ、先代や先々代の社長がBtoCのゲームソフト販売という夢を見て、ここまで育ててきたのに、イラスト制作というBtoBの仕事をソフト開発部門にやらせるのもどうなのかなぁ……ということに、自分としては悩んでいたんです。
 |
そこで、僕はサイベルというパソコンゲームメーカーの副社長だった藤井さんという方とすごく仲が良いんですけど、その藤井さんに飲みながら相談したんです。そうしたら「今日の谷さんの話は、これまでの付き合いの中でも最も谷さんらしかった。すごく工画堂らしかった」と言っていただいて。それでものすごく背中を押されたような気持ちになって、このイラスト制作の仕事をもっとがんばってみよう!と覚悟が持てたのです。
だから本当に、いろんな人とのご縁が、いまの仕事につながっているんですね。
「完成がいちばん近い」という理由で登場した“百合”路線
──2009年に経営が急激に落ち込んで、ソフトウェア事業を大幅に整理された。そこからイラスト制作事業に力を入れつつ、ソフトウェア事業を立て直していくアクションというのは、いったいどういうものだったのですか?
谷氏:
立て直していく一手ねぇ……。それはこちらを見てもらうとわかりやすいでしょうね。
 |
これはね、工画堂の巻物なんですよ。工画堂がどういうふうにやってきたかというのを、ビジュアル的に見せられるといいかな、と思って作ったんです。僕は2000年に社長になったじゃないですか。なので便宜的に、2000年からしか作っていないんですけど。
──さすがはグラフィックデザインの会社ですね。
谷氏:
これでおわかりの通り、2009年までは毎年みっちりとソフトが出てきていたんですが、2010年からはスカッと白いじゃないですか(苦笑)。
 |
この時期にどういう考え方を持ってやってきたかというと、サイバーフロントさんにパブリッシングを委託して、ウチは作るほうにしばらく集中することを考えました。ウチが作ってサイバーさんで売るというのを、調整期間としてやってきているんですね。
昔みたいに2タイトル同時に出すぞとか、3ラインを同時に走らせるぞ、とかいうことはできない。お金もないし人もいないし、厳しい時期ですから。そのときにいちばん“ソフト完成の終点が近い”ところにあったタイトルを、優先的に作ったんですね。そのタイトルが、「しまりすさんちーむ」の『白衣性恋愛症候群』だったんです。
 |
──そこで“百合”路線の「しまりすさんちーむ」が出てくるんですね。
谷氏:
ゲームをひとつ作ると、次はそれのアレンジ版、その続編、リメイク版……みたいな感じで続いていけたので、ここ10年は「しまりすさんちーむ」が中心となっていきました。しまりすさん“だけにした”というわけじゃなくて、順序としてそうなったんです。
実際のところ、ほかのものもけっこう作ったりはしているんですよ。ただ、それぞれがあんまり上手くいかなかったというか。たとえばガマニアさんに『Web POWER DoLLS』というのをライセンスしたりもしていたんですけど。僕らのイメージではこれが大ハネして、リーマンショックの時に掘った大きな穴が埋まる予定だったんですが(笑)。
北川氏:
自社開発をだいぶ絞り込んだ一方で、OEMのチームは活況だったので、じゃあみんなでOEMのチームを手伝おう、という方針になりました。昼間はOEM、夜は自社開発ではないですが、二毛作のような感じで、ここ5年ぐらいはやっていたんじゃないですか。
谷氏:
開発も営業も、みんなでイラスト制作のお手伝いを。
北川氏:
僕もずっとお手伝いをしていましたね。
 |
ソフト開発があるからこそ、イラスト制作の仕事が有利になる
──現在の工画堂スタジオは、売り上げの構成比みたいなものはどうなっているのでしょうか。
谷氏:
イラスト制作が50パーセントですね。それからグラフィックデザインが25パーセント、ソフトウェア開発が25パーセントといったところでしょうか。
──昔ながらの堅い仕事も、いまでもやられているのですね。
谷氏:
はい、もちろんやっています。本業ですから。
 |
──その中でソフトウェア開発の業務を残さないといけないというのは、どういう想いなのですか?
谷氏:
それはねぇ……。もしこの会社にMBAを持っている人がヒョイと来てね、経営コンサルをするとしますよと。パッと決算書を見て「あっ、このソフト開発部門は切りましょう」ってやったら、黒字の良い企業ができあがりますよ、きっと(笑)。
一同:
(笑)。
谷氏:
そんなことは誰でもわかることだし、短期的な目線で判断したら、そうすべきなんでしょうけど。ところが、それをやってBtoBだけの会社になったら、その後の受注活動はものすごく苦しむんじゃないかなと思うんですね。
実際、イラストの仕事を取りに行くと、「工画堂さんって僕、『パワードール』をすごく楽しく遊ばせてもらったんですよ」とか、「そんな工画堂さんにイラストを発注できるなんて光栄です!」とまで言ってくれる人たちが、けっこういるんですよ。
工画堂はこれまでいろんなゲームを開発してきた“実績”を以てイラスト制作をしているんです。だから成果物はどこよりも良いものでなくてはならない。それゆえ、イラスト制作部署が出来上がった当時からいままで、「イラスト制作日本一」という理念に沿って取り組んでいます。
 |
これがもしBtoBだけをやっていて、ほかの会社と差別化のできないイラスト事業だったとすると、「あっ、工画堂さん、またお願いしますよ、安ければ」っていう、そんな会話になっていくんじゃないかと思うんです。
会社って、その会社を俯瞰して見たときに、どんな考え方の上にできあがって、歴史を積み上げてきたのかっていうことをちゃんとアピールしながら、それを長く継続していかないと、本来的にはダメなんじゃないかなと思っていて。
──おっしゃるとおりだと思います。
谷氏:
いま、BtoBのイラストを描いている人たちと面談すると、「私は自分のゲームが作りたい」って言うんですよ。それってウチのことを、ゲーム会社だと思っているわけじゃないですか。「工画堂にいれば自分のゲームを作れそうだ」という思いがあるから、優秀な絵描きさんがウチに来てくれるという側面もあるんですよね。そこがおもしろいところで。これがただの下請け企業になっていたら、そんなことはないでしょうから。
北川氏:
いまの話と、ちょうど逆もあって。
たとえば、ひとつ前に出た『夢現 Re:Master』というタイトルは、藤ちょこさんにキャラクターデザインをお願いしたんですけど、藤ちょこさんを起用できたのは、イラストのチームがあったからなんです。

『夢現 Re:Master』も新作の『ユメミドリーマー』も、グラフィック制作の部分はほとんど内部の、イラスト制作チームの手を借りながら作っています。普通だったらちょっと手配しづらいような、ハイスペックなグラフィッカーさんたちを制作チームに迎えられていて。そういうところで両輪の片方、イラスト制作の部門が相当パワフルに回っているので、ソフトのほうがずいぶん助けてもらっているというような状態にはなっています。
──なるほど。
北川氏:
あとは協業案件で、『白と黒のアリス』というタイトルをオトメイトさんで出しているんです。これはグラフィックとプログラムが工画堂で、パブリッシングと広報まわりをオトメイトさんがやっているというスタイルなんですけれど。これも、キャラクターデザインはイラスト制作チームの人間が担当し、プログラムはソフトの人間がやるという。2社合同のうちの片方は、社内の違うチームが相乗りするという形になっているんです。

オトメイトさんがそれを「やりましょう」と言ってくださったのは、イラストチームが『うたの☆プリンスさまっ♪』で、女の子向けのグラフィックが強いと知られていたからで。そういう形で社内の持ちつ持たれつみたいなものは、ちょっと見えにくいところですけど、実現できているかなとは思います。ここ最近は、持ってもらってばかりですけれど。
 |
──イラスト制作がソフトウェア開発を支えるだけでなく、ソフト開発を続けることがイラスト制作にも役立っているという構図なんですね。
谷氏:
僕や北川は、いちばん苦しいところをやってきた人間ですから。リーマンショックでソフトウェア事業をいったん最低限までリセットして、そこからもう一回引き上げるのがどんなにたいへんか。パソコンゲームの世界で20年かけて積み上げてきても、一回止めたらあっという間に墜落するんですから。だって、いまだに言われますからね。 「工画堂、懐かしい!」、「まだあったんだ」ってね(笑)。
 |
──(笑)。
谷氏:
まぁ、それはお決まりの文句だからいいんですけれども。やっぱり世間から見えなくなった瞬間に「ない」ものになっていってしまう。その歴史は再利用できない、活かせない。
だからウチの場合だとやっぱり、BtoBとBtoCの“両輪で”走っている会社であって。それぞれの持っている資産をちゃんと掛け算しながらやっているんだよ、というのがスタイルとして残っていかないと、おそらくダメなんだろうなと。
まぁ、止めるのは簡単ですから。「もう、出さない!」って言ったらそれっきりじゃないですか。本当に止めなきゃいけないときが来たら、そうすればいいので。でもやっぱり経営って、超長期的に考えていくべきものだ、というのが、僕の中にはあります。
……ただね、こういう話を社内で言っていると、「社長がそういうふうに言ってるから、多少調子が悪くても止めねぇな?」って、楽観視するところが出てくるんですよね(笑)。
一同:
(笑)。
個人の知恵や知識は承継できないが、「企業理念」は会社の背骨として承継できる
──現在のソフト市場を考えると、スマートフォンのゲームというのも大きな存在になっています。工画堂さんとしては、そちらでの展開も考えたりしているのでしょうか?
谷氏:
世の中がそういうふうになっているのは、十分理解できています。だけど、ウチがそのモデルに乗っかっていくことは難しい……というか、いまはできない。ただ、そうやってお金が動いている市場には、何かしらの接点を持っておかなければいけない。そこで、そちらの市場のゲーム会社さんから、イラスト制作の仕事を取ろうと。
先ほどお話ししたように、高円寺のチームが『ディメンション・ゼロ』のイラストを制作するようになったのですが。あるとき、そこのリーダーが「社長、いま僕たちがやっているのは、トレーディングカード事業ですね」と言ったんですよ。でも僕は、その言葉がぜんぜん釈然としなくて。トレーディングカード事業なら、ブームが終わったらまた別の事業に移るのか? いや、そうじゃない。あなたたちがやっているのは……「イラストレーターズ・ハブ事業なんだよね」って言ったんです。
つまり、僕らがいまやっているのは、外にいるイラストレーターの方々との交流なんだと。密接で良質な関係性。コミュニケーション力。そういったことをノウハウにして、最終成果物として出しているのが“たまたま”トレーディングカードのイラストというだけなんだ。そういうふうに考えたほうがいいよ、と言ったんです。
 |
すると、そのリーダーは目からウロコが落ちるのが早くて。「だったら、イラストならなんでもいいじゃないですか。これからはゲームのイラスト制作なんかも、どんどん取ってきていいんですよね?」って言うから、「いいも何も、いままでゲームを作るときに、同じことをやってきただろ」って(笑)。
──たしかに(笑)。
谷氏:
それ以降、トレーディングカードゲームはいまでもウチのメインクライアントなんですけれども、そうじゃないところのイラストもちゃんと手当てしていこう、というふうになったんです。それが他社との協業にもつながってきた。でもこれは、先代がボードゲームから液晶ゲームへ、そしてパソコンゲームへと変遷したときの考え方を下敷きにして、僕がアレンジしながら使っただけのことでして。そういったところが会社のノウハウや生き様として、“活かされてきている”のかな、と思います。
──そうした考え方が、工画堂としてずっと承継されてきたものなんでしょうか?
谷氏:
ひとつひとつの事業のあり方や、社会的な部分というのは変わっているので。「何を承継するのか」というのは非常に難しいことですけれど。でも先人たちの知恵や知識だとか、そういったものは“承継できない”んですよ。
 |
とくにデザイン業というのは、それぞれのデザイナーが“その人の感性”を表現したものが最新のデザインだし、それの連続なので、やっぱり「個」に依っているんですよね。個に依っているということは、その人がいなくなったら終わりなんです。それはデザインだけじゃなく、ソフトだってそうですよね。
じゃあ、どんなものを「承継する」ことがあり得るんだろう。それは「工画堂はこれだ!」っていう揺るがない部分。ここだけはぶらさない、というのをしっかりと明文化して、それをのちの人たちに何代も続けていくこと。それをひとことで言っちゃうと、「企業理念」とか「社是」とか。あるいは企業経営をする上で重要な普遍的な要素、そういったものになるんでしょうけど。それを工画堂の背骨として承継していくことが、いちばん重要なのではないかと僕は思います。
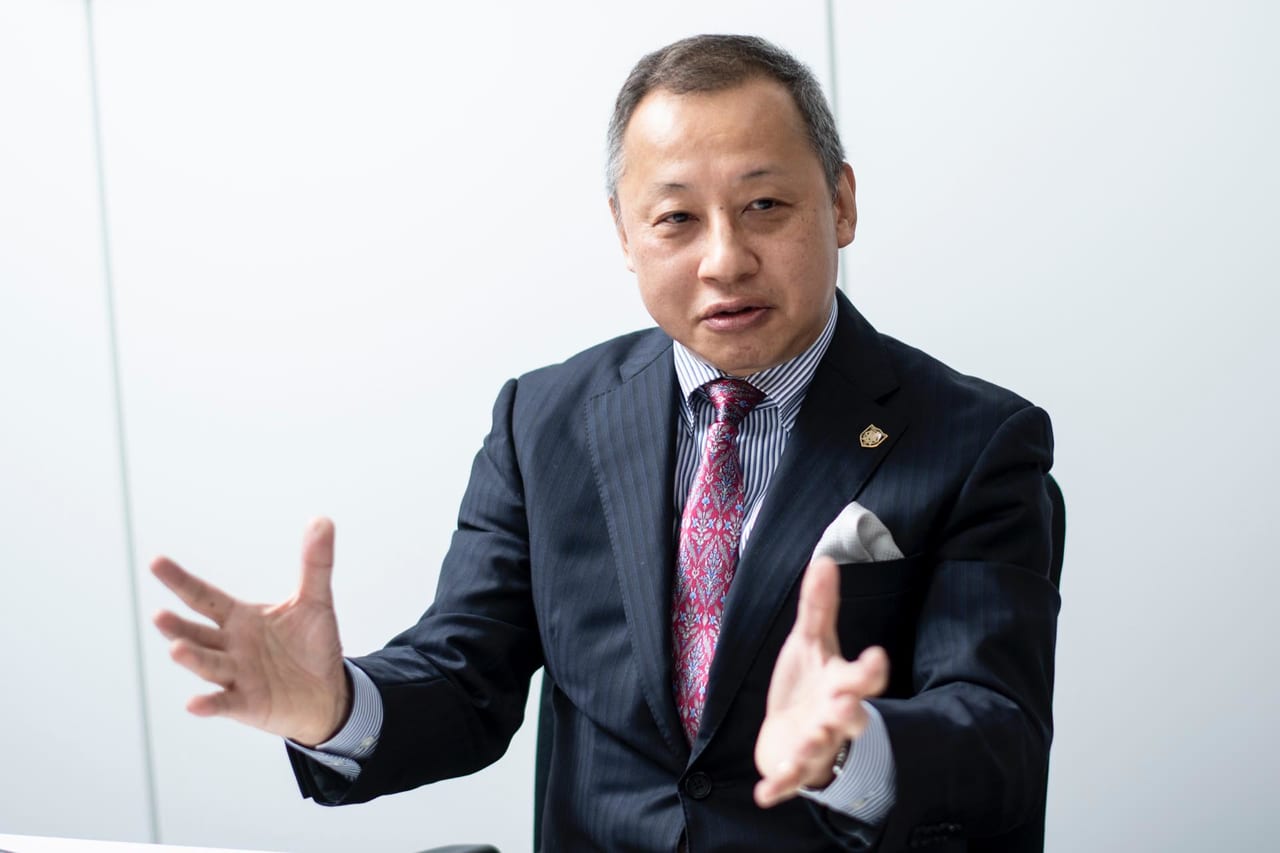 |
──ちなみに、工画堂の理念を明文化すると、何ですか?
谷氏:
社是が「感性と創造」。企業理念は「私たちの創作物を通して全世界に感動を提供する」です。
でも先ほどからお話ししているように、当社にはBtoBとBtoC、両方あるじゃないですか。なので、それぞれのところに「事業理念」という言葉でもう一段階あって。
BtoB、デザインのほうの事業理念は、「任せて安心工画堂」、「信頼のワンストップパートナー」っていう。これは実際に、大昔にタカラの人から言われた言葉なんですよ。「任せて安心だからね〜、工画堂は!」って。それをキャッチフレーズに使っているというのが、歴史の中に残っているんですね。
ソフトのほうは「コンテンツありき」という言葉。それがひとつの理念の中から派生して、こっちはここに重点を置く、こっちはここに重点を置く。でも理念は変わらない。というような形で、会社の形が出来上がる。だから両輪で回っていく。ただ、ずっとそれだけで回っていくのかっていうと、また時間が経っていくと薄まってくるところがありますのでね。
 |
なので2012年に、「クリエイターズ・ハブ理念に基づいて、外のクリエイターさんたちと幸せや豊かさを共有することで成長し、それによって社会貢献をする」ということを、「30年ビジョン」として提案しました。
──クリエイターズ・ハブというのは、具体的にはどういうことでしょうか。
谷氏:
工画堂を中心(ハブ)にして多くのクリエイターさんたちと、ひとつのコンテンツを作っていくうえで協業していくというスタイルですね。それがいま、イラスト制作などを通して、すごくスムーズにやれているんじゃないかなと。
実際の話、大手のゲーム会社さんだってそうじゃないですか。自分たちの会社だけで作るなんてことはもうほとんどなくて、外の人たちとのネットワークでやりますよね。ウチもその小さい版をやっているわけなんです。
でもそのときに、外のネットワークは「出しときゃ良いものが上がってくる」なんて思ったら大間違いで。外に出しただけだと、たいていは不満足なものしか上がってこない。それをいかに「良いもの」を維持しながらスムーズに流していけるかっていうのが、いまの工画堂のノウハウになってるんじゃないかな、と思っています。
 |
あるいは「お願いします」って言ったときに、「ああ、いいですよ」、「工画堂のタイトルだったらちょっとお手伝いしますよ」と言ってくれる関係性ですね。そういう目に見えない部分でのお付き合いの積み重ねっていうところが、強みになっているんじゃないかな、と思いますね。
要するに、自分たちは「クリエイターのために生きるぞ」っていうことをすごく大事にしていく会社だよ、と大見得きって公言していますから。その考え方に沿っていさえすれば「工画堂の本質は変わらない」と考えています。




































