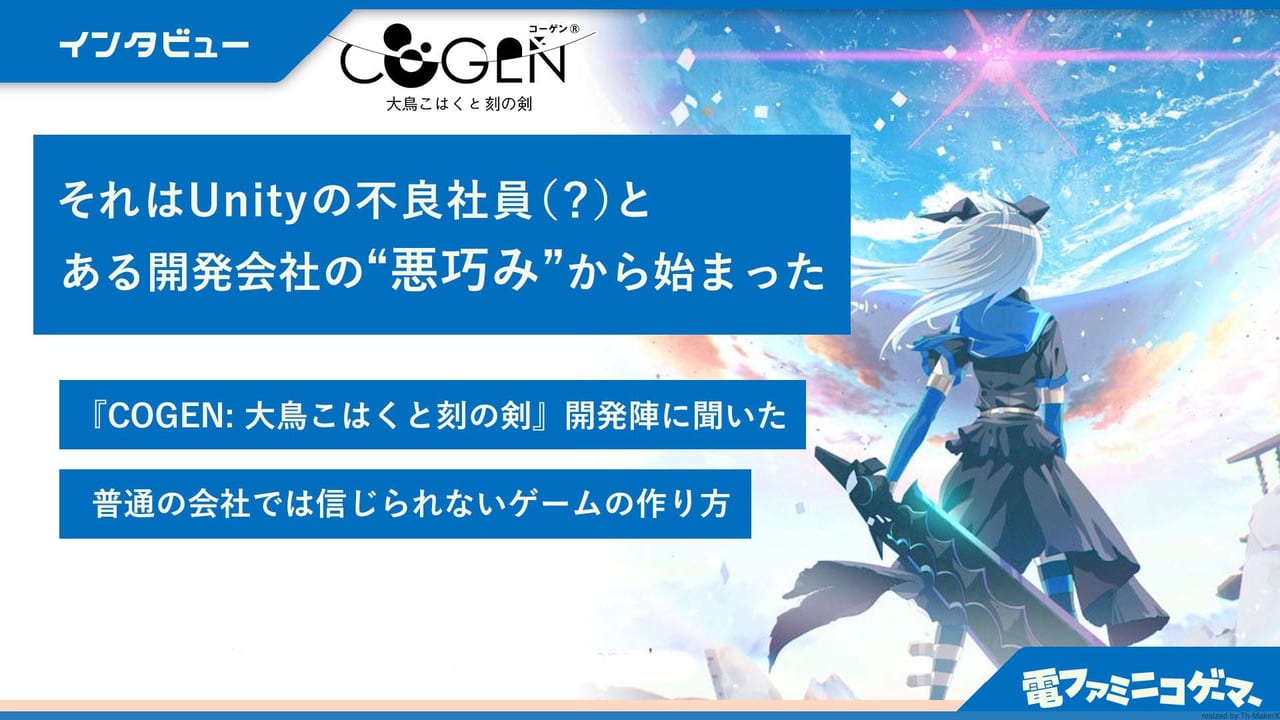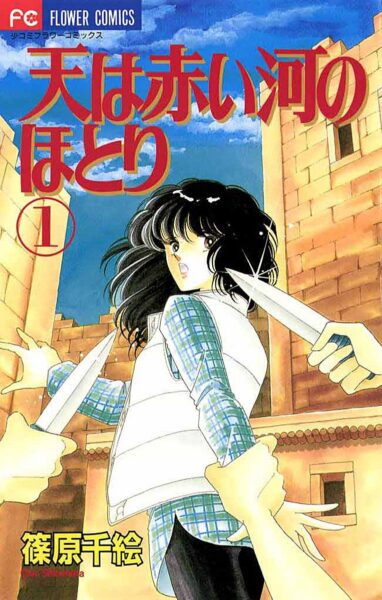会社員として仕事をしていると、「自分のやりたいこと」をやるのはとても難しい。自分のやりたいことと会社がやりたいことが一致すればそれに越したことはないが、組織のなかで自分の意見を通していくのはそれだけで大仕事だ。
とはいえ、「隙あらば自分のやりたい企画やアイデアを通してやりたい……!」という野望を抱いている方も少なくないはずだ。
しかしここに、それを本当にやりとおしてしまった男たちがいる。
当初はそんなに大きなプロジェクトでもなかったのに、うまいこと話を転がしていき、ついには1本のゲームを作り上げるまでに大きくしてしまった。
そうしてできたゲームが、この『COGEN: 大鳥こはくと刻の剣』(以下、COGEN)である。

本作は、そのプロジェクトの始まり方からして、「普通のゲームの作り方」をいっさいしていない。もちろん商業的な作り方ではないし、インディーゲームとして見てもかなり異質だ。
発起人はUnityのエヴァンジェリストという本業の傍ら、仕事終わりや休日を返上してゲーム制作に携わる。
ゲーム開発を担当する方もこれまた曲者で、ディレクターもチームリーダーも、広報も営業もいないという。その代わりに、ゲーム開発はもちろんPVの作成やSNSの運営、パッケージのデザインを含めた一から十までを現場の開発者自ら手掛けるというストロングスタイルだ。
こうして走り出していった彼らの関係性は、いわゆる「クライアント」と「パブリッシャー」に収まるものではなかった。彼らはともに、4〜5年という時間をかけて悪巧みを仕掛ける「バディ」となったのである。
というわけで、このたび電ファミ編集部がお話を伺ったのは今回の「悪巧み」を仕掛けた男たち──『COGEN』開発を担当したジェムドロップ代表の北尾雄一郎氏とゲームデザイナーの今井尊氏、そしてUnity Technologies Japanの大前広樹氏だ。

「言われた通りには作らない」「ステージが出来上がってからストーリーやキャラを作っていく」……。
そんな原作ありきのゲームとしては考えられない手法で作られた本作は、しかし開発担当の横スクアクションや往年のレトロゲームへの並々ならぬ造詣の深さによって、ゲーマーも唸る「激ムズ2D死にゲーアクション」へと鍛え上げられた。
話を聞けば聞くほどハチャメチャなエピソードがどんどん出てくるが、一方でそこには「自分のやりたいこと」を「会社員の身でありつつも、どうしてもやり遂げたい」というたしかな情熱があった。
始まり方も異質なら、作られ方も異質。そんな本作の制作秘話をぜひご覧いただきたい。
「これがユニティちゃんの原作だ!」と思える1本を作る必要性を感じた
──今回の『COGEN』の話に入る前にまず「大鳥こはく」こと「ユニティちゃん」とは、というところから入らせていただければと思います。もともとはどのような経緯から誕生したキャラなのでしょうか。
大前氏:
最初に発表したのは2013年の12月だったかな。12月のコミックマーケットでお披露目したのが最初でしたね。
 |
北尾氏:
2013年って、うちの会社ができた年ですよ(笑)。
 |
大前氏:
あ、そうだったか(笑)。で、モデルやデータを公開したのが2014年の4月のことでしたから、もう随分長いですねぇ……。
ユニティちゃんというのは、いくつかのミッションを背負って作られたキャラクターなんですね。Unityは西洋のディベロッパーが作っているエンジンで、日本のディベロッパーさん視点から見ると、キャラクターの表現などの雰囲気が違うというのがありました。
そこに魅力的なキャラクターを置くことにより、「Unityではこんなことができるんだよ」というのをコミュニティに伝えたり、我々Unityを開発している側に対しても「こういうのをやらんといかんのやで」という伝え手としての機能を背負わせたんです。
もうひとつはやっぱり創作の時に気持ちが上がる、「これなら自分も作ってみたい!」と思えるキャラクターを置きたいというのがありました。当時、意識していたのが初音ミクですね。初音ミクの場合は剣や銃を持ったりといった激しいアクションがキャラクターイメージと合わないという点もありましたから、その辺りも難なくこなせるキャラクターをきちんと作った方がいいだろうと思っていました。

それで実際にフライトユニットさんに「こんなキャラクターを作りたいんです」とお話をかけまして、キャラクターデザインなどあれこれ1年半ぐらいかけ、生まれたという経緯でした。
そこからユニティちゃんは、Unityが導入するキャラクターを動かすシステムの使い方を実践したり、3Dモデルに声、アニメーションといった新たに追加されるアセットを紹介するなど、ユーザーさんのやりたいことを応援する存在としての活動を始めました。
Unityの商売的な視点から言いますと、いろんな機能を皆さんに使ってほしいんですね。それをユニティちゃんというキャラクターを通し、伝えることによって、より多くの人が使いたくなったり、試してみたくなるだろうと。
その背中を押すためのミッションを背負ったキャラクターなんですね。
 |
──僕の記憶が間違っていなければ、当時って動画の世界だと「フリー素材」みたいな概念があって、それが作るハードルを下げる役割を担っていましたし、初音ミクやゆっくり霊夢なんてまさにその位置づけになっていたように思います。
ゲームの世界だと、まだUnityが世に出てきて間もなく、ユニティちゃんも姿を見せていない頃で、何とかハードルを下げたいみたいなことをすごく仰っていたように覚えています。
大前氏:
そうですね。ただ、実際に「クリエイターを応援しよう!」とは言っても、「実は作りたいものがない」という人が一番多かったりするんですよ。なにか作ってみたいという思いはある。だけど、具体案は全然ないというのがほとんどでして。
北尾氏:
エンジニアにも「実験したい」という思いはあっても、大きなゲームを作るほどではなかったり、ゲーム作りをやらない人も過半数いらっしゃるんですよね。
大前氏:
ただまあ、当時はねぇ……Unityに入っていたアセットの3Dモデルって、低品質な配管工のおっさんだったんですよね(笑)。
北尾氏:
そうそう、黄色いヘルメットを被った(笑)。
一同:
(爆笑)
 |
大前氏:
なんというか、マリオのパクリの6頭身のおっさんみたいな“何か”がいたんですよ。このキャラクターで何か試したいと言っても、そりゃあ「ウッ……」となってしまうよねと言いますか(笑)。
仮にそれで技術的な凄いことをやったとしても、見てくれる人なんて限られてしまうのは目に見えていますし、その意味でもちゃんとしたキャラクターで担保しようと思いました。
初音ミクがそうですが、当時のニコニコ動画で「ニコニコ技術部」がいろいろなことを実験しているのを見て、キャラクターを魅力的にすれば、作る人の「何かやってみたい」という気持ちを刺激する広報役として働くというのをすごく実感していたんですね。だからユニティちゃんにはそのミッションを担ってもらうんだ、と掲げていたところがありました。
──それでユニティちゃんは与えられたミッションをしっかりこなして、十分活躍していると見えていたんですよね。だから、なぜここに来て、ユニティちゃんを主人公にしたゲームを作ることになったんだろう?と思ってしまいまして(笑)。
大前氏:
いろいろあるのですが、やっぱり「二次創作などで盛り上がってほしい」という思いがあったんです。キャラクターコンテンツというのは連続性を持って、ずっとやっていかないといけないんですよ。そうしないと、キャラクターが死んでしまいますから、何か考える必要があるだろうと。
 |
そもそも、キャラクターというのは好きだから見てくれる、というのがあるんですよね。アセットである以上に本人のファンを増やす、というのは僕らとしてもやらなくてはならない大きなミッションでした。
ただ、我々も大きな予算がかけられる訳ではなかったんです。なのでマーケティングの予算をチョロまかしつつ(笑)、自分たちが使える範囲内でボイスドラマを作ったり、コミックマーケットに出展してみたりなどの活動をしてきました。
ですが、断片的なコンテンツしか作れないんですよね。それだと二次創作をしたくても広げようがないですし、ものすごくニッチな世界になってしまう。アニメをやる、みたいな話もお金がないので難しい……と言いつつ、結局できちゃったりしましたが(笑)、それも結局は断片的なものでしたし、やっぱり「これがユニティちゃんの世界の原作だ!」と思えるような1本がないと、今以上のブレイクスルーを起こすのも難しいだろうという話になりました。
それで、原作となり得るものをしっかり作りたいとの内部的な結論が出て、それを叶えるために今回の『COGEN』が作られるに至った、という経緯ですね。
──けど、最初はあくまでもデモとして走り始めたんですよね?
大前氏:
はい、まあ……最初の掴みを作る、という感じでしたね。
北尾氏:
僕らも薄々気付いてはいたんですよ。「大前さんはきっとユニティちゃんのゲームを作りたいんだろうな」と。先ほど仰られた通り、断片的にキャラクター性を出したり、グッズを出すなどしていましたが、連続性のあるお話というか、土台となる世界観をちゃんと展開しているコンテンツがなかったんですよね。
なので長い目で見ると、おそらく作りたいんだろうな……というのは感じていましたね。
 |
権利元はUnityでありながら、販売はジェムドロップという本来あり得ない形になるまで
──そのように大前さんの頭の中に「原作になるものを作りたい」との思いがあったとは言え、最終的にひとつのゲームにするという目標は当時からあったのでしょうか?
大前氏:
あるにはありました。けど、「焚きつければ行けるかも」という感じですね(笑)。
──そんな『COGEN』は2Dのアクションゲームとして作られ、開発はジェムドロップさんが担うことになりましたけど、これはどのような流れを経て決まったことだったのでしょう。
大前氏:
まず2017年頃、「Unity自身がゲームを作って出さないから、エンジンやツールのクオリティが上がらない」みたいな批判があったんです。
自分たちの作ったツールがどうなれば正解なのか、自社で実践する必要があるだろうということは、ぼく自身も課題に感じていました。ディベロッパーさんから話を聞いて回っても、肝心の自分たちが試せていませんから、確信も得ることが難しかったんですね。
で、ちょうど同じ頃に2Dの機能が整ってきたというのがありまして。当時、Unityは「Unity 3D」というふうにも言われていたのですが、それが3Dの冠が取っ払われるきっかけにもなって。
というのも、iPhoneとかでUnityを使って作られているゲームを調べてみたら、「半分以上が2Dのゲームじゃねーか!」と分かったことがあり(笑)。だから、もっと2Dの機能を増やそうという話になって、シンガポールのチームが担当して機能が強化され始めたんです。それがある程度形になったので、シンガポールのチームに自社実践の話をしたら「出来るんだったらそりゃありがたい話だ」となって。
 |
ならば俺が、みたいな感じで、今はもうご退任されてしまいましたけど、豊田さんに「ゲーム作りたいっす」「丸々1本とは言わないから、このぐらいのお金を出していいっすか」と話してみたところ、「じゃあ、やんなさいよ」と背中を押してくれたんです。
それで3Dは難しいけど、2Dのゲームなら形になる所まで予算をギリギリ出せるだろうし、まとまるのではないかとの目算がありましたので、北尾さんの所へ持って行きまして、「アクションゲーム作んない?」とお話したんですね。
ただ、その頃作り切れるとは思っていなかったので、「プロト(※サンプルゲーム)を作ってよ」という話でした。実践も兼ねていますので、仮に上手くいかなくても機能が検証されて仕事としてまとまりますから。
行けそうだったら、そのまま制作を続行してもらって、Nintendo SwitchとかPlayStationで遊べるようにできれば、と。それで出来上がったゲームを遊んでくれたユーザーに、このようなものをUnityで作れるんだと伝えられて、なおかつユニティちゃんのファンにもなってくれればと思っていました。
で、北尾さんが「やるよ」と言ってくれたのですが、そこからが長くて……(笑)。
北尾氏:
そうですね。結果的に予算は数倍に膨れ上がっていきましたので、「代わりにうちが拠出するから製品として出してもいいですか」と聞いたら、「OKですよ」と。じゃあもう製品にしちゃおう、限定版も出しちゃおうみたいなことになっていきました(笑)。
 |
──それはすごく珍しいパターンですよね。Unityから追加の予算が出るというのが普通なのかもしれませんけど、ジェムドロップもそれを拠出するというのはあまり聞かないケースだな、と。
大前氏:
聞かないどころか、普通はないです!(笑)基本的にはうちが権利元ですから、販売はうちやろ、って話になります。
北尾氏:
普通はそうなんです。けど、Unityさんはゲームエンジンの会社で、そもそもパブリッシング部門を持っていないんですよね。
大前氏:
そうなんですよね。持ってませんし、社内的にも持ちたいと思っていません。
北尾氏:
でしたら我々が見ますよ、と。あと、弊社もいくつかダウンロードのゲームソフトを出しているのですが、パブリッシング事業をやりたいという願望は元からすごく強いんです。
パッケージのデザインから、ゲームを商品として流通させる過程まで一通り担当するというのは会社としての最終目標であり、通過点だと思っていましたし、独立した意味のひとつでもありますので、乗っかろうと。いつか製品として出していいよと言われたら、やっちゃおうという勢いでした。
まあ、作り始めた間にもいろいろありまして……。たとえば『ユニティちゃんはコロがりたい』という3Dアニメを作ることになったのですが、「1クール作らない?」との話が入ってきたのが放送2ヶ月前ぐらいだったとか(笑)。
大前氏:
あれは……ヤバかった!(笑)ヒリヒリしましたよね。
北尾氏:
最初に『COGEN』を作り始めて少し経ってからの話でしたね。ただ、「うちとやるなら100ぐらいにしてお返ししたい」という思いが強いですし、弊社のクリエイターからもやりたいとの声がありましたから、「もう好きにやっちまえ」ですよ(笑)。
大前氏:
作り始めた最初の方は仕事を頼んで、「プロトを作ってください」「それで、続きをやりたかったらどうぞ」という流れだったんですね。とは言え、権利元で発起人ですから、ビルドは都度もらいながら触っていました。
ただ、その頃は停滞していたんですね。いろんなアイディアを入れているけど、どこをどのように楽しんで、誰に向けて作っているのかがボンヤリしていたんです。ただ、僕はその時に原作側の人間として見ていたので、どこまで言ったらいいのか分からなくて。
現場がいろんなアイディアを入れ、あれこれ試している最中に「上の偉い人がワーワー言った結果、ゲームがおかしくなってしまう」というのは割とありがちなんですよね。だから、基本的に投げ込まない方がいいと思って待っていたんです。
 |
けど、暗中模索している時間が割と長くて、「そろそろ何か入れた方がいいのかな」と問題意識を持つようになりまして。ただ、僕はゲーム開発の場ではディレクターとしての実績がありませんし、何より同じ会社でもなければ、ずっと仕事しているチームでもないんですよ。そこに入って取り組むのは違うかな、と気が引けていまして。
そんな時期にアニメの話が入ってきたんですね。もともと、キャラクターのファンを増やす活動には僕自身、ずっと取り組んでいましたので、映像作品をちゃんと作るというのを探求すべきではないかと思いました。それで北尾さんに「アニメ作りたくない?」と声をかけたんですよね。「締め切りは1ヶ月後です」とも言って(笑)。
北尾氏:
「なに言ってるんだ、こいつ!?」でしたよ(笑)。
大前氏:
「バカじゃないのかな!?」みたいな話ですよね(笑)。まあ、さすがに全話作ってとは話しませんでしたけど、北尾さんが「全話一括ならいいよ」と仰ってくれまして。じゃあ……ということで始まったんですね。
あと、ユニティちゃんの原作は僕とntnyさんのふたりで担当しているんですね。ただ、当時ntnyさんはVTuberの年末ライブのイベントがあって、そちらに呼ばれた都合もあって忙しく、関わるのが難しかったんです。
それで、僕がアニメの方をディレクターとしてやることになり、そこからジェムドロップさんのチームと仕事をしたんです。それを通して「あ、一緒に仕事ができるな」という手応えを得まして。それなら『カペラ』、当時の『COGEN』の開発コードネームなのですが、そちらにも踏み込もうとなりました。それが本当に制作の中では転換点でしたね。
北尾氏:
そうでしたね。確か3年前ぐらいでしたでしょうか。
大前氏:
放送が2019年でしたから、ちょうど3年前ぐらいですね。
 |
最初はやられにくいゲームだったが、停滞期を経た末に死にまくるゲームへと“覚醒”
──その停滞していた時期というのはどういった状況で開発を進められていたのでしょう?
北尾氏:
まずサンプルゲームとして作る所から始まった、というのは先ほどの通りです。掲げていたのは「サンプルゲームを作る」「ユニティちゃんが主人公」「2D機能を使ったゲーム」「ドット絵のゲーム」というものでした。
 |
──ステージクリア型のアクションゲームというのもその時点で決まっていたのですか? 比較的最近の横スクロールアクションゲームと言いますと、探索型やローグ系がトレンドになっていたりしますが……。
大前氏:
ステージクリア型というのは早い段階で決まっていましたね。
北尾氏:
逆説的にそうなっちゃったんです。Unityで使えるサンプルのゲームを作らなきゃという所から始まっていますから、ちゃんと閉じなきゃということでステージクリア型にしよう、と。
大前氏:
けど、探索型は止めようという話はしていましたね。2作目ぐらいからならやってもいいかもしれないけど、最初は止めましょう、という感じに(笑)。
北尾氏:
そこから形作っていったのですが、我々としてはユニティちゃんを主人公にするなら、敷居を低くするべきだろう、と。
いろんな人に遊んでもらい、ユニティちゃんを知ってもらうという目的がありましたから、最初は難易度が低いゲームにしていたんです。あと当時、レトロゲームっぽいものにしたいのもあり、いろんな要素を詰め込んでいきました。たとえばパワーアップ要素とか武器のチェンジ、能力アップ、一番大きなものでは体力ゲージですね。なので、今とは違ってやられにくいゲームだったんです。
ところが作っていたらなんか刺激が足りない、「これ!」と言えるものがないという問題が出てきまして。それで、何か新しい仕掛けを入れるという話になりました。
それでちょうどその頃、僕は『SEKIRO(SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE)』を遊んでいたんですね。『SEKIRO』は遊ばれた方にはご存じの通り「死にゲー」で、少しでも気を抜いたら簡単にやられちゃうんですが、そこから復帰して再開するまでにちょっと時間がかかるんですよね。

しかも当時、僕は初期型のPS4、SSDにも換装していないもので『SEKIRO』を遊んでいましたので、余計に長く感じたんです。完全に自分が悪いんですけど(笑)。それで「すぐに巻き戻せないのかな……」と思いまして。
当時だと、同じ時期に『Katana ZERO』も出ていて、これもとても難しいゲームですが、やられるとすぐに巻き戻って再開できるんですね。ただ、『Katana ZERO』はステージが丸ごと元に戻るというものでしたから、じゃあこの「巻き戻し」をもっとうまくできないかな、となりまして。ひとまず、お試しがてら「巻き戻し」を入れてくれないかと現場のスタッフにお願いしたんです。

ただ、この「巻き戻し」ってプログラム的にはメチャクチャ大変なんです。それでも今日は居ないのですが、メインプログラマーの犬伏が頑張って入れてくれたんです。入れてくれはしたのですが……まだその当時は3秒の縛りもなく、ギュルギュル延々と戻せちゃうものでして。加えて体力ゲージも残ったままだった。
まさにここから停滞している時期に入るんですが、「見た目的には面白い、だけどピリッとこない」という状況に陥ってしまったんです。
その頃に『ユニティちゃんはコロがりたい』の制作が始まり、終わった辺りになって大前さんとディスカッションしたんです。そこで「死にまくる方に振ったらよくね?」という話になりまして。
「とりあえず体力ゲージを無くしましょう」、「敵は完全に殺しにくるようにしましょう」ということになりました。それで普通のアクションゲームの2~3倍は敵の弾が飛んでくるようになりまして(笑)。
加えて一撃死なので、すぐにやられてしまう。けど、巻き戻してやり直せるという流れが出来上がりまして、ようやく「これ面白いかも?」と活路を開けた感じでした。そこから弾は打ち返せるようにしたい、とかも出てきましたね。
大前氏:
あ、でも弾を打ち返す機能は最初の時からありましたね。巻き戻しも後付けで入れたという感じではなく、『COGEN』の下地にしている『The Phantom Knowledge』というコンテンツが元としてありました。
『The Phantom Knowledge』はUnityにタイムラインという、カットシーンを作るための機能が実装されたことをお伝えするプロジェクトとして、ユニティちゃんを使ったり、『エースコンバット』のチームに音楽を発注したりして制作したんです。それがシリアス寄りの作風で、アクションゲームの題材としてハマりそうでしたから、やりませんかということで北尾さんに話したんです。
ntnyさんにもユニティちゃんをリブートするなら、『The Phantom Knowledge』をベースにした方がいいということで話題にあげていたんですね。
それで、北尾さんからこれはループモノのお話っぽいから、時戻しの機能を入れたいとの話があって、実装してもらったように僕は覚えています。それで、弾の打ち返しとかのアイディアもたくさん入っていたんですけど、面白さには繋がっていなくて。
ちょうど『ユニティちゃんはコロがりたい』が終わった辺りに死にゲーへの転換を提案し、いろいろ整理していく中、打ち返しは当時から面白かったから残った、という感じでしたね。他にも面白い所を全部ピックアップして強化することをやりました。そしたら、徐々に真ん中にあるジェムが見えてきた感じで(笑)。
開発チームがやりたいことを中心に要素を揃えていくという流れへと変わっていきました。僕がディレクションをしていた時期の中で、一番大きく変わったところというのはその辺でしたね。
あと、このタイミングで今井さんも覚醒されたんです(笑)。
今井氏:
(笑)。
 |
北尾氏:
今井はレベルデザインの99%を担当しているんですね。僕らおじさんたちは遊んでもっとこうしよう、ああしようと言ったぐらいで(笑)。それをデザインしたのは全部彼でした。