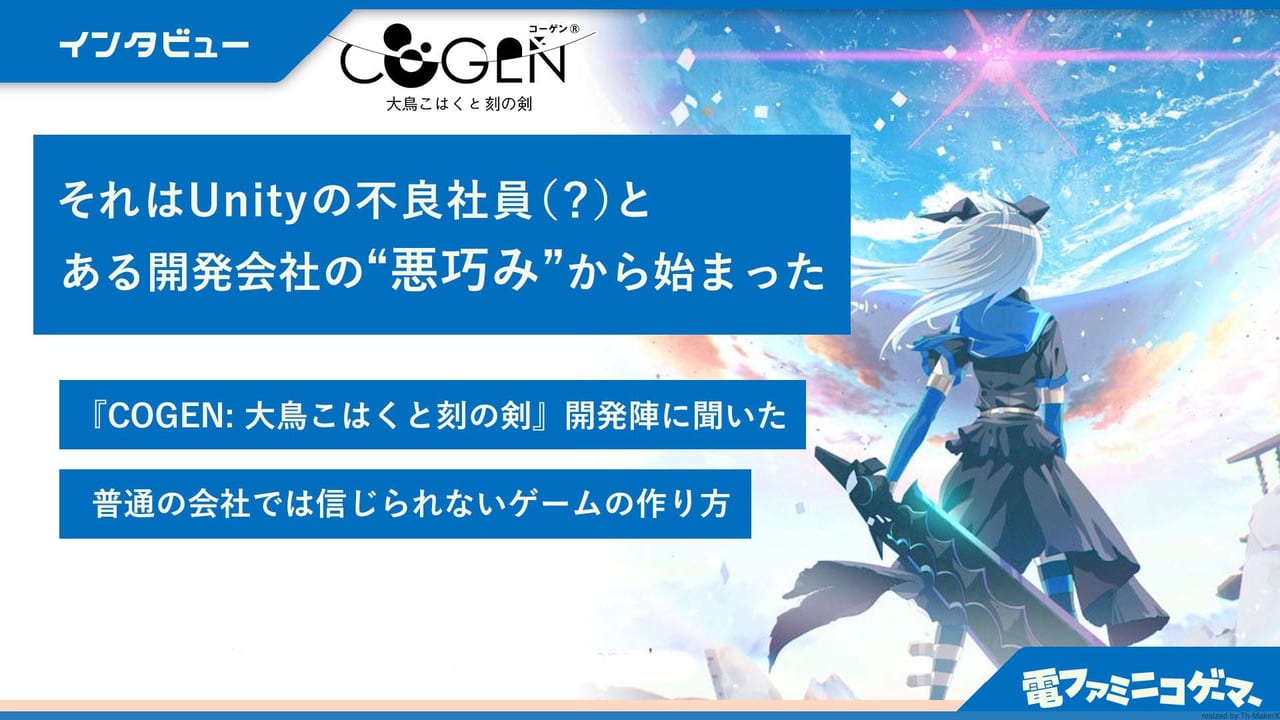新潟の専門学校に野生児がいた
──つまり、ジェムドロップ側の開発ディレクターは今井さんということなんですね。
今井氏:
いや、ディレクター……ではないですね。
大前氏:
ゲームデザイナーですね。
北尾氏:
そもそもこのプロジェクトってディレクターが不在なんですよ。いろんな人が管理しているものがまとまった、という感じでして。もともと、ジェムドロップという会社自体がプロデューサー、ディレクター不在なんです。
 |
弊社は60人ぐらいの体制で、複数のチームが動いているんですが、基本的に私が外とのやり取りなど、プロデュースとディレクションをやっているんです。現場は完全に現場主義で、まずお互いにこれどうしようと考えてもらい、その過程で行き詰まった時に私の所へ聞きにきて、「じゃあ、こうしよう」というふうにジャッジするというスタイルにしているんですね。
なので、チームごとにディレクターというのは基本的に存在しないんですよ。
──え、でもチームリーダーはいるんですよね……?
北尾氏:
チームリーダーも厳密には居ないですね。
今井氏:
まあ、そうですね。
大前氏:
その作り方でどうして完成にまで至れるのかという(笑)。
北尾氏:
(笑)。まあ、1個のチームは全部小さいんですよね。普通の会社なら60人規模なら60人で1本作るというのが多いですけど、うちは『COGEN』の場合ですとコアメンバーは2~3人しかいません。
大前氏:
停滞していた頃に僕が途中から入り、1回ディレクションして、1年ぐらいディレクターを引き受けたという感じでしたね。ただ、全部ディレクターがやるのではなくて、今井さんと犬伏さんのコアメンバーと話し合い、分かったらそのまま作っていただいて、後になって見せてもらって調整する、というものでしたね。
 |
北尾氏:
大前さん自身が外にいらっしゃる御方ですから、普通のゲーム開発と違ってずっと付きっ切りという訳ではないですからね。どれぐらいのペースでしたっけ?
大前氏:
2週間に1回でしたね。Slackとかではずっとやり取りしていましたけど、ジェムドロップのオフィスに来てビルドをチェックするのはそれぐらいのペースでした。端から端まで全部遊んで、こっちから「あーせい」「こーせい」じゃなくて、課題を出して後々に取り組んでもらうという感じです。
北尾氏:
まあ、普通のクライアントとパブリッシャーとの関係では全くないですね。
大前氏:
そうですね、ほとんど開発メンバーのひとりという感じでした。その意味では、箸の上げ下げまでみっちりディレクションするようなものではなかったです。
北尾氏:
事実上は僕が最初からプロデューサー兼ディレクターをしていたのですが、途中からディレクションの方が難しくなってきまして。なので、今井は若手ですし、「社内の若手から1本作れる人間が育ってくれるといいな~」という願いを込めて見守っていました。今日初めて聞くかもしれないけど(笑)。
一同:
(爆笑)。
 |
北尾氏:
停滞した時期がありましたけど、だいたい1年ぐらい前からは手放したままでも自走してくれる状態になっていきましたね。
大前氏:
そうですね。型が決まりましたから、事細かに言う必要もないだろうと。北尾さんの言った通り、自走できるチームですから、こちらは監修と調整に徹しました。
しかも、大体1を伝えると10ぐらい返してくれるんですよね。たまに12、13ぐらいまで返してくることもあって、2~3削らせてみたいなこともありましたが(笑)。
ただ、すごくやりやすかったですし、僕の方は原作側としてやらなければならない仕事があって、それは外注できないということで、そちらに時間を使うようになっていきましたね。
──ちなみに今井さんが『COGEN』のチームに入った理由とか経緯はなんだったのでしょう。
北尾氏:
実は最初から入っていないんですよね。
今井氏:
はい、そうですね。
 |
北尾氏:
最初は別メンバーで作っていたんです。それが3年前、大前さんともそんなにやり取りせず、プロトを作っていた頃のことですね。その時に彼は別の企画をやっていました。
ただ、ゲーム化の動きが本格化していく中でステージや仕掛けの話が出てきて、ちょうどそのタイミングで彼の手が空いたんです。確か『クライスタ』を担当していた頃ですね。
で、彼は横スクロールアクションゲームが好きであるなどの経歴が分かっていましたから、入れるのがベストだろうと考えて仕向けました。「横スクロールアクション好きだよね?」「はい!」というふうに(笑)。
──そんな今井さんの経歴をお伺いできればと思うのですが(笑)。
今井氏:
は、はい(笑)。ジェムドロップには新卒で入社しまして、最初にやったのが『ヘディング工場』でした。そこからいろんなことをやりつつ、ですね。大きなところでは『クライスタ』でゲームデザイナーを担当しました。その後に『COGEN』という流れですね。

北尾氏:
新潟の専門学校に行ったら野生児がいたので拾ってきました。
一同:
(爆笑)。
北尾氏:
名指しで採用した感じだったよね。
今井氏:
そうですね……! 自分ひとりだけでしたね。
──今井さんのどの辺りに惹かれたのですか?
北尾氏:
なんと言いますか……「純粋にゲームを面白くしよう」という意志が強かったのがあります。よくある「RPG作りたい」、今だと「あのバトルロワイヤルシューターみたいなのが作りたい」みたいなのではなくて、「あれもやりたい、これもやりたい」という思いが強かったんです。
そこが弊社の方向性とも合致していまして、「じゃあ、うち何でもできるけどやってみる?」と聞いたら「やりたいです!」と返ってきた、というのがひとつですね。
もうひとつは歳の割にレトロゲームをすごくたくさん遊んでいるんですよ。昔のゲームは機能が限られている中で、ゲームの仕組みで面白さを出しているものが多いですが、それをよく理解しているというのもありました。
私も昔はプログラマーで、トライエース在籍時は『ヴァルキリープロファイル』の1と2、『スターオーシャン3』を作って、仕組みの面白さの重要性を把握していて、『COGEN』はそこを重視したいという思いがありました。話をしてみたらウマが合ったので、惹かれたという感じですね。

ただ、どうして世代じゃないのにファミコンとかスーパーファミコンのゲームをやっているんだ?という(笑)。
──今はおいくつなのですか?
今井氏:
今は27で、今年で28になります。どうして昔のゲームを遊んでいたのかというと、僕の兄弟がスーパーファミコンを持っていまして、それがゲームを始めるきっかけになりました。 ただ、当時の小遣いは500円ぐらいしかなくて、それで買えるゲームソフトってファミコンやスーパーファミコンの中古ソフトぐらいだったんですね。それで小学校高学年辺りからですが、ハードオフのジャンクコーナーに出向いて買い漁るようになりまして、それでたくさん遊びました。
──その頃だと確か、DSやPSPなどが主流でしたよね……? そちらと一緒に遊ばれていたと?
今井氏:
もちろん、最新のゲームも追いかけていましたけど、レトロゲームの方も一緒に遊びつつ……です。今も続けています。
──それって友達と遊ぶ時は最新のゲーム、ひとりの時はファミコンというような感じだったのですか?
今井氏:
そうですね……! ひとりで遊ぶ時もあれば、みんなでモンハンを遊んで飽きたら、面白いゲームがあるんだぜーって言って一緒に遊んで、みたいにやっていましたね。
 |
──そういうのって当時では珍しかったんですかね? 周りにもやっている人はいらしたのでしょうか?
今井氏:
周りでレトロゲームを遊んでいるという人はあまり居なかったですね。何か遊んでいると、「うわ!これ保育園の頃にやったことがある!!」みたいに友達が反応するぐらいで(笑)。そんなに「ウオーッ!」みたいなのはなかったです(笑)。
北尾氏:
何が魅力だったんでしょうかね(笑)。僕らおじさまたちはファミコンもスーパーファミコンもリアルタイムで「これが最新だ!」というものを当時遊んでいましたから。
今井氏:
まあ、やっぱりクリアした時の達成感ですね、どうやっても自分の腕でやるしかないという(笑)。ジャンプとキックしかできないのにメチャクチャ難しく、クリアした時に誰かに褒められる訳でもないけれど、それを成し遂げてやった感が好きで、ずっとやっていましたね。
北尾氏:
ある意味、『COGEN』に繋がっていますね(笑)。
今井氏:
そうですね(笑)。『スパルタンX』とか、ナイフを投げてくるだけなのに上か下かを見極めたり、後ろから抱き着いてくる男が来た時はこうするみたいな駆け引きが面白くて、虜になりましたね。
大前氏:
小学生ぐらいだとやっぱりルールがシンプルな方が燃えるんですよね。それにいろいろ言われないというか、チュートリアルもありませんからね。
今井氏:
そうですね。説明書が無く、そもそもボタンが少ないからというのもありましたし。
 |
大前氏:
シンプルで遊びやすいとか、入りやすいというのはありますよね。ロードもないですし(笑)。
今井氏:
ただ、一番苦戦したのはセレクトボタンですね。このボタンで操作を変えられるというのは一番「えっ!?」と思いました。
大前氏:
あ、そうか!説明書読まないと……!
今井氏:
はい、ソフトしかないですから、どうやってもカーソルを動かせないというのがありまして。「何かしないといけないのかな?」と思ったら、実はセレクトボタンをポチっと押すだけだったという。
北尾氏:
昔は十字キーの上下でメニューが切り替わらないものとかありましたからねぇ。
今井氏:
「あ、そこか!」みたいな(笑)。
北尾氏:
そういうことから、割と稀有な人材だったんですね(笑)。
 |
方向性確定と共に開発が進み、ひっそりDLCが作られていた
──そんな今井さんの視点から見て停滞していた時期とか、そこからの変化というのはどんなものだったのでしょう?
今井氏:
別のチームにいた時も思っていたんですが、「もうちょっと難しい方がいいんじゃないのかな……?」というのはありました。ただ、最初は難易度低めでいろんな人に遊んでもらうというのを掲げていましたので、「いや、でもそれはなぁ……」と。いざチームに入ってからも、もう少し難しくしていいんじゃないのかとは思っていたんですが、でも……と気が引けていました。
その後、大前さんから「難しくしよう」と来た時は「じゃあ、一気に」と(笑)。いろいろなものを取っ払いつつ、自分の中で「やり過ぎだろう!」というぐらいまで持っていこうと思いました。それでやってみたら割と好評でしたので、それからは思いっきりそちらに舵を切って突っ走りましたね。自分でも思うところがあったからこそ、というのもありました。なので、やり易かったです。
大前氏:
問題意識を共有する所で右往左往することはなかったですよね。あとは順番の話だけで、そこの整理ができれば後はけっこう、すんなりと進みました。ステージも数が決まっていましたし、敵キャラクターもある程度グラフィックが描かれていて、これ以上は追加できません、という状態にありましたし。まあ、敵キャラクターは増えたんですけど(笑)。
 |
あと、ゲームは難しくていいけど、システムが敵になっちゃダメだと。これは僕が昔、フロム・ソフトウェアに在籍していた頃に学んだことでもあるのですけど、「システムに邪魔されるせいで難しい、理由も分からずに死んでしまう」みたいなのは止めようと言って整理していきました。
たとえば、自分の目に見えていてその意味が分からなくてやられるみたいなのはいい、だけど画面外から撃たれたり、押されたりするのはダメだよ、という具合に口酸っぱく言わせていただきましたね。ただ、もうそれを伝えて整理するぐらいで、そこから先は分かった上で自走してくれた感じでした。
北尾氏:
そこは僕からも提案を出していて、たとえば敵が持つ銃の弾道には射線(※ゲーム中ではレーザーサイトとして表示)を出すとか、そうすることで「あ、来るわ」と分かって、失敗してもそれが原因だと理解できるんですよね。
それなら、どこまで巻き戻せば前に進めるんだろう、というふうに持っていけますから、その辺は上手く設計できたなとの手応えがありましたね。
──しかし、外部のディレクターが立つというのも相当珍しいケースですよね。フリーのデザイナーさんとかではやられる方もいますけど珍しいですし、あまつさえ途中から入ってフェードアウトというのもなかなか聞かないです。会社的にもどうしてディレクター不在の体制にしているのかというのはすごく気になります。
大前氏:
まあ、別にフェードアウトはしていませんけどね。ただ、全部引き受ける必要は無くなったといいますか。手放しはしていないです。
北尾氏:
権利元はUnityさんですし、僕らも勝手にキャラクターの設定を変更したりはできませんから。
大前氏:
ん? あれ? いや、でも敵増やしたよね?(笑)まあ、それはいいや。
北尾氏:
(笑)。まあ、ディレクターを何名か置いてすごく作家性の強いものを作るのはできると思いますし、それがある意味、スタジオの強みになるのは確かですね。たとえばフロム・ソフトウェアさん、コジマプロダクションさんとかはそうですし。私自身もそれがやりたいか、やりたくないかで言えばやりたいんです。
ですが、どうしても作れる本数に制限が出てしまうのと、長い目で見ると大それた話ではありますけど、やっぱり若手の作家の数を増やしたいというのがすごくあるんですね。
そうなると、私が全てにおいてディレクションすると、私個人の作家性が出過ぎてしまう。なので、そうならない形でやりたいと思っているんです。まあ、結果論ではあるんですが、本数が増えると1個に対する作家性は減ってしまうので、そこは仕方がないかな、と。ただ、なるべく指示待ちの人間を置きたくないんですね。
 |
自主性を持って、各々のやりたいことをゲームに詰め込むというのをやりたい。究極的には、「このゲームはわしが作った」というふうにスタッフ全員がひとりずつ持ってほしいというのが狙いとしてあるんです。
誰かのおかげではなくて、何かが出てこれが流行ったのはわしのおかげ、キャラクターが可愛いと言ってもらえたのはわしのおかげみたいに。そう形にして、開発者満足度みたいなものを上げたい意図があるんですね。
まあ、それは究極の話であって、実質的には難しいのですが、なるべくそういうスタジオにしていきたくて、そうなると指示待ちの人を置くと完璧に近いディレクションなり指示が必要になるんですよね。それは我々のスタジオとしては目指している所ではない、と。
指示して箱を決めると、箱の通りには仕上がる可能性はありますけど、それを超えるものはどうしても出てこなくなりますから。まさに先ほど、大前さんが10頼んだら12出してくるとか、あの人に1だしたら10になっていた、みたいなのは本当に目指しているところでして。そういう歪な形を作れるのが僕らの強みであると同時に、やりたいことなんですね。
──まさに土地は限定されているけど、容量や面積は大きいみたいな感じですかね。
北尾氏:
そうですね。
大前氏:
僕もUnityに所管を設けた時、そのような社是で取り組んでいたところがあったんですが、そういうチームは仕事がしやすいんですね。なので、今回は技術的なアドバイスを全然していないんですよ。
僕は出自がプログラマーで、本来はそれが自分の強みであるはずなんですが、僕ができてもこのチームが出来なかったら仕方がないので、基本的にはやらないと。チームでできることに自信を持って作ってもらうことがディレクションの上で重要でしたので、今井さんも犬伏さんもこれができる、と思ったことを基本、面白くするためにガイドするというのはやりました。Unityならこれできるでしょ、みたいな話はしなかったです。
 |
北尾氏:
でしたね、一切なかったですね。それをあえて言わないのはやり易かったと言えばやり易かったですが、それはある意味、信頼されているからなのかな、というのは思っていましたね。
大前氏:
あと、今井さんがレトロゲームとか、いろんなゲームを遊ばれていますので、話が通じやすかったんですよね。仮に遊んだことがなかったゲームがあった時も、北尾さんがレトロハードを用意してくれるとかもありましたし(笑)。
北尾氏:
何と言いますか……アクションゲームの宗派が違っているんですよね。大前さんは若干トレジャーさん寄りで、今井はカプコンさん寄りでして。ただ、どちらもそれを分かっていますので、通訳した上で「じゃあ、君はこれを遊びなさい」という具合にNINTENDO64と一緒に『ゆけゆけ!!トラブルメーカーズ』【※】を渡して遊んでもらったりとかしましたね(笑)。
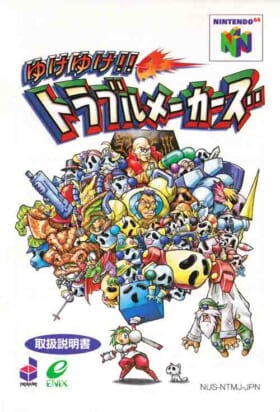
(画像はゆけゆけ!!トラブルメーカーズより)
──宗派の違い……?それは具体的にはどのようなものなのでしょう?
大前氏:
コントロールの癖みたいなものかな……。たとえばジャンプの挙動とか、トレジャーさんのアクションゲームだと独特の癖があったりするんですよ。
ただ、別に特定のゲームをインスパイアしようというのはありませんでしたから、どちらかというとコミュニケーションの手段、「あれのこれ」みたいな感じと、話しやすくするためというのが目的でしたね。
──ただ、アクションゲームって手触りがだいぶ重要じゃないですか。それこそジャンプなら、どれだけちょっと動かせるのか、飛び上がるまでの速さとかタイミングとかでだいぶ変わってきますよね。その辺の手触りの調整も今井さんがやられたのですか?
北尾氏:
それはほとんど犬伏ですね。多分、今井は触って「こうかな?」とまでは言っていると思いますが、指示はほぼゼロだよね?
今井氏:
そうですね。ここはこんな感じで、みたいな作り方でしたね。
北尾氏:
それを犬伏に伝えて彼がプログラミングし、出来上がったものを遊んでフィードバックし……という流れを、この場の席の距離感でずっとやっていたような感じでしたね。
大前氏:
最終的には『COGEN』の動きはこれだ、というのを決めるため、作っていった感じですね。なので明確にどれかの宗派でやっています、というのはないです。
北尾氏:
いろいろインスパイアはされていますが、結局は巻き戻してナンボなものでして。自動で死んだ瞬間で止まるように見せて、実は止まった瞬間から自動で数フレーム勝手に戻っているようにしているんです。
死んだところでピタッと止まるんではなく、その時に若干戻している。そのような調整は完全にこのゲーム向けと言いますか、オリジナルの調整が入っている感じですね。
 |
大前氏:
あと無敵時間を少し入れてくれ、どこでも動きをキャンセルできるようにしてくれとか、そのような話はずっとしていました。やっぱりシステムが敵になってはいけないというのは重要で、それが『COGEN』を気持ちよく遊ぶための一番難しいところですから。
巻き戻しは行動の途中まで戻す訳じゃないですか。それがシステム上の都合で思った通りにできない、できなくなってしまうという問題が大量に発生してしまっていたんです。そういうのを無くすため、行動を全部キャンセルできるようにしてほしいと。まあ、無茶なことを言っているなとは思いましたが(笑)、そこまで持っていけたのは本当に犬伏さんの大事業でしたね。
今井氏:
本当にけっこうな時間がかかりましたね……。
大前氏:
ジャンプにも2段ジャンプの2回目をいつ押したか問題みたいなのがあるんですよ。なので、空中で死んでしまう時にもう1回、ジャンプしないと巻き戻しても意味がなくなることがありますから、必ずジャンプできるようにしましょうとか、無敵時間を入れましょうとか、いろいろやり取りしたものが今の形になっていますね。
 |
北尾氏:
ゲーム自体は1年前には大体メカニクスも全部できてたんですよね。ただ、調整にだいぶ時間をかけた感じで。
今井氏:
はい。手触りに関してはかなり時間をかけましたね。
大前氏:
最初は動きを直すところだけでも3ヶ月は使いましたからね。やっぱり最初はそこがよくなくて、剣を振るまでに1~2フレームあったり、ジャンプしている時に剣を振って着地するとキャンセルされてしまうとか、いろんな問題があって、その細かい部分を直したりとかたくさんしましたね。壁蹴りも壁を触っていない状態でも蹴れるようにしたり。そのようにしないとユーザーさんが気持ちよくないだろう、と。
北尾氏:
落下している最中、壁から離れた瞬間でも数フレームはジャンプを受け付けるとか、ギリギリの所からジャンプして着地するとか、そのような調整は細かくやっていましたね。
大前氏:
まあ、そこはチームが自主的にやっていたので、どんどんいい感じになっていきましたね。
北尾氏:
それで残りの1年間は調整しつつ、その隙間にコラボを進めたり、追加のDLCステージを作ったりとかしていましたね。
大前氏:
DLCの話をされた時はマジでビックリしましたね(笑)。僕が「いやー、終わったー」と思って行ってみたら、「実はDLC作っているんですよ」と来て、「マジで!?」みたいな(笑)。ちょっと待ってよ、という。
北尾氏:
コラボも他社のキャラクターで丸々プレイできちゃうんですけど、いいですか?と(笑)。
大前氏:
マジでビックリしましたね。原作側の仕事としてはストーリーを入れる仕事を一生懸命、ntnyさんと一緒にやって、全部仕上がって終わったーみたいになっていた所に「実はDLCが……」ですから。「ストーリーどうすんねん!」という(笑)。
「コハク……コハクか!俺らもこはくじゃあないかッ!」
──そのDLCのひとつ、『白き鋼鉄のX(イクス)2』(以下、イクス2)の主人公「アキュラ」のエピソードですが、これはどのような経緯から決まったのでしょうか。あと『イクス2』と『COGEN』って発売日も被っていますけど(笑)、それもどうしてそのようになったのでしょう。
北尾氏:
コラボは全部、僕の一存で決めました(笑)。『イクス2』を作られたインティ・クリエイツさんは、ずっと2Dアクションを作り続けていて、5~6年前から『蒼き雷霆(アームドブルー)ガンヴォルト』シリーズで成功を収められ、ディベロッパーからパブリッシャーへと上手く切り替わった会社さんなんですよ。

それを横目で見ながら、「インティさん凄いな、僕も学んでみたいな」というのがひとつとしてありました。あと、日本のディベロッパーが作っている2Dアクションが減ってほしくないというのと、せっかく同じ2Dアクションを作るのですから、一緒に何かやれたらというのがありました。
それをインティさんの社長である會津さんに持ちかけたんです。會津さんも「こういうゲームを作ってくれる会社がもっと増えてほしい」と仰られまして、じゃあ一緒にやりましょうということで、だいぶ前に振っておいたんです。
ただ、最初は『イクス2』ではなく、『蒼き雷霆ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』とのコラボという話だったんです。ちょうど、ガンヴォルトのヒロイン(※主人公のきりん)が剣術使いで、被っていましたので(笑)。
ところが、『蒼き雷霆ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』は開発の遅れもあって難しくなってしまったんですね。そしたら、実は裏で『イクス2』を作っているんですという話がありまして、そちらでやりましょうということになりました。

けど、具体的に何をするとかは決まってなかったんです。ただ、イクスにはコハクという女の子が出てくるんですよね。
それで「コハク……コハクか!俺らもこはくじゃあないかッ!」と(笑)。
──なるほど(笑)。

(画像は白き鋼鉄のX(イクス) THE OUT OF GUNVOLT│公式サイトより)
北尾氏:
じゃあ、「そちらのコハクちゃん貸してください!」と話したんですけど、どうもしっくり来ず、もっと面白いことをした方がいいのではと思ったんです。それで「主人公のアキュラを作る?」という方向になりました。
実は今井はインティさんのファンでして、決まって以降は彼らに黙って勝手に作り始めたんですね(笑)。で、ある程度、アキュラが動くようになってから會津さんに「ちょっとこれ見てください」と渡しまして、「やっべえ……!アキュラになっとる!」と(笑)。そこから「いいですか?」と伺ったら「全然いいですよ!」となって、出す形になりました。
それでお互いノリノリになって、折角コラボするなら普通のメーカーがやらないことをやろうということで、発売日も被らせたんですね。普通のメーカーなら絶対ずらしますし、一緒にもしないのですが、そのようにした方が話題にもなりますよね。
もちろん、リスクもありますが。結局、あっちも買わないといけないし、こっちも買わないといけないしで。だから、どちらかの数は減るんでしょうけど、それでも話題にはなりますし、相乗効果も確実にありますし、どうせコラボ両方入れ替わり付いているのなら、同発にしちゃいましょう、となりました。
ただ、これでどちらも逃げも隠れもできない状態にもなったんですね(笑)。万が一延期にでもなったりしたら……と、怖かったです(笑)。
 |
──ただ『イクス2』と『COGEN』、どちらの購入も考えていたユーザーからは「なんでどちらも遊びたいのに同じ日に出るんだよぉッ!」みたいな悲鳴が割と発売日発表当時に出ていましたよ(笑)。
大前氏:
「両方買いたくてもお財布が辛い!」というヤツですね(笑)。
北尾氏:
まあ、普通やらないことをやろうと言いますか、インティさんもどちらかというとそういう考えの会社さんなんですよね。普通はつまらないよねと。だからトップで決めちゃって、トップダウンでそのまま下ろしちゃって(笑)。
今井氏:
そうですね(笑)。当時、ガチャっと会議室から出てきた後にイクスの資料が出てきまして、「いや、これは……え!?ガンヴォルト3じゃないんですか!?ってか、イクス2出るの!?2出るんですか!!?」という(笑)。
皆さんが発表を聞く前から知っていましたので、けっこう待たされるなと思いつつ「じゃあ、やりましょう!」という感じで突っ走りました。それで、山田一法さんの楽曲を桜庭統さんにアレンジしてもらいたいという話をしたら、「じゃあやりましょうよ」となって「え、本当に!?」と(笑)。
北尾氏:
向こうで山田さんが書いた曲を桜庭さんにアレンジしていただいて、こちらで桜庭さんが書いた曲を山田さんにアレンジしていただいた曲が、それぞれ相互で入っているんですね。なのであっちも買わなきゃ、こっちも買わなきゃという(笑)。そういうのは狙っていますね。
──そう言えば、桜庭さんが音楽を担当されることになったのはどのような経緯から?
北尾氏:
実は最初に大前さんとお話をした時は別の有名な作曲家の方が候補にあったんです。ですが、スケジュールが合わなかったんですね。あと、最初は複数の方々に曲を書いてもらうのもいいんじゃないのかなと思い、その方以外にも桜庭さんといった方々に参加してもらおうと考えていたんです。けど、ntnyさんから「ブレるから止めた方がいい」と。
 |
大前氏:
そう。作品全体として世界観を音楽に背負ってもらうなら、ひとりのコンポーザーにした方がいいよという話をしていましたね。それはまあ、その通りだなと。
北尾氏:
それで、僕が桜庭さんとも連絡が取れますので、どうですかねと打診させていただきました。あと、桜庭さんは古くはPCゲームの時代からさまざまな楽曲を書かれていますが、ここ20年はRPGが大半を占めていたんですよね。
だから、これはそろそろアクションゲームの曲を書いてもらわなきゃと(笑)、僕のチョイスで決めさせていただきましたね。
大前氏:
チョイスの話で言うとエグゼブレイカーの声優さん、坂泰斗さんもこちらで選ばせていただいたんですが、今思うとけっこう当たりを引いたなと思いますね(笑)。収録当時はほぼ無名だったのですけど、今ではいろんなゲームやアニメの主人公をやられたりしていますから。
北尾氏:
『鬼滅の刃』の“サイコロステーキ先輩”【※】も坂さんですからね(笑)。
※サイコロステーキ先輩
『鬼滅の刃』に登場する鬼殺隊隊士の俗称。大口を叩きながら登場して間もなく、敵の鬼にサイコロステーキのごとく斬り刻まれ、退場するインパクトの強さからファンに呼ばれるようになった。漫画版は36話(那田蜘蛛山編、単行本5巻掲載)、アニメ版は18話に登場。
大前氏:
そうだった(笑)。演技も上手ですし、イケメンで背も高いという2.5次元俳優を地で行く方で、これは当たるでしょうという感じで選ばせていただきましたが、本当にそうなって良かったと思いますね。ユニティちゃんの角元明日香さんも同じ感じで選んだのですが、今ではアイドルマスターとかで活躍されていますし。
 |