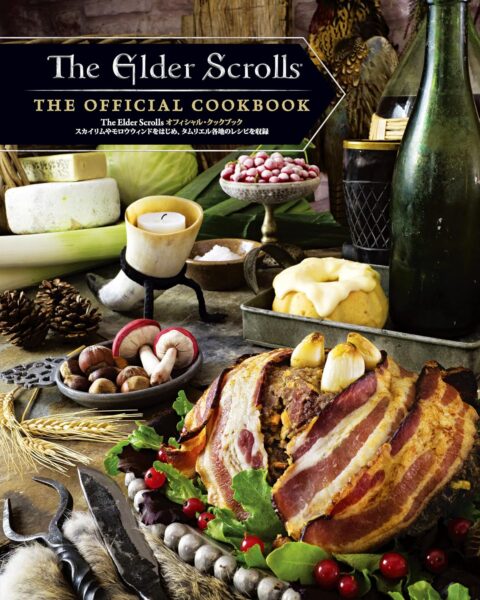4月28日より全国で公開されている映画、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』。すごく、すごく面白い映画だった。
気が付けば任天堂に「マリオの映画が超面白かったので、宮本さんにインタビューさせてくれませんか?」という旨の企画書を送っていたほどにすごかった。
その打診は有難いことに受け入れられ、「宮本茂さんへのインタビュー」が実現してしまった。
 |
ここで読者のみなさまにご理解いただきたいのは、「なんかぬるっと宮本さんにインタビューできました」みたいなノリで書いているけれど、そもそも「宮本さんがガッツリ登場する」こと自体がとんでもなく貴重な機会なのだ。だから、もうこの時点で最後まで読む覚悟を決めてほしい。
「この作品について、この作者に聞いてみた」というインタビューは数あれど、「マリオの映画について、宮本茂に直接聞いた」というインタビューは……もうレアとか貴重とか奇跡とかミラクルとかそういうレベルではないのだ。
宮本さん自身の口から、「この映画はどう作られ、何を目指し、結果的にどう完成したのか」という始まりから終わりまでが語られる機会は、もうこれっきりかもしれない。
「任天堂とイルミネーションの共同制作」という独自の制作スタイルは、どのように構築されていったのか? 具体的に、今作に宮本さんと任天堂はどう関わっていたのか? 宮本さんが「任天堂の新人研修で必ず言うこと」とは? そして、映画の制作中に宮本さんがふと思い出した、「横井軍平さんのある言葉」とは……?
今作の企画の立ち上がりから、物語、設定、キャラ、映像制作……。ありとあらゆる切り口から『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に迫った今回のインタビュー。まだ今作を見に行ってない方は、きっとこの映画を見に行きたくなる。そして、この映画を既に見た方は、きっと理解が深まる。そして任天堂ファンから、宮本さんのファンまで……間違いなく大満足のインタビューだ。
読者のみなさまには、ぜひ最後の「ゴールポール」までお楽しみいただきたい。
 |
聞き手・文/ジスマロック
編集/クリモトコウダイ
カメラ/佐々木秀二
※今回のインタビューには、一部『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のネタバレが含まれています。
※インタビューは他メディアとの合同で行われました。
「マリオがやっと人間になった」宮本さんが語る、今作の立ち上がり
──今回の『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は、初代『スーパーマリオブラザーズ』の発売から約40年近く経っての公開となりました。この長い年月があった中で、なぜこのタイミングでの映画化となったのか……ということを最初にお聞かせください。
宮本氏:
昔アメリカで「ミッキーマウスとマリオの人気調査」というアンケートがあったんです。その時のアンケートでは、マリオの人気がミッキーマウスを上回りました。でも、その当時は「何十年も先に生まれているミッキーマウスと、新参者のマリオを比べるのはおかしい」と考えていたんです。
ただ、その機会に、「ミッキーマウスはアニメーションの進歩と一緒に育ってきたし、マリオもデジタル技術の進歩と一緒に育ててみようかな」と、ふと思ったんです。そのアンケートが良いきっかけになり、「新しいハードがひとつ出たら、新しいマリオをひとつ作ろう」という方針が決まりました。
ハードのメモリーが4倍になったらひとつ作り、CPUが速くなったらまたひとつ作り……これまでの歴史を見てもらえばわかると思うんですが、同じハードではそこまでマリオをたくさん作っているわけではないんです。
それくらいのスパンで作っていると、自分たちにも「次はどんなマリオを作るのか」はわからないんです。どんなゲームを作るかもわからないのに、映画や小説を作ってしまうと、「マリオの好きな食べ物」「マリオの家族」といったゲームに関係のない設定が生まれてしまいます。
要は、ゲーム以外で生まれた設定やルールに、ゲーム側が制限を受けたら嫌やと思って……(笑)。
だから、「マリオはデジタル技術のゲームでしかやらない」と、ずっと言っていました。たまにライセンスは出してもいいけど、僕たちはそこには一切関わらないスタイルでした。ただ、「ゲーム機を持っていない人にも任天堂のコンテンツを届ける方法を考えた方がいい」とも考えていました。
そこから、「任天堂のキャラクターIPを育てる」、「モバイルコンテンツを作る」、「映画を作る」などのさまざまな企画が動き始めました。そこから数年が経ち、「映画を作るにしても、僕らが作りたい方向で自由に作りたい」と考えました。
つまり、他社などにお金を出してもらうと、任天堂が自由に映画を作れないんですよね。そして「任天堂が制作に加わる」という結論に至り、イルミネーションのクリスさん【※1】に出会った……という経緯ですね。
※1「クリス・メレダンドリ氏」
イルミネーションの創業者であり、最高経営責任者でもあるクリス・メレダンドリ氏。
 |
──「任天堂側で自由に作りたい」という方針があったとのことですが……具体的に宮本さんと任天堂はどのくらい今作の制作に携わられていたのでしょう?
宮本氏:
基本的には、スタートの時点で「任天堂とイルミネーションで、一緒に作りましょう」ということは決まっていました。ユニバーサル側も、イルミネーションとクリスさんに制作を委ねている形でしたね。なので、最初から僕とクリスさんの2人で相談しながら作り上げていきました。
そこから任天堂とイルミネーションの両社から制作チームが出たんですが、最終的な全体メンバーの圧倒的多数はイルミネーションチームでした。アニメーションを作るわけだから、当然のことですね。
少数派の任天堂チームには、「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターを作ってきたチームの人たちや、「ゼルダの伝説」シリーズのデモシーンなどを専門に作っているチームの中の、映画好きな人たちを集めてきました(笑)。
その任天堂の映画プロジェクトチームとイルミネーションチームで毎週会議をしながら今作を作り上げていきました。ただ……ちょっと映画を知っている人って……妙に舞い上がって映画のことをいろいろと語るじゃないですか?
一同:
(笑)。
宮本氏:
任天堂チームには、「それは禁止!」と伝えました。映画を作るのはイルミネーションが本業なので、あくまで僕らは「ゲームのことをよく知っている観客として、意見を言う」「ゲーム制作側の知っている情報を、できるだけイルミネーションに提供する」ということを心がけていました。
たとえば、任天堂チームからは「ここはヒップドロップをしてほしい」「クッパは振り回して投げてほしい」という、あくまで「ゲームを知っている側」からの提案をいくつか出しました。その提案をキャッチボールしながら、毎週できあがった絵をチェックする感じです。
そのやり取りに関して、ちょっとラッキーだったことがあって……元々、イルミネーション自体がフランスとロサンゼルスのリモートワーク形式になっていたんです。
なので、そこに日本の任天堂が入っていくこと自体には、あまり抵抗がありませんでした。最初は打ち合わせのためにロサンゼルスにも行っていたんですが、結局はもうほとんどオンライン会議でした。
頻繁にオンライン会議をしながら、データを送ってもらって、できあがった絵をチェックして……。脚本作りの段階から数えると、6年間の制作でしたね。とても新鮮で、楽しい思いをしました(笑)。

──以前のジャパンプレミアでも宮本さんは「8bitだったマリオが、40年越しに“人間”になった」とおっしゃられていましたが、今作で改めてブルックリンに暮らしている配管工としてのマリオの姿が描かれているところを見た感想などはいかがでしょう?
宮本氏:
やはり、「マリオがやっと人間になった」ということに尽きます。
僕は最初、漫画家になろうと思っていました。でも、任天堂での最初の仕事は漫画とはあまり関係ありませんでした。ゲーム機の本体を作ったり、コインの投入口やコントロールパネルを作ったり、ゲームのカタログを作ったり……そういう仕事をこなしていく中で、徐々にゲームの中の絵を描くようになりました。
そして『ドンキーコング』を作る中で、「これはひょっとして、アニメーションを作れるんじゃないか?」と思いました。ただのドットを描くのではなく、そこにアニメーションを作ろうとしたんですね。それでドンキーコングやマリオを漫画の要領で2コマや3コマで描いてたら、結構「動いてる」感じがしたんです。
当時はまだ「ゲームデザイン」という仕事自体が存在していませんでしたし、「デザイナーがゲームを作る」という発想すらありませんでした。そこで「漫画がアニメーションになるような感覚で、ゲームをデザインする」こと自体が仕事になると思ったんですよね。

宮本氏:
さらに遡ると、子供の頃『チロリン村とくるみの木』『ひょっこりひょうたん島』【※2】を見た時に、「人形劇の作家になりたい」という夢を抱いていました。「漫画家になりたい」と思う前は、「パペットショーをやりたい」と思っていたんですよ(笑)。
そして『スーパーマリオ64』でマリオを3Dモデルにしたら、今度はもっとディティールを決めていけるようになった……つまり、『スーパーマリオ64』の3D化によって「ゲームでパペットショーをできるところまで来た」と思いました。個人的に「この先のゲームは、そのパペットショーをどう進化させるかやな」とも考えていました。
ところが、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の制作では、そのディティールのすごさにちょっとビビってきてね……(笑)。正直「あの巨大なスクリーンで、今作ってるマリオが動いたらお客さんはどう思うんだろう?」ということがちょっと心配になりつつも、クリスさんやアニメーターさんといろいろお話しながら今作を作り上げていき、いざ完成したら、「マリオが人間になっていた」んです。
本当に「大丈夫だ。マリオが人間になっている」と自分で感じました。それ以外にも、大きいスクリーンでお話を描くにあたって、それぞれの登場人物の動機をしっかり作り込むことも意識しました。
たとえば、ピーチ姫も「キノピオを守るために戦っているお姫様」というキャラクター像と動機をしっかりと決めていきました。そして、結果的に出てきたものが「だいぶ人間になった」と思えるようになったのだと思います。しっかり作っただけに、喜びもひとしおです。
※2「チロリン村とクルミの木」「ひょっこりひょうたん島」
どちらも、NHKにて放送されていた人形劇。前者は1956年から1964年まで放送。後者は1964年から1969年まで放送。
マリオのキャラを、映画でどう描いた?なぜ「配管工から物語が始まる」のか?
──マリオに家族がいたり、ピーチ姫の出自が語られていたり……『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』には今作独自の設定もいくつか登場しています。こちらのオリジナル設定は、どのように決まって行ったのでしょう?
宮本氏:
最初に「面白い脚本を作ろう」という考えから始めると、不用意に新しいものを作ったり、無駄な設定が増えますよね。だから、「できるだけシンプルな脚本から作ろう」 ということを最初に決めていました。
そして、任天堂の作品に登場するキャラクターたちを、僕は「任天堂タレント事務所」って呼んでるんですけど……今作の登場キャラクターにおいても、その「任天堂タレント事務所のメンバーで固める」ことを決めていました。まぁ、他の事務所から人引っ張って来ないように……(笑)。
どうしてもお話を作るために新しいキャラクターは必要になってくるんですけど、その新キャラをできるだけ抑えた上で、「みんなが知っている任天堂のキャラクターたちでお話を作り上げていく」という方針でした。任天堂タレント事務所のメンバーで作れるお話にしたかったんですよね。
ただ、「マリオに家族は欲しいよな」とも思ったんですね。これは僕の考えがステレオタイプかもしれないんですけど……まずマリオがイタリア系の移民で、そこからブルックリンに住んでいるわけです。
そして僕は、マリオをブルーカラー【※3】のキャラにしたい。そうすると、やっぱりファミリーがいて、みんなでご飯を食べている家庭があってほしいんです。整合性から考えても、マリオとルイージが2人でニューヨークに住んでいるのはどうしても成り立ちません。
そういう意味で、「マリオの家族を作る」ということは昔からの課題でした。ただ、「マリオにはすごく可愛くて、背の小さい妹がいる」という設定を作ってしまうと……背の高い妹が必要なゲームを作る時に、縛りになるじゃないですか(笑)。
※3「ブルーカラー」
賃金労働者のうち、主に製造業・建設業・工業・農業などの生産現場で、生産工程や現場作業に直接従事する労働者を指す概念。肉体労働に従事する労働者の制服や作業着が青系であったことが、その語源。
一同:
(笑)。
宮本氏:
とにかく、必要のないものは作らない(笑)。
だから、「お父さんとお母さんとおじいちゃんと、あと親戚何人か……」といったように、マリオの家族を描くにしても、割と絞り込みました。
実は、今作に登場するマリオのお父さんとお母さんは、20年ほど前に小田部さん【※4】と一緒に描いたスケッチを元に作ったんです。
※4「小田部羊一氏」
アニメーター・キャラクターデザイナー。「スーパーマリオ」シリーズや「ゼルダの伝説」シリーズのキャラ監修やイラスト監修を行った。
 |
──月並みな質問なのですが、今作の中で宮本さんが気に入っているキャラクターや、シーンなどがあれば教えていただきたいです。
宮本氏:
ありきたりですけど……全部です(笑)。
この前も「この映画の見どころを教えてください」と聞かれたんですけど……やっぱり全部です。ただ、それだと答えにならないので、強いて挙げるとすれば「エンディング」です。
こんなに最後のスタッフロールが楽しいのは、やっぱり音楽が素晴らしいからなんですよ。マリオのゲームを遊んだことがある人は、エンディングであの音楽が流れるだけで嬉しいのに、そこにアニメーションまでついているんです。エンディングまで退屈しません。

宮本氏:
キャラクターは、さっきも言ったように任天堂のタレント事務所で固めた上で……それぞれのキャラが1レベル上がったような感覚があるんですよね。「マリオが人間になった」と言いましたけども、多分ノコノコやキノピオ、カメックも全員レベルがひとつ上がったと思うんです。
特にノコノコは「ヘルメット」だけでもスケッチを何十回もやり直しているんです。「ノコノコはどういうヘルメットが似合うのか」というやり取りを何度もしながら作りましたし、それぞれのキャラクターがイキイキと仕上がっていると思います。
その中でも大きくレベルが上がったのが、やはり「ピーチ」と「クッパ」ですね。
『スーパーマリオUSA』ではプレイ可能なキャラクターだったり、『スマブラ』でパラソルを持って戦ったりしてるピーチですけども、やっぱりどちらかと言うと「助けてもらうシンボル」「守られるお姫様」のイメージが強いですよね。でも、今回は「キノピオのために戦うピーチ」にしようと決めていました。エレガントなお姫様でありながら、凛々しい。
マリオとの関係も、「恋愛感情があるのかないのか、微妙なところで収める」ということができたので、ピーチもすごく生き生きしたキャラクターになりました。
──ピーチ姫がファイアフラワーを取るシーンが、私はすごく好きです!
宮本氏:
あぁ、ありがとうございます。
あそこは、お客さんにピーチの姿が変わったことがわかってもらえるかどうかが不安だったんです。詳しくない人は「ファイアフラワーを取ったから、ピーチの服が白くなっている」ということはわからないと思うんで、そこが不安でした。
この映画の中でもいろいろな発明があって、その中でも特に印象的なのが「キノコ王国の王様」についてです。やっぱりキノコ王国がキングダムである以上、普通は「ピーチ姫がいるってことは、王様もいるのか?」と思うじゃないですか。ゲームの「スーパーマリオ」シリーズではあちこちの国に王様がいたりするので、僕はキノコ王国の王様をどう描けばいいかを悩んでいたんです。
でも、そこは脚本家のマシューさんが、一言で説明できるあらすじを作ってくれたおかげで、僕らも腑に落ちました。「王国(キングダム)って言ってるけど、王様もいなかったんや」と。
『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で、キノコ王国の設定はすごくハッキリしたと思います。
 |
宮本氏:
それで、「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターたちを、僕は「マリオ劇団」と呼んでるんです。任天堂企画の中の、「マリオ劇団」です。だから、クッパに関しても次回では悪役ではなくて、どっかのエエとこの旦那役をやるかもしれないわけですよ。
要は、「クッパも完全な悪役ではなく、どこかに愛せる部分があって、別の作品ではまた違う役で出てくるかもしれない」ということをやりたかったんです。ただ、ここは結構イルミネーションさんと議論を重ねた部分ですね。初めて見たお客さんが満足するような1時間半の映画を作るには、やっぱりヴィランはとことん極悪なヴィランじゃないと、主人公や物語に思い入れが生まれません。
……という話を最初はしていたんですが、いろいろ試しながら作っていく内に、作ってる側も段々調子に乗ってきて、クッパにピアノを弾かせたり歌を作ってみたり……(笑)。
一同:
(笑)。
宮本氏:
ハの字眉毛で目が点になったクッパのシーンがどんどん増えてきて、「いや、ちょっと表情緩めすぎと違うか?」と思うくらい、現場もどんどんノリ出して(笑)。最終的には可愛いところのあるクッパになりました。
最後らへんは、逆に任天堂チームから「もうちょっとクッパの愛嬌を抑えよう」と演出し直したくらいです。ピーチとクッパのふたりは、本当にキャラクターとして成長したと思いますね。
──ちょうど触れられていた「クッパの歌唱シーン」ですが、すごくクッパが可愛らしいと思いました。あのシーンはイルミネーション側からの提案だったのでしょうか?
宮本氏:
これはね、イルミネーションからです。
僕らは、まずクッパがエルトン・ジョンやビリー・ジョエルのように歌っているのを「面白い!」と感じました。面白いし、意外性もある。ただ同時に、「クッパの指で弾ける鍵盤はどんな大きさやろ?」「クッパ城に置かれていても違和感がないように、骨のついた鍵盤になるんだろうか?」といったように、周りのいろんなディティールがどうなるのかが心配でした。
……けど、実際は普通のピアノで、なんかサイズのこととかあんまり気にせずに弾いてますよね(笑)。あまりディティールを気にしすぎずに作り上げていたので、良かったと思います。
クッパの声優を担当した俳優のジャック・ブラックさんも、あのシーンはすごくノリノリで、一緒に歌まで作ってしまったんです。とてもライブ感があって良かったですね。
そしてアメリカのプレミアでは、ジャック・ブラックさんは自前でクッパのコスプレを作ってきたんです(笑)。ジャケットの背中にトゲをつけて、鱗のシャツを着て……本当に全部自前のコスプレだったので、ビックリしました。
 |
──特に驚いたのが、今作では「マリオとルイージが配管工から、世界を救うスーパーマリオブラザーズになっていく」というストーリーが描かれていることでした。個人的な話になってしまうんですが……私が初めて遊んだマリオはDSの『New スーパーマリオブラザーズ』なんです。
だからこそ、「スーパーマリオブラザーズではないマリオとルイージが描かれている」ことがすごく新鮮だったのですが……なぜ今作はこういったストーリーを描こうと思ったのでしょう?
宮本氏:
これは映画化とかは一旦別にして、影の設定として決めていたんですよ。実は大昔にライセンスで作られたマリオの映画も、そういうストーリーになってるんです。
元々ゲームのストーリーでも「土管がいっぱいある、ニューヨークの地下で活躍する1作目マリオブラザーズ」から、「その土管が不思議な世界に繋がっていく2作目スーパーマリオブラザーズ」に繋いでいました。
『ドンキーコング』も舞台はニューヨークですし、そこから「舞台は、ニューヨークの中でもブルックリンやろうな」と決めて行ったり……その辺りの舞台設定やストーリーはすんなり決まっていましたね。

宮本氏:
だから、そこは結構「自分の作ってきたマリオの歴史をストーリーに組み込みたい」と思っていたところなんです。
ただね、クリスさんと最初の頃に話したのが、「ゲームの映画化って面白くないんですよね」ということで(笑)。
一同:
(笑)。
宮本氏:
だって、ゲームはインタラクティブで、自分からどんどん積極的に考えて入っていって、自分が遊ぶから面白いわけじゃないですか。
僕らはゲームを通して、遊ぶ人が「次はあれをしたい、これをしたい」と思えるようなネタを仕込んでいく作り方はよくわかります。たまに「お姫様はただ助けてもらう女性でいいのか」とか言われるけど、お姫様が勝手に活躍して抜け出したりしたら、クリアするためのゴールがなくなってしまうんで、僕らとしては困るわけですよ(笑)。
そういったところも含めて、ゲームはプレイヤーの中にお話ができあがっていくもんですよね。
でも、映画ってゲームの全く逆で、基本的には受動的に見るものです。そして作品の方からお客さんに働きかけるために、意外な展開や、観客がついていけないような話をバンバン振って、最後に「あー面白かった!」と思うのが映画じゃないですか。
だから、クリスさんには「ゲームのあらすじをただ追ったら、大して面白くないですよ」と最初に伝えていました。そこから映画として面白くするためにああしてこうして色々やって、いざできあがってみたら……「これ、ゲームの流れを追いかけてるじゃないか」って(笑)。
これってわからないもんで……「ゲームのあらすじを追うのは避けよう」と思って作っていたら、結果的には最初に自分が考えていた「マリオの歴史をストーリーに組み込みたい」も含めたゲームの流れを追うようなストーリーになっていて、両方が上手くいきました。
正直、ここのストーリー周りに関しては「こんな幸運なことはないんと違うか」と、自分でビックリしています(笑)。
 |
映画の模索中、宮本さんがふと思い出した「横井軍平さんのある言葉」とは?
──「宮本さんの映像作品のお仕事」としては、2014年に公開された「ピクミン ショートムービー」がありますが、この作品から今回の『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の制作で活かされたところなどはありますでしょうか?
宮本氏:
いや、そこは特にないですね。
「ピクミン ショートムービー」は4コマ漫画の延長なんですよね。「4コマの起承転結を使った上で、ピクミンらしい不思議なものを作りたい」という考えから作り始めています。そもそもの「生きる、死ぬ」ということに対して特に興味を示していないピクミンたちを見て、人が何を感じるのかなっていう……そういう哲学的な要素を含んだ不思議な4コマ漫画を作れへんかな、と考えていたのがあの作品です。
ちょうどあの頃、さっきも話した「任天堂のIPを映像化する」という企画が立ち上がり始めていたので、まず最初に「商品としての目的はないけど、とりあえずピクミンでショートムービーを作ってみたい」と当時社長だった岩田さんに話したのが「ピクミン ショートムービー」の始まりです。
だから、あの作品は「映像を作って全部を見るということは、難しい」という経験をしたこと以外は、今回の映画とはあまり関係ないです。短編の制作と、長編の制作は全然違う仕事ですよね。

宮本氏:
ただ、僕はここ10年以上、社内で「NHK朝ドラ評論家」という肩書を持っているんです。
毎日NHKの朝ドラをチェックして、いろいろと批評するわけですよね。「素晴らしい!」ってべた褒めする時と、「なってない!」って文句を言う時と……(笑)。
それを繰り返していく内に、「ドラマを作る」ということに興味を持ちました。
自分がすごく面白いと思う朝ドラは、やっぱりセリフ回しがイキイキしているんですよ。アドリブを重視している監督の方が面白いんです。でも逆に、「監督が現場にいて、よくこのセリフでOKを出したな」と思うようなシーンもあるわけです。ドラマを作る上では、そういうイキイキした会話が大事です。
ただ、僕のその評論がだんだんうるさくなってしまって、嫁さんには「もうどっかでひとりでしゃべって!私に言わんといて!」って言われたんですけど……(笑)。
一同:
(笑)。
宮本氏:
「嘘のような本当の話」という言葉がありますけど、逆に僕はゲーム作りで「本当のような嘘の話」を大事にしようと思っています。完璧に嘘の話なんですけど、どこかにリアルがあることで、本当の話だったように見える。それがドラマでも大事です。
だから、嘘の中で一番大事な「本当(リアル)に見える部分」をいい加減にしているのを見ると、ガッカリするんですね。そういう意味で、今回の映画の制作では「日本語版も最初から一緒に作りたい」とクリスさんに話していました。あと「単純に僕が英語の脚本を見せられてもニュアンスがよくわからない」という理由も含めて、日本語版も一緒に作り上げていきました。
日本語版は吹き替えの収録や編集にも一緒に立ち会ったくらい、「クリスさんに恥ずかしくない日本語版を作ろう」と決めていました。なので、ここ数年の映画製作の中では、結構ドラマを意識した日々を送ってきました……(笑)。
 |
──今作で特に驚いたことが、「ゲームの映画」として映像面が徹底されていることでした。「2Dマリオ」の画面を映像表現として盛り込んでいたり、一方で「3Dマリオ」を彷彿とさせる際立ったアクション映像など、とにかく「スーパーマリオというゲームを映画化する意味」を考えた上で作り込まれた映画だと感じました。
この「ゲームの映像の気持ち良さ」を表現するために、宮本さんや任天堂から何かアドバイスなどはあったのでしょうか?
宮本氏:
これもイルミネーションさんと一緒に作り上げたところです。特に監督と音楽監督のセンスが素晴らしくて、あのふたりの力でドライブ感のある映像を作れたと思います。
クリスさんに最初に相談したのは、「マリオの映画で、お客さんは何を見に来る?」ということでした。そしてお客さんは、アクションシーンが見たいはずです。特に「自分が経験したあのゲームのアクションを、本当のように見せてくれるシーン」が欲しいはずですし、そこはすごく大事にしました。
香港のアクション映画のように、「見てて爽快で、嘘のような動きを本当のようにする」ことを意識しました。ただ、そのアクションシーンは脚本では全部書けないんですね。脚本にはあらすじしかないけど、そのあらすじの間に入ってくるアクションシーンがこの映画では一番大事で……。
制作中、そのアクションシーンをどうやって作るかをいろいろ模索しました。最初は制作チームもみんな肩に力が入ってて、「すごくリアルなセットを用意して、その中でゲームのようなアクションをどんどん積み上げていく」とか言うんですけど、どうも実際に完成した絵が見えないんですよ。

宮本氏:
冒頭のブルックリンで、工事現場にマリオが乱入してきて、横スクロールのようにアクションをするシーンがありますよね。その模索中にあのシーンを作ってみて、大昔に横井さん【※5】が言っていた「任天堂のゲームの大事なところは、横で見ている人が『俺に代われ!』って言うところ」ということを思い出したんです。遊んでいる人だけじゃなくて、横で見ている人もよくわかる。
だから、僕らも「見ててわかるようなゲーム」を作ってきたんですね。
それはゲームが3Dになっても努めてきたことなんですけども、今回の制作でそれはやっぱり映画も一緒だと思いました。映画でも、あんまり景色をリアルに作り込んで複雑なカメラワークにすると、見てる方がどんな状況なのかよくわからなくなるじゃないですか。そこで冒頭の横スクロールのシーンを見て、みんなが「あぁ、ゲームに近くてもいいんだ」と、良い意味で割り切ったんですね。
たとえば、湖の上に浮かんでいる『スーパーマリオメーカー』のコースも、実際にゲームを遊んだ人が見ると状況がわかりやすくなっているんですよね。最後の方のアクションシーンとかも、「なぜあんなコースがあんなところにあるのか」ということを結構考えた上で作っています。だから、映画も割とゲームのシーンに近い仕上げ方で作っていきました。
意外と、映画になってもゲームのように「本当にその世界があるように見える」ということが段々とわかってきて、楽しく作れました(笑)。
※5「横井軍平氏」
任天堂元開発第一部部長の故・横井軍平氏。宮本氏と並び、任天堂を世界的大企業へと押し上げたゲームクリエイターと言われている。『ゲーム&ウォッチ』『ゲームボーイ』『バーチャルボーイ』など、数多くの任天堂製品の開発に携わった。
 |
宮本氏:
キノコ王国やピーチ城の周辺も、「どんな街並みになっていたらいいのか」「階段はいくつぐらいあるのか」とかをいろいろ議論しました。
最初は王国の中をバスが走ってたりしたんですけど、「いや、キノピオは車には乗らへんよな」と思ったり、じゃあ代わりに牛が車を引っ張るのかと考えたけど「いや、牛がキノコ王国にいたら困るよな」と思ったり……(笑)。
とにかく、いろいろ作ってきた結果として「結構本当にありそうなキノコ王国」のイメージを生み出せました。
──今作を見てて特に思ったのは、「1時間半ずっと楽しい」ということでした。とにかく、強烈に楽しい映画だと感じました。もちろん映画ではあるんですが、アトラクションやテーマパークのような楽しさがある作品だと思います。まさに映画を見た帰り道も、「1日中遊園地で遊んだあと」のような浮足立つ感じがあって……。
あの「とにかく楽しさを詰め込んだような空気感」はどのように作られたのでしょう?
宮本氏:
どうでしょうね……作るのに時間がかかったから詰め込めたんですかね(笑)。
一同:
(笑)。
宮本氏:
製作チームの中には、マリオのことをよく知っている人がいっぱいいます。だから、とにかくあちこちに余計な小ネタを詰め込んでくるんです。今日も監督としゃべっていたら、僕の知らない小ネタをひとつ明かされたぐらいで……(笑)。そのくらいの密度で映像を作れたのは、すごくありがたいですね。
もうひとつあるとしたら……やっぱり大人と子供がね、一緒に映画館に行くじゃないですか。なんとなく僕のイメージでは、大人が子供に「このアニメを見せたい」と思って映画館に連れていくと、子供がちょっとしんどくて映画館で飽きちゃったりもしますよね。
だから、家族で映画館に行った時に「子供が連れてくれって言っても、大人が連れていこうとしても、両方とも見たら楽しかったと思えるような映画」を作りたかったんです。映画館で1時間半を気持ちよく過ごして、大人も子供も「わあっ!」って明るくなるような映画です。
そして、「マリオってどんなキャラクター?」といろいろ考えた時に、やっぱり「根っから明るい」というのが大事だと思うんです。根っから明るいのが、マリオの大事なところです。
今はキャラクターにも「影の部分」が求められるじゃないですか。でも、「キャラクターの影の部分」って別に言わなくても元からあるもんなんです。だからこっちが影の部分を特に書かなくても、根っから明るいようにマリオを作れば、お客さんには納得してもらえると思いました。
 |
宮本氏:
USJに「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を作る時、実際の僕の仕事は「ARを使って、こういう技術で、こういうことをインタラクティブに……」といったような企画を作る仕事でした。ただ、それより前に、「スーパー・ニンテンドー・ワールドに行ったら、子供が床をゴロゴロ転がった。しょうがないので大人も付き合ってゴロゴロ転がったら……なんか楽しかった!」みたいな場所にしたいと思っていたんです(笑)。
今回の映画もそれと同じで、そういう「大人と子供が一緒に楽しめる」ような作品をみんなが作ってくれましたし、結果的にできあがった1時間半の映画が、僕ですら退屈じゃなかったんです。僕はもう制作中の段階も合わせると100回ぐらい『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を見てるんですけど、それでも楽しかったです。