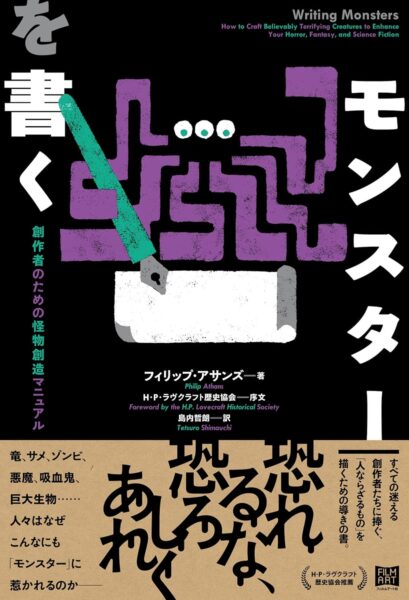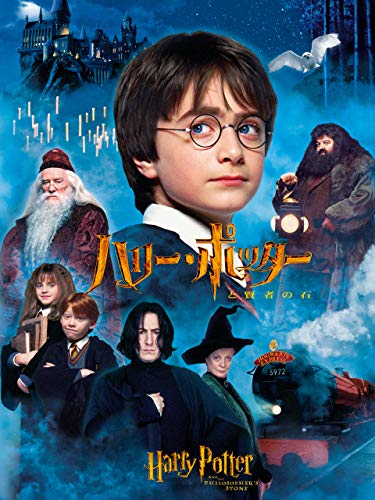「魔法律」という世界観は、元弁護士かつめんどくさいファンタジーオタクだからこそ生まれた
──本作の舞台は、魔法が技術として体系化され、契約によって運用される世界です。この「魔法律(まほうりつ)」という設定、すごく重厚ですよね。
新川氏:
自分は「めんどくさいファンタジーオタク」なところがあるんです。日本のライトノベルやファンタジーって、魔法の定義はけっこう曖昧なことが多いじゃないですか。もちろん、ロマン先行でそれでもいいのですが、私の作品ではキッチリしたかったんです。
──具体的に、どのように組み上げていったのでしょうか?
新川氏:
西洋のハイファンタジーにおける魔法は、キリスト教以前か以後で大きく考え方が変わります。キリスト教以前であれば、素朴な精霊信仰に近い。
キリスト教以降であれば、科学的に説明がつかない不可思議な現象は、「神による奇跡」によるものか、「悪魔との契約」で授かった邪な力か、のどちらかで理解されることが多いです。特に、「魔女」という概念は、悪魔と契約して邪な力を得た者と整理され、キリスト教の異端尋問としての「魔女裁判」という歴史的な出来事につながるわけです。
ライトノベルの世界で一般的なのは、おそらく中世以降、キリスト教化された西洋社会だろうと思います。さらに、「神による奇跡」をベースにした魔法の世界はかなり書きにくい。となると、「悪魔との契約」ベースで魔法の世界を構築する必要があると思いました。
しかし、日本ではキリスト教的な基盤があまり強くありません。神がいない土地には、反対概念である悪魔もいないはずだし、当然、魔女というものもいないはずです。そんな土壌で、どうやったら「ラノベらしいファンタジー世界」を成立させることができるのか、頭を悩ませました。
「ギリギリこれならありうるかな」と思えたのが、魔法は明治維新の時に「西洋の技術」として輸入されたという解釈です。
──なるほど。魔法をオカルトではなく「明治維新で輸入されたテクノロジー」と定義したわけですね。だから本作に出てくる魔法律学校も「旧制一高」【※】を思わせるものになっていると。
新川氏:
そうです。旧制一高は西洋式のエリート教育を目指していましたし、現代よりもずっとダイレクトに西洋文化を輸入していました。
そのひとつとして、魔法技術が輸入されることはありうる。そう考えると、歴史改変SFとして、自分の保ちたいリアリティラインを満たすことができます。
歴史改変SFを書くとき、私は社会制度や法制度をかなり厳しく検討するようにしています。魔法技術が存在する世の中だとして、そんな便利で強力な技術を野放図に誰でも使えるわけがありません。必ず、規制されるはずです。魔法の使用は免許制になるはずだし、免許を取るためには試験があり、そのための教育機関も存在するはずです。
ですから、魔法を使う免許を得るための学校、魔法律学校が存在するはずだと思いました。そして、魔法律学校のなかで最も名門とされる学校は、西洋教育をいち早く取り入れた「旧制一高」を前身とする学校であるというのが、歴史上必然なのではないかと考えました。
※旧制一高…かつて日本に存在したエリート養成の最高峰とされる高等教育機関。現在の東京大学教養学部の前身にあたる。
──たしかに、強大な力だからこそ、管理されていて然るべきですね。
新川氏:
そもそも、世の中のコンテンツに出てくる「魔法」や「契約」がカジュアルすぎると思います。悪魔との契約で魔法の力が得られるというのは定番の設定ですが、悪魔はどうして人間に魔法の力を授けてくれるのか。何かしら対価を要求するはずだし、狙いがあるはずです。そこには悪魔との駆け引きが必要となり、厳密な契約が必要です。そのあたりは自分が元々弁護士だったために気になるのでしょうけど。
「悪魔との契約っていうけど、みんなちゃんと契約について考えていないんじゃないか?」という疑問がずっとありました。
なので、弁護士としての経験を活かして「ガチの契約書」を作って作中に登場させました。条文の書き方、免責事項、管轄裁判所……法的にちゃんと成立する契約書になっています。
読者からすると、急にガチな契約書が出てくるので、難しく感じるかもしれませんが、ガチなほうが(邪気眼的な)中二病世代の読者としても嬉しいのではないかとも思っています。
──子ども向けだからといって曖昧にせず、作り込まれているんですね。この重厚な設定とライトノベルらしい読みやすさの両立はどのように叶えていますか?
新川氏:
なるべく分かりやすさ重視というか、キャラクターの物語として読めるようにしています。世界よりは、キャラクターを書きたいですし、キャラの話として読んでくれれば共感できて作品に入っていきやすいと思います。
設定の細かいところはほぼ自己満足なので、正直そんなに伝わらなくてもいいんです。読者さんは気にしなくていいと思っています。
──設定を世界の説明ではなく、キャラの肌感覚に翻訳して書くということですね。
新川氏:
本作は、魔法を寡占するエリートと、魔法を使わない一般人という階層に分かれています。つまり背景に格差社会が置かれているんですが、これも“格差社会がある”という設定だけだと入っていきづらいですよね。
でも主人公の椿なら、格差社会のいちばん下なので、不便な生活を強いられている。彼女が仕えるマリスは魔法の才能に恵まれている格差社会のいちばん上で、すごく華やかな生活を送る。そしてその格差に不満を持つ人たちが、格差社会自体を打破しようとしている……といったように、階層やその格差が「各キャラにとってどういう意味を持つか」が書かれてると、話に入っていきやすいと思います。
これは一般文芸の小説を書くときとあまり変わらないというか、お仕事小説とかの書き方と一緒ですね。
テンプレに縛られない、流動的に変わっていくキャラクターたち
──ハーレムを構成する面々、麗矢、伊織(いおり)、左衛門(さえもん)は、どういったバランスで設計されたんでしょうか。「ライバル」「チャラ男」「データキャラ」といったような、いわゆる属性から逆算したのでしょうか。
新川氏:
キャラが被らないようにすることは考えていますが、属性テンプレに従って作ってるわけではありません。基本的には、物語の構造から逆算しています。
本作は「フランス革命」みたいな話で、体制側のマリス、革命軍側の伊織、その間で揺れる椿、という構造なんです。物語的にも、マリスみたいな俺様タイプと対等に渡り合える麗矢のような親友キャラは必要ですし、左衛門のように予想外の方向に引っ掻き回してくれる人も必要です。
──妙なリアリティを感じるときがあるのですが、モデルがいたりするのでしょうか。
新川氏:
私の周りにいるハイスペック男子たちをモデルにしています。だいぶ薄めてはいますが。



──「テンプレ」でいうと、本作の関係性は「テンプレの入口」から入ったのに、途中でテンプレが外れていく感じがします。主人公の椿は、仕えているマリスへの執事としての忠誠心も存在しつつ、かなりしっかり自我がありますよね。
新川氏:
本作は、ガワだけテンプレみたいな感じなんです。入口だけテンプレで、中身でやることは結果的にあまりテンプレに則っていません。
別にテンプレが悪いとは思いませんし、読者が世界に入っていくための補助線としてテンプレ的な属性は大事だと思います。ただ、現実に「100%の〇〇キャラ」みたいな人間はいないので、誠実にキャラクターを書いていけば、必ずテンプレから外れる部分が出てきます。俺様キャラのマリスであっても、ページを重ねるほどに、彼なりの繊細さが滲み出てきます。
マリスに仕える椿についても、「俺様に振り回されるキャラ」として単純に処理すればいいかというと、そうではないと思います。全国模試1位でスポーツテスト1位、家事もできる、格闘技も強い……そんなハイスペな子が、他人に一方的に振り回されるはずがないんです。自分の価値観をしっかり持って動いているはずです。だからこそ、自分の価値観では看過できないことがあれば、相手が誰であろうと異議を唱えます。
あと、ライトノベルとしては遠回りというか、不器用な方針ですが、ふたりを安易に恋愛関係にしないようにも気をつけています。それぞれに他の選択肢はたくさんあるのだから、一緒にいる時間が長いだけでは相手を恋愛対象として好きになることはないだろうと思っています。
──物語が進むにつれて、キャラクターの関係性も変化していますよね。テンプレ的な属性から逆算した展開を予想しているとことごとく外すというか。
新川氏:
テンプレ展開から外そうと思って外しているわけではないです。単純に、人間関係は、時間軸に沿って当然変わるものだと思っています。
キャラクターたちが時間を積み上げてるから、その関わりによって距離感は変わっていくはずです。そのこだわりは、著者の首を絞めるんですけどね……。ホームズとワトソンみたいにずっと変わらないほうが、みんながずっと読める作品になるとは思います。
一応、巻ごとに「このキャラとこのキャラはこうなる」という大きい流れは決めているんですが、すべてのキャラについて決めているわけではないです。自然な流れに任せています。
──恋愛や好意の描き方も、固定されていない印象があります。マリスが「いや、俺レベルになると男も女もいける」と言っていたり、椿がスミレにドキッとしたり。バイセクシャル、あるいはパンセクシャル的な、クィアな要素があるようにも感じました。
新川氏:
自分は、人間とはそういうものではないかと思っているんです。
人間の「好き」って、恋愛感情だけで成り立ってるわけじゃないと思うんです。人の「好き」という感情はもっとグラデーションがあって、恋愛と友愛はそこまでハッキリ分かれるものじゃない。人と人の関係性や好きって気持ちには、もっといろんなバリエーションがあると思っています。
──なるほど。具体的にどのように描いていますか?
新川氏:
本作では、友情と恋愛をハッキリ分けて書いていません。
例えば、異性愛者、男性のことが好きな女性だからといって、その好きが100パーセント恋愛ってこともなくて、友情がけっこう混じってる恋愛だったりとかもします。その逆に、女友達に彼氏ができたときに感じる悲しさみたいなものとかはあるわけで……。女友達に対する気持ちが100パーセント友情かっていうと、それも違いますよね。
なので、キャラクターたちも当然、絆が深まっていくとどちらかに割り切るのは難しい気持ちになっていきます。人と人の関係として捉えているからこそ、あんまり男女を気にして書いてないかもしれません。
──すごく、腑に落ちました。
ちなみに、主人公・椿との関係性においては、いじめっ子だったスミレが一歩リードしている気がするんですが、これはなぜなのでしょうか。個人的に、スミレと椿の関係性がいちばん好きなので気になっていました。
新川氏:
可哀想なことに、椿がスミレのことを全然恋愛対象として見てないがゆえにリードしちゃってるってことだと思うんです。これがちょっとでも脈があれば、椿も照れて回避すると思うんです。でも本当に女友達だと思ってるから、距離が近くてもそんなに照れない。
──なるほど……。

ちゃんと頑張る子が、ちゃんと報われる話にしたい
──主人公が男装をしているのは、どんな理由から採用した設定なのでしょうか?
新川氏:
この作品はいろんな男の子が主人公に興味を持つハーレムタイプの作品です。
このタイプの作品において、男装モノっていうのは結構ド典型ですよね。男装しているから、生活圏に男の子がたくさんいる。わかりやすくそのフォーマットに乗っかる意味でも、男装させています。
──しかも、めちゃくちゃハイスペですよね。主人公は「日本でいちばん優秀な15歳の女の子」でしたよね。
新川氏:
主人公がハイスペなのは、女性向け作品の性質上の意味もあるんです。
本作はハーレムものですから、多数の男の子から関心を寄せられます。だから、関心に見合う魅力が必要となります。ここが欠けていると、「どうしてこの子だけこんなに愛されるの?」と、読者さんからヘイトを買うことになります。
なので、完璧で健気で、好感度が高い主人公にする必要がありました。それでも許せないという読者さんはいると思いますが。とはいえ一般的な感覚として、こんだけ頑張ればモテてもよかろう、というラインがあると思うんです。
──男装しているからこそ、流血を伴うようなガチバトルの描写も存在していますよね。
新川氏:
主人公の椿と彼女が仕えるマリスが喧嘩をするシーンがあるんですが、マリスは椿を殴ったあと、仲直りするときにも、殴ったことを謝らないんです。編集さんには「謝らせなくていいんですか?」って言われましたが、「男同士の喧嘩では謝らないだろう」と思いました。
バトルシーンでも、椿は慮らなければならない、大切にしなければならない「女」ではなく、力をぶつけ合う対戦相手として描いています。「女」だと意識されていないこそ、彼女の格闘技能力が純粋に評価される。
それから、この「ハイスペな男装キャラ」という造形は、自分の実感に基づいた設定でもあります。
──実感、というと何か元ネタになった出来事があったのでしょうか。
新川氏:
『魔法律学校の麗人執事』を書くまでに、ライトノベルを3、4作ぐらい書き直しているんですが、ちょっとずつ作品が変遷していくうちに、最終的には「自分の実感が伴った話じゃないとちゃんと書けないな」と思ったんです。
で、ここからが実体験なんですが……。
弁護士時代に婚活をしていたことがあるんです。で、ハイスペ男性専門の結婚相談所は入会金が20万円とかするので、私は5000円くらいで入れる普通の相談所に入ろうとしたんです。
そしたら、「うちに入っても釣り合う男性とは出会えないから、入らない方がいい」と入会を断られたことがあるんです。
──ええっ!それは、新川さんがハイスペすぎる「女性」だからでしょうか。
新川氏:
はい。すごくジェンダーに根ざした事象ですよね。
私は仕事を頑張りたいタイプなので、相手の年収に興味がないし、専業主夫になってくれる男性のほうが望ましいくらいだったのですけど、意外と成立しない。「私が男だったら婚活市場で無双できたのに」「超優良物件のはずなのに」って思いました。
周りを見てみたら、ハイスペな女友達は割と同じようなことになっていました。仕事もして家のこともして……なのに、恋愛だけはうまくいかないって子が多い。でも、じゃあ女の子として弱いフリをするのがうまくなったらいいのかっていうと、それも違う気がします。
──男性なら武器になるはずのものが、逆に自身を傷つけてしまうと。その経験が、今回の「男装」設定に繋がっているんですね。
新川氏:
これは現実が歪んでるんですけど、「女」って属性だと能力を正当に評価されない、人間扱いしてもらえない社会構造がある。人間の土俵に乗るために男装させざるを得ない、というのもあるかもしれません。
なので、「何でもできる系の女子が男装して、ほんとにモテる」みたいな話にしようと思いました。主人公を男装させることで、本来の能力が、正当に評価されてモテるという状況を作ることにしました。
──では、最後に改めて伺いたいのですが、新川さんは『魔法律学校の麗人執事』をどんな物語にしたいですか?
新川氏:
ちゃんと頑張っている子が、ちゃんと報われる話にしたいです。
かっこいい活躍や、それに見合った評価は、主人公が自分で汗水垂らして獲得してほしい。「最後は王子様に解決してもらう」みたいな話にはしないつもりです。
(了)
今回のインタビューで我々が目撃したのは、東大卒、元弁護士という稀代の知性が、そのリソースを惜しみなく「エンタメの解明」に注ぎ込む姿だった。
「ライトノベルはマンガの濃縮還元である」という鋭い定義から始まり、リアリティラインの制御、さらには「なろう系」のフォーマットに秘められた普遍的な救いまで。彼女が語る言葉のひとつひとつは、単なる創作術を超えて、私たちが日々享受している「物語の快感」の正体を鮮やかに照らし出すものであった。
何より印象的だったのは、あれほどまでに冷静なロジックを積み上げた先にあった、新川氏のあまりに純粋な「祈り」のような結びの言葉だ。
「ちゃんと頑張っている子が、ちゃんと報われる話にしたい」
「ハイスペックゆえに拒絶される」という理不尽な実体験。能力があるのに、属性や性別によって正当に評価されない。そんな現実を、同氏はロジックという武器で解体し、ライトノベルという物語の中で塗り替えようとしている。
王子様に頼るのではなく、主人公が自分の力で掴む。
それは、合理性を突き詰める元弁護士としての顔と、物語の力を信じる作家としての顔、その両方を持つ新川氏だからこそ描ける、新しい時代の「ヒロイン兼ヒーロー像」なのだろう。
最新刊『魔法律学校の麗人執事』第3巻は絶賛発売中。
さらに、公式Xにて本作のPVが公開されているほか、あわせてプレゼントキャンペーンも開催中だ。
PVには野々宮 椿役:上田 瞳さん、条ヶ崎マリス役:阿座上洋平さん、高遠伊織役:田邊幸輔さんが出演。賞品は声優陣と新川帆立氏のサインが入ったサイン色紙となっているほか、応募者全員にスマホ用オリジナル壁紙もプレゼントされるとのこと。フォローとリポストのみで参加可能なので、ぜひチェックしてほしい。
/
— 『魔法律学校の麗人執事』(新川帆立:著)【公式】 (@MagicLawAcademy) December 19, 2025
『#魔法律学校の麗人執事』
PV公開記念🎊
\
フォロー&RPキャンペーン✨
 ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
抽選で3名の方に豪華サイン色紙が当たるチャンス💪
&
応募者全員にスマホ用オリジナル壁紙3種をプレゼント🎁#魔法律 #麗人執事 #新川帆立
応募方法は⬇️をcheck!! https://t.co/2hMJNMUAni pic.twitter.com/8yxRTJP2NF
属性やテンプレにキャラクターを閉じ込めず、変わり続ける人間関係をそのままに描く本作のフラットな在り方は、既存の境界線に息苦しさを感じてきた者へ、たしかな救いを与えてくれる。今回の取材は、その救いの正体をロジックによって解き明かす、答え合わせのような時間であった。
「頑張っている子が報われてほしい」と願う切実な物語は、かつての新川氏がそうであったように、今も現実の理不尽に立ち向かっている誰かにとっての救いとなるだろう。