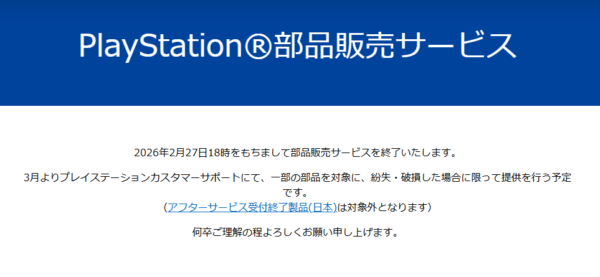「そのマンガ家が持っている良さを、どれだけ早く編集が理解し、マンガ家本人に悟らせるか」
講義後半は、受講者から事前に集めた質問に加え、その場で挙手により、質疑応答が行われた。マンガ制作の細かな現場の話や裏話から、学生ならではの編集職への興味や意欲、そして出版や雑誌、マンガ界の展望まで惑わず回答する鳥嶋氏。
ここでは、おもなものを順不同でお届けしよう。
Q.担当された作家さんで、いちばん苦労したのは誰でしょう?
鳥嶋氏:
いちばん苦労したのは、『ピアノの森』の一色まことさんかな。彼女の最初の連載は『ジャンプ』の『はなったれBoogie』という僕が担当したマンガなんですが、連載を目指して準備してきて、「連載会議を通った」と伝えたときに、「連載を辞めたいんです」と言われたのがいちばんたいへんでしたね。

Q.自分では「売れない」と思ったが、売れたマンガがあれば教えてください。
(原田氏)これ、よく耳にしますが、『ONE PIECE』でいいんですよね?
会場:
(爆笑)。
鳥嶋氏:
はい。『ONE PIECE』でいいです。いまを以て僕は『ONE PIECE』を3巻までしか読めません。あの画面構成はちょっと僕には理解できないものです。
Q.鳥嶋さんが担当されてヒットしたマンガに、共通点ってあると思いますか?
鳥嶋氏:
あります。「子どもに伝わったもの」ということです。子どもに伝わってヒットしたものって、大人にも届くんですよ。でも逆はない。
必ず前向きで明るいものが多いんですよね。子どもに「主人公は自分だ」と思わせるためには、やっぱり明解じゃないといけない。ヘンに陰があったり、くよくよ悩む主人公はダメなんですよね。
考えさせられたのは、僕が現場でマンガを作っていたときに『ガンダム』が当たっていると聞き、劇場に観に行ったときのこと。アムロというグダグダ悩んでいる主人公を観て、「ああ、なんてアニメだ」と思ったんです。
ですが、もうちょっと年齢が上の人にとって、「これはこれはである種の等身大なんだな」とも思ったんですね。
ただ巧いのは、シャアという、ちゃんとしたカッコいいヤツが脇にいるんですよね。グダグダしているヤツだけだったら、ぜんぜんヒットにならないけど、シャアを作っているあたりに、僕はプロとしての腕を感じました。
Q.鳥嶋さん自身がいままで読んだ中で、バイブルとしているマンガはありますか?
鳥嶋氏:
バイブルというか感謝しているのは、ちばてつやさんの『おれは鉄兵』です。

僕は『ジャンプ』のマンガが嫌いだったので、新人時代に資料室でずっと昼寝をしていたんですが、ふと見回したら、『ジャンプ』に限らずいろいろな雑誌があるので、片っ端から読んだんですね。
するとマンガには、読みやすいマンガと読みにくいマンガがあることが解った。そこでトーナメント方式で読みにくいマンガを外し、最後まで残ったのが『おれは鉄兵』だったんです。
その1話19ページを、「なぜこのコマ割りなのか」、「なぜこのアングルなのか」、「このコマとコマの関係はどうなのか」、「見開きの中でどういう風にコマを組んであるのか」と考えながら50回読んだんです。
それでマンガの文法、コマ割りを理解したんですね。新人マンガ家と打ち合わせるときにこの理解が正しいのか確かめながら使ってみたら、打ち合わせたマンガ家がみんなみるみる巧くなっていった。「マンガっぽかったもの」が「マンガ」になってくるんです。それを具体的にやって、いちばん成果が上がったのが鳥山明さんですね。
ですから、ちばてつやさんの『おれは鉄兵』にはとても感謝していて、つい最近も読み直してみましたが、やっぱりちゃんとしているんです。ほかの剣道マンガとどこが違うか読み比べてみてください。
先日『ジャンプ』の編集者にどこが違うかをクイズとして出したところメールが帰ってきました。マンガオタクの編集者でしたので答えは正解でしたが、興味がある方は、ぜひいろいろ読み比べてみてください。面白いと思います。
Q.集英社から白泉社に移られて、「文化が違う」と思ったことがあったら教えてください。
鳥嶋氏:
白泉社には集英社ほどのどうしようもないクズはいませんでしたね。その代わり、ものすごく切れる社員もいませんでした。白泉社の100名ほどの規模というのは、いい意味でも悪い意味でも、みんな知り合いなんです。意思疎通が巧くできる単位で、派閥もない会社。
ですが居心地がよすぎて、やっぱりある種の競争原理が働いていなかったんです。ですから僕はそこをかき混ぜて、外の空気を入れて、会社の外にどれだけ触れてもらうかということを、自分が社長のときの進めました。その結果、かなりの部分で「積極的に何かやろう」という気運になってきました。
それまででいちばんマズかったのは、「お金を使うな」と歴代の経営陣が言っていたことでした。お金を使わないということは、設備や才能に投資をしないということだから、新しいものを作れないんですよ。
正しくは、「お金を使ってもいいけど、無駄金を使うな。使った結果をちゃんと検証しろ」と言わなきゃいけない。
僕が来て3年かけて土壌作りをしたので、白泉社はいま、いい会社です。いま入ってオススメの会社だと思いますよ?
Q.『Dr.スランプ』をアニメ化するときに、集英社から大反対を受けたと聞きましたが、エピソードなどあれば教えてください。
鳥嶋氏:
あれは当時の編集長が、非常にいい人なんですが脇の甘い方で、『Dr.スランプ』がヒットしたとき、担当や作家にも無断でいろいろなところに商品化を許諾していたんですね。そのうちに当時編成局長だったフジテレビの日枝久さん(現・取締役相談役)が「アニメ化をしたい」と話しに来たんですが、すでに許諾がいろいろとなされていた状況が仇になったんですね。アニメ化に際して、本来ならスポンサードしてくれるところに優先的に商品化の許諾をするものですから。
「一度整理しなければアニメ化できない」と集英社が言われたとき、「それはできない」と断ったということがありました。たぶんそれを指しているのだと思います。
そのあとに整理をしたからアニメ化できたんですが、逆に言うと、当時の集英社サイドに、編集長を含めて誰もアニメーションについての知識がなかったということですね。だからゴタゴタしたという話です。
Q.メディアミックスのお話の中で、今日唯一お話が出ていない実写化に関してはどうお考えでしょうか。
鳥嶋氏:
厭なことを聞いてくれるねえ(笑)。僕の映像化に関する最大の失敗は、皆さんご存知のように20世紀フォックスの『ドラゴンボール』の実写(『DRAGON BALL EVOLUTION』・2009年)ですね。

失敗したあとハリウッドに行って、映像に詳しいいろいろな弁護士に話を聞きました。腕利きの弁護士たちの結論はたったひとつ、「カネを出さないヤツに口を出す権利はない」というものでした。
お金を出さない場合は、「これだけはどうしても厭だ」ということを、ずらっと契約書に列挙しておくしかない。するとそれはルールだから、それだけは守られる。とにかくお金を出さなければダメなんです。
件の『ドラゴンボール』において、イエスノーの権利を持つためには、50億の出資をしなければなりませんでした。集英社がそのとき50億を出していれば、シナリオについてイエスノーが言えて、あのシナリオを潰せた。
ですが当時の50億というのは、集英社の年間の営業利益の6~7割くらいかな。ですから、とてもそれを出す覚悟はなかった。いまなら僕はハリウッドの状況を知っていますから、「50億は出す。その代わりアジアの配給権がほしい。ちゃんと君たちにお金で返すから」と言って交渉し、出資してイエスノーの権利を手に入れるようにしますね。
Q.たとえばゲーム産業でも、任天堂などの例外はありますが、新規のユーザーを育ててこなかったがゆえに、いまの翳りが見えている気がします。マンガ雑誌に関してはどのようにお考えでしょうか。
鳥嶋氏:
ゲームでも、子どもを手に入れているものはあるんですよ。『ポケットモンスター』がそうですし、それから一時期の『妖怪ウォッチ』がそう。ちゃんと子どもを向いて狙って作れば、子どもは動くんです。ただ、子ども向けのものは、当たる確率が低いんですね。
それはクリエイターがみんな大人だから、自分たちの感性で「面白い、面白くない」と言って作ると大人向けになってしまうからです。子どものためのものを作るには、「子どもが何をどう感じているか」を、ちゃんとリサーチしながら作っては壊しを繰り返し、その上に築き上げていかなければならない。任天堂はそれを考え続けているからできるんですよ。
いまそれをマンガがちゃんとできていないのは、やっぱり子どもをちゃんと見ていないから。『コロコロコミック』は唯一ちゃんとやっているかな。
「『ジャンプ』がいま頑張っている、部数も下げ止まった」と言うけど、やっぱり小中学生の男の子向けのアクションのマンガを作れていないと僕は思います。これが作れなければ、『少年ジャンプ』の「少年」の意味がないんですね。つまり『少年ジャンプ』は本当の意味で復活していない。
 |
よくアメリカで言うsix-eleven、6歳から11歳向けのボーイズアクションは、いちばんおもちゃが売れる層なんです。さらにこの層は、クレジットカードを持たず、スマホからコンテンツを買えないから、じつはネットの影響を受けないんですね。
依然として子どもをどう狙っていくかが重要になるわけです。
すると「日本は少子化だから」という声が挙がりますが、じゃあ日本の子どもをぜんぶ取ったのかと言うとそうではない。取れればそれなりの数にはなります。
だからそう言いながら物を作っている人間は、やっぱりエクスキューズしているだけ。真剣に向きあって企画を作ればちゃんと取れるものだと思います。
Q.マンガの編集者にはどういった方が多いですか? どんな人がなぜマンガの編集者になろうと思うのでしょう?
鳥嶋氏:
いいマンガ編集者になろうと思ったら、マンガをあまり読まないほうがいいんじゃないですかね。いちばん向いてないのは、マンガが好きすぎて、作家との打ち合わせのときに自分の好みを押しつける編集者。居てほしくないくらい、いちばんジャマになります。
マンガ編集に相応しい人間は、目の前の人間の才能を理解し、「これをなんとか世の中に出したい」と思える人間ですね。要するに自分が強い、自分の手の中に何かギュッと握った人間は、編集に向きません。
Q.編集者になるために必要な勉強やスキルは?
鳥嶋氏:
編集部にやってきた小学生の見学者によく言っていたことですが、3つあります。
まず国語を勉強すること。マンガは絵とセリフでできています。
絵を隠しても誰が喋っているか判る喋り言葉を作れるかどうかは、ひとつのセンスです。じつはヒット作を作ったマンガ家って、みんな文章を書かせるとものすごく巧い。味のある文章を書きます。ところが編集者の文章って、形は整っているけど、ほとんどの人がダメ。ですからまずは国語をちゃんと勉強してください。
つぎに、友だちをたくさん作ってください。これはキャラクターをたくさん知っていないと、キャラクターの書き分けができないし、判断もできない。
「厭なヤツでも、どこが厭か観察してくれ」と言います。そういうことをちゃんと知っておかないと、キャラクターは書けない。
3番目は、カラダを鍛えておくこと。週刊誌連載はものすごくハードです。
鳥山先生がよく週刊連載は「おろしたてのゴワゴワのパンツを穿くよりキツい」って言っていましたからね。体力勝負です。
もうひとつ真面目に付け加えると、好奇心を持ってほしい。人が何かを面白いと言っていたり、何かが流行っていたり、何かに人が並んでいるのを聞いたりしたら、必ず首を突っ込んで見てきてください。
僕もときどき陥りやすいんですが、ありがちなのが、「あー、あれね」とそれらを莫迦にすること。これがいちばんダメなこと。僕らが相手にしているのは基本的に子どもです。子どもの視点になって物を見て、面白いかどうかを自分が整理できないとダメですから。好奇心を持ってください。
Q.たとえば広告系のものを描いたりなど、マンガで食べていく方法がいまは雑誌以外にもいろいろあり、マンガを描きたい人たちのゴールもけっこう多様化していると思います。そういう状況で作家が編集者と組むということのメリットや魅力を、どういう風に伝えていらっしゃるのでしょう?
鳥嶋氏:
ちょっとした儲けでいいなら、いろいろとダメ出しをされて面倒臭いから、編集と付き合わなくていいと思うんですよ。ただ、大儲けだとか、とにかく広く自分の描いているものを伝えようと思うなら、編集者と付き合っていたほうがいいと思います。
なぜなら編集者って、いろいろなチャンネルや、どこにお金があるかなどの情報や知識を持っていて、作家をそこにマッチングできると思うんですね。
 |
ただ気を付けなければいけないのは、やっぱりどの編集を選ぶかということ。病気になったときに、どのお医者さんを選べばいいのか手がかりが少ないのと同様、編集をどう探すかは非常に難しいんじゃないかなあ。
だからそこは残念ながら、口コミなどで辿って探すしかないんじゃないでしょうか。だからできれば、いろいろな編集者が評価され、マッピングされたものが出てくるといいと思うんですけどね。
Q.新人作家を発掘するときに、いちばん気をつけているところはどこでしょう? 「新人のこういうところを見る」などありますか?
鳥嶋氏:
いちばん気をつけているところは、才能の見極めを早くして、ダメな人には早めにダメと知ってもらうこと。そうしないとその人の人生の無駄遣いになります。
逆に「これだ」と思う人には、できるだけ早く、作業の中で自分の良さを知ってもらう。そのふたつですね。
Q.持ち込みを待つよりも、同人誌などを出している人をスカウトするのが新人の発見には手っ取り早いと思いますが、それでも持ち込みから新人を発掘する理由はなんでしょう?
鳥嶋氏:
じつはコミケに興味を持ちまして、堀井雄二さんと取材に行き、記事ページも作ったことがあります。コミケのパンフレットに「ジャンプ」というロゴも載せ、コミケのファンから大ブーイングを買ったんですが、そこで何名かスカウトし、事後に打ち合わせをしました。その結果、コミケにいる人たちはぜんぶダメだと解りました。
なぜかというと、好き勝手に描くことはできるけど、直しができないんですね。ということはプロに向かないんですよ。
直すというのは、一度描いたものを、読者の目線に近づけて繋げるということです。ということは、読者に繋げられない作家であり、それでは原稿料がもらえないということですね。
非常に厳しいことを言うようですが、基本的にコミケのマンガは、人のキャラクターに勝手に乗っかり、ごっこ遊びをしているだけです。
Q.マンガ家と組んでマンガを企画・構成していくうえでいちばん大切なことは何でしょう?
鳥嶋氏:
「そのマンガ家が持っている良さを、どれだけ早く編集が理解し、マンガ家本人に悟らせるか」ですね。
僕はよく言いいますが、マンガ家って「描きたいもの」を描きますよね。それって、じつはそれまで見たいろいろなもののコピーなんですよ。
本人が「描けるもの」とは違うもの。そうしていろいろ読み切りを描いて読者の反応を見ると、たいがい「描きたいもの」はウケないんです。
そこで「描きたいもの」を潰していって、その作家にしか描けないものが作家の中に見つかったとき、ちゃんとそれを読者に提示すると伝わるんですね。それが「描けるもの」。
それはマンガ家の原点であり、僕は「オリジン」と呼んでいます。自分のオリジンを描ける作家がヒット作家になる。そういう意味で、マンガ家は、最後は人間性なんだと思います。
Q.マンガで「キャラを立てる」とはどういうことでしょうか?
鳥嶋氏:
「ものすごく好きな女の子がいて、一所懸命に口説いてやっとデートに漕ぎ着け、デートに向かう。その途中で交通事故があり、目の前に人が倒れている。さあどうする?」というエピソードを新人マンガ家によく言います。普通は、倒れているのが知らない人だからデートに行きますよね。だけどこれが兄弟だったり、友だちだったら、デートを袖にしてでも助けますよね。それは身近な人だからです。
それくらいキャラクターを読者に身近な相手だと感じさせる。「この人は私の知り合いだ」と感じさせる。これがキャラクターを立てるということです。
Q.日本だと、編集者と作家、あるいはそこに原作者もいるチーム制でマンガが作られている感じがしますが、アメリカンコミックには、プロデューサーがいて、シナリオライターがいて、ペンシラーがいて、インカーやカラリストがいるというプロダクション化が進んでいます。これに関してどう思われますか?
鳥嶋氏:
単発などで描くにはそれもいいんでしょうけどね。僕はアメリカンコミック全体にメリット、デメリット双方を感じています。
 |
メリットは、著作権がぜんぶ一元管理されていること。だからコミックを新しいものに何か変換しようとするときに、一気に動くことができる。
たとえば日本もそうですが、作家さんがこのあとだんだん亡くなっていったときに、「著作権管理をどうするか」が大きな問題になっていくと思います。このとき著作権が会社にあれば、会社自体は死にませんから管理はちゃんとできるんです。
一方でデメリットは、個人に著作権がないということですね。僕はゲーム関連の人といろいろと話をしますが、経営者はお金持ちになっても、ヒットゲームを飛ばした人に著作権はない、つまりお金は入らないんですよ。
「ゼロから1にした人がいちばんたいへんなのに、この人が報われない物作りってなんだろう?」と思いますね。
だから産業として考えると、アメリカのやりかたはオーケーだけど、個人クリエイターレベルの視線で言うと、アメリカのやりかたに僕は疑問を持ちます。
Q.無料だったり、個人が描いてアップして終わるくらいの軽いマンガによって、いまマンガ全体の読者層というのは広がっていると思います。反面、「その程度でいいや」という人もけっこうおり、そういう層が増えると、だんだんマンガ全体の質が下がってくるんじゃないかと思います。質のいいものを維持して、質のいいものの読者を拡げていくことに対して、何かお考えはありますか?
鳥嶋氏:
どれを読んでも「いい」となればいいんです。いまタダで読めるものは、提供する側含め、「タダだからこんなもんでいいだろう」となっているから問題なので。
いつもいろいろな疑問が湧いたときに僕は立ち戻るんですが、やっぱり最終的には「面白いものを作る」、これしかないんじゃないですか? すべての解決策はここに戻ります。面白いものを作ってそれで市場を埋める、これしかないと思います。
Q.マンガ家を発見・育成するのは編集者という話ですが、会社が編集者を育成することに何かお考えをお持ちでしょうか。
鳥嶋氏:
それはいま僕が悩んでいるひとつの問題なんです。
よくある話ですが、これまでならマンガ編集は「先輩の背中を見て学べ」とか、「見て盗め」などと言われていました。それはマンガ雑誌自体が右肩上がりだったことが背景にあります。
乱暴な編集のしかたでも成功体験が得られたので、その中でも学んでいくことができたんですね。
ところが、いまはマンガ編集になった瞬間に、会社として利益や数字を上げなきゃいけないというプレッシャーがあり、失敗することが許されない。そうすると、なかなかやっぱり育つことが難しい。
だからいまは、もう一度マンガのメソッドや基本を、文法的なことなども含め、編集者にちゃんと教えなきゃいけないと思っています。そのうえで「どうマンガ家と向き合うか」などの話になる。
そろそろ出版社が本腰を入れて「編集を育てる、社員を育てる」ということを考えなきゃいけない時代が来ていると思います。
Q.いまの『ドラゴンボール』ビジネスの展開を見て、鳥嶋さん個人が思うところがあったら伺いたいです。
鳥嶋氏:
さっきも言いましたが、僕は日本のマンガ、アニメ、ゲームに関わる経営者のレベルの低さに非常にがっかりしています。
というのも、そこで儲かったお金は、子どもなど、読者やユーザーからのお金なんですよね。たまたまそこにいて資本を出したから儲かっている人たちがいるけど、これは市場に還すべき義務があると思うんです。
なぜ義務なのか。これはちゃんとしたマンガの市場がないところにはマンガの文化が続かないのと同様に、マンガやアニメ、ゲームで儲かったら、つぎの世代の発見、育成、市場作りや土壌作りにお金を出さないと文化が続かないから。
ここについて、残念ながら日本の経営者は哲学もないし、市場に関して気持ちがない。だからダメです。だからおそらく三代でどの会社もダメになるでしょうね。本当にちゃんとした経営なら、ちゃんとした才能に対してどう投資するかを考える。これしかないと思うんですよ。
たとえば、マンガだったら「鳥山(明)さんみたいになりたい」、アニメだったら「庵野(秀明)さんみたいになりたい」など思う。そして「なってよかった」となれる。そういう才能のバトンタッチがいい形でできるような環境をどう整えるかです。
「そのためにお金を還せるかどうか」、大事なのはここだと思います。ですから僕は、東映アニメとバンダイナムコが、『ドラゴンボール』で儲けたお金をマンガやアニメやゲームに投下してくれることを願っています。関わる人たちには言っていますが、果たしてどこまで響いているか。
Q.先ほどのお話にもあったように、デジタルでは、「興味をそそる売れるものしか作ってはならない」なども出てくると思います。そういう中で雑誌が持っていたスタイルは今後どういう風に時代に求められていくと思っていますか?
鳥嶋氏:
雑誌の「雑」はいろいろなものがあるから「雑」なんですが、もうそれを読者は望んでいません。それで「定期的に雑誌を買っている人はどれくらいいるのか」と今日始めに手を挙げていただいたんです。結果、白泉社の新入社員より雑誌を買われていました(笑)。
同じ質問をここ数年しているんですが、新入社員で定期的に雑誌を買っている人間がほぼゼロなんですよね。ですから、今日ここにいる皆さんは、まともなのでビックリしたんですけども。
なぜ買わないのか。白泉社の新入社員に聞くと、「手が汚くなる」、「好きじゃないものが載っている」、「持ち運びに不便」など、そういう意見が出てくる。
最初は「えええ」と思ったが、「自分がいま読者だとしたら」と思うと、ある部分は頷けるものがある。よほど自分が好きな情報が載っていないと、やっぱり雑誌は買わない。でも雑誌は本来、そういう形で始まってここまで広がって来たんですね。
ですから、いまはもう一回、雑誌が雑誌であることの意味や、その価格で読者が手に入れる価値があるかどうか問われているんだと思うんです。
 |
集英社で先輩に言われ、いまも心に残っている数少ない言葉のひとつが、「鳥嶋くん、君が作っている雑誌、君はその値段で買う? 買いたいと思わないんだったら、その雑誌は市場性がない雑誌だよ」というものです。
つねに、「仕事として成り立つようにこの値段を付けているんじゃない。価値に対して付けている」ってことは考えますね。
雑誌に残された意義は、作家や作品を育てる場であることと、その才能が競って作品を読者に提出していく場であること。これがデジタルのネット上でうまくでるきようになったら、雑誌は本当に要らなくなります。
だから雑誌のゆくすえは、編集がちゃんとこの方法を見つけられるかにあります。
あと出版社はどこもそうですが、そもそもいま出版に入る人はデジタル的なものにはあまり興味がないか弱いところがある。ですが、デジタルについて分業で外に投げていた時代は終わり、これからは最低限デジタルのことについて知識があり、外の技術者と組むときも、「自分がどうしてほしいのか」を形にできるくらいのレベルの知識がないと、編集者ってたぶん難しいと思うんですね。
つまり、出版社の編集者のありかたや社員の採りかた自体を変えていかなければいけないと思います。
Q.紙、とくに雑誌の時代はいつまで続くと思いますか。
鳥嶋氏:
なくならないとは思います。ですが団塊の世代と一緒に育ってきたものなので、その人たちがいなくなると一気に需要はなくなりますから、文章、写真、デザイン、紙質、それから書体など含め、もう一度、紙でなきゃいけない編集のしかた、雑誌の載せかたなどが問われると思うんですよ。
それは映画が一度テレビにやられて終わったけど、いまとなっては映画のほうがもう一回メディアとして考えられ、テレビが時代遅れになりつつあるのに似ています。だから、ちゃんとしたものをソフトとして考えて作れば、それは生き残っていける。
雑誌が終わりなんじゃなくて、いい加減に作っている雑誌が終わりつつあるということだと思います。
Q.雑誌が死んだあとの時代に、編集が付き、子ども向けとしてちゃんと考えられたコンテンツが、子どもたちの目の届くところで展開されるとすれば、それはどういうメディアでしょう?
鳥嶋氏:
方法はたったひとつです。いいものをタダで見せる。いま僕が集英社にいるんだったら、子ども向けに作った『ジャンプ』をタダで配ります。
──ですが、先ほどのお話からすると、タダの場所にはプロフェッショナリズムが出ない可能性は?
鳥嶋氏:
ですから、そのあとどう回収するかちゃんと考えるわけです。あざといですが、たとえば電子コミックの、最初の数巻はタダで読めるけどあとは有料というシステムなど、そういうやりかたを含め、いろいろなテクニックを組み合わせたうえで、「子どもたちを最初にどう導入するか」を考えるわけです。
知ってもらわないことには、すべてが始まりません。知ってもらうということは、伝わるということ。タダのものが溢れている中で値段を付けるのは非常に困難なので、本意ではないけども、まず子どもにいいものをタダで見せるということを、いまはやらざるを得ないんじゃないかと思います。
「それが面白い」、「それがやっぱり友だちに思える」、「それがなきゃちょっとつまらない」ということになれば、人間には欲がありますから、それは多少のお金を出してでも手に入れたいと思うはず。
それをいかにあざとくなく、スムーズにするかじゃないかと思いますけどね。
あとひとつ、子どもは大人と違って本当にお金がありませんし、不自由です。だからそのコンテンツと親しんでいるあいだは、ある種の気分転換ができる、現実を忘れられる、そういう励ましのしかただとか、コンテンツの作りかたをしてあげたいなと思いますね。
児童虐待や学校のいじめを聞くと本当に胸が痛みますから。
好奇心と想像力がカギ
気づけば、あっという間で濃密な1時間半が経過。拍手で見送られながら、「一瞬だけ大学生に戻ったみたいだった」と照れ笑いをする鳥嶋氏が印象的だった。
以下は講義のまとめとして、最後に鳥嶋氏から編集者志望の学生に向けて贈られた言葉だ。学生のみならず、現役の編集者、それからあらゆるクリエイティブに携わる人に響くものではないだろうか。
鳥嶋氏:
編集者になるために特別な才能は必要ないと思います。繰り返しますが、編集者として大事なことは、「この人はなんでこんなことを考えているのか」なんて面白い人がいたとき、それを「誰かに知ってほしい」、「伝えたい」と思うこの興味の持ちかたと紹介したいという熱意です。何もできないからこそ誰かの才能を評価できる。それが編集者。そこをやっぱり心がけてほしいです。そのために好奇心を持ち続けてください。
もうひとつは、たとえば何か企画があるときに、「○○がわからないから」と、いろいろなことを棚に上げないでほしいということ。どんな読者でも、どんなユーザーでも、僕らと同じ時代を生きています。
ということは、僕らが朝起きてから夜寝るまでのあいだ、どういう風に生活して、どういう風にメディアに接しているかを考えれば、答えの半分は出てくるんですね。想像力があれば、広告代理店に頼らずとも、マーケティングはできます。だからつねに自分と人をよく見て、なぜそうなるのかを考え続けてほしい。このふたつができれば編集者になれると思います。頑張ってください。
【あわせて読みたい】
【佐藤辰男×鳥嶋和彦対談】いかにしてKADOKAWAはいまの姿になったか──ライトノベルの定義は「思春期の少年少女がみずから手に取る、彼らの言葉で書かれたいちばん面白いと思えるもの」【「ゲームの企画書」特別編】記事では、佐藤氏の経歴を振り返りつつ、ライトノベルはどういう経緯で大きなジャンルに成長したのか、ライトノベルの本質とは何か、それを送り出してきたKADOKAWAは出版業界の中でどういう役割を果たしてきたのか、そうした話を伺った。
一介の中堅出版社に過ぎなかった角川書店が、いかにして3大出版社に追いつき、そして4大出版社となるに至ったのか。佐藤氏の話からは、チャレンジャーとしての角川だったり、ほかの出版社と比べて異質なものとしてのKADOKAWAの姿が際立って見えてくるだろう。
同時に鳥嶋氏の視点を通じて、その背景にあるマンガ・アニメや『ジャンプ』の動向、出版社とテレビ局の関係、同時代の隣接的なジャンルがどういう変遷を遂げたかという大きな流れも語られている。
あの時期頂点にいて、間違いなくサブカルチャーを担っていたふたりが見ていた当時の景色を、この記事で読者の方々とともに垣間見られれば幸いだ。