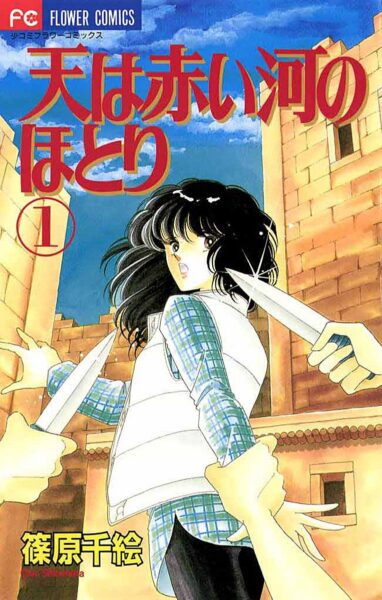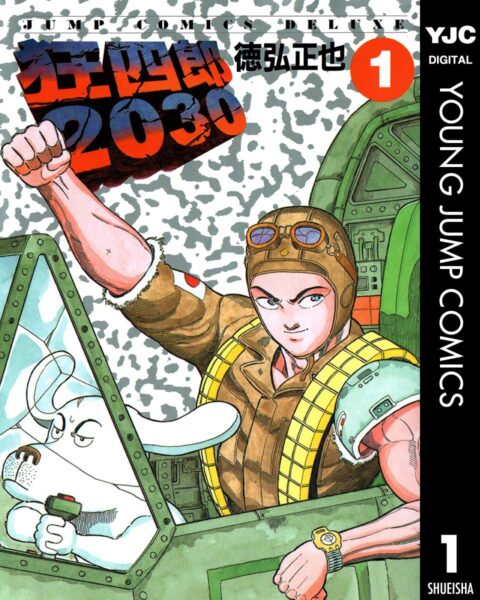2016年がVR元年と呼ばれてからはや3年、VRゲームは爆発的な普及に至らず、いまだに黎明期の扱いである。VRが一般化できない要因としては、VRヘッドセットの大きさと重さやキラーコンテンツの不足などさまざまあるものの、もっとも大きい要因のひとつが「VR酔い」である。
VRは人間の両目の視覚をCG映像で覆いつくすことにより、人間の脳を「まるでそこに存在しているかのよう」に騙しているのだが、視覚以外の感覚や現実世界における経験と一致しない場面に出くわすと、脳が違和感を覚えて酔いが発生するのだ。
この問題はおもにVRゲームの「移動」で発生する。
VRゲームの開発はVR酔いとの戦いと言っても過言ではなく、ゲーム開発者たちはVR酔いを防ぐために「移動」のさまざまなアプローチを試みてきた。たとえば、プレイヤーが指定した場所へ一瞬で行くワープ移動を採用したり、視点の回転を30度ずつ切り替わるようにしたり、プレイヤーを乗り物やコックピットといった舞台装置にぶち込むことで酔いをしのいできた。
一方で、「いっそのことプレイヤーを移動させなければ酔わない」というアプローチも存在する。しかし、ビデオゲームはプレイヤーが移動できないとゲームデザインの設計やゲームの展開の演出がしづらいのだ。
今回はこういった「動けないVRゲーム」の問題を「言葉の通じない少女との体験」に置き換えようとした意欲的なVRゲーム『ラストラビリンス』を紹介しよう。
文/渋谷宣亮
編集/ishigenn
『ラストラビリンス』はあまた株式会社が開発し、同社が2019年11月13日に発売開始したVRゲームだ。本作のディレクター/プロデューサーを担当する高橋宏典氏は『どこでもいっしょ』シリーズの生みの親であり、本作の主要スタッフは元SIE(旧SCE)系タイトルに携わった人物が多い。
本作の公式ジャンル名は「VR脱出アドベンチャーゲーム」。プレイヤーは車椅子に拘束されており、館には死の罠が張り巡らされている。そのため、プレイヤーは言葉の通じない少女と協力して謎を解くことで館からの脱出を目指すことになる。
この記事では、本作がゲームデザインをどのように工夫することで酔いや違和感を解決しようと試み、プレイヤーに劇的な感情を抱かせる唯一無二の体験になっているかを解説する。一方で、VRを志向した演出とビデオゲームの作法の矛盾によってもたらされるゲームプレイの苦しみについても触れてみたい。
ユーザを拘束することで少女との共同作業を演出
『ラストラビリンス』でプレイヤーがすることは、Flashゲームの時代に隆盛した脱出ゲームと基本的には変わりない。ボタンを押してレバーを倒し、パズルが正解になるまで物体を動かし続けるのだ。
しかし、本作は脱出ゲームを「少女との共同作業」に変換することでVRならではの”体験”に昇華しようとしている。
まず、プレイヤーは車椅子に拘束されているので動けないため、プレイヤーは少女「カティア」と協力して謎を解く必要がある。具体的には、プレイヤーの頭から発射されるレーザーポインターでギミックを操作するように指示を出す。
 |
通常、VRゲームにおいてNPC(ゲームのキャラクター)と意思疎通をする方法はいろいろあるのだが、本作はその際に発生しやすい問題点をうまく解決しようとしている。
NPCと会話がしたければ、画面上にセリフの選択UIを出すのが手っ取り早いのだが、特にVRゲームではゲームらしさが強調されるせいで現実味が薄れてしまう。一方、プレイヤーが実際にうなずきと首振りをジェスチャーによってYES/NOの意思表示をするような手法は、人間の挙動として自然であるが現実的に考えるとやや回りくどい。
そこで、『ラストラビリンス』はゲーム側から「少女とは言葉が通じないため会話ができない」という状況を提示することで、プレイヤーにうなずきと首振りのジェスチャーを使った意思表示を自然と受け入れさせている。
言葉は通じないけど意図が通じた状況では、ある種の万能感や連帯感を生み出し、心地よい気分にさせてくれるのだ。
 |
また、少女はプレイヤーの意図に従うだけでなく、指示がない場合は自律的に動く。部屋を歩き回ってギミックを物色したりプレイヤーに近づいたりしてくるので、より一層自然な人間のように感じられる。
少し嫌らしい言い方かもしれないが、少女がギミックを動かすたびに見せるか弱い挙動も、プレイヤーに親近感や庇護欲を抱かせる。本当に介抱されているのはプレイヤーの方なのだが。
このように、本作はプレイヤーが少女に対して親しみを覚えるようなゲームデザインとなっている。しかし、本作はプレイヤーの感情を喚起するさらなる仕掛けが出てきて、それこそが本作の肝となるのだ。
 |
少女に訪れる死とプレイヤーの感情の喚起
本作はプレイヤーがゲームを始めて数分でその本性を現す。プレイヤーが謎解きを間違えると、罠が発動して少女が死ぬのだ。
少女は壁や天井に押しつぶされ、ギロチンによる断頭、薬品の注射で自意識の喪失、電気椅子での処刑など散々な目に遭う。
幸いにも少女の血液や肉体の断面が描写されることはなく、推奨年齢もCERO: D(17歳以上)に収まっているので、残酷表現が苦手な人や未成年でもプレイできる。
しかし、少女の死ぬ描写で肝心な所が隠れていることにより、かえってプレイヤーに死を想像させる。一連の光景は、成年向けのスプラッターやゴア的表現とは一味違う生々しさがある。
 |
また、プレイヤーは拘束されているので、何もできずに少女が死ぬ様子を見届けるしかないのだが、死の罠は少女の後にプレイヤーも殺す。実はここにもVRゲームならではの工夫が隠れている。
VRは非現実的な体験ができるメディアでありながら基本的に主観視点であるため、「視点の人物に何が起こっているか」を表現するのが苦手である。
生きている人間が死を体験することはないため、VRで馴染みのない死の演出に遭遇しても、現実の経験に基づいた共感がしにくいのだ(銃器や刃物はわりとびっくりするけれども)。
そこで、本作は少女を先に殺すことでプレイヤーに「次はお前がこうなる番だ」と予告し、死に対する恐怖と決断の後悔を抱くように仕向けている。
もしこのゲームに少女が存在せず、プレイヤーにいきなり壁が迫ってきて、押しつぶされたり電気椅子で電流を流されたりするとどうなるだろうか。プレイヤーはあっけにとられてしまい、状況を把握して怖がることすらできないだろう。
 |
コンセプトと噛み合わないゲームメカニクスがプレイヤーをふるいにかける
本作のプレイヤーの心を揺さぶる演出には目を見張るものがあり、ゲームの序盤ではプレイヤーの体験を巧みに演出しきってみせている。しかし、ゲームが後半に進むにつれてゲームデザインとコンセプトが噛み合わなくなってしまう。本作は複数の要因が重なってプレイヤーの継続意欲を妨害している。
ひとつ目に、少女の死の演出が煩わしくなる。最初はプレイヤーが憐れんでいた少女の死も、繰り返されると悲劇の瞬間から退屈な待ちぼうけへと変化する。
一度見た死亡演出はスキップできるが、不便なメニューの遷移とロード時間のせいで快適にはならない。これが積み重なると、プレイヤーの意識が「少女が死ぬのがかわいそうだから失敗したくない」から、「メニュー画面とロード時間でストレスが溜まるのが嫌で失敗したくない」へと変質する。
また、本作における少女の機能は脱出ゲームのカーソルと同じであり、プレイヤーはカーソルに感情移入しているようなものだ。
逆に言えば、プレイヤーはパズルを解きたくてカーソルを動かしたいのに、カーソルとしての少女はそのリアルで人間らしい挙動ゆえに時間がかかるのだ。機能に人格を見出したはずの存在が、機能として見るとあまりに不十分でストレスを引き起こす原因になる。
 |
ふたつ目に、本作独特の奇妙な難易度上昇がある。序盤の謎解きはチュートリアルを兼ねた簡単なものだが、中盤からの謎解きはプレイヤーに攻略の手がかりを与えず、目指すべきゴールがわからない状態で手探りさせるようになる。
しかし、本作は謎解きを間違えると少女が死んでしまうので試行錯誤がしづらく、一方でプレイヤーがVRゴーグルをつけたまま何もせずに熟考するのもプレイヤーの体力を摩耗する。すると、プレイヤーはVRゴーグルを外して、紙とペンを用意してそちらで解き始めるのが楽だと気づく。プレイヤーがVRゴーグルを外した方が楽なVRゲームは、今まで聞いたことがない。
 |
三つ目に、本作はユーザビリティが非常に不親切である。本作は「言葉の通じない少女との意思疎通」がテーマのひとつなのだが、これに拘り過ぎてメニューなどUIが著しく不便になっている。
本作はポーズメニューが存在せず、謎解きのエリアを選択できるのは少女が死んだときだけだ。復帰時に選べるエリアもひとつかふたつのみで、チャートを見るといった機能もない。本作は分岐エンドを採用しているのに、プレイヤーが今どの場所にいるのか、何をしているのかを把握させてくれないのである。
おそらく、これはゲーム開発者とプレイヤー(および筆者)の価値観の問題である。本作の開発者はヴァーチャル・リアリティの没入感とリアリティを重視した“体験”を作ることに焦点を当てており、実際にVRならではのエモーショナルな体験を演出することには成功している。
しかし、これをビデオゲームとして捉えると、VRのために没入感とリアリティを優先した演出が引き起こす不便さや退屈さによって、「このゲームを最後まで”攻略”し続けたい」という意欲が削がれるのだ。筆者はこれをビデオゲームとして優れている作品だと評価することはできなかった。
 |
『ラストラビリンス』はVRゲームの問題点を「少女との体験」に置き換えることで解決を試んだタイトルである。実際、プレイヤーをゲームのキャラクターに共感させることで、「プレイヤーの感情を呼び起こし心をかき乱す」ことにかけては非常に優れている。
しかし、あまりにマニアックなパズルとプレイヤーに忍耐を強いるシステムによって人を選ぶ作風となっており、少なくないゲーマーにとって本作を最後のエンディングまでプレイするのは耐えがたい苦痛となるだろう。
とはいえ、ゲーム冒頭の演出の素晴らしさやプレイヤーの心をえぐるような残酷さは、VRゲームどころかビデオゲーム全体でも類を見ない完成度を誇る。本作はまさにVRの黎明期に相応しい挑戦的なVRゲームとして名前を残すのかもしれない。