物悲しい音楽とともに画面に表示される「GAME OVER」の8文字。ゲーマーのみなさまなら何度となく目にしてきた言葉でしょう。
「ゲームオーバー」という言葉は、日本語では「試合終了」や「ゲームの終了」を意味するほか、比喩的に「敗北」や「一巻の終わり」といったネガティブな意味合いでも用いられます。実はこの言葉、外来語なのか和製英語なのか、辞書によってその扱いが割れていることをご存じでしょうか。
「game over」を外来語とし、前述の日本語と同じような意味合いで英語圏でも使われているとする辞書もあれば、「game」と「over」を単純に組み合わせたものとして、あるいは「game is over」がなまったものとして、単純に「試合終了」を意味する和製英語とする辞書もあります。
それを疑問に思った調査員・タイニーPが問い合わせたところ、なんと小学館の『大辞泉』編集部から、「今回の問い合わせを機に調査した結果、今後「ゲームオーバー」から和製語であることを示す記載を外す」という旨の返答を頂きました。
もともと英語圏から入ってきたはずの「game over」が、なぜ「ゲームオーバー」という和製英語として誤解されてしまったのでしょうか? その背景には、『スペースインベーダー』ブームの影響がありました。(編集部)
文/タイニーP
なぜか一部の辞典で「和製英語」扱いされる「ゲームオーバー」
今回のテーマは「ゲームオーバー」だ。アクションゲームやシューティングゲームなどではあまりになじみ深いこの言葉。
一方で、2017年にニンテンドースイッチ用として発売された『スーパーマリオ オデッセイ』では、ゲームオーバーのシーケンスがなくなったことが話題になったのを、ご記憶の方も少なくないだろう。
マリオの体力が0になったり、奈落に落ちると、持っているコインが10枚減ってしまいます。ただし…!いくらミスしてもGAME OVERはありません。 pic.twitter.com/6oEia6LcVr
— スーパーマリオ オデッセイ (@mario_odysseyJP) July 4, 2017
ところで、筆者が高校時代に使っていた『旺文社英和中辞典』(1991年重版)は、『日本語の中の外来語ノート』という冊子が別冊付録になっていた。この冊子では、和製英語をはじめ、外国人に通用しないカタカナ語の解説に対して特にページを割いているのだが、この中に「ゲームセット」があり、以下のように述べられている。
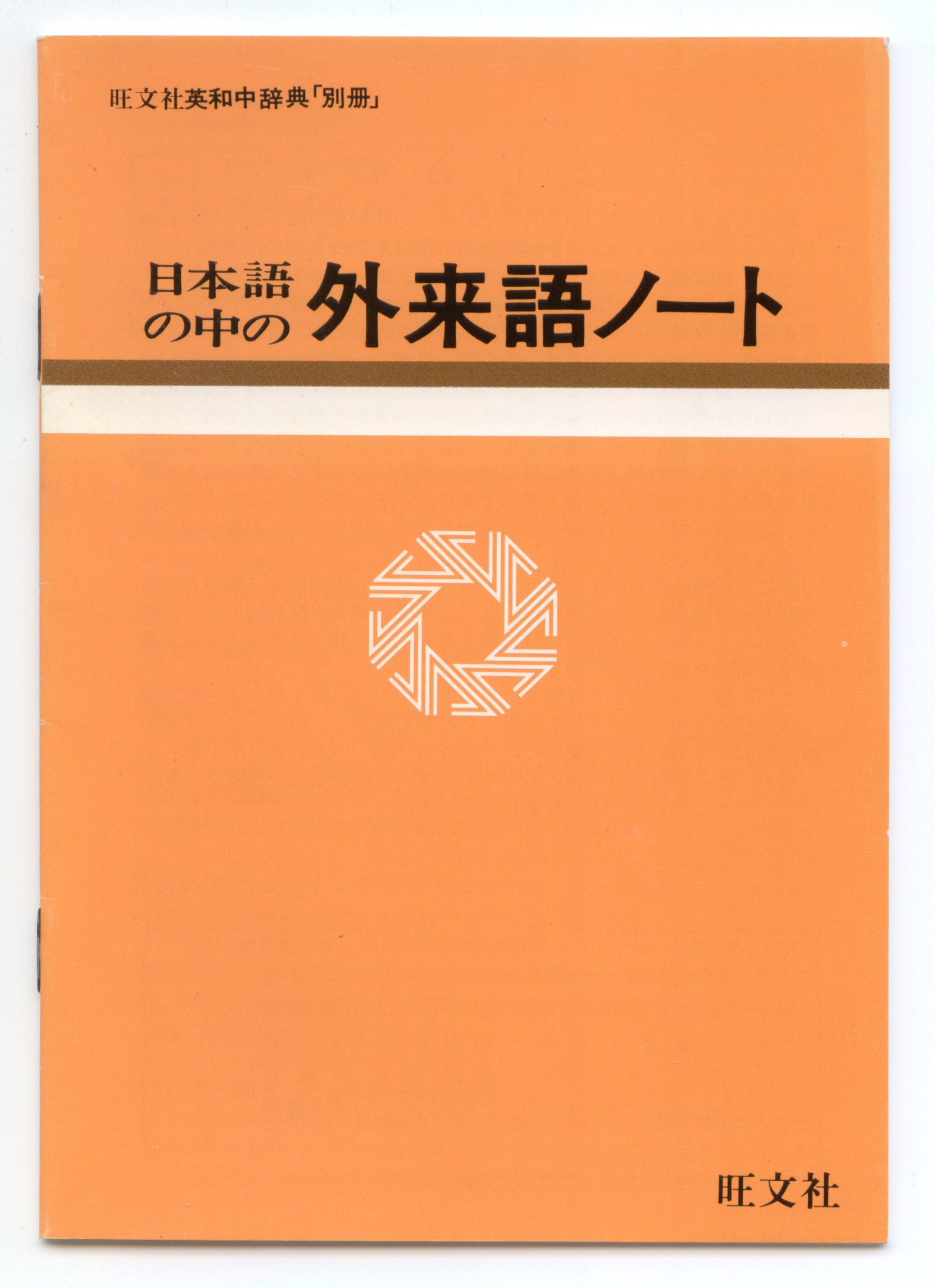
「もとはテニス用語で(中略) game and set のことで、(中略)日本では野球などでもよく「ゲームセット」というようだが、この場合は game over を使う。」
このため筆者は長らく、「game over」は英語圏ではビデオゲームを抜きにしてもありふれた表現なのだと思っていた。
ところが、この連載でもたびたび取り上げている中型国語辞典の『広辞苑』、『大辞林』、『大辞泉』を調べてみると、なかなか不思議なことになっている。いずれの最新版にも「ゲームオーバー」が収録され、おおむね「試合終了」という意味の説明がつけられているが、それぞれ言葉の由来の扱いが異なっているのだ。
『広辞苑』第七版は、外来語として「【game over】」と綴りのみ示す。『大辞林』第四版は「〔the game is overの略〕」としており、「原語音からいちじるしく転訛した外来語や、外国語に擬して日本で作られた片仮名の語(凡例より)」という扱い。
そして『大辞泉』第二版では、「《和game+over》」と、完全に和製語(和製英語)の扱いになっている。
そこで丸善出版が2014年に刊行した『和製英語事典』を確認したところ、こちらにも「ゲームオーバー」の項目があり、「試合終了という意味でかなり定着している和製英語」とした上で、次のように補足されている。
「日本発のビデオゲームの影響から、コンピュータ画面上で game over のサインをよく見ているネイティブにはそのまま伝わります。オカシナ英語がネイティブの間に定着しているということの見本ともいえるコトバです。」
もしかすると、野球などの試合の終了を「game over」と表すのは、実は英語圏では日常的・現代的ではない使い方なのだろうか?
とはいえ、ひとつはっきりしていることがある。「GAME OVER」という表現自体は、ビデオゲームのみならず、1950年代や1960年代のアメリカ製のアーケードゲーム、つまりコイン式ゲーム機にいくらでも実例があるのだ。
ピンボール、射撃ゲーム、シャッフルアレイ【※】など、ゲームの種類もさまざまだ。
※シャッフルアレイ
厚みのある円盤を板の上で滑らせて遊ぶゲーム「シャッフルボード」の変形で、ボウリングとほぼ同じルールにしたゲーム機。
日本にもこれらのゲーム機が輸入されたし、また勃興期にあったタイトー、セガ、ナムコなどの日本のゲーム機メーカーも、海外輸出を念頭にその表現をそのまま取り入れた【※】。少なくともゲーム機器にまつわる「ゲームオーバー」という言葉は、このようにして日本に入ってきたものだ。

(画像はNAMCO ARCHIVES AYUMI|ナムコワンダーランド チラシギャラリーより)
「ゲームオーバー」が和製英語と誤解されたワケ
そこで筆者は今回、『大辞泉』の小学館と『和製英語事典』の丸善出版に、「GAME OVER」がアメリカ製の古いゲーム機にもみられる表現であることを紹介したうえで、「ゲームオーバー」を和製語とした経緯について問い合わせてみた。
ここではそれぞれからいただいた返信をもとに、「ゲームオーバー」が日本の一部の辞典で和製語とされた事情を考えてみたい。なお『大辞泉』は、今回の問い合わせを機に調査した結果、今後「ゲームオーバー」から和製語であることを示す記載を外すそうだ(『デジタル大辞泉』は2019年末に早くも変更している)。
さて『大辞泉』については、「ゲームオーバー」は1995年刊の初版にはなく、同社が1990年に刊行した『例文で読む カタカナ語の辞典』の内容を取り入れたことにより新設された項目とのことだった。
そこで同書を直接当たってみると、確かに『大辞泉』第二版と同じ「試合終了。また、コンピューターゲームなどの終了」との説明で、“和製洋語”として「ゲームオーバー」が掲載されている。さすがに30年前のものだけに、この『例文で読む カタカナ語の辞典』がなぜ「ゲームオーバー」を和製語としたのかは確認できなかったという。
しかし、同書で「ゲームオーバー」の説明に「コンピューターゲームなどの終了」との一節がわざわざ入っていることは、なかなかに示唆的だ。
ここからは筆者の推測になるが、これはやはり1979年前半のインベーダーブームや、1980年代中盤以降のファミコンブームの影響が大きそうだ。これらのブームにまつわる報道の中で、それまで日本のマスコミでは目立たなかった「ゲームオーバー」という言葉を見かける機会が急激に増え、ビデオゲームと強く結びついた印象になったのだろう。
『和製英語事典』の丸善出版からの返信でも、英オックスフォード大学出版局による『Oxford Dictionary of English』で、「game over」の説明が以下のようになっていることが指摘されている。
「状況が絶望的、または逆転不能とみなされる時に使う。[おそらくコンピューターゲームの終わりの際に使われる言い回しに由来する]」(筆者訳、第3版で確認)
イギリスがアメリカとどの程度事情が異なるのか詳しくは確認していないが、現代のビデオゲームのルーツのひとつにピンボールなどのコイン式ゲーム機があるということは、日本と同じように、一般にはあまり認知されていないのかもしれない。
それはさておき、日本ではブームの周りには何かと奇妙な略語や造語、カタカナ語が飛び交いやすい。ファミコンブームについて言えば、「ファミコン」は当然のことながら、「ソフト」や「キャラ(「隠れキャラ」などの)」といった言葉も和製語の仲間だ。
これらのように単語の後半を省略するパターンのほかに、フレーズの中間の語句を抜くものもある。「time is up」が「タイムアップ」となったのもその例のひとつとされるが、「ゲームオーバー」もこうした言葉と同じ形に見えた可能性は十分に考えられる。
このような誤解や勘違いが重なった結果、一部の辞典で「ゲームオーバー」が和製語とされてしまったのではないか。これが現時点での筆者の見解だ。
黎明期のコンピューターゲームでは、「ゲームオーバー」はレアだった?
ここまで見てきたように、「GAME OVER」という表現は1950〜1960年代のアメリカのアーケードゲームにありふれていたものだった。では同じ時期、のちのパソコンゲームにつながる系譜……つまり、当時まだアメリカでさえも個人所有が広まっていなかった、コンピューターで遊ぶゲームではどうだったのだろうか。
1960年代のアメリカでは、大学や企業にコンピューターが導入される中、ダートマス大学で1964年に開発された「BASIC」をはじめ、入門者用のプログラム言語が広まりつつあった。
さらにこのダートマス大学のシステムも含め、1台のコンピューターを複数の端末から並行して利用する「タイムシェアリングシステム(TSS)」の開発が盛んになった時期でもあり、1970年代にかけ各地の高校までの学校でも、電話回線を通じて近隣の大学や企業のコンピューターを“時間貸し”で利用できる端末を設けるようになった。
このような環境整備の結果、それまでコンピューターの応用範囲の研究の一環として、あるいはその研究者や大学生、見学者のささやかな娯楽として楽しまれてきたコンピューター上のゲームは、その開発者層が10代前半にまで広がったようだ。
その集成として後世に名を残したのが『101 BASIC Computer Games』だ。コンピューターメーカーのディジタルイクイップメント(DEC)が1973年に出版したこの本【※】には、単純な数字あて・単語あてゲームに始まり、コンピューターと対戦するスポーツゲームなど、さまざまなゲームプログラムの遊び方、プログラムリスト、実行サンプルが多数収められている。
※前書きでは、「これはコンピューターゲームやシミュレーションの最初のコレクションではない。しかし(中略)BASICで書かれたゲームのみのコレクションとして最初のものだ」(筆者訳)と述べられている。
なお、このころのコンピューターの利用環境ではブラウン管のディスプレイはまだ広くは普及しておらず、TSSではテレタイプ(通信機能を付加できる電動タイプライター)を端末に使うことが多かった。
これらは出力をロール紙など縦につながった紙に印刷することがほとんどだったので、「ゲーム画面」と呼べるものはない。いわゆるアスキーアートによる図形を印刷して、何らかの状況や動きを示そうとするものも一部にはあったが、文字のみで遊ぶゲームも少なくなかった【※】。

Dominic Alves from Brighton, England – ASR 33 Teletype, CC 表示 2.0, リンクによる
※一方で、単にアスキーアートで大きな文字や図形を印刷するだけというプログラムもいくつか収録されている。現代のビデオゲームには直接はつながらないが、これも当時の“コンピューターを使った遊び”に含まれていたのだと考えられる。
さて、この『101 BASIC Computer Games』のプログラムリストを見てみると、ゲームの終了時に「GAME OVER」と印字するようになっているものは、数えるほどしかない。「GAME IS OVER」を加えてもかなりの少数派だ。
よくあるパターンは、「YOU WON!!!」、「I WON!!!」といったメッセージやスコアなどに続いて、再プレイするかどうかをたずねる文章が印字されて入力待ちになるというものだ。
なぜこのように、「GAME OVER」の利用例が少ないのか。これらのゲームプログラムの作者の大半がアーケードゲームに疎かった可能性もあるが、根本的には、ゲーム環境の違いの影響が大きいだろう。
当時のコイン式ゲーム機は、ゲーム盤面やスコアボードの中に、スコア表示部や「GAME OVER」の表示部などが個別に組み込まれており、盤面自体とこれらの仕組みによって、ゲームの状況をリアルタイムに確認できた。
これに対しこの時期のコンピューターのBASICは、そもそもリアルタイムの入出力を想定していない。つまりその上で動くゲームもリアルタイムには進行せず、ゲームの状況の変化は、プレイヤーの入力が確定した後の応答として印字されるものでしか把握できない。
さらに「ゲーム画面」がない以上、印刷用紙のどこに何の情報が印字されるかは、せいぜい水平位置について定められる程度でしかない。
そのため、ゲーム終了時に重要なのはむしろスコアを含むゲーム結果を説明する印字であり、「GAME OVER」のような終了のみを知らせるメッセージは、あってもなくてもよかったのだと考えられる。
『インベーダー』が変えた「ゲームオーバー」
ところで、先に『Oxford Dictionary of English』での「game over」の説明の中に、「絶望的」・「逆転不能」といった意味の記述があることを紹介した。
日本でも、辞典類ではあまり触れられていないものの、「ゲームオーバー」がこれらや「敗北」の比喩……つまり「一巻の終わり」に相当する表現として使われることは決して珍しくない。
日本で「ゲームオーバー」にこういったネガティブな意味合い、特に「敗北」のニュアンスが込められるようになったきっかけは、やはりあの『スペースインベーダー』にあるとみて間違いない。
もちろん先にも触れたとおり、そもそも「ゲームオーバー」という言葉が日本で広く知られるようになったのも、インベーダーブームがひとつの契機だったと考えられる。つまり、それ以前からアーケードゲームにどっぷり漬かっていた“筋金入り”の人々を除けば、「ゲームオーバー」には当初から「敗北」のにおいが付きまとっていたと言っていいだろう。
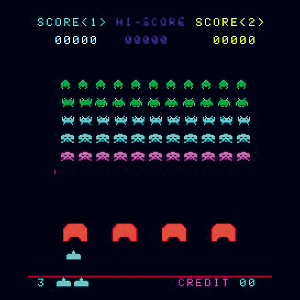
こういった認識が広がったのには、インベーダーブームが社会現象として取り上げられるほど巨大なものだったことも当然寄与しているが、根本的な理由は『スペースインベーダー』のゲーム内容そのものにある。次はこの点について見てみよう。
以前の連載でも述べたが、『スペースインベーダー』までのビデオゲームは、プレイ時間や、射撃・投球の回数があらかじめ決まっているものが大多数だった(高得点の“ごほうび”としての時間延長などはあったが)。
これはビデオゲーム以外のコイン式ゲーム機も同様で【※】、たとえばプレイヤーと機械・コンピューターとの対戦ができるものでも、ある時間や回数の中でプレイヤー同士が互いに得点などを競うルールの上で、機械側が片方のプレイヤーの代わりをする形になっていた。
※ピンボールについては、プレイヤーの操作でボールをはじく「フリッパー」が導入されてからの隆盛の中で、「投球回数が決まっている」という要素は残りつつも、腕前次第で延々とプレイすることも可能となっていた。
『スペースインベーダー』がこれら従前のアーケードゲーム機と大きく異なっていたのは、インベーダーがプレイヤーのビーム砲を攻撃する意味合いだ。
インベーダーの攻撃は、コンピューター側が点を得るためやプレイヤーの得点を妨害するためではなく、とにかく一刻も早くプレイヤーをゲーム終了に追い込むためのものだった。もちろんそのスリルがインベーダーブームをもたらし、またその後のアーケードのビデオゲームに強大な影響を及ぼしたのだが、それゆえに「敗北」と「ゲームオーバー」が同等のものとして結び付いたわけだ。
「ゲームオーバー」の“ニクい味付け”
さらに『スペースインベーダー』は、ゲームオーバーにまつわる“ある手法”をも決定的に印象づけた。それを説明するために、アーケードゲームでの「GAME OVER」の使われ方をもう少し見ていくことにしよう。
先の繰り返しになるが、ビデオゲーム隆盛以前のアーケードゲーム機では、ゲーム盤面やスコアボードの中に「GAME OVER」をランプで示す機構が含まれていた。そしてこれは、単にゲームの終了をプレイヤーに知らせるためだけでなく、「ゲーム機は稼働中だが、今はゲーム中ではない」という状態を示すためにも使え、実際に少なからぬゲーム機がそうしていた。
その場合、ゲーム中以外はずっと「GAME OVER」のランプが点灯したままだったわけで、この表示には暗にコインの投入を促す意味合いもあったと考えられる。
一方アーケードのビデオゲーム機は、1970年代前半のごく初期の段階では、ハードウェアの制約により数字を表示するのが精いっぱいで、「GAME OVER」を画面内に表示することはできなかった。
これが1970年代後半になってようやく、マイクロプロセッサー(CPU)の導入や半導体メモリーの価格低下によって、画面に「GAME OVER」などと表示するものが増えてきた。
そしてこれらの多くは、他のアーケードゲーム機にならい、ゲーム終了のタイミング以外に、デモンストレーションなどゲーム中でないときにも「GAME OVER」を出すようになっていた。
ところが『スペースインベーダー』では、「GAME OVER」はゲーム終了のタイミングでしか表示されない。しかも1文字ずつ、ゆっくり表示されるようになっている。
これはデモ画面中の「PLAY SPACE INVADERS」などのメッセージの表示と同じ手法で、見ている人の注意をひき、印象を強めようという意図が込められていると考えていい【※】。

(画像は【実演】レインボー|taitochannelより)
※1文字ずつゆっくり表示されるのは、ハードウェアの制約によるものではない。デモ画面での「INSERT COIN」や「TAITO CORPORATION」の文字表示は一瞬で行われている。
つまり『スペースインベーダー』は、「GAME OVER」の表示自体にささやかながら“演出”を取り入れたビデオゲームでもあったということだ。これによってプレイヤーの「やられた! くやしい!」という感情を増幅させ、再プレイへの意欲を喚起しようという目論見は、少なからず成功したはずだ。
そしてゲームオーバーの演出には、やがてコナミの『フロッガー』(1981年)やナムコの『ディグダグ』(1982年)のように、「GAME OVER」の表示と専用の音楽を組み合わせる手法も加わる。これらが『スーパーマリオブラザーズ』などのファミコンのゲームにも受け継がれていったわけだ。
「祝ゲームオーバー」っていったい何!?
こうして「ゲームオーバー」は、ファミコンブームの渦中の子どもたちにも当たり前に使われるようになった。ただし、そこに生じていた「敗北」との結びつきは、ここまで見てきたように、インベーダーブーム以降のアーケードゲームからもたらされたのであって、ビデオゲーム全般に普遍のものではない。
それをファミコンユーザーに広く知らしめたゲームとして真っ先に挙がるのは、やはり『ドラゴンクエスト』シリーズだろう。1986年発売の第1作の、王様の「しんでしまうとは なにごとだ!」の一言だけで「主人公が死んでもゲームオーバーにはならない」というルールを説明しきった手管には、今さらながら舌を巻いてしまう。
さらに、その前年に発売されたファミコン用『ポートピア連続殺人事件』も、真犯人にたどり着かずに捜査を終結させてもゲームオーバーにはならない。
このころは、アドベンチャーゲームやRPGであっても、プレイヤーのミスを原因とするゲームオーバーはあって当たり前で、『ドラクエ』によってその傾向がすぐに変わったわけではない。
しかし、この後の家庭用ゲーム機やパソコンのゲームにおいて、プレイヤーのミスをルール上でどう扱うかを考える際の、重要なモデルケースになったことは間違いない。
一方、これとは異なる形で「ゲームオーバー」にまつわる思い込みを揺さぶったのが、ハドソンが1983年末に発売したパソコン用アドベンチャーゲーム『デゼニランド』だ。
このゲームでは、最終目的を達成しゲームの舞台であるデゼニランドから脱出すると、割れたくす玉から「祝ゲームオーバー」と書かれた垂れ幕が下がっている様子を描いたグラフィックが表示される。
実はなんと、これが最終画面……つまり現在でいうエンディングの画面となっていたのだ。
もちろん『デゼニランド』には、当時のアドベンチャーゲームらしく、プレイヤーがうかつな行動を入力すると、ミスとしてゲームオーバーになる仕掛けがあちこちに施されている。つまり最終画面の「祝ゲームオーバー」は、このような“常識”を逆手に取ったシャレの一種だったわけだ。
これは『デゼニランド』自体、ギャグやパロディーを満載したゲームだったからこその“大ネタ”と言えるが、そのことをうまく理解できなかったプレイヤーもそれなりにいたようだ。
『マイコンBASICマガジン』1985年5月号の「山下章のレスキュー・アドベンチャーゲーム」のコーナーでも、この「祝ゲームオーバー」の画面を「脱出の方法が悪かった(つまりプレイヤーのミスの)結果」ととらえてしまった読者からのハガキが紹介されている。

とはいえ、このようなネタはともかく、エンディングをゲームオーバーととらえること自体は別段おかしいことではない。
特にアーケードゲームの場合、インカム(店側の収入)の観点から、ストーリー上のエンディングを迎えたあとは、ナムコの『ドルアーガの塔』のようにゲームオーバーとするか、もしくはカプコンの『魔界村』のように難易度を上げて最初のほうの面に戻るかのいずれかとせざるを得ない。従ってアーケードゲームになじみの深い向きほど、このとらえ方への抵抗感は少ないだろう。
「ゲームオーバー」に“終わり”はあるか?
こうしてみるとゲーム用語としての「ゲームオーバー」は、日本に入ってきた当初から、アーケードゲームの仕組み、ゲームデザイン、ひいてはビジネスモデルに強く影響され続けてきたことがわかる。
そしてアーケードのビデオゲームは、1990年代以降もさまざまな変化を遂げた。たとえば記録カードや外部とのネットワーク通信の導入により、プレイヤーの腕に関わらず1回あたりのプレイ時間がほぼ同じ、あるいはそれに近い仕組みのゲームを成立させやすくなった。
このように、プレイヤーがミスしてもプレイ時間への影響はなく、また上手いプレイヤーへの“ごほうび”も、プレイ時間の延長とは違う形でもたらされるゲームでは、「ゲームオーバー」と「敗北」などのネガティブなイメージとは、あまり結びつかないだろう。
ゲームセンターにこのようなビデオゲームが増加している現在では、対戦格闘ゲームが花盛りだった1990年代に比べると、「ゲームオーバー」と「ゲーム終了」などとの意味合いに大きな差がなくなってきているとも言えそうだ。
するとアーケードゲームでは、あえて「ゲームオーバー」という言葉を使う理由も薄らいでいると考えてもおかしくない。
とはいえ、この理屈はピンボールをはじめとする海外製のゲームに当てはめることは難しい。それに、家庭用ゲーム機を中心に、何度となく復刻されている古典的名作はもちろん、いわゆる新作レトロゲームなど、プレイヤーのミスによるゲームオーバーをゲーム体験に組み込んでいる作品もまだ根強くある。
ゲーム用語の「ゲームオーバー」は、そう簡単に終わりを迎えることはなさそうだ。
コラム:「ゲームオーバー」は「オカシナ英語」?
本文で取り上げた『和製英語事典』では、「ゲームオーバー」について、「オカシナ英語がネイティブの間に定着しているということの見本ともいえるコトバです。」と解説していた。
この説明は筆者にはかなりの驚きで、どのような判断でこのような記述に至ったのか、丸善出版に問い合わせたところ、門外漢の筆者に懇切丁寧な返信をいただいた。
その返信の中で、「ゲームオーバー」を「オカシナ英語」としたことについて、主に以下のような経緯が挙げられた。
a) 『Oxford Dictionary of English』などで、「game over」がinformal(略式・口語的)であると示されていること
b) やはり『Oxford Dictionary of English』などで、「game over」を「状況が絶望的、または逆転不能とみなされる時に使う」と説明しているのに対し、日本では「ゲームオーバー」が「試合終了、ゲーム終了」の意味で定着しているという違いがあること
このうちa)については、「game over」が略式の表現であることは筆者にももちろん異論はない。ただ、この表現が生まれたのが日本ではなく、アメリカからもたらされたものであることは、本文で示した通りだ。
日本語でも、略語や口語表現が「改めて考えると奇妙に感じる」ということはしばしばあるわけで、英語圏でも事情はそう変わらないということだろう。
またb)は、和製英語の類型のひとつである、「同じ表現でも、英語圏で使われる場合と日本で使われる場合で意味が大きく異なる言葉」のことを想定していると考えられる。しかし、これも本文で記したように、日本でも「ゲームオーバー」を「一巻の終わり」の意味で使うことは珍しくない。
また「ゲーム終了」の意味で使うことについても、日本と英語圏で特に違いがあるとは考えにくい。
このように、『和製英語事典』で「ゲームオーバー」が「オカシナ英語」とされたのは、アメリカ製のコイン式ゲーム機について日本ではあまり知られていないがゆえの、誤解から来たものということになるだろう、というのが筆者の見解だ。
とはいえ、この回答は本稿の執筆に至った大きなきっかけであり、その多くを参考とさせていただいた。この場を借りて、ご回答いただいた『和製英語事典』著者の亀田尚己氏、ならびに窓口となっていただいた丸善出版の小林氏に改めてお礼申し上げたい。
【この記事を面白い!と思った方へ】
電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。
頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応
※クレジットカードにのみ対応
【あわせて読みたい】
「レトロゲーム」という言葉の由来を探る──「回顧・懐古」から「レトロ」へ、そして「オールドゲーム」から「レトロゲーム」へ2016年の「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」を嚆矢とする「ミニ」シリーズがゲームメーカー各社から次々と発表され、「レトロゲーム」は今やゲーマーのみならず、一般的にもすっかりお馴染みとなりました。
今回はいつからこの「レトロゲーム」という言葉が使われるようになったか、そして復刻やリメイクによって、いつから往年のゲームが「レトロゲーム」と呼ばれるようになったのかを探っていきます。


































