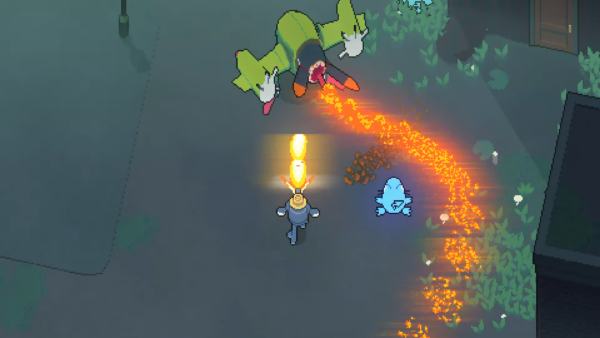ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、6月13日にリリースするトレーディングカードゲーム『マジック:ザ・ギャザリング』(以下、マジック)の新セット『マジック:ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』 のPRイベントを、5月14日にクラブエックス 品川プリンスホテルで開催した。
『マジック』といえば、元祖戦略トレーディングカードゲームとして全世界で5000万人以上のプレイヤーとファンを持つタイトルだ。それが、スクウェア・エニックスの人気RPGである『ファイナルファンタジー』シリーズのナンバリングタイトル16作品とコラボするということで大きな注目が集まっている。
今回のイベントでは、会場内にカードやクラウドとセフィロスの等身大アクリルパネルなどが展示されていたほか、オープニングでこの日のために結成されたアコースティック楽団による生演奏で、『ファイナルファンタジーXIII』の楽曲である「閃光」が披露されるなど、かなり気合いの入ったものとなっていた。
こちらの記事では、当日会場で発表されたカードの情報などをまとめてレポートしていく。






スクエニのアーティスト・板鼻利幸氏と松田俊孝氏がゲストで登壇し、手掛けたアートの制作にまつわる裏話を語った
イベントでは、ゲストとしてスクウェア・エニックスのアーティストである板鼻利幸氏と松田俊孝氏が登壇した。
板鼻氏は、『マジック』のルールを覚えるより先に美しいアートがいっぱいあるゲームということから、アートブックを集めていた。そうしたこともあったため、今回のコラボレーションの話しが来たときは世界的なゲームに自分が参加できることに、嬉しさよりも先に驚きが強くきたという。
一方、松田氏は元々『マジック』で徹夜することもあるほどのファンだ。そのため、コラボレーションの話しを聞いたときは、社員としてよりも一ファンとしてドキドキワクワクしたと、素直な感想を述べていた。

板鼻氏が手掛けたカードのアートは、《迷える黒魔道士、ビビ》だ。ビビはクリーチャーでない呪文を唱えることでどんどん成長していくカードとなっている。『ファイナルファンタジーIX』の中では、マスコット的な存在にみられがちだが、様々な出会いや困難を乗り越えていくうちに成長を遂げていく。そうした要素がこのカードの能力としてよく表されている。
ちなみに、最初にビビを描いてくれといわれたとき、板鼻氏はいろいろと悩んだそうだ。ビビ自体は表情がなく、引っ込み事案のキャラクターでもある。黒魔導師でもあるため攻撃魔法を打つ絵にしようと考えながら描き始めた。
しかし、戦っているだけでは、「こんなにアグレッシブだったっけ?」という違和感がある。そこで、ゲームに登場するブリ虫を追加し、それに驚いて魔法を放ったといったストーリーにして絵のゴールが見えてきたのだという。
松田氏がアートを手掛けたカードは《苦悩の竜騎士、カイン》だ。こちらは『ファイナルファンタジーIV』に登場する竜騎士のカインを描いたものである。竜騎士というジョブは、ジャンプという技を持っている。この技を使うと画面外に飛び出していき、2ターン後に落ちて敵にダメージを与えることができるというのが特徴だ。
その時のRPGはターン制が当たり前であったにも関わらず、それを無視して壊していくという遊び心が『ファイナルファンタジー』にはあった。また、松田氏は竜騎士が飛んで行った後で、彼は今何を見ているのだろうかと考えていた。そのときの思いを、自信も好きな『マジック』という舞台で再現することができるとは思っていなかったため、楽しく描くことができたという。
それぞれの手掛けたカードの紹介が終わった後は、おふたりからのメッセージが語られた。
板鼻利幸氏:
『マジック:ザ・ギャザリング』と『ファイナルファンタジー』がコラボをするって、コアなプレイヤーの方やメディアの皆さんとかって、どのくらい想像されていたのかなって。ちょっと僕には読みきれないところなんですけど、僕はかなりびっくりして。そういうことが起こり得るんだっていう衝撃が初めに大きかったですね。この夢のようなコラボは本当に僕もすごく楽しみにしているので、皆さんも遊べるのを楽しみにしていただけたらなと思っております。松田俊孝氏:
1枚イラストを描かせていただけるだけでなく、数百枚のイラストをいろいろ監修させていただいたとき、大変だなと思ったんですが、『ファイナルファンタジー』を心から愛してくださるウィザーズ社の皆様、そして『マジック:ザ・ギャザリング』を心から愛している市川さん、そして山下さんという方々の熱い思いに押されて、夢を見るような気持ちであっという間に過ぎていった日々でした。『ファイナルファンタジー』という歴史を紐解きながら、この最高のゲームで至福の時間を過ごしていただけたらなと思います。
「リビングが映画館になった」。開発の最高責任者が10歳の頃に体験した『FF10』の衝撃が、今回のコラボ実現にも繋がった
イベントでは、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのエグゼクティブ・プロデューサーで、主にゲームデザインや開発の最高責任者を務めるザキール・ゴードン氏と、本セットのリードも務めたほか、今回のイベントでは通訳を行ったジョセフ・シンジ・リース氏が登壇。
ザキール氏がどのような思いで今回の『マジック:ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』に取り組んで来たかが語られた。

ザキール氏が、『ファイナルファンタジー』に出会ったのは10歳の頃だった。当時近所に住んでいた年上の友達の家に通い詰めており、一緒にゲームをプレイしていたのである。そんなある日、いつものように友人宅へ遊びに行ったところ、『ファイナルファンタジーX』の壮大な音楽が流れ、リビングが映画館になったような体験をしたという。
この出会いは、ザキール氏にとってファンタジーという世界の扉を開くきっかけとなった。そして、こうした過去の思い出を語るのは、それほど今回のコラボセットの制作が特別な経験でもあったからである。開発にかかった4年間で、ザキール氏の心の中にあった問いは、売上げや自信のキャリアのことではなく「このセットは、FINAL FANTASY ファンの期待に応えられるだろうか?」ということだった。
もちろんプロジェクトを成功させたいという気持ちもあったが、それは「10歳の自分が、夏の間ずっと夢中になって遊び続けるようなものを作る」ということがゴールだったからだ。そして、今年の2月に『マジック:ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』の最初の情報を公開することになる。
その結果、本拡張セットは『マジック』史上、世界中で成功したプレビューとなったのだ。また、ファンからの反応も「ちゃんとわかっている、そして正しく作られている」とかなり好意的に受けられたのである。
ここで、今回のコラボでも大きな役割を果たし、スクウェア・エニックスで『ファイナルファンタジーVII エバークライシス』のプロデューサーを務める市川翔一氏登壇した。『ファイナルファンタジー』シリーズの思い出を語ったザキール氏にならい、市川氏は自信の『マジック』の体験を披露した。

市川氏が12歳の頃、話題の中心は『ファイナルファンタジー』や『ドラゴンクエスト』などのゲームだった。だが、あるとき友人が赤黒い不思議な箱を持ってきた。そのなかには、不思議な魅力が詰まったカードがたくさん詰め込まれていたのである。1冊だけあったルールブックをみんなで読み合い、その日は一日中『マジック』を遊んでいた。
それから、市川氏の生活には常に『マジック』があった。『マジック』を通じて、市川氏は大事なことを学んだという。それが、「自分の運や未来を信じることはとても重要だが、それ以上にその結果をたぐり寄せるための準備が大事だ」ということだったのだ。
今回のセットは、4年という歳月を掛けて、最高の未来を信じて準備を進めてきた。先ほどの『マジック』から学んだ教訓のように、最高の結果は強いカードが得るからできるものではなく、ましてや偶然得られるものではない。その結果が得られると信じて、試行錯誤を繰り返しながらも準備を整えたから今があると、これまでの道のりを振り返る。
また、世界中の『マジック』のファンと『ファイナルファンタジー』のファンにとっても特別な存在になってくれることを心から願っているとアピールした。
悪役や武器、魔法をモチーフにしたSecret Lairドロップ3種が公開
今回発売される『マジック:ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』は、『ファイナルファンタジー』シリーズとの特別なコラボレーションで生まれたものだ。『ファイナルファンタジー』シリーズは、1987年に初代『ファイナルファンタジー』が発売されて以降、2023年に発売された『ファイナルファンタジーXVI』までのメインシリーズの世界観を丸ごと本セットに収録している。
今回のリリースされるのは、スタンダードで使用可能な全300種以上のカードを収録したフルセットのブースター製品だ。こちらは、通常の「プレイ・ブースター」に加えて2種類のバンドル商品も用意されている。
また、シリーズの各時代を象徴する4つの統率者デッキも登場する。『ファイナルファンタジーVI』はピクセルアート時代を代表する作品として、『ファイナルファンタジーVII』はPS1時代の金字塔として、そしてザキール氏が特に思い入れがある『ファイナルファンタジーX』はPS2時代の代表作。
最後に『ファイナルファンタジーXIV』はMMORPGという新たな形で、世界中のファンが親しんでいる作品を統率者デッキに落とし込んでいるのである。
それに加えて、フォイル仕様のカードが手に入る「コレクター・ブースター」など、コレクター向けの商品も充実している。統率者デッキにもコレクター仕様があり、内容は自体は同じだが全てのカードにサージ・フォイルが仕上げられている。
ここで、ザキール氏から『マジック:ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』に登場するSecret Lairドロップ3種全てが公開された。こちらは、日本では6月10日より発売される予定だ。Secret Lairドロップは英語版と日本語版の両方で展開され、ノンフォイルの通常版に加えてフォイル版も存在。いずれも期間限定での販売となっている。
『Secret Lair x FINAL FANTASY: Game Over』は、シン、セフィロス、アーデン、ケフカ、アルティメシアといった『ファイナルファンタジー』シリーズの悪役たちが、ヒーローたちに攻撃や必殺技を仕掛ける瞬間を描いている。統率者に人気の高い呪文を集めているほか、それぞれのカードの効果も悪役の特徴を表したものになっているのだ。
『Secret Lair x FINAL FANTASY: Weapons』は、クライヴ、クラウド、ユウナ、ティーダ、ガイアといったファンの人気が高い主人公たちと、彼らの象徴的な武器をカードにしたものだ。こちらのドロップでは、ゲームプレイの面白さとストーリーの深さの両方を意識してカードを選んでいる。
たとえば「クライヴのインヴィクタス」は《我々の刃》として登場。若き日のクライヴの姿が映り込んでおり、無人のメカニズムが絵で表現されている。また、「クラウドのバスターソード」は、《梅澤の十手》として登場。メインセットのクラウドに装備することで、一撃ごとに最大4つのチャージカウンターを得ることができるといった感じだ。
『Secret Lair x FINAL FANTASY: Grimoire』は、呪文をテーマにしたカードだ。『マジック』の5色のカラーを通じて『ファイナルファンタジー』の世界を表現している。5色それぞれの個性を持った呪文として描かれており、美しいアートと強力な呪文の効果の組み合わせが特徴となっている。
このSecret Lairバンドルの特別プロモカードは、《金粉の水蓮》だ。こちらには、ミッドガルの教会で咲くエアリスの花がモチーフになっている。英語版と日本語版の両方で入手可能な特典カードになっているが、セール期間中に販売されるいずれかのSecret Lairバンドルの特典として付属している。
市川氏によると、この《金粉の水蓮》は当初、海外のみで展開されるプロモカードだった。だが、エアリスをモチーフとしたこのカードはどうしても日本のプレイヤーに届けたいということで、市川氏がザキール氏に懇願し、日本でも入手可能になったそうだ。
《桃源郷の探求者、チョコ》は、『ファイナルファンタジーIX』に登場するチョコボを描いたカードだ。単体でもアドバンテージを発揮できるが、複数のクリーチャーと組み合わせることでさらに進化を発揮する。
また、『マジック』史上初の伝説のチョコボでもあるため、チョコボテーマのデッキを作りたい人にとっても、夢のカードとなっているのだ。
《モーグリたちの奮闘》は、戦闘中のトリックとして使うことで、相手の除去からクリーチャーを守ったり、有利なブロックにつなげたりと、様々な場面で活躍するカードになる。ちなみに、こちらのカードで描かれているのは『ファイナルファンタジーVI』でモーグリたちが敵兵からティナを救い出し、彼女の逃走を助ける場面だ。
召喚獣たちのラインナップから登場するのが、《リヴァイアサン》だ。『ファイナルファンタジー』シリーズではすっかりおなじみの召喚獣だが、『マジック』では戦場に出ていられる期間が限られており、「英雄譚・クリーチャー」として機能する。
市川氏によると、召喚獣は『ファイナルファンタジー』シリーズとしても重要な存在でもあるため、ただの強力なクリーチャーになってしまうのではないかという心配があった。だが、戦場に出ていられる期間が限られていることから、一時的に活躍して強力な効果を発揮するほか共闘もしてくれるという、召喚獣の持つイメージをシステムでうまく表現していると語っていた。