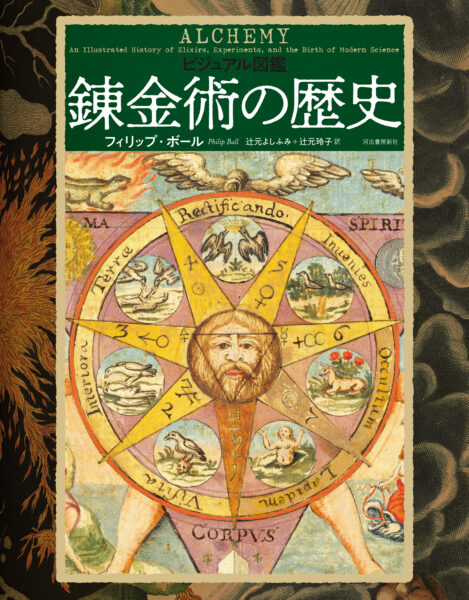怖すぎるゲーム作りは簡単、じつはバランス取りが難しい
ひととおりプレイを終えたところで、開発元であるZero Latency社のCEO、ティム・ルーズ氏に『ZOMBIE SURVIVAL』のこと、Zero Latency社のこと、VRに関する思いなどをいろいろと尋ねた。最先端を行く開発者自身はVRをどう見ているのか。
 |
──企画は当初からフリーロームVR内で歩くことが目的だったと伺いました。日本での第一弾はそれを踏まえたシューティングなんですね。シューティングを選んだ理由は?
ティム・ルーズ氏(以下、ティム):
シューティングは、お客さまが理解しやすいんです。わかりやすくて楽しくて浸透しやすいので第一弾としました。ずっと目標にしていたのは、ワイヤレス環境で完全なフリーロームが楽しめるというシステムですね。そこからいろいろなコンセプトを考え、いまは探検系のゲームやパズル系のゲームも開発しています。ですので今回の銃型コントローラーだけでなく、剣などに持ち替えたりできる技術を仕込んでいます。今後はサービスを続けつつ、何がいちばんお客さまのストライクゾーンに入りやすいかを見極めて、形を変えながらやっていきたいと思っています。
──フリーロームVRとそれ以外の決定的な違いはなんだと思いますか?
ティム:
一般的なコンソールゲームの場合、ものによっては早い段階に飽きたりしますが、フリーロームVRはその場にいたり、場の転換に立ち会ったりしているだけでもおもしろく、楽しさやプレゼンス(実在感)が維持されやすいんです。それらの体験を導くために、『ZOMBIE SURVIVAL』にはいろいろな要素を入り組んだパズルのように込めています。
──パズルのような要素とは具体的には?
ティム:
場の中で人を誘導する方法、楽しさを維持できる動き、適切な没入感の用意のしかた、そして安全に楽しんでいただくための配慮などですね。それらを抜けなく配置し、さらにプレイの進行に合わせてゲーム的なおもしろさを展開させるなど、考えることがかなり多く、システムの構築を含めていままでの年月がかかったわけです。
──『ZOMBIE SURVIVAL』でいちばん気にした部分は?
ティム:
初めてフリーロームVRの世界に飛び込んだだけで没入感そのものを感じるお客さんも多いんですよ。そういうことを知るために、メルボルンで最初に始めたβテストプレイを通じて、プレイヤーの感じるおもしろさをずっと研究してきました。非常に難しかったのは、初めて体験する方でもとりあえず楽しめ、なおかつリピーターを呼ぶための難しさを残すというバランス取りですね。
──難しそうですね。
ティム:
ええ。初めて挑む方がオーバーに圧倒されないように注意しました。最初に試したバージョンには、もっといろいろなチャレンジが入っていましたが、βテストを始めると、やっぱり対応しきれないお客さまも多く現れます。それらを外してかなりシンプルにしたんです。一例としては、リロード機能を遅くして、じつは威力も低めに設定しています。
 |
──それは敵に迫られたときに緊迫感を出すためでしょうか?
ティム:
恐怖はそういう部分で演出しないとダメなんですね。最初の18ヵ月のテストの中でとくに陥りがちだったのは、怖すぎる設定なんです。これがじつはけっこう簡単にできてしまう。ですが、あまりに怖いとプレイヤーが走って逃げてしまい、安全面に悪影響が出るんです。「怖いけど走り出さない。でもインパクトがあっておもしろい」というバランスを取るのにかなり苦労しましたね。
──そんなに怖いコンテンツだったのですか。
ティム:
最初は、懐中電灯付きのガンを持って暗闇を歩くタイプでした。真っ暗な中から敵が飛び出て襲ってくるのがあまりに怖すぎて、「これは抑えなければならない」と勉強になりました。プレイヤーの皆さんがだいたい1分でギブアップするという怖さで、そんなに楽しくないんですね。
──それも見てみたかった気がします(笑)。セガから話があって、セガとのプロジェクトが始まったのはいつでしょう?
ティム:
2015年の11月からです。
──商用化まで半年強は早いですね。内容についての要望はありましたか?
ティム:
無理なものはありませんでしたが……鶴見社長【※】からゾンビを増やせと言われましたね(笑)。「大きくて速くてもっとアグレッシブに!」という要望があっていまに至ります。
※ジョイポリスを運営するセガ・ライブクリエイションの代表取締役会長兼社長 鶴見尚也氏。
──セガと協業して、日本ぽさと言いますか、「こういうことを日本は、セガは言うんだ」と感じられた部分などは?
ティム:
ぜんぶですよ(爆笑)。いや、悪い意味じゃないですよ。「どれだけ速く話が進むんだ」というほど開発スピードはスゴかった(笑)。それがいちばんびっくりしましたね。メルボルンで展開しているものから一部のアセットを流用していますが、東京ジョイポリスのものは、大きくアーケードゲーム寄りにテイストを振っているんです。スコアが出るとか、撃ちかたや銃によって点数が変わるとか。12分でどんどん展開が進むシューティングですから刺激の洪水になっています。もちろんプレイ空間の形もメルボルンと違いますので、それに合わせて作っていますね。
──セガさんらしい仕上げですよね(笑)。
ティム:
そうですね(笑)。僕らもみんな若いころにセガのゲームをいっぱい楽しみましたので、その影響も間違いなくあると思います。
 |
身体を使うVRの臨場感
──Zero Latencyという会社についてもお尋ねします。どういう経緯で立ち上げた会社なのでしょう?
ティム:
「スクリーンを観てプレイするのではなく、ゲームの世界に入り込む」という目標を掲げ、3人の仲間で集まっていっしょに作り始めています。
私は、それまでMODを作ったりなど趣味の範囲でゲームはやっていましたが、ゲーム開発者というわけではありませんでした。キールはデジタル的な取り締まりをする公共機関CSIの職員でしたし、その彼がプロジェクトマネージャーだった時代にプログラマーだったのがスコットです。
──皆さんそういう経歴なんですね。ゲーム畑ご出身でないのは驚きです。4年前の2012年から開発を始めたと伺っていますが、それはOculus Riftがキックスターターで発表されたあたりでしょうか。そこでどうしていまのアイデアを?
ティム:
約4年は間違いないです。デベロップメントキットを触りながら、座って楽しむVR体験の限界をわりと早く感じていたので、その限界を越えるためのプラットフォームを作りたいと最初から思っていましたね。
──最初からフリーローミングVRありきだったと。
ティム:
プロトタイプのときから、このフリーローミングVRには何かがあるという可能性は感じましたね。解決すべき問題をひとつずつクリアしていくと、さらにどんどんおもしろくなっていったんです。それで3人の結束力がより強まり、もっといいものにという欲に変わりました。「必ず商業ベースになるようなものが作れる」という揺るぎない自信がありましたね。
 |
──ビジネスモデルとしては、こうしたZero Latency VRというシステムをいろいろな場に卸していくのですか?
ティム:
そこはそのとおりです。何よりフリーロームVRのプラットフォームとしていちばんになりたいんです。そうすることでフリーロームVRのおもしろさを、早く全世界に広められる。そう広く展開していくためのパーツは揃っています。さらに現在この商業レベルまで到達している企業はなく、いまはリーダーシップを取れていると思っています。
──それ相応のビジョンがあると。
ティム:
細かくは言えませんが、どんどんプラットフォームを進化させ、よりおもしろく、楽しく遊べる要素を増やすロードマップがあります。コンテンツに関しても、自分たちでも開発していきますし、サードパーティのIPを借りて協業していったり、SDKも出していたり。サードパーティの皆さんからのコンテンツもひとつの道として広げていきます。
そこからリージョンに合わせたコンテンツも登場するでしょう。結果的にメニューが増え、楽しめる環境が増え、いちばん幅広い体験ができるフリーロームVRになっていくと思います。
──ただ、VRは同時に大量の人数で体験しづらく、感想の共有もしづらいですよね。そこを踏まえた今後のアプローチなどあるのでしょうか?
ティム:
独特で唯一のエンタテイメントなので、おっしゃるように楽しさを伝達しづらいのですが、メルボルンの結果から、評判は口コミでどんどん広がっていくということがわかっています。いちばん効果的なマーケティングは、プレイの内容でなく、プレイしている姿のビデオを見せること。少人数でしか体験を共有できないことも、裏返せばプレミアム感が出ているわけで、それがソーシャルで広まっていくと、仲間で集まってやってきてくれるんです。
──なるほど。関連してお尋ねすると、いまプレイステーションVRなど、家庭用VRへの注目度も高いのですが、コンシューマー機との比較や棲み分けについてはどうお考えですか?
ティム:
まず『Zero Latency VR』について言えば、技術は時間経過とともにコストが下がるものなので、プレイスポットも増加させられますし、プレイヤーの数も増え、運営もしやすく、投資の回収もしやすくなります。それらをぜんぶ重ね合わせると本当に大きくなっていくプラットフォームだと思います。
いま体験していただいたのは6人が上限でしたが、メルボルンでは現在16人プレイを試しています。拠点を跨いだPvPなどもいろいろ研究しているので、今後浸透していくのではないかなと思っています。
そうしてどんどん大きいものを作っていけば、愛好家の人数も増え、eスポーツのようにひとつの軸になる一大アトラクションに発展を遂げていくと思っています。
──言ってみればアーケードでのプレイヤー体験が、VR全体の市場をドリブンしていくということですね。家庭用市場の先行きはどうお考えでしょう? 中には、アーケードVRには期待を感じるが、家庭用はそんな大きな規模になるかどうかという人もいます。
ティム:
プレイステーション4という市場へ浸透しているハードがあるので、家庭用ではソニーが優位に立つのではと思います。ただ不安なのがソフトそのものですね。アイデアについては問題ないでしょうけど、日本を含めたアジアはプレイのために広いスペースが取れないことが多いので、「動きのあるものがまず作れるのか?」という懸念や限界を感じます。3×3メートルの中での体験しか作れないとなると、ソフトをずっと開発し続けていくことへのハードルの高さを危惧しますね。
それから家庭用の市場にいろいろなプラットフォームやフォーマットがあると、コンテンツが分散されてプレイヤーの悩みを引き起こしますよね。その一方でVRをとりあえず体験してみたい人、遊びたい人はジョイポリスに来て1800円を払えば、自宅では20~30万円払っても体験できない、大がかりで刺激的な体験をして帰れます。そういう意味では、はっきりアーケードとコンシューマーでマーケットが分かれる可能性がありますね。
──仕事柄VRにはしばしば触れますが、視覚だけでなく、身体の体験とセットだと、臨場感や内容の存在感は格段に上がるんですよね。家庭用だけでなく、『ZOMBIE SURVIVAL』のようなものを、気になっている皆さんに体験していただいて、身体を動かすVRの楽しさを広めていくのがいちばんいいんだろうなと思います。
ティム:
ええ。まったく新しいエンターテイメントの一種なので、触っていただかないことにはお伝えしづらいんですよね(笑)。自分の身体全部を使うこと、フリーに動けること、それらを一気に体験できるのはこのフリーロームVRにしかないよさです。体験がいちばん。ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
 |
小山オンデマンド
週刊ファミ通、ファミ通.comなどを経て、電ファミニコゲーマーに参加。
稀覯本からアダルトVRまで幅広く記事を作成中。ホラー総力特集では、
年表内コラムや脳を担当。好きなゾンビはハーゲンタフ。