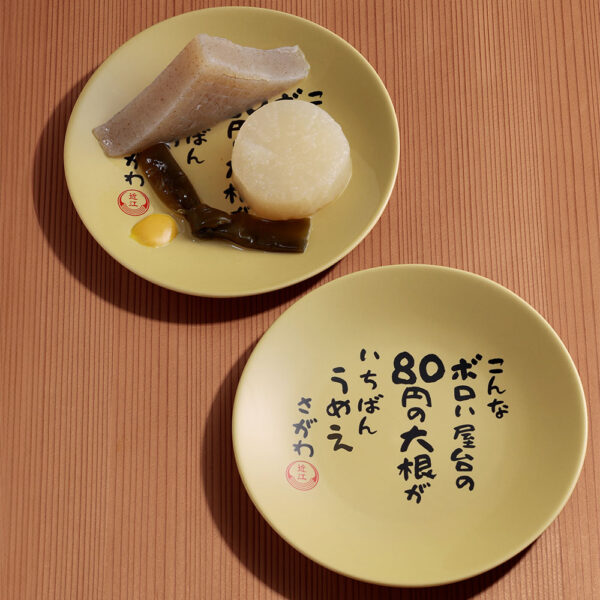10月31日、公益社団法人 日本漫画家協会は、講談社や小学館をはじめとする大手出版社17社と2協会が、「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」を共同で表出したことを発表した。
同声明では、OpenAI社の「Sora2」をはじめ、既存の著作物を利用した作品がAIによって生成・公開・公衆送信される現状において、著作権侵害に対して法的・倫理的観点から適切に行動し、著作物や創作物の「利用と保護」の両立を模索する立場を、あらためて表明している。
「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」が発表されました。詳しくは添付画像資料またはリンク先をご覧ください。
— 日本漫画家協会公式 (@mangaka_kyokai) October 31, 2025
2025年10月31日
公益社団法人日本漫画家協会https://t.co/Ywulm6w5pe pic.twitter.com/SSozt99l8z
今回の声明は、漫画の普及や調査研究、創作活動の奨励に諸外国との漫画文化の交流により文化の発展に寄与することを目的とする「日本漫画家協会」と、アニメーション製作業界の意思を統合し、関連する諸企業・団体との連携を保ち、アニメーション産業全体の持続的発展を目指す「日本動画協会」、および講談社や小学館をはじめとする大手出版社17社により共同で発出されている。
【共同発出者】(五十音順)
一般社団法人 日本動画協会
株式会社秋田書店
株式会社一迅社
株式会社宙出版
株式会社 KADOKAWA
株式会社コアミックス
株式会社講談社
株式会社小学館
株式会社少年画報社
株式会社新潮社
株式会社スクウェア・エニックス
株式会社竹書房
株式会社 TO ブックス
株式会社日本文芸社
株式会社白泉社
株式会社双葉社
株式会社芳文社
株式会社リイド社
公益社団法人 日本漫画家協会
声明内ではまず、OpenAI社から発表された映像生成AI「Sora2」において、権利者から明示的な拒否の申請がない限り、著作物が生成・公開・公衆送信されるシステムが、著作権法の原則のみならず、WIPO(世界知的所有権機関)の著作権条約の原則にも反しているという認識を示した。
そして、「第二、第三の Sora2」とも言うべき新たな生成 AI が登場することを危惧し、コンテンツ産業の一員として原則的立場を改めて表明する必要があると判断したことから、今回の声明を公表する経緯に至ったとのこと。
日本漫画家協会の基本的な考えとしては、生成 AI 技術の進展を歓迎し、その可能性を正しく活かすことで、より多くの人々が創作の喜びを分かち合える社会が望ましいとしている。
一方で、著作権侵害を容認しないという原則を改めて確認。生成AI によって人の創作物が学習され、新たに生成物が創出される際には、以下の原則が遵守・実行されるべきだとしている。
① 学習段階および生成・公表段階の両方において、著作権法の原則に沿って権利者に必要な許諾を得る等の対応を AI 事業者が取る
② 学習データの透明性が担保されている
③ 権利者が利用を許諾した場合、権利者への適正な対価還元が行われる
これにくわえて、権利者と AI事業者、関係省庁をはじめとした関係者間が連携・協力をしたうえで、生成AIのユーザーが他者の著作物をもとにしたことを知らずに、他のクリエイターの権利を損なう状況を防ぐことも必要だと考えている。
上記を踏まえて、現時点での懸念としては、「権利者によるオプトアウトが原則では権利侵害につながる」「データの学習段階における透明性担保が不十分である」の2点を挙げている。
前者では、権利者の側からの拒否を求める姿勢は、著作権法の「権利者の許諾を得てから利用する」という原則に反しているとし、AI事業者による権利者に対しての許諾申請の徹底を要求。
後者では、AIの学習段階でどの著作物や表現をもとに生成されたかが不明なままでは、権利侵害の検証が困難でとなることを主張。作品のイメージや創作者の評価を損なう悪質な行為に対応するにあたっての障害となることを危惧している。
また権利侵害への対応としては、生成AIを活用しているか否かを問わず、著作権侵害に対して法的・倫理的観点から適切に行動する姿勢を示している。
生成AIをはじめとする新しい技術を拒絶するのではなく、クリエイターの努力と尊厳を守り、ユーザーの創意や遊び心を尊重しながら、双方が安心して創作・利用できる環境を整えることを重視している。
最後に今後に向けて、コンテンツ産業の一員としてクリエイターに寄り添いながら、著作物や創作物の「利用と保護」の両立を模索するため、業界内外の関係者と協調・協力し、AI 時代における公正で透明、かつ持続可能な創作環境の構築・維持に努めることを表明している。
なお、同日には集英社からも「生成AIを利用した権利侵害への対応について」と題したリリースが単独で公開されている。
こちらはアニメやキャラクターの著作権を侵害するAI作品について、「心血を注いで作品を作り上げた作家の尊厳を踏みにじり、多くの人々の権利を侵害することのうえに成立してよいはずはありません」と言及。
同社の作品への権利侵害には適切で厳正な対応を取る姿勢を表明するとともに、法整備を含め、コンテンツ保護に向けた国家レベルでの対応を求めるなど、生成AIによる権利侵害に対し、より強硬な立場をとっていることがうかがえる。