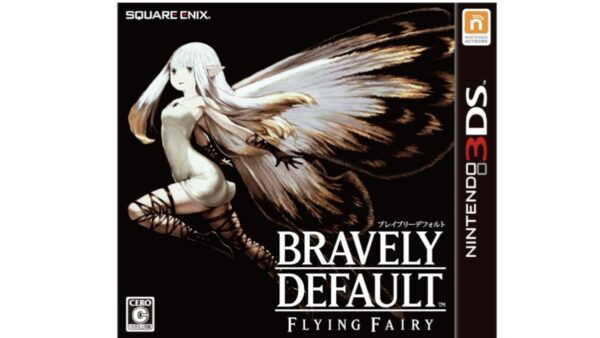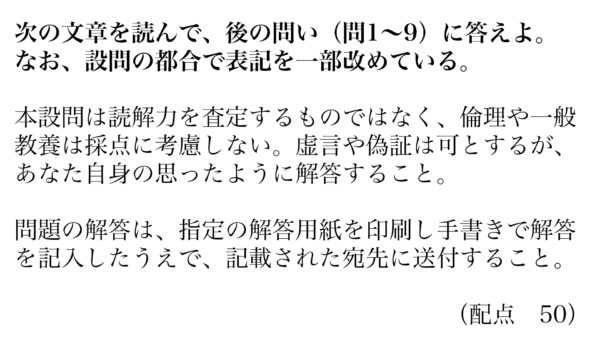「観る世代」にマッチしたスローモーション
──ここまで、『鉄拳』シリーズの近年に至る試行錯誤の歴史を伺ってきました。ここからは折り返して、近年の動向を伺っていきたいと思います。
そこでまず注目したいのが、観戦スポーツとしての対戦格闘ゲームの台頭です。YouTubeが出てきて動画を観られるようになり、現在では話題のeスポーツとして親しまれています。そうした時代の流れに対し、徹底的なアナライズをしてきた原田さんが『鉄拳』シリーズでどのように応じてきたのかをお伺いしていきたいんです。
原田氏:
直近で言えば、『鉄拳7』のスーパースローモーション演出なんかはその典型でしょうね。
お互いの体力が少なくK.O.の手前で技を出し合うと、「ブオーン」というスローモーションの演出が入るようにしたんですが、あれはものすごい反響でした。プレイ中に必ず盛り上がるので、反応を見て、我々も「狙い通りだ!」と思いましたね。
あそこで我々が考えたことは、“レイジアーツ”【※】のような、わかりやすい駆け引きのポイントを作ることです。演出を見せて「逆転しようとしている」、「起死回生を狙っている」ことをわかりやすくしたんです。

要は、みんなで一緒になって、技の入りに合わせて「ドンドドンドンドン、イェ~!」みたいに盛り上がれるようにすることで、ライブのような一体感を出せるんじゃないかと思ったんです。

『鉄拳』の場合、昔はそれが空中コンボでした。入るたびに「オイ、ウェイウェイウェイ!」と皆が言う。そして全部入るとまた「イェ~イ!」と盛り上がるんです。
──ああいう盛り上がりをシステムで生み出したスーパースローモーションシステムやレイジアーツは、確かに『鉄拳』にとって大きな変化だなと思いました。
原田氏:
しかも、じつはゲームシステムにさほど影響を与えるわけではないんですね。たまにスーパースローのせいで「本来反応できないものがガードできた」とか、「ふだん見えない駆け引きがよく見えた」というときはあります。しかし多くの場合は、どちらかがK.O.されるかもしれないときに起きる現象なので、さほど影響はないんです。
つまり演出の域であるはずなのに、あの仕様は格闘ゲーマーコミュニティのあいだでも「ものすごく革命的だ」と評価されました。
──なぜあの演出を導入するに至ったのでしょうか?
原田氏:
もともと『鉄拳4』あたりから、背景が崩れるとか、プレイ中にシチュエーションが変わるということをやり始めていたんです。
そしてじつは『鉄拳5』のときには、スローモーション演出をやりたいと思って提案していたんですが、当時は「処理的に難しい」となってペンディングしていました。そこに技術が追いついて、「いまこれを導入すれば、観客は絶対盛り上がるんじゃない?」という話になったんです。
──その気付きはどこにあったんでしょう?
原田氏:
いまや新しい世代、たとえばいまの10代やその友達をコミュニティに連れてきたとき、最初にするのは「プレイさせる」ことじゃなくて「見せる」ことなんですよ。
すると大会を見せたときも、ゲームシステムは解らないけど観戦して盛り上がることができれば、「なんかすごいことが起きている」と理解して心が揺れるじゃないですか。格闘ゲームに興味を持ってもらうには、その瞬間を作らないといけない。ストリーミングやシェア映像なども意識したゲームデザインにする必要があるとは思っていました。
 |
そのときに考えたのが、「プレイしている人と観ている人にとって、まったく同じ気持ちになれる瞬間」を作れないかということだったんです。スーパースローになると、プレイしている人も「俺のパンチとあっちのパンチ、どっちが先に当たるんだ!」と思うでしょ。それは観ている側も一緒ですよね。「どっちなんだ!」っていう感情が起きて、「ウワーッ」と盛り上がるんです。
──まさにベンチマーク路線などの例から「ガチ対戦プレイをしていない人」を見続けていた、原田さんならではの発想のように思います。
原田氏:
こういう考えかたで作るゲームって、まだあまりありませんよね。普通は、プレイする当事者、つまりプレイヤー側の気持ちよさや緊張感を第一に考えるわけじゃないですか。でも今回は、観ている人にも一緒に同じ気持ち良さや緊張感を与えたいと思ったんです。
ただ、それも観る文化が生まれたからこそです。「ライブで声が出る、もしくはストリーミング中にチャットやニコ生のコメントがブワーッっと盛り上がるような瞬間を作るにはどうすればいいか……」そんなことを意識したゲーム作りって、いままであまりこの業界にはなかったんです。
── 一方で『鉄拳』は、3D格闘ゲームの宿命か、2D格闘に比べると細かな攻防の多い、リアル……というと語弊がありますが、リアリティを感じられる方向性のゲームだったようにも思います。
原田氏:
そうですね。格闘ゲームの中で『バーチャファイター』や『鉄拳』は、ほかの2D格闘と比べると、闘いかたにちょっとリアリティがあるほうですよね。
アニメーションのコマ割りが、いわゆる漫画的な論法ではなく、重心の使いかたやスピードが2D格闘に比べると現実寄りの動きになっているのと、いわゆる2D格闘における前後のジャンプ移動はほとんどなくて、地に足をつけてクロスレンジの距離でフィジカルに殴り合うので、わりと地味なローキックだったりアッパーのようなもので勝敗が決まることもあります。

観ている側としては実際にボクシングを観戦しに行ったときのような感じを受けることもあって、盛り上がるのは「事が起きてから」という感じがありましたね。リアルなボクシングの試合だと、ものすごい接近戦で凄く小さいモーションのジャブなんかで相手をK.O.することがありますが、それが3D格ゲーの場合は、ちょっと地味に映ってしまうという。
──小パンチで勝っていいのか、ちょっと迷いますよね(笑)。
原田氏:
それをどう解消しなきゃいけないか、という課題が出てきたんですが、そのときに思ったのが、「これは明らかに、オーディエンスをどう満足させるかという課題なんだ」ということでした。これはインターネットのストリーミングという文化でも、コミュニティにおいても同じです。
──「スポーツは経験者のほうが楽しく観られる」という説があるじゃないですか。これは僕もサッカーをやっていたのでよくわかるんです。
経験者がスポーツを観ていると楽しい理由のひとつに、脳内で“時間短縮”が起きるからだと思うんですよ。ゴール前にボールが上がったとき、どんな状況でボールが上がってきたらゴールに至るのか、経験者の脳内では1秒間が100倍くらいに感じられて、シミュレーションされたりするわけです。少なくとも、記憶の中ではそうなっている。
だから「きっとこうなる。……やっぱり入ったじゃん、面白い!」という感覚が経験者にはあって、それが面白さ増幅につながっていると思うんです。格闘ゲームでも、実際に対戦中だと、体力ゲージの最後の1ミリの攻防のあいだ、明らかに脳内で時間が伸びてる感じがするじゃないですか。
原田氏:
そうですね。原理そのものはまったく違いますが、バイクやクルマで壁にぶつかるときと感覚的には一緒だと思います(笑)。スローで記憶される。
──観ている人に対してそれを演出として見せてあげることによって、そのアドレナリンが出る感覚を再現しているわけですよね。
原田氏:
この機能を思いついたきっかけは、仰るとおり、まさにスポーツからなんですよ。ひとつは、決定的瞬間のリプレイで、よくスーパースローで見せますよね。
もうひとつはアメリカのスーパーボウルの中継です。あれは完全なリアルタイムじゃなく、数秒遅れた映像を電波に乗せているんですよね。なぜかといえば、放送事故が起きたときにカットできるように。リアルタイムで流すと「しまった!」という事態が起きることがあるので、あえて遅らせているんだそうです。
それを聞いたときに「それだ!」って思ったんですよ。それがアイデアの根源でした。
ゲームだったら、今後起きることは現実よりは法則が成り立ちやすいぶん予測がつきます。現実は予測できないのであえて遅延させて中継し、慌てて編集しているんですが、ゲームならリアルタイム処理中に未来予測でできる。
この距離とこの技のもつフレームだとこのぐらいでこう当たりそう……という感じで法則が先に読めるはずなんです。ということは、そういう先読みのプログラムを用意しておき、並行して走らせておけばいい。
結果を待つのではなく、プレイ中に「それが起きる前に超スローを出す」ことができればこれはプレイヤー自身も観ている人にとっても衝撃が起きるんじゃないかと思ったんですよ。
観戦スポーツとして成熟してきた現在
──先ほどから話を伺っていると、やはり“観る文化”の台頭はやはりかなり意識して作られていると感じます。原田さんは、そうした観戦スポーツとしての格闘ゲームをどう捉えていらっしゃいますか?
原田氏:
最近すごく増えてるのが、“対戦はしないけど観てます層”ですね。ゲームを所有はするけど、ほぼ自分は競技者ではなく、人のプレイばかり観ている。この層が増え始めたため、格闘ゲームと格闘技の世界が似ていると言われているんです。
いちばんわかりやすい例だと思うんですが、UFC(Ultimate Fighting Championship)って異常に視聴率が上がりましたよね。アメリカだと、18~20代後半までの視聴割合と言われるものが、恐ろしく高かったたんですよ。
もちろんボクシングが人気だった時代もありますよ。僕らの世代だと、K-1やプライドなどの総合格闘技ブームがありましたよね。でもプロレスやボクシングはいまだに人気があって、観戦するスポーツとして集客力がある。
でもここで考えてほしいんですが、総合格闘技やボクシングなどを実際に試合を含めてやっている選手側の人間の比率って、観戦者に対して圧倒的に少ないんですよね。格闘ゲームも、この構図に似てきているんです。
──つまり、観戦スポーツとしての成長がもう始まっているということですか?
原田氏:
成長し始めている段階ですし、格闘ゲームジャンルの場合には特徴的なのは数ではなくその比率です。
たとえば観戦者の絶対数で言うと、『League of Legends』などMOBA系のゲームが圧倒的ですよ。賞金もデカいし観ている人も業界でもっとも多い部類です。

ですがMOBA系は、「観ている人=現役プレイヤー」に近い構図があって、格闘ジャンルに比べて「遊んでいる人と観ている人が非常に高い割合で被っている」というデータがあります。なぜかというと、『League of Legends』をいっさい知らない人が観戦したとしても、何がどう勝っているか、ちょっとわからないんですよ。
──その点は、格闘ゲームは大きく違いますね。
原田氏:
『鉄拳』でも『ストリートファイター』でも、細かいテクニックはわからなくても、ライフバーを見ればどっちが押してるかは一目瞭然です。
それってボクシングや格闘技の中継を観ているのと同じ構図なんですね。たとえば多くの観戦者は細かいルールや駆け引き、それからテクニックはよく解っていないし、自分はハイキックをガードしたことだってないし、そもそもハイキックなんてできない。当然腕ひしぎ十字固めひとつできない人ばっかりなわけですが、でも格闘技の試合で「何が起きているのか」ということは判る。
やはりゲームとして「操作の結果、起きていること」自体はシンプルだからですよ。
そういう意味だと、格闘ゲームのように、プレイヤーよりも観ている人の比率がここまで多いゲームは少ないんです。これは観戦するゲームとして考えたときに、大きな特徴だと思います。
観戦に目覚めた原田氏のエピソード
──ちなみに、原田さんご自身は動画などをご覧になるのでしょうか?
原田氏:
僕はもともと『ダブルドラゴン』に始まり、西谷さんの『ストリートファイター』なども大好きで、さらに鈴木裕さんのファンであり、『バーチャファイター』を作られたときには、「最新テクノロジーと流行りのゲームを組み合わせるなんて、なんてスゲーんだ」と感動したクチです。
SNKの『サムライスピリッツ』とかも大好きで、もうアホみたいにプレイしました。とにかくすべてプレイヤーとして参加していました。つまり、競技者としてたぎるものがあったんです。
 |
ただ、最近は全然違う価値観に目覚めてきて、ほぼ競技としてはやらなくなった……と言いますか、なかなか対戦する機会も減ってきたんですよ。当然勝てないし。もうこういう立場ですし、四捨五入すると50歳ですし、こうやって言い訳するぐらいプレイヤーとしての腕前が衰えています。
だけど部下や友人がいる中で人のプレイを観たり、Twitchやらニコ生などネット配信に出たりするじゃないですか。そういうところで試合を見ながら実況したり、感想を言ったりしていると、妙に楽しいんですね。この感覚って昔には絶対ありませんでしたね。
──それはひとつの変化ですよね。ゲーム楽しまれかた全体を見ても、ゲームを観ていて「語る」とか「突っ込む」とか、それらがもっている価値観が、2000年代以前とはまったく変わっていますよね。
原田氏:
数年前にふと気づいたことがあるんです。実家の親父がずっと阪神ファンなんですが、ビールを飲みながらずっと監督みたいになっているわけなんですよ。
「○○(選手)はアカン、もう交代や。相性悪いわ。今日はとくにアカン」などと言っているわけですよ。これって単なる愚痴ではなく、格闘技で言えば自分が「いまどう技をかければいいか解った。〇〇すべきだった」ということを他人に言ったりツッコんだりという、そういう類の楽しさや快感だと思うんです。
──ああ、なるほど(笑)。自分が父親の歳に近づくにしたがって、昔、父親が野球を観ながら「ここで何で出さねえんだ!」というようなことを言ってるのと同じことが起きている。ただ、それが野球でなく格闘ゲームだ、ということですね。
原田氏:
子どものころは「そこまで言うなら選手とか監督になってみなよ」と、俺は親父に対して思っていたんですけどね。でもいまなら「そういうことじゃないんだ」と解ります。
「自分が選手やプレイヤーとしてどうなのか」は棚に上げてというか、それはともかく「ああでもない、こうでもない」と解説者のごとく話しながら観るという行為がそもそも楽しいんですよ。
 |
僕など絶対に勝てないような上位プレイヤーを「あー! もったいない。いまの技はもったいないなあ」など偉そうに解説していますが、これが多くの観戦者のレベルで起きている。私はこれを「観戦者の解説者化時代」と呼んでいますが、ネガティブな意味ではなく、とにかくこの観戦手法そのものがじつに楽しいわけです。
つまりこれは逆に言うと、格闘ゲームがそれだけ観戦する楽しみを引き出せる素材なんだということだと思うんですよ。昔は自分がプレイしていなかったら「興味がない」で終わったんですけど、観戦対象として興味が湧く時代や世代がやって来た。遊ばれかたは明らかに変わっています。
──自分の「ああでもない」を吐き出す出口としてのSNSの影響も大きそうですね。
eスポーツとはまず「コミュニティ」だった
──そこでぜひ原田さんにお伺いしたいのが、こうしたeスポーツの台頭までの流れなんです。いったい、どのようにして興ったものでしょうか?
原田氏:
先ほど、ヨーロッパでの格闘ゲームの遊ばれかたの話をしましたが、その当時にアメリカでの遊ばれかたも調べてみたんです。
そこでちょっと面白かったのが、アメリカの場合、いわゆる競技者のコミュニティ、つまり団体を名乗るファンコミュニティは、なぜかゲームセンターがなくなって以降のほうが、増えてきていたことなんです。
──それは不思議な現象ですね。
原田氏:
ゲームセンターがあった時代と言いますか、ゲームセンターの全盛期には、目立った競技者の団体はなかった。それを紐解くと、つまり各地域や各地元のコミュニティの中で、競技を志向する欲求は満たされていたんようなんです。
つまり、その場所に赴けば競技者が集まっていて、そこで完結するわけですね。当然インターネットも普及していない時代なので、コミュニケーションも集まりもそれ以上拡大を見せる事はない。ですので、たとえば地元ゲームセンターに集まるコミュニティ内で誰が強いかを競い、地域のチャンピオンを決めれば、そこまでで閉じていたわけです。
しかし2000年になるころには、ゲームセンターがなくなり、彼らは拠点を失いました。それで家に籠ってゲームをするようになりましたが、家庭内で兄弟を倒すくらいじゃ物足りないわけですよ。
 |
ですから、週末にどこかへファンどうしが集まってプレイするようになった。当時はネットワーク環境が貧弱だったので、いわゆるLANパーティー的な遊びが始まり出したころだったんですよね。
それが当時のアメリカで格闘ゲームでもで起き始めていた。アメリカはその時期、急に西海岸から東海岸まであちこちで名の通った団体がいくつか現れて、競技者コミュニティができたりしていたんですよ。ある意味、アーケードという場を失った反動がそういう形で現れたという側面があります。
──ヨーロッパでは競技は行われていなかったんですか?
原田氏:
ヨーロッパとひと言で言っても、国が多いですからね。さらに各国のコミュニティも北米に比べるとかなり細分化されています。ですのでヨーロッパ全土に向けて「いわゆるトーナメント大会をやりますよ」とひと声かけたところで、1990年代当時はなかなか集まらない。
ヨーロッパのコミュニティはどちらかというと、当時はトーナメント系コミュニティよりも、たとえば日本のオタクパーティ的というか、同人誌即売会に近いコミュニティのほうが多かった。
数万人も集まるわけじゃなく、下手すると数百人レベルだと思うんですけど、どうやらコスプレコンテストみたいなものを市民会館りのようなところでやっていた模様です。さらにその当時は、そのほとんどのキャラクターが日本のゲームからなんですよ。『ファイナルファンタジー』とか『鉄拳』とか、『ソウルエッジ』や『バーチャファイター』とか。
──まさにコミケのようですね。それがわかるほど、調査の過程できちんとコミュニティの観察のようなこともしたんですね。
原田氏:
そもそもですが、国ごとにそういう異なるコミュニティがある……と気づいたのが、2000~2002年くらいのことです。EVO【※】はその前身となる小さな集まりは1995年からあったたようですが、僕らは当初じつはその動きにも気づいてなかったんですよ。

(画像はEvo 2018 Championship Series|Evo in Picturesより)
──それはどうしてでしょう?
原田氏:
その理由もはっきりしていて、競技者のコミュニティ、いわゆるトーナメント系コミュニティの発祥は時系列的にまず、2D格闘ゲームから始まって、さらにカプコンならカプコン系、SNK系はSNK系、ナムコ系はナムコ系……というように、格闘ゲームやメーカーごとに分かれていたから、日本からこの細分化された動きを1990年代当時にリアルタイムでキャッチするのはなかなか難しかったんです。そして中でも、EVOは完全にカプコン系コミュニティでしたからね。
結局、そんな経緯で対戦者どうしのコミュニティがつぎつぎできたのが、その始まりですね。早いところは1990年代後半からありましたが、多くはゲームセンターが滅んだ2000年代前半に生まれています。『鉄拳』でいうと『5』くらいの時期です。
競技団体が地域で生まれたら、今度は地域どうしでの争いや対決が起きますよね。そうして拡大していくうちに、イギリスに現れた有名な選手を日本に呼んだり、韓国に強いやつが集まると日本に呼んだり……というようなイベントが、少しずつ生まれるようになりました。
ただこのころは、まだコミュニティどうしが点のように存在していて、線には繋がっていなかった。つまり点どうしが争っているという程度でした。
──まずはコミュニティだったと。それらが線になったきっかけは何だったのでしょう?
原田氏:
暗黒の10年が過ぎて、世界に高速のネットワークインフラがある程度整って、家庭用ゲーム機に通信機能が搭載され、格闘ゲームがオンラインに完全対応されてからです。家庭用ゲーム機で言うと、Xbox 360・プレイステーション3の時代(前者が2005年11月、後者が2006年11月発売)。そのころから、格闘ゲームがもう一度見直され、かつてのアーケードコミュニティに近い、格ゲーファンの人たちが少し戻り始めたんですね。
──オンラインが点を繋ぎ始めた。
原田氏:
ええ、コミュニティと言われる集団を構成する人たちが、オンラインで対戦し始めました。このあたりから、各地の点だったコミュニティが線で繋がり始めた。
メーカーやパブリッシャー側の動きはと言うと、近年の例だと、コミュニティを線で繋ぎ始めたのはカプコンで、次いでナムコ(現バンダイナムコ)です。『ストリートファイター』のライセンスはカプコンUSAが持っていまして、その地元であるアメリカのコミュニティで起き始めていたことだけに、小野さんを含めてカプコンはコミュニティの変化に気付くのが早かった。
彼らは“カプコンプロツアー”を行い、5~10年と地元に根付いてたカプコン系、2D系格闘ゲームコミュニティを繋いでいったんです。
そして、オンライン時代になったからこそ「みんなで集まる日を何ヵ月かに一度は作ろう」という動きが逆に増えましたしね。名前の付いた大会が明らかに増えました。
──オンライン化によって再沸騰した格闘ゲームコミュニティが、企業努力に後押しされる形で、いまのeスポーツに接続されていったんですね。
原田氏:
歴史的にはおそらく、1993年にカプコンさんがやった『ストリートファイターII チャンピオンシップ’93 イン 国技館』が、ある意味で最初の大規模なeスポーツの大会じゃないですかね。じつはあそこには僕もいたんですが(笑)。
ただ、やはり格闘ゲームにとっていまのeスポーツの動きは、そもそもeスポーツではなく、コミュニティの延長なんですよ。老舗格闘ゲームコミュニティに言わせると、「eスポーツなんて騒がれる前から俺らはそういうのをやってきたし」という世界。
 |
もともとは、僕などがナムコのゲームセンターで運営していたような単体店舗の大会から始まって、それが地域連動の多店舗展開になり、今度はそれが“闘劇”【※】のようなものに繋がって、欧米では各地域でコミュニティトーナメントの動きが現れて……という流れです。
だから“eスポーツ”というキーワードは後から付いてきたようなもの。ですので当初は“eスポーツ”という言葉はできるだけ格闘ゲームコミュニティ内では使わないように気遣っていましたね。小野さんと僕はよく「格闘ゲームの成り立ちやいまの形は、正確にはいわゆる現代で言うeスポーツという形じゃないよね」とよく言っています。

(画像はInternet Archiveによる2005年11月8日の 「TOUGEKI -SUPER BATTLE OPERA-」ページアーカイブより)
現在は「いわゆるツアーのような形で点を線で繋ぎ始めたら、結果的にいまのeスポーツの流れに非常に近いものになった……」という形です。しかもeスポーツというキーワードの面から言えば、行政的な問題やゲームの社会的地位という要因もあって、日本だけこの流れに乗り遅れましたからね。
今年に入ってからもプロライセンスの話など大きな話題となっていますが、もう10年や20年とeスポーツ的な動きをしてきた側からすると、ようやくいまになって周囲がeスポーツというバズワードでもって、この世界の動きを発見したように見える。ただ、彼ら格ゲーコミュニティからすれば、再定義の時代がようやく来たという感じでしょうか。
一方で、これも現在のビジネス的な観点で見れば、大会参加者の数や観戦者の数がそのままゲームタイトルの売り上げ規模やシェアに直結しているわけではない。まだまだプロモーションの一側面の域を脱していないというところは否めないでしょうね。
──興行が収益に結びついていないと。
原田氏:
とくに格闘ジャンルだと、よくEVOの参加者数や視聴数がそのまま各タイトルの人気、つまり売り上げやシェアと直結したイメージで語られることが多いのですが、それはまったく違いますね。イメージと現実のあいだには大きな乖離があります。
前述したマニアタイプのタイトルは選手や観客などの参加率が高く、eスポーツ人口は多く見えますが、タイトルの売り上げは数万~数十万規模なので、じつはプレイヤーの絶対数が少なく、なかなか母数のシェアが伸びない。
逆に数百万規模で売れる大規模タイトルがマニア系タイトルの10倍や20倍のユーザー母数を抱えているからと言って、10倍ものeスポーツ人口を集めているかと言えばそれもない。
こういう冷静な観点で見れば、まだeスポーツ自体が、このジャンルにとってもごく一部の層のものにしかなっていないということかもしれませんね。まだまだ、これから育てていく部分なのかもしれません。
コンテンツをパーソナライズするオンライン世代
──ここで、ひとつ疑問があるんです。そうした競技としての格闘ゲームの台頭がある一方で、格闘ゲームブームが去った要因のひとつに、「構造上敗者を生み出してしまうゲーム」であったことも指摘されていたじゃないですか。これを付き合わせると、eスポーツはある一定の規模以上は盛り上がれないということに繋がりかねませんか?
原田氏:
ここで、多くの方々がしている大いなる誤解を、解いておかなきゃいけないと思うんですよ。いまから話すことは、僕がずっと統計的なデータを眺めていて俯瞰的に理解したことや、格闘ゲームを研究しているうちに「ははあ、なるほどね!」と理解したことです。
ちなみに、これまで格闘ゲームを作っている、作ってきた人々に訊いて回ったことがありますが、皆さん同意してくれた話ですね。
それは何かというと「格闘ゲームは複雑化、もしくは高難易度化したので廃れた」という大いなる誤解です。
──それは、原田さんからすると「違う」わけですね。
原田氏:
はい。格闘ゲームというものは生れたときから難しかった。言いかたを変えれば、「もともと難しかった」が正解です。少なくとも「昔は簡単だった」というのは嘘です。
それは当時のその人の絶対値でしかない、分析というより時間経過による感情的な印象論でしかないんですよ。昔はいい意味で「みんなその程度の遊びかたしかしていなかった」だけなんですよ。
──なるほど。
原田氏:
ブームの皮切りになった『ストリートファイターII』や『バーチャファイター2』を見ればわかりますが、あのあたりで出来てきたテクニックというのは、正直、「あそこでほぼ格闘ゲームは完成してるんじゃないか?」というくらい、とてつもなくたくさんあります。だから、いまでも対戦をやると恐ろしく高度な駆け引きになります。

つまり当時は、ゲーマーみんなにとって格闘は新しいジャンルだったので「みんなだいたい同じくらいの腕だった」だけなんです。戦国時代と一緒で、群雄割拠を競ってるときは面白いわけですよ。
ただ、競争はいつか成熟します。当時は単純にコミュニティが成熟していなかったわけですね。
ネットワークのインフラもなく、各地で小さなコミュニティが競うか、各家庭で遊ばれていたという時代ですから。テクニックやノウハウの共有も、月刊のゲーム雑誌の数ページをみんなが読んでいるだけという時代ですよ。
──ところが成熟したところ、見えてきたものが違ってきたと。
原田氏:
じつはとんでもない深みと頂点があって、操作の自由度も難易度も高いゲームだけど、みんなが低い山のふもとで集まっているうちは全員が楽しいわけです。
 |
ところが、このゲームジャンルの仕組みが、じつはヒマラヤ山脈レベルに高い場所を目指せるもので、「実際にチョモランマに登頂しちゃう人がコミュニティの成熟とともに現れるとどうなるか」という話です。もとのゲームに深みと頂点の高さがないと起きない現象ですよね。だから格ゲーはもともと難しかったんですよ。じつはそういうゲームだった。
──対戦格闘という仕組みの奥深さを感じます。
原田氏:
さらに小さな縮図に落とし込んで考えると解るんですが……たとえば5人兄弟がいたとします。最初は同じスタートラインで格ゲーを始めますが、だんだん腕の差がついてきます。それでも上には追いつけそうなので、下のみんなは悔しいから懸命にプレイする。プレイするので盛り上がる。
しかしあるときから三男だけが異様に研究し、寝る間も惜しんでプレイしたとしましょう。これも最初はその強さにみんな熱狂します。「すげぇな、お前ほんとに」と。しかし徐々に、何回やっても三男に敵わなくなっていきます。すると飽きます。腹も立つし、ついていけない。
でも長男だけはなんとかその三男を倒そうと頑張り、やがてこのふたりが恐ろしいレベルにマッチアップしていく。その結果、次の作品が出ても、次男や四男たちはやりませんよね? 長男と三男の恐ろしいレベルの闘いを目の当たりにするしかない。
このとき次の作品とはいえゲーム自体はそんなに変わっていないのに、見ている兄弟からは「すげぇことをやってる」ようにしか見えないのでやらない。これはゲームが複雑になったんじゃないんです。これはコミュニティが成熟したというのが客観的分析になります。それだけこのゲームにはもともと自由度と深みがあり、人間の多くの能力やメンタルを引き出せるほど高難度のベースがあったというわけです。
──別の言いかたをすると、野球と同じということですね。プロ野球や甲子園の強豪などは、きちんと数字を見ながら考えてプレイし、練習も圧倒的に普通のチームとは違う。
結果として、同じ野球と言っても30~40年前のプレイといまのプレイは別物になり、見ていると「なんて高度化した野球だ」と思うんだけれど、それは別に野球のルールが複雑化した結果かというと、決してそうではないと。
原田氏:
はい、そのとおりです。もちろんね、中にはある種の時代の寵児として、すごく複雑なゲームもありますよ。ですのでニッチな例を挙げて「複雑化している」とは言えるでしょうが、それらは特定のターゲット層に売っているものなので、統計的なデータの前では有意差に含まれないんです。
『ストリートファイター』や『鉄拳』、そして『バーチャファイター』のような、昔からある典型的な格闘ゲームは、良くも悪くも根幹のところは意外なほど変わっていないんですよ。
それどころか、入力して技が出る部分などは、どのゲームも明らかにシリーズ後半のほうがいいですからね。しかもいまはネットでなんでも情報を知ることができるし、教えてくれる人も多いし、環境そのものは黎明期よりはるかにいいわけです。
──それだけ最初期から対戦格闘ゲームは完成されていたと。
原田氏:
根幹設計が変わっていないという意味で言えば、たとえばFPSが「狙って撃つ」という根幹が変わってないのと一緒です。当然、「狙って撃つ」という行為そのものは直感的だしシンプルなので、格ゲーよりはゲームを跨いでも共通化しやすい仕組みです。
だからFPSは、ある程度ほかのFPSが現れても続編が出ても遊べますよね。FPSの場合は「もともと難しいゲームだった」というよりは、もともとが直感的なポインティングもしくはエイミングのゲームだったというわけです。
ただ、FPSもマルチプレイの場合は少し様相が違ってきています。遊べばわかりますが、もともとシンプルであるがゆえに、FPSの場合も対戦コミュニティの成熟度が近年はヤバいことになっていますね。『バトルフィールド2』(2005年)あたりでワイワイしていたころなんて再現できないぐらい、そこらへんのプレイヤーは、敵の姿を見ることなく倒されていくという。
1990年代が全盛期だったおじさんFPSゲーマーが、昔取った杵柄でマルチプレイなんかに挑むと一瞬で死にますから。『カウンターストライク』(2000年)とか、僕が初期にやっていたころとは対戦のレベルが全然違う。
──それは感じます。
原田氏:
それを指して「最近のFPSは難しい。武器も多いし複雑化した。昔はよかった」と言うのは起きている事象を正しく捉えていないだけです。
「狙って撃つ」という遊びの根幹は何ら変わらないけど、コミュニティが成熟して、昔みたいにワイワイみんなで同じように競えなくなっただけ。先に述べたとおりFPSはもともとがシンプルなので、もともとの難度が高かった格闘ゲームとは立ち位置は違いますが、重要なキーワードは同じ“コミュニティの成熟度”ですね。

逆説的に「〇〇というジャンルはゲームに進化がない」など言われることがありますが、「あらゆるゲームは、根幹的な面白さや遊びかたはあまり変わらない」という見かたもできるわけです。進化して別モノになったら、それはそれで「求めてるものと違う」となるわけでしょう? 新しいジャンルが生まれるのと進化というのは、話が違いますからね。
付随するものが生まれたり、ボリュームが増えたり、グラフィックが進化したりしても、それをもってゲームが複雑化したかというと、じつはそうではない。根幹の遊びを揺るがすわけにいかないわけなんですから。
揺るがしたら、それはまったくの別物。その場合はいわゆる発明された新ジャンルですからね。ブラッシュアップという側面での発明は多くありますが。
──ただそう考えると、いまの世代のプレイヤーは、どのように格闘ゲームを楽しんでいるのでしょうか? いまの格闘ゲームの、とくにオンライン対戦での状況を見ると、「負けるからやらない」という態度とは少し変わってきているように思います。
強者へのリスペクトのされかたも、『バーチャ』のころには鉄人と呼ばれるような現象も過去にはありましたが、それも外野から見ると、いまのプロのスタープレイヤーとは違うもののように思えるんです。
原田氏:
まず格闘ゲームって、皆さんが思ってる以上に……すごい不思議なゲームなんです。本当にスポーツに近い。私がお会いする著名な格闘家の方々も「ある意味、起きていることの構造は本当の格闘技に近い」と言うんですね。
指先の器用さや反射神経などのフィジカルな面と、知識と経験つまりナレッジとフィードバックの連続性が必要で、これは訓練と場数を積まないと絶対に解らないことが多い。それに加えてメンタルが重要です。個人の闘いなので、すべての問題を自分で背負わないといけない。自分へのイラつきとか相手へのムカつきとかなどの感情をどう制御するかで、だいぶプレイが変わってくる。
これらを「技脳体を高いレベルでひとりですべて兼ね備えないとならず、敗北をひとりで抱え込むしかないゲーム」は格闘ゲームぐらいです。だからこそ非常にしんどいゲームとも言えるんです。
逆にそれを「どう乗り越えようか」と個々にだったり、コミュニティで研究したりしていること自体が、すでに面白かったりする。コミュニティレベルは当然それぞれ違いますけどね。
──なるほど。格闘ゲームのたいへんさが、むしろコミュニティ作りの核になってるんですね。
原田氏:
しかも、じつは多くの格闘ゲームは、いまのオンライン時代を迎えたときには、もう2~3周目くらいに入っていたんですよ。その新しい世代の人は、暗黒時代のプレイヤーたちとは感覚がちょっと違う世代なんです。
──感覚がちょっと違うとは?
原田氏:
彼らは物心ついたときから、“自分でコンテンツを選ぶ”パーソナライズの文化があるんです。団塊の世代や団塊ジュニア層のように「全員がテレビを観て全員でブームを迎える」のではなく、自分の好きなものをみずから取捨選択できるインターネットインフラの中で育っている。
昔は「部活といえば全員野球部!」とまでは言いませんが、それに近いものがあって、その中で競って落ちこぼれが出る……という構造に近いものがありましたが、そうした部分での群れかたも変わりました。
 |
たとえば体育会的な大きな組織は小さくなる一方で、サークルが増えた。いやしかしサークルさえもしぼんで、さらに規模の小さな5、6人での群れかたが主流になった。そこで好きなことをやるような、パーソナライズが進んだ世代が、みずから格闘ゲームを選択してやるようになったんです。
そうなるともうブームとか関係ないんです。「たまたまお兄ちゃんがやっていた」、「友達がやっていた」などの集団属性からの情報は重要ですが、その中から自分たちで好きなコンテンツを取捨選択する世代なんです。
──なるほど。その世代はどういう特徴を持つのでしょう?
原田氏:
その世代が遊ぶときは、単なる身内だけの対戦で終わらせずに、配信したりするんです。現代は、ゲームシステムそのものよりも、ゲームの周囲のほう、ゲームを取り巻く環境のほうがよほど複雑化していて、いい意味でできることが増えている。
発信できて、それに対しフィードバックがあって、プレイヤーどうしのあいだで「あの人のファン」という関係もできてくる、いわゆるアーケード時代の名人や鉄人とはまたちょっと違う注目のされかたをプレイヤーがされる世代になってきていると思います。
──格闘ゲームには、キャラクターやストーリー、『鉄拳』で言えば三島家がというものがありますが、いまや主役は圧倒的にプレイヤーコミュニティになっている?
原田氏:
パッケージゲームとしての価値を考えると、カジュアルなオマケモードだったりムービーだったり、ストーリーだったりも、いまだに重要視されていますよ。
たとえば、単純に格闘ゲームとしての完成度で言えば、『鉄拳』シリーズでは、圧倒的に『鉄拳タッグトーナメント2』(2011年)の評価が高いんです。コアなトーナメント系コミュニティからの支持が高いわけですね。

しかし、一方でやっぱりストーリーモードが搭載されている『鉄拳7』の方がずっと売れていて、『鉄拳タッグトーナメント2』が2~3年かけて達した売り上げを、ほんの1ヵ月で抜いてしまっている。必ずしも求められるものは勝敗を決める要素だけじゃなくなったんですね。
──それは顕著ですね。格闘ゲームであっても、それだけ格闘以外の部分で求められている傾向があると。
「勝敗」のない対戦格闘の楽しみかた
──それを考えると、つまり単純な勝敗だけではない、多様な楽しまれかたが生まれてきているとわかります。たとえば、皆で麻雀を楽しむときって、負けても別に恨んだりはしませんよね。そんな感じの楽しみかたに変わっていっているんですかね。
原田氏:
それについても、売れかたを調査して判ったことがあります。格闘ゲームの中でも『鉄拳』の売り上げの多くを支えてくださっている人たちは、世界一になるつもりもなく、リージョンのトップになるつもりもなく、別に世界的なトーナメントで一位取りたいなんてそんなに思わない。
ただ、「あいつより強ければいい」。たとえば、「仲間と競えればそれで面白い」、「お兄ちゃんだけ倒せばいい」など、そんな属性なんです。
──ああ、強さの高みを目指しているわけじゃないんですね。
原田氏:
『鉄拳』にしても格闘ゲームの最前線として競っている人は、EVOに代表されるような大会にやって来る数千人の世界です。この層はいわゆるコア層の代表ですね。ただ数は多くない。無論、決勝だけでなく予選参加の数からカウントすると、結構な数にはなるのですが、それでもやっぱり、客観的にデータを並べればそのゲームの実態が見えてくる。
トーナメントに選手としてエントリーするのは数千人。予選など合わせて延べにした数でも1タイトルに対して年間で数万人です。ですがたとえば『鉄拳』などだと、売れている数で言えば、現在でも世界で各タイトルごとにライフタイムで300~400万本は売れるわけです。
では残りの9割以上は何を目指しているのかというと、ひとりで満足する人もいますが、多くは、「オンライン対戦でちょっと腕を試したい」という感じなんです。
たとえば、中高生のころぐらいだと、自分の闘争心の出口として身体能力を試したくなるわけですよ。そこに格闘ゲームがマッチする。要は試すこと自体が目的だったり、先ほど言ったように、身近な誰かを超えたいだけだったりするんです。ちょっと『鉄拳』のストーリーに似ていますよね。「親父さえ殺せればいい」という(笑)。
──(笑)。
原田氏:
このへんの事情はゲームによって大きく変わります。たとえば僕も最近よく遊ぶ『ギルティギア』を例にとると、「売上本数に対して競技者の割合が非常に高い」ということがわかります。大会参加率という切り口で言えば、ジャンル屈指の圧倒的な数字となるわけですよ。それから時間経過に対しての継続率も高かったりする。私の分析では、非常にこう、コアで尖った客層を集めるタイトルと言えますね。
(画像は公式PlayStation™Store 日本|ギルティギア 復刻版より)
このようにタイトルによって客層の傾向がそれぞれあって面白いですよ。それはすなわち「各タイトルごとの魅力が何であるか?」を示すひとつのデータになります。
客観的データを眺めながら分析すると、思っていたイメージや一般に語られる印象論とは違う事実が見えるタイトルもあります。すべてのタイトルでこの統計データを並べていくと、逆に『鉄拳』がどういう戦略でこれまでやってきたかも読み取れて面白いですよ。
少なくとも僕はこういう統計データというバックボーンを持っていて、その分析から競合タイトルを把握しているというわけです。実際には分析内容はもっと多岐にわたりますが。
格ゲーは世代交代している
──ここまで、暗黒の10年を経た『鉄拳』シリーズの変化をお伺いしてきましたが、シリーズを続けていくうえで意識したことなどはありますか?
原田氏:
幅広い客層をというのはベースにありつつも、もうひとつのキーワードが「世代交代」という事実です。
それは、いつまでも1990年代に支持してくれたおっちゃんたち、当然そこには僕も含まれますが、年齢にして40代を迎えたゲーマー層が、いつまでも格闘ゲームを支持してくれるわけではないということ……たとえば「30代半ばや後半で格闘ゲームからは離れてしまうかもしれない」という現実と向き合う、ということです。
そういうことを言うと、「オールドファンを切り捨てるのか!」とよく言われるんですが、そんなの当然切り捨てたいわけがない。
これは間違った伝わりかたをしてほしくないのですが。客層としては、横に広がる層も視野にありますが、シリーズが存続する強いゲームタイトルは、いわゆる“縦の層”、つまり世代をまたいで客層が縦に広がっているほうが当然いいに決まっていますからね。
ただ、あらゆる統計データを見てきた僕らから現実を言わせると、格闘ゲームはRPGと違って、環境の変化や年齢のせいで辞めざるを得ないゲームなんです。自分自身もそうでしたが、素早く反応できないとか、闘争心の衰えなどが起きるわけです(笑)。本当に、人間って心身の衰えとともに闘争心が衰えるんですよ。
──(笑)。解ります、はい。
原田氏:
だから格闘ゲームというのは、世代交代を意識せざるを得ないジャンルなんです。そして、世代交代に失敗したらゲーム自体が消えるんです。だから『鉄拳』は世代交代を意識した戦略をあちこちで採っていますね。
ここだけ切り取るとまるで世代交代に備えた戦略に聞こえるかもしれませんが、『鉄拳』がこれだけのシェアを得ているのは、逆に「世代や客層を広く跨げるようにしている戦略も持っているから」ということでもあるんです。
そういえばこのあいだ世代間ギャップを感じる面白いできごとが……。『鉄拳7』にギース・ハワードをダウンロードのコンテンツとして追加するとEVOで発表したときのことです。会場はもう割れんばかりの歓声なんですが、「イェ~ス!」と立ち上がって絶叫してる群衆が、どう見ても30代半ば以上、下手したら40代の人たちなんですよ(笑)。
──(笑)。
原田氏:
逆に10代の子などには、ポカーンとしている人もいたぐらい。「スミマセン、あれ誰ですか」なんてことを言ってググっている子もいましたからね(笑)。
SNKの方からも似たような話は聞いていたんですが、彼ら10代の若い世代は我々30代40代が持っているような格闘ゲームに対するノスタルジーはないわけですよ。あの光景を見て、「やっぱり世代ギャップは存在するな」と改めて思い起こされましたね。
──格闘ゲームが世代交代を余儀なくされるジャンルであるというのは、アーケードの衰退やeスポーツの隆盛など、時代の変化に応えてきた原田さんならではの認識のように思いますね。