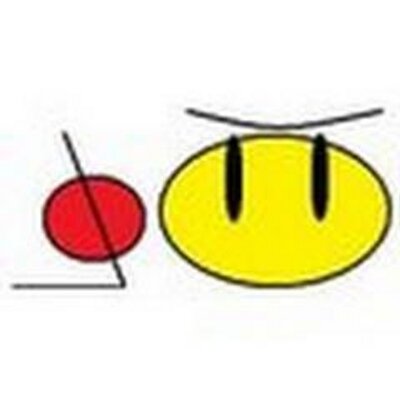高みにのぼることが最終目標ではなくなった
──今日お話をお伺いしていて、『オウガ』開発時に自分のクリエイションに絶大な自信を抱いていた松野さんと、いま目の前でそれを自嘲している松野さんのギャップが不思議なんですが……。その変化は何からきているんですか?
松野氏:
絶大な自信はもともと持っていませんよ(苦笑)。ただ、クエスト時代、最初の1年は企画の上司がいたんですけど、その方は退職してしまい、自分が企画のトップになった。
ほかのスタッフが支えてくれたからこそ『オウガバトル』2作は作れましたが、ゲームプランナーとしての力量には不安を抱えていました。
そこからスクウェアに29歳で入って経験した世界は大きく違っていて、「やはり自分は所詮、井の中の蛙だったな」と思いましたね。
──視野が広がって良かったということはなかったんですか?
松野氏:
伊藤裕之さんと出会ったときに、良くも悪くも「自分の殻が破れた」という感じは覚えたんです。成長する機会だったし、学ぶ機会だった。『FFT』もディレクターを務めましたが、ゲームプランナーとしては「まだまだダメだなあ」と。

こんなことを言うと「ネガティブすぎる」、「自己評価が低すぎる」と言われるでしょうが、ひとりの人間が自分の感性で判断して作れたのがクエスト時代。僕はその中で早い者勝ちを狙って、評価を得ただけ。
単にそれだけのことでして、ゲームプランナーとしてやっていくには実力不足だったことをスクウェア時代は痛感したんです。
──とはいえ、この企画書に現れているクリエイティビティというのは、まさにゲーム開発・運営の最先端で世界を相手に勝負している吉田さんも、いまなお「プランナーの教科書」というレベルですよね。
松野氏:
当時はともかく、いまとなっては何の参考にもならないのではないかと。いままさに『FFXIV』を作っている吉Pなら誰よりも理解していることだと思いますが、2000年代以降、もうメジャータイトルのゲームはひとりの人間の感性では作れない時代に突入しています。
ゲームをワールドワイドに展開するようになってから、世界中のさまざまな地域ごとにユーザーの反応は違ってくるわけで、そのため、クリエイターに求められるもっとも重要な技能が、“特定の地域に縛られがちな自分の感性に頼らずに、データを調べ上げてニーズを見極め、ゲームの内容に取捨選択して吸い上げる”という、いわばキュレーション能力に変わってきている。
吉田氏:
それは事実ですね。国によって感性も違うし、文化も違います。
たとえばRMTはその典型だと思います。韓国では、グローバル版と同じように業者に対してのヘイトは高いんです。
ところが“自分が人の何倍もの努力をして得たアイテムをほかのプレイヤーに何倍もの金で売る”のは比較的許容されていて、それを規制するとむしろ総スカンを食らうこともあります。
逆にアメリカのように、「業者にやられるくらいなら運営側でRMTをやろう」とする地域もありますし。もちろん『FF』というブランドである以上、「RMTは絶対にアウト」というグローバル版のポリシーはありますが、その市場が成長してきた文化によって一概に断罪できないという現実もあるんです。
松野氏:
僕が吉Pをリスペクトするのは、彼がいまのようなことをすべて解ったうえで、自分たちのポリシーを決め、第一線でしっかり運用しているから。
もちろん彼の下に多くの有能なスタッフがいるのも知っていますが、やはりプロジェクトリーダーとして運営し続けることはスゴいことだと思います。
さらに言えば、僕は吉Pに対して「悔しい」という気持ちが強い。
──吉田さんに対して悔しい?
松野氏:
素直に『FFXIV』が面白くて、面白さを競う人間として「悔しい」としか思えないからです。
クリエイターとしては、小島さんや宮本茂さんが作っているゲームにしてもえらく面白くて、「何だろう? この人たちは」と思うところがあるじゃないですか。
「自分がやって面白いと思ったゲームを作る人には憧れる」といったほうが正しいかもしれません。
吉田氏:
その気持ちがなくなったらクリエイターとして終わりだというのは解りますが、たとえば松野さんがいた時代に僕が代わりにクエストにいて、皆川さんや明彦さんがいたら、「じゃあ『タクティクスオウガ』が作れたか?」と考えますよ。
自分がこれまでさんざん失敗したうえでいまの状況に至ることを考えたら、絶対に作れない。
──だとすれば松野さんは、いまの時代でご自身はどうあろうとお考えなんでしょう?
松野氏:
もともと広告代理店に行きたかったような人間でもあるし、時代の流れはずっと意識しています。新しい情報と、その時代の「主流をなしているものは何か」ということはいつも考えている。
だけど大きな会社を離れてからは、もう確固たるマーケティングデータがないから、最後は勘頼りになってしまう。そこに強く危機感を覚えています。
とくに海外についてはまったくデータがない。ニュースサイトなどで知る情報しかないので、その意味では一般消費者と何ら違いはありません。
ところが吉Pは海外を飛び回ってプレイヤーたち、現地のスタッフやメディアと触れ合っているから生の情報を持っているわけで、『FFXIV』のストリーミング放送を見たほうが全然勉強になる。これは、あながち外れていないはず。
吉田氏:
でもだいたい、日本の場合とくに好みが多種多様化しているし、判断に正解なんてないんじゃないですか?
僕も人に訊くことはあるし、データも見ています。ですが最後は「俺はこう思う」と判断するしかなくて。「自分と同じ価値観の人が何割程度いるのか」は、売れているゲームのラインナップから調べてはいますが……。
そういったものから、「これぐらいの予算だったら、まあまあ赤にはならないかな」というような判断をしています。
でも、赤字を出したら次のゲームは作れないでしょう。そういう話でいいのではないかなと。
松野氏:
本音はそうでしょうけど、吉Pは「僕は10年後のMMORPGを見ていますよ」ぐらいは言わなきゃいけない立場では?(笑)
吉田氏:
夢も希望もない答えになりますけど、10年後のMMORPGは全盛期まではやはり戻らないかなと思います。過去にも『ソードアート・オンライン』のプロデューサーの方と対談する機会をいただいたんですけど、「10年後どうなっているか?」と訊かれてそう答えましたし……。
 |
やっぱりオンラインゲームの中でもとくにMMORPGは難しい。「初めてプレイした人に取っつきやすく」という概念と、「もうすでに成熟したプレイヤーたちに向けて」という施策を同時に考えないといけない。
だいたいゲームを作っている人で、自信に満ちあふれている人は見たことがないです。それこそ僕もそうですが、精一杯強がってみせるだけで。
松野氏:
先ほど「現代のプランナーに求められる能力はキュレーション」と言いましたが、歳を取ると、目も肥えて、自分の感性をベースとしてキュレーションすることがおこがましくなってくるんですね。
だから最近の僕はもう、ゲームを作りながら若いスタッフに「どう思う?」と意見を聞くようにしています。
ところが、そうすると「そんなのは松野さんじゃない」と言われることがあって、だんだん作ること自体が面倒くさく感じてしまう……。
──それは憧れの松野さんに聞かれたら、そう答えてしまう若手の気持ちも解りますよ(笑)。みんな松野さんの作家性に憧れて松野さんのスタッフになっているような人々なんですから。
松野氏:
作家性ですか……。よく言われますけど、自分のことを作家だと決して思っていませんね。
宣伝的な立場から“作家”と名乗ることがあったとしても、心底、作家だとはまったく思っていない。
吉田氏:
いやでも少なくとも、僕は松野さんに“松野ゲー”を求めていますよ。松野さんにしか作れないゲームってあるんです。
松野氏:
逆に聞くけど、吉Pは自分のゲームに自分らしさを求めている?
 |
吉田氏:
いや……僕は楽しんでもらって、結果として売れればそれでいいですね。
松野氏:
そうだよね? それ以上の何を求めるの?
吉田氏:
でも、僕はいまの日本には『オウガ』のような硬派なゲームが少ないとも思っているんです。
松野氏:
そこは真逆の意見でして……。
スマホのゲームが主流になっているいまの市場で、「作家性なんて誰も求めてないなあ」と。コンシューマーにすら求めなくなっている気がします。僕自身もスマホゲームにそれを求めていないし。もちろん、作家性の強い小島秀夫さんや上田文人くん【※】の新作が出たら真っ先に買い求めるけど(笑)。

(画像はプレイステーション® オフィシャルサイト|人喰いの大鷲トリコより)
──いつから「ゲームは作家性を求められていない」と考えるようになったんですか?
松野氏:
一部のゲームファンが「作家性」と言っていた時代もあったでしょう。でも、実際に市場でゲームを待っている何十万、何百万という人たちからしたら、「作家性なんて求めていない」というのが現実でした。
正確には「求めていない」のではなく、「それを意識したことがない」ですね。吉Pもそう思うでしょ?
吉田氏:
はい、僕もそうですね……。『ドラクエ』だとしても、数百万人のお客様の中で、堀井さんの名前を知っている方はそう多くはないと思います。
松野氏:
きっと宮本さんの名前だって大半の消費者は知らない。世間でゲームは、いまだにサブカルチャーのヒエラルキーの下のほうにある。
そもそもゲームに作家性を求めたのだって、監督主義指向の強い映画に倣ってメディアが作った幻想でしょう。そうやって特集を組めば売りやすいから、そういう時代を演出したに過ぎなくて。
 |
たとえばお化け屋敷にだって、業界では有名なクリエイターがいるわけなんだけど、お客さんはそんなことに関係なく、面白ければ来るわけです。ゲーム市場も同じなんです。
吉田氏:
そこはまったく同意します。面白さもプロが仕事をしただけで、「誰がやったか」なんてことは、お客さんには関係ない。
松野氏:
そう、大切なのは「あのお化け屋敷はスゴかった」と思って帰ってもらうことだけ。それに比べれば、正直なところ、作家性なんてじつにくだらない話。
そもそもゲームは集団で制作するもので、メディアのような表舞台では個人が背負ってるかのように語りますが、実際はそうじゃない。多くのスタッフの力を結集してこその商品ですから。
──どなたかに代表して全体像を語っていただかないと、その全体像を知りたい人たちへ情報が届きにくいですから、そういう形になりますよね。
吉田氏:
ストリーミングの生放送をはじめ、『FFXIV』のさまざまな場所で僕が前に出るのも、誰かを立てたほうが便利な状況だったから厄介なことでも引き受けたつもりなんです。
実際は、名前の挙がらないスタッフたちの血の滲むような努力でゲームはできあがっています。
ただ……そうそうありませんが、中心にいる人間に魅力があると、個々の才能が一点に集中する瞬間が訪れて、生み出されるようなものってありますよね?
松野氏:
それはどういう意味でしょう?
吉田氏:
たとえばスタジオジブリにも、宮崎駿さんを支える多数のアニメーターやスタッフがいる。
でも、そこにそうやって人が集まるのは、それだけ創作物や言動に魅力があって、「この人となら面白くなるに違いない」と思える人がやっぱり中心にいるからだと思うんです。
それで言うと、僕らゲーマーにとって松野泰己という存在は、唯一無二のもの。そもそも“松野ゲー”と呼ばれるジャンルがゲーマーのあいだにある時点で、もう尋常じゃない。
 |
だから僕らからすると、松野さんにいなくなられたら困るんです。同時にその期待を押しつけることで松野さんが作ることを面倒くさがっても厭なんですが(笑)。
松野さんが作るゲームを待っているプレイヤーはたぶん、「いいッス、俺らはずっと待つんで。納得いったら出してください」というスタンスだと思います。
松野氏:
そうかなあ(苦笑)。
MMOもスマホも、結局はサービスインしてからずっと作り続け、売り続けるわけで、それは個人を売りにするような性質のものじゃない。
だから、吉Pがいうところの作家性の強いゲームはインディーズとかでしか生き残れない。小島さんや上田くんらはもう別格だから。
吉田氏:
それも状況としては解ります……。でも松野さんは、それを「悲しい」とは思わないんですか?
松野氏:
悲しいというか、もともとゲーム市場はそうしたものですし、ディープなファンがクリエイターを追いかけていくことは今後も続く。それ自体は変わらないと思うけど、以前のように「個を中心」とした宣伝は古い手法だなとは思います。
 |
そもそも吉Pは、そういう時代に『FFXIV』のようなコンテンツを見事に育てて、いまに至るわけじゃない? あなたは僕を尊敬しているというけど、僕こそあなたを尊敬せざるを得ない。
百人単位の規模の開発者を動かしていくのはとてつもない能力が必要だし、そうやって生まれたあなたのゲームが面白いから僕は遊び続けているわけで。
吉田氏:
でも……そういう話を聞いていると僕はちょっと悲しいんです。それはやっぱり、僕が松野さんの作ったゲームに感銘を受けて、そこから勉強してここまで来ているから。
僕は、むしろいまの時代こそ松野さんのような開発者が求められていると本気で感じています。
松野さんも業界に入るときに、「楽しそうだな」と思って入ったわけじゃないですか。
松野氏:
まあ、それはそうですが(苦笑)。
吉田氏:
「リアルよりも楽しい世界がそこにある」と思ったから没入したわけで、それこそが憧れの元になったりするんだと思うんです。その連鎖もエンターテイメントだと思うんですが。
松野氏:
まとめかたがうまい、さすが(笑)。もう、僕の話はいいんじゃない? ちょっと話し過ぎた気がします(笑)。
それより『FFXIV』でこれだけの成果を残している吉Pが、今後どんなゲームを作っていきたいのかを聞かせてください。そもそもゲームなのか、その先のエンターテイメントなのか。
吉田氏:
いや、僕の場合は単純にアメリカに勝ちたいというだけで……。グラフィックスの質でも、オープンワールドの空間作りでも、シームレスの技術でも、すべてにおいて。
松野氏:
それは頑張ってなんとかしてください(笑)。
それより、あなたは最後に何を目指したいのでしょう? たとえば、少なくとも(映画制作を手がけていた90年代終盤)ハワイ時代の坂口さんが目指していたものは明確で、彼にとってゲームは過程でしかなくて、映画がすべてだった。とても明快でしたよね。
 |
吉田氏:
うーん……僕は自分が作りたいものを作るのが楽しければそれでいいです。外したり当たったりはどうでもいい。ただ稼がないと次が作れないので、そこは頑張りますが。
松野氏:
じゃあ『FFXIV』も基本的に仕事だから、「せいぜい楽しくやっている」という感じ(笑)?
吉田氏:
『FFXIV』は……最終的に自分から手を挙げましたが、やりたかったものをそこに投影したかと言われると、そうではないです。『FF』シリーズですから。
でも「やる」と決めたから、「こうすれば勝てるかもしれないな」と、それに合ったゲームデザインやマネジメントなどを一生懸命に考えながらやっているつもりです。
松野氏:
でもいずれ『FFXIV』から離れるときは必ず来るわけでしょ?
そのときに、吉Pがディレクションも含め、クリエイターとしてガチでゼロから作った作品を見てみたいですね。吉田イズムが発揮された作品であり、商品でもあるようなゲームをね。
真価が問われると思うけど、課せられたハードルをあなたはたぶんめげずに超えると思うし。
──それって松野さんが吉田さんに「作家性」を問うているように聞こえるのですが……。
吉田氏:
うーん……松野さんにその言葉をいただけるのは嬉しいけど、やっぱり僕にはそういう意味でのクリエイターとしての使命のような目標はないです。
僕はずっと、松野泰己という強烈な作家に憧れてきて、いつか松野さんみたいにオリジナルで勝負をして、中高生の一生のトラウマになるようなゲームを作りたいと思っていたんです。でも、いまはちょっと違うんです。
──それは何があったんでしょう?
吉田氏:
いまでも忘れられない出来事があって。
『ドラゴンクエスト モンスターバトルロード』を作っていたとき、子どもたちによる全国大会を開いたんです。そこで子どもが優勝する。するといっしょに来ていたお父さんやお母さんがやってきて、家族で泣くんです。
その光景を見たときが、僕の中で松野さんのような作家への憧れに、ひとつ区切りがついた瞬間でした。
というのも、「ああ、自分には作るものの題材は関係ないんだな」とそのときに気づいた。「自分のゲームをプレイした人が楽しい思いさえしてくれれば、自分はそれで構わなかったんだ」って。
それ以来、僕は「作らなければ」と使命のように思う題材はなくなりました。いま『FFXIV』を続けているのも、結局は「みんなが楽しんでくれているのが楽しいから」というのが最大の理由です。
──「サービス」に徹する道に目覚めたんですね。
松野氏:
……なるほど。
まあ20代のときには目標とする人がいっぱいいて、「同じ立場に行きたい」という飽くなき欲求が僕にもありました。
でもこの歳になると僕も吉Pといっしょで、「別にそれが最終目標じゃないな」と思うようになりました。
最近はTwitterやFacebookでお客さんと繋がっていると、もちろん辛辣な意見も多いし、ヘコむことも多いんだけど、繋がっていること自体がスゴく楽しい。お客さんに喜んでもらえるものを何歳まで作れるか判らないけど、「作れる限りは作っていきたい」と思うようになりました。
 |
自分ではそれを肯定的に捉えてるし、いろいろな人との出会いが視野を広げてくれたことには感謝しているんです。でも、もう「自分であそこまで尖ったシナリオを書くことはないんだろうな」とも思います。
あのころの自分と違って、ほかの人のゲームも素直に楽しめるようになったし(笑)。
昔はやっぱり傲慢だった。「自分が作るゲームがいちばんいい」と思っていたから。最近はそうではなくて、人様が作るゲームがいちプレイヤーとして楽しめるので。いま、こうやってゲームの話をしているのが楽しいと思うようになりましたね。
──お伺いしていると、松野さんご自身は語られていませんが、『FFT』から20年が経ってラムザの抱えていた葛藤に決着が着いたからこそ、今回のコラボに至れたのかもしれないと考えてしまいます。
なぜコラボの題材は『FFT』なのか
──そういう境地にたどり着いたおふたりが、いま『FFXIV』でいっしょにコンテンツを作られているわけで、これはおふたりの関係性を知っているファンにとっても、それぞれの作品のファンにとっても、待ちに待っていたものです。
松野さんに憧れていた吉田さんは、どういう心持ちでコラボレートをお願いしたんでしょうか?
吉田氏:
以前に松野さんとお食事をしたときに、松野さんは冗談だったのかもしれませんが、「吉Pなんかちょっと書かせてよ」と言った言葉尻をつかまえて、2015年の夏ごろに「やりましょうよ、ぜひ」とお願いしたんです。
候補として8人で挑む高難度のコンテンツと、24人で楽しむ賑やかなコンテンツがありましたが、「どちらかいいですか?」と訊ねたときに、「だったら自分は多くの人に楽しんでもらえる24人のほうがいいかな」と松野さんから返事をいただいたのがいまの形に繋がっていますね。
松野氏:
もともと『FFXIV』はキャラクターにしてもダンジョンにしても、「『FF』シリーズのさまざまな要素をオマージュとして盛り込んだテーマパークである」という方針を聞いていたので、そのときに3つ提案したんですよ。
ひとつは『FFT』、もうひとつは『FFXII』。どちらも舞台となっている、いわゆるイヴァリースと呼ばれる世界を拡大したもの。最後のひとつはオリジナルの何か。「どれがいい?」と訊ねたら、「『FFT』がいい」と即答されたので、じゃあ『FFT』でやりましょうとなりました。
吉田氏:
そうですそうです。
松野氏:
引き受けたあと、吉Pからもらった資料の中に世界地図があったんです。いまゲーム中で公開されている地図は一部が雲で隠れているんだけど、僕がもらった地図は雲がまったくないもので、そこに『FFXII』の舞台、ダルマスカの名前が書いてあって(笑)。

そういえば『FFXIV』の冒頭で、プレイヤーの仇となる帝国軍人が兵士に「お前の出身はどこだ?」と聞くと「ダルマスカです」と答えるシーンがあったなと思い出しました(笑)。
それは単純に開発スタッフの遊びだったんだろうけど、ちゃんと地図にも書かれていたなら、「『FFT』だけでなく、『FFXII』までうまく絡めたシナリオができないか」というのを考えたんですよ。
「いかに『FFXIV』の世界観を壊さないように、イヴァリースを溶け込ませるか」をいちばんに考えての作業でしたね。
──先ほど、吉田さんが「『FFT』と即答した」というお話がありましたが、その理由はなんでしょう? じつはそれって、作家性に紐づく何かだったりしないかと妄想するのですが。
吉田氏:
公開が『FFT』の発売からちょうど20年だったのと、『FFT』の話の続きが、松野信者のひとりとして見たい気持ちが強くて……。
そもそもあの世界には、「ラムザという“もうひとりの英雄”と呼ばれている人間が実在したのかどうか」という歴史上の謎があって、松野さんがその後を描くのか、それとも当時の物語の背景を描くのか、ファンとしては「どう考えても面白くしてくれるだろう」という期待しかなかった。

『FFXII』は「また別の機会にお願いできるのかもしれない」と思えば、イヴァリースアライアンス【※】の発端である『FFT』がいいのかなと思ったんですよ。
──『FFT』をいま書くとなったときに、過去の作品が内包していたいろいろなテーマが挙がったと思いますが、今回で松野さんが狙ったものはなんだったのでしょう?
松野氏:
まず短編なので、「『FFT』が持つすべてのテーマを放り込むのは無理」と考え、かなりバッサリ切りました。そもそも『FFT』を作り直すわけでもないので。
吉Pも言うように、今回は「プレイヤーキャラクターだったラムザの物語などなかったかのように、そのライバルであるディリータの物語だけが伝わっているイヴァリースの歴史」の真相を、物語の中からちゃんと追おうというアイデアが発端です。
「ラムザが実在したかどうか」を追うのが、今回のシナリオの核。最後は「そのラムザがどうして歴史の闇に葬られてしまったのか」、そしてそれを「ディリータがどう考えていたのか」ですね。……これ以上語るとネタバレになっちゃう(笑)。
吉田氏:
やめましょう!(笑)。
『FFT』はシミュレーションRPGというジャンルの中でも、とりわけエピソードもテキストのボリュームも多いもの。
それによって世界や人物、そのほかの設定を、余すところなくちゃんとゲーム体験として伝えているから名作なんだと思います。
僕個人としては、コンテンツをクリアしたあとに、遅筆な“異邦の劇作家”【※】が語ってくれる部分がありますよね。そこがイヴァリース、そして松野さんが好きなプレイヤーにとって最高のご褒美だと思っています。僕は読んでニヤニヤしました(笑)。

松野氏:
あれは開発スタッフの皆さんには申し訳ないけど、ギリギリで押し込みました。パッチ4.1のアップ直前だったというのに(笑)。
吉田氏:
でもあの話をあのBGM【※】の中で読めるのはファンにはたまらないと思いますよ。
※あのBGM
コンテンツプレイ中の道中に流れるのは『FFT』のバトル曲『Trisection』、中ボスは『橋上の戦い』、ラスボスは『Ultema The Nice Body』。いずれも現ベイシスケイプ代表取締役社長の崎元仁氏の手による。
松野氏:
今回『FFXIV』に参加して思ったのは、「吉Pはスタッフの個性やクリエイティビティを活かすのがとても巧いな」ということ。プロデューサーやディレクターならそうするべきなのは当然だけど、とにかく巧い。
僕と関わっているスタッフたちも、質問に対するレスポンスが速いし、否定は否定でハッキリ言ってくれる。ゴニョゴニョとしたごまかしがまったくない。
 |
「きっとこれは『FFXIV』チーム全体がこうなんだろう」と想像するに難くなく、「うまくいっているプロジェクトチームというものは、こうなんだな」と感じるところがあります。
その中心あるいは頂点に吉Pがいて、彼がたぶんそういう空気を作り、それがチームリーダーに伝達され、チームリーダーもそういう空気をコピーしてスタッフに浸透させている。
実際にできあがったコンテンツを見てもよくできていると思うし、面白い。
プロデューサーとして人を大切にしているだろうし、ノセることも巧い。「あまり否定から入らないんじゃないかな」と勝手な想像をしています。
──組織論に近いお話ですね。
吉田氏:
とくに今回スタッフが楽しくやれている要因は、やっぱり松野さんの作ってきた作品のファンが多いからでもあります。
僕らは松野さんが作ってきたゲームで育ってきて、いま自分たちもゲームを作っている。
同じような松野さんのファンの方たちを「僕らのせいでガッカリさせたくない」ということと、「松野さんに褒めてもらいたい」という動機がある(笑)。
 |
同時に、松野さんってやっぱり僕らの中では憧れの対象なので、僕に対してさえ一歩引くような若い子たちは、「自分が話すひと言や、渡す資料ひとつでも失礼にあたるんじゃないか」と結構ためらっているんですよ?(笑)。
だけど仕事は仕事で真正面からいかないと失礼なので、頑張っているんだと思います。
松野氏:
そうやって優秀なスタッフを使わせてもらってゲームを作るのはラクで楽しいですね(笑)。
しかもリスクをすべて吉Pが背負ってくれるから、僕は今回、非常に心地よくノセられています(笑)。
吉田氏:
(苦笑)。
逆に僕からの感想ですが、過去の同様なコンテンツの資料を全部渡して、「作るのに使えるコストは、これしかありません。この中で収まる物語でお願いします」と依頼するとピタリと収まってくる。
松野さんの仕事は脚本に目がいきがちですが、「その箱の中にいくつのブロックとエピソードを入れれば収まるか」、「これ以上に盛ると伝わらない」などの見極めが最初のプロットから完璧だったので、やっぱりゲームデザイナー、プランナーとしてのスゴさをあらためて感じました。
──コスト以外で吉田さんから松野さんに注文を付けることはないんですか?
吉田氏:
たとえば劇場飛空艇に名前を付けるとき、「プリマビスタにしたら、シリーズを混ぜすぎかな?」と松野さんが迷っていたときは、わりと即答で「プリマビスタで大丈夫です」と言いました。

松野氏:
劇場艇を提案したのはもちろん僕なんですが、プリマビスタは『FFIX』に登場するものなのはご存じのとおり。
『IX』のファンからすると「イヴァリースに関係ないのに登場させるなよ」というような炎上だってあり得ると思ったので迷いました。
吉田氏:
それは逆に「劇場艇なのになんでプリマビスタじゃないの?」という人もいるだろうなと思ったので、そこは大丈夫と答えたんです。
それを言うなら、『FFXIV』にはエンタープライズ(『FFIII』の飛空艇)もすでに登場しているわけですし。

松野氏:
そういう意見や判断が欲しいことは、つねに吉Pも含めてメールで問い合わせて、その都度回答をもらって作っています。
これは翻せば、そういう質問をされたほうがディレクションがしやすいから。だから吉Pやスタッフが判断しやすいような質問を極力投げるようにしています。
吉田氏:
それは松野さんが、いわゆる単純な脚本だけではなく、システムやルール設計からするゲームデザイナーだから、ディレクターだし、プランナーだからできることだと思います。
『オウガバトル』には3作目の企画があった
──そろそろまとめにかかります。しばらくコラボは続きますが、吉田さんは『FFXIV』の開発と運営を続けるとして、この先、松野さんが描いているご自身のイメージはありますか?
松野氏:
50歳を超えてからは、「老後、いかに楽しんでゲームを作るか」というのをテーマにしていて(笑)。
 |
というのもスクエニから独立した友人が、「松野さん、ノリノリになれる仕事だけ受けたほうがいいですよ」、「ノリノリじゃないと仕事のモチベーションは上がらないし、人生つまんないですよ」と言われたんです。
まあ、ゲームは楽しいものなので、「楽しんでゲームを作りたいな」と思っています。
今日お見せした資料を手元に置いておくいちばんの理由は、当時楽しんで作っていた自分がそこにいるので、「初心を忘れずに」という意図があります。
ともすると、生活のため、会社のため、売り上げのために作りそうになるけど、原点に戻って、「いつまでも作ることを楽しんでいられるようであればいいな」と思いますね。
この後の10年間は、「いろいろといい感じで、いかにゆるくゲームを作るか」がテーマ(笑)。
吉田氏:
僕は未来の松野さんに対しても複雑な思いがあって。
──と、言いますと?
吉田氏:
いまはこうして『FFXIV』でようやくごいっしょできましたが、僕は『タクティクスオウガ』の次というか『オウガバトル』サーガの続きも見たいし、『ベイグラントストーリー』のエンディングのあとがどうなるのかも見たい。でも複雑なのは、それらを松野さんがやるんだったらいっしょにやりたいんですよ。
僕はあれらに衝撃を受けて、いっしょに作りたいと思ってここまで来てるので。
かといって、それを『FFXIV』がある状態で、うかつに「全力でいっしょにやりましょう」とも、大人だから言えませんし、やるからには全力でやりたいんです。さらに「ほかの人とやってほしくない」という。
──好きすぎでしょう(笑)。
松野氏:
吉P忙しいから(笑)。
──松野さんといっしょにゼロから作れるとしたら、どんなゲームにしたいんですか?
吉田氏:
そんなにボリュームがなくてもいいからHDのゲームで、なんならレアモンデ(『ベイグラントストーリー』の舞台の都市)を舞台にして、もっとリアルタイムで、玄人がビビッとくるゲームを、松野節全開でやれたらと思います。
──でしたら松野さん、何かいいアイデアを出さないと(笑)。
松野氏:
それ、じつはひとつあって。
会社を辞めちゃったんだけど、本当は『オウガバトル』には3作目の構想があって、“オウガバトルRPG”にしようという話をしていたんです。その企画書も書いていた。
──本当ですか!?
松野氏:
そうやっていくことによって、「クエストという会社は、じつはいろんなものが作れるところだ」と示したかった。
RTSというニッチなリアルタイムのシミュレーションに始まり、ヘックス制というか、グリッド制のウォーシミュレーションへとだんだん軟らかいものに移行して、最後は「RPGという、より大きな層に向けて会社のブランドを引っ張っていこう」という計画があったんです……まあ、自分がスクエニに移籍しちゃったので(笑)。
吉田氏:
その続きのRPGを作りましょう!!!!!! いずれやりましょう!!!!!!
 |
──その最後にRPGを持ってくるという戦略は、スゴく“なるほど感”がありますね。
吉田氏:
松野さんがもし松野節でそのシナリオを書いてくれるなら、俺はプロデューサーになります。そして、伊藤さんを連れてきてゲームシステムを作ってもらいましょう。
──おふたりが組むときは吉田さんがプロデューサーなんですか。
吉田氏:
僕ですよ。だってゲームデザインでは、断然……。
松野氏:
いやいや。
吉田氏:
いや、松野さんにお任せします。僕が松野泰己に言うことなんて、何もありませんから。
そして松野さんは、「吉田、あそこはどうなってんだよ」、「あれはどうなってんだよ」と僕を追い立てていればいい。
松野氏:
意外と言わないよ?
吉田氏:
いやでも、それくらいはやっぱり言ってもらったほうが……。
──(笑)。
松野氏:
まあプロデュースはもちろん、ディレクションからゲームデザインから自分でやるなんて、いちばん面倒くさいのはわかっているから、「やれる人がそこにいるんだったら、任せたい」というのが本音ですね。あとね、若くないと兼任はもうできない、本当に。
吉田氏:
ですから僕は売るための戦略を考えて、お金と人を集めてきます。だから松野さんはゲームデザインとシナリオを……。
あ、そのかわり僕はスケジュールにはめっちゃうるさいですけど……(笑)。
──(笑)。
吉田氏:
やっぱりここまで松野さんのゲームを参考にしてきたし、本当にプレイヤーとしても松野ゲーが大好きなんです。松野さんのようになれないのはもういいんです。
でも、ああいう松野さんの作品たちに衝撃を受けて、「いつかいっしょに作りたい」くらいに思って、ここまでやってきたんですよ。
だから悩ましいですよね。『ベイグラントストーリー』をベースにした、明彦さんが描いたリアルタイムの世界を、松野さんのシナリオと皆川さんのシステムデザインで走り回るというゲームで世界に向けて勝負するというのもアリだし、『オウガ』のRPGも気になるし(笑)。
松野氏:
それはいまだったら『ダークソウル』のようなバリバリのアクション寄りになるけどね。
吉田氏:
松野さんと本気でやれるなら、ほかの仕事は全停止ですね。 いっしょに仕事すると、僕の愛情は相当ウザいですよ!(笑)(了)
 |
さて、松野泰己氏と吉田直樹氏のインタビューはいかがだっただろうか。
これまでの電ファミニコゲーマーの対談企画では、遠藤雅伸、中村光一、シブサワ・コウ、システムソフト社などの、いわば現在の日本のゲーム業界そのものを生み出した先人たちの話を伺ってきたことが多かった。
そんな彼らが黎明期という神話の時代の住人であるなら、今回の松野氏や吉田氏の世代は、彼らの生み出した世界の混沌に惹かれて住み着き、そこに豊かで高度な文明を築き上げてきた開拓者たちと言えるだろう。
とくに松野氏はこのインタビューでも明かされているように、かなり自覚的にそんなフェイズを意識して乗り込んできた、果敢な開拓者だったようだ。
インタビューで吐露された氏の言葉には、そんな「神話」と「文明」の狭間の時代を生きてなお、いまも第一線で活躍を続ける者の苦悩と葛藤がにじみ出ていたように思う。
一方、2018年の高度に発達したゲーム開発の現場で大活躍を続ける吉Pこと吉田氏の言葉からは、『FF』というブランドを背負って、大規模開発で世界を相手に立ちまわる“ものづくり”の最先端がどんなものかも見えてくる。
みずからの仕事を「サービス業」と言い切り、「お客さんが楽しんでくれればそれでいい」と語る姿は、とても清々しく、勢いに満ちている。
そんなふたりが互いに語り合ったプランナーの心得には、時代を経ても変わらない“ものづくり”の心構えが詰まっていたように思う。
そして、最後に。
筆者個人は、さすがに吉田氏にはかなわないとは思うものの、同じ古くからの熱狂的な松野ファンとして、「ああ、だから松野氏のゲームは、こんなにも心に残るのだな」と、長年の疑問が解けた感動があった。
取材中、松野氏ほどの人物が「なぜそんなにもナイーブな発言をするのだろう?」と戸惑った部分もあったが、その感受性の高さや繊細さが彼の深い洞察を生み出してきたことが、あらためて読み返してみると解る。
集団制作物であるゲームで、『オウガ』や『FFT』というタイトルが、なぜあんなにも作家性に溢れた作品になり得たのか。
それが作り手である松野氏自身の悩みや葛藤が大きく反映されていたから──というなら、いまの松野氏が描くシナリオも、きっと多くの人の共感を得るものになるのではないだろうか? なぜなら松野氏の思いは、この現代に仕事をする多くの人々の思いでもあるはずだから。
齢50を超え、いまなお自己を見つめながらゲーム制作を続ける松野氏。
そんな松野氏に誰よりも憧れ、最先端のゲーム開発の戦場を戦い抜いてきた吉田氏によるプロデュースの下、いまだからこそ描ける“松野節”を、まずはいまの『FFXIV』内コラボでじっくりと味わい、そして新規タイトルのコラボ実現をともに夢見ようではないか。
(C)1997,2007 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER ILLUSTRATION:Akihiko Yoshida
(C)2010-2018 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
(C)1997 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
【あわせて読みたい】
【新連載:田中圭一】坂口博信とFFの天才プログラマたちが歩んだ、打倒DQへの道。「毎日のようにキレてましたけど(苦笑)」【若ゲのいたり】1980〜1990年代、ゲーム業界は「青春期」だった。そんな時代に大奮闘したゲームクリエイターたちの、熱くて、若くて、いきすぎた思い出をたずねたい──そんな想いから企画されたレポートマンガ、それが『若ゲのいたり〜ゲームクリエイターの青春〜』です。
近著『うつヌケ』、『ペンと箸』に続くレポートマンガ第3弾として本作を手掛けるのは、自身がゲーム業界で働いていたという経歴を持つマンガ家・田中圭一先生!
第一回のゲストは、『ファイナルファンタジー』の生みの親・坂口博信さんです。