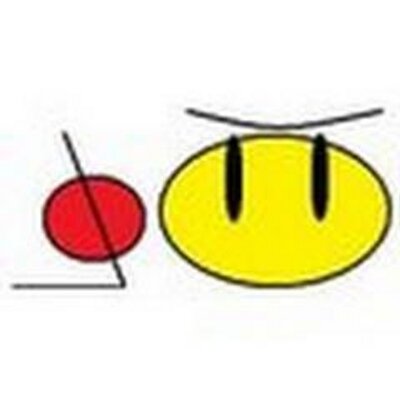人工知能は何を人類にもたらすのか?
――さて、一通り電王戦について話してきたのですが、少し最後に話題を広げて人工知能と人間の関係について聞いてみたく思います。電王戦から、それこそ未来の人間と人工知能の関わり方のようなものは見えましたか?
久保氏:
先ほども言いましたが、電王戦でドラスティックに何かがバーンと変化したわけではない。ただ、ここまで話してきたように色んな前提がふわふわと流動化しだしているとは感じます。それこそ、将棋が「情動のゲーム」でもあるというのは、まさに電王戦を通じて次第に見えてきたことだと思います。
――将棋について言えば、「前近代」と「近代」の要素を曖昧なまま共存させてきたジャンルだったことを、人工知能によって徹底的に暴かれている……というのが、今日のお話の感想として一つあります。でも、僕らの生活だって、全てが「近代」以降の価値観だけで動いてるわけでじゃないので、そこは今後どんどん自分たちの身にも降りかかってくるな、とも感じたんですね……。
久保氏:
そこについては……少し長くなってしまうのですが、先に「近代」という言葉についてお話ししますね。
 |
大学の授業で説明するときにも話すのですが、文系の学問用語としての「近代」は時代区分に留まる言葉ではありません。近代西洋で生まれた発想や行動のありかたが、わたしたちが自分たちや世界について考えるときの基本的な前提になっていて、それを「近代」と呼んでいるという感じですね。
――ああ、なるほど。日本で言えば、明治に入って「開国」でガラッと「近代」化していくわけですけど、それは単に電気が引かれて街灯がつくようになったとか、寺子屋から学校教育に変わったというような目に見える話だけじゃないですよね。それこそ色恋に対するイメージも変われば、「人間の走り方」のような身体の使い方だって変わる。もっと全体的に変化していくわけですよね。

(画像はAmazonより)
久保氏:
正確な表現ではないですが、近代というのはWindowsやiOSのような「OS」みたいなものだと言えるかもしれません。文化人類学は、近代というOSがあまり浸透していない、非近代な社会を対象としてきました。その一つの狙いとして、非近代社会でフィールドワークを行うことによって、近代というOSを批判的に検討し、その組み替えの方法やきっかけを探るということがあると思います。
ただ、僕の場合は少し違っていて、むしろ近代社会内部の現象のなかに、その相対化と組み替えのキッカケを探る仕事をしていると思っています。その鍵となる領域として、ロボットやAIと呼ばれる知能機械に関するテクノロジーについて研究している、ということですね。
――「OS」はわかりやすい喩えですね。だから、アプリの部分的なアップデートは出来ても、全体的にガラッと切り替えるのは、相当な覚悟がいるという(笑)。iOSで使えていたアプリが、WindowsやAndroidに移植できるとは限らないですからね。では、今回の電王戦で発見したOSの取り替えのキッカケになるものは、どんなものでしょうか?
久保氏:
少し専門的になりますが、そもそも近代というOSがどんなものかという話からさせてください。
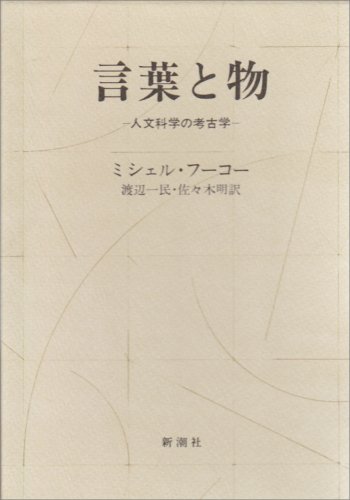
(画像はAmazonより)
この問題について考え抜いた哲学者の一人にミシェル・フーコーという人がいます。彼は1966年に出版した『言葉と物』という本で、近代以降の人間のあり方を「経験的=超越論的二重体」という仕方で呼んでいます。それは、人間という存在は物事を経験する主体(経験的)であると同時に、その経験がどんなものであるかの根拠づけとなる主体(超越論的)でもある、ということです。イマヌエル・カント【※】以降の哲学を中心にして、人間が人間自身をそのように規定してきた、ということです。
※イマヌエル・カント
ドイツの哲学者。1724年生まれ。ケーニヒスベルク大学の哲学教授を務めた。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書における「批判哲学」が有名。認識論における「コペルニクス的転回」をもたらし、ドイツ観念論の起点となった。
――今回の電王戦に対して僕が久保さんに質問している態度なんかは、まさにフーコー先生の仰るとおり、という感じかもしれないですね。電王戦での体験を「人間とは何か?」を軸に据えて聞き出そうとしてしまっているわけですから。でも、そういうふうにいちいち「人間について」反省しようとするのって、近代以降の態度なんですか?
久保氏:
ざっくりというと、西洋では近代以前に「超越論的」という部分に相当していたのは、「実在する神」ですね。人間の経験の最終的な意味や善悪を決定するのは神であり、それは人間の認識や思考を超えて実在することが当たり前で、神の実在が様々な発想や行為の前提になっていました。

(画像はAmazonより)
でも、近代以降はその「実在する神」が担っていた役割が人間に部分的に譲り渡されて、宗教的な要素は人間の内面の問題でしかないという考え方が広まっていくわけです。ニーチェの「神は死んだ」【※】という有名な言葉も、神というのを人間の内面的な信仰の対象として考える現代の私たちにとっては意味がよくわからない表現なわけです。内面の問題だから「死んだ」も何もないだろう、と。
しかし、あの表現はまさに私たちがそのようなものとしてしか神について考えられなくなった、ということを意味しています。世界を最終的に根拠づける存在として「実在する神」を持ち出すことができなくなった、ということですね。
※ニーチェの「神は死んだ」
ニーチェの主著『ツァラトゥストラかく語りき』で語られたとして、有名な言葉。初出は著作「悦ばしき知恵」。
ただ、「AI」と呼ばれる技術の周辺で起きていることは、もはや「意味づけや評価をする行為が、人間の占有物でなくなりつつある」ということなんです。
――ニーチェ風に言うなら、「人間は死んだ」ですかね。まあ、でも別に難しい話でも何でもなくて、実際に将棋ファンがソフトの評価値を見ながら観戦して、解説棋士たちも「この手は人類には早いですね」と言い出すところまで来てるわけですから、まさに今日話してきたことそのものですね。
久保氏:
これは70年代以降、ポストモダニストたちの議論で言われていた話とも違います。
彼らは知性の内部における「自己反省」という仕方で近代というOSを再検討してきたわけですが、現代将棋のような事例では、シンプルに技術的な現象として、「判断の最終的な根拠としての人間」の崩壊が、実際に起こってしまっているわけです。もう今までと同じような語り口で話すことは難しくなっていくと思います。電王戦は、その一つの現れ方にすぎない。ただ、もちろんこれは近代と伝統の様々な問題が絡まり合いながら展開していることですけどね。
――ただ、もう少し話を現実的なレベルに落とすと、我々が知的な判断をコンピュータに委ねることに、やっぱり危険がある気もするんです。例えば、羽生さんが挙げていた例で、パトロールする場所を人工知能に指示させたら、ベテランの刑事たちよりも遥かに正確に指示を出してしまったという話があるんです。
こうなると人間はお手上げだし、現実的な運用の場面でビックリするほどAIに色々なことを任せていく可能性もあるとも思うんです。でも、やっぱり人工知能の判断は、絶対の正解ではないじゃないですか。やはり私たちは、機械の判断を解釈して「人間」の方へ引き寄せないと、リスクが大きい気もするんです。
久保氏:
逆に聞きますけど、機械の判断を解釈できたからといって、人間が機械を完全に理解して制御することが可能になると思いますか?
 |
――いや、特に機械学習を用いたAIでは、面倒の方が多いかもしれません。正直なところ、ベテランの警察官の判断や熟練工の作業よりAIの方が遥かに正確だった……みたいな話が流れてくるのを見ると、もうそういうバグが混じるのを織り込み済みでAIに任せる運用を模索する方に、我々が進んでいく可能性の方が高いと思うのも事実です。
久保氏:
ソフトの判断を解釈する千田さんの試みには大変注目しています。ただ、そもそも僕らがいま生きている近代社会のやっていることは、非近代的な社会とさほど変わらないのでは? というのが僕の立場です。
例えば、非近代社会では「機械」に相当する位置に「動物」があると考えることができます。私たちがロボットやAIといった「機械人間」に魅了されつつ恐怖を感じてきたように、非近代社会では「動物人間」に関する豊かな実践があります。それは「ジャガー人間」とか、「ゴリラ人間」とか、「ハイエナ人間」のような存在との関わりです。
――ジャガー人間……ですか。きっと「精霊」みたいな架空の生き物じゃないかと思うのですが、一体どういう存在なのでしょうか?
久保氏:
例えば、エドゥアルド・コーン【※】という人類学者の、最近翻訳された『森は考える』という著作では、「ジャガーは、人間によって捕食されるけど、人間を捕食することもある」という両義性に注目した議論が展開されています。
非近代社会にとっての動物は、「人間に制御される存在でもあるけど、常に完全に制御できるとは限らない存在」であって、それを動物と人間が混ざり合った「ジャガー人間」のような存在において捉えた上で、様々な付き合い方をしているわけです。コーンが調査したアマゾン川上流域に暮らすルナの人々の場合、「ジャガー人間」は、死んだ父親とか近親者の霊が宿っていて、食べ物を分けてくれたりもするけれども、時には家のイヌを襲うこともある、親しみ深いけれども怖い存在として捉えられています。
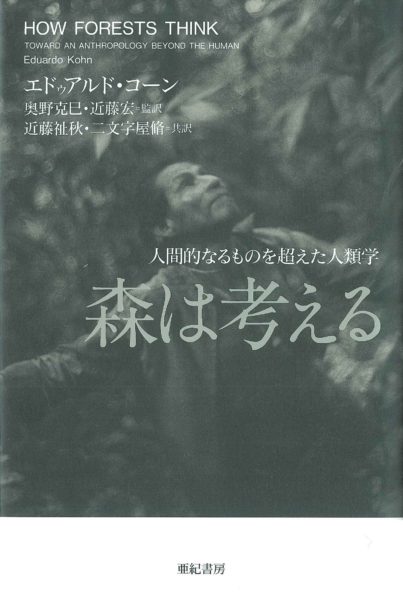
(画像はAmazonより)
これは、私たちが、ロボットやAIと呼ばれる機械に対して「人間を助ける素晴らしい技術だが、人間の仕事を奪ってしまうリスクもある!」とか言っているのと、大して変わらないわけですよ。産業社会において仕事の道具であるはずの機械に仕事を奪われることは、狩猟社会において捕食対象である動物に捕食されることとほぼ同じ意味をもつと考えることができますから。
――なるほど。
久保氏:
つまり、近代人はジャガー人間の代わりに、ロボットやAIとそういう関係を結んできたわけです。非近代人が動物に対して必ずしも上位に立てないように、近代人は機械に対して必ずしも上位に立てない。「HAL9000」【※】や「エヴァ」を考えても、ルナの人々がジャガーに感じるような「親しみ深さ」と「怖さ」が両方ありますよね。「エヴァ」なんて母親の魂が入ってますから、すごく特徴が似てるわけです。

※HAL9000
映画および小説『2001年宇宙の旅』、小説『2010年宇宙の旅』などに登場する架空の人工知能。作中では、木星探査(小説版では土星探査)のための宇宙船ディスカバリー号に搭載されていた。チューリングテストをクリアする程の高度なコンピュータであり、人間のような論理的思考回路を持つ。
実はここまで、僕は将棋ソフトに対して「人工知能」という呼び方は一切していません。それは、「ロボット」や「人工知能」というのはそれ単体で存在するものではないからです。
そもそも「ロボット」や「人工知能」は、単体ではただのハードウェアやソフトウェアでしかありません。ではなぜ、そう呼ばれるようになるのか。それは、人間との関わりのなかで人間と似た存在として捉えられることによって、です。
ジャガー人間がそうであるように、私たちが必ずしも制御できない他者の視点から自分たちを見るようになるときに、そうした他者が人間と混ざり合って、「動物人間」や「機械人間」として現れるようになる。こんなふうに、人類の営みにおいては、制御できない他者との関係を軸にして社会をまわしていくというのは、よくあることだ、ということですね。
――そう言われると、別に近代社会だって、常に制御できているわけではないですね。原発とか、その象徴みたいな話ですけども。
久保氏:
僕は、そもそもテクノロジーに対して、人間が制御できるものという前提で捉えていくと、完全に支配できるか否かという非現実的な議論にしかならないと思っています。AIにおけるシンギュラリティブームもそうでしょう。個人的には、その前提を断ち切ってしまった方が、変に「恐怖が」とか「リスクが」とか言わなくなると思いますがね。
 |
人類が、完全には制御できないような存在との関係を軸にして世界と関わるのは、わりと普通のこと。少なくとも、そこから考えてみませんか?――そういう姿勢で、僕自身は「電王戦」や「人工知能」についての論考を発表してきました。
多文化主義の「前提」とは?
――ただ今日、久保さんにお話を伺うキッカケになったのは、以前に書かれていた文章で、まさにAIBOや電王戦の話をされた後にISIS(Islamic State of Iraq and Syria)【※】を例に引きながら、そういう21世紀の社会で問題になっている「他者」との対話の可能性を、まさにAIBOのユーザーや電王戦の棋士たちが機械に向き合う姿勢から探る試みについて書かれていたからなんです。この人は、電王戦を人類社会の問題に結びつけて解釈しようとしているのだな、と。

(画像はAmazonより)
※ISIS
Islamic State of Iraq and Syria”(イラクとシリアのイスラム国)の略称。イラクとシリアで活動するイスラム過激派組織。IS、ISIL、ダーイシュ、イスラム国などと呼ばれる。シリア・アラブ共和国北部の都市ラッカを首都として国家樹立を宣言しているが、外交関係で国家の承認を行った国家はない(2017年5月17日時点)。
久保氏:
ISISについて詳しく調べているわけではないですし、軽々しく言えるようなことではないですが……僕があの文章で言いたかったのは、こういうことです。
例えば、中沢新一さん【※1】のような人類学者が、近代というOSの外側にある営みを探求して、近代社会の深層にもあるような非近代的なOSの在り方を提示していく――そういうやり方が機能していた時代は、今ではかなり呑気なものに見えるようになったように思います。
というのも、ISISのような近代的発想に上手く収まらない思想を掲げる組織が、その考え方にもとづいて「国家」を名乗ってしまって、しかもそれへの対処が現代の治安維持の中心的な問題になっている。そこでは、多文化主義【※2】や文化相対主義【※3】が前提にしてきた発想の妥当性が、かなり厳しく問われていると考えています。
※1 中沢新一
日本の人類学者、宗教学者。1950年生まれ。元中央大学総合政策学部教授。明治大学特任教授/野生の科学研究所所長。多摩美術大学美術学部芸術学科客員教授。独自の宗教体験にもとづく、アカデミズムのスタイルにとらわれない著作が、80年代にニューアカデミズムの旗手として毀誉褒貶とともに注目を浴びる。ゲームについて早くから文章を発表しており、『ゲームフリークはバグと戯れる』『ポケットの中の野生』などが有名。
※2 多文化主義
異なる文化を持つ人種、民族、階層がそれぞれの独自性を保ちながら,互いに容認し、共存していこうとする思想。少数民族のマジョリティへの、社会的・文化的な同化を前提にした「人種のるつぼ」的な同化主義に対抗して、形成されてきた。
※3 文化相対主義
人間の諸文化に優劣を設けず、それぞれ独自の価値体系をもつ対等な存在としてとらえる思想。歴史的には、自分たちの文化を、唯一かつ最高のものとして考える「エスノセントリズム (自民族中心主義)」 に対する批判の中で形成されてきた。
――性奴隷を公的に容認して、スナッフムービーをYouTubeに上げて、他国に片っ端からテロリズムを予告して……という「国家」を、さすがに「まあまあ、文化は色々ですから」とそう簡単に認めちゃっていいのか、というのは、まさにいま世界が直面している問題ですね。
久保氏:
素朴に「同じ世界」というレイヤーを皆が共有していると想定すること自体に、無理が生じつつあるのだと考えています。

多文化主義の、「色んな見方がありますよね」という発想は、「自然科学が解明するような現実の世界のあり方はどこでも同じものだ」という前提があって、その上で「同じ世界を文化によって異なる仕方で認識している」と捉えるわけです。だからこそ、呪術や精霊や神といったものも、「実際には存在しないけれど、彼らはそのような幻想に意味を見いだすような文化を持っている」と説明される。
そして、だからこそ、同じ世界を共有した上で互いの視点を尊重しよう、という話になってきた。
でも、果たして本当にそうなのか。私たちは同じ世界など共有してるのか。どこまでが「同じ世界」でどこからが「異なる認識」なのかの線引き自体を、自然科学に代表される近代的思考の側が勝手に決めてしまっているのではないか。そういうことを、今や真剣に考えなければいけないところまで来ていると思っています。これは、現在の人類学で「存在論的転回」と呼ばれている発想を僕なりに捉えた見方ですが。
――うむむ。仰りたいことは何となく分かるのですが、それって具体的にはどういうことになるのでしょうか? さすがに「こいつとは“生きてる世界”も“物事の見方”も何にも共通点がねーな」と思いながら相手と対話しても、喧嘩しか生まない気がするんですけども……。
久保氏:
そこは、先ほど千田さんに関して「ポケモン世代」という言い方をしましたけど、「ポケモン」のゲームやアニメ、さらには「ポケモン廃人」とか「ガチ勢」と呼ばれる人たちのレーティングバトルのあり方は、こうした問題を考える際に、かなり参考になるんじゃないかと思っています。
ポケモン的な多様性とは
――いきなりキャッチーなお話が飛び込んできましたが(笑)、どういうことでしょうか?
久保氏:
まず少し背景を話しますと、ここ10年ほどで、TwitterやFacebookのようなプラットフォームが急速に広まりましたよね。これらは、デジタル技術に基づいて情報発信やコミュニケーションの形式を標準化する媒体、として捉えることができます。
こうした媒体は、地域に根ざした慣習や規範や義理といった所与の基準に制約されない行動やコミュニケーションを可能にします。例えば、難民の子どもの発言もハリウッドスターの発言も、Twitterでなされる限り同じフォーマットで扱われます。一方にRTできて他方にRTできない、なんてことはないですよね。だからこそ、難民のツイートをハリウッドスターがRTして世界中に広まる、みたいなことも起こりうるわけです。
 |
――なるほど。最近ソーシャルメディアの負の側面みたいな話が噴出することが多いですが、やはりSNSなどの「共通のプラットフォーム」に乗ることで「所与の基準」から解き放たれて、なんだかんだで視野が広がった人は多いと思うんですよね。そして、これがポケモンにつながってくるわけですか?
久保氏:
例えば、同じRPGでも『ドラクエ』はデジタル化された「剣と魔法の世界」の内側を冒険するゲームですが、『ポケモン』は、まさに「標準的な媒体」と結びついたポケモンを中心とするゲームです。ここで言う「標準的」とは、どんなポケモンでも同じようにモンスターボールに入り、同じ技マシンが使え、同じように数値を見ることができて、パソコンに保存できるということです。
そして、モンスターボールやポケモンセンターといった標準化された媒体に接続されているからこそ、絵本から出てきたような「カイリュー」みたいな初代からいるポケモンも、「ロトム」や「ジバコイル」みたいな機械っぽいポケモンも、特撮映画から出てきたみたいな「マッシブーン」のようなUB(ウルトラビースト)【※】も、それぞれ違った魅力を発揮しながら同じ土俵で戦うことができるわけです。

(画像は『ポケットモンスター サン・ムーン』公式サイトより)
――優れた共通規格があれば、むしろ多様性は増幅されていくというのは、IT業界のプラットフォームビジネスの教訓でもありますよね。それこそ、ある時期のニコニコ動画や初音ミクはその象徴のような存在だったと思いますし。
久保氏:
もちろん、800種を超えるポケモンの全てに人気があるわけではないですよね。特に、Wi-Fiを使ったレーティングバトルでは、「ガブリアス」のような強いポケモンが目立ちますから、いくら多様だと言っても「強さ」によって人気順が固定されてるようにも見えます。でも、その強さも絶対ではないですね。
新しいゲームが発売されてポケモンやタイプや技が追加されたり、新しい戦い方が広まっていくと、以前の最強ポケモンが没落してトップが入れ替わっていく。さらに、新しいトップポケモンのパートナーや天敵として、あまり人気のなかったポケモンが注目されるようにもなりますね。「何が強いのか」という基準自体が様々に変化していくわけです。
 |
それこそ『ドラゴンボール』に対する『HUNTER×HUNTER』のような違いが、『ドラクエ』に対する『ポケモン』にはある。強さの基準が固定されていない、ということですね。ポケモンの場合、こうした「多様な基準の生成」を可能にしているのは、デジタルな数値への徹底的な還元だと考えています。
――なるほど。それって具体的にはどういうことでしょうか?
久保氏:
ずいぶん前からポケモンの強さに関わるあらゆる数値(種族値、個体値、努力値、性格補正、タイプ相性、技ダメージなど)が解析され、ネットで調べればすぐに分かるようになりました。レートに潜るようなトレーナーにとっては、それらの数値を把握していることがバトルの前提になっていますよね。
でもあまりにも多くの種類の数値があって、どんな組み合わせが「強さ」として現れるかは、あらかじめ分からない。だからこそ、数値の新たな組みあわせに基づいて「今の環境だとコイツがやばいんじゃない?」という判断が、ネットに投稿される「育成論」などを通じて新たに広まっていく。数値への還元がなされていなければ、「やっぱりドラゴン最強」みたいなイメージに影響されて、戦いのあり方がここまで変化することはなかったと思います。

――なるほど。確かに、年配の人は「デジタルと画一性」をすぐに結びつけてくる傾向があるじゃないですか。それに対して、今の若い人はむしろネットやパソコンのようなデジタル技術に対して、カオスなくらいに「多様性」を生むものというイメージの方が強いと思うんです。ポケモンの物語やレーティングバトルを、その象徴として読み解くのは文化論として面白いですね。
久保氏:
今のポケモンというのは、「多文化主義」のように「同じ世界を異なる視点から見る」というのではなくて、標準的な媒体を通じて「違う世界」がどんどんつながってしまうような状況において、それでも完全に一つの基準に集約されることを回避しながら、いかにして多様なものたちが共存できるか、という実験が行われている場だと思うわけです。デジタル化されない「外部」に可能性を見いだすのではなく、デジタル化を通じて多様な可能性が生まれる道筋が探られている、ということですね。
――ただ、そこで先ほどの話に戻すと、千田さんなんかは、まさに「大局観」に相当する「形勢判断」もデジタルに還元することで、新しい視点を得られるのではないかというスタンスなわけですよね。そこは羽生さんが「大局観」を鍛えるに当たって、若い頃にラグビーの試合なんかを見に行ったというスタンスとは、ちょっと違います。ただ、羽生さんは「最近の若い棋士は、未知の局面での対応力が弱いんじゃないか」とも言ってましたが……。
久保氏:
でも、千田さんは、もともと見たことのないような局面で強い棋士ですからね。むしろそうした場面での判断をより精緻にするためにソフトを活用していきたい、という言い方でした。将棋の「外部」へ向かうのではなく、むしろ徹底的にその「内部」を数値に還元することから新しい可能性を見いだしているように見えます。「野生の勘」を鍛えるのではなく、「数値化された野生」を鍛えるという姿勢ですね。
似た発想は、子供の頃に「野生のポケモン」をゲットして育てていた今の大学生たちにも感じますね。彼らには、僕らの世代にはなかったような自由の感覚、デジタル化や標準化を通じて新たな個性や関係性が見いだされていくという発想があるように思っています。
ポケモン世代の抱える「問題」
――でも、それを「自由」とか「多様性」と簡単に呼ぶのは抵抗がある人も多いと思うんですよね。実際、「標準化」というのは、その対極にあるイメージの言葉であるのも間違いないですから。
久保氏:
たしかに僕も、彼らの感覚にはついていけないなぁと感じることもあります。例えば、僕が南インドで調査をしているとき、ふとTwitterを見たら自分のいる街に来ていた日本の学生がトラブルに遭っているようだったので、「何か手助けできるかな」と思って連絡したんです。すると、その学生から「日本の知人とSNSで相談するからいいです」みたいなえらく冷たい返事が返ってきたんですね(苦笑)。
――「Twitterで博士に相談します」と(笑)。
久保氏:
僕が学生のときに個人旅行していた感覚では、インドのような環境も慣習もかなり日本と違う場所だと、現地に長くいる日本人と会ったらまずは仲良くなろうとするのが普通だったので、ビックリしました。「何のためにインドまで来てるの?」とも思うけど、僕の申し出を断ることで、「インドで知り合った日本人同士」という既存の枠組にあてはまらない関係を誰かと作っていくことが、可能になってもいます。
そうやって彼らは「外部に出るからこそできることがある」なんて思うなよ、と僕の世代を批判しているんです。
 |
いや、別に批判してるつもりはないでしょうけど、僕は「はい、すいません」って感じですね(笑)。
――でも、『ポケモン』というゲームのナラティブ構造を言うと、物語の「多様性」がモンスターによって担保されてるからこそ、「新しい人間と出会う」感動なんかに頼らなくていいというのはあると思いますね。
久保氏:
それは結構重要で、だからこそあのゲームでは、手持ちのポケモンが全て瀕死になると「めのまえがまっくらに」なるんじゃないですかね?
そして、目の前がまっくらになった状態でいかに生きのびるかは――「ポケモン世代」の別の問題としてあるでしょう。
『俺ガイル』【※】で描かれているようなリア充に対する「ぼっち」の問題もそうだし、ゾンビとか吸血鬼が出てくる作品が増えているのも、標準的な媒体に上手く接続できなくなった状況でいかに生きのびるかという問題が浮上しているからではないか、と思います。上の世代は、そのときに「お前がいる世界の外に出ればいいんじゃない?」と言いたくなっちゃうわけですが、果たしてどうなんでしょう。そもそも既存の関係の作りかたを見失ったり否定するからこそゾンビになるわけで、話はそんなに単純ではないように思います。

(画像はAmazonより)
ただ、ポケモン世代において「ポケモン」への誠実さがあそこまで重要になるのは、標準的な媒体が固定化された存在として自明視されているせいかな、とも思います。それこそ『Minecraft』になると、もっと標準的な媒体そのものが可変性を持ちますからね。それはそれで別の問題が控えているでしょうね。
――なにせ世界中の小学生がパソコンに『マイクラ』のMOD【※】を入れて、世界の法則を変更しながら遊ぶのを当たり前にやってる時代ですからね。彼らが大人になったとき、何が起きるかはワクワクしますよね。
※MOD
MODはModification(=修正・改造)の略で、ビデオゲームの文脈で語られる場合、おもにPC用ゲームの改変用データを指す。
久保氏:
その意味では、ポケモンをめぐる問題にはこれから数年がかりで決着をつけて、来たるべき「マイクラ世代」の学生を迎え撃つ準備が必要だろうな、と思っています。
人工知能とどう共存していくか
――そろそろ時間ですが……最後に一つだけ聞き逃したことを思いだしました。実はドワンゴ的には、電王戦のプロモの間を持たせる企画だった……ような気もしなくもないタッグマッチ【※】が、意外にもドラマを生んでしまったことなんですよ。これ、ある意味で人間とポケモンが共闘関係になれるかという話だったとも思うんです。
※タッグマッチ
電王戦タッグマッチ。将棋のプロ棋士がコンピュータ将棋ソフトとタッグを組んでトーナメントで激突する、お祭り的な棋戦。棋士ごとにソフトの重用ぶりが異なる点が見もので、2013年8月の第一回に始まり、過去3回催されている。
久保氏:
タッグマッチが面白かったのは、「ソフトを信用しない」棋士こそが強かったことですね。
あれはソフトの「点の思考」と人間の「線の思考」の違いが、最もわかりやすく出た戦いだったと思います。ソフトが示す候補手が良い手に見えても、それを捉える流れの感覚は棋士の側にあって、ソフトにあるわけではない。ソフトの推奨手を指しても必ずしもプラスにはならない中で、あまりソフトを信用しなかった佐藤慎一さんが結果を出したのは面白いですね。
――タッグマッチって、ある意味で人工知能に人間が無理矢理に「線の思考」を導入したという言い方も出来ますよね。
久保氏:
うーん、まぁちぐはぐな将棋でしたよね。見てる方も、どうやってアレを楽しんだらいいのか問われるような……(笑)。
タッグマッチにおけるソフトのイメージって、ガンダムのような「搭乗型ロボット」に喩えられていたけども、実際は『エヴァ』以降の搭乗型ロボットに近い感じでしたね。ロボット自体が生き物で、別に人間がいなくても動いちゃうという。佐藤さんのノリは結構アムロっぽかったですけどね。
――エヴァにアムロが乗ってみたら、意外と強かった、みたいな。エヴァに対して「こいつ、動くぞ!」と言うみたいな(笑)。
久保氏:
それ、見たいですね(笑)。
 |
ただ、佐藤さん以外の棋士がどんな将棋を指したかは、不思議と印象に残ってないんです。
搭乗型ロボットアニメって、人間がロボットを動かしているという前提があるからこそ、面白いと思うんです。だから、どっちが動かしているのか分からなくなると、シンプルに楽しめなくなる。その意味で、「エヴァ」は搭乗型ロボットの限界までいったアニメだと『ロボットの人類学』にも書いたんですが。
タッグマッチにも似た印象があります。「人間と機械が一緒に戦うんだ!」って聞くと一瞬ワクワクしますよね。でも、それって、機械によって人間が強大な力を持つというイメージで興奮してるわけですよ。実際に展開されたのは、棋士とソフトのどちらがメインなのか分からない戦いでした。トレーナーが指示していない技をポケモンが自分で出しちゃうみたいな。それを楽しむのって難しいですよね。「人工知能との共存」を考えるときも、互いに独立した人間と機械の関係というより、人間と機械が混ざったどちらが主体か分からないような存在をどう肯定できるのか、ということが重要な問題になると思っています(参考:久保明教 2015「対称性人類学からみる現代スポーツの主体 ―将棋電王戦をめぐる考察」『スポーツ社会学研究』23(1): 19-33)。
――それ、今のF1ファンには「わかる」という人が多い気もしますね。もう最近のレースって、自動車とドライバーのどっちがメインかわからないレースになっていて、みんなが楽しむのは難しい気もするんです。やっぱりエンタメとして一番盛り上がれるのは、「プロストvsセナ」みたいな人間同士の戦いとして見られる瞬間だとは思うんですよ。
久保氏:
同じような難しさは、例えば、男子100Mの世界記録を次のオリンピックまでに抜かすのではと言われている、パラリンピックアスリートにもありますよね。最新の義足を装着したアスリートがウサイン・ボルトを抜く光景を、私たちは手放しには賞賛できないでしょう。

(Photo by Getty Images)
パラリンピックを見るときはハンディキャップを乗り越える人間の強さに感動するけども、彼らがそのままオリンピックに出てくると、「義足のおかげで速いだけ、フェアじゃない」と感じてしまう。
これと似た状況になったのが、2014年の大晦日に行われた森下卓九段【※】とツツカナのエキシビジョンマッチですね。あの対局では、通常の将棋盤のほかに、「継ぎ盤」と呼ばれる検討用の将棋盤を使うことを森下さんが提案して、電王戦本戦では敗れたツツカナに対して勝利する結果になりました。
※森下卓
1966年生まれ、福岡県出身の将棋棋士。1983年に17歳でプロ入り。竜王戦1組通算17期、名人戦A級通算10期。「第三回将棋電王戦」で「ツツカナ」と戦うも、一度負けるが、同年の「リベンジマッチ」にて勝利を収めた。
――これも非難の声が出てしまった対局でしたね。まさに義足と同じように「継ぎ盤のおかげで強いだけ、フェアじゃない」と思われてしまった……という感じでした。
久保氏:
でも、棋士が継ぎ盤を使うのは、ソフトが膨大な局面を生成して指し手を検討しているのと何が違うのか、とも言えるわけです。
――実際、経緯を言うと、森下さんは電王戦以前から、これを「コンピュータと人間が将棋を指す際のフェアな条件」だと言っていたんですよね。むしろ異種格闘技戦のルールとして、コンピュータだけではなく人間側にも新しく条件を課すことで、よりフェアな戦いを目指した勝負だったとも言えるはずなんです。
久保氏:
なぜ継ぎ盤がフェアに見えないのかというと、普段の棋士はそんなことしてないから、ということになります。結局、電王戦という異種格闘技戦を最終的に成り立たせていたのは、棋士がいつもどおり盤の前に一人で座って考えながら指している、という「見た目」だったんじゃないでしょうか。そこに継ぎ盤やタッグを組むソフトが加わると、途端に何をどう見ていいか分からなくなる。オリンピックに義足のアスリートが出てくるとよく分からなくなってしまうように、です。
僕らは、あまりにも人間を中心に世界を見ることに慣れてしまっていて、その前提が壊れている状況を直視できないからすぐ否認しようとする。
 |
電王戦というのは、そうした状況が垣間見られる特異なイベントだったと思います。もちろん、「ソフト開発者も人間なのだから、これは人間対人間の戦いなんだ」、という否認の語り口も噴出しましたがね。まあ、こういう奇妙な光景が見れたのは、主催がドワンゴだったからなのかもしれませんが。
――まあ、GoogleはAlphaGoで生放送はしましたが、こういう訳の分からない企画はしませんでしたね(苦笑)。「電王戦」自体が、ウェブサービスの運営を一種の「興行」のように捉えてきたドワンゴ社の狂気が極まっていた、あの時期ならではのものだった気もします。まさに最初の将棋のお話に戻ると、「興行」というのも常に奇抜さを求められる以上、自己破壊に自己破壊を重ねていく面がありますから。
久保氏:
これまでの常識がいつ壊れるかわからないような可能性を見せてくれる場として「電王戦」は、非常に重要だったと思います。将棋って何なの? 一つの身体って何なの? 強いって何なの? 知性って何なの? 数値化って何なの? 人間って何なの? という様々な部分で前提が流動化していくわけですから。
とはいえ、ここからどうなるかはわからないですね。千田さんみたいな研究の仕方もフォーマット化されて、ただの練習道具みたいになるかもしれないですし。
ただ、僕としては、こうやって電王戦が問いかけてくれたことは、色々な問題につながるものだと思っています。自分たちは何を当たり前と見なしていて、何をそこで守ろうとしているのか。進歩とかイノベーションとか呼ばれるものが何を前提としていて、そうした前提を変えることは何故できないのか。電王戦が喚起した諸々の問いを、将棋だけでなく現代の様々な現象と結びつけながら言葉にしていく、というのがこれからの仕事になりそうですね。(了)
 |
電王戦の5年間を振り返る長大なインタビュー、読者の感想はどうだろうか。
久保氏には商業メディアでの取材ということで、ズバズバと端的にご発言いただいてしまったが、より詳細で精緻な分析を知りたい方は、ぜひ氏の学術誌などでの論文に当たっていただければと思う。
さて、今回の取材で、久保氏は電王戦について「地面が壊れる」「前提が流動化する」などの表現を用いて、棋士や、時にソフトの開発者達までもが自明に考えていた物事が、次々に崩壊していく姿を語っている。実はこういう語り口は、AIについて考える言葉として珍しい。よくあるのは、むしろ「AIが人類を超えて、怖い」「人類の十八番がAIに奪われて、困った」みたいな、AIを人間の上位にあるイメージで怖れる素朴な脅威論だろう。
しかし、まさに電王戦で人類が目撃したのは、AIによって――私たちが生きてきた「世界」や「人間」自身が“見慣れないもの”へと変貌していく奇妙な光景だったのだ。
だが、それは何を意味しているのか?
筆者なりの理解を述べれば、これは「AIもまた、人間を変えるテクノロジーである」ということではないかと思う。人工知能は、人類がこれまで手にした自動車やパソコンのような多くの技術と違って、その作動に人間の手を必要としないものだ。それ故か、「AIに面倒は任せて……」という言い方はあっても、PCやネットで「人間がどう“進化”するか」を熱狂的に語るときのように、AIで人間がどう“変化”するかを語る人は少ない。
だが、電王戦で棋士たちが目撃した光景は、むしろ将棋の指し方の水準においてまで、棋士たちの意識を根底から変化させた。そして、三浦棋士たちのように、AIにコテンパンにされて尚、むしろその戦いから見えた将棋の可能性にワクワクしている「人間」もいる。
そんな電王戦の見せた光景――それは、シンギュラリティのような話よりも遥かに、21世紀の「AIのある人類社会」を生きていく私たちにとって、大きな可能性を秘めたものだったのではないだろうか。
【編集部よりお知らせ】
本記事はNHK出版から3月10日に発売された、羽生善治氏の新刊『人工知能の核心』とのコラボ記事企画です。
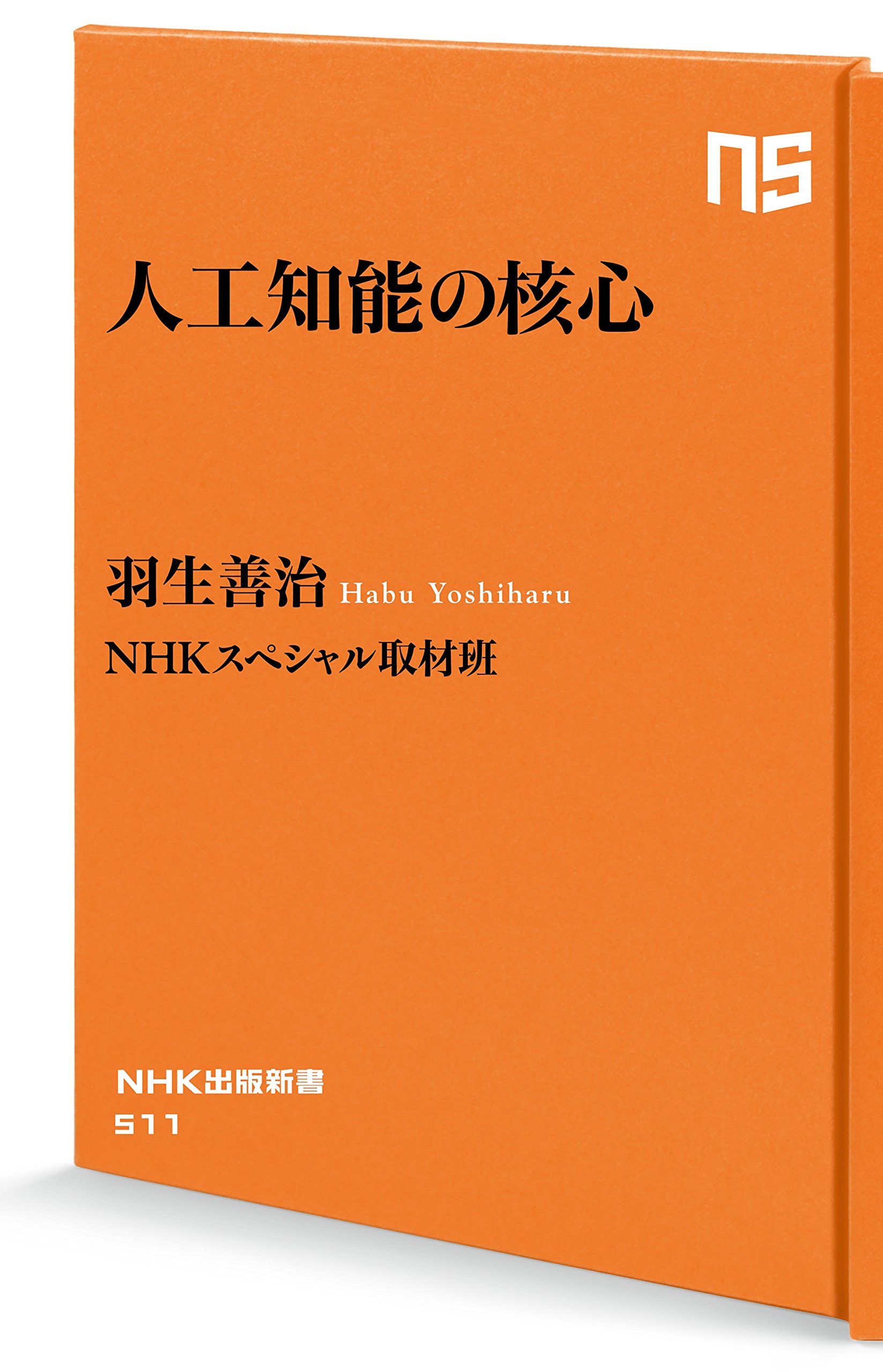
(画像はAmazonより)
羽生善治氏のAIについての取材成果が披露された本書、興味のある方はぜひ手に取ってお読み下さい。