放蕩の果てにたどり着いた「ゲームのシナリオ」
──作家論のような話も出てきましたが、おふたりは若い頃から「何かを作りたい」みたいなモチベーションを自然と持っていたんですか?
打越氏:
まあ若い頃は、人さまに見せられない内容の小説とかを、それなりに……(苦笑)。
小高氏:
僕はずっと、俗に言う“中二病”を引きずり続けてきていますね(笑)。中学校くらいのときに感じていた「俺はサラリーマンになんてなりたくねえ」、「何者でもない人間になりたくない」という、すっごい浅い動機からスタートしていて。
それこそ、中学で音楽をやろうと思っては、ギターとキーボードにすぐに挫折して、20代は映画を作りながらたいした就職もせず……そんな風に流れていった果てに、最後にたどり着いたのがゲームのシナリオだったんですよ。
──小高さんは『仁義なき戦い』などで知られる深作欣二監督のもとで助監督もされていた、実は映画畑出身の方なんですよね。そうした「表現欲旺盛」な小高さんの経歴の流れがあったときに、当時の「ゲーム」はどういう風に見えていたのでしょうか?
小高氏:
これは今もそう思っているのですが、「ゲーム業界は一番チョロイな」と思いました(笑)。だって、こんなフラフラした人間でも、好き勝手にやらせていただけているわけですよ。
もっと言うと、特に「シナリオ」は僕みたいな人間でも入りやすかったんです。当時はゲームで「心が震える凄まじいストーリー」みたいなものを目指して作られた作品って、そこまで多いわけじゃなかったんですよ。
打越氏:
僕なんかは、最近だと『NieR:Automata』には震えたけどね。
小高氏:
僕も、『STEINS;GATE』の最後には震えたので、決してまったくないということではなくて。でも当時は、門外漢の僕でさえ「もうちょっと、ちゃんと書けばいいのに」と思うような、ただ文字で埋めたような作品もけっこうあったんですよ。
──なるほど。ちょっと思うのが、小高さんがゲーム業界のことを「チョロい」と思えた理由のひとつに、世代的な利点があるのかなと。
小高氏:
世代的な利点……?
──ええ。電ファミでは「ゲーム世代の作家たち」という連載を細々と続けているのですが、その連載は「ある世代以降、表現の方法としてのゲームが浸透したことで、他業種にも影響を与えている」ことを明らかにしていこうというもので。
たとえば、鳥嶋和彦さん曰く“鳥山明のコマ割りには、無意識的に「映画のショット」が念頭にある”そうで。そのように、 “映画表現の手法”が世の中のコンテンツの表現にすごく浸透しているわけですが、それと同じことがゲームの表現や感覚にも同じことが言えるのではないかと思っていて。
それが、小高さんあたりの世代の強みになっているんじゃないかな、と。
小高氏:
ああ、それは間違いなくありますね。僕らはちょうど小学生でファミコンが出てきて、そこからずっとゲームと一緒に歩んできたわけです。だから、何かを考えるときに自然とゲーム的な表現が思い浮かぶ、最初の世代なんだと思います。近年だと、ゲーム表現のお決まりを逆手にとった『UNDERTALE』の登場だって、そうした流れにあるものですよね。
そうしたゲーム表現の素養が、具体的にどう活きているのかと言われると難しいですが……たとえば僕の場合、かなりくっきりと「どんなゲーム画面になっているか」を思い浮かべながら、シナリオを書けるんですよ。
──あるいは、『ダンガンロンパ』での“「言葉を撃つ」というアクション”って、ゲーム表現に慣れてない感覚からすると、実は意味不明に感じるものだと思います。
小高氏:
あれも賛否両論でしたけどね(笑)。それで言うと、あの演出もそうですが「ゲームだったら許されること」は、実はけっこうあるんですよ。
簡単な例でいうと、ゲームでは会話をしているときに相手の顔の表情に動きがなくても別に構わないですよね。最近の『Marvel’s Spider-Man』や『ゴッド・オブ・ウォー』でさえもそうなっていますが。でも、あれは漫画や映画では基本的に許されないことだと思います。
その意味で、ゲームって、他業種で長くやってきた人であればあるほど、参入がかなり難しい分野だと思うんですよね。やっぱり、ゲームの感覚値がわかっていない小説家やラノベ作家が書くシナリオには、けっこう手を入れて直さなきゃいけないというのは、経験として感じるところでもあるんです。
──特にRPGにおけるテキストは、かなり“端折って書かれて”いますよね。それがあまりに自然すぎて、ゲームをするほとんどの人は、意識すらしなくて済んでいると思うのですが。
小高氏:
その意味では、ゲームはかなり能動的なコンテンツなので、けっこうユーザーとの強い信頼関係のもとで成り立っているんですよね。
映画の例になってしまいますが、たとえば『カメラを止めるな!』のギミックって「映画館で一度見はじめたら、最後まで見てくれる」という信頼のもとに成り立っているわけじゃないですか。
ゲームも、プレイヤーが能動的であるがゆえに、そうした信頼感のもとでかなり自由に表現を乗せることができるコンテンツだと常に感じますね。
──特にコンシューマーゲームはそうですよね。その文脈であえて言うのであれば、スマホゲームは「離脱を防ぐ」という目的が大きな制約となって、クリエイティブの幅がかなり狭まらざるを得ない。
小高氏:
スマホゲームに関しては、最初に「ゲーム」と言わない方がよかったんじゃないかと、個人的には思っていて。実はかなり別物だと思うのに、お互いのユーザーがヘンに意識しすぎているきらいがあると思うんです。特に、コンシューマーが好きな人が必要以上にソーシャルゲームを憎む……みたいな。
スマホゲームは、自分の中ではコンシューマーとは別のものとして、むしろ“信頼関係を使わない表現に長けたもの”だと思っていますね。
 |
だからこそ、コンシューマーはその役割として、ユーザーの感覚を半歩先に連れていくような、新しい内容だったり新しい表現をすべきじゃないかと、個人的には思っています。
ゲームとシナリオにおける“作家性”
──もう少し話を続けると、“シナリオ執筆”は極めて個人的な作業であるがゆえに、大規模なゲーム開発の現場においても、比較的「作家性」のようなものが作品に反映させやすいのかなと思うんです。
そして、おふたりがこれまで語られていたクリエイターとしてのスタンスと、ゲームのシナリオを生業としていることって、実は密接な関係があるんじゃないかな、と。
小高氏:
確かに、シナリオの良いところって、最小単位で“ある程度の形”になることなんですよね。で、それを見てそこに肉付けする人たちが動いて、大きな作品ができていく。そうした流れでのものづくりであることは、特に僕みたいなタイプには非常に合っていたと思います。
──ある意味では、その最初の部分でちゃんと「カルピスの原液」を生むことができるわけですよね。すると、そこで表現されるおふたりの“作家性”みたいなものって、どういうところにあるのでしょう……?
打越氏:
これは先ほどの「カルト」の話にも関係しますが、僕はNetflixの『ブラック・ミラー』という作品が大好きなんです。
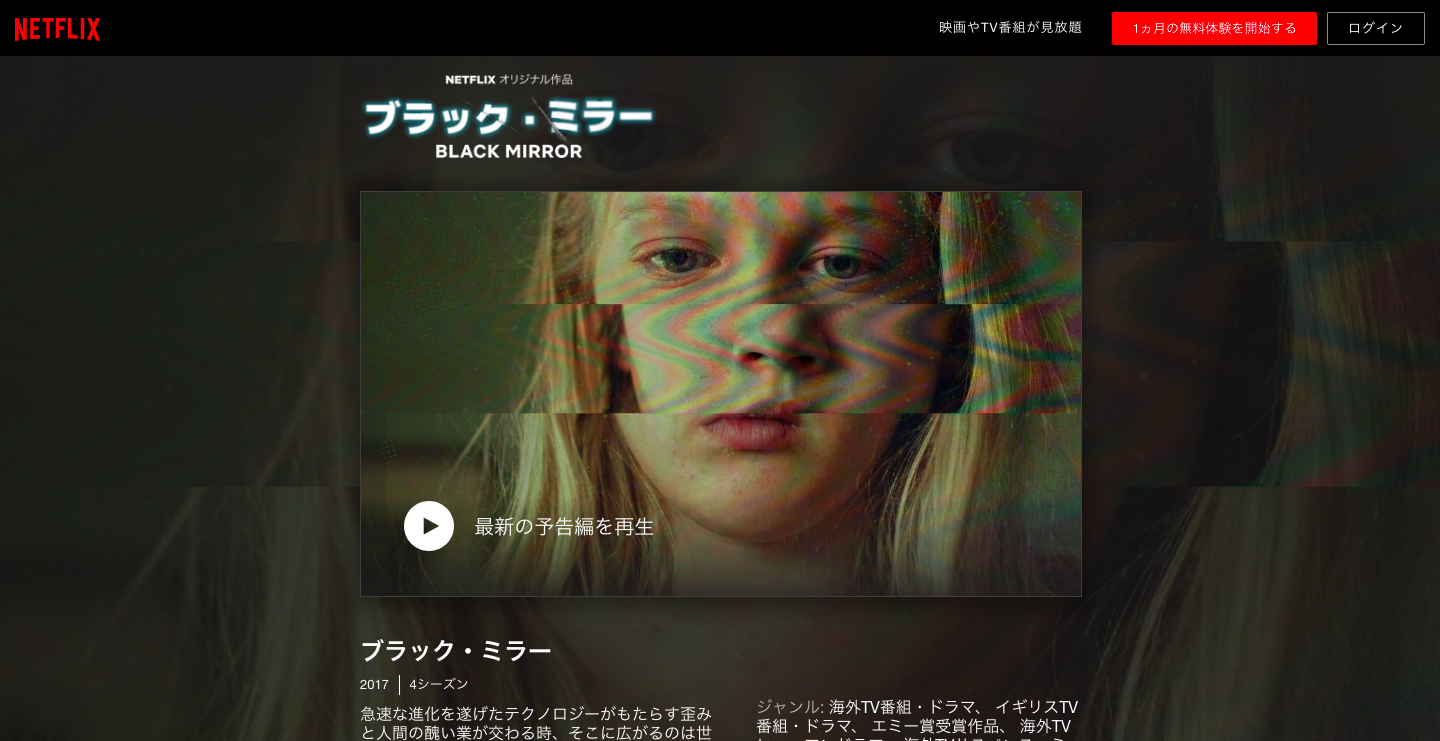
でも、あれを「おもしれえ」と言っている人って、やっぱり一般大衆じゃないと思うんです。きっと『ゲーム・オブ・スローンズ』とか『ウォーキング・デッド』よりはニッチな作品なんですね。
たぶん、そうしたニッチさの魅力の部分に、ある種の作家性があるんじゃないかと思っています。
ちなみに、小高のすごいところは、“そこも理解しつつ、もうちょいメジャーな面白さのことをわかっているところ”なんですよね。僕は一緒にやりながら、小高の力を借りて、そのレンジの幅を広げたいなと思っているんです。
──小高さんは、それについてどう思われているんですか?
小高氏:
うーん、僕は「好きなもの」がたくさんあるタイプなんですよね。というか、世の中のムーブメントにできるだけ意識的に触れて、自分のアンテナを広げておく努力は、けっこうしているんです。というのも、それをしておくと、何かを出力するときにそれらの混ぜ合わせでカオスみたいなのが起きる感覚があるんですよ。
たとえば、どメジャーすぎたらものすごくマニアックな何かを入れるし、マニアックすぎたらあえて王道にする……それで化学反応を起こしたり、「なんかひっかかる人」を増やしたい、みたいな。
そういうところも含めて、スパチュンのプロデューサーの寺澤【※】には、僕はよく「あまのじゃく」と言われてしまいますね。だから、『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』でもあんな“ヘンなこと”をやりたくなっちゃう。
あれは、虚淵玄さんからのコメントで「筋金入りの道化師であった彼らは、永続的な興行よりも一刹那に炸裂して消える花火を良しとした」みたいに言われていましたが(笑)。
※寺澤
寺澤善徳氏。代表作に『侍道』、『忍道』、『ダンガンロンパ』、『コンセプション』ほか。
──実際、あのラストは衝撃でした。続編をいつまでも作り続けようと思っていたら、あんなことはできないですし……。
小高氏:
だからまあ、理由なき反抗なんですよ。「なんかムカつく」、「なんか違うとこ行きたい」、「なんかカウンターを喰らわせたい」という……まあ、そういう過程の結果が作家性なのだと言われちゃったら、そうなのかもしれないです。
ただ、その作家性って、よくイメージされるような固定的なものというより、そのときどきの趣味や好きなものによって変わってくるような、かなり流動的なものだと思いますね。
──ちなみに、おふたりがシナリオを書いているときは、どういう感覚なのでしょう? 「これは確実に面白い」みたいな確信を持って、書いているのでしょうか?
小高氏:
うーん、「面白さへの確信」と「未知の感覚」の葛藤が、自分ひとりの中でずっと混ざりあっている感じ……ですかね。そこにはマーケティング的な根拠なんてなくて、ひたすら瞬発的に「これがいい」と思うだけ。
だから、書いているときの感覚って、もはや僕らはただの器として、宇宙パワーみたいなものの“依り代”になっているんですよ(笑)。
打越氏:
わかるわかる。“何か降りてきていることを書いてるだけ”なので、作家というよりイタコだよね。
 |
小高氏:
僕は、自分が書いた作品のセリフをほとんど忘れているタイプですけれど、たまにネットで「『ダンガンロンパ』名ゼリフ集」みたいなものを見ると、「こんないいセリフ、どこから出てきたんだ!?」と思うことがよくあります(笑)。
──(笑)。とはいえ、シナリオを書く作業そのものは、ある程度のフォーマットに沿ってやっているわけですよね。
打越氏:
それは説明に困る質問ですね……というのも、ゲームのシナリオって、毎回やりかたが違うんですよ。最初に「どうやって、この作品を形にするか」というところから考えて、シナリオの書き方そのものを決めていくんです。
とにかく、ホームシステムが違うと、書き方も違っちゃうんですよ。シネマティックなものでは、脚本みたいな感じで書くし、ポイント&クリックで進めるものだと、そのウィンドウごとに用意しますし。
小高氏:
ただ、全体の作業としては、粘土細工をいろんな角度から何度もコネるように進めていきますね。何度も読み直して「なんか起伏が足りない」と思ったら物語の波を足したり、「キャラの魅力がいまいち」と思ったらセリフを変えてみたり。
──なるほど。以前、打越さんを交えて行った「アドベンチャー座談会」で出た話で、アカデミックな視点で語ると「アドベンチャーはフォーマットで固まっており、そこに乗っかるコンテンツが違うから量産された」という説明になりがちなのですが、一方で「本当に当たった作品」を解き明かしていくと、「実は、毎回作り方がまるで違うよね」という話をしていて。
小高氏:
ああ、『ひぐらしのなく頃に』が、その典型ですよね。
──本当に革新的なアドベンチャーゲームのシナリオって、実は「ゲームのギミック」とセットで作られているんだなあ、と思った記憶があります。
小高氏:
そう思います。超ざっくり言っちゃえば、アドベンチャーゲームって「シナリオが多めのゲーム」としか言いようがないんですよ。実は“これ”といった枠がないので、それこそ色々なジャンルに自由に寄生できるジャンルだなと思いますね。
──そもそも「アドベンチャーゲームのシナリオ」という仕事自体が、かなり自由なジャンルなわけですね。だからこそきっとおふたりは、その仕事から離れない道を選び続けているんじゃないか……と、これまでの話を聞いていて思いました。
「コミュニケーションの時代」に逆張りしたい
──さて、話がアドベンチャーゲームの可能性にまで来たところで、そろそろ締めに向けて、今後TooKyoGamesも含めて、おふたりがどういったことに取り組んでいきたいと思っているのかについてお聞きしていきたいです。
小高氏:
僕は基本的に“逆張りをしたい”タイプなので、e-Sportsやオンラインゲームみたいな運営型のコンテンツが流行っている中では、「一本道のシナリオ」で勝負したいんですよね。
きっと、そうした「主流」から漏れる人たちって、常に一定数いるので、そうした人たちに向けたものを作り続けたいですね。
──そういう意味では、今のコンテンツの主流って、いったい何なのでしょうか?
小高氏:
「コミュニケーション」じゃないですか? 『フォートナイト』や『オーバーウォッチ』などもコミュニケーションが前提にあるし、映画なんかも『カメラを止めるな!』や応援上映みたいなものが象徴するように、シネコンでみんなでワイワイ観るものになりましたよね。『人狼』も、今となってはみんなで集まってやるパーティゲームですよ。
その分、「本当の日陰者」がいるところって、今はすごく少なくなりましたよね。“本田翼ちゃんがゲーム実況をしたことで、ネットでバズる”みたいなことも含めて、もはやオタク的なコンテンツは、広く市民権を得るようになっているわけですよ。
──そうですよね。ネットカルチャーや、オタク的なコンテンツって、いわゆるカウンターカルチャーに近い匂いで「認められないんだけど、これが好き」みたいな立ち位置だったと思うんです。
そうした匂いが、コミュニケーションが主流になることで、失われてしまったように感じられます。
打越氏:
あ、その話に関して、僕は実を言うと「逆なんじゃないか」と思っているんです。だって、昔で言うところのスクールカーストの下にいた現実の日陰者って、今のネットではかなり楽しんでいると思うんですよ。そういう人たちの方が、むしろネットでは日陰者ではなくなっているんじゃないかなあと。
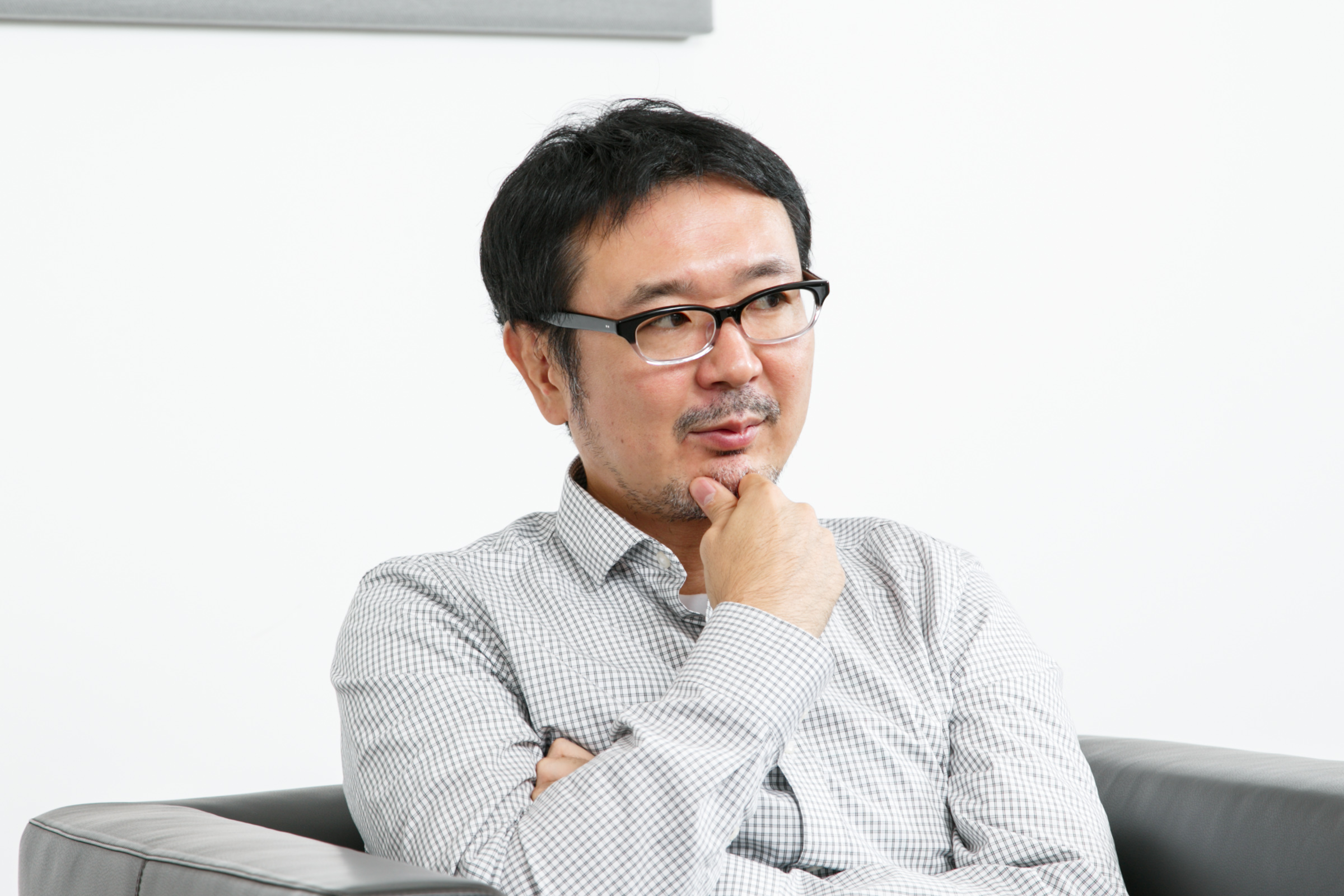 |
──なるほど。
打越氏:
そう思ったのには“あるきっかけ”があって──それは「レペゼン地球」の登場なんです。僕ははじめて彼らを見たときに、「実は彼らみたいな存在の方が、これまでネットでは肩身が狭かったんじゃないか」と思ったんですよね。そして、やっとYouTuberみたいなノリでどんどん表に出て来れるようになったんじゃないかな……と。
──それはちょっと新しい視点かもしれません。その話で言うと、これからは「レペゼン地球」みたいな存在がネットを席巻していくのでしょうかね。
小高氏:
その予感は、まさに今年のハロウィンで感じましたね。もともとはオタクたちが秋葉原のホコ天でハロウィンをやっていましたけど、それが今は渋谷にやってきたスクールカースト上位の人たちに、ある意味ではその市民権を乗っ取られたわけですよね。
その調子で、当初はオタクが楽しんでいたものが今、軒並み全部乗っ取られていっているじゃないですか。オタクがいたところに侵略者が来て、原住民はそこから逃げざるを得なくなって……という構図を繰り返しているような気がするんです。
で、そこで僕の気持ちとしては、ぜひ初心に立ち返って「ひとりぼっちの世界」に戻る動きが訪れないかなあと。「コミュニケーションとか、もうオワコンだよね」となって、みんな小説とか、ひとりでやるゲームの世界にどんどん閉じこもってほしい(笑)。
一同:
(笑)。
──でも、コミュニケーションにも良い面と悪い面があるはずなんですよね。「作家がTwitterをやることの是非」が、よく話に出ますけれど、今のトレンド的には「積極的に使いましょう、ユーザーとコミュニケーションをとっていきましょう」という方向に行っているわけですよね。
でも、「読者に向けて常時開かれているスタンスって、どうなんだろう」、ということを疑問に思うことでもあって。
小高氏:
でも、「Twitterやってないほうが、カッコイイんじゃないか」みたいな、だんだんそっちの流れになってきそうな雰囲気はあるんですけどね。
最近だと、ZOZOTOWNの前澤さんを見ているとそう思うんです。あれだけめちゃくちゃすごいことをやっている人が、もし未知のベールに包まれていたら、どれだけカッコいいんだろう……と。本当は、凄まじいカリスマとかになっていたかもしれない(笑)。
 |
──確かに、正体不明で「月に行く」という声明だけ出していたら、かなりカルト的な存在になれそうですね。
打越氏:
そういうのって、未知で謎の存在であればあるほど面白いからね。ちなみに、うちの小松崎とかもTwitterはやってないですけど(笑)。
──その流れで言うと、今後は「誰にも知られてないけれども、濃いファンの間でカルト的な熱量で支えられている」みたいな作家がたくさん生まれてきたりするのでしょうかね。
小高氏:
すでに音楽の世界はそうした「閉じた世界」になりつつあると思うんです。
ちょっと前にHi-STANDARD【※】が再結成したとき「発売日を知らせずに、いきなりレコード屋に並んで、知っている人たちだけが買う」みたいな企画をやっていて。そういう例に限らず、音楽やマニアックなアイドルみたいなものに関しては、「普通の人はぜんぜん知らないけど、ファンから熱量高く支持されている」みたいなことは多いですよ。
※Hi-STANDARD
1991年に結成された、スリーピースのパンク・ロックバンド。2000年に活動を休止し、メンバーそれぞれの個人活動を経て2011年、活動を再開。
『人狼』も、誰がやっているかわからない、未知で、危険な匂いがしていた界隈だった頃が一番面白かったし、僕が大好きだった頃の「ももクロ」も、あのアングラ感が良かったんですよね。
これからも、趣味の細分化が進んでいるがゆえに、ひとつひとつの閉じた世界でアングラ的に楽しめるものは増えていくんじゃないかと思いますよ。
──しかもそれは、SNSなどで安易には拡散されないわけですよね。
小高氏:
きっとそういうのって、SNSに書こうとは思わないんですよ。僕の場合、めちゃくちゃな内容のVシネ映画とかについて友人と話すのが大好きで。
たとえば……竹内力と哀川翔が出ているVシネのヤクザ映画『DEAD OR ALIVE 犯罪者』の終盤で、急に“ロケットランチャー”や“かめはめ波”が出はじめるんですよ。

──(笑)。
小高氏:
そこで「ここまで普通のヤクザ映画だったのに!」と度肝を抜かれるわけです(笑)。で、そういう話って、別に見知らぬ誰かにシェアしたいとかではなくて、直接会ってわかっているヤツと「あれやばいよね」って、延々と語りたいタイプのものなんですよね。
──それで言うと、『ダンガンロンパ』はまさに、結果的にメジャーになったかもしれないけれど、最初は限られた「俺だけがわかっている」みたいな感覚があったと思うんですよ。
小高氏:
でも、初週は全然伸びなくてね(笑)。一番大きかったのは、まさに虚淵玄さんとか、奈須きのこさんとか、成田良悟さんといった、あの界隈の人がTwitterとかでめちゃくちゃ長々と語ってくれたことでした。そこからクチコミ的に、じわじわ広がってくれたんですよね。
実は今更ながら、ちまちまプレイしていたダンガンロンパをクリアしたのだが。あまりの傑作ぶりにもうグゥの音もでねぇ。この神ゲーに敬意を表し、しばらくアイコンをモノクマ校長に変更しておきたいと思う。http://ow.ly/57O8C
— 虚淵玄 (@Butch_Gen) June 1, 2011
ただ、ある意味ではそこが『ダンガンロンパ』の限界で、『ペルソナ』になれない理由だと思うんです。やっぱり、どこまでいっても、根っこにあるのはオタク的な精神性によって作られたものですから。
「未知」を追い求めて独立した
──なんだか今日の話を聞いていると、ところどころに出てきていた言葉である“「未知」なものに魅かれる”というのが、おふたりの生き方の本質なのかなと思いました。もう、どうなるかもわからないままに飛び出した感じも含めて、「未知」を求めて独立したんじゃないかなと。
打越氏:
そうかもしれませんね。やっぱり、会社にいると「何年後にはこうなるんだな……」みたいな自分の姿が見えるし、その先に65歳で定年退職する未来が見えちゃうんですよね。なので、「あえてどうなるかわからないところに飛び込まないと、面白くない」というのはありますよ。
小高氏:
そうね。60歳とかで会社員……って、想像すると価値観に合わなさすぎて「ヤベー」と思っちゃう。「まだ生き延びているのかよ」みたいな感じだし、もっと、早く討ち死にしたい(笑)。もうずっと、死に場所を求めていますね。
──いろんな経験も含めて、良くも悪くも、会社員でできることが「既知」になってしまったタイミング……だったんですかね。
小高氏:
昔の自分だったら「会社作るなんて怖い」とか「失敗したらどうすんだよ」なんて思っていたのでしょうが、実際にそれをやろうと思った一昨年くらいのタイミングには、まったくそんなことを思わなかったですしね。
もう、それくらいの未知の刺激がないと体がダメになっちゃっていたんですよ。「独立した経緯は?」みたいに聞かれて正直ピンと来ないのも、そういう刺激を求めることが、自分の中でもう自然になっちゃったからかもしれません。
やっぱり、中学生のときから“破天荒なほうがカッコイイ”と思っちゃっているんですよ。「宵越しの銭は持たねえ」みたいな(笑)。
──打越さんの方は、どうなんですか?
打越氏:
え、僕は貯金してますよ?
一同:
(笑)。
小高氏:
でも、打越のほうがよっぽど破滅的なんですよ。この人、ぜんぜん家に帰らないし。
 |
打越氏:
まあ、若い頃は破滅的への憧れもあって大学を辞めたりしましたが、さすがに今はもっと素直に「この人と一緒に仕事したい」みたいな気持ちで動いていますよ。……家には帰りませんけどね。
──(笑)。最後にこれだけ聞かせてください。5年後や10年後に、おふたりはどこを目指しているのでしょうか?
小高氏:
まず、仕事で得たお金を全部ベットして、自分たちのインディー作品を作ろうというのは本気で思っていますね。それはものすごいリスクだと思うんですが、「まったく売れなかったらどうするのか」みたいなことは、考えていませんね。でもまあ、今のうちのメンバーは、そのリスクを負ってもいいと思っているわけですよ。……まあ、これが20~30人といった規模の会社になっちゃうと、「本当にそのリスクを負っていいのか君は」みたいな確認をいちいちできなくなっちゃいますけど(笑)。
打越氏:
個人的にぼんやりと思っているのは、海外をうろうろしたいな、と。とにかく新しい土地へ行けば、言語をはじめとして、あらゆることが未知じゃないですか。いずれにしても、夢物語かもしれないけれども、自分の人生の先を見たくはないですね。
小高氏:
俺も、5年後10年後なんて来なければいいのにと思って生きているよ。金持ちにも、デカい会社にしたいとも思わない。かと言って、フリーとしてひとりでやっていくのもヤダ。老いるのも飽き飽きですね。そもそも、そんな先の未来があるなんて信じたくない。
──今日の話、全体を通じて、「思っていたよりも展望があるわけじゃないし、むしろその未知さを楽しんでいる」ということがひしひしと伝わってきました。
小高氏:
いやもう、展望なんて、全然ないですよ(笑)。たとえ作品が当たったとしても、「そのあと何するんだ、どうしたいんだ」というのはまったく考えてないっす。10年後生きているのが幸せなのか、死んでいるのが幸せなのかもわかりません。
もはや、死んでしまっていてもいいかもしれないよね?
打越氏:
いや、俺は普通にイヤだよ?
一同:
(爆笑)。
──ということで、そろそろお時間です。今日はとても率直なお話をいただき、ありがとうございました!(了)
 |
「こんなにも率直な話でよかったのだろうか」──我々は取材を終えたあと、そう思わざるを得なかった。
なぜなら、「独立の理由」を語るふたりのその語り口は、抱えている悩みまでもてらいなく話してしまうほど、とてもストレートなものであったからだ。その“あっけらかん”とした言葉の数々に、まずはぎょっとさせられた。
しかし──その心境のほうは、いささか複雑なものであったように思う。とりわけ「勝てない」という言葉が印象的だったが、インディーにもAAAにもなれない状況の中、クリエイターとしてどう生き延びるか……その課題の部分に関しては特に、決して一枚岩とは言えないさまざまな考えがある。
それが今のコンシューマーゲーム業界において、「クリエイターとして生きる」ことの難しさであることを、改めて認識した次第である。
しかしながら、ふたりは色々なことを考えたうえで、それでも「未知」に向かってとにかく飛び出していったのだ。そこには「クリエイターという人種」の、ある種の生き様や、性(さが)のようなものなのだろう。
いずれにしても、その心意気を、ひとりの「カルト」の信者として、応援するのみである。
その複雑な胸中について率直に吐露していただいたことに、心より感謝するとともに、おふたりの会社の一層のご盛栄を願ってやまない。
【あわせて読みたい】
「不思議のダンジョン」の絶妙なゲームバランスは、たった一枚のエクセルから生み出されている!? スパイク・チュンソフト中村光一氏と長畑成一郎氏が語るゲームの「編集」「不思議のダンジョン」シリーズを手がけてきた、スパイク・チュンソフトの中村光一会長とディレクターである長畑成一郎氏に話を聞いた。
関連記事:
『ダンガンロンパ』を生み出した小高和剛氏が率いる新会社「Too Kyo Games」では4つの新プロジェクトが進行中。打越鋼太郎氏や小松崎類氏が所属するインデペンデントの会社に
『UNDERTALE』トビー・フォックス×『東方』ZUN×Onion Games木村祥朗鼎談──自分が幸せでいられる道を進んだらこうなった──同人の魂、インディーの自由を大いに語る





































