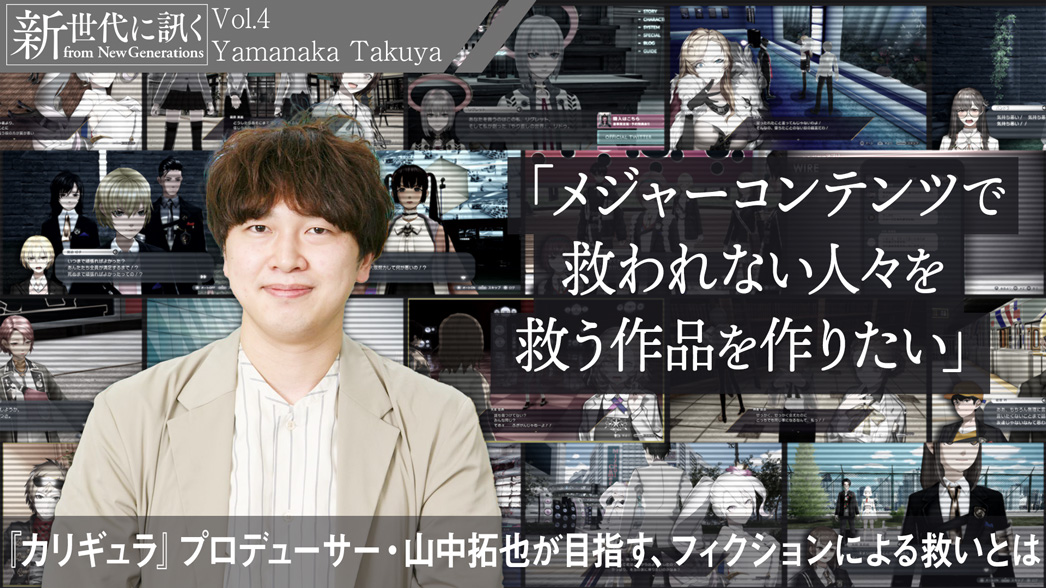「わかりにくいものがわかったときの快感」を与えるために、あえて記号的な表現を避ける
──それでいうと、『カリギュラ』含め作品を通して、山中さん自身がブランディングとしてではなく、守り通してるようなものってあるんですか?
山中氏:
「生っぽさ」というのは常々言っています。たとえば、現実にはあんまり起こらないような会話を作らなかったりですね。
僕はよく例として出すんですけど「あれは嘘をついている目じゃない!」ってセリフが嫌いなんですよ。嘘をついている目ってどれ!?って思いませんか(笑)。
──たしかに(笑)。
山中氏:
そういう現実にほとんどないようなセリフで、脚本を無理やり展開させていくことってよくあるんですが、それはやめたいと思うんです。
もうひとつわかりやすい例だと、「キャラの髪の色が性格を表している」という表現も嫌なんですよ。「赤い髪の人は熱血」って、そんな人間って単純じゃないはずです。
──ああいうのって分かりやすいから便利な側面もありますけど、現実に近づけると難しいですよね。
山中氏:
ふつう、キャラクターデザインって「シルエットでもわかるようにしなさい」というのが常識なんですが、それも嫌なんですよ。だから、たとえそれが売るのに不利になるような生っぽさであっても、自分の作る作品では踏襲していきたい。
僕がいわゆる監督的な立場でいれるので、そのへんに関しては全部破壊しにいっています。『カリギュラ』のキャラの色合いやシルエットも、記号的なわかりやすさは捨てています。同じ色が被っていてもいいし、キャラごとのカラーも分けていない。
普通はそういう演出はわかりやすいし必要なんですけど、「わかりにくいものをわかったときの快感」って、一生忘れないと思うんです。それぐらい、「わかりにくさをわかってもらったときの結びつき」というのを大事にしたいんです。
あまり気づかれづらいですけど、お芝居でも記号的な表現は排除していますね。息つぎや喋っている最中のノイズなんかも、極力切らないようにしいています。
人間だったら喋っていてどもる時もあるし、音がかすむときもある。そこに生まれる間とか、息をのむ感じとか、唾液の感じとかが、そのキャラクターに生きている感じを与えてくれると思うんです。

──なるほど。ある種のテンプレや記号的な表現に対する違和感みたいなものが山中さんの原動力なんですね。
山中氏:
そうですね。
──そうすることで届く範囲が狭まることはわかっていながらも、やっぱりそこに価値があると思ってそうするわけじゃないですか。その価値っていったい何なのでしょうか?
山中氏:
根本的に、自分がなんでそんなものを作るのかを言うと、「自分が100%好きなものが世の中にないから」だと思うんですよ。すごく好きな作品はいっぱいあるし、自分の理想の90%ぐらいは素敵な作品たちが満たしてくれるんですけど、やっぱり100%になるようなものは自分で作らないと、存在しない。
自分が100%救われていない以上は、同じように世の中に今ある作品で100%救われていない人が絶対にいる。自分の癖(ヘキ)というか、そういうところに対して実直に作っていくのが僕の生きる道だろうなと思いますね。
──「俺はこれが気に入ってるんだよ」と他人にオススメするのって、ある種の自己表現じゃないですか。それに『カリギュラ』を選んでくるってすごいことですよね。
山中氏:
僕はミクシィ世代なのですが、ミクシィではマイコミュニティという機能がトップページにあって、自分が属しているコミュニティが、9つのサムネイルで並んでたんです。あそこに並べるのって、「自分の見せたいもの」だったじゃないですか。
『カリギュラ』は、願わくばそこに並んでいてほしい作品なんです。「自分ってこういう人間なんだよと」いう形で、いわばおすすめ映画を語るのと同じで『カリギュラ』を選んでくれる人がいるといいなと思いますね。
 |
差別を描くには、差別をする人を描かなければいけない
──『カリギュラ』では「タブーを犯す」というのもテーマのひとつになっているかと思いますが、なぜそういうものを描こうとしたんでしょうか。
山中氏:
まず、「やっちゃいけないことをやりたくなる」という心理が「カリギュラ効果」と呼ばれていて、それが『カリギュラ』の全体的なコンセプトですね。
「ずっと仲良くしてきた人を裏切る」みたいなことって、ゲームの中だと自然とやっちゃってることなんですけど、そこでゲームをすごく現実に近づけることで「普通にやってるけどよくない事だよね」とか「これ現実だとタブーだよね」と思ってもらえるような気持ちが強くなると思うんです。
普通だったら危なくてやらないことも、お話をつくる中でもできるだけ入れようと思っています。前作でいうと、美笛ちゃんというキャラが太ってる人をめちゃくちゃに罵倒するシーンがあるんですけども、普通ならこういうシーンは絶対に入れないほうがいい。

──確かに危険ではありますよね。
山中氏:
作り手としては絶対にこういう表現はやらない方がいいんです。実際、危険なだけなんで。でもやっぱり、差別を描くには、差別している人を描く必要がある。そこに触れずに、「差別は良くない」と語るのは回りくどい上に嘘になってしまうので。
だからやっぱりどうしても、差別を描くなら差別主義者というものは登場しなきゃいけない。でも、『カリギュラ』の場合はそれが味方側にいるんです。
物語の味方って本来全員好かれなきゃいけないんですけど、僕の場合は別に好かれなくていいよねって思っていて。「味方側のキャラが間違っていることをする」というのは、僕なりのタブーに対しての向き合い方かもしれないです。

──差別される側だけでなく、差別する側の人のパラレルに描いているわけですよね。
山中氏:
そうですね。「たまたま集められた仲間達が全員良いやつ」というのは嘘だと思うので(笑)。それに加えて、一度間違いに気づいたからって、そのあと一切間違わないというのも嘘だと思うんです。別に一度叱られたからってすぐさま真人間になるわけじゃないし、何度も過ちは繰り返してしまうものだと思います。
──そういう面も含めて、『カリギュラ』ってけっこうプレイヤーに対して厳しいですよね(笑)。
山中氏:
厳しいですね(笑)。
──登場人物は「現実に帰りたくない」と言うし、キャッチコピーでも「現実」と書いて「地獄」と読ませたり。でも結局は、現実に帰らせようとするじゃないですか。
フィクションの中で楽しいだけの作品もこの世に存在していて、それでいいじゃないって思う人もたくさんいる中で、『カリギュラ』は「現実でコミュニケーションを取りなさい」ということをプレイヤーに伝えますよね。それってなぜなんでしょう。

山中氏:
これは僕個人の思想の話になっちゃうんですけど、「この世の中に差別がある。その中でも頑張ってそれなりに生きましょう。」と思う部分が強いんです。もちろん、職業差別や性差別などの問題で現実的に動いてる人たちってすごくかっこいいなあ、憧れるなあって思うんですけど、みんなそこまで強くはないし、みんな世界を変えるためにカロリーやコストをかけられる人たちばかりではない。
なので『カリギュラ』に関しては「世界ごと変えましょう」ではなくて、そういう世界が現実にあるってこと自体は認めて、その中でどうやって生きましょうか、という話なんです。
「現実は地獄だ」とは言っても「理想の世界に逃げましょう」ではない。理想の世界やフィクションの世界というのはあくまで一休みやひとときの癒しを得る場所でしかなくて、結局は僕たちが向き合うところは現実しかないわけで。「そこでやっていくしかないんだから、頑張るしかないよね」というのが根本にあるとは思います。
──山中さんにとって、現実はどういう意味で地獄なんですか?
山中氏:
「ぜいたくな悩みだ」と怒られるのを承知で言えば、「いつまでも幸福感が得られない」という地獄ですね(笑)。
それなりに頑張ってるつもりだし、自分を客観的に見ると20代でゲームを作らせていただいて、アニメ化もされて幸せなはずなのに、感覚として全然幸福な感じがしないんですよね。「いつになったらこの状態が終わるんだ?」という感じで、生ぬるい地獄をずっと味わっている感じがしますね。
自分の人生の終着点がどこに向かっているのかわからないまま、止まり方もわからず進み続けるしかないというか。
 |
「軸足は絶対ゲームに置いておきたい」
──山中さんはゲーム以外でもクリエイターとしての活動を広げていますが、主戦場はどこになるんでしょうか?
山中氏:
ゲームが主戦場であるという認識はありまして、軸足は絶対ゲームに置いておきたいなと思っています。
──それはなぜでしょうか?
山中氏:
すごく偉そうで恐縮なんですが、僕はどちらかといえば作家型だと思うんです。自分の作りたいお話があって、それを受け取ってもらうための手段としてゲームという媒体を選んでいる、という感覚がある。
読み終えたあとに何か新しい気づきを与えたり、今までの考え方が改まるようなお話や体験を作るというのが自分の理想なので、それを満たしてくれるのはやっぱりゲームかなと思っています。ゲームはインタラクティブなものですから、そういう体験を得るにはいちばん相性が良いのかなと。
──たしかに「考えが改まる」って受け身だけでは難しいことですよね。そこに山中さんが作りたいものをゲームで表現する必然性があるんですね。
山中氏:
一方で、ゲームだけやっているのも危険だなとも感じています。僕はゲームにおいてはプロデューサーになってしまっているので、生きていてすごく怖いときがありますよ。プロデューサーって基本的に嫌な奴が多いんで(笑)。
──(笑)。
山中氏:
それはなぜかというと、意思決定のトップがゆえに「直しが入らないから」だと思うんですよ。
──なるほど。
山中氏:
「その方向は違うよ」って言ってくれる人がいなくなるんで、プロデューサーだけをやっていると自分の知らないうちにどんどん偏っていったりする。
僕はそれが怖くて、ゲームの『アイドリッシュセブン』や、アニメ『SDガンダムワールド』のなどで、お話を書かせていただいたりもしたんです。別の分野で現場に入ることで、「誰かの直しが入る」という状況を、常に軸足以外に作っておきたいと思っています。こんなふうに、自分の価値観で作る環境と、他人の価値観の中で作っていく環境の2軸があるのは、自分としてはかなり理想的な環境だと思っています。
今後はアニメはもちろん、機会があれば実写映像にも挑戦したいと思っているのですが、そこからゲームに戻ったときに持ち帰れるものはすごく多いと思っています。ゲーム業界には一個上の世代のクリエイターさんたちが多いので、彼らと真っ向から戦うというよりかは、また別の方向で場数を踏んで成長していかないと、世の中に認められないなと思っていますね。(了)
「新世代に訊く」の第4回はいかがだったろうか。
山中氏の「メジャーコンテンツで救われない人々を救う作品を作りたい」という思いは、ブランド力も予算も少ない環境でゲームを作るためのしたたかな“生存戦略”でもあった。
しかし同時に、ひとりひとりのプレイヤーと向き合う姿勢をみせ、同じ目線から心に抱える悩みを考えていく。「優しすぎる」がゆえにカウンセラーになることを諦めたというエピソードも頷ける、山中氏のひととなりが伝わるお話を訊くことができたように思う。
『カリギュラ』という作品をプレイし、そこで何か感じたものを現実に持ち帰り、生きていく。ゲームやコンテンツは、他人の気持ちや自分の悩みと真剣に向き合い、力を与えてくれる存在であることを改めて実感した取材だった。
世界も自分も、急に変わることはないだろう。だから、結局は地獄のような現実でなんとかして生きていくしかない。そんなとき、何か「自分に向けられたもの」がこの現実に存在するということは、きっとそれだけでも救いになるんじゃないだろうか。このインタビューが、そんなちょっとした救いのきっかけになることができれば幸いだ。