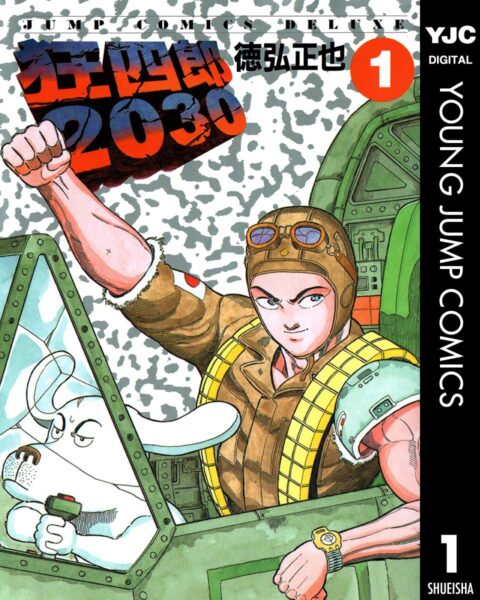プレイヤーが主人公と同化するVRでは、物語から得られる感動が10倍になる
──これに関しては僕なりの見解もあって。他メディア展開だとか移植だとかって、既存のファンがある程度は買うわけじゃないですか。その時に既存のファンの人たちが、応援隊として機能し得るかどうかが重要で。たとえ数が少ないながらも応援の土台みたいなものがあれば、そこから外に広がることができるんです。そういうファンの配分の違いとか、性質の違いみたいなものがけっこう影響しているのかな、と最近は感じています。
だからそこで重要なのは、ファンが思わず応援したくなるような熱量だとか、ファンの忠誠度(ロイヤルティー)をどう作るかだと思うんです。VRはそれに適していると思いますか?
岸上氏:
VRはわざわざゲームの中に入り込むわけだから、遊んだ人は誰でもその世界を好きになってくれると、最初はみんなそう思っていたんです。でも意外とそうじゃなかったので、VRブームが冷めてきたんですけど。
でも僕は、VRで遊んだ人はやっぱりその世界を好きになってくれると思っていて。ただ、最初の頃に出たVRゲームはミニゲーム的なものが多すぎて、短い時間しか遊ぶことがなかったから、好きになるところまで到達しなかっただけなんです。実際、『東京クロノス』や『アルトデウス:BC』はプレイに10時間、20時間かかるんですけど、最後まで遊び終わった人はものすごく感動してくれて、すごい熱量になっているんです。
特に『東京クロノス』は、VRじゃないと絶対に感動してもらえない作品だと思います。あのゲームを普通の画面でノベルゲームとして遊んだら、VRゲームほどには感動してはくれないだろうなと、これは自戒も込めて言うんですけど。でもVRだと感情を動かす力が10倍ぐらいになっていて。だから感動してくれているんです。
──「VRだと感動が10倍になる」というのを、もう少し具体的に説明してもらってもいいでしょうか。
 |
岸上氏:
VRゲームと他のゲームとの大きな違いは2つあって。まず1つ目は「体感」で、特に手の動きなんです。手の動きを使って実際に物を触ったり、投げたり、戦ったりできるから、ものすごく入れ込める。これがFacebook、Oculusを中心に、世界中のVRゲーム会社が押している部分で。
もう1つはキャラクターの存在感、いわゆる「プレゼンス」ですね。今こうやって対面で話していると、言葉だけじゃない感情が分かるじゃないですか。表情も分かるし、仕草も分かるし、感情の伝わり方が違う。Zoomの画面で怒られても「はいはい」って感じなんですけど、VRのアバターを使った会話で怒られると、本当に怒られているような感じになるんです。
そういった感情の伝わり方は、他のゲームよりもVRゲームのほうが明らかに大きいんですよ。だから共感しやすいし、感情移入しやすい。さらに、主人公目線の一人称視点でVRゲームをプレイする場合には、もはや感情移入ではなくて「同化」になるんです。ユーザーが無意識にそのキャラクターを演じてしまうんです。それは心理学的にもある現象らしいんですけど。
だから主人公の気持ちとほぼ同化していて、目の前にいるキャラクターの感情もより伝わってくる。それで感動させる作用が一気に大きくなるんだというのがありますね。
──これは余談なんですけど、最初期のオンラインゲーム業界で、既存のボードゲームやアナログのカードゲームをオンラインに移植したら、まったくおもしろくなかったんです。対面でやるとメチャクチャおもしろいのに、オンラインだと味気なくなる。
それは結局、対面で遊んでいるボードゲームというのは、目の前にいる対戦相手の身振り手振りといった情報量も含めた形で遊ばれていて、それが重要だったんだという話があって。目の前の人間が発する膨大な情報量を元に判断したり駆け引きしたりするから、対面型のゲームはすごくおもしろい。一方でそれをただオンライン化するだけだと、そういった情報が全部スポイルされてしまって、ゲームのルール情報だけの無機質なやり取りになってしまうからつまらないんだ、という講演が以前にあって。
だから、ふだん何気なく受け取っている人間の体感的な情報が、じつはすごく重要だし、おもしろさにもかなり寄与しているんです。それで言うとVRって、そうした体感的な情報を、現時点では唯一表現できるメディアじゃないですか。だから岸上さんがさっきおっしゃった感情の伝わり方の話は、すごくよく分かります。
そういう生理的な体感の部分って、エンターテイメントの世界でも、まだまだ突き詰められていないものだと思います。そうしたものとストーリー的な体験が組み合わさったものは、たしかにすごくポテンシャルがありそうですね。
岸上氏:
「目が合う」体験ってまだ、VRゲームでしかできないですよね。そこは本当に可能性の塊だと思います。アメリカのゲーム会社って、意外とそういうことを重視していないので。
──どうしてもシミュレータみたいな方向に寄っちゃうんですよね。『スター・ウォーズ』のゲームとかも出ていますけど、やっぱり遊園地のアトラクションっぽいというか。そういう意味での対人コミュニケーションを掘り下げたVRゲームは、まだ今は『サマーレッスン』ぐらいかなと。
岸上氏:
『サマーレッスン』を作った玉置絢さんとは仲が良くて、ふだんからよくしゃべるんです。“同志”なので(笑)。『サマーレッスン』からは本当に沢山のことを学ばせていただきました。
キャラクターとただ接するだけだと、それは短時間のミニゲームにしかならないじゃないですか。でも、人間には単純接触効果という現象があって、何度も繰り返し会っているとそれだけでその相手を好きになるんです。だから、VRで目が合うといったインパクトを担保した上で、本当はキャラクターと何回も会わないといけない。『アルトデウス:BC』はストーリーが長いので、必然的にキャラクターと何回も顔を合わせることになるんですけど、それ以外のゲームでもこの「長時間」や「何回も」といったところを上手くゲームデザインに落とし込めると、これはIP化につながる可能性がかなり生まれると思います。
──VRでキャラクターを好きになるタイプのゲームって、海外では何かあるんですか?
岸上氏:
海外ではほとんどないんですよね……。ちょっと別ベクトルなんですけど、『Moss』っていうVRアドベンチャーゲームがあって、最近100万本を突破したんですけど。このゲームは白いネズミをうまく誘導していって、パズルを解いたり敵と戦ったりするんです。これはネズミと自分の相互作用がおもしろくて、このネズミのことがどんどん好きになっていくんですね。
でもたしかに、他にはあんまりないかもしれません。欧米のゲーム会社はどうしてもアトラクションにするか、FPSにするかといった感じなので。たしかにそれが売れ筋だし、Facebookもそういうものを作れと言っていますから。でも一方で、日本の開発者に期待されているのはゲームデザインの進化も含めて、それとはまた違うものなのかな、というのも感じますね。
──「VR×キャラクター」とか「VR×物語」みたいな部分ですよね。そこは『東京クロノス』や『アルトデウス:BC』の成功を受けても、なお空白に近いというか。
岸上氏:
ベンチャー的なところでは他にも出てきているんですけど、まだまだこれからですよね。
そういえば、先ほどのボードゲームのお話で思い出したんですが、最近遊んだVRゲームで、『Demeo』という作品がすごくおもしろかったんです。今年の5月に発売されて、VRゲームで今いちばん売れているタイトルなんですけど。
このゲームは「テーブルトークRPGをVRで遊ぶ」というコンセプトになっていて。みんなでダンジョンのマップを囲んで、サイコロを振ったりカードを使ったりしてキャラクターのコマを動かして、ダンジョンを探索していくんです。1人用プレイもあるんだけど、最大4人のオンライン協力プレイもできて、どっちもおもしろいんですけど。
『Demeo』はとにかく、FPS系以外で久しぶりに出てきた、すごくおもしろいVRゲームですね。「なるほど、TRPGをこうゲーム化するんだ」って感じで、ちょっと悔しかったです。
今回の資金調達はこれまでの路線に加えて、「多人数で遊ぶ運営型のVRゲーム」を作るため
──資金調達の話に戻りますけど。資金調達を受ける前から続けてきた『東京クロノス』や『アルトデウス:BC』のような文脈の、ストーリーあるいはキャラクターを主としたIPのラインは、これまで通り続けるわけですよね。
岸上氏:
はい、そうです。
 |
──ただ一方で今回の資金調達を受けて、もう1ライン作りたいとお聞きしました。しかも、そちらはIPのラインとはまた違う運営型のタイトルだ、ということですが。それはいったいどのような狙いがあるのでしょうか?
岸上氏:
VRで運営型のタイトルというと、日本人がまず思い浮かべるのは『ソードアート・オンライン』や『レディ・プレイヤー1』のようなものなんですよ。つまりMMORPG的な文脈ですね。
一方で、アメリカが考えるVRの運営型タイトルは、FPSなんです。『フォートナイト』や『APEX』みたいなタイトルをVRでずっと続けていく、みたいな。これはもう実際に出てきていて、すでに人気があるんです。『Population:One』という作品なんですけど。ただこのラインは、自分たちが開発しても戦えないから、絶対にやりません。
僕らがやろうとしている運営型のタイトルは、正直なところを言うと、まだ企画が立ち上がっていないので何をやるかは決まっていなくて。
たとえばMMORPGみたいな形でみんなで遊ぶというのは、いちばん王道なんですね。でも、ただそれだけだと他の企業もいずれは参入してくると思うので、それをストレートにやるだけでいいのか、という悩みはあります。そこに何かユニークな視点を入れ込むことができたら、僕らがやる可能性はぜんぜんあると思います。
それ以外にマルチプレイヤーのゲームでずっと続いていくものだと、「人狼ゲーム」みたいなアプローチもありますし、『Dead by Daylight』や『第五人格』みたいな非対称型のアクションゲームもありますし。そういうずっと続いていくゲームで、しかもマルチプレイというのがいちばん重要なんですよね。
VRゲームって、1人用プレイのおもしろさはキャラクターとのインタラクションですけど、もうひとつのおもしろさは他の人と一緒に遊べることなんです。誰かと一緒にその場にいるような感覚でゲームを遊べるというのは、さっきのボードゲームの話と同じですよね。他の人とのインタラクションとか情報量も込みで、マルチプレイを遊べるんです。
そういったものを作りたいというのがまずあって、「じゃあ何にしましょう?」というのは正直な話、これから考えることですね。それを一緒にやれる人を今求めているし、そのための資金調達というのが大きいんですけど。
──マルチプレイの意味は分かったんですが、それが「運営型」である必要性は、どういったところから生まれてきているのでしょうか?
岸上氏:
これは業界の通説になっているんですけど、アクティブユーザーの数が1000万人を超えると、運営型のゲームやマルチプレイのゲームが出てくると言われていて。じつはこのまま行くと2年以内には、VRのアクティブユーザーが1000万人を超えるんです。Oculus Quest 2が今、北米だけで460万台売れていて、他の国を含めればもっと大きな数になりますから。もちろん、PlayStation VRとか他の機種もありますし。
これから2年以内には、上手くいけばOculus Quest 2だけでもアクティブユーザー1000万人が達成できる。そこでFacebookのマーク・ザッカーバーグが最近、「ソーシャルなVRゲームを求めている」ってよく言うんですよね。VRがいちばん普及しているアメリカだと、みんなで遊べるマルチプレイのVRゲームがいちばんホットで、今後もより増えていくだろうという予想なんです。
だからそれに対して日本でも、みんなで遊べる日本らしいタイトルを世界に向けて作りたい、というのがあります。今後の動きが大きな流れとして見えているし、プラットフォーム自身も欲しているのを公言している。それが大きいですね。
今回の増資に関しても、こんなふうに2年後の数字がある程度見えてきたことで、そこに向けて今から2、3年以内に運営型のタイトルを出さなきゃいけない、という想いがありました。「焦り」はないですけど、「急ぎ」はありますね。
あと、日本だとまだまだなのでむしろ増えてほしいぐらいなんですけど、アメリカだと今、VRゲーム会社の勢いがスゴくて。とてつもなく伸びているので、そこの危機感は強いですね。
──VRでそうしたソーシャルなゲームが求められているというのは、どうしてなんですか? VRでアトラクションっぽいゲームが主流になるのは、VRというメディアの特性から逆算すれば、よく分かるんですが。
岸上氏:
ソーシャルなVRというと、VR Chatがあるじゃないですか。VR Chatがなぜ人気なのかというと、やっぱりさっきの話と同じで、情報量が莫大なんですね。本当に他人と会っている気がする。その上でなおかつ、空を飛んだり物を壊したりといった、現実では絶対にできないようなこともできる。そこがいちばんのポイントだと思います。実際に他人と会っているような感覚を味わいながら、現実ではできない体験をできるのが、ソーシャルなVRゲームの魅力ですね。
──今、VR Chatを楽しんでいるユーザー層は、どういう人たちなんですか?
岸上氏:
意外と年齢層が低いんです。大学生とか20代ぐらいがいちばん多いんですよね。そういう意味ではたぶん、平さんたちが昔『ウルティマ・オンライン』みたいなオンラインゲームを始めたのと、まったく同じ動機でやっているんだと思います。
──そう言われて自分を振り返ってみると(笑)、他人とやり取りすることがすごく楽しく感じられたお年頃だったのかなと思いますね。現実では知り得ない人たちと一緒にパーティーを組んだりするやり取りそのものが、すごくおもしろかったというか。
岸上氏:
僕も生まれた時からインターネットを使っている世代ですから、僕よりさらに若い世代にとっては、インターネットって日常なんですよね。だからLINEやDiscordで他人とコミュニケーションするのも、彼らにとっては日常の延長でしかなくて。そういう意味では平さんが『ウルティマ・オンライン』と出会った時のような非日常を感じられるのが、彼らにとってはVRだと思うんです。
──なるほど、非日常におけるコミュニケーションのおもしろさが、ソーシャルなVRゲームにはあると。それはすごくよく分かります。非日常のコミュニケーションか……なるほど。そう考えると、オンラインVRゲームの魅力や可能性が、かなりクリアに見えてきますよね。
岸上氏:
そうですね。あと若い人は、ソーシャルな体験に非日常な刺激を常に求めますよね。ちょっと年齢がいっちゃうと、そういうのは疲れちゃうところがあるんですけど。僕もVR Chatの熱量には完全についていけるかというとそうではないので(笑)。がんばりますが(笑)。
VR Chatはコミュニケーションのおもしろさに大きく振って、クラフトで自由に作り上げるというところに重きを置いてますね。VR Chatは自由度が大きな魅力ですが、僕らが自分で作るモノはゲームとしてルールがしっかりある形でやりたいと考えています。
これは僕の勝手な仮説なんですけど、全部をコミュニケーションに振ってしまうと、逆に共通の話題が何にもなくなるじゃないですか。MMORPGのようにひとつのルールに従って行動していると、プレイヤー間にある程度共通した話題が生まれるので、入りやすいと思うんですよ。コミュニケーションに全部振ってしまうと、それに入れない人はドロップアウトしてしまう。ちゃんとゲームルールがあるからこそ成り立つコミュニケーションがあるし、もっと大きく広がるかな、というのが僕の仮説です。
──「あのボスを一緒に倒そうぜ」という動機付けがあれば、知らない人同士でもパーティーが組みやすいというのはおっしゃるとおりですね。ゲームルールがあるからこそ、コミュニケーションの障壁を下げて、もともと接点のない人たちが会話できるようになるわけで。
代表である自分を全力で否定するような「尖った」仲間に来てもらいたい
──これまでの路線とはまた異なる、運営型のソーシャルなVRゲームを作りたいという意味はよく分かりました。そこでMyDearestでは、それを一緒に進める仲間を募集したいというわけですね。
それでは、岸上さんの求めている人物像とはどういう人なのですか?
岸上氏:
求める職種ではなくて人物像ですか。僕の採用軸で言うと「僕を脅かしてくれる人」がいちばん好きなんです。僕の言うことを聞かない人とか、クリエイティブで尖っている人が大好きで。
 |
僕は一応、この会社の代表なんですけど、僕のアシスタントって1人もいないんですよ。他の役員にはいるのに、なぜか僕だけいなくて(笑)。だから僕はアシスタントとかサポートとか、そういう人をまったく求めていなくて。むしろ僕のことを全力で否定して「自分はこういうことをやりたい」と言ってくれる人が、僕のいちばん会いたい人なんです。
MyDearestという会社は僕が全面的に前に出ているので、僕のイメージが強いかもしれませんけど(笑)。でも会社の雰囲気はぜんぜん違っていて、ボトムアップの会社なんですね。僕はあくまで方向性しか定めないので、具体的に「こういうことをやりたい」という企画はクリエイターのほうから挙がりますし。
あとは社員の雰囲気として、優しい人が多いんです。それぞれの個人が尖っているからこそ、他の人の尖りにも寛容というか。「お互いにヘンなところがあるから許容し合おうぜ」みたいな会社なんですよ。僕もそれで許されているので(笑)。だから、ふだんは穏やかなんだけどクリエイティブになると我が強い、みたいな人が多いですね、傾向としては。
──三木さん絡みの話で思い出したのですが、ライトノベルの黎明期って、良い意味で勘違いをして業界に入ってきた作家さんが多かったそうなんです。純文学の世界では太刀打ちできないし、ミステリーやSFといったジャンルもすでに大御所の作家がいる。でも新しく立ち上がったライトノベルという市場なら自分でも成功できるはずだ、みたいな。そういう良い意味での勘違いって、じつは大事だと思っていて。
それと同じようにVRの世界もまだまだ黎明期で、何かの知識だとか経験が必要だとか、そういったことはないはずですよね?
岸上氏:
おっしゃるとおりです。『東京クロノス』や『アルトデウス:BC』を見て「オレのほうがもっと良い作品を作れる」と思っている人が、たくさんいると思うんです。そういう人は超ウェルカムです。もう少し婉曲的な言い方ですけど、実際にそうやってこの会社に入ってきた人が、すでに何人もいますから(笑)。
あとは『東京クロノス』をプレイして「こんな頭のおかしい企画は、今いる会社では絶対に通らないから、こちらに来ました」という人もいました(笑)。そういうノリでぜんぜん構わないです。たしかに普通の大きな会社では通らないような企画も、ウチなら通ると思いますので。「こういうことをやりたい」と入って、実際にそれができるところが、ウチみたいな小さい会社の良いところだと思います。
──ところで今の社員数は何名くらいなんでしょうか?
岸上氏:
30名ぐらいですね。ただ、それを急激に増やしたいわけではなくて。ひとりひとりにお会いして、相性が良くてスゴイなと思う方に入ってもらって、2年ぐらい先には30名×2ぐらいのチームになればいいかなと思っています。
僕らの思想としては「もっと人数を増やしたい」というよりも「少人数でスゴいことをやろうぜ」というほうが強いです。経営者の視点で言うと、ゲーム会社のいちばんの経営的圧迫点は人件費なので、できれば少数精鋭でスゴイことができたほうがいいですから。
──以前、Dr.マシリトこと鳥嶋和彦さんに、ジャンプの編集部の話をいろいろ聞いたことがあって。その中で、編集部の人数が25〜30人程度だって聞いたんですよね。で、その時に強く思ったのが、「たった25人のチームが、日本に、ひいては世界に影響を与え得るんだ」ってことだったんですよね。
岸上氏:
その話、凄くいいですね!
僕はソニーを創業した井深大さんが大好きで。じつは井深さんが書いたソニーの設立趣意書には、「規模の大を追わず」と書かかれているんですよ。世界に対して影響を与えるのに社員の人数は関係ないっていう。僕もまったく同じ思想ですね。
人数を増やせば売り上げが上がるでしょ、というのは投資家からすれば分かりやすい論理で、それに屈するベンチャー企業がすごく多くて。それで僕ぐらいの歳の経営者が調子に乗って、余計な人を増やしたりして会社が壊れていく様子を、横目でずっと見てきたんですよ。それに対してVRは市場の大波が来なかったぶん、規模を急に大きくしたりできなかったのは、むしろラッキーだったと思うんです。
──いきなりですけど、企業文化って何だと思います?
岸上氏:
僕がいちばん思うのは、言語化されていないルールっていろいろあるじゃないですか。たとえばウチの会社で言うと、クリエイターがディレクターやプロデューサーの指示にも関わらず、めっちゃ勝手なことをしましたと。それがもしおもしろかった場合、会社によってOKにします、NGにしますの対応は違うと思うんですけど、ウチはオッケーなんですよ。それはルール化なんてまったくされていないけど、そういう空気なんですね。これが企業文化だと思うんです。
そんなふうにルールブックに書いていないことが起こった時に、社員がどう対応するかが企業文化なのかなと。
──僕は企業文化って、コミュニケーションの問題だと思っていて。社員同士に共通の理解があれば「これ、いいよね」「じゃあやろう」って、会話が一瞬で終わるんです。でも共通の理解がないと「これ、いいよね」「どうしてですか? 説明してください」「これこれこういうことです」「でもそれはあなたの主観ですよね。もっと客観的なデータで示してください」と、余計なコミュニケーションがどんどんと発生していくんです。
社員同士の間に共通の理解があることを、僕は「会社の純度が高い」と言うんですけど、純度の高い会社はコミュニケーションがめちゃくちゃスムーズなんです。一方で、会社が大きくなっていろんな人が入ってくるのは良いことでもあるんですけど、いろんな文脈の人たちが集まってくることでディスコミュニケーションが発生する。その結果、何をするにしても説明コストがかかる組織になっていく。会社の純度が下がった結果、不要なコミュニケーションにかかる説明コストが増えていくことが、いわゆる「大企業病」なんだと、僕は思うんですよね。
岸上氏:
本当にそうだと思います。説明コストが増えていくことで、お互いに不和になって、負の連鎖が続きますよね。
──今日お話を伺ったように、明確なビジョンを持って新しいことに取り組んでいこうというMyDearestさんは、やっぱり純度が高い組織だと思うんです。
岸上氏:
たしかに、そんなに説明が要らないので、いろいろとラクですね。これは良いことなのか悪いことなのか分からないんですけど、今、MyDearestは創業5年目なんですけど、ベンチャーにもかかわらずほとんど人が辞めておらずずっと在籍している方が多いんです。
採用の際、僕は基本的に1次面接の時から立ち会っているんですけど。その理由は、普通の会社なら落ちるんだけど、ウチの会社には合う、っていう人がいるじゃないですか。そういう人を1次面接で落とされたくないというのがあって。三木さんも電撃文庫の小説を選考する際に「迷ったら上に上げろ」とよく言っていたらしいんですけど。
だから入社2カ月目なんだけど「入社何年目だろう、この人」みたいな風格で、普通にコミュニケーションを取れる人もいますよ。会社に合っていれば自然とそうなるし、他の人も「この人は入社何年目だろう」なんてぜんぜん気にしないですし。
──僕も採用の経験があるから分かるんですけど、みんなついつい「自分の仕事を楽にしてくれる人」を採りがちじゃないですか(笑)。でもそうじゃないんだと。それこそ自分を脅かすような人であったり、この人ならワンチャンあるかも、みたいなポテンシャルのある人を採るべきだろうとよく思うんです。それは、僕自身もベンチャー気質なところがあるからかもしれませんけど。
それにプラスして「企業文化に合う」というと平たく聞こえるんですけど、つまりはコミュニケーションがスムーズにできそうな人ですよね。
岸上氏:
そこの「自分たちと合う」っていう部分が、いちばん大きいかもしれませんよね。ウチの採用の2次面接は、現場のクリエイター5、6人が取り囲む形なんですよ。その2次面接で現場の人たちと話が合って盛り上がっていれば、「もう採用でいいかな」と思うんです。逆にどんなに優秀な人でも、そこで盛り上がっていなかったら「違うかな」となるんですよね。
 |
──盛り上がれば採用というと、表面的に見れば「好み」だとかそういうふうに見られるもかもしれないけどそうではなくて、日常の業務にあたっていかにコミュニケーションに負荷がかからないかを見ているわけですね。
では最後になりましたが、MyDearestに加わりたいと考えている方々に対して、代表の岸上さんのほうから何かメッセージを。
岸上氏:
「僕を脅かしてくれる人」みたいな言い方をするとパンチが強いかもしれませんけど、基本的には寛容な会社ですから。あとは「自分のスゴイ考えがあるんだけど、実現できていない」という人には、ウチの会社は向いていると思います。自分のやりたいことがけっこうできる会社なので。
さっきの話とは矛盾するんですが、極論すると、他にないものがあればコミュニケーションなんてできなくてもいいんです。それは僕らが代わりにやるよ、みたいな。そういう天才的なエンジニアも実際にいますので。
とにかく、自分に何か尖ったものがあって、他とは合わないんだけどもしかしたら自分は合うかもと思ったら、どんどん応募いただければと思います。そこでポテンシャルを感じたら、ぜひ採用させていただきますので。
──IT系の会社というと、社長に何かビジョンがあって「オレについてこい」という会社が多くて。岸上さんにもそういう面はあるんですけど、一方で、これは三木一馬さんとの出会いが大きいのかなと思うんですけど、岸上さんには「自分が才能に奉仕したい」という編集者的な性質もあるのかなと感じます。
自分のビジョンは確固としてあるんだけど、一方で現場のクリエイターに対するリスペクトがあって、自分はそちらを応援する役割だ、みたいな。それがコンテンツ会社の社長としての、岸上さんの特質なのかなと思います。
岸上氏:
ありがとうございます。世間のイメージとは違ってワンマンな会社ではなくボトムアップの会社だと思います。むしろ僕は毎回、周りからボコボコに怒られているので(笑)。(了)
個人的な話で恐縮だが、筆者(伊藤)は今から6年前の2016年に、起業直後のMyDearestがVRイベントに出展しているところに偶然出くわして、とあるゲームメディアのWEB記事内で紹介している。岸上氏によると、MyDearestがメディアから取材を受けたのはそれが最初だという。
その時の展示はまるで学生サークルのように手作り感のあふれるものだったが、そこで行われていた内容は「VR空間に自然な形で文章を表示してドラマを描く」というものだった。VRで物語を表現しようとする試みは、その当時非常に新鮮だったので、筆者も興味を惹かれて取材を行ったのだ。
そう、今回改めて振り返っていただいたように、岸上氏をはじめとするMyDearestのメンバーたちは、起業直後から「VRで物語性の強い作品を作る」という目標を掲げていた。その目標に向かう歩みを一歩ずつ着実に続けてきた結果、『東京クロノス』や『アルトデウス:BC』といったタイトルを世に送り出すことができたわけだ。これらの作品が、日本はもとより世界でも高く評価されているのは、まさに初志貫徹の成果だろう。
そして2021年現在、MyDearestは9億円の資金調達により、新たな挑戦へと乗り出そうとしている。今回の取材で伺ったように、そこには今後数年間のVR業界の変化を見据えた上で、同社がこれまでにも発揮してきた強みを存分に発揮するための確かな戦略があるはずだ。
MyDearestが今後どんな新しいVRゲームを生み出すのか、筆者も“最古参”のファンのひとりとして注目していきたい。