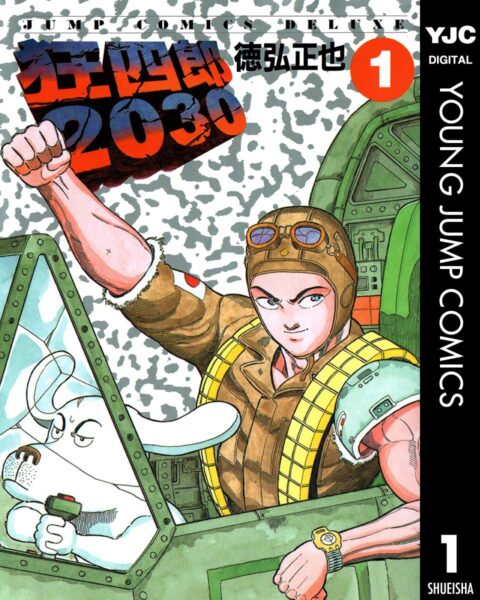MyDearestといえば、『東京クロノス』や『ALTDEUS:Beyond Chronos』(以下『アルトデウス:BC』)といった作品で、ドラマチックでボリュームのあるアドベンチャーゲームをVRで描き出すという試みを続けているゲームメーカーだ。2021年6月30日に、同社は新規投資家を含むベンチャーキャピタル数社より、新たに9億円の資金調達を実施したことを発表した。
 |
9億円といえば、インディゲームとそれほど変わらない予算規模でゲーム開発を行っているMyDearestにとっては、かなりの巨額だ。しかし何より興味深いのは、同社がこれまで手がけてきたのはいずれもVRゲームであり、今回の資金調達も基本的に、新たなVRゲームの開発を目的にしているという点だろう。
VRといえば、2016年にOculus RiftやPlayStation VRといったデバイスが登場し、「VR元年」と呼ばれて世間の注目を集めたものの、その後はあまり大きな話題になっていないため、ブームは過ぎ去ったと考えている人が少なくない。そんな中でMyDearestは、クリアまでのプレイ時間は約20時間、キャラクターのセリフはフルボイスという、一般のノベルゲームと変わらないボリュームのVRアドベンチャーゲームをリリースして、高い人気と評価を獲得してきた。今回の資金調達が可能になったのも、そうした実績が投資家から認められたからだ。
9億円の資金調達を受けて、MyDearestは現在開発が行われている「クロノスユニバース」の新作『DYSCHRONIA: Chronos Alternate』に加えて、まったく新たなVRゲームの開発をスタートさせるという。またそれに伴い、新たなクリエイターやスタッフの採用を開始しているとのこと。
MyDearestはいったい今後、どのような方向へと向かおうとしているのか。そして彼らはVRで何を目指そうとしているのか。電ファミニコゲーマーではこれまで、『東京クロノス』や『アルトデウス:BC』の作品やクリエイターについての取材を行ってきたが、今回はMyDearestという企業そのものに注目して、同社代表取締役の岸上健人氏にお話を伺うことにした。そのため取材の内容は、同社が起業された経緯などについても及んでいる。
 |
岸上氏によると、MyDearestが新たに開発しようとしているのは、マルチプレイの運営型VRゲームだという。そこにはいったいどんな狙いがあるのだろうか?
聞き手/TAITAI
文/伊藤誠之介
編集/クリモトコウダイ
撮影/増田雄介
※この記事はVRゲームを一緒に作る仲間を集めたいMyDearestさんと電ファミ編集部のタイアップ企画で
「VRで起業します」と宣言して入社したソフトバンクを“予定通り”1年で退社
──本日は、MyDearestが9億円の資金調達を受けて、今後いったいどういった方向へ向かうのかについて伺えればと思います。その前にまずは、MyDearestというスタートアップ企業がどのように立ち上がって、いかにしてここまで歩んできたかをお聞きしたいのですが。
岸上氏:
分かりました。MyDearestは、2016年に生まれた会社です。2016年にはOculus Riftの製品版やPlayStation VRが発売されて、「VR元年」と呼ばれた年です。その後、VR元年が何度もタイムリープしていくんですけど(笑)。
 |
そもそもは、僕が大学時代の時にOculus Riftの開発者キットが出てきて、それでVRにハマったんです。大学の卒業後はソフトバンクに就職したのですが、もともとソフトバンクには「VRで起業します」と宣言して入社したんですよ。入社から1年後にVR元年がやってきて、ソフトバンクにいた仲間やVRの業界にいた仲間と一緒に、MyDearestを起業したという形ですね。
──岸上さんはソフトバンクで、経営者養成学校みたいなところにいたそうですね。
岸上氏:
「ソフトバンクアカデミア」のことですね。要するに、孫正義の後継者育成機関みたいな感じなんですけど。中身としては、孫さんが興味を持っているお題に対してプレゼン合戦をして、それをメンバー同士で採点し合って、勝ち抜いた人が孫さんに直接プレゼンする、みたいな感じでした。
──それはソフトバンクの社員が参加するものなんですか?
岸上氏:
ソフトバンクグループの人と、外部の人が半々ぐらいで参加していて。僕はソフトバンクに内定していた時に合格したので、社外枠で入った後に社員になるという、ちょっと謎な感じだったんですけど。
ただ、アカデミアはあくまで業務外の活動なので、ソフトバンクの仕事としては、僕は法人営業でスマートフォンやロボットを売ったりしていました。あとはソフトバンクでのVRの立ち上げも、ちょっと手伝ったりしていたんですけど。
だから正直を言うと、ゲームとかはまったく関係のないところからの出身です。ただとにかく自分がVRとゲームやエンタメが好きで、というところから立ち上げたのが、MyDearestですね。
──ということは、最初は必ずしもゲームを作ろうとは思っていなかったんですか?
岸上氏:
そもそもは「VRでエンターテインメントを作ろう」というところからスタートしているんです。「今はお金も少ないしゲームを作るのは大変だから、まずはゲーム以外のことをやってから、後でゲームを作ろう」という考え方でした。
でも実際にVRの市場を見てみると、「VRでは絶対にゲームしか売れない」と確信したんです。だから本当はもっと時間をかけてゲームにいきたかったんですけど、思っていたよりも早く、ゲームを作ることになりました。
──「VRでは絶対にゲームしか売れない」と確信したのは、なぜですか?
岸上氏:
2016年のVR元年には、VR業界のみんなはそれぞれ好きなことをやっていたんです。でも翌年の2017年に「VRってぜんぜん来てなくない?」みたいな空気になるんですよ。そんな中でもVRで売れているものを調べたら、本当にゲームしかなかったんです。ゲームだけが唯一収益化できていて、「これはゲームをやらなきゃいけないな」と。
でも「VRでゲームを作る」といっても、アメリカを見ていると、みんなFPSを作っているんです。それを見て「これと同じ土俵で戦っても絶対に勝てないな」と。一方、アメリカで作られるVRゲームには、物語性のあるゲームがまったくなかったんです。いやまぁ、ちょっとぐらいはあったのかもしれないですけど、ほぼゼロぐらいの勢いで。
でも日本はRPGの国、ゲームに物語性を求める国なので。日本でVRゲームを作るのなら、その強みを活かしたほうがいいだろうと。それで、もっと日本らしいというか、VRでもっと物語性の強いコンテンツを作ろうと考えたんです。
でも「物語を作る」といっても、僕らはその点で素人しかいなかったので、どうしようかなと思った時に、三木一馬さんと出会ったんです。
今、編集者の最前線はどこなのか。元カドカワ社長が『ソードアート・オンライン』担当編集に“退社理由”を聞く【三木一馬×佐藤辰男】
──三木一馬さんというと、電撃文庫で『ソードアート・オンライン』など数多くの人気作を手がけた、ベテラン編集者ですよね。
岸上氏:
はい。三木さんがちょうどKADOKAWAを辞めて独立して、ストレートエッジという会社を立ち上げた時に、徳島の「マチ★アソビ」というイベントで講演会を開いたんです。僕は徳島出身なのでそのイベントに行って、講演の後に三木さんのサイン会があったので、その列に並んで。それでサインをもらう時に「三木さんに弟子入りさせてください!」とお願いしたんです。その場では「気持ち悪っ! 無理」って言われたんですけど(笑)。
物語性の強いVRゲームを作るため、編集者の三木一馬氏に弟子入り
岸上氏:
その時に、無理やり三木さんの名刺をもらって、「興味なかったら無視してください」と会社の資料を送ったら、会ってくれて。
その当時は、三木さんもストレートエッジを立ち上げた直後でほぼ三木さんお1人だったんですけど、「オレから正式に時間をとって教えられるかはわからないけど、横についていて自由に学んでくれればいいよ」みたいな感じで、カバン持ちみたいなことをやらせてもらえることになったんです。
──それは、三木さんかなり懐が深いですね。
岸上氏:
それで三木さんからは、編集者としての物語作りを学ばせていただくと同時に、ゲーム業界の方を紹介してもらってゲームを教えてもらったりと、編集者としてだけではなくてプロデューサーとしても、いろんなことを学ばせてもらいました。MyDearestという会社としては、それが原点ですね。
 |
──そうやって三木さんのカバン持ちをしているあいだ、会社としてはどういう状態だったんですか? もう起業はしていたんですよね。
岸上氏:
起業した創業メンバーが集まって、何をしようかなと考えている時期ですね。ちなみにその時はMyDearestの事務所も、ストレートエッジのオフィスの一角に間借りさせてもらっていたんですけど。
──三木さんのカバン持ちをやっていた時は、給料とかは特にもらわずに?
岸上氏:
もちろんです。こちらが勝手にくっついていただけですから。オフィスを間借りさせてもらえただけでも、有り難かったですけど。
──三木さんについて回ると言っても、全部の打ち合わせに出ているわけではないですよね。どういうものに同席したんですか?
岸上氏:
それが、作家さんと三木さんが小説の打ち合わせをする現場とかにも参加させてもらえたんですよ。「こんな現場に立ち会わせてもらっていいんだ!」と驚いたんですけど。それ以外にも、メディアミックスの会議だとか、アニメの打ち合わせだとか、いろいろでしたね。
役割としては、議事録を取るとか、雑用があれば手伝うだとか。でも特にやることがなくても、意外とついて行かせてもらえたので。そこは本当にスゴイなと思います。
──三木さんは岸上さんのことを、他の人にどのように紹介されていたのですか?
岸上氏:
「スタッフです」の場合もありますけど、三木さんともう少し親しい人に対しては「本当にワケの分からんヤツですけど」みたいな感じでしたね(笑)。
僕はMyDearestの名刺をそのまま渡していたので、それで相手から「どういう方ですか?」と聞かれて説明する、みたいな。
そうやって週3日ぐらいは、三木さんにくっついていた気がしますね。それを2年ぐらいやらせてもらっていました。
──三木さんから相当にいろんなものをもらっていますね。
岸上氏:
本当にそうだと思います。この時の経験は本当に勉強になりましたし、三木さんの人脈からいろんなところにつながったというのがあったので。
当時はすごく厚かましいお願いもいろいろしたんですけど、三木さんからは怒られながらも、言えばやってくれる人だったので。そこはスゴイなと思います。僕は三木さんに一生頭が上がらないですね。
──三木さんと行動を共にしていた際に、特にここが勉強になった、ということは?
岸上氏:
三木さんが担当される作家さんの目利きというか、三木さんはすごく尖った人、突き抜けた才能を持っている人を好むんですよ。これは編集者あるあるなのかもしれないですけど、三木さんの場合はそれが極端で。「自分が関わればこの人は売れる」という人に関わっていたんです。その三木さんの自信もスゴイんですけど。だからたぶん世間一般の編集者から見る目線とは、少し違うんだと、僕は思ったんです。
──それは分かります。それに編集者あるあるでいうと、きっと三木さんは、すでにできあがっている人にはあまり興味がないんですよね。すでにできあがっている人でも、たとえば小説で成功した人をゲームに持っていったりだとか、そういうことをやるというか。
岸上氏:
完全にそうですね。そこの学びは本当に大きくて。そういう編集者の見方が、僕をはじめとするMyDearestのプロデューサー陣には根づいていると思います。
 |
あとは、僕自身が編集者みたいな立ち位置なので。僕が何かできるわけではないというか。作品を作るのはクリエイターなので、というのはものすごく徹底していると思います。なので、おもしろいものを作る人が偉いというか、僕は何も偉くないので。
実際、僕の言うことを聞かないクリエイターも、この会社にはいっぱいいますから(笑)。三木さんもよく「作家はオレの言うことを聞かない」とぼやいていたので(笑)。「でも売れる人って、だいたいそうなんだよ」って。
──そもそも、いちばん最初に三木さんと会った時に、どういった話で盛り上がったのですか?
岸上氏:
そういう意味では、VRというご縁があったのかもしれないですね。僕自身『ソードアート・オンライン』のファンでしたし、「日本の会社として『SAO』みたいな文脈をちゃんと広げていかないといけないんです」と語ったりもしたので。でも自分はド素人だから、三木さんの下でエンターテインメントとは、編集者とは、プロデューサーとは、というのを教えてほしいとお願いして。
──今になって振り返ると、その岸上さんの願いに、三木さんはなぜ応えてくれたんだと思いますか?
岸上氏:
三木さんは超売れっ子の編集者だから、この作品が売れるかどうかの目線はもちろん持っているし、ふだんから「売れるものを」と口にはするんですけど、意外といちばん見ているのは、本人の熱意のような気がするんです。
アニメのスタッフとかでも、仕事を右から左に流すというか、ただやっているだけの人を、三木さんはものすごく嫌うんですよ。そうじゃなくて本当に熱意のある人となら、三木さんは一緒に組みたがるんです。だからもしかしたら、自分が「弟子入りさせてください」とお願いした時も、そういう部分を感じ取ってもらえたのかもしれないですね。
あとは、僕もたいがい変人ですけど一応は社会人経験があったり、ソフトバンクにいたりしたというのも、それも「尖り」というか、自分がなんとかしたらこいつも売れるかも、と思ってもらえたのかもしれません。僕も三木さん本人に聞いたことがないので、分からないですけど。
状況分析から「VRでミステリーアドベンチャーゲームを作る」という方向性を導き出した
──三木さんのところでカバン持ちのようなことをやりながら、一方でMyDearestが進むべき方向性として、VRで物語性の強いゲームを作りたいと。ただ気になったんですが、その時に思い浮かべたゲームというのは、RPGなんですか? その後に実際に作られた『東京クロノス』は、RPGではなくてむしろアドベンチャーゲームに近いですよね。
岸上氏:
自分はRPGもアドベンチャーゲームも大好きだし、じつはアクションゲームも大好きなんですよ。子どもの頃に遊んでいたのは、むしろそっちなんです。昔遊んでいたゲームだと、『ロックマンDASH』が大好きで。そういう意味ではキャラクターだとか、ゲームを操作している中で感じる物語みたいなものが、いちばん重要だと思っていて。
でもそれを自分で作るのは、予算の関係とかいろいろ含めて大変なので、『東京クロノス』はもうド直球で、物語性1本だけで作ったんです。つまり自分自身の作るものが、必ずしも自分の一番好きなジャンルではないと。それはある意味、プロデューサーらしいのかもしれませんけど。
──ということは、テキストアドベンチャーだとか、シナリオといった面に踏み込んでいくのは、三木さんとのやり取りがきっかけになっているわけですか?
岸上氏:
そうですね、その影響は大きいです。
ただ、三木さんについていって三木さんから学んだのは、「自分は三木さんにはなれない」ということで。それはある意味、当然なんですけど。
そこでじゃあ、僕自身の強みや弱みは何なのかと振り返った時に、じつは僕は会社では、すごく経営者然としているんですよ。現場というよりはどちらかというと、人・カネ・情報を集めているというか。
──岸上さんは、企画そのものに口を出したりするのですか?
岸上氏:
場合によりますね。「このクリエイターの才能を活かそう」という場合は、徹底的に任せます。でも、たとえばFacebookと話して、今はこういう方向性で絶対にやらなきゃいけないという場合には、「こういう方向性でやってほしい」と、クリエイターに頼んだりもしますね。
──戦場を設定して、その戦場でどう戦うのかは現場に任せるというか。
岸上氏:
戦場というより方向性ですね。方向性だけを示して後は任せる、みたいなスタイルです。
──なるほど。それでは、ここまでのお話を踏まえて、『東京クロノス』の企画が立ち上がっていく経緯を、改めて教えてください。
岸上氏:
「VRでゲームを作らなきゃいけない」となった時に、物語をものすごく尖らせていくことができるジャンルは、テキストアドベンチャーだろうと考えたんです。僕自身も好きですし。
 |
さっき「VRはFPSが多い」と言ったんですけど、VRはもうひとつ、ホラーゲームも多いんですよ。ゾクゾクする感じがVR向きなんですけど、ただFPSと同じで、普通にホラーゲームを作っても競合が多すぎる。「じゃあホラーじゃなくてゾクゾクさせられるものは?」と考えて出てきた答えが、ミステリーやサスペンスだったんです。それならお話でいろんな捻りもできますし。たとえば『STEINS;GATE』だとか。『ダンガンロンパ』はもうちょっとゲーム的な要素が強いですけど。
だから「VRのテキストアドベンチャーでミステリーをやろう」というところまでは、僕のほうで設定して。そこから先は三木さんにも相談したり、あとはちょうどそのタイミングで、柏倉晴樹【※】という人物と出会って。
※柏倉晴樹
グラフィニカでCGアニメーターとして活躍し、映画『楽園追放 -Expelled from Paradise-』ではモーション監督を担当。MyDearestでは『東京クロノス』『アルトデウス:Beyond Chronos』の監督を務めているほか、『アルトデウス:BC』では原案も手がけている。
──ということは、柏倉さんと出会ったのは「ミステリーアドベンチャーで行こう」と決めた後だったのですか?
岸上氏:
後ですね。柏倉は当時、ゲームエンジンとVRにすごく興味を持っていて。彼はアニメ業界にいたからこそ、ゲームエンジンやVRといった新しいテクノロジーに魅力を感じていたみたいなんです。あとは柏倉本人が、VRで物語性のあるものを表現することに惹かれたみたいで、それでMyDearestに入ってくれたと言っていましたね。
──岸上さんは以前からnoteで、「VRでテキストアドベンチャーを作るだとか、オリジナルのIPでやるとかいうことは、合理的な経営判断ではなかなか決断がつかない」と書かれていますよね。でも、それがなぜ決断にまで至ったのか、今ひとつよく分からなかったんです。
岸上氏:
会社のやり方として、他人と同じことをしていたら生き残れないというか、存在価値がないと思っていて。他社と競って勝てるというイメージは、常にないんです。とにかくユニークなこと、独自性のあることをやらなきゃいけないと、創業当時から考えていて。いわゆるブルーオーシャン理論みたいなことを常にやろうとしていたんです。
あとは『東京クロノス』の企画を考えていた当時、周りからは「VRでオリジナルIPは難しいから、他からIPを借りてくるべきだ」と、ずっと言われていたんですね。それはスマホゲームの成功法則でもあると思うんですけど。でもその時に僕は、川上量生さんが経営の話をする時に「どこで苦労をするべきか」と語っていたのを思い出したんです。
事業を始めた最初のほうで苦労をするべきか、それとも後になって苦労するべきなのか。いずれオリジナルIPを作らなきゃいけなくなるんだったら、今ならまだ予算規模も少ないから、何回かトライアルできるんじゃないかと。これは川上さんの話を僕が曲解しているだけなのかもしれないんですけど、そこで僕は「じゃあ、最初に苦労したほうがいい」と思ったんですね。
──世の中にはめちゃくちゃ大勢の人がいて、だいたいのことって誰かが先にトライしているじゃないですか。それでもやられていないことは、実際にやってみると上手くいかない理由があるか、やったところでやっぱり先がないものだったりする確率が高いんですよね。そういう意味で、「VRでアドベンチャーゲームを作って、それがはたして売れるのか?」みたいな不安は、考えなかったのですか?
岸上氏:
もちろん不安はあったんですけど、じつはMyDearestでは『東京クロノス』の前に、『Innocent Forest』というVRで読む小説や、『夢の相談所』というVRで読むマンガを作っていたんです。それはゲームじゃないので母数はすごく少なかったんですけど、でも一部から熱狂的な声をもらっていたんですね。そういう熱狂的な声があれば、ゲームという形で母数を広げた時にも、ある程度の市場があるだろうと思ったんです。だからそういう意味では、一応は検証していたのが大きかったですね。すごくコアなファンがついてくれていたので。
──なるほど。いきなり思いついてやったわけではなくて、ちゃんと段階を踏んでいたと。
岸上氏:
そうですね。意外とちゃんと段階を踏んでいますね(苦笑)。