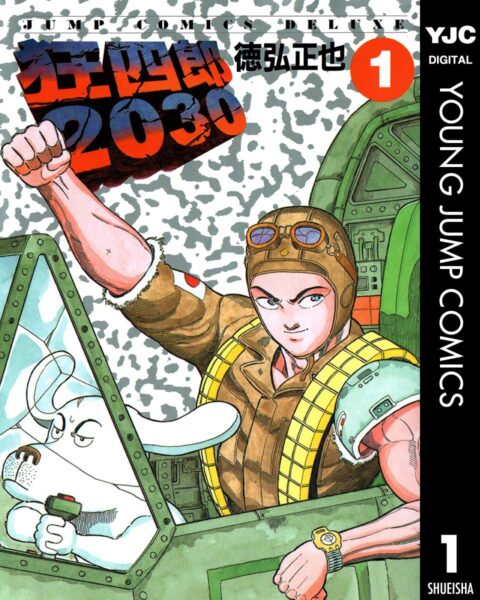イラストやゲームの雰囲気で目を惹かなければ、VRは興味すら持ってもらえない
 |
──では、VRゲームとして他の作品との差別化を模索している中で、いくつか実験的なタイトルを作っていて、その結果として『東京クロノス』が出てきたわけですか?
岸上氏:
そうですね。『東京クロノス』を作ったのは、起業して3年目だったんです。それまでの2年ちょっとの間、いろんなことをやっていて。ただ、方向性はずっと一貫していたので、そこで検証したものをすべてつぎ込んだのが『東京クロノス』でした。
それで『東京クロノス』を出す時に、「勝負作で社運がかかっているので、プロデューサーに入ってください」と三木さんにお願いしたんです。そうしたら超忙しい時にも関わらず、本当にやってくれたんですよ。「オレは今、『ソードアート・オンライン』の小説の原稿を横に置いて、このゲームのシナリオを読んでいるんだからな」って怒られたこともありましたから(笑)。
──三木さんにプロデュースをお願いしたことというのは、具体的には何だったんですか?
岸上氏:
ストーリーやキャラクターのクオリティが、三木さんに認められるものになっているかどうか、みたいなところがメインでしたけど。後はゲームとしてどうなのか、という部分もありましたね。
──作家やイラストレーターは、誰が決めていったんですか?
岸上氏:
作家に関しては、僕らが探してきた人を「この人はどうですか?」と三木さんに提案して、意見をもらう形でしたね。三木さんの抱えている作家さんを紹介してもらうのは、さすがに厳しかったので。
 |
イラストレーターは何人か候補を出した上で、三木さんにも意見をもらって、LAMさんに決まりました。LAMさんに関しては、監督の柏倉が「この人がいい」と提案してきたんです。
──ということは三木さんの人脈を使ってというよりは、本当に制作面でのアドバイスを仰いだという形だったと。
岸上氏:
まさにそういう形ですね。作家は当然なんですけど、イラストレーターに対する三木さんの考え方も、すごく参考になりました。「イラストレーターに関しては、フォロワー数とか人気とかは一切関係ない。良いと思うかどうか、それだけだ」と三木さんは断言していましたね。
LAMさんも当時からイラスト好きな人には人気があったのですが、まだ商業デビューしていなくて。今は大人気ですけど、当時は「そんな新人にキャラクターデザインを任せて大丈夫なの?」と周囲からよく聞かれていたんです。その時に三木さんの教えである「良ければいい」というか、我々としてはこの人が絶対にいい、と思える人がLAMさんだったので。
──イラストレーターの選定ってどうしても、好みとかの話に終始しがちじゃないですか。だから、議論するにしても何かひとつ軸になるものが必要だと思うんです。『東京クロノス』ではそれが何だったのか気になります。
岸上氏:
LAMさんの絵柄って、今はいちばんの主流の一つになっていますけど、当時は「尖ってるね」と言われていたんです。デザイナーが描くキャラクターというか。デザイナーからイラストレーターという流れの走りが、LAMさんだったと思うんです。LAMさんも元デザイナーなので。
LAMさん本人は当時、「とにかく目力を意識している」と言っていて。だからTwitterでイラストを見た時に、0.3秒で目に留まる。僕らはVRだからこそ、イラストで興味を持ってもらえないと終了なので。そのためにもイラストは、見た人全員の目に留まって「おっ、なんだこれ?」と思ってもらえるものにしたかったんです。そのコンセプトにLAMさんがバチッとハマって。
雷火噬原 pic.twitter.com/UX6HdULmQP
— LAM (@ramdayo1122) September 18, 2021
だからとにかくイラストは重視していました。当時のVRゲームはなぜか、キーアートとかのイラストがあまり重視されていなくて。でもイラストで興味を持ってもらえなかったら、ただでさえVRに興味がないんだから,一生興味を持ってもらえないんじゃないか、ぐらいに考えていました。今はさすがに、イラストがそこまで軽視されることはなくなってきたんですけど。
──イラストに限らず、新規のものにどうやって興味を持ってもらうのかというのは、難しいですよね。イラスト以外ではどういうことを考えていたのですか?
岸上氏:
イラスト以外だと雰囲気ですね。『ダンガンロンパ』や『STEINS;GATE』みたいな作品と近しい匂いを感じてもらいたかったんです。VRゲームという時点で新しすぎるので、ゲームコンセプトやストーリーまで新しすぎると、誰も興味を持たないと思ったんです。だから「VRゲーム以外の文脈はこういう雰囲気ですよ」というのを、意識して伝えていましたね。
──それは「オレの好きなタイプの新しいゲームがVRで出る」みたいな関心の惹き方ということですか?
岸上氏:
そういうことですね。やっぱり新しすぎてもダメというか。いちばん良いのは、売れている路線からちょっとだけズレたもの。そこに人間は興味を持つと、三木さんもよく言っていたんです。あとは、あるメディアで流行っているものを別のメディアに持ってくるとか。これは三木さんの編集者視点、プロデューサー視点から来る考え方だと思うんですけど、そういうところを意識していましたね。
「新しすぎてもダメ」というのは、僕らがVRをやり始めた2年間で、イヤというほど感じたことだったので。だから3年目は、ちゃんとユーザーに好きになってもらえるものを作る、という意識でやろうと。今もそれは根強くあるんですけど。
──1年目、2年目というのは、手応えはなかったんですか?
岸上氏:
じつは、僕らがいちばん最初に作ったゲームは『School of Talent: SUZU-ROUTE』という普通のノベルゲームだったんです。まずはVRと関係のないノベルゲームを作ってみて、それをSteamで出したら爆死して。その次にVRで小説を作って、次はVRでマンガを作って……というふうに段階を踏んでいったんです。その過程で徐々に手応えを感じるようになったんだけど、でもまだ採算は合わない、みたいな感じでしたね。
僕らの中でもダメな理由は分かっていて。当時のVRはOculus Riftをはじめとする、PCにつなぐタイプのVRデバイスが主流だったんですが、これだと日本ではPCゲームが売れないし厳しいなと。海外ではいいんですけど、今度は母数が少ないので。
そうやって悩んでいる時に、Oculusの創設者であるパルマー・ラッキー【※】を、僕らが徳島のマチ★アソビに呼んだんです。僕らはその頃、Gear VRというスマートフォンをゴーグルに装着するタイプのVRデバイスに向けて開発していたんですけど、それを見たパルマーから「Oculus Riftでやればいいのに」と言われて。「でもそれだと母数が少ないから、単体で動作する機種でやりたいんだ」と言ったら、パルマーが「それなら今、Oculus Goというデバイスを開発している」と教えてくれたんです。そういうデバイスを開発しているのなら、じゃあOculus Goに賭けてみようと。
結果的に、『東京クロノス』を最初に発表したのとOculus Goが発売されたのが、ほぼ同時ぐらいのタイミングになりました。
※パルマー・ラッキー
2012年、19歳の時にPC向けVRヘッドセット「Oculus Rift」のプロトタイプを開発。Oculus社の創業者のひとりとして、現在へと至るVRブームの火付け役となった。2014年に、Oculus社を20億ドルでFacebookに売却し、現在はドローン開発などの新たな事業に乗り出している。
──Oculus Go自体はすでに生産を終了していますが、その後に同機のコンセプトを発展させたオールインワン型の「Oculus Quest」が登場して、その最新モデルである「Oculus Quest 2」は、現在のVR市場を牽引する人気プラットフォームになりました。そういう意味では、岸上さんの賭けが見事に当たったわけですよね。
それで、『東京クロノス』が発表された際の反響は?
岸上氏:
『東京クロノス』は徳島のマチ★アソビで最初に発表したんですが、その初報がけっこうバズったんです。たぶん、当時はLAMさんのイラストがめちゃくちゃ新しくて。それで三木さんも関わっていてけっこう豪華なスタッフだというところで、注目されたんだと思うんですけど。LAMさんのイラストで、ミステリーでという僕らの狙っていたことが、わりと予想通りに反応があったので、「これはイケるな」と思いました。
その後にクラウドファンディングもやって、それも成功して、そこから『東京クロノス』のリリースへと勢いをつなげていった感じですね。
──クラウドファンディングは、どういう意図があったのですか? 資金調達よりもプロモーションの意味が強かったように感じましたが。
岸上氏:
『東京クロノス』の時はお金も少なかったので、本当に資金調達の意図もありました。ただ、もちろんプロモーションの目的もあって。
 |
まず課題として、VRのヘッドセットがなかなか普及しないと。それならヘッドセットを持っていない人にも、ゲームのコンセプトや僕らの姿勢に興味を持ってもらって、クラウドファンディングに参加してもらいたい。そのへんはニワトリが先かタマゴが先かって話なんですけど。
実際に、クラウドファンディングで支援してくれた人の半分ぐらいが、VRデバイスを持っていなかったんです。まずはクラウドファンディングに参加して、VRデバイスは後から買うという。だから既存のVRユーザーというよりは、VRの世界を一緒に広げる仲間になってくれる人たちが集まってくれたんですよ。
VRゲームってそれまでは、もともとVRに興味がある人たちのコミュニティの中でしか、ほとんど反応がなかったんです。それが『東京クロノス』では、普通にゲームに興味のある人たちが、クラウドファンディングに大勢参加してくれて。これまでのVRゲームとはまったく違うクラスタの人たちが入ってきてくれたというのが、相当大きかったですね。
──たしかに、初期のVRコミュニティはプログラマーや技術者といった人たちが主体で、実はゲーマーがそこまで多くはなかったですよね。
岸上氏:
そうなんです。それまではゲーマーに届いていなかったんです。『東京クロノス』のクラウドファンディングで、ゲーマーの人たちにも注目してもらえたというのが、いちばんインパクトが大きかったと思います。
「ゲーマーに届ける」というのが、今でもVRゲームの大きなネックなんですよ。そこはいまだに悩みますね。以前よりはゲーマーの人たちも増えてきましたけど、まだまだ少ないので。
──そして『東京クロノス』は成功したと。
岸上氏:
はい。制作費のわりにはけっこう黒字だと思います。
資金調達にあたっては「VRゲーム発のオリジナルIP作り」が高く評価された
──『東京クロノス』『アルトデウス: BC』と2作続けて成功しましたが、その後を見据えて今回のような大きな額の資金調達に向けて動き始めたのは、いつ頃だったんですか?
岸上氏:
資金調達自体はこれまでにも、何度かやっていたんです。それこそ『東京クロノス』のクラウドファンディングが成功した直後にも、それを見て投資してくれたベンチャーキャピタルがありましたし。『東京クロノス』が終わった後にも、大型の資金調達をやろうと思ったんですけど、その時は「1本しか当たってないじゃん」と言われて。
なのでいちばんのきっかけは、『アルトデウス: BC』が出た後ですね。2本連続でヒットすると、投資する側も「何か理由があるんじゃないか?」と思ってもらえるみたいで。あとはファンコミュティも、けっこう分かりやすいぐらいの大きさになったので。ベンチャーキャピタルがいろんな数字面を見て、ファンコミュティが盛り上がっていると言えるのが大きかったですね。
あとは「VRゲーム発のIP作り」という文脈が強かったりもします。オリジナルIPはビジネスの幅の広がりが大きいので、そこを評価してくれた投資家もいましたから。「最初に苦労する」という話が見事にここで活きたというか。「他社のIPだったら絶対に投資していなかった」という人もいたので。
──そこはオリジナルIPを生み出した強みですね。
岸上氏:
もうひとつ、オリジナルをやって良かったのは、クリエイターさんにも興味を持ってもらえることですね。「自分もオリジナルをやりたいんです」ということで、けっこう尖った人が来るんですよ。道場破りみたいな感じで(笑)。
──そうやって道場破りでやってくるようなクリエイターさんは、ゲーム業界の方が多いのですか?
岸上氏:
『アルトデウス: BC』以降は、ゲーム業界の人がグッと増えたんですけど。その一方で「自分はゲーム業界出身ではないんだけど、こういうものを作っています」という人もいますね。
VRゲームは今、コンソールの黎明期みたいな感じなので、わりと何でもできる人、なんでもやりたい人が来がちなんです。いろんな領域をまたいでいる人だとか。コンソール黎明期の宮本茂さんや堀井雄二さんたちって、デザイナーとエンジニアを兼ねていたり、デザイナーとシナリオライターを兼ねていたりしたじゃないですか。それを例に出すのはさすがに畏れ多いですけど、それに近しい空気は感じますね。
──その当時の堀井雄二さんやさくまあきらさんって、出自は雑誌などのライターじゃないですか。つまりその当時の目新しいものとしてコンピュータやゲームに注目して、「これは超楽しい!」って自分で作り始めた人たちで、決してコンピュータの専門家などではなかった。そういったノリに近いんですかね?
岸上氏:
その意味で象徴的なのは、入社初日に僕とケンカをした人がいて(笑)。でもその人が、今作っている『DYSCHRONIA: Chronos Alternate』のディレクターなんですよ。
「物語を自分で作りたい」と、SF小説を何百冊も読んでいるような人なんです。僕もそれなりに勉強しているつもりだったんですけど、その人が挙げた本はぜんぜん分からなくて(笑)。この人ならたぶんゲームの物語も書けるだろうな、と思って書いてもらったら、もう天才的だった。
その人には『アルトデウス: BC』の途中から入ってもらったんですけど、そこまでにいろんな文脈があるから、その人の意見をすべて採用することはできないじゃないですか。なので「それは今はできない」と揉めたんですけど、その人はそれで僕に嫌われたと思っていたみたいで。でも僕は天才だと思っていたので、次回作のディレクターに大抜擢しました。
その人が分かりやすく才能が尖っていたんですけど、弊社には、他にもそんな人が何人かいるんですよ。
──MyDearestさんの社員構成でゲーム業界にいた人とそれ以外の人は、どれぐらいの割合なんですか?
岸上氏:
『アルトデウス: BC』以降でゲーム業界出身の人がグッと増えて、今はたぶんゲーム業界、アニメ業界、それ以外の出身の人がそれぞれ1/3ずつぐらいですかね。以前はアニメ業界とそれ以外の出身の人の比率が、もうちょっと高かったです。
 |
──それ以外というのは、IT系ですか?
岸上氏:
IT系の人もいますし、出版系もいますし、本当にゲームやITとは何の関係もない業界出身の人もいますね。今はコンソール系からの転職がいちばん多いです。
──クリエイター主体のゲームスタジオでいえば、たとえばTYPE-MOONさんみたいに同人サークルだったり、同じゲーム会社にいた仲間が一緒に立ち上げた会社がありますよね。一方で、もうちょっと違う文脈で立ち上がったゲーム会社だと、これはスマホゲームのスタジオに多いんですけど、ゲーム業界というよりはIT業界寄りな人たちが起業したゲーム会社もあって。そういう意味ではMyDearestさんって、どういう会社なんだろう? とずっと疑問に思っていたんです。先に挙げた2つのどちらの要素もあるし、それ以外の独特な雰囲気もあるし。
でもこうしてお話を聞いていると、岸上さん本人と、岸上さんの元に集まってきたクリエイターさんたちのバランスなんだろうなと。代表の岸上さん自身がクリエイターに寄り切らないことで、絶妙なバランス感覚になっているというか。
岸上氏:
たしかにITでもないし、ゲーム業界というかモノ作りだけでもないしという、独特なところはありますね。
──ただ、クリエイターと起業家って会話が噛み合わないことも多いなと思っていて。そのへんで岸上さんはどうなんでしょう。やっぱり噛み合わないのですか?
岸上氏:
僕はやっぱり変わってるんだと思いますね。普通は噛み合わないと思うんですけど、僕はふだんそういう創作話ばっかりしているので。それはもともとマンガや小説が好きだというのもありますし、三木さんから学んだところもありますし。
派閥をあえて乱暴に分けるなら、僕らはモノ作りの色がはるかに強いんですよ。ITはあくまでモノ作りのためのツールであって。僕らの発想自体はモノ作りありきになっています。
──なるほど。岸上さんが起業するまでの経歴から受けるような、IT系出身というイメージとは違うと。
岸上氏:
そうですね。スマホゲームの会社はIT系の考え方で動いているところが多いんですけど、VRゲームではそういうところはだいたい失敗したんです。結果的に、コンソールゲームの発想やノウハウで動いている人たちが生き残って。
あとは、スマホゲームの場合はKPIといった形で数値的な結果がすごく分かりやすかったんですけど、VRゲームは数値による評価が難しくて。そのせいで、VRゲームは投資家から人気がなかったんですけど(笑)。だから僕らはゲームの結果というよりは、ファンコミュティの数値で結果を証明したところがあって。
何が言いたいかというと、数値から導き出されるビジネスモデル、つまりスマホゲームにおけるガチャみたいなものが、VRゲームには存在していないんです。今のところはコンソールみたいにゲーム1本につきいくら、という買い切りの形が主流なので。そのおかげでビジネスモデルに振り回されずに、クリエイターが「まずはおもしろいものを作ろうか」というふうに、自然となっていったんです。そこは良かったですね。
メディアを超えて展開した時に、ファンが減らずにむしろ増えればIPとして成立する
──VR発のIPであることがポイントになっているというお話でしたが、IPが立ち上がるにはどういう条件が必要だと思います?
たとえばスマホゲームって、ものすごく多くの人にダウンロードされるんだけど、それがIPになることは必ずしも多くないじゃないですか。その一方でコンシューマゲームだと、10万本ぐらいしか売れていなくてもIP化して、何かのきっかけがあるとそれが爆発することもある。『STEINS;GATE』なんかはまさにそんな感じで広がっていったし、10万本くらいからスタートして、スマホゲームで大爆発したのが『Fate』ですよね。
最初のユーザー数の多さが必ずしも人気IPの条件じゃない。だとしたら、人気IPになるために必要な条件や要素というのは、いったい何だろう? とよく思うんです。
岸上氏:
いちばんの学びになったのは、これはまさに平さんが言語化されていたことですけど、「運営型ゲームは嫌いになってやめる」 問題ですよね。あれは本当にそうだと思って、ビビッときたんですけど。
コンソールゲームの場合は、エンディングを迎えて感情が最高潮になった状態で終わるじゃないですか。さっき説明したように、VRゲームって今のところは完全にコンソールゲームなんですよ。だからクリアしたユーザーさんには「終わってしまった哀しさ」があるので、グッズや何かしらの追加コンテンツを求める声がスゴイんです。でもスマホゲームはゲームがずっと続くから、運営に文句を言う人が増えていってしまう。これは運営型ゲームという構造上、もうしょうがないなと思って。
僕らのところには文句なんてぜんぜん来ないんですよ。応援の声しか来ないです。もちろんたまには文句も来ますけど、それよりも「追加でこういうものはないんですか」みたいな声のほうが、ずっと多くて。こういう声が多いのならIP化というか、新しいメディアに展開してもついてきてくれるのかなとは思います。そこはVRゲームだからというよりも、コンソールゲームとスマホゲームの違いに近い部分でしょうね。
──でも、たとえば100万人が体験するスマホゲームと10万人が体験するコンソールゲームとでは、10万人のほうが熱量が高いからIPとしてはイケるよねというのは、客観的に見たら説得力があるようでない話だと思うんですよね。
だって100万人が知ってる作品なわけで。投資家やエラい人から見たら、100万人遊んだゲームの方が良いように思ってしまいがちじゃないですか。
それでも、僕らから見ると、10万人のほうがIPになり得るという肌感が間違いなくある。これについてはどう思われますか?
岸上氏:
それはすごく本質的な問いだと思っていて、僕も日頃から考えているんですけど。IPになるというのはつまり、キャラクターや物語にファンがついていることだと思うので。そういう意味では、メディアをまたいだ時にファンの人たちがついてきてくれる率が高いかどうかが、IP化の指標なんじゃないかな、と思っていて。
たとえばスマホゲームやコンシューマゲームを漫画化しました、小説化しました、という時にと、ゲームのほうでは売り上げが上がっているのに、漫画や小説のほうには誰もついてこないという現象があるじゃないですか。でも一方で人気のある作品だと、アニメだとか他のメディアになった時にファンの人がすごく盛り上がって、新規の人を呼び込もうとするんですよね。それでメディア展開によってファン全体の人数が増える。「IP化する」というのは、そういうことなのかなと思います。
たとえばスマホゲームのユーザーが100万人いるとして、それをアニメや漫画にしたらユーザー全体の数は200万人、300万人にならなきゃいけない。メディアをまたいだ時にファンの人数が減ってしまったらいけないと思うんです。
──ゲームのコミカライズやノベライズって、ややもするとファングッズ化してしまう傾向があるじゃないですか。それは岸上さんが言うように、既存のファンの何割かしか買わない、むしろ閉じているものになっているんです。本当なら漫画で新たに知ってくれたファンが増えなければいけないのに、100万人のファンの中から10万人が買うようなものになってしまう。もちろん、そこにはいろんな難しさがあって、結果としてファングッズになってしまうんですけど。
逆にメディアを超えることで外に向けて丁寧に広げていったものとしては、たとえばゲームがアニメになったことで人気が爆発的に拡大した『ポケットモンスター』があるし、『Fate』もコミカライズ化やアニメ化で、もともとのゲームのファンだけではない、その外側に向けて広がっっていった。今の『Fate』のファンのうち、最初の『Fate stay/night』のゲームをやったことがある人ってどれぐらいなんだろう、ってなるわけじゃないですか。
でもじゃあ、外に広がる、広がらないメディアミックスって、何がそれを分けると思います?
岸上氏:
あんまり本質的じゃないかもしれないですけど、僕が思っているのは「やめないこと、終わらないこと」なんです。
 |
IP化するタイトルって、要するにブランドみたいなものなので、信頼も重要なんですね。たとえば既存のタイトルを別のメディアに展開した時に、それの人気がないと打ち切るじゃないですか。そうすると、ファンからしたらその時点で終了だし、新規の人には「意外と人気がないんだ」みたいに受け取られるし。
メディア展開をした時に、それがおもしろいか、ヒットするかというのはある意味、運なんです。たとえば『Fate』のメディアミックスって、本当に沢山の媒体で展開され続けて、その過程でufotableのアニメ化で大成功したじゃないですか。 とにかくメディア展開を続けていたことが重要だったんじゃないかと思っています。他にも『名探偵コナン』も、僕が子どもの時にアニメがスタートしましたが、とにかくずっとアニメを続けていて、爆発的に人気の出るタイミングが来て、今のような状況なのだと思います。
そういう意味では続けることって、ものすごく大事で。ずっと続けていくうちに、どこかでそのメディアならではのおもしろさが生まれて……これはまぁ、運もあると思うんですけど。そこで漫画なら漫画、アニメならアニメのファンが増えて、最終的にIP全体のファンが増えていく。そこにたどり着くまでやめないというのは、それは体力とか気力の問題になってくると思うんですけど。