『killer7』で三上真司氏とモノ作りをできたことは、グラスホッパーの財産になっている
──須田さんご自身の感覚として、自分の作品ですごく手応えのあったタイミングというのはいつ頃なんですか? 端から見ると『killer7』あたりでワールドワイドな評価を得たのかなというふうに感じるんですけど。
須田氏:
ターニングポイントは確かに『killer7』だと思いますね。カプコンさんと組めたこと、三上真司さんとしっかりモノ作りをできたことは、今のグラスホッパーにとって相当な財産だと思っています。
自分たちが思っていた以上に世界中で評価されましたし、完成した時に「誰も見たことのないゲームができたな」という手応えもありました。「新しい」という言葉がふさわしいゲームができたし、自分にとっての代名詞になるゲームができたと思いましたね。

想像以上に反響も大きくて。『NO MORE HEROES』のプロモーションで海外を回った時に、初めて『killer7』の評判を生で聞いて、それにはちょっとビックリしました。
あとは、別のメディアで恐縮ですけど、某メディアの編集長さんが「僕はこの業界に見切りをつけて辞めようと思っていたんですけど、『killer7』に出会って、この業界はまだイケるんじゃないかと思ったので、もうちょっとがんばってみようと思います」と言ってくれたことがあって。本人も忘れてるかもしれないですけど(笑)、それを聞いた時にすごく嬉しかったんですね。そういう力のあるゲームを作ることができたのか、と思って。
──『killer7』って、当時の売れ線とはまったく違う、異質なゲームだと思うんですよ。なぜああいうゲームにしようと思ったんですか? 逆張りしようと思ったのか、それとも自然にそうなったんですか?
須田氏:
グラスホッパー・マニファクチュアというスタジオを長いタームで考えた時に、どうしていこうかというイメージはなんとなくあったんですね。そんなにスタッフも多くなかったので、まずアドベンチャーゲームからスタートして、次は3Dのアドベンチャーゲーム、次はアクションアドベンチャー……という、この流れをどうやって達成していけるかなと。
『killer7』はちょうどアクションアドベンチャーというタームだったので、アクションアドベンチャーというジャンルで、しかも『バイオハザード』を発明した三上さんと組む以上は、僕も発明しなければならないと、そういう責任というか十字架を背負うことを、勝手に思ってですね。それで「すべてのデザインを発明しよう」という意識で作ったのが『killer7』だったんです。
 |
だから、ストーリーからアートから入力から、すべてのデザインをこれまでにまったく世にないものにしていこう、とにかく一個一個発明していこうというものを積み上げていった感じです。何かを目指すというよりは、僕は三上さんを意識して作っていたところがありますね。「三上さんが恥ずかしくないものを作らなければいけない」と、ずーっと考えて。
──当時、三上さんと仕事をするきっかけはどういったものだったのですか?
須田氏:
電話で急に呼び出されたんです。ヒューマン時代の同僚で河野くん(一二三さん)【※】が三上さんに紹介してくれたんです。それで三上さんのところに行ったら「須田さん、一緒にゲームを作りませんか」と言われて。それで「ぜひお願いします」と。
※河野一二三
ヒューマン時代に『クロックタワー』『猫侍』『御神楽少女探偵団』といったアドベンチャーゲームを制作したゲームクリエイター。ヒューマン退社後は、巨大な専用コントローラーを使用するXbox用ロボットアクションゲーム『鉄騎』をカプコンで制作している。
──三上さんからのご指名だったんですね。
須田氏:
そうなんですよ。三上さんがヒューマンそのものを評価してくれていて。「あの会社はとんでもないゲームが出てきていたけど、あそこの企画の人たちって、どんな人なんだろう」と、ずっと注目してくれていたらしいんですよね。それもあって声をかけてもらって。
──三上さんとのやり取りだったり、カプコンさんとお仕事をすることで学んだことはありますか?
須田氏:
たとえば、プロト版が出来上がって最初のステージを三上さんのところに持っていってプレイしてもらった時に、「須田さん、この走りのモーションスピード、3倍になりません? 次は3倍にしたものを見てみたいです」と言われたのは衝撃でしたね。
僕にとっての体感は、アドベンチャーゲームの体感だったんですけど、それを3倍にしてみたら、当たり前ですけどメチャクチャ速いんですよ。でもそうすると、急にアクションゲームのリズムになるんです。「あっ、これか!」と思って。ゲームを作る時の体感スピードが違うんですよね。
 |
三上さんの持っている技術というのは、「アクションゲームの体感」というものが遺伝子として継承されているところなんじゃないかと思うんです。
入力した時の第一歩の出方とか、走る時の速度感だったりとか、あとはエイムの瞬間に1フレーム遅延を見抜いたりとか、そういうホントに細かいところなんです。遊び心地といいますか、ボタンを押して入力した時の反応をすごく繊細に見てらっしゃるところがあって。そこは本当に勉強になりましたね。アクションゲームってこんなに違うんだ、って。
──企画とかではなくて、そういう手触りのところをかなり入念に見ていたわけですか?
須田氏:
そうですね。たくさんアドバイスしてもらいましたね。
あとはテキストも何人かの方にお願いしていたんですけど、それが三上さんにすぐバレるんですよ(笑)。
「これ、須田さんの文章じゃないすよね? ダメですよ、須田さんが全部書かないと」と。「ここは僕じゃなくてもいいんじゃないですか?」と伝えたら「ダメです、全部須田さんが書いてください」と返されたり。そのぐらい三上さんは僕のシナリオやテキストを買ってくれていて。ちょっと調子こくぐらい、ベタ褒めしてくれたんですよね。
だから「自分の書くものがそのぐらいの力を持っているんだったら、失礼のないようにエネルギーを込めて書こう」というのはありましたね。本当に、三上さんに自分を「出し尽くされた」というか。
でもそのぐらい、僕らグラスホッパーの持っているスペックをフルに引き出そうとしてくれたんだと思います。そういう意味ではプロデューサーとしてもスゴイ方だと思いますね。
──『killer7』は開発期間が長かったですけど、そのぶん三上さんとのラリーが続いたというか?
須田氏:
そうですね。開発期間をチョコチョコ延ばしてもらったり、ドーンと延ばしてもらったりして。そこも三上さんが全部かぶってくださって。
僕にとって第二の師匠は三上さんだと思っていますし、これは三上さんからも公認をもらっていて。「須田さんが弟子ならいいかな」と言ってくれたので(笑)。
 |
ひたすら調整を繰り返す中から、アクションゲームの爽快感が生まれてくる
──先ほど、グラスホッパーの長期的なタームでのお話がありましたが、ということは当初から、「最終的にアクションゲームに行く」というのを決めていたのですか?
須田氏:
そうですね。僕はアクションゲームが好きなので、自分が好きなゲームを作りたいじゃないですか。僕はRPGが肌に合わないので。
──アクションゲームのポイントというのは言語化が難しいと思うんですが、やっぱりその部分に価値があると思うんですけど、須田さんとしてはどう思われます?
須田氏:
アクションゲームを作るのは、調整の繰り返しで「当たりを探していく」みたいな感じがありますね。
 |
これも三上さんの言葉なんですけど、「アクションゲームにはどこかでゲームの神様がご褒美をくれる瞬間がある」というものがあって。実際、僕にもそういう瞬間が何回かあったんです。
遊んでいて「おかしいな」とプログラマーの席でずっと直してもらっていて、ある瞬間にポーン! ってハマる瞬間があるんですよ。たとえばヒットストップを10フレーム増やしただけだったり、射程を通常の当たり判定の1.5倍まで増やしてエフェクトも伸ばしてもらったりした時に、それで突然「決まったな」という瞬間があるんです。その積み上げのような気がしていて。
とにかくベタ付きで直して組み込んで、また直して組み込んでという作業の繰り返しの中で、だんだんと「当たり」に近づいていく。そこにアクションゲームの爽快感が生まれてくると思うんです。
仕様書通り、設計図通りにパーンと入れて面白くなることなんて、まったくなくて。最初に組み上げただけの段階だと、ほぼつまんないですよね。そこからいかに面白くしていくかは、本当に地道なチューニングの中からできあがっていくのかなと思っています。だから言語化できるものがないというか。
──最新作の『No More Heroes 3』も、そういった手触りの部分は須田さんご自身で全部チェックされたのですか?
須田氏:
そうですね。今回は、「無音のタイミング」と「倒した瞬間に曲が鳴る」ところは、ちょっと気を遣いましたかね。

──『No More Heroes 3』は戦闘が格段に面白くなったと思うんですけど、それは須田さんがディレクターとして前線に戻られたのが影響しているのかな? と思ったんですが。
須田氏:
僕と山﨑(廉氏)のダブルでディレクターをやっていて、ふたりで積み上げた部分もありますし、プログラマーの弘中(徹氏)が最初のボスファイトの骨格を作っているんですよ。
弘中はたぶん、業界でいちばんボス戦を作っている男だと思うんですけど、彼が作ったものに対してどんどんチューニングを加えていくなかで、より気持ちよく、面白くしていくというのが僕らの作業だと思っているので。
──今回はリモートで最後の仕上げまでやったんですか?
須田氏:
やりました。完全リモートです。
 |
──「素材を作っている間はリモートでもいいけど、最後の仕上げはリモートだと難しいよね」みたいな話を、いろんなゲーム会社さんで聞くことが多いのですが、その点はどうでしょう?
須田氏:
そこはできるかぎりリモートでスケジュールギリギリまでいじりましたかね。やっぱり触ると直したくなるので。
──プログラマーのすぐ横で作業する感覚は、ZOOMをつなぎっぱなしで、みたいな形で?
須田氏:
それもありましたし、夜中に僕がバーッと調整指示したのを、昼間に組み込んでもらって、それをまたチェックしたりとか、10年前に戻ったような作り方でしたね。スタッフ間ではそれこそZOOMつけっぱなしで、特にモーションとプログラムって、本当に横にいてやらないといけないぐらいのものなので。そこはもうお互いが画面をつけっぱなしでやりあってましたね。
──そういった手応えのチューニングみたいなものは、プロトタイプの段階ではどこまでやるものなんですか?
須田氏:
『No More Heroes 3』は意外と早かったですね。ただ、ヘンリー戦がいちばん最初にできあがったんですけど、ヘンリー戦というのはある意味、人間対人間の組み合わせなので、これまでのノーモアの延長でできるんですよ。そこでひとつ、コンバットのメインループができあがったので、「これでイケる」というのはけっこう早かったです。

そこからさらに他のボス戦も作っていくんですけど、今回は対宇宙人なので、各宇宙人ごとの戦闘はまったく別物になっていくんですよ。それぞれを1体1体チューニングしていくのは時間をかけて、マスターギリギリまでやっていました。
──でもゲームの大枠は、プロトタイプの段階でできあがっていた?
須田氏:
今回はできましたね。『No More Heroes 3』は比較的早かったほうだと思いますけど、他のタイトルだと、プロトタイプの段階では中途半端な場合もあります。
──大枠が比較的早くできあがったのは、シリーズで培ったものがあるからですか?
須田氏:
そうですね。ただ『1』『2』をけっこう忘れてるんですよ(笑)。これだけ間が開くと忘れているので、改めて遊んでみて。『3』に関しては「『1』と『2』に負けないように」ということをチームの中でずっと言っていました。
今回はほぼ新生チームに近かったんです。どちらかというと『Travis Strikes Again』からのチームですね。ただ何人かは、『1』から関わってくれているスタッフもいるので。

──チームとしては何人ぐらいでしたか?
須田氏:
『Travis Strikes Again』の時は10人未満でした。外部のスタッフさんにも参加してもらって、なんとかたどり着いた感じです。今回の『3』は、コアメンバーは20数人ですね。ビー・トライブさんにも大きな部分で参加してもらったおかげで、あのボリュームが何とか仕上がったんですけども。
グラスホッパーイズムとは、オリジナルな発明ゲームを常に作り続けることである
──グラスホッパーさんとしては今後も、2ライン、3ラインという形ではなくて、ひとつの作品を総力戦みたいな形で作っていくのですか?
須田氏:
はい、今まではそうだったし、これからもそれが基本になるとは思います。
 |
過去に複数ラインをやった時代もあったんですけど、その時に思ったのは、さっき平さんもおっしゃってましたけど、ディレクターが足りないんですよね。ラインを複数立ち上げたところで、僕らはディベロッパーなので開発責任があるじゃないですか。結局、仕上がらなかった時の責任が大きくなってしまうので。
その時の経験も踏まえて、まずはグラスホッパーの顔である僕自身のゲームを作ろうと。最近は海外でも「Suda Game」と呼ばれ方をしていて、複雑なんですけど(笑)。でもまずは僕のゲームを作るチームを強くしていこうというのが、大前提としてありますかね。これがデカい柱になるので。
ただやっぱり、若い子たちに経験をさせるようなインディーチームも作りたいんですよ。それは同時にやっていこうとは思います。
──その意味では、必要以上に開発規模を大きくすると言うのは、須田さんとしては違うかなという想いがあるのですか?
須田氏:
そうですね。求人で言うと今は30人規模のチームをこれから3年の間にまずは50人、丁寧に丁寧に人を増やしていって、そこから先はマックスで80人ぐらいですかね。そのぐらいのペースで新卒も含めてちゃんと人材を育てていって、コアチームとしては80人以上はちょっと無理かなと思っています。それ以上になると、チームとして機能しなくなってくるので。
──モノ作りをする人って、判断軸が自分の中にある人と自分の中にない人がいると思うんです。それで言うと須田さんの持っている判断軸って、どうなってるんでしょうか? いったいどういった判断から『killer7』や『NO MORE HEROES』が生まれてくるんだろうなと。
須田氏:
真面目な話をすると、僕は「開発」という言葉って何なのかと、昔から考えているんですが、開発の「開」は「開拓」のことだと思っているんです。それで「発」は「発明」だと思っていて。だから僕らの仕事は、開拓をして発明をしていくことだと。それが僕のゲーム作りの根っこにあるんです。
 |
だから判断軸もそうなんですけど、まず「発明」ということがすごく重要で。今はなかなかできないんですけど、1日に1個、何か発明をしていこうと思うんですよ。小さなものでもいいんですけど、たとえば他のゲームでやったことのないようなボタンの押し方を思いついたら、それも1個の発明だし。キャラクターの新しいイメージが出来たら、1個の発明。
それを毎日積み上げていくことで、圧倒的な発明ゲームができあがると思っているんですね。
この発明が自分の中から生み出せればいいんですけど、とはいえ発明するのは誰でもいいと思うんですよ。ベテランでも若手でも誰でもいいんですけど、スタッフの意見が発明的で面白かったら、もうそれは採用なんです。
それが自分の中で重要で。特にアイデアというものに関しては「面白い人が勝ち」なので、あんまりプライドを持たないようにしているんです。誰かが出したアイデア、セクションがぜんぜん違うプログラマーやサウンドの人が出したアイデアでも、面白ければそれが採用でいいんです。それが僕にとっての判断基準かな、と思っています。ベテランだからこそクソみたいなプライドは捨てるべきです。
それをすべて活かしきってまとめあげるのが、ディレクションの仕事なので。どんな球でも受けとめられるようにするのがディレクションの仕事ですし、どんな化け物が来ても全部料理できるようにする、というか。
たとえばゲーム業界じゃない人と組んだとしても、その人とちゃんと一緒に仕事をして料理する。最後は何とか自分の力でまとめ上げられるという経験ですかね。
だからこそみんなに自由に球を投げてもらって、その中でいちばん良い球を選んでいって、自分が最後に1本のゲームへと仕上げるという。僕はずっとそれを繰り返してきた感じがあります。
──その時の、アイデアの良い・悪いはどうやって判断されます?
須田氏:
それは僕が面白いと思うかどうかですね。
 |
グラスホッパーのスタッフの中にはキャリアが長い人もいるので、一緒にディレクションした山﨑もそうなんですけど、「これにしよう」「いいと思います」という意見がピシッと合うので。そこはやりやすいといいますか。
これだけスタジオを長くやってきてベテランも揃ってきているので、言語化できない“グラスホッパーイズム”ってものを、みんながちゃんと持っているんだろうなと思いますね。
──今おっしゃられたグラスホッパーイズム、グラスホッパーらしさって、須田さんの中ではどう定義づけされていますか?
須田氏:
それがわかんないんですよね(笑)。別の取材でスタッフの話を聞いていてなんとなくそうなのかなと思ったのは、グラスホッパーってオリジナルゲームの開発に特化していて、オリジナルゲームを普通に作れる会社だと思うんです。逆に言うと原作モノは苦手というか。
なのでグラスホッパーイズムとは「オリジナルを常に作り続けること」であり、グラスホッパーはオリジナルなモノを常に創造していくことが得意な集団なんじゃないかと、すごくフワッとしてますけど、それが僕らの姿なんじゃないかと思います。
あとは共通言語としてのB級映画とかカルトムービーとか、僕がそっちの趣味嗜好なので。そこに『ガンダム』が入ってきたり。
たとえばウチの若手スタッフで『ガンダム』を見たことのない子が、僕が『ガンダム』の例えをすると「じゃあ見ます」という、そういう社風なので。あとはたとえば、僕はカーペンターの『ゼイリブ』【※】って映画が好きなんですけど、ゼイリブの例えをするとみんなが『ゼイリブ』を見たり、そんな会社です(笑)。
だからみんな、僕の趣味嗜好を楽しんでくれるというか、それを苦痛ではないと思ってくれる集団なのかなと思いますね。

(画像はAmazon | ゼイリブ 通常版 [Blu-ray] | 映画より)
──日本って下請けのゲーム会社さんもたくさんあるじゃないですか。みなさん「オリジナルゲームをやりたい」と言うんですけど、その能力みたいなものをなかなか持てない状態になっていて。
一方でグラスホッパーさんのように、覚悟を決めてオリジナルを作っているところもあるわけじゃないですか。それって技術的な問題よりは、マインドも含めてなのかな、と思うんです。
須田氏:
オリジナルを作るのは覚悟というより、僕としては「習慣化」していないと無理だと思うんですね。ウチはもう、オリジナルが習慣化しちゃってるんですよ。
──オリジナルの習慣化って、どういうことなんですか?
須田氏:
「今度は須田さん、どんな球を投げてくるんだろう」というのを別に怖がらないというか、それを受けとめられるように待ち構えている……みたいな雰囲気ですかね。「またどうせ変わったゲームを作るんだろうな」というのが日常化して、その日々の延長にオリジナルがある感じなんだと思うんですよね。
原作ゲーム、既存IPのゲームをずーっと作っていると、オリジナルを作れなくなるというのはよく聞きますね。お題目が急にフリーになった瞬間に「いや、指示してもらわないとできません」みたいなのが習慣化してしまう。
逆にオリジナルを作っている人が原作ゲームを手がけると「なんで自由に作れないんですか」ということも起こるので。なんか、キャリアの初期の段階で決まってくるのかな、みたいなところもあるんじゃないですかね。
これからは1本1本、全部フルスイングしてホームランを狙うつもりです
──今回、グラスホッパー・マニファクチュアがNetEaseの傘下に入ったことで、具体的にどんなメリットがあると思いますか?
須田氏:
独立系のスタジオをやっていると、どうしてもタイトルが「1個の点」にしかならないんですね。パブリッシャーもファンベースもそれぞれのタイトルで別々です。せっかくスタジオとしてやっているんだから、どうしてもこれを線につなげたかったんです。
グラスホッパー・マニファクチュアという名前を表に出しているスタジオなので、これがファンベースにつながらないというのはもったいないと、昔からいろんな方に言われていて。でもそれってなかなか実現できないことでもあるんです。
 |
NetEaseから話をもらった時に「1本、2本の話はしたくないです。まずは10年で3本ぐらい。できればその先もずっとご一緒したい」ということを言ってもらって、「本気でウチのことをほしいと思ってくれているんだな」と感じたんですね。
先ほどお話ししたように、僕は線にしていきたかったので、長いおつきあいができるというのが重要だったんです。新しい自分たちのIPを作って、そのファンベースを育てて、これを拡大していく。最終的にはAAAタイトルを作れるだけの力をつけるというのが、ひとつゴールとしてあるんですけど。
80人のコアチームでAAAタイトルを作るという理想像に向かって、グラスホッパーというスタジオをより強固にしていくことを、NetEaseもすごく応援してくれているんですよね。
──NetEaseさんのように大きな会社の傘下に入るというと、「買われてしまった」とか「上から押さえつけられる」という誤解を受けることもあると思うんですけど、じつはちょっと違うじゃないですか。
須田氏:
そうですね。
──開発会社とパブリッシャーの関係って、基本的には受発注の関係ですけど、それに対して今回のグラスホッパーとNetEaseとの関係は、むしろベンチャー企業とインキュベーターの関係に近いですよね。
須田氏:
それに近いです。
──この関係が、世の中にちゃんと伝わっていないと思うんです。こういった関係だからこそ、10年といった単位でやっていけるんだよ、というのをもっとちゃんと伝えていくべきだろうと。
須田氏:
そうですね。そこは丁寧に伝えていきたいところでもありますし。
 |
「売れるゲームを作るために投資するわけじゃありません。魅力的なスタジオにしてください。魅力的なゲームを作ってください」というのがNetEase側の想いなので。クリエイターとして、そう言ってもらえるのは幸せだなと思います。
しかも「3打席三振でもいい」ぐらいのことを言ってくれているわけですよ。これは思いっきりバットを振れるなと(笑)。だからフルスイングしてやろうと思っています。そこはクリエイター冥利に尽きますよね。
僕が死ぬまでに、あと10本ぐらいはゲームを作れると思うんですけど、その10打席を全部フルスイングして、全部ホームランを狙っていこうと。この場合のホームランの定義はよくわからないのですが、そのぐらいのことをNetEaseが考えてくれているので。
──今までのグラスホッパーさんは、いろんなクリエイターさんとコラボレーションされていたと思うんですけど、NetEaseさんの傘下に入ることで、その点に変化はあるんですか?
須田氏:
『No More Heroes 3』でもゲーム畑の外にいるみなさん、音楽だと金子ノブアキさんと組んだりだとか、牛木匡憲さんというイラストレーターさんにお願いしてスゴイ絵を作ってもらったりというのをやりましたけど、今後はそういった方たちとのコラボレーションもより積極的にやっていこうと思います。
僕らのゲームにまったく違うところからクリエイティブのエネルギーを注ぎ込んで、新しいものを生み出してくれるという、このうねりはずっと続けていこうと思っています。
──須田さんは、いつもゲームの外にある「これ、いいよね」というものをゲームにうまいこと持ち込んでくるなぁという印象があって。でも、そういったものをゲームの中に落とし込むのは、けっこう大変だと思うんですよ。
須田氏:
逆にそれが楽しいという部分もありますね。自分たちだけでやってると、慣れというか手癖でできちゃう、みたいなところがあるじゃないですか。でも新しい方と組むと手癖とは違うところで、もう一回ピシッと襟を正しながら向き合わなきゃいけなかったりもするので。そういう意味で、緊張感をもたらせてくれる良い作用だと思っています。
あとは、そういう外にいらっしゃって活動している、魔物みたいな方と組む楽しさはすごくありますね。それを料理できる楽しみであり自信みたいなものも常に揺らいでいなくて。
自分の中では『シルバー事件』がその料理にトライした作品だったんですよね。いろんな映像手法を使って、それを一本のゲームとして組み込むという。でもあの当時と比べたら、ぜんぜん仕事がしやすいといいますか。当時の映像屋さんは、ゲームに対して頭ごなしに否定してきますから。納得できないからカメラを回さない、なんてこともありましたね。
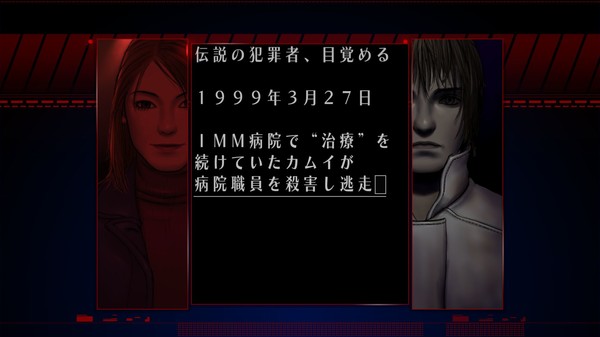
今は有難いことに「知ってます」「須田さんですね」みたいに、自己紹介なしに仕事しやすくもなっていますし。そこは逆に言うと、もっとやらなきゃもったいないなと。世界中に面白い人たちがたくさんいるので、そういう人たちをファミリーとして一緒にモノを作るということをやらないと、損するぐらいの気持ちではいますかね。
──今なお自信を持って、というお話があったんですけど、須田さんのその自信の根拠って何なんでしょう? 若い時って、根拠なき自信があるじゃないですか。でも年齢を重ねてくると根拠なき自信がなくなって、根拠のある自信に変わってきますよね。
それ自体はあんまり良いことでもないと思うんですけど、須田さん的には根拠なき自信と根拠ある自信の良い配分というか、そういったものってどうなっているんだろうなと。
須田氏:
「根拠のある自信は経験だけ」だと思うんですよ。踏んできた場数みたいなものとか、開発の経験もそうですし、経営者としての経験もそうですし。
根拠のない部分は、ストレートはもう160kmは出ないけど、まだシンカーは投げられますよ、キレは増してますよみたいな(笑)。仕事の物量の多さはもう無理なんです。シナリオを書く時間も減っていて。今回の『No More Heroes 3』も、少ない時間で書かなきゃ、と思うと書けるんですよね。
昔は徹夜しても何も書けなかった、みたいなこともあったんですけど。でも今の生活のスタイルだと、限られた時間で書かなきゃいけなくて。そこに順応していくといいますか、能力がどんどん特化していくので。
──須田さんのインプットって、今はどういうものなんですか?
須田氏:
インプットはあんまり入れてないかもしれません。作るために掘る、みたいなことは昔からしてないですね。今後あるジャンルを作りたいと思ったら、そこを掘って研究してってこともやんなきゃいけないと思うんですけど。
 |
今の僕自身は無理はしなくてもいいんじゃないかなって思うんですよ。若い頃に背伸びして吸収したものを、今はどうやってアウトプットして全て根こそぎ吐き出す時期なのかなって。あとは普通の生活の中で見える景色だとか、時代の空気みたいなものを自分の中で嗅ぎ取って出していくというほうが自然なのかなと。
──モノを作るというのは100個ぐらいの判断をする必要があって、その判断をするのがディレクターだと思うんです。100個ぐらいある判断のうち、90個ぐらい正しい判断をすると素晴らしいゲームになる。
でも100個の判断のうち90個正解するって、ただの確率だけでは絶対にできなくて、相当に精度の高い判断軸がないとたどり着かない。なのでディレクターって大事だよね、という。
須田氏:
そうなんです、判断なんですよ。いかに正解をジャッジしていくのか。
──そこで須田さんは須田さんなりの判断軸を持ってジャッジして、『No More Heroes 3』みたいな作品が生まれるわけですよね。やっぱり須田さんのゲームは須田さんあってのものなんだなと、今日改めて感じました。そんな須田さんから生まれる次のゲームを楽しみにしてます。
須田氏:
ありがとうございます。そのためにも、大々的ではないんですけど「積極採用」していきます。新しいゲームを作りたくてくすぶっている人が、業界にたくさんいると思うんですよ。グラスホッパーってなんか怖そうだなと思っている人もたくさんいると思うんですけど(笑)。
でも、2022年の3月にはとんでもなくカッコいいオフィスがオープンしますので。そのオフィスを見たらみんな殺到すると思うので、今のうちに応募してくれたほうが、採用の確率が上がると思います(笑)。
──『No More Heroes 3』で久しぶりに現場に降りてきて、ディレクターを務められましたが、今後はどのように?
須田氏:
この流れでいきます。もうエグゼクティブなんとかって役職は要らないかなと。ただ、若手がインディータイトルを作ったりする場合には、プロデューサーとして就くとは思いますけど。
これから1本1本、大事にゲームを作っていきたいので、そこに賛同してくれる方はぜひ、応募してほしいです。本当に今のうちですので。(了)
 |
今回の取材は、あらかじめ時間が限られたなかで行われたため、須田剛一氏のこれまでの歩みを網羅するといった形にはならなかった。とはいっても、須田氏がゲーム業界を志した経緯からディレクターとしての原点となったヒューマン時代、そして須田氏自身がターニングポイントと語る『killer7』の開発と、その要点となるエピソードを聞くことはできたように思う。
もし機会があれば、今回一端を聞いただけでも波瀾万丈なヒューマン時代の話題をはじめ、須田氏のゲーム作りをより深く聞いてみたいと思う。その時には、新体制を迎えたグラスホッパー・マニファクチュアが本格的に動き出し、その新たな方向性が具体的に見えてくるのではないだろうか。
いずれにしても今後、須田氏自身が語ってくれたようにこれから先の数年で、グラスホッパーによる「フルスイング」のゲーム作りを見ることができるはずだ。それがいったいどんな「発明」によるオリジナルなゲームとなっているのか、今から大いに期待したい。
なお本文でも触れたように、グラスホッパー・マニファクチュアでは現在、プログラマーからモーションデザイナー、プランナーからキャラクターアーティストまで、さまざまな人材を募集中だ。本稿を読んで興味が湧いた方は、ぜひ下記リンクから応募してみてはいかがだろうか。
「世界と対峙するゲームスタジオ」が今、あなたの才能を待っている。

































