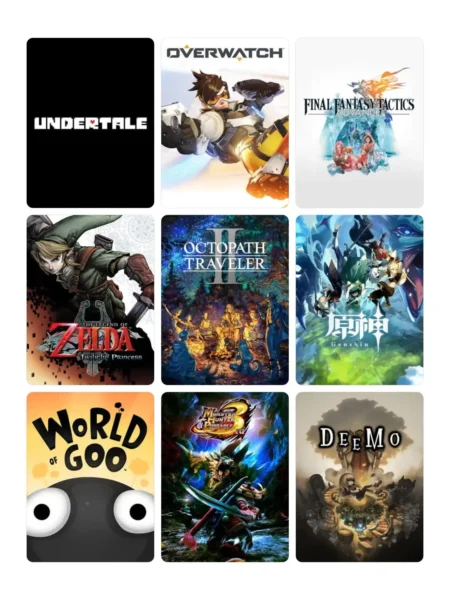どうしてもゲームとして見られて、期待されてしまう
伊東氏:
ふと思い出しましたが、『デスカムトゥルー』のとき、FMV(フル・モーション・ビデオ)という言葉を広めようとしていましたよね。
小高氏:
そうですね。正直、ゲームとして売っても売れないだろうと思っていたので、アドベンチャーではなく、FMVという新しい言い方をして……。さっきのカテゴライズではないですが、いかにゲームじゃないように見せようかと。
『デスカムトゥルー』では持ち出しが多いんですね。基本的には現物出資でして。トゥーキョーゲームスとしても、音楽とシナリオ、シナリオアシスタントなど、何人か人員を出しているわけですが、工数はもらわず、売れた額のレベニューで返ってくるという感じなんです。そうしないと成り立たなかったんですね。
 |
そもそも、いろいろな会社に持ち込む前に「実写モノは無理だ」という感じになっていた。そんな中、イザナギがやろうと言ってくれて、全部の予算は出さないから、こちらからみんな出して……という感じでした。キャストも、タレント事務所は海の者とも山の者とも知らない人間とは組んでくれませんから、たくさんコネを使ったんです。
それこそ本郷奏多くん【※】なんて『ダンガンロンパ』の舞台繋がりで、声優としても起用していますので。栗山千明さんは最初、違う人に頼んでいたんですけど、断られてしまって。「どうしよう……」となっていた中、『ダンガンロンパ』で対談したことがあったし、『ダンガンロンパ』が好きだというのも知っていましたので、「もしかしたら栗山さんなら可能性があるかも」とお声がけさせてもらい、受けていただけたというものでした。
※本郷奏多:アニメ『ダンガンロンパ3 The End of 希望ヶ峰学園』の未来編・絶望編に登場する御手洗亮太を演じている。
──そんな経緯だったのですか……!
小高氏:
あと、舞台となったホテルも、大学時代の友人がそのホテルのコンサルタントをしていたんですね。それで話してみたら雪がない時期はお客がいないので、ロケ隊が来るだけでも嬉しいし、宣伝にもなるからということで、メチャメチャ安くしてくれたんです。そこから友人のCM制作会社に撮影を丸ごと依頼して。普段はCMとか、短い映像をやっている人たちが多いので、ドラマだとみなさん、監督も含めてテンションが上がっていました。言い方がアレですがやりがい搾取をして(笑)。そうやって実際の制作へと入っていきました。
その中で、膨らむのは避ける方向にし、そのためにゲーム的な要素も少し諦めたりしました。撮影時期も本郷くんとかにスケジュールを聞いてみると、ここを逃すとずっと後ろになるということでしたので、撮りきらなきゃダメだと。それでもう、すぐにやり切るという大前提、尺がオーバーしても切るしかないという姿勢で取り組んだんです。
 |
それで間に合ったのはFMVだから、というのもありました。言い訳としてはアレですけど、僕がゲームだと思っていたらゲーム性は妥協できなくなる。「これは譲れない」とか、いろいろ出てきてしまう。だから、あれは僕の中ではゲームではなくて映像作品だと。お金の面でも自分や作品としての妥協点も結構知れたので、FMVというのは僕のプライド的なところもあるんです。
伊東氏:
アドベンチャーゲームという括りの中のものじゃない、『ダンガンロンパ』もアクションゲームだけど、結局アドベンチャーゲームに括られてしまっていると……。
小高氏:
まあ、『ダンガンロンパ』のそれは本当に言い訳ですから(笑)。
伊東氏:
けど、フルモーションビデオゲーム、FMVというのは日本だと馴染のない言葉ですから、新しいものが出てきた感はあるんですよ。
小高氏:
そうですね。だから、FMVでやれば、チャンスがあるかもしれないと思っていて。なおかつ、どこかで動いているかもしれないし、いち早く作りたいなと。
『レトロチカ』はゲーム寄りでしたが、『バンダースナッチ』がありましたので、これはみんな一斉に作っているかもしれないぞ、と。だからこちらはスピード勝負、フットワークだけは軽いぞという勢いで(笑)。それこそ契約書を結ぶ前にシナリオを書いては、キャストと交渉するというぐらいに進めました。
さすがにスパチュンでも許されないことですけど、それぐらいのフットワークでやれて、FMV一発目として出すというのが唯一、僕らの勝ち筋であり、突破口になり得るかもしれないという気持ちでやっていましたね。
伊東氏:
意外にFMVって日本だとないんですよね。大抵はゲームの体裁を取っているものが多い。ああいう映像に寄ったものが珍しいんですよね。
小高氏:
けど、『デスカムトゥルー』もやっぱりゲームとして見られてしまって。プレイステーションやNintendo Switchで出しているのも要因としてあるとは思いますけどね。だから、やっぱり難しいですよ。どういう形で、どのように売ればよかったのかはわからない。
江原氏:
私が思ったのは、小高さんが出ちゃうとゲームとして期待してしまうんだろうなとは思いましたね。
 |
小高氏:
名前を隠せば良かったんですかね。
江原氏:
けど、宣伝するなら小高さんが出てくるしかないじゃないですか。致し方ないと思います。あくまで傍目ですが、みんな『ダンガンロンパ』を期待して買って、そしたらボリュームが少なめで、行き違いが起きてしまったという風に見えました。
伊東氏:
あと、アドベンチャーゲームという言い方だと、ワールドワイドというか、欧米ではだいぶ違うんですよ。『ラスト・オブ・アス』や『トゥームレイダー』みたいなアクションアドベンチャーゲームも普通に含まれてくる。
我々がやっているものはビジュアルノベルとか、選択式コマンドアドベンチャーゲーム、ポイント&クリック型アドベンチャーゲームと言われて、結局そこに落とし込まれてしまうんですよ。
 |
『レトロチカ』も選択式コマンドアドベンチャーゲームって言われたくないんです。そうじゃなくて、自分の頭で考える体感型のゲームだと。ただ、そんな言葉も付けられず、フワッとしちゃっているんです。
たちばな氏:
『デスカムトゥルー』って結構、シームレスさという部分にこだわった作りになっていますよね。『バンダースナッチ』だと止められるとか、熟慮してからアクションができる部分がある。私はどちらかというとシームレス派で、映像の人間として止められない方が好みというのは正直あります。
例として不適切かもしれませんが、私の中のゲーム体験として脱衣マージャン的なものがありまして(笑)。あそこで繰り広げられる映像は、嘘というか、当然今自分に対してリアルタイムに繰り広げられているものではないというのがハッキリしているじゃないですか。その要因の一つに、タイムラグの問題があったように思えるんですよね。ゲームで良いスコアを出した、その次に若干のタイムラグで、明らかに何か切り替わった世界の中で求めていた映像が見れるみたいな。今の時代、あういうのが致命的というか、そういう原体験も含め、何か嘘っぽく見られるんじゃないのかというのを乗り越えられる一つの有効策がシームレスなのではと思っています。シームレスによるリアリティというか。
これは没入の話にも繋がると思うんですけど、そこは小高さん的にはどうでしたか?
 |
小高氏:
僕は多分、次に何かやるとしたら“止める”と思いますね。それは『デスカムトゥルー』を作ったこと、『レトロチカ』をプレイしたことで、逆にゲームくさいほうが独特だなと感じまして。ひとつのジャンルとしておもしろそうだな、と。まあ、個人的な気持ちですけど、シームレスよりは止められるほうがいい。
江原氏:
止めるところもプレイヤーのマインドセットを作るみたいな感じですかね。「ゲームだぞ」って思わせると言いますか。
小高氏:
そうですね。「ゲームだぞ」、「あ、いまやっているのってゲームなんだ」っていう。
伊東氏:
コンセプト的には『レトロチカ』もそうだったんですよね。
江原氏:
そうですね。私は「ゲームにしてくれ」ってお願いしましたので。
小高氏:
ゲームとして見るのか、映像作品として見るのかというのがあって、『レトロチカ』は明確にゲームだな、と。『デスカムトゥルー』は映像作品を目指したところがあり、なんでしたら映画館でプレイしたいぐらいのことを言っていたので、実際は結構大きく異なる気はしますね。
ボタンを押すだけで納得感が増し、気持ちも乗っかる選択肢の不思議
──ちなみにその「止める」、「止めない」において、伊東さんが考えたことはあったんですか?
伊東氏:
最初は制限時間制があってタイムゲージが減っていき、それが終わったら強制的にどちらかと選ぶというシステムもあったんです。ですが、「じっくり考える推理ゲーム」というコンセプトを核に据えたので、それをブレずに貫いたほうがいいと考え、映像を止められるようにしよう、となりました。
 |
ただ、そうすると、BGMが繋がらなくなるんですよ。映像をその選択肢で止めることになりますから、ループしちゃうんです。制限時間があれば、BGMが綺麗に繋がって、ひとつのシーンに出来上がるというメリットがあるのですが、今回はそれを捨てました。じっくり考えるという方向に振ったということですね。
──TIPSは映像が止まらずに出てきますけど、そういう止める場所、止めない場所とかは結構意識されたんですか?
伊東氏:
TIPSはドラマの中で出てくるものを単純に文字化しただけですので、流れていっていいという考え方ですね。
それもあって今回、ひとつだけの選択肢とか、いままで私が作ってきたゲームにはなかった手法もやっています。あと、選択肢にはシナリオの理解度を高めるためのものも結構あるんです。
 |
江原氏:
プレイしているときに外的要因で注意散漫になることはどうしてもあると思います。リマインドの意味での選択肢も置いているんですよね。
伊東氏:
選択肢ってゲーム的な物語を分岐させるだけのものじゃないな、という気がしましたね。小高さんがまだやられていない4章の選択肢って、そういうのが多いんですよ。シナリオを理解するための選択肢と言いますか。
小高氏:
ひとつだけの選択肢ってスマホのゲームだと結構ありますよね。同意させるためのものとか。
伊東氏:
最近のインディーゲームでも見られますよね。
江原氏:
納得度が上がるんですよね。
小高氏:
上がりますね。僕自身、ボタンを押すだけでもゲームだと思っていますので。
たちばな氏:
小高さんが以前おっしゃっていた「1行でもボタンを押して送れば、それはゲームだ」というのはすごく印象に残っています。『デスカムトゥルー』は、選択肢に対して頭を使う度合いが、後半にかけて段々と減っていくんですよね。そういう体験コントロールをしている演出が素晴らしいと思っていて。最後のほうなんて、「もう、これしかないだろう!」という確信のもとにボタンを押す。それは正解を探す行為ではなく、「行けーッ!」という応援のプッシュと言いますか(笑)。そういう考え方があるんだ、というのはものすごく新鮮でしたね。
 |
小高氏:
そうですね。僕がゲームを作っていると、なんと言いますか……どうしてもそうなっちゃいますね。
──選択肢があって選ばなければならないというのは、割と操作することへのドライブ感を重視されていますよね。
小高氏:
そうですね。RPGでもたとえば『魔界塔士サ・ガ』でラスボスを一撃で…とかそういうのって心に残るじゃないですか。うまく言葉にできないんですけど……ああいうのはまさに“ゲームの力”ですよね。
──小高さんの作品って、後半になるほどボタンを押すことと、プレイヤーのドライブ感、気持ちが乗ることが一致する設計になっているように思えるんですよね。そこが多分、特徴なのかなと。
小高氏:
あの行為になんて名称を付けたらいいのかわからないですけど(笑)、最終的に物語もそうですが、気持ちの問題に僕はなりがちなんですよね。『ダンガンロンパ』も希望と絶望というフワッとしたものだったりしますし、根性論みたいな「やればなんとかなる」みたいな言葉が好きと言いますか。それをゲームに落とし込むのに連打とか、「押せーッ!」とか(笑)。そうすることで、プレイヤーとしては気持ちが乗るんですよね。
 |
微妙な芝居、小さな演技こそCGが真似できない実写の長所
──いわゆるアドベンチャーゲームの系譜というのがあるじゃないですか。『かまいたちの夜』はフローチャートそのものを遊ぶことから”かまいたち型”と呼ばれたり、『ポートピア連続殺人事件』、『逆転裁判』などは話の流れを楽しむタイプという具合にカテゴライズされている。
『ダンガンロンパ』は少し違っていて、基本は1本道だけど、ボタンを押す行為が気持ちを乗せる行為であることにフォーカスしている。
『レトロチカ』もあまり見たことがないタイプである気がするんですよね。選択肢による分岐があるわけではないけど、お話の中に仕掛けがあり、それをじっくり見てあとで解くという。『トリックロジック』がそうだったのかもしれませんが、このあたりはどう分析されていますか?
伊東氏:
どんな体感を提供するかまでは私もあまり気が回らなかったんですが、今回で言えば選択肢は想像を補うものという考え方ですね。登場人物の女の子が選んでいるのではなく、「こういう展開なのか?」と探るイメージです。この本は破れていて、ところどころ読めなくなっている。そこに選択肢を出して補完するという。
小高氏:
逆に選択肢はどういう基準で作っているんですか? 絵なのか、体系なのか、構造なのか……。
江原氏:
インターバルが目的だったと記憶しています。定期的にインタラクトを用意する必要があるかなという。
伊東氏:
ずっと作り続けているとよくわからなくなってくるんですけど(笑)。普通に「ここでインタラクション欲しいよね」という感じですね。
 |
小高氏:
リズム的な?
伊東氏:
そうそう。それです。
小高氏:
そうすると体感と言いますか、システム的な感じなのかもしれませんね。
伊東氏:
そうですね。ここで主人公に勝手に行動されちゃうと、あまりよくないなという感じです。ここだけは勝手に行動されたら困るというところに選択肢を入れています。
小高氏:
感情や同期をコントロールする意味では選択肢って使えますよね。誰かが倒れていて、犯人の影を見たとするじゃないですか。そのときに助けるのか、追いかけるのかで、ドラマやアニメにせよ、どちらかを描いた時点で「いや、助けろよ!」「いや、追いかけろよ!」というツッコミが出る。
 |
ただ、ゲームはそれを選択肢にすることで納得させられるんですよね。「こういう理由だから、いまはこの人は放っておいて大丈夫だ」と説明し、追いかけてあげれば頭がスッキリするというか。だからゲームの選択肢って、本当に便利だなと思いますね。間違えれば説明し、行動が一致すれば、その時点でプレイヤーが納得してくれますし。
それで思い出したんですが、僕は『レトロチカ』の3章をプレイしていてい、すごく可能性を感じる場面があったんですよね。探偵役のキャラクターが泣くじゃないですか。謎が解ける前から。言語化が難しいんですけど、あれが何というか新しいな、と。
伊東氏:
あ〜、真相がわかっているから……
小高氏:
そう、真相を知っているから泣くという。心情に共感はしなかったんですが、あのやり方には可能性を感じるなと思ったんですよね。
伊東氏:
そこに注目していただいたのはありがたいです(笑)。あれは、没入感から離れていくところなんですよね。最初、どうしようかと思っていたんですよ。プレイヤーを置き去りにして、探偵の主人公がどんどん落ち込んでいきますから、大丈夫かなと(笑)。
 |
小高氏:
あまり見ないパターンだと思いましたし、伊東さんが考える通り、ああいうのは淡々とやっていくのがセオリーで、そのほうが盛り上がりますからね。なのに泣き出すというのは、なかなか他のゲームでは見ないことだなと(笑)。だからこそ、何かに使えそうだなと思ったし、逆に謎を完璧に解けているプレイヤーからしたら、ものすごく共感しやすくなるんじゃないのかなと。僕はそうなりませんでしたけど、少なからずいるかもしれない。
そういう微妙な芝居、小さな演技ってアニメとかCGでは難しいですし、実写映像でしかできないものだな、と。あの感じは参考になると言いますか、可能性を感じさせられましたね。
伊東氏:
いくつかあるエピソードの中のひとつとして、ああいうのがあってもいいのかなとは思っているんです。大体のゲームは、プレイヤーを持ち上げていくというか、解決編で調子を乗せ、爽快なほうに進むという作りですが、あのシーンではプレイヤーの「やるぞ!」という気持ちとは逆に主人公のテンションが下がっていくという。
江原氏:
外しの展開ですよね。
伊東氏:
そうですね。ただ、意外とあれでキャラクターが立っていると言いますか。
小高氏:
そうなんですよね。キャラクターが立つところでもある。
たちばな氏:
演出的には狙っていなくて、どちらかというと役者から出てきているんですね。そういう映画的なものは、捨ててはいけない実写の可能性だと感じています。
 |
私にとっては、いかにしてゲームの興奮、ドラマの感動といったおもしろさを分けて両立できるか、というのが『レトロチカ』の制作的な裏テーマでもありました。おもしろいというのは絶対的な正義ですけど、おもしろいということを指標にしすぎると、思考停止に繋がりかねないと思っています。それは言葉にするとおかしく聞こえるかもしれませんが、興奮に負けない感動を作るということなんです。興奮によって感動が起きるのではなく、興奮によってかき消されてしまわない感動を作るということです。そしてそれは理屈で説明できない領域にあることも多く、だからこそ制作中に発生した誤算の中に可能性があったりします。闇雲に誤算を拾えばいいということではなくハズレも多いですが、時に奇跡に近い、何か意図しないものが生まれてくるかもしれないというのが撮影現場の尊さであり実写だからこその意味でもあったと思います。
小高氏:
確かにそういうのは実写にはありますね。普通のゲーム作りとか、CGでは生まれてくるようなものじゃない。
江原氏:
テスト撮影で発見できたんですが、実写がCGより強い部分って“機微と所作”だと思ったんですよ。視線の動きだけで、「あいつのことを疑っているに違いない」とか。CGだと破綻しちゃうことが、実写だと自然に成立する。映像監督をやっていただいた芝崎さんには「そこをがんばってほしい」とお伝えして、高めていってもらったというのはありましたね。
実写であるがゆえ客観性が増す
伊東氏:
そう言えば、小高さんは『HEAVY RAIN -心の軋むとき-』【※】ってやりました?
小高氏:
もちろん、やりましたよ。だいぶ前だから、記憶は薄まっていますけど(笑)。
※『HEAVY RAIN -心の軋むとき-』:2010年に発売されたミステリアドベンチャーゲーム。心に傷を負った男が誘拐された息子を救うためにさまざまな試練に翻弄される。
伊東氏:
父親が部屋の中に複数ある道具を使って、とある行動の選択を迫られるシーンがあるじゃないですか。私はあの場面に「これをやらせるためにいままでさまざまな操作をさせてきたんやろ」と感じたんですよ(笑)。
 |
小高氏:
意地悪さを感じましたよね(笑)。
伊東氏:
ただ、あそこにアナログ的な感度があって、グッとくるんです。あの感覚がアドベンチャーゲームらしいなと思ったんですよ。
小高氏:
あれはまさにゲームですよね。触覚を重視しているというか。映像だと触覚はいまのところないですよね。だからこそ、ゲームと映画の混じり合いには可能性というか、掘り様があるのではと思いますね。あれだけ3D音声に爆音などをやっているなら、いつかはゲーム会社と組んで、触覚も体感させる映像作品みたいなものをやってみてほしい。そこに新しいビジネスが生まれる可能性もあると思うんですよね。
伊東氏:
メタバースが普通になってきたら、それこそライブでお芝居しながら、自分でインタラクションさせていくなんてこともできるかもしれませんね。触覚以外に視線もインタラクションだと思うので、こちらを見ていたらこうだけど、違う方向を見たらこうなっていた、という感じに。
小高氏:
一方で面倒くささもありますよね。僕はVR否定派なんで(笑)。面倒くさいというか、「そこまで入りたくないです!」という。
伊東氏:
(笑)。
小高氏:
「あなたがこの世界に入れますよ!」と言われてもそこにいたくないんですよ!(笑)。「いいです、遠くから見ていたいだけなんです!」と。
現実世界での体感型とかであれば行くんですけどね。「あれをVRでやれますよ!」と言われても、まずやらない。
江原氏:
脱出ゲームはいいけど……みたいなものですよね。
小高氏:
そうです。脱出ゲームはやる。けど、VR脱出ゲームはやらない!(笑)
江原氏:
(笑)。
たちばな氏:
VRは体験強度に関しては間違いなく高いじゃないですか。ただ、ストーリーが作りにくい。世界観は作れますし、体験の強度もすごくなりますけど、ストーリー自体を味わってもらうにはVRって不向きな感じがするんです。それはVRの自由度がゆえに体験の編集権をこちらが持っていない、というのが課題として大きいんですよね。どう移動しても、どう視線が振られても一様に味わえるストーリーというと、緻密には設計できないし、そもそもストーリーというのは時間軸上に発生するものなので、時間のコントロールができないとストーリーはコントロールできないとも言えます。
 |
もちろん、そこは両立する方法もあります。さきほど話した、ゲーム的興奮とドラマ的感動の関係というのはまだ道半ばで、私にとっては追いかけていきたいテーマです。
──その辺って『シュタインズ・ゲート』はうまくやっていたと思うんですよね。あれは岡部倫太郎(オカリン)という主人公が体験することとプレイヤーが体験することが一致しているんですよね。だから、自分が主体的に物語を体験させるという意味においてはすごくうまくやれていて、「主人公=自分」にすごく近い。
『レトロチカ』は視点がどこにあるのかというのはすごく気になっていて、プレイヤーはプレイヤーだけど、主人公がキャラクターとして存在していて、その主人公が本を読んでいるみたいな感じになっている。では、プレイヤーの視点はどこに置かれているのか、というのはちょっと聞いてみたかったんですよね。そもそも、どの辺を意識されていたんですか?
たちばな氏:
私としては、そもそもストーリーにおける主体と主人公は違うというのが根底にあります。『シャーロック・ホームズ』はホームズが主人公だけど主体はワトソン、『ドラえもん』はドラえもんが主人公だけど主体はのび太、という感じですね。私の中の主人公の定義というのは、役割に対する期待に最も応える人というものなんです。主体はその世界を主体的に体験し目線を担う人間であると。
 |
『レトロチカ』はそこをすごく迷ったんです。結論として、プレイヤーがコントロールする河々見はるかは主体。でもストーリーにおける主人公というのは彼女ではなくて、半分は彼女が演じた過去の四十間佳乃、そしてもう半分が現代の相棒である四十間永司になるんです。特に現代視点から見れば、相棒の永司が、四十間家にまつわる謎や親の死をどう乗り越えるか、というストーリーになっています。
伊東氏:
そこにゲーム的にはるかでもない、プレイヤーというのが露骨にゲームと向き合うことになる。プレイヤーにゲームシステムが直接訴えかけてくるような感じで。主体がさらに1個足されるんですね。
──そこがまさに新本格ミステリ的で、おもしろいなと思ったんですよね。お話があり、読者が揃っているから「読んでね」、「先を考察してみてね」という。そこはすごくミステリ感がありました。
伊東氏:
だからあまり感情移入させる気はないんです。主人公は先ほどたちばなさんが言った通り、四十間永司であり、四十間佳乃なんですよ。そのふたりの物語なんですね。
 |
江原氏:
『シュタインズ・ゲート』には未来から来たという人物がいたじゃないですか。あの子の物語を追うようなイメージが『レトロチカ』でしょうか。翻弄されるキャラクターが平岡祐太さん演じる四十間永司と久坂如水なので、それをオカリンの目線で見ている、と。
伊東氏:
だから「プレイヤー=オカリン」みたいに、どこまで研ぎ澄ませて感情移入させられるかみたいなことはずっと言われていて、感情移入できなかったという声も多いんです。けど、そこはあまり考えなかったです(笑)。
──一般的な作法で言えば、主人公と一体化させるのがゲーム的であり、ゲームの良さだみたいに言われがちじゃないですか。『レトロチカ』からは「そうじゃないんだな」ということをすごく感じたんですよ。一歩引いている感じで、推理編になるとさらに距離を置かれる感じがありますし。
たちばな氏:
小高さんが『デスカムトゥルー』のときにおっしゃっていた「栗山千明は栗山千明だから」というのは実写ゆえのものだと思うんですよね。だから、感情移入しようにも、しきれないというか、役者さんの姿が透けて見えてしまう。はるか役の桜庭ななみさんは、背景が良い意味で透けて見えないというところが私にとってはキャスティングに繋がったところでもあります。SNSでの発言とかで、できる限り実像みたいなのが見えない、詳らかにしていない人がいいのでは、というのはひとつの意識としてありました。
 |
マルチロールシステムにも関わってきますけど、100年の物語という設定でありつつ、“現代に撮影した”という感覚がメタ的にあるんですね。けれど、マルチロールシステムによって、その違和感が必然性に変換できたのは本当に大きかったです。
キャラクターも時代で違いつつ、どこか同じ人が演じることによって連続性が生まれていて、例えば現代では物静かな庭師を演じた池内万作さんが、大正時代では主人公のお父さんを演じるときに、違うキャラクターなんだけど、どこか重なってくる。そしてそれは邪魔じゃなくて、究極生まれ変わりの人と解釈して見てもいいんです。実際、温和な性格はどこか通じるところもあったりして。あそれが時代の変遷をテーマにしたストーリーにも繋がっていて、とても良い世界観を生み出してくれたと思います。
小高氏:
正直、実写と漫画は近いと思うんですよね。漫画は『ワンピース』であったらルフィであるように、基本的に主人公目線で見ないとおもしろくないと言いますか、自分目線ではないんですよね。自分を投影させることがない。
『シュタゲ』は何が違ったのかと言えば、モノローグがやたら多いんですよね。あれで「これはあなたの物語ですよ」とずっとやっていきますから、最終的にゲームプレイがシンクロする。じつは『デスカムトゥルー』もモノローグは多めにしているんですよ。ある程度「この人の目線で見てね」という気持ちがあって。
『レトロチカ』はモノローグが多くないので、感覚的にはドラマを見ている気持ちに近くなるんですよね。少し思ったのが推理編に関して言えば、僕はあれを女の子(河々見はるか)の視点だと思ってやっていたんですよ。逆にあれ、プレイヤーでもよかったかもな、と。「読者の君に問題だ」というノリでも良かったかもしれませんね。それぐらい突き放してしまう感じで。
 |
やっぱり実写を使っている時点で、投影は難しいんですよね。FPSにもTPSにも絶対にならないですし。
伊東氏:
そうですね。客観性が出てしまうんですよね。
小高氏:
仮に実写で投影できるようにするとしたら、『シュタゲ』みたいにモノローグを多くし、なるべく近づけていくパターンしかない。それが武器なのかどうかはわからないけど、実写という表現の特性ではありますよね。