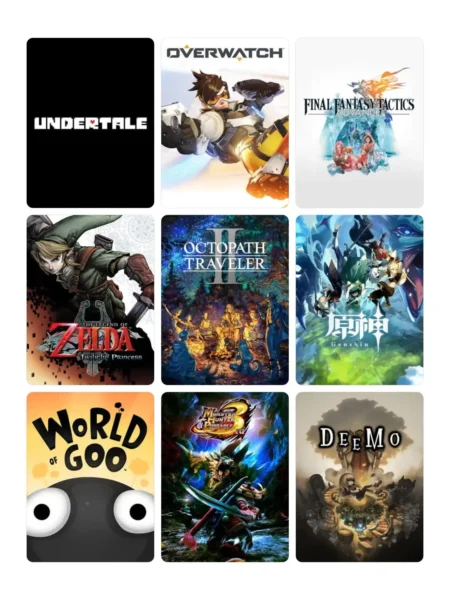実況との相性がよさそうなのに配信禁止というもったいなさ
伊東氏:
多分、キャラクタービジネスもちゃんとやれと言われた場合、こういう作りにはならないはずなんですよ。主人公にちゃんと長所と短所、絶望に陥る瞬間みたいなのを必ず入れないとダメみたいな話だと思うんですよね。
 |
小高氏:
でも、そこは揺れ動いてもいいという一面もありますからね。主人公目線で見る人もいれば、俯瞰視点で見る人もいる。ゲームと実写の融合だからこそ、フワフワしていてもいい気がするという感じなんですよね。
──先ほど、システム用に推理を考えたわけではないという回答がありましたけど、逆にこのシステムって汎用的だと思ったんですよね。たとえばリアル脱出ゲームって、汎用的なシステムがあって、そこに世界観が乗っかれる。つぎは『金田一』で、つぎは『ガリレオ』でやってみるというのもできるんですよね。
要はこのフォーマットでさまざまなミステリ、事件の1回目とかそのようなものをやって、あるタイミングで「あなたが解いてみなさい」とやるのは成立すると思ったんです。マーダーミステリーやリアル脱出ゲームみたいな形で。その辺ってどう思っていますか。
伊東氏:
やれると思います。問題編の中に謎を解くための手がかりを全て揃える条件さえあれば、「さあ、考えましょう」というシステムでなんでもできてしまうかと。
江原氏:
問題は『ガリレオ』や『金田一』でやってしまうと、ロイヤリティでスクエニの取り分が減ってしまうという……(笑)。
 |
一同:
(笑)。
──リアル脱出ゲームにせよ、マーダーミステリーにせよ、あれらがそれなりに成立するなら、コンピューターゲームのフォーマットで持っていけるとは思うんですよね。僕は衝撃的だったんですが、コロナになってリアル脱出ゲームとかがオンラインに移行し、体験の強度がすごく下がる弊害を受けながらも、割と成立してしまっているというのがありますので。
伊東氏:
そのような場を置いて、クリエイションできる仕組みで推理編を作り、みんながそれぞれ仮説を置いていくみたいな形で、そういうことはできると思っています。
たとえば小高さんが、ひとつの謎に対してある仮説を作り、隠しておく。そうすると、他のプレイヤーがやったときに“小高”と書かれている仮説が出てくるみたいな感じですね。
 |
江原氏:
『トリックロジック』のオムニバス形式のシステムとは相性がいいのかもしれないです。
──マーダーミステリーとか、実況でも結構やられていますけれど、あれが成立するのって、シナリオが大量にある中で「これはおもしろそう」、「僕もやってみたい」、「みんながやっていないのをやろう」という需要があるのも大きいと思うんですよね。
コンシューマーゲームのように、7000~8000円で買うものだとなかなか成立しませんが、フォーマットがあって、「シナリオ1個500~1000円です」、「見ていないものは別に買ってやりましょう」といった形なら、割と突破口になるのではないのかな、と。
伊東氏:
なるほど。いまは目線がひとつですけど……たとえば、キャラクターがたくさんいて容疑者と犯人がいます。それに選択肢という形がいいかはわかりませんが、いろいろとインタラクションしていく。そうすると最終的にいずれかのキャラクターに肩入れしたり、人の裏側が見えたり、謎や秘密も見えたりする中で推理するというのはおもしろいかもしれないですね。
──一方で『レトロチカ』は基本的に配信がNGになっていて。それがもったいないな、と思ったんですよね。
伊東氏:
いやぁ、もったいないですよ……。
──生放送というか、実況でやるおもしろさは確実にあるなと感じたんです。でも、それができない。ビジネスモデルの問題なのだろうなと考えつつも、ゲーム自体は本当に実況向きだと思うんですよ。
小高氏:
最初に対話があったらいいのにと伊東さんに言いましたけど、あれ、実況だったらセルフツッコミができるんですよね。「そんな訳ねーだろ!」とか(笑)。それなら成り立つな、というのは確かにあるかもしれない。
 |
伊東氏:
10年前に戻ってしまいますけど、『トリックロジック』が似たような感じだったんです。あとは、関西ローカルで『安楽椅子探偵』【※】というドラマがあって、問題編と解答編があり、1週間のインターバルが設けられていたんですね。そのあいだに自由に考えてください、と。
※『安楽椅子探偵』:綾辻行人と有栖川有栖の共同執筆による、視聴者参加型の推理ドラマ。出題編と解決編にパートが分かれており、視聴者が推理して誰が犯人なのかを応募する“犯人当て懸賞企画”が行われていた。
小高氏:
あれは結構、そうそうたるメンバーでやっていましたよね。
伊東氏:
綾辻行人さんに有栖川有栖さんとか……。それを当時の2ちゃんねるとかも含め、考えていたんですよね。ああいう遊びができるとおもしろいし、それこそエピソード形式で配信して、ここから先は誰も答えを知りませんという状態で、みんなで考えて推理するというやり方だと、段々盛り上がっていく可能性はあると思うんですよね。
ところが、ゲームでエピソード形式をやると、売り上げが右肩下がりになっていく……。
江原氏:
そうなんですよね……。古くはドリームキャストの『エルドラドゲート』シリーズ【※】とか、ああいう続くタイプのものって右肩上がりになった事例はあまりないはずです。なので、まとめてパッケージングするのがいいかなと。
 |
最近の話で、他社のタイトルで第1話を無料で配信し、あとはエピソードごとに売る手法を取っているものがありますが、続くエピソードの売上はだんだん下がっていったようです。
『レトロチカ』はひとつのパッケージとして、お話の滑り出しはしっとりしてるけど、最終的な満足度は高いというゲーム性にしたので、エピソード分割販売だと価値を感じてもらいづらいです。そもそもコンシューマーゲームである以上、パッケージ全体の完成度が高いほうがゲームファンは納得しやすいのかなと思うところもあります。
※『エルドラドゲート』シリーズ:2000年から2001年にかけ、カプコンより発売されたドリームキャスト用連作ユニットRPG。全7巻が発売され、1巻に複数話を収録。キャラクターデザインは『ファイナルファンタジー』で知られる天野喜孝氏が手がけた。
小高氏:
そういえば、発売前の体験版は出さなかったですよね。
江原氏:
体験版はこれからでも検討したいですが、序盤は本当にスピード感がないので、魅力を感じてもらえるものかどうかと (笑)。
小高氏:
確かに切るところもなさそうでしたから……(笑)。
江原氏:
そうなんですよね、どこで切るかが難しくて(笑)。やるなら序章と1章を丸ごと、とかですかね。
──体験版では実況や配信がOKとなるのですか?
江原氏:
体験版を作れるならですが、体験版部分の実況配信は許可したいと思っています。製品版は一切禁止にしちゃってるので。
伊東氏:
本当に配信向きだとは思うんですよ。いろいろな仮説が出てきて「どれが正しいのか」、「これがこれなのか?」、「だから犯人はこいつだ!」というのを頭の中で考えていくわけですから。
 |
──本当に実況向けだと思います。多分、視聴者とシンクロしそうな気がするんですよ。
江原氏:
誰かの推理を見るのもおもしろいんですよね。
トンデモ推理が後半に集中している理由
──余談になりますが、いわゆるトンデモ推理はどれぐらい意図して入れているんですか? 明らかに「そんなことはないだろう」みたいなものもありましたので(笑)。
伊東氏:
あれはですね……編成としては撮影シナリオチーム、ゲーム開発チームがあって、撮影シナリオチームがシナリオを仕上げた段階で、問題編だけをゲーム開発チームに見せるんです。それでみんな、自由にいろいろと「こういう推理をしました」と書いてくれるんですよ。それを引っ張ってきて間違い仮説やハズレ分岐にしたという感じですね。
たちばな氏:
トンデモ推理は後半が結構多いと思います。理由の一つに俳優が撮影していく過程で次第に遊びだしたんですよ。俳優の生理として分岐するものに対して違う人格を演じるというのがすごいストレスで、切り替えが頻繁にできないんですね。正解ルートに集中しがちなので、理解はあっても体がついてこないというのがあったんです。
 |
そんな中、マンネリ化してきたことも含め、俳優が少しオーバーに演技したり、コメディ要素を面白がり始めたんですね。時には大真面目にやっているのに笑えてしまう箇所もあったりして。俳優や監督からも「普通に推理していると選ばないものに関しては遊んでいいですか?」と言われるようになって、次第にメリハリがついていくようになったんです。撮影の中盤くらいに、ちょうど後半の台本を仕上げているときにそんな感じだったので、後半の分岐シナリオに所々トンデモ推理をぶち込むみたいな修正を加えたのを覚えています。
小高氏:
でも、あのトンデモ具合は『街』や『428』っぽいと思いましたよ(笑)。
江原氏:
チュンソフトさんっぽさですよね(笑)。
 |
伊東氏:
解決編でハズレ展開がたくさんあるほうがゲームとしてはおもしろいとは思うんですけど、そこまで撮影するのは大変なので、そのかわり推理編であからさまにハズレっぽい仮説を出すことで、消去法で正解推理を導き出せるようにしようとは思いました。
小高氏:
逆に仮説が成り立ちそうな事件を選んでいるのかな、とも思ったんですよね。だから、最初にフォーマットに合わせて謎を作っているのですか、と思ったんです。
確かにハズレとやっておけば、この枝は終わりとなりますね。やっぱりミステリものでこのルートは違う、という説明は大変ですから。全部潰す必要がある。
江原氏:
プレイヤーのあいだでどうウケるのかは楽しみですね。推理編の仕組みもあれがおもしろいということなら、そのまま順当に続編を作ればいいということになりますし。もっとゲーム的なインタラクトがほしいという意見が出てきてもおかしくはないかなとは思うので、この辺は感想を見てみていきたいですね。
「19世紀イギリス・ロンドン」=「日本の昭和時代」?
──海外でも展開されるということですが、その辺の戦略とかはどういう感じなのでしょう。
江原氏:
日本での販売が最も重要なのは間違いないです。パッケージがあるのは日本とアジアだけで、欧米はダウンロード版のみなので。
ただ、最初から英語ボイスを入れたり、9言語字幕対応にすることで、自らマーケットを狭めることはしないようにはしました。
 |
──なるほど。海外へ展開するにあたって、日本の実写作品という視点があるじゃないですか。その勝ち筋はどこにあるのかなというのが気になっているんですよね。小高さんがおっしゃっていましたけど、あの世界観や時代設定はどこまで海外を意識したものなのかな、と。
それと、韓国は既に実写作品の突破口があるのに対して、日本の実写作品の突破口はどこにあるのかも気になるんですね。何となく僕がいま見ている限りだと、昭和の日本ってじつはそれになり得るんじゃないのかなと思うんですよ。
『全裸監督』はどういう捉え方だったかわかりませんが、その辺りの突破口や勝ち筋に関して、たちばなさんと江原さんはどのようなイメージを持っているのか、お聞きしたいなと思います。
たちばな氏:
そうですね……Netflixだと、明確に時代劇はやらないと言っているんですね。私たちは日本らしいものというとつい、サムライが出てくるものを考えるんですけど、じつはグローバルでは必ずしもそういうのに興味がなかったりする。外国人が日本に来て、「みんな京都に行っているでしょ?」と思うのに等しいおこがましさと言いますか、勘違いだったりするんですね。渋谷のスクランブル交差点だったり、新宿の歌舞伎町、秋葉原などといったところに、日本らしさみたいなのを割と感じているところがある。
 |
おっしゃるようにその絶妙な感じが昭和には漂っているんですよ。年代にも寄りますけど、記憶の届くノスタルジーさがあり、それでいて少しハッちゃけていて、なんとなくモダンっぽさがある。大正ぐらいまでいくと、もう何でもありな感じになるけど、昭和は現在からみても新鮮で、発見がある。新宿のゴールデン街とか、お祭りの出店、駄菓子と書かれた暖簾にワクワクすると言いますか。そういう精神性が存在しているように思えます。
──精神性ですか……。
たちばな氏:
ノスタルジックさと非日常的でワクワクする感じと言いますか。
江原氏:
予算書を作ったとき、海外でも売らないと黒字化できないとは確定していました。なので、謎を作るときには「日本人にしか分からない仕組みの謎は作らないでください」と最初からお願いしていました。
そのうえで……一時期、日本のゲーム業界は海外でウケようとするあまり「外国人はこういうものが好きでしょう?」と憶測でものを作って、結果それが海外でも日本でもウケないという病にかかっていたように思います。
ですので、当たり前の話になりますが「まずは自分たちがおもしろいものを作りましょう」と。
──素直に作り上げるということに集中したんですね。
江原氏:
あと、ちょうどシナリオを作っている時に『ゴースト・オブ・ツシマ』が発売されたんですよ。海外の人が作った日本のゲームで、日本人からすると変な部分もあるのですが、海外のユーザーは「これが日本を再現したゲームなんだ」と思っている。本来、コストパフォーマンス的には、日本のスタジオが日本を舞台にしたゲームを作るほうが圧倒的にいいじゃないですか。実際、ここに住んでいて日本のことに詳しいので(笑)。
なので、先ほどたちばなさんが言った精神性の部分、“わびさび”みたいなものは日本のもともとの強みであり、それを素直に最大化していけばいいんじゃないのかな、と。ゲームの中身ももちろんそうですが、トレーラーが象徴的です。日本人の強みである表現、世界観、味わいを前面に出すようにしています。
──でも『ゴースト・オブ・ツシマ』はそうですが、あれは必ずしも正しい日本ではない、時代劇っぽさが強調されたデフォルメされたものという感じですよね。いまはその日本らしさを分けている、受けているものってデフォルメされた日本なのかな、と。『全裸監督』とか、あとはバブル期の勢いのあったころって日本がデフォルメされて、支持されている感じがあって。そういう日本をフィーチャーして売ろうとしている人たちが、あの辺りをどう捉えているのかは純粋に気になったんですよね。
小高氏:
僕は『アクダマドライブ』というアニメで昭和180年ぐらいの設定をやったんですが(笑)、あれはレトロフューチャーを取り入れているんですね。そのときに1960年代の宍戸錠さんが出ている鈴木清順監督の映画を観まくったんですが、もはや近未来なんですよ。いまの時代からプラスしたのが近未来、マイナスしたのが高度経済成長期で、完全にSFになっているんですよね。ビルがすごい建っているし、舗装された道路から少し外れると土になっていたり。これはすごいなと思いまして。なので昭和って、いまの若い人が見てもSFに感じるかも、という妙な魅力があると思うんですよね。
 |
それに日本人って基本、島国の人間ですから真似るのが大好きじゃないですか。でも、昭和はギリギリのバランスで、うまく真似られなかったと思うんです(笑)。シティポップとか、多分あの時代なら向こうの音楽を聴いて、こういう感じだろうと数枚のレコードしか確かめずにやっている。それが結果としてうまい具合に日本っぽさができて、海外の人が聴くと「なんじゃこりゃ」みたいなことになるんですね。キャラクターショップとかのビカビカの色彩もそうですが、ああいうのも独自に編み出してしまった感じがあって。曲がりくねったものが昭和にはあったかのように思うんです。
平成になると、真似方がうまくなっているので、アメリカ人とかもそのままになって新しさはないのですけど、昭和はなんかそういうものが時代的な背景からいろいろ生まれたのもあって、最後の曲がった下敷きみたいになっている(笑)。
だから、もう二度とあれはできないような感じがするんですね。
江原氏:
まさにガラパゴスですよね(笑)。情報の隔絶が独自進化を促したと言いますか(笑)。
伊東氏:
最近、発表された『昭和米国物語』とかまさにそれですよね。
小高氏:
そうですね。あれはおもしろいですよね。
──あの『昭和米国物語』の注目のされ方と当たり方って「なんなんだ!?」と思って。
小高氏:
実際、昭和って曲がりくねった感じがあるんですよね。「なんでこんなのが?」ってのが山ほどある。テレビとラジカセが一体化した製品とか、「なんで一体化するの?」っていう(笑)。
江原氏:
ありましたね。ツインファミコンもそうですが、なんでもかんでもガッチャンコしてしまう(笑)。
小高氏:
その節操のなさがまさに昭和って感じで、魅力的に感じるんですよね。僕らもそうだし、海外の人たちも最近は僕らと感性が似てきちゃっているから、そうなのかもしれない。
──19世紀のイギリス・ロンドンとかも魅力的に感じるじゃないですか。それに近いものが昭和の日本にはあるという感じで。
小高氏:
そうですね。近いものがあると思います。
──レトロ感と新しさというか、独自性が発揮されている感じがしますよね。
江原氏:
熟れすぎて、いまとなってはファンタジーの世界になったんでしょうね。昭和のバブル期は。
 |
小高氏:
『アクダマドライブ』でもSFの世界なのでお金は電子マネーなのですけど、払うときにはハンコを使うという(笑)。なぜハンコがおもしろいかと言ったら、海外の人はハンコを知らないんですね。だから、それをすごいと言ってくれたりする。そういうところに言葉だと言いにくいんですけど、妙なものがあるんですよね。
昭和の鈴木清順監督などの映画も、改めて観てみるとすごく魅力的ですし。何か独特な新しさがある。
それで思い出しましたけど、『レトロチカ』の3章で支配人が怒るじゃないですか。ドラマが始まってすぐに怒られるのは昭和の感じがあっていいなと思いました。
伊東氏:
怒るだけではインパクトが弱かったので、「何かパーンってやってください」と撮影監督にお願いして、わざわざテーブルに段ボールを置いて、やってもらいました。
小高氏:
あと、もうちょっとタバコを吸っていてほしくもありましたねぇ。
伊東氏:
タバコはねぇ……。
小高氏:
まあ、ゲームだから……。
江原氏:
そうですね。CEROだったり、海外での展開を考えると…
伊東氏:
現場的にも面倒くさいところはありますよね。
 |
小高氏:
確かに。現場管理的に他のスタッフの前で吸って、役者も吸って副流煙がどうこうみたいな問題とかもありますし(笑)。
江原氏:
(笑)。まあ、コロナ禍だと余計にあったかもしれませんね。
伊東氏:
昭和感で言うと、マッシュルームカットとかやたら濃いもみあげとか、もっと昭和コテコテのキャラ立てをしても良かったんですけどね。
 |
たちばな氏:
そういう意味では割とお行儀のいい感じにまとまったというか。
小高氏:
まあ、そうですよね。タバコをスパスパしておじさんたちは喜ぶかもしれないですけど、若い子たちは苦情を出すかもしれませんから、入口はそっちのほうが圧倒的にいいですね。
江原氏:
多分、小高さんとの差別化もあったと思います。すさんだ世界観やデスゲームに近しくすると、小高さんお得意の領域に行ってしまう(笑)。
伊東氏:
まあ……同じ方向性は無理なので(笑)。到底かないませんから。
小高氏:
そういう意味でも謎から解き方まで、真摯だなと思います。『ダンガンロンパ』は僕の場合、いまは気にしている人はいないですが、ミステリの定石を裏切っていくことを信条にしていましたので。
だから『レトロチカ』は真摯。そこはマーダーミステリーとかに近いと思いますね。
伊東氏:
私自身がクラシカルなんですよね。最近のミステリもあまり読めていませんので……。
江原氏:
新本格ミステリってクラシカルであることを内包しているものだと思います。お約束を守ってくれるところが嬉しいですから。
小高氏:
まあ、一周回って戻った感じというか、結構戻っていますよね。
江原氏:
『屍人荘の殺人』や『硝子の塔の殺人』は新しいものを取り込みつつ、回帰した印象を受けました。どちらもメチャクチャおもしろいですよ。そういえば今村昌弘先生には『レトロチカ』のレビューコメントをいただいています。他にも我孫子武丸先生など推理作家の方々からレビューコメントをいただいて公開させてもらっています。
小高氏:
皆さんクリアされているんですか?
江原氏:
はい、オールクリアしていただきました。
「『ダンガンロンパ』は1回、終わらせましょう。」
伊東氏:
宣伝と言えば……トゥーキョーゲームスとコラボとかできないものなんでしょうかね。
小高氏:
いやぁ……トゥーキョーがいまのところ、何もないんですよね(笑)。
 |
伊東氏:
じゃあ、新しくコラボを(笑)。
小高氏:
スパチュンと作っている『超探偵事件簿 レインコード』は完全に“ド”ミステリなので、タイミングが合えば……ですね。まだちょっと先の話になりますけど。
伊東氏:
新規でもなんでも、何かやってみたいですね。
小高氏:
それこそ『デスカムトゥルー』が出たときのように特別ドラマをYouTubeで公開するとかもありですし。
伊東氏:
あ、いいですね。別々のゲームがクロスオーバーするような。
小高氏:
ミステリというところで、何かやりたいですね。『ポートピア連続殺人事件』、『逆転裁判』、『ダンガンロンパ』とそれぞれの時代を象徴するミステリが出てきていますけど、ここしばらくそういうのが出てきていない。
 |
その意味で『レトロチカ』は久しぶりの新作ですし、僕も『レインコード』を2020年代のミステリのエポックメイキングになりたいという思いで作っていますので、ここら辺で盛り上げていきたいですね。
江原氏:
というか、ずっと不思議に思っていたことで……『逆転裁判』がそうでしたが、3部作で一度終わってしまうのって理由があるんでしょうか。小高さんも『ダンガンロンパ』が3部作で終わりましたから、まさに当事者ですよね。4作目が出ない理由ってあるんですか?
伊東氏:
あれ、小高さんは明確に終わらせるつもりだったんですよね。
小高氏:
そうですね(笑)。『ダンガンロンパ』は1回、終わらせましょうと。
江原氏:
それは続きを作りたくなかったから終わらせたんですか?
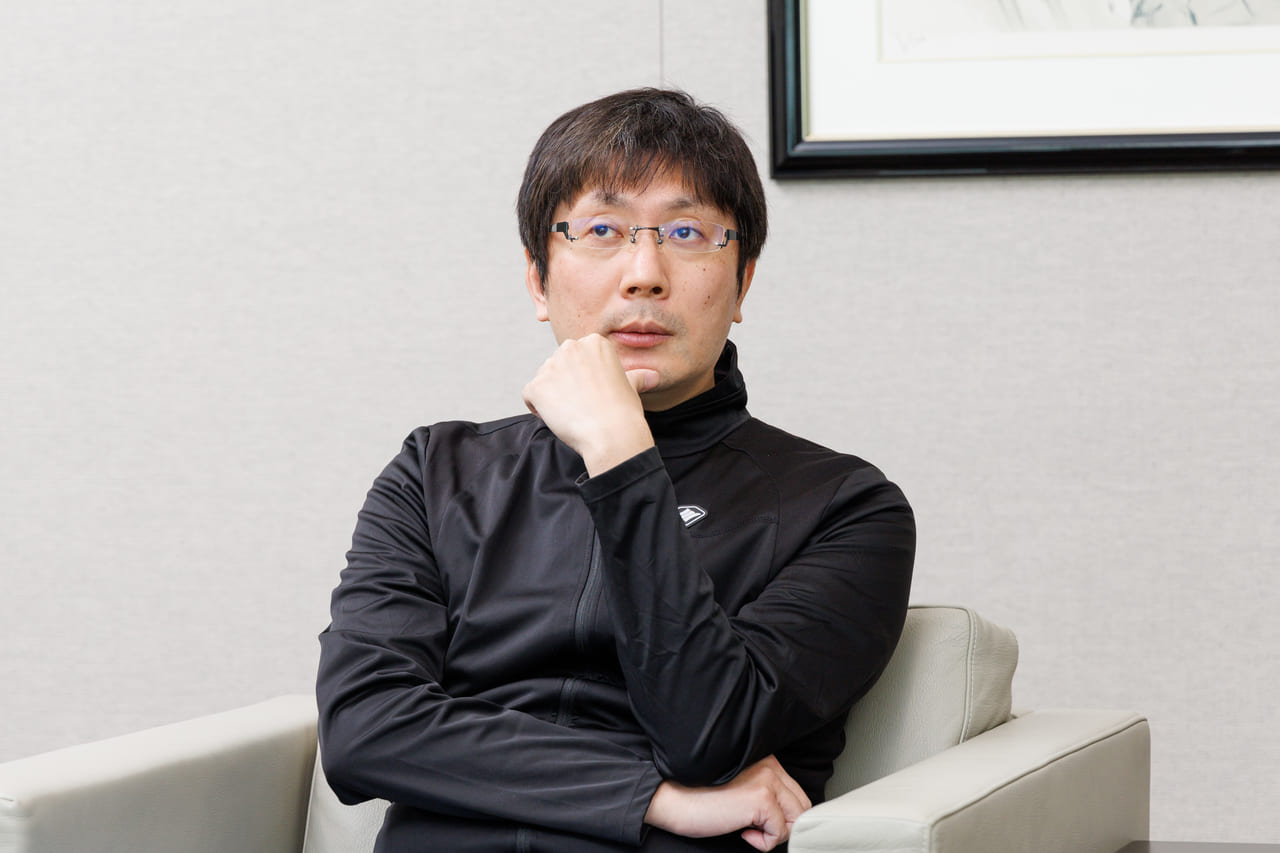 |
小高氏:
いや、単純にもっといろいろ作りたいものがあったからです。あと、“終わる”というのが新しさだとも思っていて。シリーズって基本的に続いていきますけど、終わった感じが出るものって珍しさがあるからやってみたかった、という感じですね。
別にあのような終わり方をしたから次は作れない、と言ったらそうでもないです。そのときは「ごめんなさい」という顔をしてまたやればいいかと思っています(笑)。
江原氏:
(笑)。『逆転裁判』も一度3部作で幕を閉じましたし、何かあるのだろうか、先輩たちは何かを感じているのだろうか、とずっと思っていたんです。
小高氏:
うーん……どうでしょうかね。けど、ミステリのシナリオって普通に書くよりも圧倒的にカロリーが高いんですよね。
江原氏:
確かにそうですね。次回作を考えたとき、お客さんのハードルが上がっているから、1作目ほど驚かせるのが難しいというのはあると思います。
小高氏:
実写の場合だと、そこはリアリティ重視で作れるから強いんですよね。ただ、ゲームの場合……小説もそうですけど、続編になるとトリックをどんどんエキセントリックなものにしていかないと肩透かしになっちゃう。東野圭吾作品のように実写のようなイメージで作っていれば、そうはならないかもしれませんが『ダンガンロンパ』もそちらに足を突っ込んじゃったんですよね。ゲームである以上は派手さがどうしても必要ですから。それで大変になってくる、と。
江原氏:
『ダンガンロンパ2』も学園かと思ったら……という感じでしたよね。
小高氏:
個々の事件もそうですね。殺し方を派手にしていかなければとか。それで本格派で攻めるのが難しくなってしまうので、確かにシナリオを書くカロリーは高いな、と。
なんか違う話にズレちゃいましたが(笑)。
実写の映像には“早さ”がある。そのメリットを『レトロチカ』で発見できた
──最後に今日の座談会のまとめとか、『レトロチカ』をどのような人に遊んでほしいかというのをおひとりずつ、お聞きできればと思います。
たちばな氏:
普段、そんなにゲームを遊ばれないという人もキャストの役者さんがきっかけでもいいですし、何かしら新しさを身近に感じるということから手に取ってもらうといいなと思います。それは自分が関わる意味、映像業界的なことでも思っていますので、そういう方向から「おもしろかった」と言ってもらえると嬉しいです。
 |
──以前、映像とゲームの領域にはすごいポテンシャルがあるとおっしゃっていましたが、たちばなさんが今回、得られた手ごたえってどういうものがあったんでしょうか。実際、それに立ち向かおうとする人がすごく少ないという現状があるのではないですか?
たちばな氏:
手応えですか……それはメチャクチャありました。ゲームの持つインタラクティブ性とか、そういうのが楽しくてしょうがないほど可能性を感じさせられたし、因数分解していく必要があるなと思いました。
あと、今回初めてというわけではないですが、映像のメリットとして“早い”ことをすごく感じたんですよ。私個人はいままで当たり前だと思っていたのですが、「そんなに驚かれるんだ」という反応がゲームの制作チームなどからあったんです。それをうまく活かした作品になったこと、逆に今回見つかったことを大切にしたうえで、ゲームの魅力を利用した新しいものを作れそうだという、鉱脈の一端が見つかったような気がしたんですね。
 |
──“早い“というのは、具体的にはどんなところに感じたのですか。
たちばな氏:
作ろうと決めてから完パケするまでの早さです。先ほどの『デスカムトゥルー』の話もそうですけど、基本的にゲームを作るのって時間がかかるというのがありますよね。そのゲームを遊んでいる瞬間というのはプレイヤーにとっては「今」ですが、「作られていたのは結構前からだぞ」というメタがあるわけじゃないですか。
なので、ずっと作り続けていると、早く出来上がったものが時代遅れになってしまうこともあり得る。そのとって出しできる良さを活かせる方法はないのかな、と思うんですよね。そこがどうしても難しくて、答えが見つからない。
だけど、安易にVRには行きたくないという思いも私の中にはあって。それでいて映画で終わっていてもいけない。そこを今後、どうにかしたいということを悶々と考えていますね……。
 |
──なるほど……ありがとうございます。江原さんはいかがでしょうか。
江原氏:
私はずっとミステリが大好きで、それらを読んで育ってきたんですね。『逆転裁判』も好きで、それがあったから新卒でカプコンに入りましたし、小高さんの『ダンガンロンパ』もすべて発売日に買って遊びました。
『コナンVS金田一』は面白かったですよ。あれが小高さんのゲームだったというのには本当にビックリしましたが(笑)。
小高氏:
ふっふっふ(笑)。
江原氏:
ミステリが好きでいままで生きてきて、そのゲームのプロデュースをできて、現場に恵まれたお陰で一定の自信を持てるものを世に出せたのは、すごく良い経験になると思います。
あと私が望むのはプレイヤーにも評価され、少なくとも次回作を出せるだけの販売本数を達成することですね。次回作があるならどんな形になるだろう、とはぼんやり考え始めています。
でもまだまだ『レトロチカ』が売れないとその未来はないので、気になった方は新品かダウンロード版でお買い求めいただけますと(笑)。
 |
──伊東さんは?
伊東氏:
今回は配信がNGとなっていますが、友達とか、親子でワイワイ言いながらやってもらえると、おもしろいかなという気がします。そういう遊び方をおすすめしたいですね。
あと今回、小高さんとお話ししながら思いましたが、犯人を当てるミステリの醍醐味とおもしろさは伸びしろがあるな、と。フロム・ソフトウェアさんがやられている緩く繋がるオンラインとか、そういう要素を取り入れていくと、もっとみんなで解いている感じが出せるのかなと思いましたね。前に出た『Detroit: Become Human』( デトロイト ビカム ヒューマン)の他のプレイヤーの選択割合表示とかもおもしろかったですし、ネタバレにならない程度に「ちょっと教えてあげたい」という介入ができるアイデアが固まれば、より犯人当てミステリはおもしろくなるように思いますね。
 |
小高さんも同じゲームクリエイターなので、考えていることがよく似ているのがわかると、今回聞きながら思いました。ゲームのコア部分をよく見てくださって、汲み取っていただいたことには感謝の限りです。ありがとうございます。
──犯人当てミステリをどうゲームのシステムに落とし込むのかにすごく真摯に挑戦したというのは感じましたので、本当にこれがどう受け止められるのかは興味深いです。というわけで……なぜか小高さんが締めになってしまいましたが(笑)。
小高氏:
『レトロチカ』のことなのに(笑)。いやぁ……全人類買うべきじゃないですか?!
一同:
(爆笑)
たちばな氏:
それをTwitterでつぶいてくださいよ(笑)。
小高氏:
そうですね、ほとんど『NieR』(ニーア)の精神的続編ですので、『ニーア』が好きな人は買ったほうがいいです。スクエニさんの人間じゃないので、僕にクレームは言わないでほしいですけど、『ニーア』好きは全員買ったほうがいいと思います!(笑)
 |
江原氏:
いやいやいや! ヨコオさんは『レトロチカ』の存在を最近認知してくれたくらいだと思いますよ (笑)。
小高氏:
とにかく、『レトロチカ』がおもしろかったら、ついでに『デスカムトゥルー』もやってくれると嬉しいです。安いんで、チラッとやっていただければと(笑)。
──いい締めでした(笑)。本日はありがとうございました。
座談会の中で、ひと際印象的だったのは、CGではない生身の人間が関わるからこその長所(強み)が明確に語られたことだ。
演出ではなく俳優から出る細やかな所作、それこそ目線ひとつで自然と感情が伝わる部分は、CGとの大きな違いだろう。加えて、撮影期間が制限されることによる完パケまでの早さも強みといえる。
一方で、実写の難しさも浮き彫りとなった。撮影においては撮り漏らした場面を後からやり直すのは難く、実在する建造物などを極力映さないようにする配慮も必要となってくる。
また、実在する人物が役を演じているため主人公に自分を投影しにくいといった問題も挙げられるだろう。
とはいえ、実写ゲームの可能性は大いにあるように思える。
韓国が、『パラサイト 半地下の家族』をはじめとする映画やドラマ、さらにはBTSの活躍によって土壌を整えているように、日本の映像コンテンツの突破口としてのゲームが台頭していく──という未来だってあり得るかもしれない。
ゲームなら海外へのアプローチがしやすく、俳優のモチベーションも上がりやすい。映画業界とゲーム会社が手を組む、というようなことが本当に起これば、臨界点を超えていける可能性があるのではないだろうか。
そのためにも『春ゆきてレトロチカ』が国内に限らず、海外も含め、どのように支持が固まるのか見逃せないところだ。本作が一定の成果を出すことに期待したい。
Nintendo Switch版
— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) June 14, 2022
『春ゆきてレトロチカ』を1名様にプレゼント@denfaminicogame@numan_edd
をフォロー&本ツイートをRTで応募完了
ご応募は6月20日まで!
小高和剛×『春ゆきてレトロチカ』主要制作スタッフによる”ぶっちゃけ”座談会
詳細記事はこちら▼https://t.co/QeBy3GBPkY pic.twitter.com/QitzyjSZlz
Play Station4版
— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) June 14, 2022
『春ゆきてレトロチカ』を1名様にプレゼント@denfaminicogame@numan_edd
をフォロー&本ツイートをRTで応募完了
ご応募は6月20日まで!
小高和剛×『春ゆきてレトロチカ』主要制作スタッフによる”ぶっちゃけ”座談会
詳細記事はこちら▼https://t.co/QeBy3GBPkY pic.twitter.com/Ze6vPcYLti
Play Station5版
— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) June 14, 2022
『春ゆきてレトロチカ』を1名様にプレゼント@denfaminicogame@numan_edd
をフォロー&本ツイートをRTで応募完了
ご応募は6月20日まで!
小高和剛×『春ゆきてレトロチカ』主要制作スタッフによる”ぶっちゃけ”座談会
詳細記事はこちら▼https://t.co/QeBy3GTYz6 pic.twitter.com/klizaMURCQ
Amazonギフト券5000円分
— 電ファミニコゲーマー (@denfaminicogame) June 14, 2022
を1名様にプレゼント@denfaminicogame@numan_edd
をフォロー&本ツイートをRTで応募完了
ご応募は6月20日まで!
小高和剛×『春ゆきてレトロチカ』主要制作スタッフによる”ぶっちゃけ”座談会
詳細記事はこちら▼https://t.co/QeBy3GBPkY pic.twitter.com/AhUCc8EQEO
【あわせて読みたい】
『全裸監督』Pが訊く、来たるべき“インタラクティブ映画”のあるべき姿とは? 『デスカムトゥルー』の挑戦から、未来のエンタメ像を考える『デスカムトゥルー』のシナリオを執筆し、ゲームディレクターを務めた小高和剛氏と、本作のプロデューサーであるイザナギゲームズの梅田慎介氏、そしてたちばなやすひと氏の3名による鼎談を企画した。