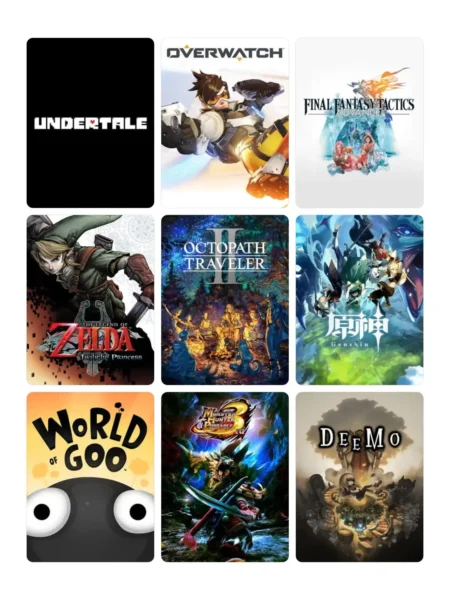昔と違い、日本と同じタイトル名のままでも海外では受け入れてくれる
伊東氏:
海外にアプローチするという観点でも、役者さんからすればゲームって結構いい媒体なのかもしれないです。
たちばな氏:
はい、それは今回の俳優さんたちにとっては最大のモチベーションでしたね。
 |
伊東氏:
たとえば『仮面ライダー鎧武/ガイム』のファンって、海外にもたくさんいるんです。その『ガイム』の海外ファンの人たちに、役者さんが新しい自分を届けたいというとき、他の日本のドラマや映画に出てもなかなか届かないんですが、ゲームだと届くというのはあると思います。最近だと、Netflixでも届くようになりましたけどね。
江原氏:
やはり海外でリメイクされると、キャストが西洋人に代わってしまうというのがありましたから、そこがモチベーションになったというキャストの方々は多かったと伺っています。
伊東氏:
でも、そうか……Netflixって、海外で全部の日本のコンテンツを観られるわけじゃなないですよね。
 |
江原氏:
そうですね。リージョンロックがありますし……。
たちばな氏:
ただ、ある種のブレイクスルーポイントはあって。たとえば韓国ドラマが世界で観られているというのは、「観てもいい」と思える土壌が育っているというのがある。アカデミーを獲った『パラサイト 半地下の家族』とか、BTSの活躍によって、「観てもいい」という土壌が出来上がっているから実際に観てくれる。そういう臨界点を超えるのは容易じゃないことですが、韓国はそれを突破しています。すごいことですよね。業界が一丸になってやらないとグローバルに届けるって達成できないものだと思います。
小高氏:
その土壌を作れる武器というのが日本だとゲーム、アニメなんですよね。
たちばな氏:
そうなんですよね。当たり前のように世界で親しまれている。
伊東氏:
小高さんのファンも海外のほうが多いぐらいですからね。
小高氏:
僕のファンというのがそもそも存在しているのかはわかりませんが……(笑)。
けど、TwitterやInstagramのフォロワーはそうですね。半分以上は海外のファンです。
 |
──『ダンガンロンパ』もSteamだと海外の比率が高いですよね。
小高氏:
そうですね。『ダンガンロンパ』も半分ぐらいは海外ですし。
江原氏:
『ダンガンロンパ』って販売累計は公表しているんでしたっけ?
伊東氏:
この前したんですよ。
江原氏:
あ、されたんですね。なんでも500万本ぐらいとか……?
小高氏:
そうです。560万本と発表していましたね。
江原氏:
いや、本当に夢があるなと思いましたね……! 『逆転裁判』もそうですが。
※注:カプコン公式サイト掲載の「シリーズソフト販売本数」によれば、2022年3月31日時点で『逆転裁判』シリーズの全世界総売上本数は890万本(リマスターなどを含む33タイトルの合計値)。
小高氏:
『逆転裁判』は海外ではタイトルが変わっちゃっていますよね。
江原氏:
『Ace Attorney』となっていますね。
※注:海外版『逆転裁判』のタイトルは『Ace Attorney』。主人公の成歩堂龍一も「Phoenix Wright」と設定されている。
小高氏:
そうそう。『ダンガンロンパ』も最初は『Trigger Happy Havoc』を強調していたんですけど、いまは“Danganronpa”が浸透していますね。
※注:『ダンガンロンパ』の海外タイトルは『Danganronpa: Trigger Happy Havoc』。タイトルロゴでは『Trigger Happy Havoc』が強調され、『Danganronpa』が副題のように位置付けられている。
江原氏:
ハッシュタグを「#danganronpa」と統一できていることで、『ダンガンロンパ』はSNSで強い立ち位置にあると、小高さんが先日某所でおっしゃっていましたが、「なるほど~」と思いましたね(笑)。
 |
小高氏:
まあ、あれは打越【※】が調べたんですけどね。朝5時ぐらいに送られてきて。
「1日中、なに調べているんだ!?」っていう(笑)。
※打越鋼太郎氏:小高氏と同じくトゥーキョーゲームス所属のクリエイター。代表作は『Ever17 -the out of infinity-』、『極限脱出』(ZERO ESCAPE)シリーズ、『AI: ソムニウム ファイル』など。
江原氏:
ははは(笑)。けど、それを知って、『レトロチカ』のタイトルを日英で分けたことを改めて再考すべきと思いました。元々考えていたタイトル名だと商標が取れなかった事情もあったんですが、その壁を越えてでもどうにかするべきだったと。
小高氏:
上田文人さんの『人喰いの大鷲トリコ』も海外だと『The Last Guardian』になっていますよね。どうもここ2~3年で、海外版もタイトルが一緒のほうがいいらしいとの結論が出たらしく、僕もいまは一緒のものにしようと言っています。日本生まれのものはそのまま、『Danganronpa』のようにローマ字読みにしてしまえ、と。
江原氏:
海外のゲームファンは『ダンガンロンパ』でも特に首をひねったりしないんですか?
小高氏:
ひねらないですね。最初は『Trigger Happy Havoc』と、親切心で付けたんですけど、みんなその名前ではなくて『ダンガンロンパ』と呼んでくれる。その意味では、昔と違って日本のものが受け入れられるようになってきていますね。
 |
昔は海外でウケそうなものを作って、自分から迎えにいくような感じでしたが、いまはまったく逆。セガさんの『龍が如く』は『YAKUZA』というタイトルで売れているし、アトラスさんの『ペルソナ』もほとんどそのまま出している。『ダンガンロンパ』も翻訳はそのままで、「この概念って、向こうにはないんじゃない?」となってもそのまま変えずに突き付けています。もっと自然な日本っぽさを楽しんでくれる人が、ニッチであろうといると思いますし。実際、実写映画を通してアジアの作品を見る人が増えつつあるところもあるし、掘り下げていけるのではないのかな、と。その意味でも映像は使えるんじゃないのかなという気はしますね。
江原氏:
実際、韓流ドラマがその突破口を開いたとは思いますね。『レトロチカ』の対応言語数が多いのもそこに期待をかけているというのがあります。
小高氏:
まあ、韓流ドラマが普通に流れているから、昔ほど意識しなくなってきているんでしょうね。
 |
江原氏:
おもしろいものを作りさえすれば後は勝手に売れるだろう、というのは時として制作者の傲慢になってしまうケースもありますが、世界に共通するおもしろさというのはきっとあるのだと思います。
撮影時最大の難題“ライツ”。そして誰ひとり妥協しない現場勢の本気
小高氏:
『レトロチカ』は時代ものにしているじゃないですか。あれは海外でも受けるから、という戦略からそうしているんですか?
江原氏:
私はそのつもりです。着物や袴とかは入れてほしいと、伊東さんとたちばなさんにお願いしたんですよ。
あれ、でもどちらが先でしたっけ……? たちばなさんが先に「時代もので」と言ったんでしたっけ?
たちばな氏:
はい。私は「犯人を見つけた、やったー!」だけで終わりたくないと最初に言いました。なぜいま、この作品を作るのかというテーマ性をどうしても入れたいと話し、加えて長い時間軸を持ったストーリーにしたいと言いました。最初は、「和」がテーマになるのであれば、それこそ明治、大正、昭和、平成、令和という5つの時代を駆け抜けるものができたら素敵ですよね、なんて話だったと思います。
その上で興味を引き付けられるポイント……江原さん的に見せるべき絵と言いますか、絵力をより強めて欲しいというのが乗っかってきた感じです。私的にもすごく共感しましたので、その方向で進められていった感じです。
小高氏:
まさにストーリーとプロデュース側の双方で合致した感じですか。
たちばな氏:
そうですね。あとぶっちゃけた話をしますと、予算の問題とライツ的な問題がありますよ、と。
 |
実写映画などに比べ、私にとってゲームの難題はライツだったんです。つまり、商標的なものが映るというのが基本的にダメ。その制約が映画やドラマ以上だったんですよ。基本的には看板やロゴは映っちゃダメ。遠目でもエキストラ以外は映っちゃだめという感じで、「これ、どうしよう……?」となって。
小高氏:
ん? ……あ、そうか! 実写ゲームってそれがあるのか。忘れてました(笑)。
江原氏・伊東氏・たちばな氏:
(笑)。
小高氏:
いまって、CGでもそのまま作らないじゃないですか。東京タワーにせよ、商標や肖像権を侵害しないレベルで変えていきましょう、みたいに。CGだとやって当たり前な感じですけど……そうか、映像もそうなってくるんですね。
たちばな氏:
前回、小高さん、梅田さんと話したときに、いろんな場所に行けるとか、髪型や衣装がコロコロ変わることが実写のメリットなんだ、というのにはものすごく納得したんですが、そういう制約に悩まされ、実現できなかったことも多かったです。それもあり、ワンシチュエーションでストーリーを作る方向に傾きました。ただ、実写のポテンシャルを有効活用すれば別の形もあったとは思います。そこは今後に繋がる部分かなと思います。
江原氏:
ワンシチュエーションとミステリってもともと相性がいいので、たまたま今回はうまくはまりましたね。お屋敷が舞台のミステリってワクワクしますから。
たちばな氏:
そうですね。その相性の良さに救われたというか、その意味で妥協ではなく納得して取り組めたのは私の中でも大きかったです。
江原氏:
ロケーション数はがんばりましたよね。
 |
たちばな氏:
できるだけ同じに見えないよう装飾を工夫したり、別場所なんだけど近くで探して、移動の時間を抑えるとか、いろいろ頑張りましたね。ちょっと移動したら、こういう山の中もあるぞ、みたいに(笑)。
小高氏:
泊まりで行ったんですか?
たちばな氏:
ほとんどは都内近郊だったので毎日通っていました。4章の旅館だけ静岡だったので4泊くらいして一気に撮り上げたとか、泊まったのは限定的です。
江原氏:
神奈川の端っこで寒さに震えながら灯篭流しを23時ぐらいまで撮影して帰宅、次の日に朝5時にロケバス集合して群馬県みたいなこともありましたね。
小高氏:
えーっ!? きっつ!(笑)
たちばな氏:
ありましたねぇ……。だから何度か、スタッフも限界というときがありました。
ただ、『デスカムトゥルー』も多分、そんな感じだったと思うんですよ。もう合宿のような感じで。
小高氏:
まあ、そうですね。ずっと泊まっていましたし。
 |
たちばな氏:
これはプロデューサーあるあるなのですが、撮影が始まる前にはみんなで楽しめる時間を作るとか、一緒に温泉に入りましょうとかいろいろ考えるんですよね。ところが、いざ近くなってくると撮影、撮影、また撮影という(笑)。そういう人間的な豊かさを削って頑張らなければいけない現場も申し訳ないのですが、最終的には作品ファーストで頑張ってもらいました。
江原氏:
本当に日本人の美徳だなと思うのですけど、現場で誰ひとり妥協しないんです。台詞のリテイクもすごい数が出る。実写映像に関わっている人たちのプロ意識の高さというものをすごく感じました。ここまでやっているのに日本のドラマや映画が海外でウケる数が少ないのはどうしてなのかなと、うら寂しい気持ちにもなりましたね。だから、私はこのゲームが売れて、世界から評価されてほしいなと心から願っています。
たちばな氏:
一方で誰かがコロナに感染するとか、そういうリスクも常に抱えていましたね。これはやっぱり実写における最大の短所かと。
 |
江原氏:
1回、CGのゲームにする話も出ましたけど、それは長所を消すことになるのですぐに消えまして。
たちばな氏:
代わりが効かないことの短所と長所、「CGでいいじゃん」という言葉が常に浴びせられる中、実写でなければならない意味というのは、私にとって考えさせられたテーマでした。
ある日突然、流れ着いた末に決まった『レトロチカ』の制作
たちばな氏:
江原さんから予算の話がありましたけど、テクノロジーの進歩によって、将来的に実写のほうが安くなるという逆転現象が起こると思っているんですよ。そのときに「安いから実写にしよう」と言われてしまうのは嫌だな……と思っていて。
小高氏:
しかし、この企画って最初から実写だったんですか。そもそも、立ち上げはどんな経緯から?
江原氏:
はじめは実写のスチル(静止画)ベースのゲームを作ろうとしていました。でもいろいろあってそのプロジェクトはご破算になったんです。
その後、たちばなさんと伊東さんと「どうしましょう?」という感じでイチから議論しました。大体、3ヶ月ぐらいでしたかね……。実写でミステリ、時代ものというのがそこで決まっていきました。
たちばな氏:
ただ、私自身は実写であることにはそんなにこだわっていなかったんです。
コロナのこともあって、「どうします?」と江原さんが言ってくれて、最終的には伊東さんが気を遣ってくれたのもあったと思いますが「実写でやろう」と言ってくれた感じでしたよね。
 |
小高氏:
会社の反応はどうだったんですか?
江原氏:
「やってみたら」と言ってくれましたね。そして、決まったあとは任せてくれました。
このゲームが受け入れられる土壌がいまのゲームマーケットにはあると私は踏んでいましたし、日本単体で黒字化できなくても対応言語数が多ければ海外の売上でカバーできるだろうと。
小高氏:
それって何年ぐらい前の話ですか?
江原氏:
3年前ですね。
小高氏:
すごく長い期間がかかっているわけではないんですね。『428』は10年ぐらいかかっているという話でしたし。
一同:
(笑)。
伊東氏:
でも、あれも3年ぐらいですよ。
江原氏:
2年半から3年が最低ラインですよね。
 |
伊東氏:
人件費が一番かかりますから。
たちばな氏:
江原さんががんばって通してくれた、というものはすごく感じましたよ。
『レトロチカ』と比べられるのは『428』……?
伊東氏:
表現を実写にするかCGにするかで、私としては普通のドラマや映画があるとはいえ、実写の強みを活かしたいと思ったんですね。なので、自然とそうなったところはあります。
ただ、スクウェア・エニックスって、ひとつのキャラクターを作ったあと、そのビジネスを展開していくじゃないですか。小高さんも3年ぐらい前に飲んだとき、包み隠さず「キャラクタービジネスやりたいんだ! 大儲けするんだ!」っておっしゃっていて(笑)。
小高氏:
大儲けしたいですね(笑)。しますよ!(笑)
伊東氏:
(笑)。スクウェア・エニックスはゲームコンテンツだけではなく、そこから派生してキャラクターのグッズとか、実写化の舞台とか、スピンオフのゲームとかも作って展開させていくんですね。どんどんビジネスを膨らませていくのが、最近の日本のゲームの成功パターンみたいな感じになっていると思います。
小高氏:
さらに付け加えるなら、アニメもそうですよね。アニメもほぼ9割の収益がキャラクタービジネスですから。もう、円盤が売れる時代ではなくなって、グッズを買わせるのがメインになってきている。
伊東氏:
ただ、実写だとそこが見えないというか、読めないんですよ。
 |
江原氏:
アパレルへの派生展開も他のタイトルならありえるのですが、今回はそれもできないですね。特徴的な衣装はすべてJOTARO SAITOさんの作品なので。スクウェア・エニックスのマーチャンダイジングチームに意匠を複製したグッズを作ってもらって利益という結果を出して、次回作を会社に提案することもできたかもしれませんが、それすらも『レトロチカ』の表現をよりよくするために可能性を潰してしまった(笑)。なのでクロスメディア展開がやりづらいタイトルです。
伊東氏:
その意味で言うと、これは実写だったけど、スピンオフはアニメでやるとか。あるいはレゴを出すとか(笑)。そういう展開になりそうだとは思うんですよね。
たちばな氏:
そういう考えはなかったんですけど、なんだかすごくキャラクタービジネスがやりたくなってきました(笑)。
あと、ゲーム業界のことで、すごく素敵だなと私が思うことなのですが、作り手側とユーザー側もリテラシーが高いんですよね。その作品が生まれるプロセス、過去にどんな類似作品があったのか、その文脈に対する関心が非常に強い。
映画やドラマの世界だと正直、あまりないと言いますか、そこまでファンを信じていないような感じなんですよね。大きな塊にガーッと投げつけ、そのときたまたまヒットするかどうかになってしまっていると言いますか。
小高氏:
いや、ゲームもまだまだだと思いますよ。それこそ「アドベンチャーゲームというのはこうだ」と決めつけ、ユーザーや雑誌、webメディアがレビューしがちだったりしますから。
 |
『デスカムトゥルー』で一番非難を浴びたのは、「『428』に比べて圧倒的にボリュームが少ない」だったんですけど、「当たり前だろ!」というか(笑)。そもそも販売価格や制作の規模からして違うし。けど、それって実写ゲームの前例が少ないことも影響していると思うんですよね。
伊東氏:
同じことは『レトロチカ』でも言われると思うんですよ。
小高氏:
そういう人は少ないとは思いますけどね。章ごとの内容が長いですし。『デスカムトゥルー』はもとから圧倒的に短いので、その分、価格もお安くしたんですけど、うまく伝えきれなかったという(笑)。
ただ、ユーザー側からすればあまり関係ないんですよね。そもそも『428』って、Steamだと3960円で売られているじゃないですか。だから、いくら2000円で売ったとしても、近い価格帯で売られている『428』と比べられて「肩透かしだ」となってしまう。
それが本当に意見としては多かったです。そういった理由で1点のレビューをつけられましたし。
 |
江原氏:
Apple Storeで見ましたけど、すごく胸が痛くなりましたね……。
小高氏:
ただ、『レトロチカ』はボリュームがあると思ったし、言い方として変ですけど、ゲーム部分で結構時間を使えているじゃないですか。
それがあるから、体感としては普通に1章をプレイするだけでも、ある程度お腹いっぱいになれる。ちゃんと時間がかかるからこそ、やり応えがあるんですよね。
伊東氏:
フルプライス7000円とかの世界で、「その金額を出すのなら相応の体験を」と求める気持ちはわかるんですけど、最近だと脱出ゲームでも1回3000円ぐらい取られるじゃないですか。その2回分ぐらいと思えば安いし、映画4~5本分と思っても安い。だから、コンシューマーゲームって結構お得だなという気はするんですよね。
小高氏:
そうですよね。コンシューマーゲームはだいぶお得だと思います。
江原氏:
フルプライスだと、300時間ぐらい遊べるゲームと比べられちゃうんでしょうね。
伊東氏:
たとえば、オープンワールドゲームのプレイ時間の多くは移動が占めているわけじゃないですか。移動もない、スキル上げもない、戦闘もない。「そんなゲームで何百時間も遊べるとか大変でしょ?」という話をこのあいだ、スパイク・チュンソフトの人としたんですが(笑)。
小高氏:
ユーザー側としてもカテゴライズして遊ぶし、その先入観がいいのかどうかは本当にわからないですけどね。
江原氏:
『レトロチカ』は何と比べられるんでしょうかね……。
小高氏:
まあ、『428』だと思いますよ。
伊東氏:
『デスカムトゥルー』や『ダンガンロンパ』とも比べられそうですね。
江原氏:
『逆転裁判』も……。
小高氏:
ミステリものと分類すると『逆転裁判』はあるでしょうね。
江原氏:
だとしたら初作比較とすると、引けを取らないぐらいのボリュームはあると思いたいですが。
伊東氏:
ただ、そういうボリュームの話は何とか打破していきたいと思うんですよね。別に6時間でいいじゃん、1時間1000円でいいじゃん、という気はしているんです。
たちばな氏:
私の目線からだと、まずアドベンチャーゲームに対する危機感があるのかという問いかけと、尺の話ですよね。長ければいいのか、短くてはいけないのかというのはすごく重要なテーマである気がします。
 |
小高さんが話されているのは、アドベンチャーゲームという括りの中でいる限り、狭い世界であるということですよね? ただ、そこを求める声はあるし、いい意味で裏切っていかなければならないんでしょうね。
伊東氏:
イザナギゲームズさんがシューティングゲームとミステリを組み合わせた新作『冤罪執行遊戯ユルキル』を出されましたけど、ああいうのが求められているかもしれませんね。
『ダンガンロンパ』もアクションゲームの匂いを感じさせるものでしたし。
──でも小高さん、『ダンガンロンパ』はアドベンチャーゲームと言いたくないんだ、ってことを言っていましたよね(笑)。
小高氏:
一番最初はそうでしたね。そもそも、ジャンル的にはアクションゲームなんですけどね(笑)。ハイスピード推理アクション。アドベンチャーゲームと言ったことは1回もないです。
江原氏:
私は、まったくそういうのを見ずに、アドベンチャーゲームだと思って遊んでいました(笑)。
 |
小高氏:
そうなんですよ。海外だとビジュアルノベルと言われるんですが、公式にはアクションゲームなんです。
伊東氏:
寺澤さん【※】が言っていたんですけど、「アドベンチャーゲームはもう頭打ちだから、そうは言いたくないんだ」と(笑)。
※寺澤善徳氏:『ダンガンロンパ』シリーズのほか、『侍道』シリーズ、『ザンキゼロ』などを手掛けた元スパイク・チュンソフトのプロデューサー。現在フリーで活動中。
小高氏:
そう。売る一番最初のときに言っていました。