人口の1/3が65歳以上の高齢者になり、超高齢化社会によって生産労働者人口が減少するなどさまざまな問題が引き起こされる「2030年問題」に直面していく日本。人の仕事がAIに取って代わられるとも言われている。
2030年までに起こりうるさまざまな変化に、ゲーム産業、あるいは産業分野に未来はあるのか。そして、ゲームクリエイターを含めた産業を支える働き手たちは、この未来にどう立ち向かっていくべきなのか──。
 |

そこで電ファミ編集部がお話を伺ったのは、「Unity Technologies Japan」の執行役員・大前広樹氏だ。
「Unity」は2005年の出現から現在に至る17年間で、個人制作のインディーズゲームから大手が制作するビックタイトルまで、さまざまな規模のゲーム開発プロジェクトで採用されるゲームエンジンに成長し、ゲーム開発ツールでは世界的シェアを持つまでになった。
基本無料など初心者でも比較的手軽に高いクオリティのゲーム開発が可能となり、マルチプラットフォームへの対応や、2D・3Dゲームの垣根なく活用できるなどの利便性によって、“ゲーム開発の民主化”をもたらした。
くわえて、その使い勝手の良さから、アニメ、自動車、ロボティクスなどゲーム産業の枠を超えた他産業分野にも進出し、さまざまな領域で使用されている。2022年10月25日(火)・26日(水)には、Unityの大規模オンラインカンファレンス「SYNC 2022」を開催。さまざまな産業分野に広がるUnityの開発事例や技術的なナレッジをテーマにした数多くのセッションも配信される予定だ。

大前氏にあらためて「Unity」とはいったい何か、「Unity」による他産業の現状を振り返ってもらうとともに、これほど幅広い分野で着実にシェアを伸ばしてきた「Unity」にとっても次なるチャレンジである「2030年はどんな未来になっているのか」を聞いてみた。
執筆/阿部裕華
編集・取材/TAITAI
「ゲーム産業の人」と「ゲームを学びたい人」のニーズに上手くはまった開発プラットフォーム
──「2030年はどんな未来になっているのか?」の話しに入る前に、大前さんから見て「そもそもUnityとは何だったのか?」というところから入らせていただければと思います。ゲーム産業においてUnityは何をもたらしたのでしょうか?
大前広樹氏(以下、大前氏):
ゲーム産業の人たちのニーズと、ゲームを学びたい人たちのニーズの間にできていたギャップに、上手くハマった新しいゲーム開発プラットフォームが「Unity」だったのだと思っています。
「Unity」が出現する以前のゲーム開発の世界にもゲームエンジンはあったけど、当時は企業も個人もゲームを作るために個々でゲームエンジンを作っていた。それぞれが別の山に登っている状態です。
こと企業においては、「CEDEC」などの交流会でノウハウを共有する場で「こういうエンジンを作ってこういう風に使った」という話しを聞いて、「自分たちもやろう」と思っても、他人の登っている山と自分たちの登っている山は違うから、ノウハウの使い道がない。共通の山に登らない限りはどうしても概念上の意見交換にしかならない。そこにUnityという共通のひとつの山が現れた。

共通の山を登ることでノウハウを共有し合え、かつ良いものを組み合わすことによる化学反応が起こった。自分がゼロから作った山ではないゆえの不都合さもあるけれど、総じて「こっちの方が良い」となったんです。
ゲームを学びたい人たちにとっても、「Unity」出現前は「ゲームの作り方」という本はあっても、ブレゼンハムのようなゲームに向いたアルゴリズムの学び方だったりとか、あるいは「DirectX」の使い方のようなAPIに関する話か、あるいはプロ向けの非常に高度な内容が主流でした。
学びを深めるために専門的な学校に通っても、発表の場でたどり着けるラインが「3Dモデルのキャラクターを歩かせてボタンを押して攻撃する」くらいのところで力尽きてしまっていた。そして、ゲーム産業に入ってみると学ばなければいけないことの多さに絶望する。
「影響を受けたゲームと同じようなゲームを作りたい」と思っていたのに、そこに至るまでの距離が離れすぎて途方に暮れる状態。そういう課題をすべてすっ飛ばしてくれたのも「Unity」だったんですよ。ゲーム開発を始めるまでに必要なイニシエーションのプロセスが全部なくなって、いきなりゲームの内容から考えて動かせる状態になった。しかも深く掘り下げていくと、中でどんなプログラムが走っているかも分かる。
「Unity」に流れていった企業からすれば、「ゲーム開発の限定的な知識しかなくても、Unityが使えれば採用する」となるわけですよ。需要と供給のバランスがキレイに揃ったことで、パラダイムシフトが起こった。それが「Unity」の出現によるゲーム産業の「革命」、「民主化」と言われることに繋がったんじゃないかなと。
──企業を含めプロフェッショナル以外、それこそ学生や素人にも「Unity」が使われていったのはどんな要因があったと考えますか?
大前氏:
やっぱり無料化に踏み切ったこと。それまでは何百万か何千万円も支払わないと手に入らない環境、あるいはそれ以上の環境が無料で手に入ったのは大きいですよね。
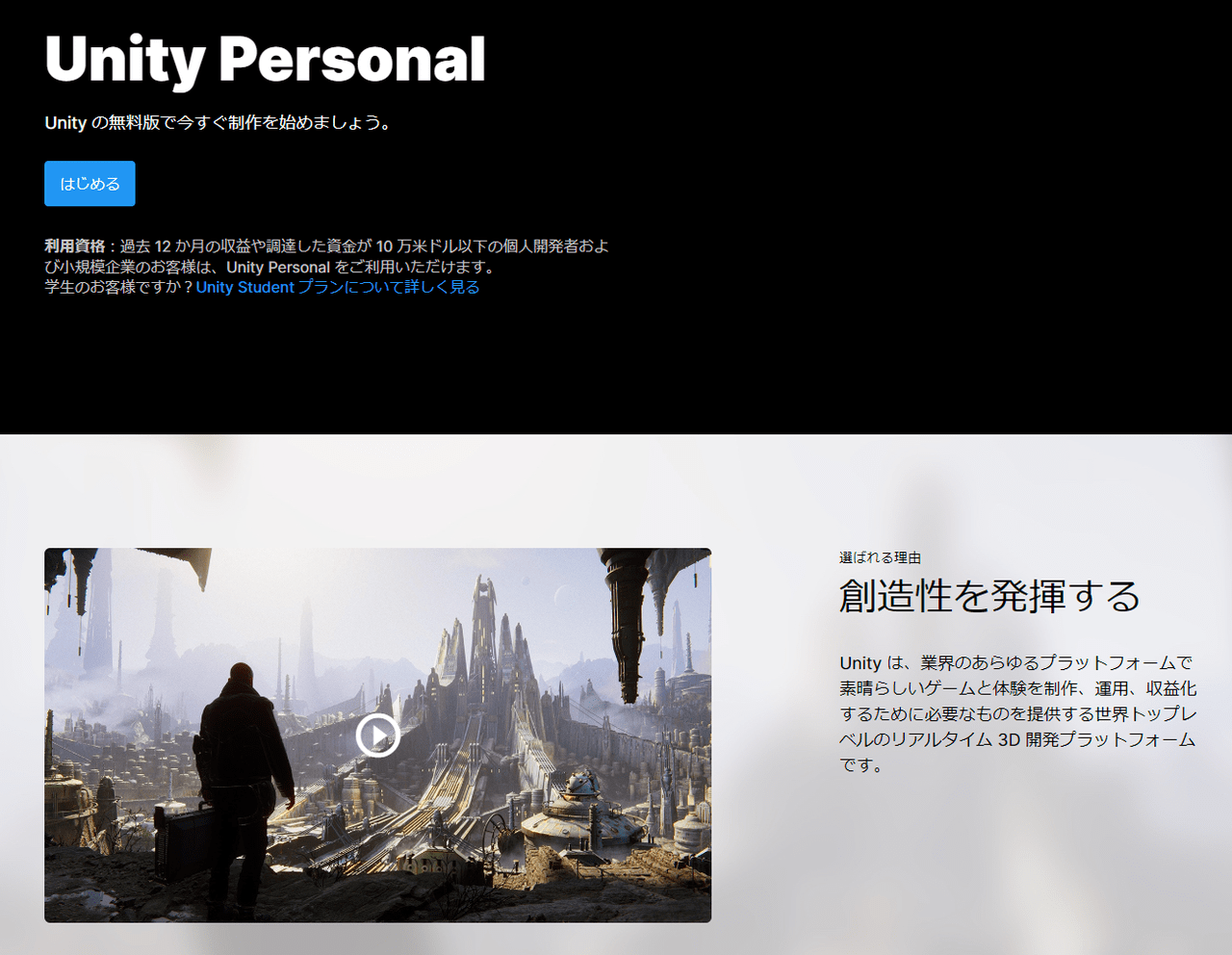
(画像は「Unity Personal」公式ページより)
それ以外だと、「Unity」はどのゲームを作るにしても、良くも悪くも特定の用途にはまり切らない設計になっていたのが要因としてあると思います。8割くらいの環境は整っているけど、2割くらいは自分でツールやシステムを作らなきゃいけないところがあった。
逆に2割の余白があることで、どういうゲームでも作れるようになっているんですよ。この「8:2」の法則がちょうどよくて、「自分のゲームが作りたい」と思った人たちが、「Unity」の上に自分の必要な開発環境を足してゲームを作れるようになったんですよ。
──2005年にUnityが出て、2007年にiPhoneが出ました。iPhoneでは個人開発のゲームを配信できるようになりましたけど、「Unity」がアプリゲームに適した開発環境だったのも、大きくシェアを伸ばしたひとつの要因でしたよね。
大前氏:
たしかにそのタイミングまでは、新規の人たちが「Unity」にいっぱい入ってくるイメージはあまりなかったですね。
iPhoneの登場により、クリエイターとユーザー、クリエイターとマーケットの関係が大きく変化しましたよね。個人ゲーム開発者や小さなゲーム開発企業が、App Storeで作ったゲームを直接販売する。それによる「クリエイターとユーザーが直接繋がったら商売になる」という文化圏が生まれた。
そして、それまでは売上の3割から4割しか開発者の懐に入ってこなかったのに、突如として7割入ってくる世界ができた。期間関係なく配信していてもストア代金を取られずに売上の7割が懐に入ってくるなんて、昔では考えられなかった状態ですよ(笑)。
そんな中で「どういう風にゲームを作って出したらいいんだ」と考えたとき、適切なテクノロジーの位置にたまたま存在したのが「Unity」だった。iPhoneのために作ったゲームエンジンではないし、ほかに同じようなゲームエンジンがあれば、ほかのツールがその位置になり得たとも思います。たんに「Unity」が需要にハマって、アプリゲーム開発に最大採用されるポジションになったに過ぎない。
──コンソールゲームの開発環境に「Unity」を使うのがスタンダードになっていくのは、それよりもう少し先という認識で合っていますか?
大前氏:
ええ。しばらくはコンソールゲームへの期待値と現実が上手くすり合わない状態がありました。「Unity」のバージョン2ぐらい、2006年ごろのタイミングで、Wiiに一度対応してみたことがあるけど、まったく上手くいかなくて。
メモリ制御やパフォーマンスの問題など、ゲームエンジンとしての性能が担保できているとは言い難く、かなりつらい戦いを強いられている感じがありました。「これでみんな幸せになれるぞ」と言うには憚られていて、そんなにメジャーなポジションにはなりませんでした。
──Unityが完全にコンソールゲームにもアジャストできたタイミングはいつ頃だったんですか?
大前氏:
Nintendo Switchで完全にすりあったと思っているので、2017年ごろのタイミングじゃないかな。そのころからゲーム制作の順番が変化してきて、「Unityをコンソールゲームで使おう」という話しが増えてきたように思います。
以前は勝ちハードに向けた企画を設計して、それをベースに開発するという順番で進めていた。それが徐々に、まず作りたいゲームを企画して開発したあとに、オーディエンスがいそうなプラットフォームに持っていくという順番になった。後者の順番だと複数ハードに対応している開発環境や、高いコストを負わなくても別のプラットフォームに展開できることが重要になってくる。
そういうマルチプラットフォーム化はエレクトロニック・アーツみたいな大企業だけがやっていたけど、いまは基本的に企業もインディーズ(個人)も生存戦略として必要になってきた。
またプラットフォーマー側も、バリエーションに富んだタイトルを生み出せるなど力を持っているインディー開発者へ近づくために「Unityのようなゲームエンジンがちゃんと使えるようにしなければ」と考えているようにも感じています。
──Nintendo Switchなんかは、明らかに「インディゲームのプラットフォーム」として大きなポジションを得ていますよね。
大前氏:
そうですね。とくに最近はコンシューマーゲームのストアも、“タイトルの許認可”に対するコミュニケーションが明らかに変わってきていると思うんですよ。マーケットにアプローチできること、マーケットの中で繋がれるユーザーがいること自体を重要視しているように感じる。
要するに「すべてのタイトルがマスにアピールできるコンテンツである必要はなく、小さく刺さるゲームがたくさんあっても良い」ということです。その変化を「Unity」が起こしたかというと、「Unity」だけの成果ではないと思いますが、それに大きな影響を与えたことは間違いないですね。
「Unity」アニメ制作の現状はインディーズゲーム黎明期と同じ?
──「Unity」はここ数年、ゲームのみならず映像やアニメ制作におけるツールとしてのポジションも開拓していますよね。
大前氏:
僕らはテクノロジーを作る上で「そこに助けたいクリエイターがいるか」を重要視しています。映像産業のクリエイターのみなさんから「新しいテクノロジーを使って一緒に作ってみたい」という話しを聞くことがあり、まずはプロフェッショナルの方たちに向けて開拓を始めました。
※「Unity」で制作された映像作品のショーケース映像。
ただ現状は、アニメ制作におけるプロフェッショナルの世界にUnityはあまりフィットしないと感じています。
──なぜフィットしない状態だと?
大前氏:
今のアニメ制作現場はとても多くの人たちが稼働しています。そうしないと30分の映像が出来上がらないから。一方、Unityのアニメ制作に適しているのは少人数のチームなんですよ。
それこそUnityは3DCGのリアルタイムレンダリングが可能だから、監督を含めストーリーテリングを考える人にとっては、制作過程で演出的に変更したい箇所があるとすぐに修正ができる。
※「Unity」で制作され2016年に公開された『第9地区』ニール・ブロムカンプ監督(Oats Studios)の短編映像『ADAM』。アーティストやデザイナーがシーンを撮影するのに些細な変更を行なっても即座に反映され、撮り直しにかかる時間とコストを大幅に削減。こ通常であれば一年は掛かるところを5ヶ月間で完成させた成功例として公式サイトで紹介されている。
一方で画を作るアニメーターたちは設計書に従って描くわけだから、大人数で制作を進行していると何か少しでも変更があった場合、その担当のアニメーターに共有して修正してもらう必要が出てくる。それってすごく効率が悪いんですよ。
「Unity」によって、大人数で予定調和的に作っていくより、小規模な人数でいろんなアイデアを試行錯誤して、現場でそれを取り入れながら作るという今までにない作り方ができるようになった。
だけど、それは現状の制作現場にねじ込んでも良いことはないんですよね。作り方を根本から変えないといけない。曲がりなりにも商業生産ラインが成立している企業が「Unity」を選択したいかというと選択しないでしょうと。
現状の商業の作り方に対して「最高だ」とみんなが思っているかというとそうでもない。小さいチームで多くのイノベーションが起きる作り方をしないと先がないと言っている人もいます。ただ、いまはその人たちが「Unity」一本で作ろうと思えるほどアクセルを踏める状態にない。ほどなくして出てくるのではないかと思いますけどね。
──現状もまったくいないわけではなさそうですが……。
大前氏:
例えば、Nintendo Switch用ソフト『Fit Boxing』のシリーズを原作としたアニメ『キミとフィットボクシング』は「Unity」を使用し、少人数のチー
──アニメのクオリティ的な面は、どうなんですか?
大前氏:
インディーズゲームの黎明期と同じという印象ですね。それこそ『キミとフィットボクシング』はゲームのアセットを活用して作っています。ビジュアル的にはゲームのカットシーンに近い作りだけど、SNSのコメントを見てもみなさん普通のアニメとして見ている。ただ、やはり従来の「アニメ」と呼ばれて想像するものとは違うものだとも思います。
以前はインディーゲームも大手ゲーム企業が出すようなゲームはなくて、別枠として受け入れているようなところがあった。それが、いまでは商業生産ラインのゲームかと思うようなインディーゲームも生まれているわけですよ。これに至るまでには10年くらいの歳月がかかっている。アニメに関しては、当時のインディーゲームの入り口なのかなと思っています。「Unity」は、その入り口を一生懸命支援しようと試みている感じですね。
あとは、ユーザー側の価値観も変化してきていると思っていて。『キミとフィットボクシング』の前にもVtuberが出演者として活躍しているアニメ作品【※】があって、そうした作品には「アニメのカテゴリに入るのか?」という声もあったけど、ユーザーはあまり気にせず消費している。今ではYouTubeでVTuberの動画を見る人が増えてきて、人々が3DCGアニメに慣れ親しんできた。
※Vtuberが出演者として活躍しているアニメ作品:大前氏は作品名を挙げていないが、2019年には30人以上のVtuberが出演するオムニバス作品『バーチャルさんは見ている』が放送された。
VTuberの映像を観ていると、キャリブレーションミスで変な挙動をしちゃうことがあるじゃないですか。一昔前なら「エラーを直さなきゃ」と思っていたところを今は気にせずに出しているし、ユーザーも気にしていない(笑)。
それはユーザーがどんどん慣れ親しんでいることで、今までは完璧じゃないといけなかったところをスルーするようになったんですよね。アニメのクオリティとして完璧ではなくても「これはこれで良い」と受け入れてくれることが増えていくのではないかと思います。
──制作環境やユーザーの価値観を含めて、アニメのあり方が今まさに変化し始めているんですね。
大前氏:
そういう感じはしています。僕はその変化、とくに新しい作り手、新しい作り方が日本から起きると良いなと思いつつも、未来を思うとそれは難しいのかなと感じる事もあります。そういう大きな変化って、需要がある地域の若者が起こしているように思うんです。結局、どんなコンテンツ産業でも、イノベーションが起こるのは「ベテランが監督していない領域」なんですよ。
アニメを含めた大規模な映像制作現場は、ほぼ確実にベテランが監督していますよね。そういう歴戦の猛者みたいな人がいるから作画崩壊のような事故が防げ、すばらしい作品が世に出ている事実はあるけれど、逆に若手のアニメーターが冒険できる領域が減ってる側面もあると思うんです。
日本はそういうガッチリした製作体制が組まれている国だけど、いま若者が多く活力がある東南アジアやアフリカの国なんかは、そういうのがない分、「Unity」みたいなものに手が出しやすいだろうなと。
※中国の若き女性映像制作者イービン・ジアン氏らが2020年に完成させた短編アニメーション『Windup』。ホームオフィス用の一般的なデスクトップコンピューターとUnityで制作された作品で、さまざまな映画アワードのアニメーション 部門で受賞を果たした。
そして、自分のクリエイティビティを発揮したい若者はTikTokやYouTubeへと流れている。そういう人たちは「3DCGを学んでそれでアニメーションを作るんだ!」という人と系統が違うかもしれない。「3DCGってなんやねん!」と思っているような人々でも、企画やストーリーテリングは上手だったりする。
そっちがどんどんマジョリティになっていくと考えた時、彼らのクリエイティブがスタンダードになっていく。昔、ニコニコ動画で映像を作っていた人たちが今は映像作家として活動しているのと同じようなことが起こるのではないかと思います。
──ベテランがいない場所の人たちが「Unity」を手にした時に、何を表現してくれるのか未知の期待があります。文脈がないからこそ、爆発が起こり得るのではないかという話ですよね。
大前氏:
起こり得ると思うし、「Unity」はそういうものに寄り添っていく存在になりたいですよね。ゲームの話しになりますが、クリエイターのやりたいことを実現するために必要な要素を粛々と用意していくことに「Unity」の開発役割をシフトしていく一方、AIを使った制作支援の研究開発をしているんですよ。それがいつツールとして実装されていくのか僕にはまるで分からないんだけど……(笑)。
アニメでも同様に、クリエイターが「こういう風にしたい」と言ったことからデータに落とし込む翻訳作業をできる限りAIに任せていく。「Ziva Dynamics」【※】も同じ意図を持っていて。たとえば、ライオンの筋肉の動きを作るプロセスをAIに任せることで、誰もが「これこれ」と思える良い感じのデータを挿入してもらえるとか。その分、労力を省力化できるから、クリエイターが選択に集中できる。そういうアシストが「Unity」でできるようになると良いなと思っています。
※Ziva Dynamicsは2015年にカナダ・バンクーバーで創業したソフトウェア会社で、おもに機械学習などを用いた高度なシミュレーションでリアルタイムキャラクター制作などを実現するソフトウェアを展開している。2022年1月にUnityが同社を買収した。
──そういう意味では、コンテンツ制作ツールの中にAIを取り込んでいくムーブメントはあるのか?をあらためてお聞きしたいなと思います。
大前氏:
ムーブメントはなくはないです。最近僕が見た中で「すごいな」と思ったのは、イラスト自動生成AI(「Midjourney」)が数百種類のダンジョンのタイルを生成するという話。言葉を指定するだけでさまざまなバリエーションの絵が生成されるんですよ。
それと「AIで生成した画像だけでUnityでシューティングゲームを作ってみた」という投稿をTwitterで拝見したときも、これは来ちゃったなと思いました。
つまりAIは、ゲーム世界に取り込めるデータを再生成する翻訳作業として、大きな能力を発揮すると思います。イラスト自動生成AIにおける言葉の表現の翻訳というのもそのひとつ。そもそも人間の動きや表情などは身振り手振りをすればデータとして存在するはずだけれども、それをゲームで扱うために翻訳するのはものすごく大変。そこでAIの力を借りるわけです。
ひとつはモーションキャプチャのような、データを取り込んで表現する部分にAIの力を借りる。いままで「Vicon」などの高い機材を使わないとどうしようもなかったことが、「Plask」のようなサービスを使えばWebカメラ一個で録れるようになってきた。すると個人でもモーションキャプチャを使ったゲームが作れます。
マテリアルでもAIの力を借りられると思います。現実世界にある素材を写真撮影してデータとして取り込む。そのデータをテクスチャとして3D空間に上手くはめ込む作業をAIにやってもらう。身の回りにあるジャストなものを取り込んで3D空間で使えるようになる、ということは今後たくさん起こると思います。
──ただ、最近流行っているAIによる画像生成の凄みって、過去にあった「あれ、いいよね」というモチーフの抽出をやってくれることだと思うんです。
それってデータの補正や補完ということではなくて、たとえば、昇龍拳のような動きを取り込んでアニメチックに再現するとして、それを写実的に行うんじゃなくて、一番カッコいい昇龍拳の動きを抽出&表現できることが重要だと言いますか。
大前氏:
これは確実に起きる話だと思うのですが、次のステップとして、キャプチャしたモーションから、昇龍拳のようなカッコいいタメの動きに“添削”してくれるAIが生まれるんじゃないかなと。いろんな作品の動きを「Stable Diffusion」と同じような形でラーニングして、決まった角度で見たときと同じようにキーフレームを整理・追加・削除するAIが追加されるはず。
記憶が正しければですけど、たとえば『アンチャーテッド』などは、標準の敵モーションに対して味付け用のキーフレームを用意して、標準のモーションにこの味付けフレームをブレンドすることで、敵キャラクターの動きにバリエーションを持たせていたんですよ。そうすることで安価にそれぞれの敵に特徴的な動きを付けている。
3DCGアニメーションは、そもそもそういう風に加工や合成がしやすいデータなので、たとえばスタンダードなモーションに「ディズニー風」や「ジョジョ風」というキーワードを追加すると、それっぽく処理したアニメーションができてしまう、みたいなことも可能だと思います。その世界では、無限のバリエーションの中で選び取っていくことになるのだろうなと思います。
──AIを活用する世代のクリエイターの役割が、ある種の取捨選択だったり、編集的なものの色合いが強くなっていく可能性はありそうですよね。


































