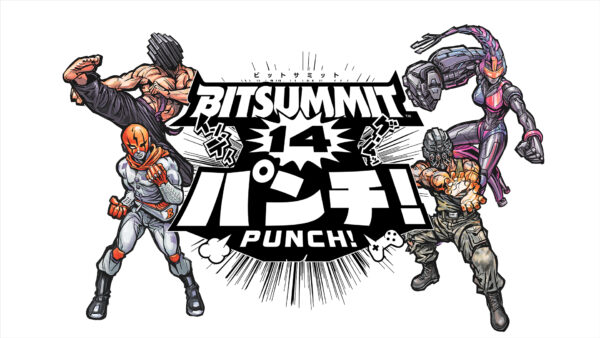アドベンチャーゲームは、やはり“独自性のあるシステムとストーリーが混然一体となった作品”こそが面白い……!
筆者のみならず、そうした唯一無二性を求めてやまないゲーマーの方々も多いはずだ。具体的なタイトルを出してみよう。
コマンドを入力して地下迷宮を探索する『Zork』、コマンドを選択して殺人事件を解決する『オホーツクに消ゆ』、選択肢がある小説を読み進める『弟切草』、美しい島でマウスでクリックしながらパズルを解いていく『Myst』、過去を調査して名簿を完成させる『Return of the Obra Dinn』、未知の言語を解読する『7 days to end with you』……。
これらをざっと並べたとき、ゲームシステムという観点でみるとほとんど「別ゲー」であることに気付く。たとえばアクションゲームだと反射神経を用いてキャラクターなどをうまく制御しつつ、クリアしていくゲームシステムが根幹にある。RPGだと成長システムや戦闘システムの楽しさがある。つまりこれらのジャンルには、何らかのシステム的な共通項がある。
しかしアドベンチャーゲームというジャンルの場合、システム的な共通点は必ずしもなくていい。要は「物語」や「謎解き」さえ主軸に置かれていれば、ゲームシステムは“何でもあり”なのだ。そしてそのゲームシステムを使って、どのような物語を語ることができるのか。こ
の多様性こそがビデオゲームのストーリーテリングの実験場としてのアドベンチャーゲームが機能している役割、いわばジャンルの存在意義ともいえるものだろう。
そして2010年にニンテンドーDS向けに発売された『ゴースト トリック』もやはり、「物語」や「謎解き」に、独自のシステムをプラスした忘れがたい作品だ。
『逆転裁判』シリーズの巧舟氏が手掛けたことで知られており、他にはないゲームシステムを持っている。そのゲームシステムは「〇〇システム」といった名称は与えられていないが、ゲーム内では「死者のチカラ」と説明されているものこそが、独自システムの総称として理解していいだろう。
その『ゴースト トリック』のHDリマスター版がPS4、Xbox One、Nintendo Switch、PC(Steam)向けに6月30日に発売される。
今回のリマスター版は、現行機向けにグラフィックが高解像度化されており、さらに高フレームレート化に対応した。またオリジナル版は2画面だったが、今回はユーザーインターフェースを1画面で快適にプレイできるように最適化されている。
今回はこのリマスター版の2話まで遊ぶことができる体験版を一足先にプレイしたので、改めて本作の独自システム「死者のチカラ」の真骨頂とは何かを考えてみたい。そして併せて巧舟氏をはじめとした開発スタッフにメールインタビューを実施することができたので、最後まで読んでいただければ幸いだ。
記憶を失いタマシイとなった怪しい男の物語
 |
本作の主人公は、サングラスをかけ赤い服を着た、金髪のトンガリ頭という怪しげな風体をしている男。しばらくプレイすると「シセル」という名前がすぐに判明するが、それ以外はこの男が何者なのかはわからない。なぜなら彼は何者かに殺されてしまっており、街の片隅で死体となって横たわっているからだ。彼は自分の記憶を思い出せぬまま、タマシイとなって目覚めたのだ。
そしてシセルの目の前では、殺し屋が女を殺す瞬間が繰り広げられていた。しかしシセルは死体であり、何もすることができない。女が殺されそうになった瞬間──「あの方を救えるのはアナタ様でございます」という不思議な声が響く。
謎の声に言われるがまま、シセルはタマシイとして、近くの物体に憑りつきつつ、操ることで、死にゆく人々の「運命」を変えていく。なぜ自分は殺されたのか、誰が自分を殺したのか、そして自分は何者なのか。
エキセントリックな個性的なキャラクターや独自のユーモアに惹きつけられていると、いつのまにか伏線が繋ぎ合わさる真相に至り、そこには怒涛の結末が待っている……という巧舟氏ならではシナリオは本作でも健在だ。
独自システム「死者のチカラ」による2種類のパズル
 |
上記のプロローグでも描かれているが、シセルの前には次々とキャラクターたちが現れ、そして死んでいく。これらはまずカットシーン的に提示される。
だがシセルは時間を巻き戻すことが可能で、さらに時間を止めながら物体に憑りつき操作することで“間接的に”救済することができる。つまりさきほどのカットシーンに「介入する」ことができる。これが大まかに言えば「死者のチカラ」だ。
物体の操作をどんどんと繋ぎ合わせて救済というゴールに導く流れは、NHKの番組「ピタゴラスイッチ」に登場するような、球をゴールまで転がす「ピタゴラ装置」に例えられることが多い。もちろん、「球」が「キャラクター」の役割をはたし、最終的に「ゴールまで流れを紡いでいく」というパズルという意味では大きな共通点がある。
 |
しかしピタゴラ装置は、球が移動するレールを追っていけばゴールが見えているが、『ゴースト トリック』の場合は最終的なゴールがどのような形になっているのかはわからない。また主人公がタマシイのために「移動」するのは一筋縄ではいかない。操作したい物体になかなか到着できないことがしばしばあり、これらも物体を操作して打開しなければいけない。つまり本作は「流れを紡いでいくパズル」に加えて「移動」自体もパズルになっているわけだ。
物体を操作するとどのような挙動になるのか、それに対してキャラクターたちはどのようなリアクションを取るのか、この手探りで試行錯誤を繰り返すのが本作の真骨頂だ。
「ビデオゲームの物語」に対する棄損とそれに対する解答
これは一般論だが、ストーリーというは主人公に何らかの目標や動機があり、それを達成するために奮闘するものである。そしてゲームもまた、プレイヤーにとってゴールに到達したり、相手に勝利するなどの目標がある。
しばしば「ゲームに物語は必要ない」と乱暴に言われることがあるが、それはゲーム自体が目標を持っているからだろう。つまり物語上の目標を必要とせずとも、ゲームを思わず進めてしまう仕組みが、そもそもゲームに含まれているわけだ。
ビデオゲームにおいて、ゲームシステムの目標を阻害するために「物語」が存在したとき、それは「物語が邪魔」と棄損され、「物語」が嫌われ者として標的になるわけだ。そうした嫌われものは、ゲーム的な仕組みが含まれていない、「鑑賞するだけのカットシーン」についてしばしば向けられてきた。
 |
一方で本作『ゴースト トリック』は、人間ドラマが展開している場面に対して、「死者のチカラ」として時間を止めたり、スタートに戻ったり、物体に憑りついたりして、いわばカットシーンに介入できるようなゲームデザインを構築することができた。
筆者が『ゴースト トリック』が特に優れていると感じるのは、ピタゴラ装置ではなく、こうしたゲームとストーリーの目標が一致して仕組みとしての「死者のチカラ」を作れたことだ。物語はゲームの足を引っ張るものでもないし、その逆でもない。本作はその融合によって強固なストーリーゲーム体験が生み出せることを証明している。
巧舟氏をはじめとした開発スタッフにメールインタビュー
さて、ここから本作の生みの親である巧舟氏をはじめとして、丸山敦史氏、和泉真吾氏の開発スタッフにメールにて取材することができたので、インタビューをお届けしたい。

──オリジナル版が発売されたのは13年前ですが、改めて振り返って『ゴースト トリック』は巧さんのなかでどういう作品なのでしょうか?
巧氏:
あくまで、ぼくの中でのハナシですが…『ゴースト トリック』は、当時も今も変わらない自信作です。
もちろん、完璧な作品なんてあり得ませんが、システムもシナリオもキャラクターも音楽も、ぼくにとってはすべて最高です。当時のチームの熱量は圧倒的で、二度と作れないレベルのゲームになったと思っています(…実は『逆転』も『大逆転』も同じ所感ではあります…)。
──なぜ今回のタイミングでリマスター版が実現したのでしょうか。署名運動などもありましたが、ファンの声が届いたのでしょうか。
和泉氏:
はい、移植のご要望がたくさん寄せられていた作品だったことと、遊んでいただいたユーザーの皆様の満足度が非常に高い作品だったので、これを13年前にお届けできなかった方に、ぜひ遊んで欲しいと考えたことが今回の移植を決めた理由です。
そのため今回の移植では、マルチプラットフォーム対応とアジア言語の追加対応を行いました。
また、原作の発売から13年が経過していますが、いつの時代にも、どこの国の方でも、どんなハードでプレイしても変わらない「普遍的な面白さ」を持ったタイトルという点も大きかったです。
 |
──今回のリマスター版で、こだわった部分、注目ポイントを教えてください。
丸山氏:
リマスター版の注目ポイントはやはり個性的なキャラクターですね。今回のリマスターにあたりキャラクターの表情や服装などを加筆修正し、よりキャラクターの個性が引き立っています。また、新要素の「イラストアツメ」では、そのキャラクターのデザイン案やモーション案を見ることができ、いろいろな方向からキャラクターを楽しむことができます。
──オリジナル版の企画の出発点を教えてください。そこからどのようにして『ゴーストトリック』の基本コンセプトに至ったのかをお聞きしたいです。
巧氏:
『ゴーストトリック』のインスピレーションの源は、「『逆転裁判』とは違うスタイルの新しいミステリを作りたい」というテーマでした。
最初に浮かんだキーワードは“群衆劇”…謎めいた人たち全員が主人公のゲーム。最初に考えた企画では、ゲームの舞台は一棟のマンションで、そこに暮らす様々な住人たちを観察して、彼らが抱えた謎を解いていく、というゲームでした。
そこで、そういう「観察」ができる主人公は、どんな存在なんだろう…と考えた時に浮かんだのが「タマシイ」でした。最初のゲームコンセプトは、“演じる”というキーワードで、主人公はモノやヒトにとりついて、そのヒトが持つ固有の能力を利用して謎を解いていく…というゲームでした。
そこまでは比較的スムーズだったのですが、うまくまとまらなかったので、思いきって“ヒト”を削って、“モノ”に絞って考えていった…という感じです。
 |
──『ゴースト トリック』はシステムの考案が先なのでしょうか。それともストーリーが先にあったのでしょうか。
巧氏:
このゲームのテーマのひとつは、「物語とパズルの融合」でした。避けたかったのは、シナリオを楽しんでいるところに、物語と関係ないパズルが差し込まれて興味をそがれてしまう状態。イメージとしては、パズルを解くことで、同時に物語も進行するようなゲームにしたかったのです。
そのため、物語とゲームのルールは、互いに影響しあいながらできあがっていきました。これは、ゲームデザインとシナリオをひとりでやっているからできたことなのかな、と思います。
──『逆転裁判』のシナリオと違って、『ゴースト トリック』のシナリオの書き方に違いはありましたか。
巧氏:
やはり、ミステリーとして最初に考えるのは最終的な“着地点”だったと思います。主人公の正体と、「死者のチカラ」にまつわる部分ですね。それとほぼ並行して、オープニング…物語をどこから始めて、どう展開させるかを考えました。そして次に、“群衆劇”に登場する人物たちの案をいろいろ考えました。どんな職業で、どんな悩みを抱えていて、それがどうやって解決されるか…個々のエピソードをいろいろ考えました。
そして、使えるアイデアを選り分けて組み上げて…それにあわせて、必要なステージをリストアップして、パズル案を考えるのと並行して第一稿を書きました。…実際は、そんな整然とは進みませんが、こんな感じでしょうか。そこから実際にゲームを作りながら、シナリオはどんどん変わっていくわけですが…それは『逆転裁判』も同じですね。
 |
──シセルはサングラスをかけた赤い服を着た金髪のトンガリ頭という、主人公としては異例なキャラクターデザインになっていますね。
巧氏:
実は、シセルのデザインには、ほぼ時間がかかっていないんです。企画当初、会社にプレゼンするための映像を作る時、仮のキャラクターモデルが必要だったので、当時の弊社のとあるゲームに登場するモブキャラの中から何人か借りてきて流用したのですが……その中に、シセルの原型になるヤツがいたのです。トンガリ頭でサングラスをかけた彼が。
その服の色を変えて、頭身を調整したのが妙に気に入ってしまって…結局、そのまま主人公にしてしまいました。決して手を抜いたわけではなく、ホントに“一目ボレ”してしまったのです。
当時、マッタク異論は上がらなかったので、それはもう「運命」だったのだと思います。ちなみに、それがなんのゲームだったのか……探してみるのも一興かと(笑)。
 |
──ところで巧舟さんは最近、何に関心を持たれていますか。近況を教えていただけますか。
巧氏:
最近、海外の簡単なミステリーを探して原書で読むのにハマっています。紙の本ではムリですが、kindleを使えば、知らない単語をタッチすると一瞬で意味を教えてくれるのが、気絶するほどベンリです。
決して日本語に飽きたわけではないし、特に英語が得意でもないのですが、“暗号解読”、“謎解き”の趣きもあって楽しいです。
──今後、『ゴースト トリック』はリマスター版に限らず展開することはありますか。続編やスピンオフ、メディアミックスなどのアイディアや、巧さんの「新作」は何か準備しているのでしょうか。
和泉氏:
今は『ゴーストトリック』をできるだけたくさんの方にお届けすることで頭がいっぱいなので、今後のことは考えられないですが、続編やスピンオフの制作を検討したくなるくらい、多くの皆さんに本作をプレイしてもらえることを願っています。
巧氏:
『ゴースト トリック』の困ったところは、これ以上ないほどキレイに終わってるコトですね。でも、《死者のチカラ》には、まだ可能性がありそうです。ぼくはミステリーが好きなので、これからも“驚き”を大切にしたモノ作りをしていきたいと思っています。だから、いつかまた新しいプロジェクトが発表される時、みなさんにシッカリ驚いてもらいたいので……今後のことは、秘密にしておきます。
──ありがとうございました。(了)
当初「ヒト」にも憑りつく仕組みを考えていたこと、さらに「シセルの原型になるキャラクター」や「《死者のチカラ》には、まだ可能性がありそう」など気になる発言が飛び出した今回のインタビュー。
本音をいえば、2017年の『大逆転裁判2』以来の巧氏の新作をプレイしたいが、巧氏のモノづくりの「これからも“驚き”を大切にしたモノ作りをしていきたい」という決意を伺うことができた。久々に『ゴースト トリック』を堪能しつつ、イチファンとして「今後のこと」を気長に待ち続けたい。