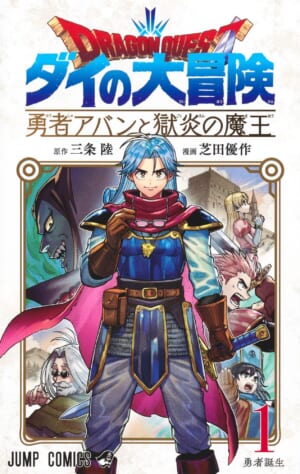『ダイの大冒険』のロジックバトルに影響を与えたのは、あの特撮
──こちらも『三条陸 HERO WORKS』からですが、「ポップ」が鳥嶋さんから「早く殺せ」と言われてそこに三条先生が反論する……というエピソードが書かれていました。実際、三条先生にとって「ポップというキャラがヒットする勝算」はあったのでしょうか?
三条氏:
そこは漠然と「ポップならできる」と考えていました。逆に「ポップのようなキャラを用意しておかないと、他のジャンプ漫画のヒーローと比べた時に、『ダイの大冒険』は負ける」と思ったんです。
当時のジャンプにおけるヒーローの描き方は、「最強の主人公がひとりいる」「主人公を支える最強の仲間たちがいる」の2パターンがオーソドックスなものでした。ですが、『ダイの大冒険』はそのどちらと戦っても有利ではないと判断しました。
だからこそ、「ダントツで強い最強の主人公を別ベクトルで支えられるキャラがひとりいて、時にはそいつが主役を張る」という、その2パターンのどちらでもないキャラの描き方を思いつきました。なので、「勝算があった」というより、「ポップというカードを入れることで他にはない個性が出る」と考えていました。
「このままでは他の漫画と真っ向から戦えない」「この漫画でしか読めないものがないとダメだ」などの考えから、ポップは生み出されました。そして、ダイの勇者然としたキャラクター像は読み切りの段階で決まっていたので、作品の空気を単調にしないためにもダイとは正反対の性格のポップを入れる必要がありました。ちょっと野心的なところがあって、あまり「良い子」とは言えない感じです(笑)。
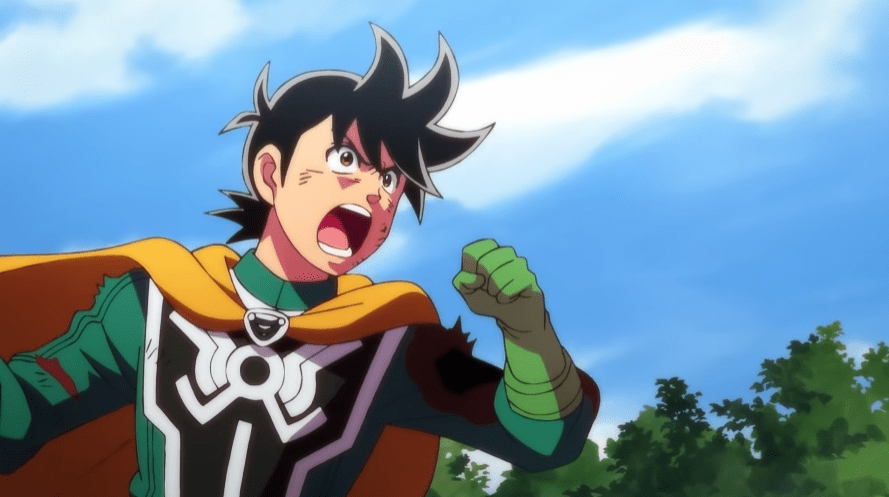
三条氏:
『三条陸 HERO WORKS』でも書きましたが、ポップは『機動戦士ガンダム』で言うところの「カイ・シデン」なんです。そして、最初からカイのことが好きな人はまずいないと思うんですよ(笑)。
だけど、ジャブローくらいからカイがめちゃくちゃ頼もしく見えてきます。シリーズの途中から「やっぱりコイツがいないとダメなんだ」と思えるようなキャラがひとりでもいると、作品全体で主人公が活躍するシーンとは違った魅力を出すことができるんです。
あまりにも主人公がダントツで強すぎてしまい、そこに対する2番手が完全に「2番目の強さ」に設定されていると、1番手と2番手で感じる「感動の色」が同じなんです。作品全体で、「同じ色の感動」を作ることしかできません。
ですが、ポップのような「全然期待していなかったヤツが勝った」パターンは「感動の色」が全く違うんですよね。そういう色の違う感動こそ、あとになって「なんだかんだあの作品で一番盛り上がったのはあそこだよな」と思い返したりするんです。
──たしかに、ポップの活躍はあとになればなるほどじわじわ「良さ」が来るような感覚があります。実際、当時の読者からのポップの反応はどういった感じだったのでしょうか?
三条氏:
クロコダイン戦を描いたあたりで、読者にもポップが認められてきているような感覚はありましたね。そしてバラン戦でポップがメガンテを使う回が一番読者アンケートを獲得できた回でしたし、むしろ「ポップが活躍する回の方が順位が上がる」という認識でした。
やはり主人公のダイは勇者としてやらなければいけないことがあるので、少なからず最終的な興奮や感動の色が定まったものになってしまうんです。「想定通りの活躍になってしまう」と言いますか。
逆に、ポップのような読者の想定外の「感動の色」を出した時は、明確にアンケートの結果に出ていたんですよね。
──ちょうど今お話していただいたクロコダイン戦もそうなのですが、『ダイの大冒険』は「2回戦うパターン」が多いですよね。あの「2度戦う」スタイルは意図的なものだったのでしょうか?
三条氏:
あのリターンマッチ形式は意図的なものです。そして、『ドラゴンボール』がゴジラだったとしたら、『ダイの大冒険』はガメラ【※10】だと思ったんです。
ゴジラは「ゴジラが圧倒的に強い」という前提でお話を作るので、対怪獣にせよ対人間にせよ、基本的に1度のバトルで決着をつけます。要は「ゴジラが最強」なんてことはみんな知っているから、1度のバトルでも面白くできるんです。そして、『ドラゴンボール』も「悟空」という圧倒的なヒーローを立てていますよね。
逆に、ガメラは同じ相手と大体3回くらい戦うんです(笑)。何度か戦う内にちょっとずつ相手怪獣の弱点がわかってきて、最後はその情報の全てを駆使して勝つんですよね。そこがやはりゴジラの映画とは全く違った面白さです。
しかも超常存在に近いゴジラと違って、ガメラは「僕らの友達の怪獣」に近いんです。子供たちもガメラに感情移入しながら見ることができますし、何度かのリターンマッチも許容できるんです。
あと、東宝の怪獣映画って高級でカッコいいんだけど、ちょっと眠たいシーンが多かったりして……。
一同:
(笑)。
※10「ガメラ」
大映が1965年に公開した特撮映画『大怪獣ガメラ』に登場した怪獣。後にシリーズ化され、怪獣映画の一大ブランドとなる。
三条氏:
そういう意味でガメラの方が画面のテンポが良いし、楽しんでもらうためのアイデアがいっぱい入ってるんです。大人になった時に見ると、意外とガメラの方が面白かったりするんですよ(笑)。
この「テンポとアイデア勝負」「戦闘のロジック」に関しては圧倒的にガメラの方が好きでした。
──『ダイの大冒険』のロジック的なバトルは、やはりガメラから影響を受けた部分が大きいのでしょうか?
三条氏:
そうですね。そして個人的には、『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』がすごく好きなんです。まず、ギャオスって弱点が何個もあるんですよ(笑)。ガメラと3ラウンド戦う中で段々とギャオスの弱点が暴かれていくのに、それでもギャオスを倒せません。
その「弱点が3つも4つもあるのに、それでも倒せない強敵」というだけで、敵キャラとしてすごく面白いんです! 回転に弱い、後ろが向けない、太陽光線に弱い、高熱に弱い……たくさんのギャオスの弱点が判明して、人間もガメラも対策して立ち向かうのに……それでも勝てない!
「これだけベールが剥がされても倒せない」というだけですごく強敵に見えますし、ガメラの「敵怪獣もかなりキャラが立っている」ところは『ダイの大冒険』の敵キャラ描写に活かされていますね。
──今でこそ「ロジック、頭脳戦を重視したバトル漫画」は数多く世に出ていますが、『ダイの大冒険』はあの当時にロジックを意識したバトルをあそこまで展開しているのも印象的です。そこに、王道の「ダイの圧倒的な強さ」も噛み合うことで、熱さが生まれているように感じました。
三条氏:
ダイは、「圧倒的な力を持っているけど、それをコントロールできない」ということを序盤の壁にしています。「力が思うようにならない」ことをドラマとして引っ張っています。
そしてこれは『仮面ライダーV3』【※11】から着想を得ている部分です。「V3」は26の秘密を持つ最強のヒーローなのですが、V3に変身する風見志郎自身は「V3にどんな能力があるのか」を知らないんですよね。それが何度か、V3のピンチを演出するんです。
あの「最強の力を持っているのに、思うように勝てない」ことのロジック的な上手さに、子供ながらにすごく興奮した覚えがあって……(笑)。
「仮面ライダーV3は1号と2号の強さを併せ持ったライダー」と言われると、それは強くて当たり前なんです。ですが、「変身する本人が、自分自身どのくらい強いのかわからない」というロジックが入ってくると、一気に面白くなりますよね。あの「仮面ライダーの圧倒的な強さ」「ハラハラするドラマ性」の両方を満たしている『仮面ライダーV3』の面白さは、子供ながらに興奮していました。
※11「仮面ライダーV3」
初代に続く、「仮面ライダー」シリーズの2作目。仮面ライダー1号・2号の後を継ぐライダー3号「V3」の戦いを描く。
──やはり「圧倒的に強い」という気持ち良さは大切ですよね。
三条氏:
先ほどの「ゴジラとガメラ」も当てはまりますが、やっぱり「強いヤツがいて、カッコよくて気持ちいい」ことひとつ取っても、その段取りには好き嫌いがあるんですよ。たとえば「好きなお風呂の温度」に関しても、人によっては42度が熱すぎると感じたり、そこがちょうどいい人もいますよね。
そこの「どのくらいの温度が好きか」を自分自身で把握しておくことが、原作者の強みに繋がると思います。
もちろんゴジラもガメラも見る分にはどちらも好きですが、自分で描くとなると「ガメラ的な、ロジックを意識した戦い方」の方が好きなんです。そして、「ロジカルな戦い」そのものがジャンプの雰囲気に合っていますよね。ジャンプって、戦いのロジックだけを永遠に研究し続けているようなところがあるから……(笑)。
一同:
(笑)。
三条氏:
そして、ジャンプの読者に戦いのロジックが嫌いな人はいないですよね(笑)。
逆を言えば、「バトルのロジックが弱いと、ジャンプの読者は離れてしまう」とも考えていました。だからこそ、『ダイの大冒険』ではバトルのロジックは常に意識していましたね。
「仮面ライダーにジャンプのノウハウを持ち込む」とは、どういうこと?
──やはり三条先生は「特撮」をご自身のルーツに持ちながら、その知識などを漫画媒体のジャンプで展開されたのがすごいと思います。
三条氏:
たしかに、そういう人はあまりいないかもしれないです。やはり僕の「他所で手に入れたもの」が、たまたまその時のジャンプのニーズに噛み合ったのが大きいと思いますね。ジャンプ内の作家に持ってないものがあったからこそ、スタメンに入れてもらえたのではないかと。
こういうことが起きるからこそ、どんな仕事でもひとつひとつをちゃんと吸収した上で、次のフィールドに活かしていくことが大切です。そういう意味で、『ダイの大冒険』と全く逆のことが起きたのが『仮面ライダーW』です。仮面ライダーの脚本を全くやっていなかったのに、いきなりメインライターでしたから(笑)。
一同:
(笑)。
三条氏:
普通はサブライターからメインライターに昇格するんですが、僕の場合は「いきなりメイン」のパターンが多いんですよね。
『ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU』【※12】だってテレビアニメの脚本を一度も書いたことがない中でいきなりシリーズ構成でしたし、『獣電戦隊 キョウリュウジャー』も戦隊の脚本を書いたことがないのにいきなりメインでしたからね。
※12「ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU」
2005年から2006年までテレビ朝日にて放送されたロボットアニメ。かつて東映アニメーションが制作した『大空魔竜ガイキング』を原点とした作品。三条氏がシリーズ構成を務めている。
──特に『キョウリュウジャー』でも三条先生が全話書かれていましたよね。昨年の『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』でも井上敏樹さん【※13】がほぼ全話を担当されていましたが、実際「全話書く」ということはどのくらい大変なのでしょうか?
三条氏:
『キョウリュウジャー』に関しては、当初「16話と劇場版まで連続で書いてくれないか」と言われていたんです。
ですが、その当時の「スーパー戦隊で連続でスタートから一番長く書いた脚本家」は『百獣戦隊ガオレンジャー』の武上純希さんで1~18話でした。だから、「どうせなら一番連続で書いた人になりたい」と考えて20話くらいまで書かせてもらったんです(笑)。
そして半分くらいまで書いた段階で、「まだ書ける」と思ったんです。そのまま終盤までスルスルと行ってしまって、劇場版もVシネも全部書けてしまいましたね。
とはいえ、『キョウリュウジャー』に関してはスタッフやキャストのみなさんに助けられた部分が大きいですね。書いていて詰まることが全くなかったので、「全話書けちゃった」という感覚です。しかも「すごい頑張って全話やり遂げた」ですらなく、「あれ?まだ全然書けるぞ?」という余裕すらありましたね。
それこそ、井上さんがまさにこのタイプだと思います。役者さんの演技などを脚本に吸収しつつどんどんアップデートしていくスタイルは特撮においてかなり重要ですね。
※13「井上敏樹氏」
『仮面ライダー555』『仮面ライダーキバ』『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』などを手掛けた脚本家の井上敏樹氏。描かれる独自のキャラクター像やシナリオから、ファンの熱量が高い。

──実際、特撮のような1年分の脚本を書かれる場合はどのような作業で進められるのでしょうか? 何話かをストックするような形なのでしょうか。
三条氏:
それはもう番組によって全然違いますね。
余裕のある時もあれば、ストックが全然ない時もあります……(苦笑)。
少し過去の話になるんですが、『ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU』の際に井上さんと初めてお会いしました。そこから井上さんに実写の『キューティーハニー THE LIVE』に誘っていただいたのですが、あそこで一度特撮脚本を経験していなければ『仮面ライダーW』でメインライターはやりきれなかったと思います。
──『仮面ライダーW』が紆余曲折があって完成したことは『三条陸 HERO WORKS』内でも語られていましたが、やはり事前の打ち合わせも大変だったのでしょうか?
三条氏:
やはり番組に関しては大勢で作り上げていくものなので、全員の目指す「ひとつの完成像」を作り上げるのは中々難しいんです。
そして、当たる作品と当たらない作品があるのは、その「完成像」を作れるか作れないかにかかっているのだと思います。この完成像を作れるかどうかは、本当に「その時の運」としか言いようがありません。
そしてここも普通とは違うのですが、『仮面ライダーW』には週刊少年ジャンプのノウハウが入っているんです。キャラの立て方なども含めて、ジャンプの週刊連載と毎週日曜朝に仮面ライダーを放送することはちょっと似ています。
だからこそ、『ダイの大冒険』などの週刊連載を経験したことが『仮面ライダーW』にはすごく活きています。だから、『仮面ライダーW』は平成ライダーの中でもかなり漫画チックな番組に仕上がっているんですよね。
──『仮面ライダーW』において「ジャンプのノウハウ」を活かしたところをもう少し具体的にお聞きしたいです。
三条氏:
それこそ「先代ヒーローがいて、新たなヒーローに受け継がれる」ところなんかは、まさにアバンからダイに勇者の意志が受け継がれるのと丸々同じ骨格のものを使っています。
先ほど挙げた「ロジックを意識した戦い」も、まさにジャンプのノウハウが活きたところです。『ダイの大冒険』などで「この技を使って、こうやって逆転する」というバトル展開を毎週書いていましたから、特撮の「作劇の中にパワーアップアイテムを組み込む」ことをあまり苦に感じませんでした。

三条氏:
そして、企画当初の『仮面ライダーW』は「主人公は、ひとりのハードボイルド探偵」というものを想定していました。ですが、テレビ局さんが「ハードボイルド探偵ものが子供たちに支持されるとは思えない」という懸念を抱いていました。さらに、Wのデザイン自体がツートンカラーになった時に、「ツートンカラーであることの説得力」が必要になりました。
それを一挙に解決するために「バディ探偵もので、ふたりの探偵が合体する仮面ライダーになるしかない」というアイデアを考えました。そこから「視聴者が感情移入しやすい半人前の探偵で、先代から継承する主人公」と「ハードボイルドでストーリーの中核を握っている謎の存在」というふたりのキャラを考え、最終的に「翔太郎」と「フィリップ」になります。
そして翔太郎の「ハードボイルドな先代に憧れている、“ハーフボイルド”」という構造を作れた時が、『仮面ライダーW』の成功の第一歩だったと思います。テレビ局さんも気に入ってくれましたし、僕としても「これは、『ダイの大冒険』とは逆の構造なんだ」と納得することができました。
──「逆の構造」とはどういった意味でしょう?
三条氏:
要約すると、『仮面ライダーW』はポップが主人公で、ダイが相棒なんです。
「大筋のストーリーと世界観を担う」というダイのポジションをフィリップが務め、「それに一生懸命ついていく相棒」というポップのポジションを翔太郎が務める構造になりました。この構造を作り出せてから、翔太郎とフィリップのかけ合いが格段に書きやすくなったんですよね。
とはいえ、「ハードボイルド探偵」という元のコンセプトを守るためにも、各エピソードの最後には必ず翔太郎がビシッと決めるシーンを入れていました。そうすることでプロデューサーさんやテレビ局の方も納得してくれましたし、やはり特撮の脚本は「橋渡し」的な役割も重要になってきますね。
この「みんなの意見の相違をまとめ上げつつ、ひとつの完成像に持っていく」ということは、粘り強さが必要です。せっかくの仕事なのに、周りが揉めていると嫌じゃないですか(笑)。
さまざまな問題を解決するためにも、みんなの意見をしっかり根掘り葉掘り聞いた上で、それぞれのパーツを組み上げていくのは脚本家の役割だと思います。
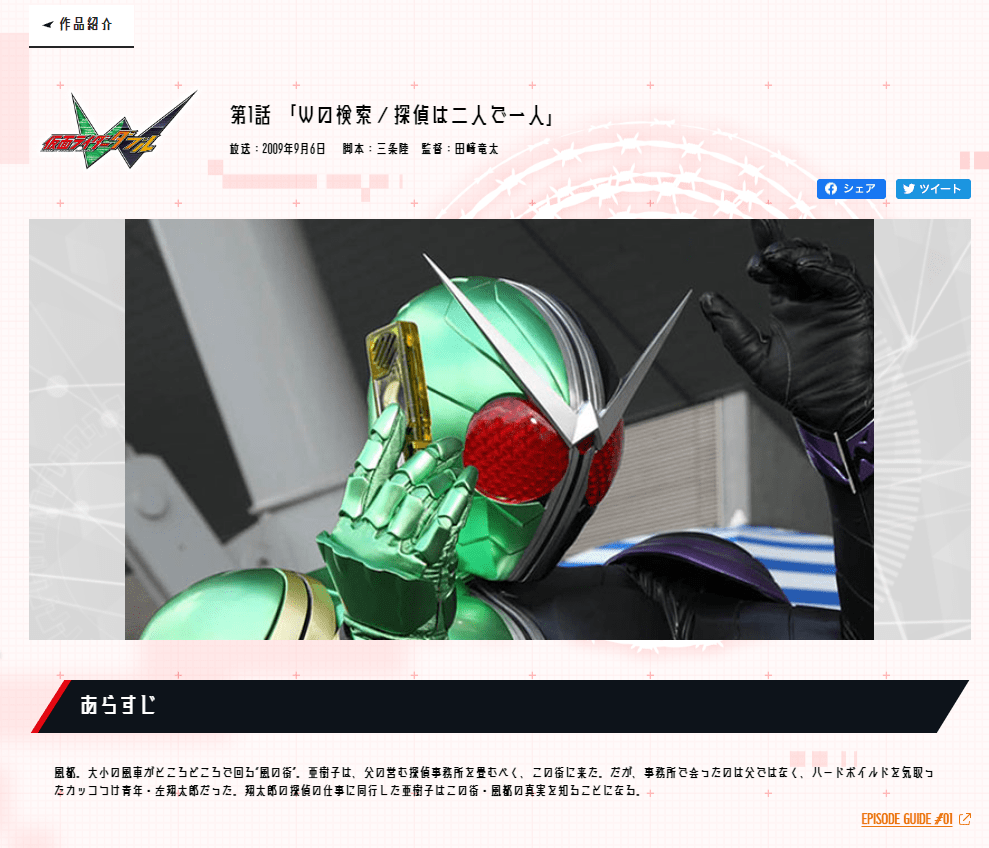
──やはり『仮面ライダーW』といえば、あのシンプルかつカッコいいフォルムが印象的です。
三条氏:
仮面ライダーとしての「W」がシンプルな色で左右にスパッと分かれることは、ある程度決まっていました。だからこそ、「ディティールは仮面ライダーらしくしよう」ということを大切にしましたね。
ですが、「身体が真っ二つの仮面ライダー」というアイデア自体は、僕が本格的に参加する以前からあったんです。そこから「ベルトにふたつの音声ユニット(ガイアメモリ)を入れて、開くことで音を合わせる」という「ダブルドライバー」の設定を固めていきました。
加えて、完成したフィルムでも「メモリの入れ替えで片側だけがフォームチェンジするのも、今までのライダーと違ってカッコいい」という反応が大きかったので、ふたつセットでフォームチェンジするのではなく、片方のメモリを何度も入れ替えながら戦うのが「仮面ライダーW」の特徴になりました。
──フォルムの面で言うと、「仮面ライダージョーカー」【※】もすごくカッコいいですよね。
三条氏:
「仮面ライダーW」自体がディティールの仮面ライダーらしさを意識していたので、黒一色になった「仮面ライダージョーカー」【※14】は結果的に仮面ライダー1号に近くなっているんです。
ちなみに、翔太郎役を演じてくれた桐山漣くんは『仮面ライダーBLACK』世代でした。だからこそ、「ひとりで仮面ライダーになってみたい」という願望もあったようで……それを劇場版の『仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ』で叶えてあげた形ですね。
僕としても「漣くんに全身真っ黒のライダーでライダーパンチとライダーキックを言わせてあげたい!」という気持ちがすごく湧いていましたし、ある意味「1年頑張ってくれた漣くんへのサービス」みたいなものですね(笑)。
※14「仮面ライダージョーカー」
左翔太郎が単独で変身した仮面ライダー。全身黒のビジュアルと格闘を主体にしたバトルスタイルが印象的。やや特殊な立ち位置でありながらも、そのカッコ良さからファンの多いライダーでもある。

──『三条陸 HERO WORKS』で、『魔法戦隊マジレンジャー』の「マージ・マジ・マジーロ」という呪文を三条先生が考案されたことも書かれていました。『仮面ライダーW』のふたりが合体する設定もそうですが、やはり三条先生は「子供の心を掴む」のがすごく上手いと感じます。
三条氏:
東映の塚田さん【※15】が『魔法戦隊マジレンジャー』の設定を考える時に、「キャッチーな呪文がない」ということで悩んでいたんです。特に、「この番組がマジレンジャーであることが一発でわかるような、“個性のある呪文”が欲しい」ということで塚田さんは苦心していました。
そこでアドバイザー的なポジションとして僕が呼ばれた際に、なんとなく「塚田さんの番組って『アバレンジャー』も『デカレンジャー』もEDでアバアバ、デカデカ言ってるから、『マジレンジャー』でもマジマジ言えばいいんじゃないですか?マージ・マジ・マジーロみたいな……」と言ったら、その場で「それだ!!」と呪文の名前が決まったんです(笑)。
その時の「三条陸にお願いしたら一発で解決した」という印象が塚田さんの中で強かったらしく、『仮面ライダーW』で再び塚田さんにお声がけいただいた形でしたね。
※15「塚田英明氏」
東映所属のテレビ企画制作部長兼チーフプロデューサー。『特捜戦隊デカレンジャー』『仮面ライダーW』などの人気タイトルを手掛けた。
後年振り返った時、あのシーンだけ妙に印象に残った。それは「感動の色」
──『勇者アバンと獄炎の魔王』の1話では『ダイの大冒険』の番外編を再構成していたり、『風都探偵』【※16】では劇場版の「ビギンズナイト」を再構成されていました。三条先生の中で、「1度描いたものを漫画で再構成する」ということの狙いなどはあるのでしょうか?
三条氏:
もちろん再構成することによって別の面白さが出る……という狙いもあるのですが、実は「原作と作画のテンポを合わせる」という意味があったりします。
そしてこれは『ジガ-ZIGA-』【※17】での経験が活かされているところが大きいです。
『ジガ-ZIGA-』は早めに打ち切られてしまった作品なのですが、作画の肥田野先生とかなり早くテンポを合わせることができたんです。そこで「やはり連載漫画は“原作と作画のテンポが合う関係”に、いかに早く入っていくかが大切」ということに気づきました。
僕はネームを切るタイプの原作者ではなく、文字だけの原作を書くタイプだから、より合わせに行くのが難しいんです。だからこそ、「『ジガ-ZIGA-』の後半くらいのシンクロ率にいかに早く辿り着くか」が重要だと考えました。
なので、『勇者アバンと獄炎の魔王』では「過去に僕が書いた原作をそのまま芝田先生に渡してネームを再構成してもらい、それを稲田先生が昔切ったネームと比較してもらうのが、一番学習速度が早いのではないか」と思ったんです。
※16「風都探偵」
『仮面ライダーW』のテレビシリーズの続編に相当する漫画作品。2017年から連載が開始。
※17「ジガ-ZIGA-」
週刊少年ジャンプにて連載された漫画作品。全2巻。原作の「佐野ロクロウ」が三条氏の別名義であったことが『三条陸 HERO WORKS』にて明かされた。
──ある種、「チュートリアル」的な狙いがあるのですね。
三条氏:
そうですね。作画の芝田先生も1話を再構成していく中で、「こういう狙いがあって、このネームになっていたのか」と気づかれていたようなので、この作戦は結構成功しましたね(笑)。
──すごく単刀直入な聞き方になってしまうのですが、三条先生にとっての「面白い原作を作るためのロジック」などがあれば、ぜひお聞きしたいです。
三条氏:
僕は、面白い作品を見たら必ず「この作品が面白かったのは、なぜなんだろう?」と考えるクセがあります。逆に、面白くなかった時も「これはなぜ面白くなかったんだろう?」と考えるようにしています。下手したら、後者の方が長く考えているかもしれません(笑)。
一同:
(笑)。
三条氏:
とにかく、僕は「この主人公は、このキャラがいるからあまりヒーロー性が感じられないんだな」「これは受け入れられないヒーローだと思ったけど、この設定があるからカッコいいんだ」などの面白さのロジックを解析する癖があるんです。
その解析の中から、「自分が気に入ったもの」「自分が燃えたもの」などのパーツを探してきて、その「面白かった理由」も含めて忘れないようにします。常にその方法が成功するわけではないのですが、この解析を繰り返すことで、自分の作品の「答え」を見つけられる感覚があるんですよね。
加えて、「自分の好き嫌い」を解析することも重要だと思います。
たとえば「スターウォーズが面白かったから、自分もこんな作品を書こう!」と考えても、大規模な群像劇が苦手な書き手だったら全然ダメですよね(笑)。つまり、「自分はこういう性格だから、このジャンルの作品を書くのが得意」という自身の性質まで解析して、データバンクに入れておくことが大切ですね。
どんなにすごい成功例でも、結局使うのは自分です。自分に全然向いていない成功例をデータとして持っていても、仕方がないんですよね。
そして、この「自分の好き嫌いの解析」は、まさしく「ポップ」に活かされています。
僕は『機動戦士ガンダム』が好きだったんですが、一方続編の『Zガンダム』にはあまり乗れなかったんです。その理由を自分なりに考えていった結果として……「カイ・シデンのようなキャラがいなかったから」という結論が出ました。つまり、「感動の色」が1色しかないように感じていたんです。
──先ほども話題に出ていましたが、その「感動の色」についてもう少し詳しくお聞きしてもよいでしょうか?
三条氏:
僕があまり乗れない作品は、感動の色が単一なことが多いんです。同じ感動だけがずっと続いてしまう作品は、どうしても印象に残らなかったりします。
すごく極端な例になってしまうのですが、僕が『ダイ・ハード』の1作目で一番好きなところはラストの「トラウマで銃を撃てなくなっていた警官が、主人公のために銃を撃つ」シーンなんです(笑)。
『ダイ・ハード』は全編100点満点の映画なんですけど……いつも思い出すのはあのシーンなんですよね。だって、あのシーンだけ明らかに感動の色が違うんです! そして、それと同時にあそこの興奮もすごいんです!
最強の主人公であるマクレーンが赤色の感動を持っているとしたら。あそこの警官のシーンだけは青色や黒色の「色が違う感動」です。マクレーンが出せる感動とは全く違う色があそこにはあって、だからこそ何年経ってもあのシーンを忘れないんですよね。
僕が100点満点だと思う作品は、絶対にそこの「感動の色」が1色だけではないんです。ああいう2色目、3色目の感動を出せる作品は本当に強いと思います。
先ほど話題に出た「フレイザード」なんかも、「ただ悪いヤツなのではなく、爽やかさすら感じる」というふたつ目の色を用意することで、より味わい深い悪役にできました。
──「感動の色」という表現も含めて、三条先生は言葉のニュアンスを明確にする技術が卓越しているのではないかと感じています。抽象的なニュアンスなのではなく、ハッキリと表現しているからこそ、それが作品の完成度に直結しているのではないでしょうか?
三条氏:
僕は抽象的な言葉からニュアンスを何段階か積み重ねていって、しっかり意図が伝わるようにしゃべることが多いですね。たとえば、一口に「熱いキャラ」と言っても、「どういう熱さ」なのかを作画の方に理解してもらうために細かく表現します。「周りが感化されてしまうようなカリスマ的な熱さ」「触るとやけどするような危険な熱さ」など、より細分化してイメージを伝えますね。
たぶん、ここで「単に熱いキャラです」だけで作画担当の方との意思疎通が終わってしまうと、表面的なところしか伝えきれないのだと思います。
ただ、やはり作画の方は「絵から吸収する」のが一番早かったりします。そのキャラの印象や家柄などの背景はイラストひとつで伝わることもありますから、一旦僕の方でキャラのラフを描くことも多いですね。
──やはりそこの「イメージの伝え方」に三条先生流の技術があるのですね。
三条氏:
技術というより、「細かくニュアンスを伝える」ことそのものを楽しんでいるところはありますね。作品を面白くすることにも繋がりますし、自分自身もニュアンスの細分化を楽しんでいます。この「伝え方」は、いつも考えていることですね。
もう少し簡単に言えば、「過去のこういうキャラみたいな感じ」という例を挙げる伝え方も、ある意味ではニュアンスの細分化だと思います。とにかく、自分の中のイメージが鮮明に伝わることが大切です。

──具体的に、三条先生はどのようにキャラクターを作っていくのでしょうか? やはり、実在の人物をモデルにされることが多いのでしょうか。
三条氏:
やはり「周囲の人の良いところをキャラにする」パターンが多い気がします。つまり、僕は基本的に人の「良いところ」を見ています。鳥山先生は鳥嶋さんをピッコロ大魔王にして近藤さんをフリーザにしていましたが、僕は鳥嶋さんをマトリフにして近藤さんをアバンにしています。
つまり……鳥山先生と僕は完全に見てるところが逆なんですよね(笑)。
一同:
(笑)。
三条氏:
やはり鳥嶋さんも近藤さんも、根はすごく良い人なんです。そういうところを素直に「すごいな」と思ったうえでキャラクターに投影しているのではないでしょうか。もちろん、実際に担当編集としてあのおふたりがついていた鳥山先生と僕とでは、明らかに見え方が違うと思うんですけど……(笑)。
だから、周りのいろいろな人の在り方をしっかりと見た上で、「良いところ」をベースにしてキャラを作っているのだと思います。逆に、先ほど話題に出た「ザボエラ」はそこから逆算して作っているところはありますね。「本当は良いところがある人なのに、ダメになってしまう」という。
──三条先生が描かれる作品は、「悪役でもお互いをリスペクトし合っている」という印象があります。『ダイの大冒険』の六大団長などが、特に印象的です。やはりあの空気感は三条先生の「良いところを見る」というスタイルが出ているのでしょうか?
三条氏:
それはやはり、僕の人の見方が出ているところだと思います。やはりひとつでも美点があれば、そこをしっかり「良いところ」として捉えたいです。どれだけ仕事がダメだったとしても、すごく性格が良かったら、やっぱりそれはその人の一番良いところなんです。
だからこそ、人の「弱点」も受け入れられるんですよね。たとえば、「こんなに人がいいから、みんなのことを考えすぎて仕事で失敗してしまうんだろうな」とか(笑)。
加えて、僕はキャラを作る時に「ブラックボックス」という表現を使います。
要約すると、「言葉をブラックボックスに入れた際に、ちゃんと返事が返ってくるのがキャラクターである」ということです。「死ね!」と言われた際に「なんだと!?」と返すキャラなのか。それとも「ふざけるな!」と返すキャラなのか。その「ブラックボックス」の部分が重要です。
このブラックボックスがあることによって、読者にも「このキャラはこう返すんだな」というキャラの法則性を把握してもらうことができます。そのブラックボックスを開示して、「このキャラはこの言葉を聞いたら黙っていられない」「このキャラは聞き流す」といったように情報を固めていくのが僕なりのキャラ作りですね。