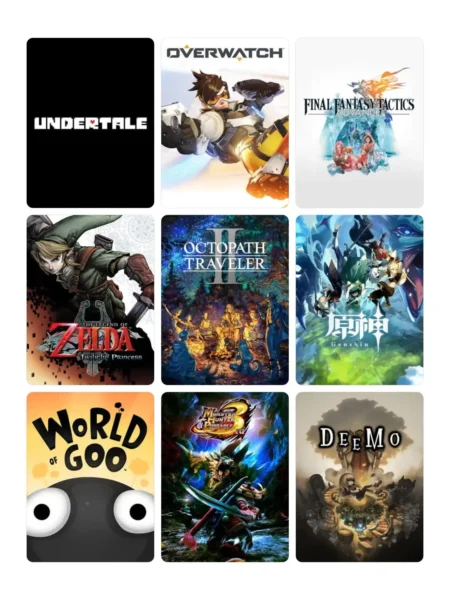1999年に公開され社会現象とまでなったキアヌ・リーブス主演のSFアクション超大作『マトリックス』。その最新作『マトリックス レザレクションズ』が本日12月17日に公開した。
さまざまなフォロワーを生み出し「映像革命」とも評される『マトリックス』の新作が公開されたのだから、それはエンタメ分野における、ひとつの事件といえるだろう。
シリーズは人類と機械との戦いを描き、『マトリックス リローデッド』、『マトリックス レボリューションズ』をあわせて三部作として完結したかに思われた。だが、最新作『マトリックス レザレクションズ』では、救世主ネオが再びその戦いに身を投じていく。
第1作目『マトリックス』が多くの人々を魅了した要因はいくつかあるだろう。哲学的なテーマを内包した仮想現実の切り口や、サイバーパンクの世界観とワイヤーアクションの融合。さらにはハイスピードなカメラの動きにも関わらず、登場人物たちの動作はスローモーションな新感覚の映像「バレットタイム」を大々的に導入したことなどが挙げられる。
そのなかでも本稿では「仮想現実」にフォーカスをあててみたい。
Oculus Quest 2などのVRデバイスの普及や「メタバース」が注目を浴びていることはもちろんだが、最近では『フリー・ガイ』や『レディ・プレイヤー1』、『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』など「仮想現実」を舞台とした映画が増えており、「タイムトラベルもの」といったジャンルと同じく「仮想現実もの」といったひとつのジャンルが隆盛しているからだ。
監督のラナ・ウォシャウスキーは、両親の死が『マトリックス レザレクションズ』制作のきっかけと明かしているが、おそらくこういったトレンドとも無縁ではないはずであり、そうであるからこそ今まさに続編が制作されたのだろう。

仮想現実をテーマとした映画は1990年代に多く存在していた。しかし、その中でももっとも大きく人々の心を捉えた作品は『マトリックス』をおいてほかならない。
それはなぜか? その理由のひとつに、『マトリックス』が他の作品と比べて「ゲーム的」だったからではないか、と筆者は考えている。
本稿では上記で挙げた『マトリックス』の「映像革命」と呼ばれていた要素(バレットタイム、ワイヤーアクション)の視点から抜け落ちていた、『マトリックス』のゲーム的な要素を抽出して再評価しつつ、近年における仮想現実ものの映画の特徴を言及する。さらに『マトリックス』と同時代の「仮想現実もの」の映画との比較しつつ、最後には最新作『マトリックス レザレクションズ』に踏み込みたい。
「仮想現実もの」として鮮やかだった『マトリックス』

価格:21,780円(税込)
発売日:11月17日(水)
© 1999, 2003 Village Roadshow Films (BVI) Limited. © 1999, 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
『マトリックス』が仮想現実ものとして優れていたのは、従来の『トロン』(1982年)のような作品とは決定的に違うことだ。『マトリックス』における仮想空間では、現実から移行するものではなく、「我々が見知ったこの世界こそが仮想現実であり、そこから現実の世界へと目覚める」と主客を転倒させることだった。
もちろんこうしたアプローチは『マトリックス』と同時代の『13F』や『トゥルーマン・ショー』、さらに遡るとフィリップ・K・ディックの小説『時は乱れて』や、哲学の懐疑論まで遡れるだろう。
だが『マトリックス』の場合、「この現実は仮想現実だった」という筋書を物語のプロローグと捉えており、「ディストピア的な現実」と「ユートピア的な仮想世界」の戦いを主軸に、「自由意志とは何か」というテーマを内包していた。
さらに重要なのが、こうした現実と仮想現実の立ち位置を逆転させたうえで、サイファーというキャラクターに「ユートピア的な仮想世界で十分ではないのか?」という疑問を語らせていたことだ。

価格:21,780円(税込)
発売日:11月17日(水)
© 1999, 2003 Village Roadshow Films (BVI) Limited. © 1999, 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
『マトリックス』は「仮想現実もの」であれば必ずつきまとうこの「サイファーの問題」を、20年前の時点でしっかりと提示してという点は刮目に値する。とはいえ、『マトリックス』が三部作を通してこの問題に対する「答え」を出せたのかどうかについては少々、疑問符はつく。
たとえば『マトリックス』から20年弱の時を経て公開された『レディ・プレイヤー1』においても、やはりこの「サイファーの問題」に決着はつけられていなかったと思う。映画のラストで「現実の大切さ」を説かれても、現実は荒廃しており、そうしたディストピア的な現実を肯定的と捉えられるのは一部の特権的な人間だけだろう。
その点で『フリー・ガイ』が巧みだったのは、現実と仮想現実の優劣をつけなかったことだ。あの映画では現実も仮想現実もそう悪くないものとして描かれている。
はたして『マトリックス リザレクションズ』は「サイファーの問題」に対して、どういった答えを見出せているのか。それは本稿の最後に触れよう。
『マトリックス』の「ビデオゲーム」を感じさせる要素

近年、『フリー・ガイ』を筆頭に『トゥームレイダー』、『ジュマンジ ウェルカム・トゥ・ジャングル』、『シュガーラッシュ』、『名探偵ピカチュウ』、『ソニック・ザ・ムービー』などビデオゲームを題材にした映画が活況だ。
またビデオゲームが直接的に題材になっていなくても、ビデオゲームを参考にしており、実際にそのように感じさせる『オール・ユー・ニード・イズ・キル』やドラマ『ウエストワールド』なども忘れがたい。

これらの作品は、従来のビデオゲームの映画化とは明らかに違う。端的にいうとビデオゲームを思わせるルールや仕組みが物語のレベルにおいて含まれているからだ。その特徴は以下のように要約ができる。
■ビデオゲームの経験が息づく映画の特徴
・世界に特定のルールが存在することに気づく実存的不安が描かれる
・ルールはキャラクターを束縛するものだが、難局を乗り越える武器にもなる。
・キャラクターは死んでも復活する。そのキャラクターは、以前に死んだときの経験を活かす/死ぬ前の記憶が前世の記憶として蘇る。
・プレイヤー/アバターという概念があり、そのアバターは現実の見た目や姓と一致していなかったりする。
・この世界が有限であることを察する。そして「世界の果て」を目撃しようと渇望する
・ルールには綻びがあり、その見つけることでルールから脱出し自由を得ることができる。
こうした要素はゲーマーにはおなじみとも言えるものだが、映画やドラマのストーリーテリングに取り入れられたことで『ウエストワールド』や『オール・ユー・ニード・イズ・キル』、『ジュマンジ ウェルカム・トゥ・ジャングル』、『フリー・ガイ』などは、これまでにない新鮮味のある物語を提示することに成功している。
こうした作品は、ゲームを単に映画化した「シネマ・ゲーム」ではなく、映画の物語にゲーム的なルールや仕組みを取り入れた「ゲームデザイン・シネマ」とも呼べるような新しい流れの作品といえるのではないだろうか。
「ゲームデザイン・シネマ」としての『マトリックス』

価格:21,780円(税込)
発売日:11月17日(水)
© 1999, 2003 Village Roadshow Films (BVI) Limited. © 1999, 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
いま改めて初代『マトリックス』を振り返ってみると、仮想現実を鮮やかに描いただけではなく、その描写にはいくつものゲームデザイン的な要素が含まれていることに気付かされる。
赤いピル/青いピルといった「選択肢」を強調するモチーフをはじめとして、仮想現実世界でのルールはかなりゲームっぽさを感じさせるのだ。登場人物たちは、こうしたルールを利用したり恐れることで物語を進行させていく。ざっと列挙するだけで、以下のようなルールが挙げられるだろう。
■『マトリックス』の代表的なルール
・現実世界には赤いピル/青いピルのうち、赤いピルを選択することで行ける。
・仮想現実で死ぬと、現実世界でも死ぬ(「心が現実にする」)
・仮想現実と現実世界は有線の電話を用いて移動する。
・仮想現実に変更が加わるとデジャヴュが起きる。
・エージェントは不死身で倒しても近くの人間に乗り移る。
・ある特定のスキルはインストールして、すぐに習熟が可能。
・格闘術に習熟しても、エージェントはさらに強い。
・救世主として目覚めると、万能といえるほど強くなる。
たとえば1990年代における仮想現実もの映画で『マトリックス』と同じくらいに有名な作品として、アーノルド・シュワルツネッガー主演の『トータル・リコール』(1990年)がある。この作品は、機械によって記憶が操作されているタイプの仮想現実だ。
記憶を操作するタイプの仮想現実というのは、主人公の主観を操作することである。ゆえにビデオゲーム的な要素は希薄だ。
ところが『マトリックス』の場合、大多数が共有できるプラットフォームとしての仮想現実になっている。『マトリックス』は、ゲーム的な仕組みで捉え直すと、大規模参加型のオンラインゲームに近いといえるわけだ。
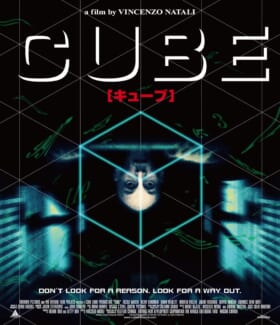
同時期に、ゲームデザインしていた映画として代表的なのは『CUBE』(1997年)だろう。実際『CUBE』は、現在では「デスゲームもの」として評価されている。『マトリックス』や『CUBE』は、ゲームのルールや仕組みを導入する同時代性を持っていたわけだ。
1990年代の仮想現実映画『13F』、『ニルヴァーナ』
1990年代には仮想現実を扱った映画がいくつかあった。『オープン・ユア・アイズ』(1997年)、『ニルヴァーナ』(1998年)、『13F』(1999年)などが代表的な作品だが、これらは実はビデオゲーム的な経験をあまり見出せない。
『オープン・ユア・アイズ』は、『トータルリコール』と同じ記憶を操作するタイプなので割愛するが、ビデオゲームに馴染み深い人からすると、『ニルヴァーナ』と『13F』は、かなりユニークな仮想現実の概念を提示していると感じるはずだ。

たとえば『13F』は、仮想現実やアバターの概念がとても奇妙である。この作品の仮想現実では、プログラムの住民たちは自我を持って生きている。
ここまでは普通だが、なぜか仮想現実にアクセスしようとしたとき、その自我を持ったプログラムの住民の意識を乗っ取るような形でアクセスしなければならない。そして仮想現実で命を落とすと、自我を持っていたプログラムの意識のほうが現実世界に投影されるのだ。
『13F』は、仮想現実の先駆的映画『あやつり糸の世界』(1973年)のリメイクであり、 原作は1950年代に書かれたダニエル・F・ガロイの小説『模造世界』だ。まだビデオゲーム産業がない時代だったがために、こうした個性的な仮想現実の設定になっているのだろう。
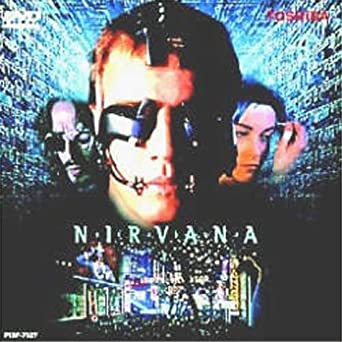
また『ニルヴァーナ』は、ビデオゲームのキャラクターが自我に芽生えるのが物語の開幕だ。
この作品がユニークなのは、自我が目覚めたゲームキャラクターが「自分を消去してくれ」と懇願してくるところだ。近年のビデオゲームでも作中のキャラクターが存在していることを問いかけるメタフィクションな作品があるが、『ニルヴァーナ』はそれを先駆けているとは再評価できる。
物語は不憫に思ったゲームクリエイターが、そのゲームキャラクターを死なせてやる(消去する)ために旅立つ。ところがこのゲームクリエイターもどこか死に場所を探しており、ゲームキャラクターと連絡を取り合ううちに奇妙な友情が芽生えてくる。こうした描写は涙を禁じ得えず、『ニルヴァーナ』は現代のビデオゲームにはない魅力をいまだに放っている。
これらと比較すると、『マトリックス』における仮想現実の考え方が、いかにも現代のビデオゲームと近いことがわかるだろう
現実の同一性や固有性を揺らがせる『マトリックス』
繰り返すことになるが、『マトリックス』の衝撃とは、「我々の知っている現実世界こそが仮想現実だ」と提示したことだ。こうした物語は当然ながら、シミュレーテッド・リアリティとして、我々の現実世界の信頼性を揺るがしてくる。
『マトリックス』がゲーム的であると捉え直すと、そこにさらなる推察が導かれないだろうか。
奇しくも12月10日には、実写と見分けがつかない映像美を披露した技術デモとしてのゲーム『マトリックス アウェイクンズ』の配信が開始された。
今度はビデオゲームという形から「映像革命」としてのシリーズの存在感を改めて見せつけた形が、こうした実写と見分けがつかないビデオゲームもまた本編と同様に、現実の信頼性を揺るがせてくると思うのだ。

批評家のレフ・マノヴィッチはその著書『ニューメディアの言語』で、GGと実写が見分けがつかない時代が到来しつつあることを見据え、「映画はアニメーションのひとつのジャンルである」と喝破した。もはや写真や実写映画に実証性、信頼性はないのかもしれない。
しかしビデオゲームも論じられているこの著書が刊行された時期(原著は2001年)に顕在化していなかったのは、メディアだけでなく現実そのものがゲーム化しつつあるという視点だ。『ポケモンGO』などのARゲーム、教育現場や都市設計におけるゲーミフィケーションや、AIの活用はこの現実のゲーム化を促進させていく行為だ。
ARグラスが普及し、都市がスマートシティになると、現実の社会はどんどんビデオゲームのような光景になっていくだろう。
そして一方では、VR技術や『マトリックス アウェイクンズ』のようなCGの発展によって仮想現実が現実と見分けがつかなくなっていく流れがあるわけだ。現実からゲーム、ゲームから現実へと両者はお互いの立場から距離を縮めようとしている。

その先に待っているのは「この世界は現実なのだろうか?」というわざわざ疑問に思うまでもない、現実のゆるやかな消失だろう。現実がゲームになり、ゲームが現実として接触したときこそ、「仮想現実のシンギュラリティ」ともいえるパラダムシフトが起きるかもしれない。
ここまでのことを踏まえつつ『マトリックス レザレクションズ』に踏み込んでみよう。ネタバレを大いに含んでいるので、未見の人は気を付けてほしい。