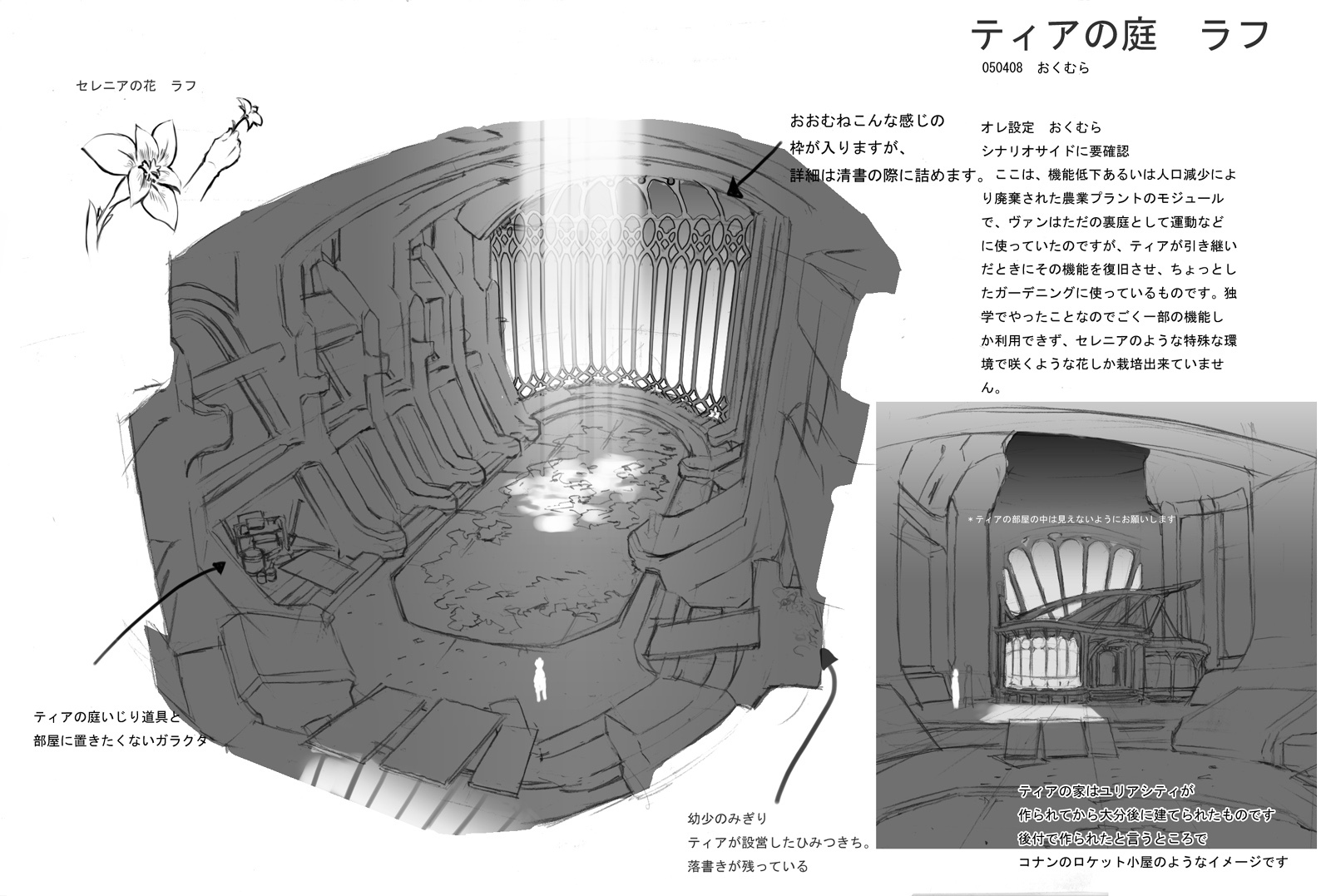ジェイドは子安さん指名って、本当ですか?
実弥島氏:
それで言うと、私の友人のお子さんが小学校低学年くらいのころに、「こんなゲーム作ったから、あげるね!」と言って、『アビス』をプレゼントしたことがあるんです。
遊んでくれたその子が、「ジェイドが一番好き!カッコいい!」って言ってくれていたので、そのときに「あ、間違ってなかったんだな」と思えました。
樋口氏:
それは、カルマを背負ったことにならないですか?(笑)
実弥島氏:
いや、違うんですよ!
ジェイドって「女の子に向けて作ったキャラ」だと思われがちなんですけど、私は中二くらいまでの男の子は、「かっこいい大人の男」みたいな雰囲気をまとったキャラが絶対好きなはずだと思って、ジェイドを作ったんです。
だから、あのときに「自分は間違ってなかった!」と確信を持てましたね。
──ちなみに、ジェイドは実弥島さんが子安(武人)さんを指名して書かれたキャラクターなんでしょうか?
実弥島氏:
それは……半分アタリで、半分ハズレですね。
最初はとくに子安さんを意識して書いていたわけじゃなくて、もっとクールで冷たいキャラだったんです。ある意味では、ルークと同じくらい別の方向に尖っている感じでした。
ただ、あるとき開発の女の子たちに呼ばれて、「ジェイドは子安さんでお願いします」「子安さんにしてくれないと会議室から出しません」と言われて。
一同:
(笑)。
実弥島氏:
当時はそこで「わ、わかりました。じゃあ声優の希望に子安さんって書きます」と。
ただ、子安さんに演じてもらうなら、もとのキャラクターじゃつまらないだろうなとも思ったんです。そこで当て書きをする形で、いまのジェイドの面白味や悲しい部分を強めて……「子安さん風」に肉付けして作っていきました。
むしろ、最初から当て書きをしていたのは、ガイ役の松本(保典)さんですね。私、勇者シリーズの『太陽の勇者 ファイバード』【※】が好きで……「火鳥にいちゃんの声だな、これは!」と思っていたら、スタッフのみんなに「え、わからない……」と言われて(笑)。
そこで、とりあえずルークのオーディションに松本さんを呼んで、スタッフのみんなには「聞けばわかる」と。だから、松本さんはルークを演じてくださいと言われていたのに、みんなはガイだと思って聞いていたという……。
※「太陽の勇者 ファイバード」
サンライズが制作していた、ロボットアニメ。『勇者シリーズ』の第2作目にあたる。主人公の火鳥勇太郎を、ガイ役の松本保典氏が演じている。
──たしかに、ガイはドンピシャのキャスティングですよね。アクゼリュス後にアラミス湧水洞で帰ってきてくれるところとかも、すごく心強かったです。
実弥島氏:
やっぱり、あそこでガイが帰ってきてくれないと、本当にユーザーさんの心が折れたまま戻ってこられないですからね。そういう意味でも、やっぱり松本さんの包んでくれる声がいいだろうなと思っていました。
「自分たちが面白いと思うものを出すんだ」という心意気で通した
──『アビス』は、そこの「ユーザーを信じているところ」がすごいと思うんです。ここまで「プレイヤーは最後まで遊んでくれるだろう」と信じて、振り切った作りをしているところが、あの完成度に繋がっている気がします。
実弥島氏:
そこは、たぶん長谷川さんの思想もあるのかなと思います。
『シンフォニア』を作っていたときに、長谷川さんは「プレイ体験として、ユーザーの選択が大事なんだ」とおっしゃられていたんです。
『アビス』では選択肢はないけれど、そこもユーザーのプレイ体験を信じて「こういう風に思ってくれるだろう」「こう遊んでくれるだろう」という計算をしていないと、そこは成り立たないんですよね。
樋口氏:
やっぱり、「シナリオでこういうことを見せたい」という狙いだけが先に立ちすぎると、今度はゲーム体験の方がおろそかになるんですよね。
これはいまでもRPG制作の現場で使う手法なのですが、そこのプレイ体験を総合して、まずゲーム全体の設計図を作るんです。どこで何が起きて、ここでパーティーの誰かが離脱して、ここから戻ってくる……そういうのを一旦図面に起こします。
そうすると、「ここらへんってダレてない?」「このへんって敵が強いのにヒーラーがいないよね」みたいな要所要所の問題が見えてくる。そこのゲーム体験をベースにシナリオを調整する作業を、いまでもRPGの制作ではレガシーな仕事としてやっていると思います。
とはいえ、よそのタイトルの作り方は見ていないから、ほかがどうしているのかはあまりわからないんですけど……少なくとも『アビス』は、そこをかなりちゃんとやっているのかなと思います。
穴吹氏:
チームの中には『シンフォニア』の開発経験を経て、『アビス』の開発では「自分たちが面白いと思って作った作品は、ちゃんと刺さる」という自信みたいなものがあったように思います。
それもあって、「自分たちがこれは絶対に面白いと思っているから、『アビス』も行けるだろう」という判断になったのかなと。
実弥島氏:
基本的に、自分たちが面白いと思っていないと、先に進めないですよね。
むしろ、「これは面白い」と思っているからこそ、このゲームをどう伝えていくかを考えて、ゲーム体験的な「ここをダレないようにする」といった調整が入るのだと思います。
穴吹氏:
やっぱり「時代」なんですよね……。
この作り方は、いまだと難しいですよ。
ちょっとインディーゲームに近いというか、本当に「自分らが面白いと思うものを出すんだ」という心意気一本で通してる感は、改めて考えるとありますね。
──『アビス』は、そのユーザーへの信頼や、「一度失敗したところから変わっていく」というルークのストーリーを含めて、すごく「性善説」に基づいて作られているゲームだと感じていました。
実弥島氏:
当時から、なんとなく言語化できない「テイルズらしさ」というものを、『シンフォニア』や『アビス』を作るときには意識していたんです。
その「テイルズらしさ」がなんなのかと言ったら、「性善説」がそのひとつなんじゃないかと思います。結局のところ、人を信じている。それが「テイルズらしさ」を担保しているのかなと。
だから、『アビス』もそうなっている。
逆に、これが『テイルズ』じゃなかったら、もっとひどい内容になっていたかもしれない。
そして、あの当時のユーザー層である中高生くらいの人たちが、ちょっと斜に構えたり露悪的になったりしていても、その奥にはちゃんとピュアなハートが残っている世代だと思うんです。
だから、どんなにひどい世界になっても、どこかに希望が残っていればついてきてくれるんじゃないかなと……『テイルズ』というシリーズだから、それを信じている空気感なのかもしれないです。
樋口氏:
あと、やっぱり『テイルズ オブ ファンタジア』【※】が強烈だったのもあるかもしれないですね。『ファンタジア』が一貫して性善説のゲームだったし、当時はいまほどシリーズも出ていなかったから、「あれがテイルズだ」というイメージがあったんです。
その『ファンタジア』に影響を受けた人たちが作っているから、「テイルズらしさ」もそこで醸成されていったのかなと思いますね。

1995年にナムコから発売された、RPG。『テイルズ オブ』シリーズの第1作目であり、時空を超えて旅をするストーリーや、勧善懲悪ではないテーマ性などがファンの心を掴んでいる。(※画像はPS版)
実弥島氏:
私も『ファンタジア』がすごく好きだったので……そこで「テイルズらしさ」を考えたときに、ダオスといろいろなことがあったけど、最終的に人は信じられるんだなと思ったんです。
作中で「この世に悪があるとすれば、それは人の心だ」「しかしそれは同時に善でもある」と言っていた通り、「人の心は悪だけじゃない」ということが心に刻まれていたし、『アビス』を遊んだユーザーさんもそこをわかってくれるんじゃないかと……もしわかってもらえなかったとしたら、こちらの表現が足りていなかったと思っています。
それが届いた方も届かなかった方もいるけれど、とりあえず「これだ」と思ったものをぶつけるしかないというか……「信じて、ぶつけて、返事を待つ」みたいな感じでしたよね。いま改めて思いますけど、こんな作り方しちゃいけないですよね!
穴吹氏:
いや、本当にあの時代に出せてよかったなと思います。
発売から20年経ってこういう取材を受けてること自体を含めて、僕らのなかでも『アビス』はちょっと特別なタイトルになっちゃってますよね。とにかく、開発中も濃かったです。僕はもう、毎日長谷川さんに泣かされてる思い出が……。
一同:
(笑)。
実弥島氏:
開発期間が短かったから、余計に濃かったですよね。
短いからこそ凝縮しなきゃいけないことも多くて、結果としてシナリオも濃くなったし、システムを含めたいろいろな遊びの要素も濃くなっていった印象があります。
樋口氏:
僕は現役でゲーム開発に関わっているんですが、本当にいまでも「現役でこの仕事をやれているのは、このときに『アビス』を作ったからだ」と思いますね。
この開発を経験したことがいまもすごく生きているし、このころ一緒に仕事をした関係性はいまでも続いていたりするし……僕のなかでも『アビス』は、すごく特別なタイトルです。