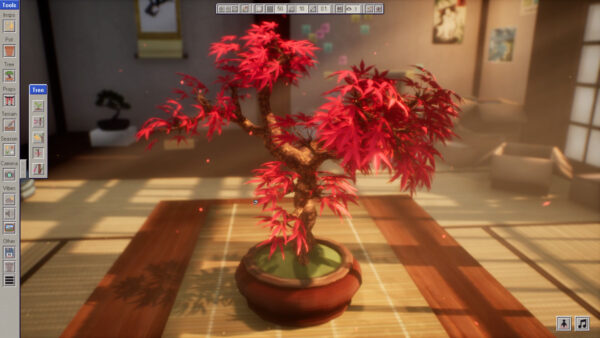「年間1000万円をお渡ししますから、好きなゲームを創りませんか?」
この魅力的なキャッチコピーは、『群像』や『週刊少年マガジン』で知られる講談社が立ち上げたプロジェクト「講談社ゲームクリエイターズラボ」によるものだ。しかも、その開発支援金に加えて、「成果物の権利は開発者へ帰属する」という太っ腹な仕組みとなっている。
インディーゲームクリエイター、もしくはゲームのアイディアはあるのにと悩む人にとっては、この言葉はまさに夢のような話。その情報はが瞬く間に拡散され、SNSでも話題をよく見かけるようになった。
講談社が年間で最⼤1000万円を支給するインディーゲーム開発者の支援プロジェクトを立ち上げ。9月15日より第1弾のメンバー募集を開始
しかし、疑問に思うことが多くあるはずだ。なぜ大手出版社である講談社がゲームを、しかもインディーゲームを支援するのか。漫画や小説などゲーム業界外の人々が、どのように開発者をサポートするのだろうか。こういった投資企画では権利は投資元に帰属するのが普通だが、作家に帰属させるのにはどういう意図があるのだろうか。
そこで今回は、立ち上げ人である講談社取締役の森田浩章氏と『ヤングマガジン』編集次長の鈴木綾一氏に、講談社ゲームクリエイターズラボについて詳しくお話を伺った。 ……のだが、そこでは思いがけず、インディーゲームへの取り組みだけではない、講談社そのものについての話を聞くことができた。作家と1対1で話すとはどういうことなのか。編集者とはどういう存在なのか、そしてどうあるべきなのか。紙の本が厳しくなるこれから、出版社が社会の中で担うべき立場とは。
講談社で編集という仕事について30年以上が経つ森田氏の、止まらない好奇心と新しいものに対する欲望。現役編集者として現場の最前線で活躍中の鈴木氏の、出版業界きってのチャレンジ精神。
ベテランの編集者ならではの視点から語られる新しいコンテンツとの向き合い方は、誰もが興味を持つ内容となっているだろう。

とにかく新しい才能を見たいから、インディーゲームクリエイターを支援する
──まず、なぜ講談社がインディーゲームを支援するのか?という点についてお聞きしたいと思います。というのも、真っ当にゲーム業界に参入しようとするのであれば、講談社ほどの規模なら、ほかにいくらでもやりようがあると思うんです。
森田浩章氏(以下、森田氏):
講談社でゲームはやってなかったわけじゃないんです。『七つの大罪』のゲームを韓国のゲーム会社さんに作ってもらったりだとか。でも、基本的にはただ権利を貸しているだけで、開発にはタッチしていないわけです。それで一度、開発に関わろうとしたら大失敗。億単位のお金が吹っ飛んだことがあったんです。
そういう背景があって、ゲームをやるなら得意分野の「1対1の打ち合わせ」で、その才能に賭けていくほうが早いんじゃないかと思ったのが事実ですね。
──なるほど。ゲームでも個人単位なら、漫画家さんと日々行っている「1対1の打ち合わせ」のノウハウが活かせるわけですね。
森田氏:
ゲーム会社の人たちが作るゲームって、めちゃくちゃお金をかけるじゃないですか。うちの役員会議で「20億でゲーム作りたい」と言っても誰も賛成してくれない。だから、その方向では対抗できないなと。
一方で、今は機材や販売ルートの整備が進んでいて、個人でゲーム開発している人が増えていると、鈴木に教えてもらって。「いやそれだったら、うち得意技じゃん」というノリですよ。
鈴木綾一氏(以下、鈴木氏):
漫画の出張編集部で、大阪コミュニケーションアートという専門学校に行ったんですよ。そこの卒業制作展示にふつうにVRゲームがあって。「2年でここまでできるんだ!」と感動したんです。漫画でも2年でプロレベルになれる人もいるのでこれはすごいぞ、と。だからその才能を応援したいんですよね。
森田氏:
とにかく新しい才能を見たいんですよ。
自分は講談社で漫画部門にいて30年になるんですけど、これぐらいのキャリアになっちゃうと、新人賞の作品を読んでもどこかで見たことがあるというか。
その点で言えば、僕はゲームには詳しくないし、漫画家とは違うゲームクリエイターの本質的な部分も知らない。だからいまは、新入社員のようにワクワクしているんです。
発表してから5日くらいで応募が40〜50通、今日(10月1日)までで120通くらい集まりまして。簡単な企画書なんだけど、読むとどれも面白くて「ヤバイのばっかりだな!」と嬉しくなっちゃって。「こんなところに才能が埋もれてたんか!」と(笑)。
──(笑)。それって、どういう企画書なんでしょう?
鈴木氏:
基本的に書式は自由ですね。企画概要と、それに附随するものを送ってもらうだけです。添付URLだけ貼っている人もいれば、設計図みたいなものもあります。読んでて面白いですよ。企画名で「世界一面白い格闘ゲーム」だとか、それだけでカッコイイなと(笑)。
森田氏:
発表する前は、「最悪、5人しか応募が来なかったらダメもとでその5人に1000万円あげちゃおうよ」と言っていたんです。今では「ここから5人に絞らなきゃいけない」という贅沢な悩みになってしまいましたね。まだ締め切りまで1ヶ月以上あるから、もっと来たらどうしようかと(笑)。
──こういうのは締め切り直前に駆け込みでたくさん来ますからね(笑)。
鈴木氏:
1000万円という金額は、マガジンで1年間連載したときの原稿料とほぼ同額なんです。毎週20ページで、52週連載すれば、それだけで1000万円かかるので。
──なるほど。週刊連載漫画1本にかけるのと同じぐらいのお金と気持ちを投じようということですね。
森田氏:
そうそう。それだけのお金をかけても、漫画は9割がた失敗しますよ。でも、うちの会社には「その1000万の失敗をどうするんだ」という人は全くいない。クリエイターや創作物のチャレンジに対する投資を惜しまないのは、当然だと皆が思っている。その姿勢が当たり前なところが、講談社のいいところですね。
今回のゲームクリエイターズラボの理想を言えば、3年やって15人ずつに1000万投資して、1本当たればいいかなと。当たらなくても、「ナイスチャレンジ!」と褒めてあげたい。
 |
まだ漫画が「下流」だった時代、その面白さに感動して泣く
──とにかく新しいものを見たい、そのためなら投資は惜しまない、と。でも、講談社で長年漫画編集をしてきた森田さんのような方が、どうしてそこまでゲームに新しさを感じたのかが気になりますね。そもそもからお聞きしてしまうんですが、森田さんは入社当初から漫画編集者だったんでしょうか。
森田氏:
そうですね。入社が87年なので、33年前からずっと漫画を担当しています。今は取締役になり。漫画を統括しています。
──30年前の漫画や漫画編集者の扱いって、どういう空気感だったんでしょうか。ちょっと失礼な言い方かもしれませんが、野蛮な扱いを受けていたイメージがあります。
森田氏:
当時の社内では下層の方ですからね(笑)。
──文芸などを担当しているエリートの方が居て、けど漫画のほうが売り上げを立てている。講談社の中で、漫画がどういう立ち位置として捉えられていたのかをお聞きしたいです。
森田氏:
僕が入社したときは漫画が盛り上がり始めていたので、そこまでではなかったけど、先輩から聞く差別意識は酷かったです。小説家を相手にする文芸が一番で、その下が雑誌、さらにその下が漫画という扱いでしたね。
──漫画の部署に配属されて、どういうことが面白いと思いましたか?
森田氏:
大学時代から漫画はある程度読んでいたんですけど、入社してすぐにすごくビックリしたことがあったんです。『モーニング』で新人賞、ちばてつや賞というのをやっているんですけど、その受賞作の合本がめちゃくちゃ面白かったんですよ。とにかく新しい才能が来ていることを実感しました。

僕は、どっちかというと小説志望で講談社に入っていて、「漫画って実際どうなんだろう」と思っていたんです。そんな中、合本を電車の中で読んでいたんですけど、感動して泣いちゃって。
合本って商品じゃないから、コピー紙で写植も適当に貼っているようなものなんです。でも、こんなに感動できるものを描ける人がいる。これは本気でやるべき仕事だなと思いました。
当時付き合っていた彼女は漫画を馬鹿にしていて、「漫画に配属になったよ」と言ったら死ぬほど怒られましたね。カッコ悪いって言われちゃいました(笑)。
──もともと漫画が大好きでというわけではなくて、小説が好きだったんですね。
森田氏:
そうですね。出版社に入る典型的なパターンですけど、僕は文学青年で本ばかり読んできました。漫画を読んでいたのは、バイト先が中華料理屋さんだったからです。
15時から17時の休憩時間に暇つぶしで延々と読んでいたんです。そこでは大人の漫画誌、『モーニング』、『ヤンマガ』、『ビッグコミック』などを片っ端から読んでいました。
 |
──若い才能や“磨けば光る原石”を探し当てる感覚って、編集者のような仕事をされている方にはわかるかもしれませんが、一般の読者にはなかなか伝わりづらい部分だと思うんです。森田さんは、具体的にどういうところを見ているのでしょうか。
森田氏:
文学青年だったこともあって小説は昔からかなり読んでいて、それなりにその面白さや可能性を見る目は養われていたのかもしれません。けど、面白いストーリー、素敵な絵、かっこいいセリフや愛すべきキャラクター、そういう要素が全て含まれたジャンルが漫画だって新入社員のときに知ったんです。「これは小説より可能性がある」というのが合本を読んだときの感想で、光る原石だらけに見えました。
今の編集者って、漫画志望で入ってくる人がけっこう多いんですよ。小さいころから漫画を読んで、アニメを観て育って。それで漫画をやりたいって講談社に入る人がすごく多いんだけど、僕のキャリアはそうじゃなかったです。入社して、はじめてそのすごさを思い知ったって感じですね。
──そんなふうに「漫画ってすごいな」と思ったあとに、取り組んだことってどういうことだったんですか。
森田氏:
漫画家さんは、底知れぬ知識を持っている方々なので、1対1で話すことが大変でした。大学出たてのペーペーとベテラン作家だと知識量に圧倒的な差があって、何もアドバイスできないんです。その知識量を埋めるためにどう生きていけばいいのかというのをまず考えました。
たとえば、小説という意味では本を読んでいる量はそんなに変わらない。そういうことで映画が足りないのか漫画が足りないのか、何が足りないのかを考えまして。まあ、人生経験が足りないのは当然なんですけど、それでも映画をいっぱい観たりする。そうすると、徐々に作家さんより映画を観る量が増えてきて、そこである程度は対等に話せるようになりました。
「作家さんと話す」とは、お悩み相談をすること
──抽象的な質問になってしまうのですが、「作家さんと話す」って何をすることなんでしょうか。編集って、一般の方からはすごく見えにくい仕事じゃないですか。漫画ならまだしも、ゲーム開発者の担当編集って、いったい何をするの?となってしまうかと思うんです。
森田氏:
結局は、クリエイターの「お悩み相談」ですよね。どんなクリエイターもお悩みばっかりなんです。それは新人でも中堅でもベテランでもそうです。キャリアを積んだアニメ監督でもそうだし、多分ゲーム業界の方々でもそうだと思います。「これであってんのか」とか「これでウケるのか」、「分かってもらえるのか」という悩みですね。その回答を求めている。
──「お悩み相談」ですか。それって、具体的にはどんなふうに進むんでしょうか。
森田氏:
漫画家さんとの打ち合わせに行くと、20ページ程のネームを渡されるんです。多分渡した方がドキドキしていると思うんですよね。年齢は作家さんが上なんですけど、20歳くらいの僕にネームを渡して読ませる。それで、第一声で何を言うか。それをすごく待っていて、そのプレッシャーをひしひしと感じるんです。
読んだのが面白ければ、「面白いです」と素直に言えるけど、面白くないときになんて言うか。それが、編集スキルですよ。
僕は、素直に「面白くない」と言うタイプの編集者だったけど、漫画の編集者が100人いたら100通りのやり方があると思います。なぜ面白くないかをちゃんと言って、どういう解決策が考えられるか、こうすればもっと面白くなると提案して、それでも納得しなかったら、どんどんアイディアを出すという形ですよね。その過程は、まさにお悩み相談だと思います。
──どちらも意見を譲らないこともありそうですね。
森田氏:
最終的にこっちが折れるパターンも当然あるんですよ。作家さんが、これが面白いんだと言って、僕は面白くないと思ってというすれ違いが発生します。そういう議論を経て、お互いに納得して、その通り描いてくださいってパターンもあります。とにかく、打ち合わせで会話をすることが編集者の仕事であるということですね。
 |
──面白くなかったときに、「何がどうダメかを説明する」のって難しいじゃないですか。とくに若いころは言語化の蓄積も少ないし、最初はどうしていたのか、どういう過程で言語化を習得していったのかをお聞きしたいです。
森田氏:
もうはじめは連戦連敗ですよ。相手も同じ新人作家で、こっちも新人編集ならほぼ対等な関係で打ち合わせできるんですけどね。中堅やベテランの作家さんって僕よりもぜんぜん年齢が上なわけで、その人たちには連戦連敗です。もう向こうの言うとおりになっちゃいます。
ただね、やっぱり何か言わないと信用してくれないんです。毎週、面白い面白いと言っているだけじゃ、信頼なんて全く得ることができないので。「僕は面白くないと思っています」というのをちゃんと言うことが大切です。最終的に面白くないネームが原稿になっても仕方がないと思うんだけど、ハッキリと言わないと全く信頼してくれなくなっちゃうんですよね。
──ただうなずいているだけじゃダメだと。
森田氏:
場合によっては、ベテラン作家さんのほうも「今週はイマイチだな」と思いながら僕に読ませているはずなんですよ(笑)。
鈴木氏:
本当にうまいベテランの人ってわざと、そういうことやるときがありますよね。「ここに気づけるか?」みたいに仕掛けてくるんです。
ひとりの編集者を育てるのは、ひとりの漫画家を育てるよりも100倍難しい
──作家さんの側でも、若手の編集がどう反応するかというのを観察していると。「何がどうダメか」を的確に言えないにしても、どう気に入らないんだろうかというのを引き出そうとしているんですね。
森田氏:
そういう優秀な作家さんばかりだと楽なんですけど(笑)。
編集長や作家さんによく言われていたのは、「君がいちばん最初の読者なんだよ」ということです。当時『モーニング』は100万部くらい出ていたから、ざっと100万人読んでるとして、そのうちのいちばん最初の読者が君なんだから正直な感想を教えてって、いろいろな作家さんに言われました。
鈴木氏:
そのときから複数担当制だったんですか?
森田氏:
いや、1人だね。
 |
鈴木氏:
『マガジン』とかでは、若手は先輩編集者のサブにつくことが多いです。そして、打ち合わせでは「まず若いのからどうぞ」と言われます。とにかく、ベテラン作家と先輩の前で何かを言わないといけないんです。
──集英社の『ジャンプ』では1対1で、講談社は複数人体制だとよく言われていますよね。
鈴木氏:
とくに『マガジン』は複数人体制が基本ですね。
森田氏:
才能が『ジャンプ』に流れていた時代があったので、編集者の手を入れて『ジャンプ』と対等に戦おうと。つまり、向こうが2人で作っているのなら、こっちは4人くらいで作って対等に戦える作品するというポリシーでした。
鈴木氏:
ベテラン作家さんとしては若手の編集者に、編集の仕方を教えていきたいという気持ちがあるんだと思います。それを若い作家にも伝えてくれないかという意思を感じるときがあるんですよ。
 |
──それって、作家さんはどういう意図で編集者を育てようとしているんでしょうか。たとえば普通の会社だったら、部下を育てる意味があるじゃないですか。一方で作家さんは、その若手編集者が自分の担当になるかどうかは分からないですよね。
森田氏:
一人前の漫画編集者を育てるのは、ひとりの漫画家を育てるよりも100倍くらい難しいんです。でも、ひとりでも優秀な編集者を育てちゃえば、100本くらい良い作品を生み出してくれる。だから、結局はその編集者が転職して小学館や集英社に行っちゃっても、そっちで面白い漫画を作れば、漫画界全体としては盛り上がりますよね。
もちろん自社や編集部の利益も考えますけど、漫画というジャンル全体が沈んじゃうと元も子もないじゃないですか。
だからこれまで、いろいろなベテラン作家さんに「申し訳ないけど、担当は新入社員しか付けられない」、「できればその新米編集者を育てて欲しい」と言ってきました。それが結局は『マガジン』をよくすることだし、漫画界をよくすることだと思っています。
──「ひとりの編集者を育てることは、ひとりの作家を育てるのより難しい」という話は業界のいろいろな人から聞くんですけど、これもなぜそうなのかを言語化するのが難しいと思うんです。
森田氏:
たしかに難しいですね。ただ、今聞いてて思い出したのは、漫画家はスペシャリストであるということです。売れっ子になればなるほど、生涯で書ける作品は3、4本になっちゃいますよね。しかも似たようなテーマを描いたりするわけで。だから、漫画家はスペシャリストとしての能力がかなり要求されると思います。
それに対して、編集者はゼネラリストじゃないといけない。さまざまな作家さんや作品と関わっていくので、どんな作品にも対応できるように育たなければならないんです。だから求められる能力もちょっと特殊で、そこに難しさがあると思いますね。
優秀な編集者の条件は、「新しいものを見せてくれる人」
──では、森田さんが優秀な編集者に求めるものっていったい何なんでしょう。
森田氏:
とにかく新しいもの、新しい世界を見せて欲しいですね。僕はもうすぐ57歳で、会社人生もそろそろ終わりじゃないですか。そんな人間に、新しいものを見せてくれる人は偉いと思いますし、そういう人は可愛がりたい。
もちろん、日々連載漫画を面白くしてくれる人に対するリスペクトはあるけど、ちゃんと話を聞いてみたいのはそういう人ですね。
編集者を育てるというよりも、わがままになっちゃうけど僕自身が育ちたいんですよ(笑)。もうちょっと高い視点を持ちたいというか、ゲームやVRのこともけっこう知っているんだよ、というふうになりたい。ほかの役員はSteamって言われても何のことだかわからないですから。
──モノを作るのは作家さんであって、編集者は直接モノを作るわけではないじゃないですか。そこで、編集者が得る満足感って、いったいなんだろう?ということに興味があるんです。
森田氏:
それはありますよね。
──今の森田さんのお話に、近い答えを最近見つけたんです。それは「新しいことに立ち会う」ということ。天才を見つけて育てるとか、新しいことを始めるとか。間接的かもしれないけど、作家さんに機材を用意してあげたことがきっかけで、その作家さんが後のゲーム業界に影響を与える作品を作るのかもしれない。編集者の本質って、そういう新しいものの始まりに立ち合いたい、みたいな好奇心にあるのかなと。
森田氏:
その先にどういう新しい世界が、地平線が広がるのか。それを見てみたいですよね。
みなさんはおいくつかわからないですけど、僕はこの歳になって初めて「自分は新しい世界が見てみたいんだな」と分かってきたんです。
だから、今回は講談社ゲームクリエイターズラボという名前だけど、社長が「いろんなクリエイターズラボを作っちゃえばいいんじゃないの」って言ってくれたときは嬉しかったです。「いろんな新しい世界を見てきていいよ」って勝手に解釈したからですけど。
 |
鈴木氏:
インディーゲームだけじゃなくて、アニメや音楽とかもということですよね。
森田氏:
そういうのが新しくて面白いなって。