近年、ゲームの“大作化”はとどまるところを知らない。オープンワールドが定着し、数十時間、場合によっては100時間以上プレイできるようなゲームデザインも当たり前となった。
ゲームデザインの変化にともない、開発側にとってもユーザー側にとっても重要となってくるのが「ミニゲーム」や「サブストーリー」。メインシナリオが重厚さを増していくとともに、かつては「オマケ」だったこれらの要素もまた、メインシナリオの補強材として、そしてユーザーの息抜きの場として必須となりつつある。
そうした潮流を、国内ゲームでもっとも濃密に体現したゲームといえば、やはりセガゲームスの看板タイトル『龍が如く』だろう。『龍が如く6 命の詩。』(以下、『6』)にて初代からの主人公・桐生一馬の物語は一旦終了したが、現在新シリーズの準備が進められている他、漫画『北斗の拳』とコラボレーションした『北斗が如く』が3月8日に、そしてPS4版『龍が如く3』が8月9日に発売されるなど、その勢いはまだまだ衰えない。
国内外でヒットを飛ばしてきた本作の魅力の一片は、強烈なインパクトを持つミニゲームや、入念に作り込まれたサブストーリーにある。ではこれは、世界的な潮流を意識した上でのゲームデザインだったのだろうか?
じつは、『龍が如く』シリーズの、ミニゲームの方向性を決定づけた人物がいる。その名は、堀井亮佑。『龍が如く2』(以下、『2』)から開発に関わり『龍が如く3』(以下、『3』)のミニゲーム、「カラオケ」を設計・開発した、1982年生まれの若手クリエイターだ。

「カラオケ」は、キャラ崩壊のそしりをものともしないド肝を抜く演出で、プレイヤーを爆笑の渦に叩き込み、その後のシリーズの方向性にも多大な影響を与えたことで知られる。しかし堀井氏はそれを、革命志向や海外展開への意識からではなく、ただただ「情熱の結晶」として作り上げたのだという。
「新世代に訊く」は、新時代のゲームクリエイターにスポットを当て、“次世代のレジェンド”たちの姿を追う連載である。
第二弾となる今回は、ゲームの「オマケ要素」開発からIP自体のイメージをも変えることになった、新時代の革命児とも言うべき堀井氏の精神に迫りたい。
聞き手/斉藤大地、クリモトコウダイ
編集/クリモトコウダイ
編集協力/小池未樹
撮影/佐々木秀二

『龍が如く』はミニゲームを積むゲームスタイルの先駆け
──最近、ゲーム全般におけるミニゲームの立ち位置がちょっと変化してきたように思うんですよ。簡単に言えば、ミニゲームをストーリー中に挟むとか、ちりばめるという手法が主流化しつつあるんじゃないかと。『グランド・セフト・オートV』シリーズや『ポケモン」シリーズにもミニゲームが多用されていますし、『ニーア オートマタ』では急にシューティングゲームが始まったりするじゃないですか。『龍が如く』って、実はそういう今の流れをかなり先取りしていたのではないでしょうか。
堀井氏:
たしかに、“本来そういうゲームでもなかったのにな”というゲームにもミニゲームが入ってきている印象はあります。
──もう確立された大きなシステムやストーリーだけでは足りなくて、意外とミニゲームとの組み合わせで頑張っているんじゃないか、と思うところもあります。
堀井氏:
手軽なゲームはスマホでできる時代ですから、コンシューマーゲームにはその分「壮大さ」や「やり込み」、「ボリューム」が求められるようになってきています。
昔はそれこそ、ミニゲームの延長のようなワンアイデアでコンシューマー作品を一本作る、ということも珍しくなかったですが、最近はそういうものはインディーを除けばかなり少ないですよね。
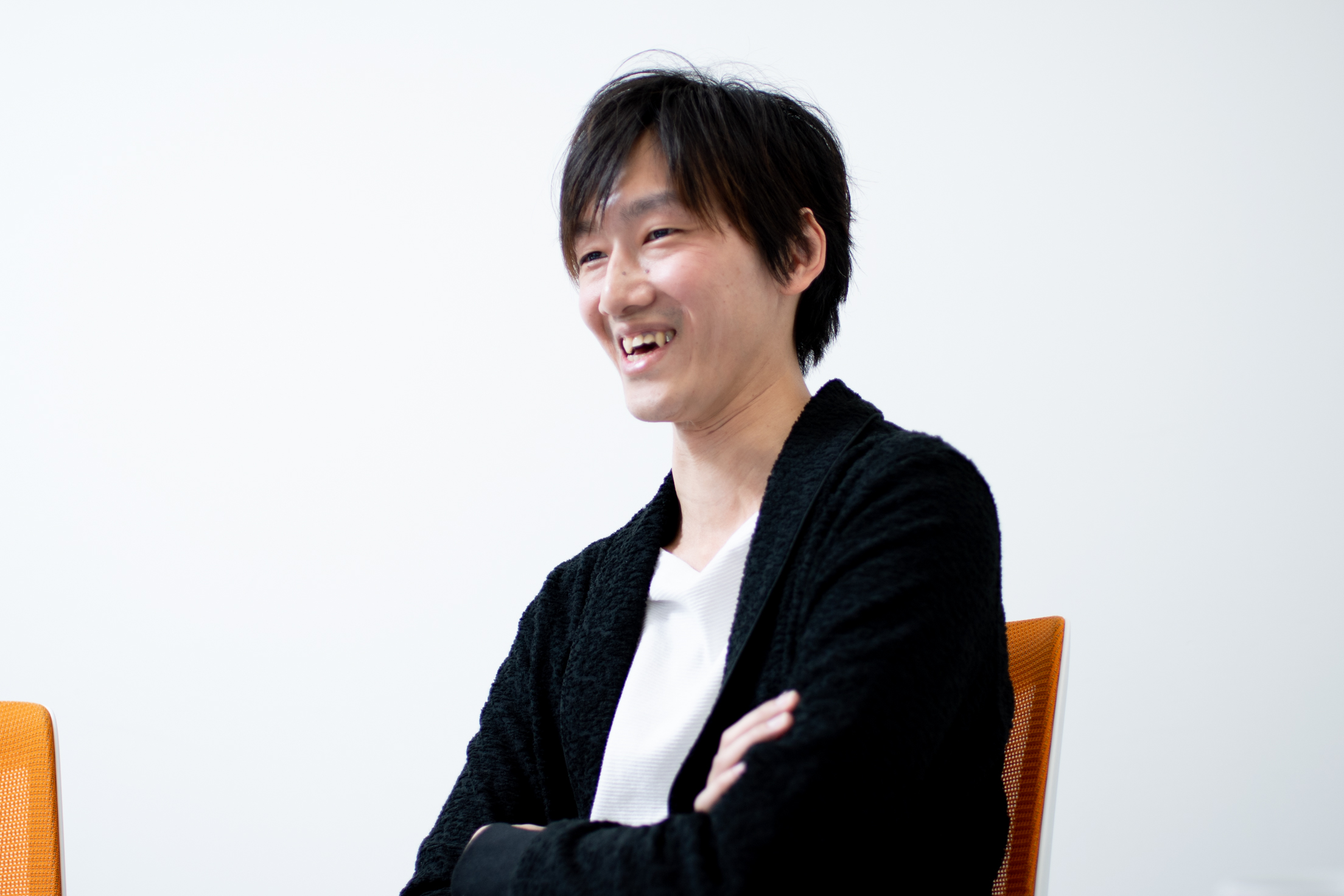 |
昔に比べて、ユーザーのゲームに対する要求レベルは確実に上がっていますし、一本のソフトの中でもある程度色々な体験ができるような幅や深みが求められる時代になったんだと思います。
──そうですね。ユーザーがゲームに求める理想というか、ハードルも高くなっているし、同時にユーザーがちょっと飽きっぽくなっている気がします。
堀井氏:
今はスマホアプリでパパッと始めて、ササッと終わらせて、ということができる文化があるわけですから、ある程度ゲームへの集中力が落ちてしまうのは必然なのかもしれません。ただそれって、コンシューマーゲームにとっては結構致命的なんですよね。
アプリゲームなら、ちょっと触って「あーこれ飽きたな、こっちやろう」ってすぐさま別のものに切り替えられますけど、据え置きゲームは簡単にソフトを切り替えられないし、ある程度の時間続けてもらう前提で作ってるので、ソフトをすぐに替えられたら困ってしまうわけです。だからチャンネルの切り替えというか、一本のソフトのなかである程度「飽きたら違うことができる」ようにしておかないと、今はちょっと厳しいのかな、という気がします。
大ヒットした『ペルソナ5』にしても、RPGがベースであるものの、それ以外にもいろいろな遊びが入ってますよね。そういった、時代に求められているゲームデザインの実現に、ミニゲームは欠かせないものだと言えると思います。
──また世界観やキャラクターを魅せると言う面でも、ミニゲームやサブストーリーのようなものは非常に重要ですよね。
堀井氏:
そうですね。メインストーリーの中だけでキャラクターや世界観を深く描ききることは、大作化が進む今の時代ではかなり難しいと思います。
『龍が如く』に関して言えば、主人公の桐生一馬はメインストーリー中は基本的にずっと男らしい格好いい人間として描いていますが、サブストーリーでは格好いいだけじゃなく、格好悪い姿や可愛らしい姿など、人間的な一面を魅せることでキャラクターに深みを与えています。
メインストーリーの中で、例えば女の子に対してこの人はどうするんだろうとか、こういう状況になったときにどうする人なんだろうとか、そういったものを描くとなると、ボリュームが大変なことになりますし、ゲームとしても間延びして冗長になってしまう。なので、キャラクターや世界観の深掘りはサイドコンテンツ側に寄せる、というのは理にかなったゲームデザインだと思います。
『龍が如く』と共に始まったプランナーキャリア
──そんなトレンドの流れがある中で、『龍が如く』シリーズにおけるミニゲームの新たな境地を切り拓いたのが堀井さんですが……まずはどんな仕事をされてきたのかをざっくりお聞きしたいです。
堀井氏:
セガに入社したのが2006年なんですけど、最初から『龍が如く』チームへの配属だったんです。
2005年に『龍が如く』(以下、『1』)が出て結果が出て、ちょうどこれから『龍が如く2』(以下、『2』)を作るぞ、という時期でしたね。それから『龍が如く OF THE END』(以下、『OF THE END』)など一部の作品をのぞく、ナンバリングとしては最新の『6』まで、同じチームで『龍が如く』シリーズを作り続けています。
『龍が如く』パッケージ(画像左)と『龍が如く2』パッケージ(画像右)
『龍が如く』シリーズはいわゆる大作規模の作品なので人員も多く、内部でたくさんのチームに分かれています。
大枠で「デザイン」、「プログラム」、「企画」といった職種ごとに分かれたチームがあって、さらに僕のいる企画チームは、メインストーリーを作る「ストーリーチーム」とバトル部分を司る「バトルチーム」、そしてストーリーとバトル以外の全般を担当する「アドベンチャーチーム」の3つに分かれています。
僕は、入社直後の『2』のときはストーリーチームに配属となり、音声収録のサポートをしたりムービーシーンの字幕を入れたり、といった細かな作業をやらせていただきました。次の『龍が如く 見参!』(以下、『見参』)ではバトルチームに移って、「ヒートアクション」という必殺技のようなものを中心に担当しました。

──なるほど。バトル関係をやった後は……?
堀井氏:
『見参』から『龍が如く4 伝説を継ぐ者』(以下、『4』)まではバトル班にいたんですが、バトルの仕事と並行して手掛けていた、サブストーリーやプレイスポットが好評をいただいたこともあり、徐々にシナリオ関連やミニゲームデザインの仕事の比重が大きくなっていきました。その流れで『バイナリー ドメイン』では、バトル班から卒業して、会話イベントのシナリオや海外版の音響監督を任されることになったんです。

なので、その頃は海外にひとりで数ヵ月出張したりしていましたね。そして『バイナリー ドメイン』が終わったタイミングで『龍が如く5 夢、叶えし者』(以下、『5』)のチームに入って、作品全体の仕様やゲームデザインをまとめる、メインプランナーという職を初めて任せていただきました。そこからはシリーズを通して、大体メインプランナーや、それに似たポジションをやらせていただいています。
──堀井さんは、この世代のクリエイターにしては作ったゲームの本数が非常に多いですよね。
堀井氏:
そうですね。5年に1本、という人も珍しくないので、そこは恵まれているなと思います。『龍が如く』シリーズ作を大体1年に1本出していくぞ、という当時のスタジオの方針のおかげですね。今は少し間隔が空くようになりましたが。
 |
ただ、短いスパンで出し続けると、ユーザーさんが離れずについてきてくれたりとか、反省したことをすぐ次の作品に反映できたりもするので、そこはよかったと思います。個人的には、もうちょっとゆっくりしたかった部分もありますけど……(笑)。
クリエイターとしてはやりがいのある良い環境だったんじゃないでしょうか。
桐生のキャラ崩壊 「カラオケ」の導入秘話
──堀井さんの代表的な仕事と言えば、やはり『3』で誕生したカラオケのミニゲームですよね。最初にあのノリを持ち込んだときの、社内の反応はどうだったんでしょうか。
堀井氏:
最初はもう、ボロクソに言われましたよ……「なにやってんだお前は! 滝修行【※】が受けたからって調子に乗ってんだろ!」と怒られて(笑)。今でこそ違いますけど、当時はまだ桐生のキャラをそこまで崩すようなことはやっていなかったので、やはり内部から批判というか、「こんなことを桐生にやらせるなんて絶対ダメだ!!」という反応はありました。
桐生役を務める声優の黒田崇矢さんにも驚かれましたね。「今回の『3』は歌があります、あと、合いの手も入れていただきます」と伝えたら「……合いの手?」と返されて。「そうなんです。僕に続けて言ってくださいね。いきますよ……お姉ちゃん! はい!」とノリノリでお願いしたら「おいおいちょっと待て、俺がやるのか!?」というようなやり取りがあって(笑)。
※滝修行……堀井氏が初めて担当したミニゲーム。『見参』に登場。セクシーな煩悩の誘惑に惑わされずに入力を行う、という奇抜なリズムゲーム。これが好評となり『3』でのカラオケ担当抜擢に繋がったとか。
──導入までには、『プロジェクトX』ばりの苦難があったんじゃないかと思いました。
堀井氏:
そうですね。桐生が激しい合いの手をしてキャラ崩壊することへの拒否感がチーム内にあったので、激しい合いの手と同時に、テンションの低いクールな普通の合いの手も録って、とりあえず最初は「バリエーションとして激しい合いの手もとりましたが、基本的に普通の合いの手でやるつもりです」とチーム内には説明しておきました。ただ、実際には「激しい合いの手」のほうを実装して、出来上がったものをプレイさせることで、周囲に面白さを伝えながら説得していった感じです。
 |
もちろん、合いの手でのキャラ崩壊も、考えなしにやったわけではないんです。『1』、『2』である程度桐生のキャラが確立できていたので、「ちょっと崩したものを入れてもいける時期なんじゃないか」とか、逆に「こういうところで崩していかないと、ゲームとして今後発展していかないな」という感覚もあったんですよ。だから、総合的にいいタイミングかなとも思っていました。
チャレンジしてみたら、それが意外にも反響が良くて……。今思えば、ここがひとつの転機になっていた気はしますね。
──ちなみにシリーズの総合監督を務める名越(名越稔洋氏)さんは、カラオケに対してどういうリアクションだったんですか?
堀井氏:
名越や、当時のプロデューサーの菊池(菊池正義氏)や横山(横山昌義氏)には、苦笑いされつつも「やってみたら?」という感じで、わりとすんなり受け入れてもらえました。
周りには結構いろいろ言われたんですけど、名越たちは背中を押してくれたので、それはありがたかったです。
──カラオケの作り込みって尋常ではないのですよね。ミニゲームのレベルではないというか……。
堀井氏:
僕の情熱の結晶ですから(笑)。
元々バンドをやっていて、ミュージシャンを目指していた時期もあったくらいなので、音楽関係に関しては並々ならぬ情熱とこだわりを持っているんです。
カラオケのゲーム自体も、担当を任される前段階から勝手に構想していたくらいで。実は、そもそも僕がカラオケ大好き人間なんですよ。
──あ、そうなんですか。
堀井氏:
ええ。あまりにも好きすぎて、自分の歌える楽曲をリストにして持ち歩いているくらいです。2018年で、ついに持ち歌が7000曲になりました。このリストを眺めて「はは、こんなに歌えるんだ、まじ俺すげぇなぁ」と悦に浸るのが僕の趣味なんですよね……。
(リストをその場に広げて)今年で、はじめてから15年目くらいですかね。未だに更新し続けています。1年で300曲増やすのを目標に頑張っています。
──これはすごいです(笑)!
「街ありき」の進化
──堀井さんは『2』から開発に参加されていますが、開発の体制で当時と今では違っているところはありますか?
堀井氏:
体制は大きく変わらないかと思いますが、開発自体の規模や開発環境は全然違いますね。当時はチームの人数が今よりずっと少なかったですし、開発のための設備やツールもまだ充実していない部分がありました。
パソコンのパワーも今に比べたらかなり低いですし……。たとえば一箇所を手直ししたときに、それを再チェックするまでに30分から1時間かかるとかそんなことがザラで。
──なるほど。『2』までの頃と『5』以降を比べると、サブストーリーを含めたシナリオの厚みとか、ミニゲームのボリュームとクオリティが段違いだと思うんです。これは、最初からこうしたある種オープンワールド的な方向性を目指していて、開発スペックがようやく追いついたということなんでしょうか。それとも、それこそカラオケあたりを機に、「こっちを強化しよう」という転換があったんですか?
堀井氏:
当時オープンワールド化の流れが業界全体にありましたが、その流行に乗ろうという発想は、少なくとも現場にはなかったように思います。
サイドコンテンツが厚くなっていったのは、シンプルに正当進化していった結果なのかなという気はします。サブストーリーのクオリティを上げたのも、単純に桐生や街の人々のキャラクターをより深く描くためですし、プレイスポットが増えたのも「神室町」という舞台をより楽しくリアルなものにしようと思ったからにすぎません。

そもそもの話になりますが、『龍が如く』のサイドコンテンツは、基本的には「街」を作るために存在していると考えています。
『龍が如く』は神室町という、歌舞伎町をモチーフにしたリアルな街を舞台にしていることが、他のゲームにはない大きなセールスポイントです。そうなると当然その舞台には、歌舞伎町のような体験ができることが求められますよね。
キャバクラに行けない歌舞伎町なんか歌舞伎町とはいえないわけですから、必然的にキャバクラがスポットとして入ってくるわけです。

──舞台のリアリティを味わわせるためのミニゲームだと。
堀井氏:
はい。繁華街というものをよりちゃんと描くのであれば、入れない店だらけにしておくのではなく、それを入れるようにしていくのは必然の流れですよね。カラオケもそうです。『2』にはカラオケは入っていないですけど、実際の繁華街には山ほどカラオケ店があるんだから、ゲーム内で入れないのはおかしい。プレイスポットが増えていったのは、基本的にはそういう考えによるものです。

(Photo By Getty Images)
だから、ひとことで言うと「街ありき」なんです。街ありきでシナリオとミッションがあって、その街に触れていく中で、桐生というキャラクターのさまざまな側面が浮かび上がっていく。桐生が羽目を外したり、多彩な表情を見せるようになってきたのも、シリーズを重ねるごとに街が充実してきた結果だと思っています。
──言い方として正しいかわからないですけど、海外のシミュレーター趣向と近いものを感じます。日本はゲームにおいてシナリオをかなり重視するけれども、それに対して海外はどちらかというと、空間のシミュレーション自体を好む傾向にあるそうで。
堀井氏:
そうですね。趣向としてはそっちに近いのかもしれないです。








































