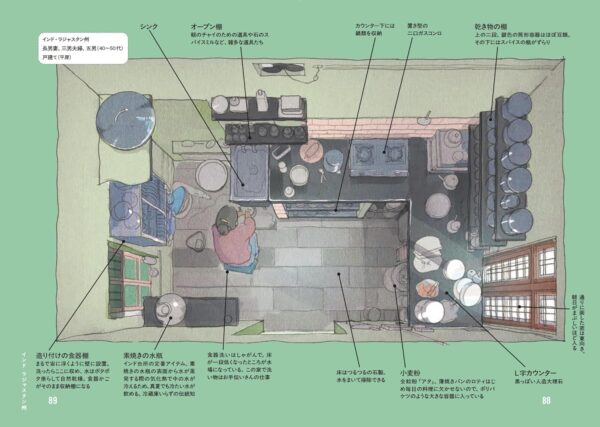インディーゲームは「自分がやりたいから」という理由でやれてしまう強さがある
 |
――インディーの話とはちょっと違うかもしれませんが、特にエンタメって、例えば80点のものと90点を超えてくるものって、全然価値が違ってくるじゃないですか。90点を超えた瞬間に大ヒットの可能性が出てくる、みたいな。
でも制作する過程では、0点から50点、もしくは80点までは、かけた時間やリソースに対して比例して品質が上がっていくんですけど、そこから先をあげるのはとんでもなくコスパが悪い世界にいかざるを得ない。
会社組織という中では、これがすごくやりづらくて。だけどインディーは規模も小さいし、「自分がやりたいから」という理由でやれてしまう強さがあるのかなと。
吉田氏:
開発における最後の半年間のマネージって、本当に難しくて大事なんですよ。色々と告知しますし、マーケティングも動いています。ユーザーさんにも待ってもらってますし、期待感が高いうちに出したい。
ただ、やればやるほど良くなっていくので、どこで止めるか。これが本当に難しいですね。どこのデベロッパーに聞いても、妥協して出したと言うと思います。「100点です」と言う人はいないと思うんです。自分の子供を取り上げられたり、「お前もう会社に来るな」と言われたような感じで、泣く泣くまとめて出す……というのが多いので、そこのマネージメントは私も非常に気を使ってやってましたね。
でもね、最後にドカーンと行く時もあるんですよね。弊社で出して滅茶苦茶ヒットし、名作と言われるようなタイトルも、完成の1~2ヶ月前は相当ひどい状態だったとか、よく聞くんですよ(笑)。
――ゲーム制作の現場の実情を知らない人には分かりにくいと思いますが、ゲームって9割くらいできていてもつまんないんですよね。
吉田氏:
見た目は綺麗で完成したものと違いが分からないんですけどね、傍から見ている人にはね。
E3とかのプレゼンにかける労力、デモでひとつのステージだけでも凄く楽しいものに仕上げる労力って、凄まじいですよ。それを全部のゲームでやらないといけませんし。映像だけ作るのと、プレイアプルなものでユーザーさんに楽しんでもらう形にするものは、相当の違いがありますね。
 |
インディーゲームが溢れている現状について
――二元的に語るのもどうかと思いますが、インディーゲームは商業的なパッケージタイトルとは違う性質や特性があって、全てとは言いませんが、その中からとんでもなく面白いものが出てくる。
昔は絶対数がまだまだ少なかったので、インディーゲーム自体を啓蒙することが、頑張って作った人への応援になっていたと思うんです。でも今は、Steamとかで出ている年間のインディーゲームは1万タイトルとも言われています。こういった現状でインディーゲームをどうやって応援していくべきなのか、問われているのかなと思いまして。
以前だったら「みんなインディーゲームを遊ぼう」で済んだんですが、ここまで溢れてきてしまうと、スタンスなどを変えざるを得ないのかなと。その点について、吉田さんはどのように思ってますか?
 |
吉田氏:
その点については、メディアの方と我々プラットフォーマーの存在意義とでも言いますか、責任として似ている部分があると思います。これだけたくさんのゲームが出て、世界中の人がUnityやUnreal Engineを手軽にダウンロードできて、誰でもゲームが作れるようになり、これまでゲーム業界に入るチャンスがなかった方でもゲームクリエイターになれる。こういった環境ができたのは、非常に素晴らしいことだと思うんですけど、一般の人どころかプロでも追い切れないほどのタイトルが出てしまっており、「何がいいのか」「どのゲームを買えば楽しめるか」がユーザーさんには分かりにくいですよね。
そこでメディアさんや我々がしっかりと目利きをし、「このゲームはすごくいいですよ、楽しいですよ、お勧めしますよ」とフィーチャーし、ユーザーさんの目に届きやすくする。ブログや映像などで、代わりにプロモーションを行うのが責任だと。
インディーゲームの人たちって、マーケティング担当がいなかったりしますから。セルフパブリッシングされるようなチームは、本当に作ることで精一杯で。中には「いいものを作って出せば売れるだろう」と思っている人もいますが、「いえいえ、そうじゃないです。そんな甘い世界ではありません」「代わりに私たちがフィーチャーしますよ」と言ってあげて、ユーザーさんに届けていくのは本当に大事な仕事だと思ってますね。
――クリエイターさんの中には、作ることに関心はあるけど宣伝には全く関心がないパターンも結構あると思うので、そこをどうサポートするのかは、我々メディアの仕事のひとつでもあるかなと自覚しています。
吉田氏:
私が2008年に日本へ戻ってきた時に、「日本ではインディーゲームがあんまり騒がれてない」「海外では滅茶苦茶売れてるゲームが、こっちでは発売されてない」「ローカライズもされてないぞ」みたいな状況だったんですよね。
その後、インディーゲームの祭典「BitSummit」が始まって盛り上がり、ファミ通さんでもインディーゲームがクロスレビューの対象になったりして、全体的に盛り上がってきたなと思いました。平さんが以前おられた4Gamer.netさんは、わりと早い段階からインディーゲームを取り上げられていましたよね。
――4Gamer.netはもともとパソコンの、特に海外のゲームをピックアップするところから始まったメディアでして。日本のゲームメディアとして当時あり得なかったんですが、東京ゲームショウはガン無視、みたいな(笑)。
吉田氏:
なるほど(笑)。
――ひたすら海外のゲームを紹介するといった出自があるので、Steamのインディゲーム立ち上がりといったところも割と早い段階から注目し、興味を持ってプレイなどもしていたのが大きかったのかなと思います。
吉田氏:
私はインディーゲームが本当に好きで、こんなにいいゲームがいっぱいあるのに、日本のユーザーさんが知らないのは本当にもったいないと思っていました。
「BitSummit」も毎年行くようになり、プレゼンみたいなものもさせていただきました。「BitSummit」には、海外のデベロッパーさんに来てくれるんですよね。「BitSummit」は京都で開催しているので、半分は京都に行きたいという気持ちで(笑)。そこで、日本のメディアと海外のデベロッパーの交流が生まれたりしています。
面白いなと思ったのが、「BitSummit」を立ち上げた京都在住のデベロッパーの人たちって、半分くらいは日本人じゃないんですよね。
オンラインイベント「BitSummit 外伝」が6月27日・28日に開催決定。延期された「The 8th Bit」の代替として開催、“仮想デベロッパーブース”の設置予定も
――「Q-Games」とか。
吉田氏:
日本が好きで京都にオフィスを構えて、彼らが日本のインディーゲーム市場を盛り上げる役割を買っていて。そこのファミ通さんや電撃さんが乗ってこられて、ライブ配信を行ったりしてますね。
そうやって日本でも徐々に広がりを見せ、インディーゲームにこだわらなくとも「面白いゲームだったら遊んでみよう」というユーザーさんが増えてきたと思います。また、人気のあるYouTuberさんがインディーゲームを取り上げて「これは面白い!」と発信され、そういったところからもユーザーさんがゲームの情報を取れるようになっている。
このように少しずつながら、日本でもインディーゲームの市場が盛り上がっています。そうなると次は、日本発のインディークリエイターがもっと増えて欲しいなと思いますね。そろそろ、次に行ける段階に入ってきたのかなと。
いま海外のインディーゲーム文化と日本のインディーゲーム文化が重なりつつある
――日本のインディーゲームや同人ゲームの流れみたいなものって、少なくともオフィシャルな場で語られたことはそんなにありませんよね。
日本では、コミックマーケットを中心に同人ゲーム文化というものがあり、それとは別にインターネット上で入手できたり遊べたりするフリーゲームという文化もありました。そして、フリーゲームを実況して楽しむといった流れも、ニコニコ動画などで見受けられました。
海外におけるインディーゲームのブームと、日本のちょっと特殊な形での盛り上がりは、それぞれ違う流れだと思うんです。でも、それが今は重なってきている。例えば、『天穂のサクナヒメ』とかが代表的な作品ですね。あれって、同人文脈の人たちが作ったゲームですが、Steamとかを含めた商業プラットフォームで大成功を納めました。

吉田氏:
『天穂のサクナヒメ』も、基本は2人で、すごく長い時間をかけており、完成度も素晴らしく高かった。あれがグローバルでもセールスを出したというのは、素晴らしいことです。
ああいった国内で作られたもの──他には『クラフトピア』(POCKET PAIR, Inc.)とか──がヒットすると、「じゃあ我々もやってみよう」と足を踏み出すデベロッパーさんが増えるんじゃないかなと思ってます。
――『クラフトピア』にせよ『天穂のサクナヒメ』にせよ、50万本を超える日本発のインディーゲームが出てきていて、これは結構な事件だなと思っています。ここから、100万、200万という更なる飛躍に繋がっていけると一番いいですよね。
吉田氏:
アメリカにある「InnerSloth」が開発した『Among Us』は、1億とかを超えるダウンロード数ですが、わずか数人で作ったんです。あれは、日本人が作ってもおかしくなかった。それを考えると、「やってもいいんだ」「SteamやiTunesで出してみよう」と、どんどんトライして欲しいですよね。
出版社はインディーゲームクリエイターの背中を押す存在
――日本のインディゲームシーンを盛り上げるひとつとして、出版社がインディーゲームの応援をし始めるという流れが、去年から今年にかけて起こってきていますね。
吉田氏:
我々もお誘いを受け、「ぜひぜひ、ご協力できるところはやりましょう」という形で「集英社ゲームクリエイターズCAMP」にはPlayStationとして関わらせていただいています。こういった取り組みは私も素晴らしいと思っています。
なぜ、日本でインディーデベロッパーが増えないのかと言えば、その課題のひとつに、文化的もしくは社会的な背景として昭和を引きずっている部分があるのかなと。「大きな会社に入れたら、いい生活ができる」みたいな。そこから独立してリスクを取るなんて、「食えなくなるかもしれないからやめなさい」と親が止めたりして。
ですが、海外は非常に動きが速いので、 若い時から自分で会社を興すような文化も見られますよね。
それに対して日本人は、優秀な方が大企業に入ってそこに長く居続ける形になるケースが多い。海外で見られるような、いいゲームを作ったチームが丸々独立し、自分たちが本当に作りたかったゲームを作り、そこから完成度の高いインディー作品が出てくる。こうした流れが、これまでの日本では作りにくかった。
 |
そこに、出版社さんや大手法人が、もしくはパブリッシャーさんでいいんですが、背中を押して最初の1歩をサポートする。そして、世の中に向けてプロトタイプを問うような機会を、独立を考える方々に与えてあげることが、今の日本が抱えている文化的な課題にぴったり合っているんじゃないかなと思います。
特に私は集英社さんの話を聞いて、漫画業界などで培われてきた編集者的な視点でアーティストをサポートしたり、アーティスト同士の横の繋がりを促すとか、そういった動きにすごく期待しています。
さきほどの『天穂のサクナヒメ』もそうですけど、いいなと思うインディーゲームって、ひとりもしくは少人数で作っているケースが多いんですよ。ものすごく才能のある人が、時間と情熱をかけて作られていて、非常に素晴らしいんですけど、「やりたいことが自分と似ている人」と気楽に出会えたりチームを組めれば、さらに凄いゲームが出来たり、もっと早く作れるかもしれません。
そこから、50万本の壁を突破するゲームがもっと生まれる可能性もあるので、「背中を押す」「人を横で繋げる」という取り組みは、すごくいいなと思います。
――出版社はもともと、本を売るビジネスモデルだったじゃないですか。アニメにするのも、極論を言えば原作の本を売るのが軸なんです。で、そこからアニメそのものも売れるようになったし、アニメ化でIPが認知されてキャラクタービジネスにも発展して。
そうなると、「出版社の本質とはなんだ」という話になるんですよ。本を刷って売る出版だったのに、実態としてはコンテンツを作るソフトメーカーでもあり、編集者にフォーカスしていくと“エンタメに特化したマッチングサービス”みたいな部分が本質なんじゃないかといった話があって。
吉田氏:
それは、非常に自然なことである、という話ですね。
――はい、そうです。そして、紙によるビジネスモデルからの脱却を各社さんが模索している中で、編集者の価値といった部分を、漫画ビジネスだけでなくゲームやアニメとかにも向けたり、もしくはそれを繋げて価値をかけ算するような、システマティックな流れのひとつなのかなと僕的には解釈しています。
あと、海外のインディーゲームの会社やクリエイターは、いい意味でビジネスライクと言いますか、投資も集まりやすいし、辞めるときもポジティブというか「若いうちにチャレンジしろよ」みたいな感じで。出来る人ほど独立して投資を集めて、失敗したらしたで、みたいな。
日本で会社を興すと「自分で借金して」みたいに考えがちなんですけど、海外だと投資で興し、失敗したら事業責任とはあるにせよ、自分が借金を背負ったりはせず、次のプロジェクトに進む。そういう、ポジティブでスタートアップ的な概念が大きいのかなと思います。
吉田氏:
エンタメのプロダクトって、ヒット作がものすごい規模になるじゃないですか。10本打って3割ヒットが出ればカバーできる、みたいな。なので投資側も、ポートフォリオの考え方で投資するんです。
1タイトルだけだとリスクが高いけども、10タイトルに投資して3つヒットすればリターンが回る。そういう形でのベンチャーキャピタルの市場があるので、経験値のあるデベロッパーがチームごと独立するような形は、非常に安心して投資しやすいのだと思います。
インディーゲームの定義とは
 |
――その辺りも、最近ちょうど変わり始めてますよね。まさに『天穂のサクナヒメ』とかが、次にやりたい人たちにとっての成功事例になりました。そこから、インディーゲームにおけるクリエイターさんの市場というか業界も活性化しうるのかな、と。
こちらは少し話が変わるのですが、インディーゲームと一言でいっても、何がどこまでインディーなのかなって。最近はかなりあやふやですよね。
以前は、10人以下の人たちが作ったゲームをインディーゲームと呼ぶみたいにしてた部分があったと思うんですが、今は100人規模のスタジオで作った作品も、インディーゲームとして出てくるじゃないですか。なんでそうなったんでしょう?
吉田氏:
インディーって狭い言葉の意味で言うと、インディペンデントのインディーですよね、もともとは。そこでパブリッシャー対デベロッパーみたいな昔の構図があり、パブリッシャーがお金を出しているのでデベロッパーは言うことを聞き、ゲームを作る。そこからデベロッパーが独立し、自分が発売元になれるというのが、狭い意味でのインディーゲームだったと思います。
今は、タイトルが非常に多くなり、インディーデベロッパーもゲーム制作に集中したい。そんな中で、インディーデベロッパーが出来ないもしくは苦手なマーケティングなどを担うインディパブリッシャーという新しいグループが出てきました。
インディパブリッシャーは、インディーデベロッパーがやりたいものを投資などでサポートしますが、一番大事なIPはインディーデベロッパーが持ったままです。あくまで、投資やプラットフォーマーとの関係、ローカライゼーションといったサポートに徹する形ですね。
で、本来はパブリッシャーからのインディペンデントだったので「インディーパブリッシャーってなんだ?」っていうね(笑)。また、「インディパブリッシャーが出しているインディーゲームは、果たしてインディーゲームなのか?」と(笑)。
そういうところを考え始めると訳が分からなくなるので、そのゲームが「インディースピリットを持って作られたゲーム」であれば、私はインディーゲームでいいんじゃないかなと思っています。
我々が発売元になり、お金も出した『風ノ旅ビト』って、やっぱりインディーゲームだと思うんですよ。あれは本当に、インディースピリットに溢れたゲームでしたね。極端な例で言えば、小島監督曰く「『DEATH STRANDING』はインディーゲームです。」みたいな話だってある(笑)。
『DEATH STRANDING』(SIE)は、小島監督の「作りたい」という想いが隅々まで通った形で完成されていますよね。そういう意味でインディーゲームだと言われているのだと思いますけど、そういったクリエイターの強い想いが作品になって世に出されているものを、私はインディーゲームと呼んでいますね。

――インディースピリットというのは、独立独歩性みたいなものですか?
吉田氏:
そうですね。クリエイターが一番作りたいものを作ってます、っていうところです。
――そのご意見には賛同なんですが、一方でインディーゲーム市場の魅力って、チャンレンジャーが参入でき、勝ちうる点だと思うんです。そこで、100人規模で開発したゲームもインディーですと言われ、インディー市場での戦いになると、ひとりで作ったゲームはなかなか勝てなくなりますよね、構造上。
そうなると、本当は作家性で勝負して欲しいのに、作家性ではないところの仕組みや構造で勝負が決まってしまう──そうした圧力のようなものが高まってしまうのは、どうなんだろうなと思いまして。
吉田氏:
インディーゲームの良さって、「自分の作りたいものが作れる」「自分で決められる」「作ったものは自分のものになる」に加えて、注目すべきは「ユーザーさんとの繋がりを直接持てる」という点でして。デベロッパーあるいはゲームを中心としたゲームコミュニティを、自分たちで作って大きくしていけるんです。
パブリッシャーがいる場合だと、仕事の役割分担などがあるのでなかなかそうならない可能性もあるんですが、インディーズだと例えばDiscordなんかで自分のコミュニティを作り、ひとつヒット作が出るとそこにファンがつきます。
そうなると次回作の告知もしやすいですし、ファンの人たちに向けてクローズドβを遊んでもらい、意見を聞いた上で発表しようとか、次のタイトルを良くする活動にも繋げられます。また、そういった形で参加してくれたユーザーさんは、まずますファンになることでしょう。タイトルを初期の頃からサポートして、意見も出したりすると、告知もしたくなるんですよね。そうすると、口コミで広げてくれます。
こういった形で、インディーゲームの黎明期にヒットを出した人たち──スーパーインディとも呼ばれていますが──は、儲かったお金で人を雇って大きなものを作れるようになりますし、デベロッパーとしての名前が認知されてファンが増え、次のタイトルを成功させる可能性を高めています。
そこで色んな形での格差、例えばインディーコミュニティの中でもスーパーインディと呼ばれているチームと、少人数で初めてゲームを作るチームとの差が出てますよね。そこはもう仕方のないことで、新しいチームはスーパーインディの良いところを学び、目指せばいいと思うんです。
 |
そして、インディデベロッパーとして成功してお金もあり、ノウハウも得た人たちが、パブリッシャーになる動きが最近増えているんです。自分たちが持っているノウハウやお金を使い、他の新しいインディーデベロッパーに投資をする。あるいは、パブリッシングの手伝いをする。また、自分たちが持っているコミュニティで、新しいインディデベロッパーのゲームを告知してあげるといった流れなどが、最近増えてきています。
また投資側も、インディーデベロッパーがパブリッシャーになる段階で、上場したりお金を集めたりといったタイミングに合わせて積極的に投資をするといった流れもありますね。もともとインディーパブリッシャーとして成功しているDevolver DigitalやAnnapurnaといった会社も重要ですし、成功したデベロッパーが自分たちのお金でパブリッシングもサポートするといった形も増えています。
そういった方々が業界の中で作れている新しいゲームを見て、それを拾い上げ、世の中への告知のサポートをする──こういった繋がりも使っていけばいいし、そのために何をすればいいかと言えば、作っているものを世に発表することですよね。Twitterでもいいので「こんなもの作ってます」とアップして、それで意見をもらうと。
あるいは、自分が尊敬しているインディーデベロッパーやパブリッシャーをフォローして、そこから関係を作り、作品を見てもらうとか、そういったことをやっていくのがいいんじゃないかなと思います。
――ネガティブに捉える必要はなくて、新しいゲーム業界の新陳代謝の流れなんですね。インディーゲームから始まり、パブリッシャーに行くという形が、ただポジティブに起こっているだけなんだっていう。
吉田氏:
はい、そう思います。しかもインディーの中って、みんな苦労してきた歴史を背負っていますので、他のインディーデベロッパーに優しいんですよね。教えてあげたり助けたりするのは、よく聞く話ですね。
――さきほど、コミュニティを作っていくという話がありました。全部のタイトルがそうだとは思いませんが、「インディーゲームはコミュニティが大事」とみんなよく言うんですよね。Discordでコミュニティを作ったり、Twitterでアナウンスしたり、あるいはSteam上でやりとりをするなど。
吉田氏:
アーリーアクセスとか。
――ええ。で、それまでのパブリッシャーのゲームだと、点の接し方のような形でしたよね。ゲームが出る、アップデートがある、くらいのやりとりで。それが、もうちょっと恒常的なやりとりになっているのかなと。
その上で、あそこで起こっている新しい楽しまれ方を見ていると、僕からすれば“ある種のアイドルの追っかけ”あるいは“プロレス”といった、成長する過程そのものをみんなで応援して楽しんでいるノリがあると思っているんですよ。
『クラフトピア』がまさにその典型だったと思うんです。まず、『クラフトピア』はいいゲームですよという前提でお話するんですけど、あのゲームってバグだらけなんですよ。とんでもないバグがいっぱいあって。作っている溝部さんにお話を伺うと、「ぶっちゃけ、バグはいっぱいありますし、検証していません」と言われるんですよ(笑)。
そんなのあり得ないじゃないですか、今まで通りの考え方だと。でも、それをオープンにした上で、言われたらすぐに直します、対応しますという姿勢があるんです。それって、すごく新しいスタイルだなと思うんです。

吉田氏:
スピード感は大事みたいですね。いただいた意見に対して、応えていく。それは結構労力が必要なことです。
さきほど、インディーゲームの魅力として、小さいものが大きなものを倒す快感があると仰いましたが、業界でも著名なアワードを、インディーゲームが獲得することが当たり前のようにあります。
大手のAAAタイトルと同じように、ごく普通にインディーゲームがノミネートされて、ベストゲーム賞を取ってしまう。去年、弊社は『The Last of Us Part II』や『Ghost of Tsushima』、PS5用『Demon’s Souls』などを発売して好評もいただいたのですが、「Supergiant Games」という20人くらいの会社が開発した『Hades』(Supergiant Game)というインディーゲームがこういったタイトルと並び、しかもトップアワードを攫っていくんです。

これは最近のゲーム業界ではよく見られる光景でして。こういうアワードは業界人が投票しているので、業界人が感じる新鮮さや、次の世代を作ってくれそうな感覚を得られるゲームを、みんなが応援する。それがインディーゲームの役割でもありますし、そこを業界全体で応援している部分もあると思うんです。
そして『Hades』は、Steamよりも先にEpic Gamesのアーリアクセスで出て、1年以上もアップデートしているんです。そして完成度が高まったところでバンッと出て、去年のゲームオブザイヤーにノミネートされました。このアーリーアクセスのプロセスを取っていなければ、あの完成度の『Hades』は生まれなかったんじゃないかなと思いますね。
英国アカデミー賞のゲーム部門が発表、『Hades』がベストゲーム賞を含む5部門で受賞。最多ノミネートの『The Last of Us Part II』はファン投票を含む3部門に輝く
――メディア的な視点で少し補足をすると、今ってマーケティングでも口コミがすごく重要ですよね。そして、メディアに携わっていると分かるんですけど、どんなに面白いゲームでも、世間がその面白さを知らない状態で記事を書くと、リアクションって薄いんですよね。
例えば、『十三機兵防衛圏』(アトラス)というゲームの場合、あの作品の発売当初は開発会社であるヴァニラウェアのファンなどが一部が騒いでいた状態だったんですが、実際に本格的に火が点いたタイミングはちょっと後だったんです。
ゲームを買って遊んで「超面白かった」と思う人たちが増えた後に、これは面白いという情報や記事が出ることで「そうそう!」とリアクションされるようになり、話題が大きく広まり始めたんです。その土台があったからこそ、より拡散したのだと思っていて。
『Hades』とかもおそらく、一緒に応援し、フィードバックもあり、実際にゲームも面白いと感じたコミュニティの土台が出来た後に、アワードに選出されたり、メディアがリリース記事を出すことで、既にいるファンたちがそれを応援する。こういった、コミュニティの土台が出来るという流れが、フィードバックで完成度が高くなるのと同等くらいの価値を持っている気がします。
『十三機兵防衛圏』が狂気的に傑作すぎたので、思ったことをちょっと書く
吉田氏:
去年、弊社も頑張って応援した『Fall Guys』も、そうでしたよね。パソコン上でかなり長い間、クローズドβやオープンβをやってましたから。そこでファンがすでに暖まっていた段階で、PlayStation 4版も含めてすごく盛り上がりましたね。
――『Fall Guys』がパソコン上で盛り上がっている時って、能動的なユーザーが中心でしたよね。それが、PS Plusのフリープレイに出たことで、受動的に遊ぶ人がバーッと増えた。あの、階段を一気に駆け上がるような流れというのは、運もあるんでしょうけど、すごくコミュニティが機能した例だったなと感じています。
吉田氏:
インディデベロッパーへのアドバイスとして、コミュニティマネージャーは大事だよと良く言われていますね。早い段階でゲームを発表したりアーリーアクセスをやっていくと、ユーザーさんからの意見がどんどん来るので、それを色々と整理して早いレスポンスを返すことでコミュニティが活性化する。これがすごく大事みたいです。
インディーゲーム の中におけるVR市場について

――インディ市場が挑戦者のフィールドであるという話がありましたが、どんなジャンルでも、新しいプラットフォームや新しいデバイスって、挑戦者が参入するタイミングでもありますよね。でも、段々と成熟していってしまう。
インディーゲーム市場という大きなパイは成熟していくんですけど、その中のカテゴリーのひとつ……例えばVRというものについて、インディーゲームのディベロッパーやクリエイターが活躍するフィールドとして新しく出てくる。この、インディーの中におけるVR市場についてどう思われます?
吉田氏:
私はPlayStation VR(PS VR)の開発にも携わっており、「インディーとVRが大好物の吉Pです」と自己紹介をしていたくらいなんですが(笑)、PS VRの立ち上がりって、会社が「これからはトレンドを見て、VRが……!」みたいなものではなく、それこそスタジオの連中が色々と実験して遊んでいるのを見て、「あれ、こんなことも出来るの?」という草の根の活動がプロジェクトになり製品化したんですよ。
VRのコンセプトって、90年代とかにも映画になったりしていて……つまり待っていたんですよ。「いつになった出来るんだ」と。自分が生きている間に、この世界が実現して欲しい。あるいは、そこで表現したいものが自分にはある、TVの画面は狭すぎる、みたいな。
そういった人たちがずっといて、技術はどんどん進み、デバイスも安くなり、性能も上がった。そして、「今できるんだ」と動き出し、草の根ネットワークが広がっていく。我々や「Oculus」「HTC VIVE」の人たちって、みんな仲良しなんですよ。やりたいから、作りたいから作ってる。それは、インディーゲームデベロッパーも一緒でして。
大手はどうしてもビジネスプラン的な分析をしないといけないんですが、まだ1台も世に出ていないような市場には、なかなか投資しづらいんです。そんな中で、インディーデベロッパーは「作りたいからやるんです」「作っちゃいました」ですよね。
手作りで作られたような、「Oculus」の最初のデバイスが出て、それをキックスターターで買って、「ひとりでこんなの作っちゃいました」みたいな。そういう人たちがどんどん発表するので、それを見て「こんなのが出来るなら、自分もやりたい」と広がっていく。そこはもう、インディーデベロッパーの真骨頂だったのかなと思いますね。
――今この瞬間にVRを楽しんでいる方々って、まだまだ尖った人たちがメインで、数はそこまで多くない。そのため、売れる絶対数が限られます。1万本や2万本、多くても10万本という中で戦うとなると、インディーという市場で発展していくのは必然なのかなと思います。
吉田氏:
必然だと思いますね。新しいメディアが出て、新しいコンピュータの形が出てくると、まず真っ先にゲームが作られるんですよね。大きな市場になる前は大手はまだ入らなくて、例えば「Facebook」が昔ソーシャルゲームをやられていた時、「Zynga」は後に巨大な会社になりましたが、最初はまだ誰も知らないような会社で、そこが作ったゲームをみんなが遊んでいました。iPhoneでも『アングリーバード』とか、その当時は誰も知らないような会社さんが出てきて、ヒットを出す。そういった流れはやはりありますし、VRも同じ道を歩んでいるのかなと思いますね。
――そんなVR市場も、今は100万本売れるゲームが出てきているので、どこかのタイミングで起こるブレイクスルーを待っている状態なのかなと。最近だと、他社さんの製品なので恐縮ですけど、Oculus Quest 2とか凄く品質がいいですよね。
吉田氏:
PS VRでも最近出ました『ALTDEUS: Beyond Chronos(アルトデウス)』などを手がける「MyDearest」は、メンバーがまだ20代ですよね。これまでの日本のADVゲームをVRにして、自分も参加してキャラクターのひとりになれるという。これは、戦略的に考えているところもありますよね。
(「MyDearest」代表取締役CEOの)岸上さんのお話を聞くと、自分たちは大手のような資本力や技術力はない。その中で、VRにおけるこのADVの形はまだ誰も作ってないし、日本にはこれが作れるクリエイターがいる。だから、日本で作る難しさを強みに変えている、みたいなお話を伺いました。
そして、Oculus Questの売れ行きなども追い風となり、グローバルで認知されてヒットされた。これは、素晴らしい話だなと思います。

――岸上さんが仰っていて面白いなと思ったのが、「VRでテキストADVをやるって意味が分からなすぎて、誰もが反対した」というエピソードなんですよ。だって普通はVRって、3D空間の中で動けたり振り向けるのが重要だとみんなが思ってますから、その空間でテキストを読むって何ですか、みたいな。
でも、誰も想像しない、やろうと思わないところに踏み込んでいって、独自性を発揮していくのは、本当にベンチャーそのものだなと。
吉田氏:
大手だとね、企画会議で落とされちゃう(笑)。
――あり得ない(笑)。大手では潰されちゃう企画を、本当に信じてやってるんですよね。素晴らしいです。あと、VRってまだまだ試されていないことだらけなので、さきほどのインディースピリッツじゃないですけど、インディーとの相性はすごく良いかなと。
水口(哲也)さんと話をしていた時に、TVの画面に落とし込むことで色んなものがスポイルされるということを仰られてまして。人間が普通に受け取っている情報量って、こうして話しているだけでもかなり多いんですよね。ただの言葉のやり取りだけじゃなくて、身振り手振り、表情とか声のトーンとか、すべてが“体感できる情報”なんですけど、それを何かしらの形に落とし込みと、いろんなものが削ぎ落ちちゃうという話なんですが。
吉田氏:
そうそう。最初、このインタビューはリモートでやりますかという話もあったんですが、実際に会ってお話した方が非常に盛り上がりますよね。
――VRというのは、現実世界にある膨大な情報を、よりダイレクトに表現できるところが素晴らしいんだという話を、水口さんから伺いました。
吉田氏:
今回の「Game Vket ZERO」にOculus Questで入ってみたんですが……去年から新型コロナの影響でイベントが全てキャンセルになり、ありとあらゆるイベントがオンラインイベントになりましたよね。で、他のオンラインイベントだと「あれ見たよ」という感じだったんですが、「Game Vket」の場合は「Vketに行ってきました」って自然に言えるんですよ。
――「見ました」じゃなくて。
今VR空間で何が起こっているのか──バーチャルに住む人々が想像する未来とアバター即売会「バーチャルマーケット」という可能性
吉田氏:
Vketに入ってみると、人が集まってるブースがあって、「人気があるんだな。なんだろう」と興味が惹かれたりして。で、近くにいる人の声も聞こえるので、外国の方が「これはなんなんだ?」と英語で喋ってるのが伝わってきたりとか。
そういった、リアルイベントで楽しめるものが、VRの中で楽しめる。そういう良さがあるなと、すごく感じましたね。ただ課題もあって、イベントに行ってきた感はすごくあって嬉しかったんですが、リアルイベントならそこで遊べますし、作り手と話も出来ますよね。特にインディーイベントの場合は、各ブースにクリエイターの方がいるので、交流できる点もすごく好きなんですよ。
VRでのオンラインイベントだと、そのままゲームは遊べないですよね。ゲームの情報もブラウザとかで見るので、少し距離を置かないといけない。VRの中でインタラクションを作られているブースもあるので、そこは楽しかったんですけど、ゲームの展示会としてはやや離れているもどかしさがありますね。
あと、新しいイベントだからかもしれませんが、展示されている方がブースに立っているのが見当たらなかったので、そこはちょっと残念だなと。もちろん、1週間ずっと立ち続けることなんて出来ないと思いますが。
 |
――VRが持つ課題のひとつだと思うんですけど、VRは現実空間的なものは表現できるし、体験もできますが、そのままやってしまうと現実と同じ面倒くささがある。また、情報量や体験価値としては現実に敵わないという面もあって、要は現実の体験の良さをどう抽出するのかが問われているのかなと。
その抽出について、海外の方ってわりとリアルに「再現しよう!」となりますが、日本だと「いいところだけ取る」みたいな考え方が強いと思います。なので、日本のVRのクリエイターが、いい落としどころを見つけてくれたら面白いんですよね。
吉田氏:
バーチャルマーケットとかVTuberって、日本発で最先端ですよね。
――VTuberって、吉田さん的にどうなんですか?
吉田氏:
自分もVketで女の子のアバターになれて楽しかったんですが(笑)、キャラクターに自分を投影する、あるいは投影されたキャラクターを楽しむというのは、日本人にとってすごく馴染みやすい文化ですよね。
世界で見ると、VTuberを知らない方がほとんどだと思うんですけど、だからこそVTuberの文化をもっと成熟させていけば、漫画やアニメで日本の文化が広がったように、ここもまたひとつの突破口となって、世界に受け入れられるようなタイミングが将来的に出てくるのかなと思っています。
――VTuberも象徴かなと思いますし、さきほどの出版社の件も含めて、日本がもともと持っている文化みたいなものが最新技術と接続したという話だと思うんです。日本独自や固有の文化・コミュニティが最先端の分野とくっつくことで、世界で勝ちうるコンテンツに繋がっていく。そういう可能性というか、将来への期待があるのかなと。
残念ながらそろそろお時間なのでまとめとなりますが、今までの話を振り返って、吉田さん的にインディー市場やインディークリエイターに期待すること、伝えたいメッセージなどはありますか?
吉田氏:
私は本当にインディーゲームが好きで、弊社のワールドワイドスタジオでゲームを作っていた時も──大きなゲームが中心だったんですが──小さいゲームから新しいものが出てくることが多くて、この動きがないとゲーム業界は死んでしまうと思うんです。
それを作り出す新しいクリエイターの登場であったり、経験豊富な方が「実はこれを作りたかったんだ」と世に出していくといった流れが、この日本でもやりやすい環境に少しずつなってきていると思います。
発表できる場や、取り上げていただけるメディア、YouTuberやインフルエンサーの方、あるいは投資をしてくださる企業なども増えてきているので、自分たちあるいは自分が表現したいと思っていたものを世に出して、一歩踏み出して欲しいなと思います。。
商業的に必ずしも成功しなくても、そこで得られるものはすごくあると思うので。世に出すことでフィードバックを得たり新しい人間関係ができて、そういったことがまた次へと繋がります。ぜひ勇気を持って、1歩踏み出していただきたいなと思います。
そして、「PlayStationでもゲームを出したいぞ!」というインディークリエイターの方は、「プレイステーション パートナーズ」 というwebサイトがあり、そこでPlayStationのデベロッパーとして登録していただけます。ここでの登録は法人の方に限られるのですが、たくさんの情報が得られるので、ぜひ登録されてみてください。
――それって、昔のライセンス契約とは違う形なんですか?
吉田氏:
今は、デベロッパー契約とパブリッシャー契約が分かれていないんですよ。今はデベロッパーの方がセルフパブリッシュするようになってますし。それをひとつにまとめた契約を、サイト上でかなり簡単に出来るようになっています。
――今日はありがとうございました。
吉田氏:
ありがとうございました。