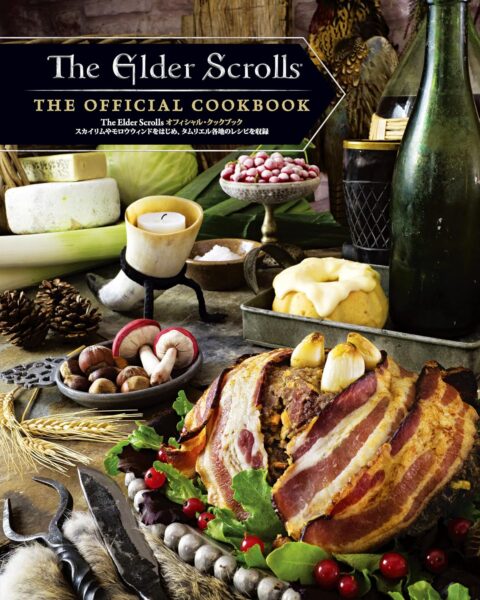富澤氏は企画の発案者でありながら、終始“謎の立場”で関わることに
──ちなみに平尾さんは初めて『ポンポさん』を読んだときに、どう感じたのでしょうか。
平尾氏:
トミーから送られてきたURLを踏んですごくかわいらしいキャラクターがバーンて出てきたとき、「トミーは僕に何を読ませる気なんだ?」と最初は感じましたね(笑)。
だけど、同時に「これはイケそうだな」とも思ったんですよ。
それまでもいくつか監督の依頼をいただく機会はあったんですが、僕の過去の実績の影響でバイオレンスものが多かったんです。それに加えて、作品の詳細を聞いてみると、自分のやりたいテーマとはズレていることが多かった。
なので、「自分が本当に合うと思う作品が来ない限りは絶対にやらない」と決めていたんです。
そんな状況で『ポンポさん』が送られてきたとき、「きっとこれは絵柄ではなくて、自分のやりたいことが描いてあるんだろうな」と思ったんです。
富澤氏:
ちゃんと僕の意図が伝わっていてよかったです(笑)。
平尾氏:
で、読んだら本当に僕のやりたいテーマが描かれていた。主人公のジーンくん【※】に、自分を重ねることができたんです。
さらに、「マイノリティはマイノリティのままでいていい」と肯定するメッセージに溢れている作品でもあって。そこはすごく共感できる部分でもあった。

(画像は劇場アニメ『映画大好きポンポさん』公式サイトより)
最大の決め手になったのは、読み終えたときに、「こういうふうに映像化したら面白いんじゃないかな」というイメージがパっと頭に浮かんだことですね。それですぐさま、トミーに「やろう」と連絡しました。
──ちなみにKADOKAWAなどと話をまとめていくとき、富澤さんはどういう立場だったのでしょうか。
富澤氏:
これがなかなか説明しにくくて。思い返せば、最後まで“謎の立場”でしたね(笑)。
──謎の立場、ですか。プロデューサーというわけでもないんですね。
富澤氏:
そうですね。映画版『ポンポさん』については、本業のバンナムのプロデューサーとしてではなく、ほぼ個人として関わる形になっています。そもそも、バンナムからは出資の形では参加できていませんので。
 |
だから、座組み作りについても完全に手弁当で。専門外のアニメの企画仕事をひとりでこそこそやっている感じだったので、「もしこれが形にならなかったら、誰に土下座するのかよくわからないな」とヒリヒリしていましたが(笑)。
一同:
(笑)。
富澤氏:
結果的には様々なご縁で書籍化を含めて映画の主幹事を買って出てくださったKADOKAWAさんをはじめとした皆さん、自分が信頼を置ける方々にこの作品を託すことができて大変感謝しています。
でもそんな謎の立場だったからこそ、少しでもお手伝いできるところを遊撃手のように立ち回っていた感じですね。クリエイティブ周りでもコミュニケーション周りでも、ご相談を受ければなにか意見を出したり、信頼できる方をご紹介したり。
とはいえ、企画立ち上げ以降で私に出来たことはほんの一握りでしかなく、平尾さんの頑張りと、松尾さんを筆頭とするCLAPの皆さんや製作委員会の皆さんが最後まで粘り通してくださったからこの作品がこうして世に出たのだと思いますので、ただただ感謝しかないです。
特に松尾さんは制作プロデューサーとして平尾さんとのタッグをやり切ってくれたわけですから、このタッグをまたみんなで支援して次に繋がることを心から期待しています。今度こそアラン君【※】みたいにお金を持ってこないと仲間に入れてもらえないと思いますが(笑)。

(画像は劇場アニメ『映画大好きポンポさん』公式サイトより)
「幸福は創造の敵」の意味とは?「みんな幸せだったら、映画なんて見に行かないんじゃないか」
──映画版『ポンポさん』では、「いいシーンを作るためには、大切なシーンでも切り捨てなきゃいけないんだ」というセリフが印象的でした。「幸福は創造の敵」というキャッチコピーとも重なるテーマにも思えるのですが、平尾さんの内面と重なるところがあったのでしょうか。
平尾氏:
「幸福は創造の敵」というセリフ自体は原作者の杉谷さんが考えられたもので、そこにインスパイアされた部分は大きいですね。
「本当に表現したいもののために、大切なものでも切らないといけないときがある」というテーマは、自分の当時の心境や、作品としてどう見てほしいかといった思いがリンクして出てきたものだろうな、と思っています。
──その平尾さんの思いがどういうふうにリンクしたかについて、もう少し詳しく聞かせていただけますか。
平尾氏:
ものづくりをしていると、やっぱりどこかで何かについて深く考えていかざるをえなくなると思うんです。それは同時に「自分は何を作りたいのか?」と、自分自身を深く見つめなおすことにもつながっていく。
そうなったとき、何かどうしてもやりたいことがあったとして、そのために何も捨てないままで、本当にやりたいことを成し遂げられるんだろうか?と疑問に思ったんです。
 |
映画を作る過程は必ずしもハッピーなことばかりではないし、表現したいシーンのためには、どれだけいい絵が撮れていても切り捨てないといけない。でも、それって人生も同じなんじゃないかと。
僕が今ここにいるのは、自分がある選択肢を選んで、もう一方を切り捨ててきたからですよね。でも、その都度どっちを取ったのかは紛れもなく自分自身ですし、絶対に他人のせいにはできない。
「幸福は創造の敵」とは、そのことを言っているんだと思ったんです。そして、僕自身にもその言葉はとても響くものだった。
同時にこれは、「ものづくりをしていない人にも伝わるメッセージだ」とも感じたんですよ。
──『ポンポさん』はとりわけ創作やものづくりに関わる人からの評判が高い作品でしたが、平尾さんはそこからさらに普遍的なものを感じ取ったわけですね。
平尾氏:
そうですね。決してものづくりに限った話ではなく、何かやりたいことがあって、何かを手に入れようとしたら、必ずどこかで決定的な選択を迫られる時がくる。『ポンポさん』を観たことで、その時が来たときに背中を押してあげられるような映画にしたいなと。
──「何かを得るために、何かを犠牲にする」と言うとネガティブな意味合いに聞こえますけど、『ポンポさん』ではまったくそんなニュアンスはないですよね。
平尾氏:
その通りですね。『ポンポさん』って「選択」を不幸な意味合いで捉えていないんですよ。選択はつねに切り捨てを伴うけれども、それは「本当に大事なものを諦めないための選択」なんです。
選択をこのように捉えることができたら、いざ決断をしないといけないという時に、勇気が湧いてくると思うんですよ。
富澤氏:
平尾さんから原作にない追加シーン案をもらったときに、まさにその「諦めないために諦める」という言葉が出てきた時点で、僕はもう「これこそが平尾さんだ」と思って(笑)。
 |
平尾氏:
ありがとうございます(笑)。
富澤氏:
このテーマは、僕の人生にもピッタリ当てはまるものでした。
とはいえただ闇雲に「諦めなければダメ」と言いたいわけではないんです。もちろんクリエイティブにはいろんな形がありますし、「俺は全てを諦めないままに、最高のクリエイティブをやってやるぜ」という考えも全然アリだと思います。
それでもやっぱり、今まで切り捨てて切り捨ててやってきた、あるいは切り捨てざるを得なかった、これしか選べなかった人たちに向かっても、「それでいいんだよ」と言ってあげたい、あるいは言ってほしい、とも思うんです。
仮にそう言ってあげられたとして責任が取れるわけではないんですが、やはり多様性を認めつつも、「何かひとつを選ばなければ芸術や集団作業はままならない」というひとつの真実はお伝えしたいなと。
平尾氏:
結局、「映画って何のために観に行くんだろう?」と思ったことがあって。多分みんな幸せだったら、映画なんて観に行かないんじゃないかって思うんですよ(笑)。
何かしら満たされない渇望があったり、現実には足りない何かを補うために観に行くっていう部分は大きいと思うんですよ。そのうちのひとつが「幸福」であってもいいんじゃないかなっていう気はしますね(笑)。
富澤氏:
「幸福は創造の敵」というキャッチコピーを見て観に行く人が何を思って見に行くのかというのは、かなり限定される気もしますが(笑)。
まあ、宣伝する側もある程度覚悟を持って客層を絞っている側面もありますよね。なにしろもうひとつのキャッチコピーは「映画を撮るか死ぬか」だから。
一同:
(笑)。
人間関係をとるのか、それとも作品をとるのか
平尾氏:
ものづくりをしていると、人を傷つけてしまうことも多々あって。特にアニメーションは集団作業ですから、だめな場合はしっかりと否定しなきゃいけない場面も出てきます。
そうしていくうちに縁が離れていく人もいれば、繋がり続ける人もいる。それを繰り返していると、「縁が離れた人を追いかけても仕方ない、いま繋がってる縁を大事にしよう」という考えになるんですよね。
──やっぱり、「こだわり」って対立も生んでしまうところがありますよね。
平尾氏:
そうですね。お互い表現したいものがある場合は、必ず衝突がありますね。でも、「なんでもいいよ」と言われちゃうとそれはそれで少し寂しいんですけど(笑)。
 |
──たしかに衝突しちゃうのって、お互いにこだわりや譲れないものがあるからですもんね。そこを突き詰めていけば突き詰めていくほど、壊れるものも大きいというか。
平尾氏:
人間関係をとるのか、それとも作品をとるのか(笑)。
一同:
(笑)。
平尾氏:
意見がぶつかった時に少しでもこっちが譲歩すれば、人間関係を守れることもあるかもしれないですが、それで本当に一番大事な作品の根幹になる部分を妥協していいのか?となったときには、どっちを選択するかは難しいですよね。
僕の場合はその選択をしてきたからこそ、人に嫌われた部分があると思います。でも、結果的に作品が良いものになったときに、「あれだけ言い合ったけど、良かったよ。また誘ってよ」と離れた方が戻ってきてくれることもあるんですよね。
だからやっぱり、この職業に関しては人間関係も大事なんですけど、結局のところは作品で語るしかないとは思っています。
富澤氏:
「どっちが面白いか」という選択を積み上げていった責任のありかって、作品そのものなんですよね。あのときの考えとは違ったけど、「ここにあるものは美しい」と思えるのであれば、クリエイターだったら認めざるを得ないというか、認めたくなるものだと思います。
そもそも全員が同じことを考えて同じようにすることなんてあるわけがないし、いくら企画書がスムーズに書いてあったとしても、やっぱりズレは最後の選択にまで起きてしまうものです。でも、監督という立場は選ばせてもらうからこそ責任があるものとも思うので。
そんな選択の連続のなかで、平尾さんは最後まで意見を貫いているから、戦った相手も作品には満足してくれていると思いますよ。
それは『ポンポさん』でも『GOD EATER』でもそうだったと思うんですけど、そうやって貫き通したからこそ、今では清々しい思い出になってますし(笑)。
平尾氏:
清々しかったかな(笑)。
富澤氏:
いや、本当にそう思いますよ。たとえば途中で平尾さんが折れちゃって、「意味なかったじゃん」となってしまうのが一番つらいことなので。
決めて選んで、大切なものを切っていくのを最後までやりきることって本当にしんどいことだと思います。切られる側も支える側も、お互いにその選択への想いを抱えながら、少しずつ完成に向かっていくというのが、制作現場のリアルなんだと思います。
平尾氏:
あれもこれも、なかなかスマートにはいかないものなんですよね。アニメや映画に限らず、ゲームの現場もそうだとは思いますが。
 |
映画版『ポンポさん』には、平尾監督自身の感情が高いシンクロ率で投影されている
──映画版『ポンポさん』には、平尾さん自身の投影があるんでしょうか。
平尾氏:
作品を作るときって、多かれ少なかれ自分自身を投影してしまうものなんじゃないかなと思います。とりわけ僕の場合はどうしても入ってしまう方なので、そこは作る前に話をさせていただいていますね。
とはいえ、今回の『ポンポさん』は自分と波長がすごく合っていたと思うんです。これはトミーがもってきてくれたおかげもあると思いますが。
その話で言うと、アニメ版『進撃の巨人』を監督した荒木(哲郎)くんにも『ポンポさん』を見てもらったとき、彼はずっと「シンクロ率が高い」と言っていました(笑)。
一同:
(笑)。
富澤氏:
やっぱり監督をされると、そういうことがあるんでしょうね。向き合う作品に対して、自分をどう合わせていくのか、乗せていくのかというのは絶対に考えないといけないところですよね。機械的に映像化しているわけじゃないし。
平尾氏:
そうですね。他の監督さんたちも感情を乗せて作品を表現されていると思うので。
──いま平尾さんがおっしゃったように、クリエイティブなものって、作画や演出みたいにテクニカルな良さがある一方で、そういう「上手さ」とは違う、人間的な感情や気持ちに訴える部分があるじゃないですか。
そこの重要さってどういうふうに捉えているんでしょうか?
富澤氏:
どう気持ちをのせていくかってことですかね?
──そうですね。テクニック面が稚拙でも、感情に訴える場合ってけっこうあると思っていて。必ずしもテクニカルな良さだけが、作品の良さではないんじゃないかと。『ポンポさん』を観たとき、その「感情に訴える」感じが印象的だったんです。
最初に富澤さんから『ポンポさん』の件を紹介されたときも、普通の「知り合いが作ったので観てみてください」みたいなのとは雰囲気がちょっと違うというか、ただならぬ気配を感じたんですよ(笑)。
富澤氏:
あー、TAITAIさんにご紹介したときですね。きっと僕もそこに過剰な気持ちが乗っていたのだと思います(笑)。
平尾氏:
この答えが正しいかどうかわからないんですけど、作る側も観る側もみんな、登場人物のキャラクターを見ているんです。
『ポンポさん』の劇中で「君の映画に君はいるかね」というセリフがあるんですが、映画のなかに自分を見つけることができたときって、きっと「その映画がその人だけのものになる」瞬間だと思うんです。
だから、自分が作る側になったときに人に何かを伝えられるかどうかって、自分の気持ちを込められるかどうかにすごく大きく左右されるんじゃないかな。
 |
その作品を撮る監督さんもキャラクターと同じ感情に近い体験はあるはずで、だからこそ、アニメとしては絵がただ動いているだけかもしれないけども、見ている人にはキャラクターが行動しているように伝わるんだと思うんです。
もちろんその感情を伝えるためのテクニックの上手さがあるからこそ伝わる、ということもあるんですけど、「まず先に何を伝えたいのか」を体現するものがキャラクターなので、それがしっかりしてないと何を言っても嘘くさくなっちゃう。
だから正直、僕にとってテクニカルなものは、ストーリーを伝えるための手段でしかないんです。ただ、そこにちゃんとキャラクターが生きていて、そこに感情が乗っているか、それがきっちり描かれているか、そこに大事なものを乗せられているかどうかじゃないかなと思っています。
富澤氏:
4年の制作期間の中で、そういう想いを絶やさず燃やし続けながら作品に落とし込んでいくことのすさまじさって、もはや恐ろしいぐらいですよ。
たとえば僕の本業のゲーム制作ですと、最近の現場は、かなりシステマティックに、制作過程から仕上げまで、分業するのが基本なんです。そこではどうしてもアニメのようなキャラクターの熱量が表現しにくかったり、ユーザーのプレイ上の感情とのバランスやコントロールなども必要なので、どうしても流れで見ると平熱化しがちだったりする。
だから、今回『ポンポさん』の制作で見たような、個々人の思いが繋げている統合性から生まれる美しさや豊かさみたいな、ゲームだとなかなか出せない部分はとても羨ましく思います。
 |
「これは君が見たい作品になっているか?」
──平尾さんから見て、今回のプロジェクトに対する富澤さんの動きはどう見えていたんでしょうか。先ほど、富澤さんは「謎の立場」とおっしゃっていましたけども。
平尾氏:
僕はトミーのことは「発起人」だと思っているんです。今回の映画は、トミーが「『ポンポさん』を映画化しよう」と声をかけてくれたところからスタートしているので。
ポンポさんも映画のなかで言っていましたけど、「誰のための作品なのか?」と悩んだとき、いちばんの拠り所になるのはそこなんだと思います。つまり、トミーが「僕の作品を見たい」と言ってくれたこと。
だから、たびたびトミーには「これは君が見たい作品になっているか?」と相談して。それはすごく支えになりましたし、作品の指針にもなったと思います。
富澤氏:
そんな責任の重いことを定期的に言われたら……(笑)。
一同:
(笑)。
富澤氏:
でも実際、全力で向き合うつもりでしたし、平尾さんから都度そう言ってくれるのは僕にとっても喜びでした。まあ、突然「曲作りのための仮歌詞を考えてくれ!」と言われて徹夜で作詞したりとか、いろいろと大変なこともありましたけど(笑)。
とはいえ、平尾さんのサポートを十分やりきれたか、と言われるともっといろいろやれることはあったなと思います。大人の事情もあって、本業そっちのけで全力投球というわけにはいかないところもありましたし。
でも、平尾さんが迷ったときや、大事なときに声をかけてもらえて、僕の言葉を頼りにしていただいたのは本当にありがたいことですし、僕の役目は最低限果たせたのかなとも思います。
 |
でも、アイディア出しについてはちょっと反省しているところがあります。僕の感性って明らかにマイナー側なので、自分の好みを入れ過ぎちゃうとマイナーに寄っちゃうんですよね。
だから、本業でのプロデュース作品では自分の好みを入れる割合は2%ぐらいなんですけど、『ポンポさん』は15%ぐらい入っているんです(笑)。
一同:
(笑)。
富澤氏:
ちょっと危ないんですよね(笑)。
「ここまで言っちゃうとまずいかも」と自分なりにバランスを取ってはいたんですが、やっぱり思い入れが強いぶん、自由に言っちゃうことが多かったと思います。
平尾氏:
もちろん、脚本なんかは大勢の方との打ち合わせで決めていくので「最終的にどうするのか」のジャッジは自分がさせていただきました。
でもやっぱり、この映画はトミーが最初に発起人として「やりたい」と言った企画でもある。最終的に違う意見を採ったとしても、僕としてはその点をなるべく大事にしようと思って。だから大丈夫ですよ(笑)。
 |
──ちなみになんですが、富澤さんは映画版『ポンポさん』にクレジットはされているんでしょうか?
富澤氏:
「スペシャルサンクス」の筆頭に載せていただいていますね。エンドロールに「発起人」なんていう謎のカテゴリーはないんです(笑)。
一同:
(笑)。