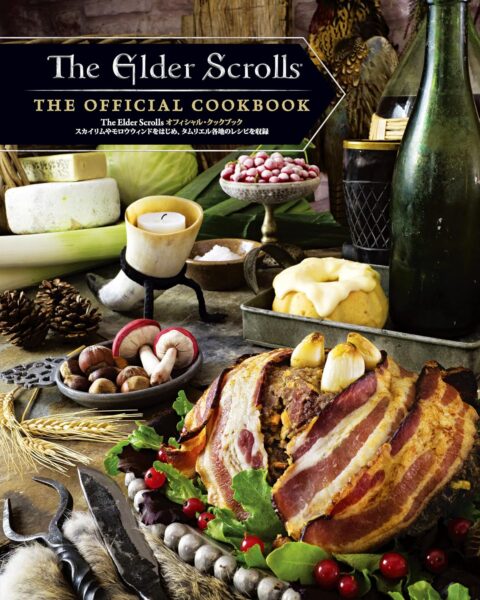かわいらしい絵柄に、映画への情熱、そしてすべての“モノを作る人々”へ向けられたメッセージ性──2021年6月4日に公開された劇場アニメ『映画大好きポンポさん』が、各所で話題となっている。
モノ作りに携わる人間の目線で描かれた、仕事への情熱や苦悩、直面する数々の問題。見る人が見れば──いや、多くの人間がなんらかの形でぶつかるであろう葛藤を、ストレートに表現している本作の内容が、そうした熱っぽい口コミを生み出しているのだ。
実際、本作には、その映像としてのクオリティの高さもさることながら、どこか私小説的な雰囲気を帯びた、独特の雰囲気がある。作り手側の気持ちというか、情念みたいなものが随所に滲み出ており、何かちょっと、ただならぬ雰囲気が感じられる”匂い”があるのだ。
──これは、いったいどういういった作品なんだろうか?
好奇心が刺激されるままに、今回電ファミでは、本作の監督を務めたアニメーション作家・平尾隆之氏と、『テイルズ オブ』シリーズのプロデューサーを務める富澤祐介氏のお二人に話を伺った。

ここでなぜ、映画と関係がない富澤祐介氏の名前が出てくるのだろうと思われるかもしれない。しかし、取材を進めると分かってくるのだが、実は彼こそが、「ポンポさん」の劇場版に向けて、大きな原動力となったキーマンでもあった。
二人は、『GOD EATER』【※】というゲーム作品を通じて知り合い、一緒にモノ作りを経験した戦友でもある。

(画像はAmazon | GOD EATER(ゴッドイーター) – PSP | ゲームソフトより)
しかし、乾坤一擲の気持ちで取り組んだアニメ版『GOD EATER』はさまざまな苦難に見舞われ、残念ながら不振に終わってしまう。ほどなくして平尾氏は、自身が所属していたufotableも退社。
「もう、監督は二度とできないかもしれない」
そんな大きな挫折感を味わいながらも、当時、平尾氏が最初にコンタクトを取った相手が、だれあろう富澤氏であった。とある居酒屋で、たった二人。
「僕のプロデューサーになってくれないか」
何を思ったのか、平尾氏はそんな言葉を口にする。本業がゲームプロデューサーである富澤氏は、アニメの専門家でもなければ、アニメ業界に対して強い伝手があるわけでもない。当然、その平尾氏のお願いには、すぐに応えることはできなかった。
しかし。その時の言葉が、富澤氏の心に深く刺さり、後に氏の行動が『映画大好きポンポさん』の映像化への起点となり、原動力になっていく。
そう。本作が作られる過程は、ふたりのクリエイターの逆襲の物語でもあったのだ。
今回のインタビューでは、そんな二人の出会いやことの経緯、なぜ『映画大好きポンポさん』というネット上の漫画がいきなり劇場アニメ化されるという話に至ったのか? どんな気持ち、モチベーションで本作の制作にあたったのか?など、さまざまなことを聞いてみた。
彼らの、悩みながらも、なんとか形にしようをもがく様子や、相手の期待に応えようと動く様は、どこか劇中の登場キャラクターたちとも重なるところがある。本稿では、作品の「奥」にある、情熱の正体をぜひ届けられればと思う。
『GOD EATER』をきっかけに出会ったふたり
──まずはおふたりの出会ったきっかけや関係性について、順を追ってお聞きしていければと思います。
富澤氏:
平尾さんと初めてお会いしたのは、私がバンナムで『GOD EATER』の企画を立ち上げているときでした。当時はまだ平尾さんがufotableに在籍していたころですね。
そもそも、『GOD EATER』は当時のバンナムの社長に「これからはアニメーション作ってYouTubeで流して100万再生させるんだよ!」と言われて。
当時は無茶ぶりだと思っていたんですが、今思えば、あれは正しい視点だったと思いますね。プロモアニメの立ち上げ当時は2008年ごろで、動画サイトやSNSも黎明期だったような時代です。
 |
『GOD EATER』という作品は完全オリジナルIPで、いわゆるハンティングゲームだけどウェットな物語性やキャラクター性が肝となっていて、独自のポジションを築けるかもしれないと社内で熱くなっていました。
キャラクターデザインやシナリオは頑張ったけれど、もうひとつ武器が欲しい。そこで「プロモアニメを作ろう」という話が立ち上がったんです。
※2010年公開のPSP用『GOD EATER (ゴッドイーター)』のプロモーションアニメ(Youtube)。
──確かに『GOD EATER』は独自の路線を進んでいたという印象はありますね。
富澤氏:
それで人づてにufotableというアニメ会社を紹介してもらって、「とにかく行ってみよう」という形でお邪魔しました。そこでプロモアニメ版『GOD EATER』の企画を説明してご紹介いただいたのが平尾さんだった、というわけです。
平尾氏:
もうそんな前になりますか。
富澤氏:
アニメの流儀も知らなければ、コスト感もスケジュール感も分からないまま、ゲームの素材だけを持って「作りませんか」と突撃していたので最初は怒られましたね……(笑)。
──富澤さんから見て、平尾さんの第一印象ってどんな感じだったのでしょうか。
富澤氏:
その当時、平尾さんは『劇場版 空の境界::第五章 矛盾螺旋』【※】の製作をちょうど終えたころでした。初めてお会いしたとき、「もう今は、厨二的なものって求められてないと思うんですよね。」って言われてすごくびっくりしたんですけど、覚えてますか?

(画像はAmazon | 劇場版 「空の境界」 矛盾螺旋【通常版】 [DVD] | アニメより)
平尾氏:
覚えてますよ(笑)。
富澤氏:
真正面からそう言われて、「その発言こそが厨二的では」と心の片隅で思いましたね(笑)。
一同:
(笑)。
平尾氏:
恥ずかしいですね……(笑)。
 |
富澤氏:
こんな感じで出会って、「ナイフみたいに切れ味がある人だな」というのが第一印象ではありましたが、演出もアニメーションもキレキレだったので、アニメという切り口で『GOD EATER』を作っていただければ、絶対に良いものができるだろうという確信はできていました。
平尾氏:
そうだったんですね。
富澤氏:
「こんなスケジュールで作れるわけないじゃないですか!」とか「アニメの作り方知らないでしょ!」みたいなバチバチのやり取りもあったんです、でも、平尾さんに真正面からそう言ってもらったおかげで、僕自身がアニメーションと本気で向き合う覚悟もできたんですよ。
平尾氏:
いやあ、あの時は強く言ってしまって申し訳ありませんでした(笑)。
富澤氏:
おかげさまで『GOD EATER』という作品は、作中アニメのクオリティも話題になり、アニメに近い文脈を持つゲームとして10年以上に渡って作品を作り続けることが出来ました。そこに関しては本当に感謝しています。
乾坤一擲のアニメ版『GOD EATER』は不振に終わり、平尾氏はufotableを離れることに
──それを経て『GOD EATER』テレビアニメ化の話が出てくるということですね。
富澤氏:
そうなんです。平尾さん達と『GOD EATER』の5周年を迎えるタイミングでテレビアニメ【※】に挑んだんですよね。ただ、さまざまな苦難に見舞われることになりまして……。

(画像はTVアニメ『GOD EATER]』公式サイトより)
──あのゲームをアニメに落とし込むのはなかなか大変なように見えますよね……。
富澤氏:
まず、「主人公不在のゲームのアニメ化」という難しさがかなり大きかったと思います。あとはデザイン面。巨大な変形武器「神機」を全員が持っていて、作画コスト的には「人がガンダムを持って戦っているようなもの」と揶揄されたものでした。それに加えて、平尾さん初のテレビシリーズという期待、新しい表現を模索するクリエイティビティへの挑戦というさまざまな要件が絡みあって。
平尾さん自身がすごくこだわってくださって、全話で脚本・絵コンテ・監督・音響をひとりでこなすことになるんですけど、これが結果としてスケジュールの破綻に繋がってしまい……。残念ながらテレビ放送コンテンツビジネスとしては決して成功とは言えない結果になってしまいました。
──『GOD EATER』ゲーム本編のオープニングアニメではお互いに良いものが作れたんですよね。でもテレビアニメになったときに、何かズレみたいものが生じたんでしょうか?
平尾氏:
トミー(富澤氏)が先ほど言ったように、「主人公を作らなきゃいけない」ことが大きな課題でした。
その主人公をどのようにシナリオに組み込むのか、どういったテイストにするのかをあれこれ考えていくうちに、「最終的に何を描くのか」「テーマをどうするか」という答えがなかなか見つからなくて。放送が近づいてきているのに、脚本がなかなかOKにならなかったんですよ。
 |
もちろん僕自身の実力不足やこだわりが強すぎたせいでもあるんですけども、 どんどん時間は無くなっていき、申し訳ない事態になってしまって……。結果的には、「『GOD EATER』は命のバトンを繋いでいく話なんだ」というテーマを見つけることができたんですけど、もうその時には放送が差し迫っていた。
でも、あの時TVシリーズ『GOD EATER』に関わってくれた方々はどんな状況になっても、なんとか作品を良いものにしようと粘ってくれて。そこは本当に感謝しかないですね。
良い挿入歌を持ってきてくれたり、11話以降の脚本を一緒に考えてくれたりと、トミーにもいろいろ迷惑をかけました。
富澤氏:
高円寺のホテルメッツに泊まって一緒にやりましたね(笑)。
平尾氏:
そういう現場レベルでの協力って、本来であればプロデューサーの立ち位置にいる人がやることではないと思うんです。だから、あのときは本当に助かりました。
当時は僕の不甲斐なさから現場の支援が得難い状況だったので、すごく嬉しかったんです。
もちろんメインスタッフは「これは面白いものだ」と信じてついてきてくれたんですけど、やっぱり会社の雰囲気みたいなものはあるじゃないですか。それこそ四面楚歌じゃないですけど(笑)。
富澤氏:
じつは、ウチも内部ではそんな感じでした(笑)。
一同:
(笑)。
平尾氏:
「おそらくそうだろうな」とは思っていたんですが、申し訳ない……。
 |
富澤氏:
僕にとっても、テレビアニメ版『GOD EATER』は大きな反省点になりました。平尾さんはもちろんですが、僕自身もたいへん悔しい思いをしました。関わってくれたたくさんのスタッフやファンの皆さんにも申し訳ない思いもあったので、スケジュールは破綻してしまったとしても、作品としては表現したいことを最後までやり遂げることが何より大事と思って12話までご一緒しましたし、結果として終盤の3話にこの作品の思いというものが強く宿ったのではないかと思います。
そんなこんなで制作は大変でしたが、だからといって「平尾さんともう仕事したくない」とは思いませんでした。
──それはどうしてなのでしょうか。
富澤氏:
平尾さんは、どんな状況でもこだわりを貫く方なんです。僕自身も似たタイプなので、共感できるところが多くて。
ただ、一方でプロデューサーの目線から見ると、企画と人というのはマッチングも非常に重要だということもこの10年で強く気づかされたことです。
だからテレビアニメの『GOD EATER』が平尾さんのこだわりに対して、本当にマッチしていた作品だったのか?という部分は検証しないといけない、という思いがありまして。そう考えていくうちに、「平尾さんともう一度映像作品を作りたい」という思いだけは、明確に残ったんですね。
それがバンナムの仕事になるかどうかは、「ぶっちゃけどっちでもいいや」というぐらいの気持ちでした(笑)。いったんビジネス的な縛りからは自由になって、「平尾さんがモノづくりで輝いてくれる題材があれば、正解なんだ」と勝手に思いながら、2016年あたりから「何かネタがあったらやろうよ」と、ふたりでたびたび話していました。
平尾氏:
僕がufotableを出ることになったとき、すぐトミーに電話して高円寺の飲み屋で会ったんです。
そこで「また一緒にやりたいんだ!」とその場でオリジナルのアイディアを話したりしたのは覚えています。そこからトミーとはちょこちょこ会うようになって、『君の名は』【※】の試写会にも誘われて、一緒に見に行ったりしたんですよ。

(画像は映画『君の名は。』公式サイトより)
で、それがすごくよく出来ていた。間違いなくヒットするだろうな、という予感がしたんですよ。その時エンドロールにヒットメーカーの川村元気さん【※】の名前を見つけて「なるほど」と。
トミーもそれを知っていたのか、見終わったあと、お互い無言のまま、ガード下の居酒屋に入っていってちびちびお酒を飲んでいました。
※川村元気
『君の名は。』や『天気の子』をはじめ、『告白』や『モテキ』、『何者』などヒット映画を数多く手掛けた敏腕プロデューサー。脚本や映画監督も務めるほか、小説家・絵本作家としても活動しており、著書に『世界から猫が消えたなら』『億男』『ふうせんいぬティニー』シリーズがある。
富澤氏:
そのとき、平尾さんに言われた一言がずっと自分の心に刺さり続けていたんです。
平尾さん、覚えています?「僕のプロデューサーになってくれないか」って言ったこと。
平尾氏:
覚えていますよ(笑)
富澤氏:
こっちとしては「ん?今、俺と結婚してくれ」って言った?みたいな重さの受け取り方をしたんですよ!(笑)
 |
平尾氏:
(笑)。つまり、波長の合う部分がありながら、違う視点を持っている者同士が組めば、面白いものが作れるんじゃないかと。自分にとってはそれがトミーなのではと思ったんですよね。
富澤氏:
『君の名は。』を観に行った時は本当にお互いに「これは悔しいな」と感じていましたね。そういう出来事を経つつ、何か一緒にできるきっかけを探していました。
ゲームの企画でいい機会があればよかったんですけど、当時ちょうど僕も『テイルズ オブ』シリーズのプロデューサーを担当し始めたころだったのもあったのですが、手元の企画をそのまま平尾さんにもっていくのが正しいかどうかはわからなくて、悩んでいました。
何かいいものがないかなっていうことを悶々と1年ぐらいお互い考えていました。で、ここからやっと今日の本題に入ります(笑)。
平尾氏:
『映画大好きポンポさん』ですね(笑)。
「とにかく、この作品にぴったりの監督だけは押さえているから映画にさせてくれ!」
──ちなみに、富澤さんは『ポンポさん』以外に平尾さんに提案したものって他にあったりしたんですか?
平尾氏:
いえ、『ポンポさん』だけでしたね。ある日突然LINEで送られてきて(笑)。
富澤氏:
pixivで原作を読んだとき、「コレだ!」と思ってまっさきに平尾さんにURLを送ったんです。
僕の脳内には「平尾さんだからこそできる」というフォルダーがあるんですが、なかなかピッタリ入るものってなかったんですよ(笑)。半端なものを持っていっても、平尾さんの大復活にはならないと思っていましたので。
──映画版『ポンポさん』のそもそもの起点は富澤さんだったんですね。
富澤氏:
そうなんです。正直に言って、『ポンポさん』は本当に自分の物語であり、かつ平尾さんの物語でもあるはずだ!って直感したんです。「この作品をうまく映像化できるのは、絶対に平尾さんしかいない」と。
 |
正直言って座組も制作スタジオも何も決まっておらず、あるのは平尾さんというこの作品にベストマッチする監督だけという状態でした。それでも、平尾さんは「やってみたい」と言ってくださったので本当に良かったです。
平尾氏:
その時はまだ杉谷さんにも会ってなくて、製作委員会も立ち上がっていなかったですから、どうなるかわからなかったけど。
富澤氏:
そんな状態で“思い”だけ押さえさせてもらって申し訳ない(笑)。
まずは企画書作って、座組を組んで出資者を集めたりしてから、原作者さんにお伺いを取って……というのがふつうのやり方なんですけど、そんなことをやっていたらとても時間がかかってしまう。うかうかしているうちに、どこかに映像化の権利が取られてしまう!と思って。
その時点で即、『ポンポさん』の版権を管理している大阪のプロダクション・グッドブックに飛んだんです。「とにかく、この作品にぴったりの監督だけは押さえている」とだけ話して(笑)。
──すごい行動力ですね(笑)。
富澤氏:
そこで原作者の杉谷先生とお会いして、「『ポンポさん』を撮らせたい監督がいるので、原作をお預りさせてください」とお願いしました。
なぜかゲーム会社のプロデューサーが突然手土産もなくお願いに来たのですから、先方からしたら本当に訳がわからない状況だったと思います。今思い返せば、よく僕を追い返さずに話を聞いてくださったものだと……(笑)。
──本当に突然ですけど、どうやって話が進んだのでしょうか。
富澤氏:
まず、打ち合わせで先方のプロデューサーである溝部さんはこうおっしゃられました。「すでに『ポンポさん』の書籍化のオファーが10社以上来ている。だが映像化の話は君が初めてだ。もし映像化するなら、どの出版社と組むべきだと思う?」って。
これは当然の質問だと思います。メディア展開を行うなら統一の取れたアライアンスが重要になりますから。
 |
映像化の際の座組みに出版社が含まれるのは今や当然のことです。要するに溝部さんの質問は「君はどんな座組みを組めるのか?」というプロデューサーとしての本質的な質問でもありました。
もちろんそうした質問をいただくことは想定していましたが、その時の僕の答えは、「座組みはこれから東京に帰って考える。出版社への提案も含めて、必ずベストな座組みを組むから預からせてほしい」という茫洋としたものでした。
──それでも結局、富澤さんの熱意が通じたということなんですね。とはいえ、当時は内心ヒヤヒヤだったんじゃないでしょうか。
富澤氏:
そんなことなかったんですよ。半ば呆れられながらも関西空港まで送ってもらっている車中で、全く不安は無く、ウキウキしながら東京に帰ったのを覚えています。自分の中では光り輝く瞬間に一歩近づくイメージでいっぱいだったんです(笑)。
──そこからは映画化に向けてどういう過程を踏んでいったんでしょうか?
富澤氏:
座組みについては、書籍を担当してくれたKADOKAWAさんを主幹事としながら組んでいきました。僕の知人にも声をかけて、プロデューサーとして参加してもらったりもして。
映画のプロジェクトはモノによっては数年かかるんですけど、『ポンポさん』もそれなりの時間をかけることになりましたね。
 |
平尾氏:
座組みについては、本当に「縁に救われた」というところが大きいですね。
『ポンポさん』の話が出たとき、ちょうど僕は小説を書いていて、そのつながりでKADOKAWAの方を紹介することができた。また、同時期にMADHOUSEの同期だった松尾さんがCLAPという制作会社を立ち上げたばかりで、ちょうど作品を探していたところもあり。
『ポンポさん』は、そんなふうに自分たちの持てる限りの縁が、偶然ひとつずつ繋がっていって成立した作品なんです。
だから、今回集まってくれた方々がみんな原作も含め『ポンポさん』を好きでいてくれているのが本当に嬉しいですね。