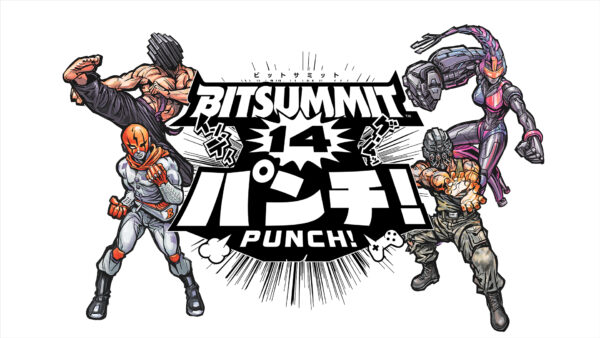「人狼ゲーム」が日本のテレビ番組や実況配信で取り上げられ、一大ジャンルとして定着してからはや数年。現在、新たに『Project Winter』や『Among Us』が登場し、デジタルの分野でも人狼ゲームが世界的な活況を博している。
人狼に代表される「正体隠匿系ゲーム」の流行は一過性のものではなく、もはやアナログ/デジタルの分野で「RPG」のような人気ジャンルとして定着しつつあると言ってもいいだろう。
こうしたブームのなか、「正体隠匿系ゲームをデジタルゲームにどのように落とし込むか?」、「どうしたらそれに触発された新しいゲームを作り出せるのか?」というアイディアの模索は、人狼に魅せられた多くのゲームクリエイターにとって共通のテーマだったはずだ。
 |
今回、電ファミニコゲーマーでは、KONAMIから今年4月に発売された異色のオンライン対戦型の正体隠匿系ゲーム『CRIMESIGHT』(以下、『クライムサイト』)のプロデューサーである長田毅志氏と世界観監修を担当したイシイジロウ氏、さらに『グノーシア』を制作したプチデポット代表の川勝徹氏をお呼びして、鼎談をお届けする。
KONAMIの『クライムサイト』は「対戦ミステリーシミュレータ」と銘打たれており、未来の世界で作られた仮想空間上にある洋館のなかで、キャラクターに指示して「これから起きる殺人事件」を未然に防ぐ/達成するという新感覚なゲームだ。
一方で『グノーシア』は、AIキャラクターたちと実際に人狼ゲームで対戦しつつ、同時にストーリーが進行するゲームで、クオリティの高さと人狼ゲームとアドベンチャーゲームの融合は多くのプレイヤーを驚かせたことは記憶に新しい。
 |
本記事では発売したばかりの『クライムサイト』の制作背景を聞きつつ、人狼ゲームはどうしてここまで人を魅了するのか、そして正体隠匿系ゲームにはどのような可能性が秘められているのか大いに語っていただいた。「人間味」や「ハプニング」などといった刺激的な考察の数々を、ぜひご覧いただきたい。
聞き手/TAITAI、福山幸司
文/福山幸司
編集/ishigenn
プランナーから「人狼ゲーム」のプロデューサーへ
──今回、『クライムサイト』の世界観を監修されたイシイジロウさんの自己紹介は割愛させていただきまして、長田さんと川勝さんから自己紹介していただければと思います。
長田毅志氏(以下、長田氏):
『クライムサイト』プロデューサーの長田と申します。今回の『クライムサイト』では、初のプロデューサーとなります。イシイさん、川勝さんという大先輩のお話を聞けたらなと思います。よろしくお願いします。
川勝徹氏(以下、川勝氏):
プチデポット代表の川勝徹と申します。プロデューサー、ディレクター、プロモーションマネージャーなどを兼務しておりまして。『グノーシア』をはじめ、4人でどこまで世界に向けてゲームが作れるか挑戦しています。よろしくお願いいたします。
──『クライムサイト』と『グノーシア』は、どちらも「人狼」というアナログなコミュニケーションゲームをモチーフにしています。「人狼をいかにしてデジタルなものに落とし込んで遊びにしたのか」が今日お聞きしたいことです。アナログとデジタルの関係や、人狼の面白さとは何か。
ただ、その前に長田さんがどういう経歴や文脈を持った人なのかを、ちょっとお聞きしてみたいなと思います。まず、おいくつなんですか。
長田氏:
世代的にはアドベンチャーゲームブック、パーティジョイ(ボードゲーム)、ファミコンときて、そこからデジタルゲームの世界にドハマリした感じですね。
──プランナーとしてKONAMIに入社したんでしょうか。
長田氏:
はい。プランナーとして中途でKONAMIに入社しました。 プランナーというと、ゲームシステムやゲームステージの作成、バランス調整等を行ってゲームを面白くする役割なんですが、今回は売り側の視点も考えなくてならないプロデューサーという役職をいただきました。
──ただ、長田さんは本作に関してはプロデューサーだけでなく、ゲームシステムのほうも作られていますよね。
長田氏:
『クライムサイト』のほうは、企画の立ち上げ時点から私自身がプランニングして開発して、初期の方はゲームディレクションを行った上で、形が見えてきた段階でディレクターは別の方にお任せしました。そこからプロデューサーとして売る方向に考えをシフトしていった感じですね。
──自宅にボードゲームを300個くらい持っていらっしゃるとか。
長田氏:
そうですね。電車のなかでアナログゲームの取扱説明書だけ読んで想像して遊んだり(笑)。

「ボードゲームの日本普及」と「人狼の人気確立」を振り返る
──アナログゲームとの出会いはどのあたりなんですか?
長田氏:
幼少期には『人生ゲーム』とか『パーティジョイ』で遊んでいましたね。小学校に上がる前から家族麻雀の卓は囲んでいました(笑)。ファミコンが出てからは、しばらくデジタルゲームばかりやっていたのですけれども、KONAMIに入社してゲームを仕事として考える必要が出てきたときに、少しコンピューターゲームに対して閉塞感を感じていたんですね。
2000年代の前半くらいですかね。PCが一般に普及し、FLASHやVB、ツクール等、いわゆる「ゲーム」を個人でも制作することのハードルは相当下がっていたと思うのですが、とある企画募集があった際に、少し考え方を広げなくてはと思い、そういえばボードゲームは今現在どんな進化を遂げているのだろうと思ったときに、『バトルライン』というドイツのボードゲームをプレイしました。
驚きましたね。それまではどこかでやはり双六の延長といいますか、子供向けのゲームメディアだと思っていたんだと思います。

イシイ氏:
ボードゲームを販売している「すごろくや」が出来たのが2006年で、そのタイミングで日本ではドイツのボードゲームの何度目かのブームが来ているんですよね。おそらくそのあたりの時期ではないかと思います。
長田氏:
そうですね。僕が何か買ってみようかなと思ったときに、すごろくやとメビウスゲームがあって、日本でも取り扱ってるんだと。
イシイ氏:
すごろくやは元チュンソフトの丸田康司さんという方が店主なんですけど、『MOTHER2』や『風来のシレン2』のプログラマーが作ったボードゲーム屋さんなんです。あと、早すぎたゲームキューブ用MOの『ホームランド』のディレクターも務められた。
日本語化したりルールを説明するDVDを独自に作って、それを付属して売り出した。そこから日本でのドイツのボードゲームの普及が加速したと思っています。それまでのボードゲームは輸入が多くて、プレイするのが大変でした。リテラシーが高くないといけなくて。
長田氏:
すごろくやは、店内で実際にゲームを遊べるのが大きいですね。試遊ができる。

──メジャーなアナログゲームでは、『カタン』と『ドミニオン』と『人狼』が普及しましたね。この3つが桁数が多く遊ばれてます。
イシイ氏:
そうですね。『カタン』はカプコンさんがドイツボードゲームブーム以前に日本語版を販売されていたんですよね。すごろくや以外でもドロッセルマイヤーズが出てきたりして。ドロッセルマイヤーズはスクウェア・エニックスさんの流れだから、ビデオゲームの人たちがボードゲームのブームに貢献したのは面白い流れですよね。
長田氏:
アナログゲームは、アートワークはあるもののアニメーション処理やサウンド、エフェクトなどの演出で刺激を持たせるわけにいかないから、基本的にはゲームシステムのみで60分なり90分で遊ばせなきゃいけない。この潔さが好きだと思って買い始めました。こんなのもあるのか、こんなのもあるのかと買っていったら、押入れが即いっぱいになりましたね。

イシイ氏:
そのころの本格的に流行りだす前の人狼は、ちょっとハードな文化の人狼でしたよね。次は誰を吊るとか、効率とかセオリーを重視していて。そこに人狼TLPTなど演劇系の人狼が出てきて、人を魅せる、楽しませる人狼も生まれてきました。人狼に新たなパーティーゲーム的な文化が加わった節目だったのではないでしょうか。
──もともと人狼は勝利を重視するゲームだったのに、勝ち負けに関係なく遊ぼうよという流れになったわけですね。
イシイ氏:
勝ち負けに関係なく遊んで、しかも脱落した人がそのあとも楽しんで見ることができるようなプレイングが増えていった気がします。ちょっと近寄りがたい部分もあったゲームだったのですが、脱落した人さえも楽しませる新しいプレイ文化によって、人狼ゲームは一過性のブームではなく生き残った気がします。
──ゲーム実況文化も大きかったと思いますね。誰かのお手本があるので理解できる。真似する何かがなければ、やってみたいとは思わなかった。
イシイ氏:
そうですね。そういう意味では、ゲーム実況文化に対しても、さらに可能性を感じませんか? ゲーム実況に合ったゲームシステムもありえますよね。プレイするより見る方が面白いゲームとかもたまにありますから。
ゲームはプレイするプレイヤーより、ルールを作ったゲームデザイナーの方が影響力があるという考えもちょっとあるじゃないですか。でも、やっぱりプレイヤーがゲームをどう遊ぶかで質が変わるんだという体験を僕は人狼ゲームから学ばさせていただいたんですね。プレイヤーのスキルやスタイルでゲーム自体の文化を変えていけるんだって体験をできたことも、人狼ゲームに深く参加してよかったと思っている大きなポイントです。
アナログの「人を感じる」「対面での面白さ」をデジタルゲームに
 |
──そんな人狼に影響を受け開発された『クライムサイト』ですが、生まれた一番最初のきっかけはなんですか。
長田氏:
以前制作に関わっていた作品の開発チームで合宿をしていたときに、スタッフで人狼をプレイしたのですが、そのときに人狼は論理も確かにあるけど、雰囲気で吊られたり、生かされたりするところがある。これはどちらかというと推理や論理というより、ストーリーを楽しむ側面もあるゲームなんだなと感じたんですよ。その面白さをオンラインのデジタルの方に持って来れないかと。
──「パズルではなくストーリーとして楽しむ人狼」が『クライムサイト』の着想になった?
長田氏:
はい。人狼は言葉を介して、お互いを探り、論理で人狼を導き出して暴くこと・もしくは暴かれないことをゲームとしての「勝利条件」に据えてはいますが、「面白さ」はそこだけではなく、「今回こんな風になった」、「この人がこんな役割でこんなことを喋った」というストーリーとしての側面がある。
これは楽しいなと思いました。ただ、「ストーリー」である以上、この面白さを出すには言葉が必須になっている。そこで、言葉を越えて騙し合いをさせつつ、人とのやり取りを介してそこにストーリーを感じられるようにできないか、と思ったんです。
 |
長田氏:
『クライムサイト』では、ゲームで用意したいわゆる「シナリオ」ではなく、「なぜこのプレイヤーはこのキャラクターをここへ動かしたのか?」と推測するところで、相手プレイヤー自体を感じさせるようにしようと考えました。「スタンプ」や「PING」といった、プレイヤーの感情や意思をキャラクターを介さずに直接表現するシステムを導入しようと考えたのもここからです。
というのも、アナログゲームならではの面白さというのは、対面している人間の反応も込みでゲームの面白さだと思うんですよね。金銭やマス目、トークンといったものは、モノ自体は確かにアナログですが処理としてはデジタルな要素なわけです。アナログゲーム「ならでは」の面白さというのはそこではなくて、たとえば自分が指した一手に対して、相手の表情がちょっと変わるとか。息を飲んだとか、そういったものだと思うんです。
──「対面」というのはアナログゲームの本質に近い要素かなと思っています。人と人とのやり取りがゲームの情報量として含まれているので、それがオンラインのデジタルになったときに、表情みたいなゲーム自体には含まれない情報量がゴソっと削ぎ落しされてしまいがちになるのではと。
長田氏:
ええ。デジタルの対戦ゲームで勝敗の後に屈伸して煽ったり、『フォートナイト』で撃ち倒した後でダンスしたりといった行為は、一般的にはマナー違反とされてますが、それに近いかもしれないですよね。
ゲームのデジタルな勝敗自体に基づいたものではなくて、人が人を感じさせる行為です。だからこそ憎たらしいし、楽しいのだろうなと。仮にキャラクターが同じ行為を取ったとしても、快・不快の感じ方が相手との信頼関係の有無に影響されていると思います。
 |
長田氏:
そういった考えで、『クライムサイト』でもプレイヤーさんのリアクションをちょっとでも感じられるように、行動決定したあとに相手のカーソルの動きが見えたりとか、感情を表現する「スタンプ」が押せたりできるようになっています。
ゲームからひとつ離れたメタな層というか、プレイヤー同士の生のリアクションを見ることができるようにしようと思い、自分なりの解釈ではありますがアナログゲームの面白さの一部をデジタルで表現してみようと思った部分でもあります。