知られざる「縛りだらけのインディーゲーム開発」の世界がここにある。
世は大インディーゲーム時代。
『天穂のサクナヒメ』や『NEEDY GIRL OVERDOSE』などのインディーゲームが100万本以上を販売する現代、インディーゲームに注目しているゲーマーは多いことだろう。
そんなインディーゲームについて、多くの人は「職人的な個人、少人数の有志が個性的なゲームを作る、自由なゲーム」というイメージを抱いているのではないだろうか。
実際、漫画『デベロッパーズ~ゲーム創作沼へようこそ~』やドラマ『アトムの童』などでも、インディーゲームを扱う物語は天才的な開発者、やる気と才能ある有志の集まりがゲームを作る姿が描かれている。
それは一面の真実ではある。が、実は表に出づらい縛りだらけのインディゲームの世界もある。
すでにある程度の規模を誇るゲーム会社や、複合企業で制作されるインディーゲームである。その昔、ゲームの販売は体力のあるメーカーが行うもの【※】だったが、ダウンロード販売が主流になった近年は誰もがゲームをリリースできる。
となると、昔は自社販売できなかった会社が「俺たちもゲームを自分で作って出したい!」と動き出すわけだ。
※パッケージソフト主流の時代は少額・小ロットのゲームを開発・リリースすることは難しかった。最低でも数千円の定価を設定し、数千本単位で作らなければならなかった。ダウンロード販売が始まっても高額の開発機材準備が参入のハードルになるなど、近年まで企業が小規模のゲームを出すことは難しかった。しかし、開発環境もPCだけですむSteamの市場が日本でも大きくなり、近年ようやく視野に入ってきた。
ところが、企業がインディーゲーム開発に乗り出そうとすると個人・少数集団の開発とは異なる問題に直面する。個人開発では「作ろう」と思えばインディーゲームを作り始められるが、会計監査がある企業では「それは利益が出るのですか?」という質問に回答する事業計画書を先に提出しなければならない。
1本のゲームを作るためだけの特別な人材を集めるのではなく、自然と社員から人材を選ぶことにもなる。ゲーム発売時期も「期をまたぐ前に出してね」と、決算の圧力がある……経営面の縛りだ。さらに、開発ノウハウの欠け(請負と開発では必要なノウハウが異なるのだ)、販売ノウハウの不足など、「経験が中途半端にあるのでハマってしまう落とし穴」のようなものもある。
これは多くの人が想像する「自由なインディーゲーム」のイメージからかけ離れていることだろう。日本企業においてこんな話はしばしば聞かれるのだが、監査のある企業ともなれば内部事情を話しづらいし、知見が共有されることはまれで、当然皆さんの前にもその話題は出てこない。結果、「あなたの知らない世界」になってしまうわけだ。
本インタビュー連載「縛りだらけのインディーゲーム開発」では、同じような苦労をしている開発会社に知見を共有すべく、実際のプロジェクトの事例をもとに会社役員としての問題、開発チームの苦労、マーケティングの落とし穴など、4回程度に渡って開発で直面した苦労を赤裸々に語っていく。
あなたの知らない「縛りのなかで自由を目指すインディーゲーム開発」の世界が、ここにある。
本連載で語られるのは、SEモバイル・アンド・オンライン株式会社(SEM&O社)の事例だ。同社はゲーム開発支援(SES)業務・受託開発、そしていくつかの自社運営型やコンソール型のダウンロードゲームを手がけている。だが2023年に新卒中心のチームを作り、新規にSteam向け自社ゲームの開発にチャレンジすることを決定する。
だが、そこには「縛りのあるインディーゲーム開発」ならではの問題が横たわっていた……。
第1回では、同社取締役エンタテイメント事業部長・尾崎耕平氏の赤裸々な苦労話を語っていただく。聞き手はプロジェクトのゲーム制作ヘルプを頼まれ、何の因果かこんな記事まで書くことになったゲームライター(?)岩崎啓眞である。

プロジェクトのはじまりは「新卒の教育」
岩崎:
まず最初にお聞きしたいのが、この「新卒中心のチームでSteam向け新作ゲームにチャレンジする」というプロジェクトの始まりというのは、どういうものだったのかということです。 尾崎さんの頭の中でこのアイディアが出てきたのはいつごろだったんですか?
尾崎:
去年(2023年)の年が明けてすぐのころ、どういうふうに事業の方向性を伸ばしたらいいのかなと思ったのがきっかけです。
うちの会社の売上構成は自社ゲームサービスとSES【※】で大体半々なのですが、2023年の初頭はSESの市況が活性化してたんです。どちらかというと売り手市場で、スタッフの入場(仕事)もすぐに決まるような具合でした。そもそもの背景として、この4年間ぐらい、SESはそういう状況で続けられていたんですね。
なので「じゃあSESを拡張しよう」となったときに、今までは外部の業務委託のスタッフに協力いただいたり、自分のネットワークにある会社の方からとか、当社の社員以外にも増強してやれていました。
ところが、それ以上に人が足りないっていう状況になってきまして。中途採用も積極的に行っていたのですが、売り手市場だからということもあり、なかなかいい人がいなくて採用が進まなくなってしまったんです。
なので、中途採用と並行して「新卒からちゃんと育てていく」流れもあったほうがいいんじゃないかと。まず、SESの方でそう思ったのが始まりですね。
※SES:「システムエンジニアリングサービス(System Engineering Service)」の略。多くの場合、契約で定めた期間、クライアントに対してエンジニアの技術力や専門スキルを提供するサービスを指して使われる。具体的にはクライアントがゲーム開発をしようとしているとすると、プログラマ2名、プランナー1名が6か月参加するというような契約をする。
「派遣と何が違うんだ?」と思うかもしれないが、SES契約では貸しているスタッフに対して指揮命令する権利はスタッフが所属している企業にある。そのため、クライアントはSES契約で働いているスタッフに対して直接指揮命令することができず、契約しているSES企業を通じて間接的に要望を伝える形になる(もちろん契約している範囲では指示できる)。
岩崎:
ゲーム開発支援の需要が多くて好景気になり、人を増やすほど拡大できる状況が4年も続いたら人材が売り手市場になって確保が難しくなったので、SESの人材増強のひとつの手段として、新卒から育てるのもいいだろうと思ったわけですね。
尾崎:
はい。同時に自社ゲームサービスは収益がでているタイトルはあるんですが、やっぱり何年も運営していくと、さすがにいつかは売り上げが落ちていくと考えるのが一般的ですよね。
そういうことを踏まえて、当社のゲーム事業を分散経営の視点で見ると、今後の事業がSES・受託だけに集中するのはリスクがあります。またコンテンツの収益状況によって、SESの待機メンバーを移動できる可能性の高い、自社ゲーム部分の拡張も行うべき課題としてあったわけです。
岩崎:
なるほど! SES市場にあまり適していないと思われる社員の仕事がなくなっても、自社ゲームサービスがあれば会社も戦力の有効活用ができるし、社員のキャリアも作りやすくなるという話ですね。
尾崎:
それでトライアルとして自社ゲームの拡張機会を増やしていたのですが……そうはいっても、みんな現状のプロダクトでパツンパツンになってしまいリソースが足りない。そこではじめは「海外のライセンスをやろう」という話になり、例えば台湾のコンテンツを取ってきたりとかしていたわけです。
岩崎:
はい。ものすごくよくあるパターンですね。僕も中国の開発スタジオのゲームだの、韓国のスタジオのゲームだのを買い付けに行ったことがあります。
尾崎:
それが移植費やらMG【※】やらで、およそ数千万ぐらいかかったわけです。ところがやっぱりコンテンツがダメで、運営開始から6ヶ月ぐらいで閉じてしまった。これが閉じた後、ほとんど何も得るものが残らないんですよね。
※MG:ミニマムギャランティ。ゲームが完成したときに相手に対して払う、最低保証の金額のことをゲーム業界ではMGと呼ぶ。
「何も得るものが残らない」のは、ゲーム内で使用したリソースは契約にもよるが会社のものではない可能性が高く、修正などは開発会社にお願いすることになる。そのためプログラムのノウハウはほとんど積まれないし、運営のノウハウがそう積まれるわけでもない。つまり失敗すると、結局のところ「赤字を出しただけ」ということになってしまう。
岩崎:
はい、わかります。
尾崎:
そういうわけで、失敗すると何も残らないことをやり続けるのも今後どうなのかなという思いはありました。そこで、さきほどのSES増強のための新人教育というところと、自社ゲームの新しいトライアルっていうところを合わせてしまえばどうかと考えたんですね。
正直、自社ゲームが売れるかどうかは絶対にわからないじゃないですか。売れない可能性のほうが高いわけですよ。だったら、最低でもその自社のスタッフの教育研修という意味が残るっていうわけで、これでやってみようということでプロジェクトを立ち上げたんです。
岩崎:
なるほど。つまりSteamに打って出るというよりは、そもそもは新人教育の要素が大きかったわけですね。
尾崎:
昔、モバイルで運営と保守の仕事が増えてSES事業を本格化させる前、プレイステーションなどのコンソールが中心だった時代の開発受託は“マグロ釣り”みたいな仕事でした。チームでひとつひとつ提案を作って、受注した場合は大きな金額が動くというようなイメージですね。
マグロが釣れなければゼロで、釣れたら1~2年は食える……みたいな。そんなスタイルでやってきたんですけど、受託事業をSES事業にシフトしてからは、もうちょっと事業としての仕組み・サイクルで成長できないかなと思ったのもありました。
岩崎:
(笑)。まあゲームを作るというのはギャンブルですから、マグロにたとえるのはアリですね。
尾崎:
SESのメリットは月々にスタッフが問題なく仕事できていれば、毎月報酬をいただけることです。長期案件が多い場合もあり、そうすると年間である程度の利益と計画が見えるので、年の最初に投資が決定できることも大きいです。
これが大型の受託タイトル案件をチームで動かすことになると、最終的にどのくらいの利益が残るかはギリギリにならないと分からない場合が多いので。たとえ、利益が出たとしてもマグロ釣りということもあり……次年度にその利益を差し引いて目標を作ることはできないので、投資計画は立てづらかったです。
岩崎:
わかります。
補足:受託タイトルは、相手が予算を持っていて、その中で期限があって作ることになる。なので、契約によっては完成してすら利益が残るかわからないときがある。ただし契約が1本あたりの印税契約であったり、一定以上売れたらボーナスが入るような形のことが多いので、売れれば大きな利益になる。というわけで、やはりマグロに例えるのはアリなのだ。
尾崎:
あらかじめ計算できるのがSESのメリットなので。そういう形で組んだら、持続可能なスパイラルで組織が成長していくんじゃないかという非常に楽観的な計画を立てていました。
岩崎:
ああ、つまりSES市場があの時に活況な市場だったということもあって、そのSES側で通用する人を教育するために、新卒を取る。同時に自社側のゲームの売り上げがもちろん永遠に続くわけじゃなく、いつかは落ちるだろうから、そこを埋めるためにも自社ゲーム開発に力を入れて行こうという流れだったわけですね。
尾崎:
乱暴な言い方をすれば、「宝くじを買いながら、最低でも教育研修が残る」という話ですね。
あと、もう一点は新卒の方を定期的に入れていかないと、どんどん組織が老朽化するんですよね。年を取ったスタッフがダメというわけではなくて、それぞれの世代の良いところが適材適所でバランスよく機能し、循環していくべきだ……と思っているんです。
新卒の方とか、新しいスタッフが入ってくると、昔からいるスタッフにとってもカンフル剤になったりするんですよね。今はテレワーク中心になっているのでなかなか難しいんですけど、やっぱりそういう循環もないといけないなと。下手したら、みんなが50~60歳の組織になっちゃうって結構怖いじゃないですか。
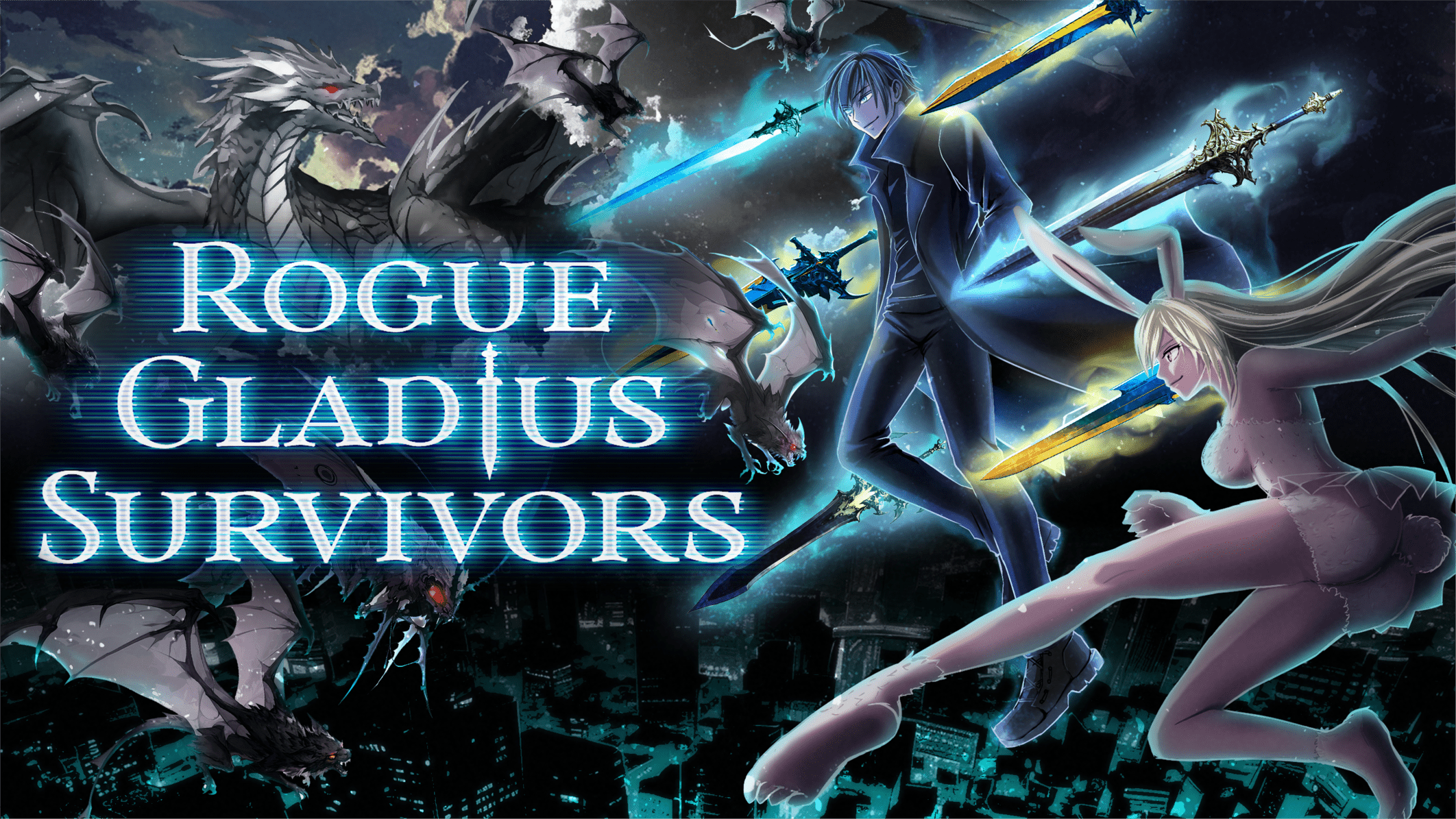
岩崎:
確かに、怖いですよね。
尾崎:
そういう「全員50歳の組織ってヤバいな」という危機感はありました。まあ、さすがにまだ20~30代の人もいますけど……。こういった思惑がいろいろ重なり合い、今回のプロジェクトに繋がったという経緯があります。
岩崎:
新卒によって組織の循環を狙いつつ、同じ宝くじを引くなら自分達で引いたほうがいいし、それが新卒の教育にもなるだろうという狙いだったわけですね。その行き先がSteamだったのは、やはり参入障壁の低さですか?
※ここではゲーム開発を宝くじにたとえているが、売り切りのゲームは売ったあとのメンテナンスコストは運営型のゲームと比較して低い。だから開発費を賭けた博打か、宝くじのようなものだということになる。
尾崎:
現状の投資コストの状況を鑑みると、サーバーの必要性が薄い、売り切りのダウンロード型のゲームからはじめる方が良いと考えていました。
売り切りであればモバイルアプリやコンシューマ機のダウンロードゲームでもよかったのですが、Steamを最初に選んだのは、今後の成長性をふくめ、Steamはグローバルプラットホームとしてはずせない場所だと考えたからです。
また海外市場に目を向けるイメージが感覚的につきやすく、このプラットホームで開発手法やプロモーション手法といったノウハウを蓄積していきたいという狙いもありました。


































