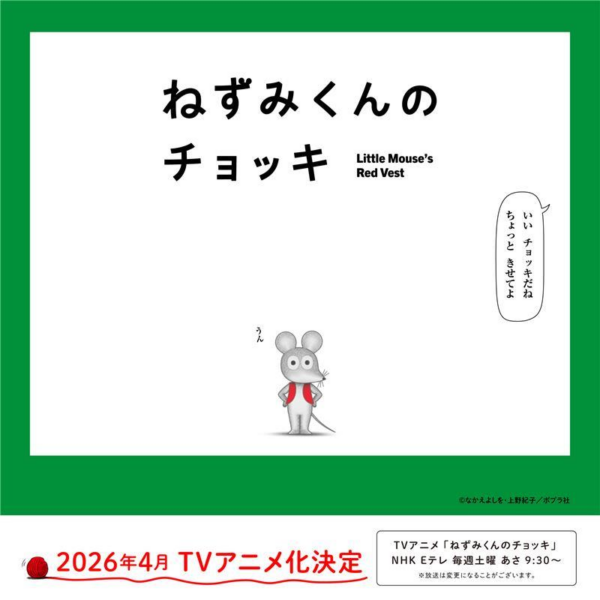■制作チーム トークセッション
新川洋司:アートディレクター、キャラクター&メカデザイン
吉池博明:リードレベルデザイナー
内田貴之:テクニカルアートディレクター、リードエンバイロメントアーティスト
酒本海旗男:チーフテクノロジーオフィサー、テクニカルディレクター
プレイヤーがさまざまなシチュエーションの中で「選択」を楽しめるゲームデザインを目指した
──基本は前作を踏襲したゲーム性で細かな部分が進化していますが、どのような狙いでシステムを構築したのでしょうか?
吉池氏:
『デス・ストランディング2』では小島監督から戦闘を強化したいというオーダーがありました。
前作ではA地点からB地点への配送で、途中途中、自然や地形が脅威になったり、「ミュール」という荷物を奪う敵がいて、その困難に対してどのようにその荷物を安全に運ぶかというのがゲーム性でした。
そこで監督からのオーダーとユーザーの皆さんからの反応。自分なりに『デススト』を強化するならどうすべきかを考えたときに、ルート選択の楽しさという部分を強化する方向でシステムを考えていきました。
──逃げるのも、戦闘するのも、ユーザーの選択しだいで、どのルートを選んでも楽しい体験が待っていると。
吉池氏:
今までは、いかに逃げるかというところがゲームデザインの中心だったのですが、ステルスとコンバット、どっちで切り抜けるにしても楽しくなるようにということを考えています。
あるいは、絶対に敵とは戦いたくない人は、他人が通らないような険しい地形を乗り越えていくということもできます。
ステルス、コンバット、迂回、この3つをそのときの状況や、プレイヤーのスタイルに応じて楽しめるように、敵の拠点やミッションも構築しています。
さらにルート選び以外にも「選択」をひとつのキーワードとして、見た目の変更などのカスタマイズ要素や、プレイヤーが自分ならどのようにこの荷物を届けようか。という計画をたてることが楽しめるようにシステムを構築しています。
──自然現象とそれがもたらす地形の変化は、前作からの大きな変化ですが、レベルデザインとしてはどのような工夫や挑戦がありましたか?
吉池氏:
「選択が楽しいゲームにしよう」という考えがありましたので、動的に環境が変化していくのは非常に重要だと考えました。
実際に配達を開始すると、さまざまな自然現象であったり、昼夜の変化によるアクシデントが起きて、スタミナやライフを消費してしまったり、向かう予定だった場所に行けなくなったりということが起きるので、それを自分のスキルやツールでどう乗り切っていくのか。
あるいはどうしようもないなというときに、「ソーシャル・ストランド・システム」で繋がった他のプレイヤーからの助けを借りてクリアすることが楽しかったりするので、そのときどきの状況に応じた選択を繰り返しながらゴールを目指すのが楽しくなるシステムにしようと思いました。
だから「TOD(時間の変化)」に関してもその一環ですし、自然災害とかも、とにかくいろんなことが起きてほしいと思っていたんですが、僕らはどちらかというと要求するほうが多くて、大変だったのは内田さんだったのではないかなと。
内田氏:
そうですね(苦笑)。
吉池氏:
PVに出てくる増水も、最初はできるかどうかみたいな反応でしたよね。
内田氏:
なかなか……(笑)。
吉池氏:
前作からやりたいとは言っていたんですが、実現できなかったんです。それで本作ではなんとかやれるということでお願いして実現してもらいました。
あとは砂嵐も最初は中に入ったら視界が悪くなる表現だけだったんですが、砂嵐って「こっちに向かってくる。巻き込まれるかもしれない」という体験の部分がおいしいところなので、移動させたいってお話をしました。
小島監督は乗り気だったんですけど、最初は技術的に難しいって話をしていて、それでも結局「これくらいならやれる」って言ってくれたので、砂嵐は発生して移動して消えていくという流れになっています。
だから初遭遇するシーンでもうまく避けられるというか、砂嵐に遭わずに済んだ体験もできます。こういった環境の変化によって、プレイヤーひとりひとりが異なる体験ができるようにというのは意識しているので、その結果をフォトモードで収めたり、友だち同士やSNSで語ってくれると嬉しいです。
──複雑な地形も多いですが、プレイヤーが程よく迷いながら自分なりの解決策を見つけられるような導線を感じました。プレイしやすさの点で、どのような点に注力されましたか。
吉池氏:
これはどちらかというと、テストプレイしてくれた人たちが頑張ってくれたのが大きいです。もちろん最初に設計、計算してはいるんですけれども、テスト中はあちこちで「わからない」など、いろいろな声があがりますから、それをひとつひとつ地道に潰していった結果ですね。
あと今回こだわった点のひとつに、各地域のキャラクターの人たちを深掘りしようというのがあります。
作品内に全部収まっているわけではないんですが設定はそれぞれ決まっていて、どこにいて、どういうことに困って、どういうことを求めていて、サムに何をしてほしいのか。というところまでイメージしながらミッションや荷物の内容を決めているんです。
それがあることで、サムがこういうことのためにやっているんだ。こういうことをしたいんだという動機づけも含めてモチベーションの維持や感情移入しやすいように設計したというのが、こだわっている点です。
ゲームのキャラクター、物だからではなくバックグラウンドまで考えてデザインしている
──本作では「DHVマゼラン」をはじめ、前作にはないメカやガジェットがたくさん登場します。が、どのようなコンセプトを持ってデザインをされましたか。
新川氏:
最初のオーダーからいろいろ考えて「潜航艇」というキーワードから「潜水艦」っぽいイメージを含め、何個かラフを書いて監督に見てもらったんです。
そのときに渡したものの中に、完成形に似たものがあって「これいいかも。メタルギアの頭みたいで」と(笑)。
トレーラーにも出てきた敵の巨人と合体みたいなのも、そういったやりとりや、デザインだったりゲームを作っていく過程の中で生まれたキャラクターでもあるので、いろんな作用が起きた中で、偶然か必然か生まれたちょっと不思議なデザインにできたかなと思っています。
あと、最初にデザインをしたころはタールの中を潜航して「BT」を狩るという設定があったので、後ろにつけている四角い箱状のものは、カーゴというか釣った「BT」を入れるようなカゴとしてデザインをしています。
船ってどうしても固いもので、動きがなかなか出しにくいというのがあったので、カゴが開いたり、そこにクレーンで掴んだものを入れるといったように、デザインとして成立するようなものは考えています。
そういう動きを出せるようにしたことで、船という固いものなんだけどいろいろな表情が見せられるようになったと思っているので、トレーラーの最後の戦闘シーンを見るとこれでよかったなと思っています。
──ありがとうございます。また、前作に引き続き武器のデザインが非常に個性的ですが、こちらにもこだわりのようなものはありますか?
新川氏:
前作から引き続いて荷物を運ぶゲームなので「武器なんだけど、折りたたむことによって箱状になって荷物になる」というのは一番こだわったところです。
武器も荷物のひとつとして捉える必要があり、これも重さとしてプレイヤーにのしかかってくるのが『デススト』の特徴で、だから何を持っていくかというのもひとつのプレイスタイルですし、ゲームの選択肢として荷物じゃないといけないんです。
だから実際デザインしているウェポンのコンセプトアーティストも、非常にリアルな武器としてこだわって作ったので、機構的にもほぼほぼ嘘はなくて、実際に作れば折りたためるんです。
CGだと、どうしても嘘をついて容積が変わったりするんですけど、それがなく破綻しないようにちゃんとデザインをしているというのがこだわったところですね。
フラジャイルの首の手は新川氏にとっても斜め上の発想。成長したルーのかわいさはスタッフのこだわりの結果
──前作に増して個性豊かなキャラクターやクリーチャーも登場します。とくにフラジャイルの「手のマスク」に関しては、小島監督からはどのようなイメージを伝えられ、ご自身ではどのようなイメージでデザインをされましたか?
新川氏:
あれは監督からのオーダーがあったんです。
コロナ禍だったのでメールでやりとりをしていたんですが「フラジャイルの首に手をつけたい」と急に来まして。最初全然意味がわからなくて「そうですか」と、生返事しまして(笑)。
想像したのは、なんかシールドみたいなプレートがあって、そこに前回のフラジャイルエクスプレスの手のデザインをこう描いたらいいのかなと思って送ったら「違う!」って。
一同:
(笑)。
新川氏:
メッセージに監督が描いたフラジャイルの絵が添付されて、レアさんの顔が描いてあって、手が首に描いてあるだけだったので、そのものをそのままキャラクターデザインとして落とし込みました。
やっぱ発想がちょっと斜め上をいってるというか、その辺をどう咀嚼して表現していくかというのは毎回面白いし、難しいところかなと思っていますね。
──ありがとうございます。キャラクターに関して、本作の成長したルーがとにかくかわいいです。本作における彼女のキャラクターデザインのポイントを教えて下さい。
新川氏:
これはモデラーやモーションを担当する人たちがこだわった部分だと思います。
その他のキャラクターは、基になる俳優さんをスキャンしてブラッシュアップして、動きもアクターさんに実際に動いてもらうんですけど、ルーに関しては赤ちゃんなのでスキャンもモーションキャプチャーもできませんから、全部手作りで作られているんです。
ルーが可愛くないと、ストーリーが展開していかないというくらい重要なキャラクターなので、ここはキャラモデラー、モーション、フェイシャル、すごいこだわった部分ですね。
これも今までのノウハウがあるからできたのかなと思いますし、結果的にかわいいと思ってもらえてすごくよかったと思います。
キャラクターはより感情に訴えかけるように、ロケーションは多数のプロセスの上『デススト』世界のメキシコ、オーストラリアを制作
──本作は本格的に現世代機限定のタイトルとなりましたが、グラフィックはどのような進化を目指したのでしょうか。
内田氏:
まず、ストーリーが本作の主軸になるので、キャラクターの表現を前作よりも上げようと考えました。
具体的には、主要キャラクターについて前作では3Dスキャンしていたところを、4Dスキャンを実施しました。また、デフォメーションもとくに強化しまして、筋肉の動きや顔の表情が最も進化した部分かと思います。
それによって、ストーリーでキャラの演技しているときに感情に訴えかけるような部分も前作より強化されていると感じてもらえるはずです。
あとはとくにライティングですね。今回はオープンワールドで新たに昼夜の変化があるので、リアリティを追求する意味では重要かなと思って、基礎研究をかなりの期間やりました。
新川氏:
もう最後の最後までやって、完成しなかったよね(笑)。
内田氏:
そうですね……いや、完成はしたんですけど(笑)。
難しいのがプリレンダじゃないムービーですね。ゲームの場合は精密なシミュレーションをリアルタイムに実施するのは難しいので、どこをフェイクに頼るか、また、どこをそのままフィジカルライティングとして残すかという点が難しいんです。
これは会社やプロジェクトによっても変わってくるのですが、問題点を洗い出して緻密に適用した結果が、ゲーム開始直後の風景です。あそこは実写のリファレンスを見ながら突き詰めた結果だと思っています。
──本作では、メキシコやオーストラリアなどさまざまな土地を行き交います。その違いを描くうえで、どういったところにこだわりを持って取り組みましたか。
内田氏:
『デススト』は荷物を運ぶ配送人というのがテーマで、風景の移り変わりやバリエーション数がそのままユーザーの体験や面白さに繋がることは、小島監督が制作の最初期から言っていたことでした。
メキシコとオーストラリアというロケーションは監督が描きたいストーリーを念頭に選ばれたロケーションでした。その中でどこを描くかというバトンは新川と私に委ねられていたのですが、そこに前作以上のバリエーションを出すのは、二作目としてゲームをアップデートするうえで強く意識していた部分です。
今回はコロナ禍もあって、何度か中断しつつ1年半ほどリモート取材を行いました。現地に赴くことはできないので、自分たちでGoogleマップを見て洗い出したところを現地のコーディネーターに撮影してもらってきています。
さらにそのときの映像から、具体的にここと指定して詳しく取材してもらう、三段構えで取材をおこなって、みんなに動画を共有しつつ、ユーザーが自然を踏破したときに快感を得られるようなロケーションを選んでいます。
その後、新川とそれぞれのロケーションにタールが侵食してきたような『デススト』世界のテイストを入れる作業を行うことで、ただの観光地ではない『デススト』世界のオーストラリアやメキシコに落とし込む。プロセス数が多く大変ではあったんですが、こだわりを持って取り組めました。
ハードの進化でクオリティの高い映像を表現するための選択肢が増えた
──開発の視点から見て、PlayStation 4からPlayStation 5に移り変わった際に大きく変わったことはありますか?
酒本氏:
正直大きく変わったということはほとんどないかと思います。
コジマプロダクションが「絵」として目指しているものの方向性自体は変わってなくて、それに対するクオリティや求められるものが高くなっているのに対して選択肢が増えたとは思っているんですが、あくまでも今までの延長線上と捉えています。
そのうえで、一番大きい変化としては、読み込みが早くなったことでローディングが数秒レベルになったことです。結果として演出の中にローディングを挟めるようになり、ユーザーがローディングという時間を認識することなく物語に没入しやすくなったと思っています。
──なるほど、前作よりもフォトリアルに近づけた秘訣のようなものはありますか?
酒本氏:
リアルさを演出するために求められる部分というのは確立はしてきていているので、そのなかでどの情報をどの程度の精度と手段で表現するかに落ち着くと思います。
ゲームはリアルタイムで動かさなければいけないので、すべての要素で最高のクオリティを出す手段が取れるわけではありませんが、『デススト2』の世界観と要素から、どれをどの程度の密度で表現したら絵としておいしいのか選択すること。
さらにそれをアーティストそれぞれが細かくコントロールすることで、今回のクオリティが出せているのかと思っています。
開発工程において前作から変えたこととしては、シェーダーを各アーティストの手元で作れるようにしています。
前作でも知識のあるアーティストがシェーダーを作っている部分があったんですが、そこでアーティストがコントロールすることによるクオリティの向上がかなりあるという話になりました。
計算の根幹はエンジニア側で手綱を握ることで、物理的に破綻しないよう担保しつつ、アーティスト個人が詳しい部分、こだわりたい部分はそれがより生かせるような形になっているので、結果としてそれぞれのこだわりが組み合わさったことも、現状のクオリティが出せている秘訣ですね。
さまざまなニーズに応えられるようキーアサインやシステムは調整。今回はバックパックも降ろせる
──センサーなどボタンの配置が前作から一部変わっていたのはなぜでしょうか。
吉池氏:
ゲームデザインに適したキーアサインにした結果ですね。
今回は監督から戦闘を強化したいというオーダーがあったので、前作からゲームデザインが変わったことで、それに応じてボタンの配置が今回遊んでいただいた内容になりました。
──前作から継続している部分は進化しつつも、かゆいところに手が届くように作られた印象ですが。どのような部分に気を使いましたか?
吉池氏:
これはプレイヤー担当の人たちが苦労して作った結果ですね。戦闘重視だとレスポンスが大事になってくるんですが、『デススト』のゲーム性は「荷物を運ぶ」という方向に対してリアルなことが大事なんです。
もちろん多少は誇張していますが、このふたつを同居させるのはかなり難儀で、かなりのやり取りを繰り返した結果、今の状態までなんとかチューニングができました。
監督からは、戦闘やステルスにより特化したプレイヤーアクションを入れたいという話もあって、荷物の影響を受けない状態も作ってくれとのことだったので、バックパックも下ろせるようにしました。
戦闘を楽しみたい人はバックパックを降ろしていただいて、まぁ忘れないようにはしてほしいんですけど、それで楽しんでもらえたらいいなと。そういう部分でも選択肢があって、幅広いニーズに応えられるようにというのはこだわりつつ、調整した部分ですね。
──今回は4段階の難易度がありますがそれぞれどのように調整しているか、また、それぞれの難易度はどのようなプレイヤーに向いているのか教えてください。
吉池氏:
まず「ノーマル」に関しては小島監督が一番遊んでほしいバランスになっていますので、監督自身が何周もして細かくチューニングしています。
一番優しい「ストーリー」モードは「お話をとにかく楽しみたい」という人向けです。前作の感想を見ていて、なかには「クリアできません」という声もあったので、ストーリーを楽しみたい人は「ストーリー」という、そのものずばりなものを選んでいただければと。
「カジュアル」に関しては、ストーリーだけじゃなくてゲームの部分も楽しみたいんだけど、あんまりゲーム得意じゃないし、手軽に遊びたい人向けですね。
そして「ブルータル」と名付けたのは今回の最高難易度で、これは開発メンバーでも人によっては大変というレベルの難易度です。
ただ「いいね」による配達人グレードの評価効率がいいというメリットがあるので、より早くグレードを上げたい人は、これを選んでもらうと楽しめると思っています。
それぞれの難易度で「スタンダードオーダー」をクリアすると称号が得られるんですけど、1番高い称号を得られるのは「ブルータル」なので、ゲームに自信のある人はそちらを楽しんでいただくのがいいかなという形で差別化しています。
新川氏:
途中で変えられるの?
吉池氏:
途中で変えられますよ。途中で変えられますけど、途中で変えた場合は、そのやっている最中のミッションに関しては低い方にあわされちゃいます。
新川氏:
せっかく頑張ったのに低いほうになっちゃうんだ。
吉池氏:
そうです、だから「もうクリアできない」ってときに下げるのはありですけど、基本的には途中で変えない方がおすすめですし、そこでズルはできない感じですね。