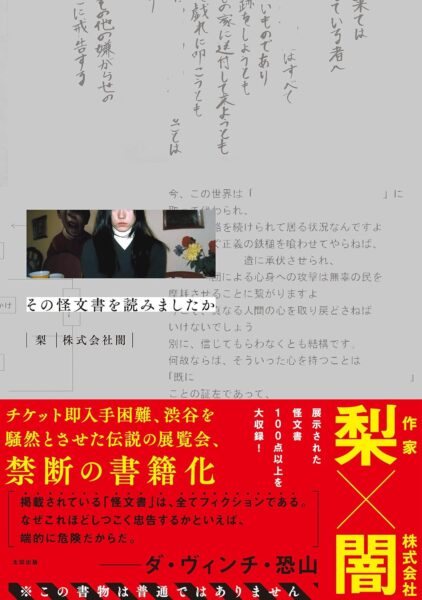2025年6月26日に発売される小島秀夫監督の最新作『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』(以下、デススト2)。
その発売に先駆けて、コジマプロダクション本社内で大規模なプレビューイベントが実施され、本イベントでは、小島秀夫監督へのグループインタビューと、コジマプロダクション制作チームによるトークセッションが行われた。
小島監督へのインタビューでは、前作の「ソーシャル・ストランド・システム」に対する想定外の反響やキャスティングの裏話が語られた。
加えて、コロナ禍を経て生まれた「繋がり過ぎることへの疑問」といったテーマが深く掘り下げられ、『デススト2』の物語を紐解くうえで重要なヒントにまで言及されている。
また、制作チームへのインタビューでは、プレイヤーがルートを選ぶ楽しさや、戦闘・ステルス・迂回など多彩なアプローチが取れる本作のレベルデザイン、DHVマゼランをはじめとしたメカや武器のコンセプトデザインなど、本作の核となるエピソードが明かされた。
さらには、フラジャイルの首元の“手”の誕生秘話から、進化した映像表現を支える技法、そして舞台をメキシコやオーストラリアへ広げた理由にまで話が波及していった。
「ゲームデザインとストーリー、このふたつをどこまで進化させられるか──」
小島秀夫監督がそう語るように、『デス・ストランディング2』は前作で築き上げた“配達ゲーム”としての基盤をさらに拡張しつつ、物語面ではサムとルーの新たな関係性を深く描く意欲作だ。
ここでは、そんな本作の貴重な開発秘話の数々をお届けしていきたい。
※インタビューはメディア合同で行われました。
【小島秀夫グループインタビュー】
小島秀夫【コジマプロダクション制作チーム トークセッション】
新川洋司:アートディレクター、キャラクター&メカデザイン
吉池博明:リードレベルデザイナー
内田貴之:テクニカルアートディレクター、リードエンバイロメントアーティスト
酒本海旗男:チーフテクノロジーオフィサー、テクニカルディレクター
■小島秀夫監督グループインタビュー
Q.『DEATH STRANDING』(以下『デススト』)の続編を作るにあたって、目指したものや前作から大きく変えたかった点とは?
小島氏:
ゲームデザインとストーリーですね。
前作で「配達ゲーム」というジャンルとしての基盤を作って、今作はその上にあるので、ある程度慣れた人がプレイすることを考えています。戦いたい人は武器を使ってもいいし、使わない人は別にそれでもいいとしています。
ちょっと思い出してほしいんですけど、『メタルギアソリッド』の冒頭、昇降機を待つシーン【※】は、問答無用でステルスをしないといけないじゃないですか。なぜかというと、その時点で武器があるとそれを使ってしまうので「隠れるゲーム」にならないからです。
※主人公ソリッド・スネークが地上に向かう昇降機を目指し、見張りの兵士をかわしながら進む場面。敵の動きや視界、足音に注意を払う必要がある「隠れるゲーム」としてのチュートリアル的な側面も強いシーン。
小島氏:
『メタルギアソリッド2』では、前作でステルスに慣れた人が遊ぶことも考えて、武器が簡単に入手できたり、主観で武器を使って正確に攻撃したりと進化しつつ、ジャンルに慣れた人のことを考えるというのは『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』(以下『デススト2』)も同じです。
今回は車やバイクも乗りやすくしましたし、配達ゲームというギミックのなかでいろいろ自由度を上げることを意識しました。
ストーリーに関しては、前回はサムとクリフの物語だったので、今回はサムとルーの関係やサム自身の深掘りというのが目指した方向です。
Q.1作目で多くのプレイヤーが「ソーシャル・ストランド・システム」を使っていたことについて、驚きはあったか?
小島氏:
そうですね。発売から5年経っても、いまだに国道ばかりを作っている人がいるというのは、驚いたというか想定していなかった喜びがありました。
モニターも実施して、スタッフの意見も聞きましたけど、当時は「ソーシャル・ストランド・システム」を楽しんでもらえるかは未知数でした。僕がプレイしたときも橋は作りましたけど、国道は作らなかったですし。
あくまで人が作ったものを利用するというスタイルでしたから、「国道だけを作る人が果たしてどれだけいるのかな?」と、疑問に思いながら発売したところもありました。こういうものを作りたい人がいるとわかったのは一番大きいところでしたね。
前作で国道を作ってくれた人たちに向けて、いろいろ考えた結果が今作でのモノレールになっています。
小島氏:
また、「ソーシャル・ストランド・システム」に関係することで言うと、「いいね」に関してはユーザーから反発があるかと思っていました。しかし、実際はけっこう喜んでもらえました。
「いいね」はお金じゃないため、アイテムが買えたり、強くなったりはしません。そこはスタッフから反対を受けていました。たしかにゲームデザイン的にはちょっと変なんですよね。普通コインを集めたらワンアップするものなんです。
でも日常の「いいね」みたいに、(ゲームシステムとしては)なんの価値もないけど「いいね」されている気持ちよさというか、「悦に入る」体験を表現したかった。
チームで議論になりましたが、最初のうちは反対していたうちのスタッフも、開発の終わりころは(チェック時に「いいね」をもらえると)喜んでいました。
こういうシステムって、発売して皆さんの反応を見ないと結果がわからないところが大きいです。ただ、皆さんのプレイデータや、フィードバックを受けた後に作った「ディレクターズカット」も踏まえての続編ですので、今作はユーザーの方の挙動は把握できているつもりです。
ただ、僕は戦闘をする際、背負子を降ろして戦うことを想定していたんですけど、(プレビューイベントでの体験会で)皆さんなかなか降ろしませんでしたね(笑)。
モニターでもそうなんですけど、背負子を降ろすと荷物がなくなると思う人が多いみたいです。これはリアルな生活でも一緒だと思ったので、あえて手を加えませんでした。
Q.なぜ新たな舞台としてメキシコとオーストラリアを選んだのか?
小島氏:
まずメキシコ(を新たな舞台として選んだ理由)は、UCAから地続きだからです。
1作目でアメリカ大陸を東から西に繋いでいきました。これは開拓時代を上書きしているんですけど、当然の流れとして隣の都市にもつなぐ必要があると。ただ、サムが何回も言っていますけど、それは侵略になるというところでいろいろ考えました。
じつは最初に考えていたのは「繋いだのは大間違いで、繋いだ後を外していく」というお話だったんです。
ただ、続編を作るにあたり、同じ場所を舞台にするかどうかを検討した際、「背景の使い回しになる」のもそれはどうかなと思って、別のロケーションを探すことになりました。
小島氏:
ユーラシア大陸は広すぎるし、アフリカでもないかなと感じました。アメリカ大陸と同じように東西に広がっていて、北と南も海に面しているようなロケーションを探すことを念頭において、オーストラリアを選んだんです。
そうなると今度は「北米大陸とオーストラリアをどうやって繋ぐの?」という疑問がでてきます。そこで、苦肉の策で「プレートゲート」【※】の設定を作りました。これを使うと続編がずっと作れるのですが、そういう予定はないです。
※プレートゲート……『デススト2』において、メキシコからオーストラリアの大陸間を結ぶ、謎の空間。
Q.『デス・ストランディング2』では人々が繋がることに対して疑問が投げかけられているが、これは小島監督ご自身の経験やソーシャルメディアに対する考え方が反映されているのか?
小島氏:
そうですね。コロナ禍で感じたことは反映されています。それ以前から『デススト2』の企画はしてましたけど、やっぱり違うなと思って全部を書き直しています。
1作目の話ですが、コロナ禍以前からイギリスのEU離脱などもあって、世界中が分断しようとしている気配があった。それに対して「繋がらないとマズイですよ」というテーマでストーリーもゲーム性も作りました。その3ヵ月後に新型コロナウイルスのパンデミックが起こって僕もびっくりしました。
21世紀には「カイラル通信」がある。まぁインターネットですね。おかげでスペイン風邪が流行った19世紀とは違うことになったと思うんです。ネットが繋がっているおかげで、僕らは生き延びていった。
小島氏:
コロナ禍で何が起こったのかというと、うちのスタジオを含めて仕事もリモートになったり、コンサートもライブもなくなってネットの配信に切り替わっていった。これは仕方がないことだと思います。
学校もそうですよね。子ども(学生時代)って、学校に行って友達と遊んだり、先生から教えてもらえる期間なのに、リモートで画面を見ているだけなんてYouTube見ているのと変わらないと思います。
世の中がどんどんメタバースの方向に進んでいって「直接対面しなくてもいい」みたいな動きになっていた。これは非常にヤバいぞと思いました。
僕が思う人間のコミュニケーションってそうじゃないんです。移動することで偶然人と出会ったり、予定外の風景を見たりだとか。そういうことが、まったくなくなってしまった。
変な話ですが「分断と孤立の危険があるから繋がりましょう」というテーマのゲームを作った後、コロナ禍を経験したら「繋がり過ぎたらダメなのでは」と思うようになったんです。
小島氏:
このあたりのことは「棒となわ」のこともそうです。いろいろ伏線を盛り込んでいて、最後には真実が明らかになります。コロナ禍に僕が感じたことを代弁する人が出てきます。
ヒントとしては、『デススト』のロゴは下にストランドが垂れてますよね。これは「繋がりましょう」というテーマだからなんですが、『デススト2』では上から糸が垂れています。映画『ゴッド・ファーザー』のロゴみたいにね。
ゲーム内でも「ドールマン」と武器工場に行ったらメカが浮いていたり、糸が出ていたりします。本作ではいろいろな人に糸が出ているんですけど、あれがちょっとしたヒントです。それと「繋がる」ということを考えると……これ以上は6月に遊んで確かめてください。
皆さんもコロナ禍を経験しているので、近い感覚を感じてもらえると思います。
たとえば、今回の体験会やインタビューについても、ゲームのコードを配布して、リモートでインタビューすることもできたんです。でも、今日ここに、それぞれの国から来ていただいたことで、いろいろな人と出会って会話をしたと思うんです。
道中でも、東京駅の風景を見たりお昼にたまたま入ったお店のこととか、そういう偶然があったはずで、それこそが人の経験です。
Q.新しいキャストを起用するうえでの、キャスティングのプロセスや基準とは?
小島氏:
キャスティングについては、コロナ禍もあってだいたい4年くらいです。
ゲームの撮影は作りながらになるので、映画のように一同で集まって三ヵ月四ヵ月の長いスパンでまとめて撮ることができないんです。だから定期的に集まって撮影するんですけど、猛烈に体力と精神力を使うんですね。
撮影もスキャンもして、それをデータにして、コスチュームを決めたり、メイクも決めたりというのを短い時間でやらないといけないので。
でも皆さん非常にタフなんです、たとえばニールを担当してくださっているルカさん。あの人、カットシーンだけじゃなくてNPCでも出てくるので「フッ」「ヘッ」「ホァ!」みたいな気合の声をずっと収録し続けている。
レアさんには撮り直しをお願いしたんですが、歯医者に行って歯のスキャンをするだけで3日くらいかかる。彼らも忙しいし、合間を縫っての対応になります。そうなってくると『デススト』のストーリーみたいに、もうお互いの絆が試されますね。
小島氏:
キャスティングの基準としては、まずは僕が好きな人です。映画を観たり、ドラマを見たりして、一緒に仕事をしたいなと思う人。そうじゃなかったら、僕から会いに行ってオファーはしません。中には僕のファンもいます。あるいは家族が僕のファンとか。マネージャーがファンとか。
ゲームの撮影では長い付き合いになるので、ご飯に行ったりしながら、この人ならできるというのを確かめつつ決めていく。
撮影後は、撮影やスキャンしたデータが僕らのところに来て、そこからブラッシュアップしていきます。たとえば、キャラ班でレアさんの担当するスタッフは、数年間毎日のようにレアさんの顔のデータの手直しをする作業を担当します。これは好きじゃないとできません。
1作目のときの話ですが、僕はリンゼイ・ワグナーさんが青春の人で大好きなんですよ。Blu-rayとか全部持っているし見てますけど、担当者は「誰これ?」みたいな感じなんです。
でも毎日彼女を作っていくので、制作の終わり頃に彼の席に行くとワグナーさんの代表作のBlu-rayボックスが置いてある。それで、なんで買ったの?って聞くと「毎日見ているとファンになります」って言うんです。
まぁオーディションもしますけど、なるべく繋がりをたどるようにしています。これは『OD』もそうですね。