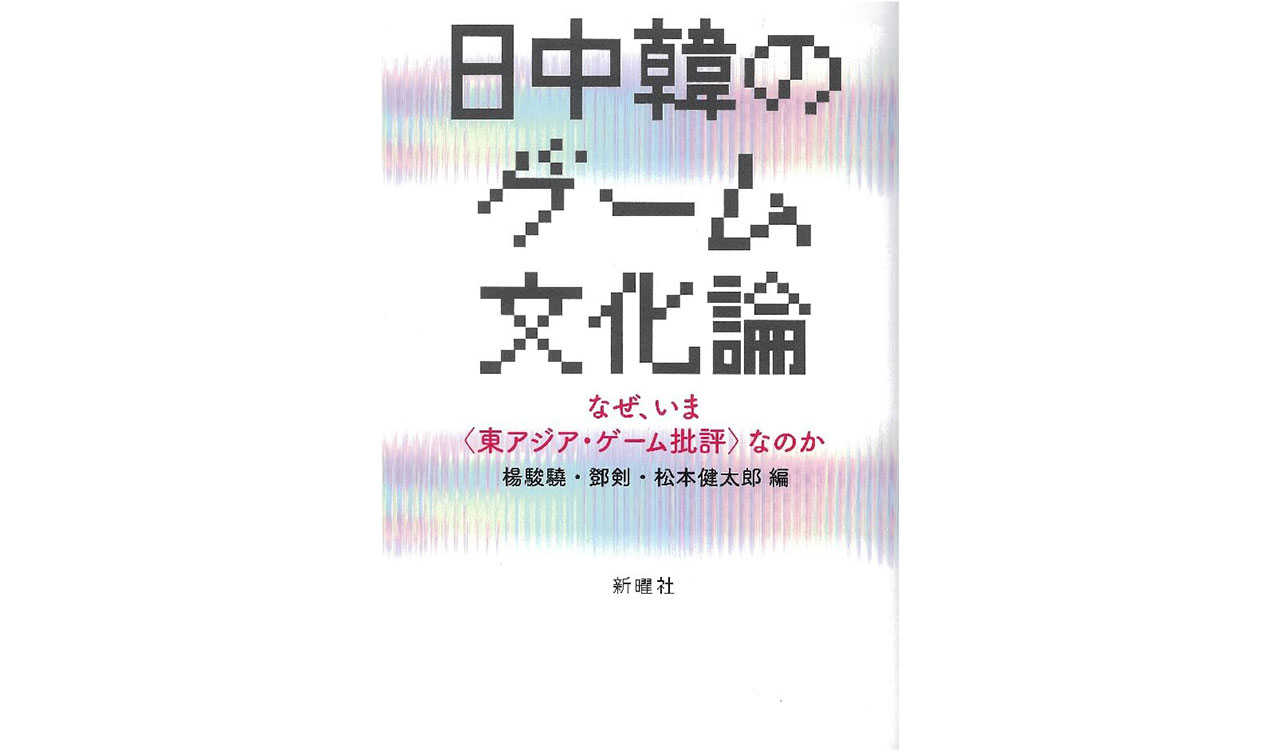中国と韓国、それぞれの研究者の視点から語られる各国のゲーム産業発達史
ここまでは本書の「日本のゲーム批評アンソロジー」としての側面を見てきたが、『日中韓のゲーム文化論』の白眉はやはり〈東アジア・ゲーム批評〉という枠組みにある。
本書のまえがきによると、日中韓の3カ国はゲーム産業における各国の台頭や、ゲーム制作の上での相互交流があるにも関わらず、人文学の領域で「東アジアのゲーム文化」という全体的な視座を獲得するには至っていないという。日中韓で行われているゲーム批評/研究は自国や欧米の視野に限定されており、東アジアという視野は皆無に近いとのこと。
人文学での現状について筆者は寡聞にして知らないが、ゲーム業界の全体的な傾向として「東アジア」という視野がほぼないのは、実感として納得できる。日本国内でも韓国や中国のゲーム企業の活動が増えてきて、資本やビジネス面でのつながりも含めた各国の関係がより深まってきているにも関わらず、である。
とはいえ筆者としては、日中韓がゲーム批評や研究の分野で相互理解、相互交流を行う上で、ことさらに互いの共通点を見出す必要はないとも思う。むしろ、相互交流を通じてお互いの違いを確認することにより、自己に対する理解と他者への理解がより深まるのではないだろうか。
その意味で非常に興味深いのが、本書の第15章と第16章だ。第15章「中国ゲーム史における社会思想の系譜──中国の現代化から資本論理まで」では中国のゲーム産業の発達史が、そして第16章「韓国ゲーム文化史の再構成」では韓国のゲーム産業の発達史が、それぞれ語られている。当該国の研究者の視点から語られたゲーム産業史は、それ自体が知識として非常に興味深く、日本との違いや共通点を確認する上で大いに役立つものだ。これらの国のゲーム事情に関心のある人は、ぜひ一読をお勧めしたい。
その上で、第15章では中国のゲーム産業史と1980年代から2020年代までの中国現代史が重ね合わされており、ゲームに対する意識の変化と中国社会における思想的な変遷が対置されている。このようにゲームを通して国家や国民の政治意識を語ることができるのは、日本との違いを感じるところだ。
筆者としては「それに対して日本のゲーム批評は……」といったことを言うつもりはまったくない。先に述べたように、日本のゲーム批評と中国のゲーム批評でこのような違いがあることを認識して、自己と他者の理解につなげることができれば有意義だと思う。
ただ一カ所、筆者が気になったのは、2010年代の中国で起こったバトル・ロワイアルゲームの流行を、中国社会で個人化された競争が過剰になり新しく現れた感覚的構造を示唆するものとして分析している点だ。しかしバトル・ロワイアルゲームは中国だけでなく、アメリカや日本でも流行しているわけで、第15章の執筆者である剣氏はそれをどのように見ているのだろうか。もっともこれは、日本に生きる我々自身が自己分析として考えるべき課題なのかもしれないが。
もうひとつ、これはあくまで余談だが、日本でも一部のゲームファンに「悪名」が轟いている中国製RTS『血獅』が、現地研究者の真面目な論文においても「中国ゲーム史上最悪の作品」と評されていたのは、思わず苦笑してしまった。
一方、第16章では韓国のゲーム産業史が語られているのだが、こちらは第15章のように同国のゲーム史と社会思想史を重ね合わせるという形ではない。むしろよりダイレクトに、ゲーム産業の発展と韓国政府による国内政策とがリンクして語られている。これはおそらく、韓国政府が1990年代以降にゲームをはじめとするエンターテインメント産業を国際戦略に基づいて奨励した経緯が反映されているのだろう。
ビデオゲーム以前に韓国社会に登場した「公衆遊技場」と、それに対する法規制から書き起こされた韓国ゲーム史は、日本との関係や共通点、そして違いを考える上でも、じつに奥行きのある内容となっている。
レベルの高い「知のバックボーン」が東アジアのゲーム文化を支える
本書第II部の中国パートと第III部の韓国パートから、先に第15章と第16章を抜き出して紹介したが、他の章についても見てみよう。
第11章から第14章はいずれも、中国の研究者がポストモダン思想を踏まえてゲームやプレイヤーのリアリズムを読み解いていく論文になっている。
これらの論文はまずなによりも、その人文学的アプローチのレベルの高さに圧倒される。論文の中ではフランスの哲学者メルロ=ポンティやポストモダンの旗手ボードリヤール、オランダの歴史家ホイジンガと、アナログゲーム業界の鬼才グレッグ・コスティキャン【※】が並び立って参照されており、そのこと自体がまず興味深い。
※グレッグ・コスティキャン
アナログゲームとビデオゲームの双方で活躍するゲームデザイナー。ウォーシミュレーション・ボードゲームの人気が高かった1970年代に、SPI社で『シーボイガンを喰った怪獣(怪獣征服)』『バーバリアン・キングス(魔法の大陸)』などのSFファンタジーボードゲームを次々に発表。1980年代には『パラノイア』『スター・ウォーズRPG』といったテーブルトークRPGを制作した。パロディ小説『ある日、どこかのダンジョンで』や、ゲームデザインに関する記事も執筆しており、2002年に発表した「I Have No Words and I Must Design」は、ゲームデザイン論の古典として広く知られている。
これらの論文から実感できるのは、中国でもゲームがある種の社会現象的な人気を博している背景に、本書で論文を執筆している研究者のような「知のバックボーン」が存在しているという事実だ。
欧米のゲームや世界的に人気の高い日本のRPGだけでなく、日本のノベルゲームが中国でも人気が高いこと、特に現地で正式にローカライズされていないような作品まで人気を集めていることは、筆者も知識として知っていた。だがよく考えれば、他国の言語で執筆された小説形式のゲームを楽しむためには、それを読解して文化的背景まで含めて理解できるだけの「知のバックボーン」が必要となるはずだ。
『日中韓のゲーム文化論』に掲載された中国の論文は、学術的研究なのだからレベルが高くて当然と考える人もいるかもしれないが、こうしたゲーム研究が世に出てくるだけの「知のバックボーン」が中国のゲーム文化、ひいては中国のゲーム産業を支える力になっていると考えるべきだろう。
あくまで筆者個人の感想としては、第11章から第14章はポストモダンのテクスト論にやや忠実すぎるのでは、とも思う。それでも第13章「デジタルな身体、擬似生命、そしてゲーム生態学──ゲームにおけるプレイヤーとキャラクターの弁証法」で展開されている「プレイヤーとキャラクターの関係が反転し、人形が人形使いを支配する」という論考は、特に興味を惹かれた。この論考は、本書の第8章から第10章で繰り広げられている日本のゲーム研究と共通するものでもある。
さて、本書第II部の中国パートがポストモダン思想による人文学的アプローチが強いのに対して、本書第III部の韓国パートは第16章のところで前述したように、対称的に実学的なアプローチが強くなっている。この特徴は日中韓のゲーム研究のスタンスの違いを考える上で非常に興味深い。
本書の第III部で特に注目したいのが、第17章「バースト・サーキットボード──草創期の韓国ビデオゲーム産業における模倣のインフラストラクチャーと技術的な実践」だ。これは1970年代後半に韓国の清渓川電子市場で行われた海賊版ビデオゲーム基板の製造が、同国のゲーム産業において初期の基盤となった事実を記録したオーラルヒストリーである。
内容が内容だけに、当時のゲーム産業に従事していた人は反発を覚えるかもしれないし、本論の冒頭で韓国のゲーム史でもこの時期については「前史」とだけしか語られていないことを示しているように、韓国国内でもおそらくはあまり触れたがらない話題だと思われる。とはいえ、それが歴史の一側面である以上は、こうして記録に残す姿勢そのものに意義があり、我々日本のゲーム関係者もここから学びを得ることは多いはずだ。
そして第III部の締めくくりとなる第18章「韓国ゲーム批評の軌跡と方向」は、前半部こそ韓国におけるゲーム関連出版物の歴史を追っているが、後半部では韓国の国内事情に留まらず「ゲーム批評とはどうあるべきか」という問題を広く問う内容になっている。ゆえにこの第18章は、〈東アジア・ゲーム批評〉を謳う本書全体の総括だとも言える。
以上、やや駆け足ながら『日中韓のゲーム文化論』の全体像を見てきたが、本書は価格も装丁も学術書的な位置づけであり、一般的なゲームファンにはやや敷居が高く感じられるかもしれない。だがゲーム批評や東アジアのゲーム文化に興味を持って本書に接する読者であれば、得るものの多い書籍なのは間違いない。
本書によって、欧米の常識に立脚したゲーム論や日本の国内事情だけに留まったゲーム批評とは異なる、東アジアのゲーム研究/批評に触れることができるのは素晴らしい。こうした東アジアのゲーム論に今後も継続的に接する機会が得られることを、日本でゲームについての文章を執筆しているひとりの人間として望んでいる。
東南アジア諸国も含めた「アジアのゲーム研究」にも将来的に期待したい
最後に『日中韓のゲーム文化論』の書評から離れて、本書に触発された筆者の個人的な考えを記しておきたい。
日中韓3カ国のゲーム産業における存在感と、本書にまとめられているようなゲーム研究/批評の実績を考えると、本書が〈東アジア・ゲーム批評〉という枠組みを打ち出しているのは、確かに納得できる。
だが、ゲーム研究におけるそうした日中韓のプレゼンスを認めた上で、あえて言わせてもらうならば、近い将来この3カ国以外のアジアの国々からも優れたゲーム研究は必ず出てくるだろうし、筆者としてはそうした日中韓以外のゲーム研究にも、もっと接してみたいと思う。
たとえばベトナムは日中韓と同じく広義の漢字文化圏に属する国であり、文化的な共通点は多い。またタイも日中韓との交流には長い歴史があり、ゲームをはじめとする日本の文化コンテンツに対する受容と理解は他の東南アジア諸国と比べても突出している。
しかもベトナムやタイでは近年、モバイルゲームやPCゲームが急速に発達してきている。ベトナムやタイでゲームについての人文学的研究や批評がどこまで進んでいるのか、筆者は残念ながら詳しくないが、これらの国の教育に対する熱量を考えれば、いずれこうした研究が世界に出てくるのは間違いないはずだ。
文化的な理解で言えば、インドネシアやマレーシア、シンガポールやフィリピンといった東南アジアの国々も、ゲームをはじめとする日中韓のポップカルチャーに対する関心がかなり高い。しかも現在、インドネシアからは『コーヒートーク』や『A Space for the Unbound 心に咲く花』、マレーシアからは『GIGABASH』など、注目すべきインディーゲームが相次いで登場してきており、これらの国々でのゲーム文化の広がりを実感できる。
イスラム文化圏でもあるインドネシアやマレーシアまで話を広げてしまうと、日中韓の「東アジア」と比較するのはやや無理があるかもしれない。とはいえ、欧米主導のゲーム研究に対峙する形で東アジアのゲーム研究という視座を打ち出すのであれば、さらにその先により広く、東南アジアなども含めた「アジアのゲーム研究」という枠組みも想定されてしかるべきではないかと、筆者個人としては思う。
もちろん先にも述べたとおり、ゲーム産業における日中韓のプレゼンスを考えれば「東アジア」という括りに大きな意義があるのは間違いない。さらに、本書のまえがきに記されている「「東アジア」は、いかにして可能なのか──これは近代の歴史が私たちに残した深刻な問いである」という言葉には、筆者も深く同意する。
その上でゲームを通じて日本だけでなく中国や韓国、さらにアジアへと思いを馳せることができただけでも、本書が〈東アジア・ゲーム批評〉を謳った価値があるのではないかと思うのだ。
2024年2月にYouTubeのポケモン公式チャンネルで、1本の短編アニメーションが公開された。日本でも話題となったアニメーション映画『羅小黒戦記』を制作した中国の寒木春華(HMCH)スタジオが手がけた「ただいま」である。
このアニメーションでは、人間と多種多様なポケモンが共存する『ポケットモンスター』の世界観と、中国の旧正月である春節に多くの人々が故郷へと帰省する「民族大移動」とも呼ばれる中国独自の風習が、まったく違和感なく融合している。
東アジア、そしてアジアにおけるゲーム文化を通じた相互影響と相互理解、その過程での差異の確認。そうしたことは実現可能であり、そこには大きな意義があることを、わずか2分間程度のこのアニメは実感させてくれるのだ。