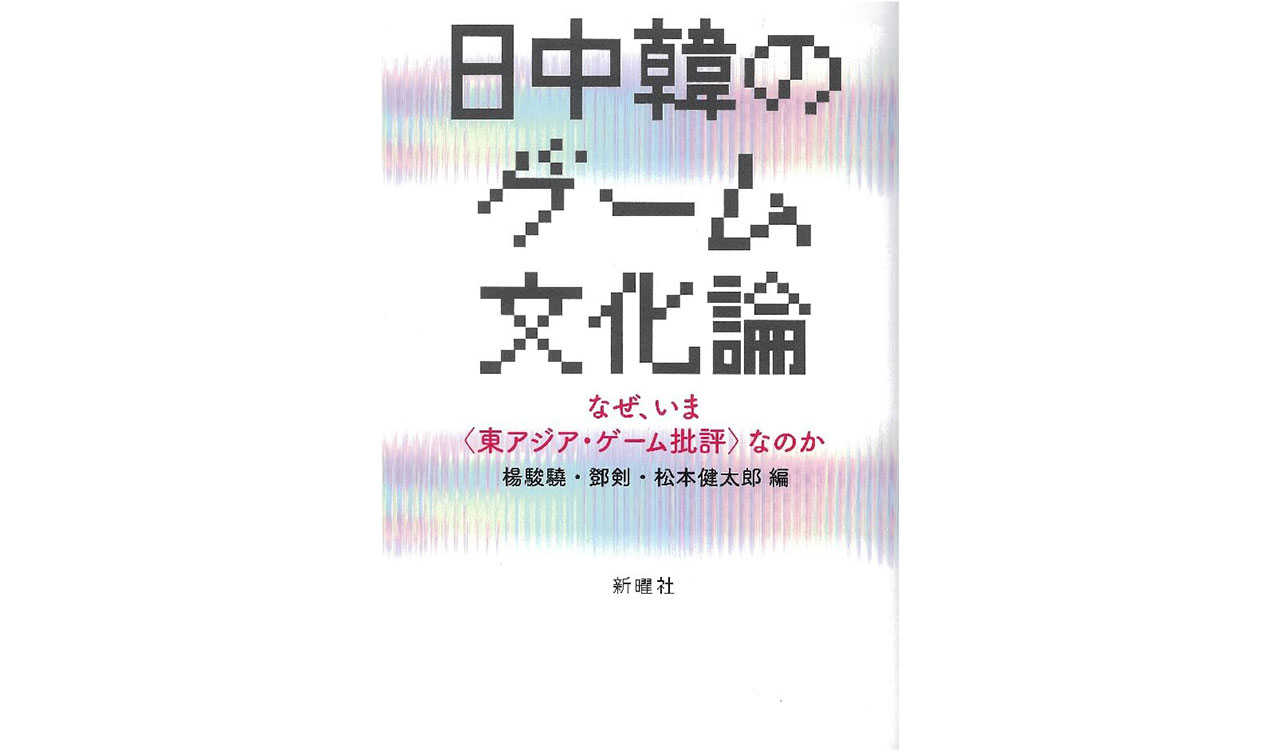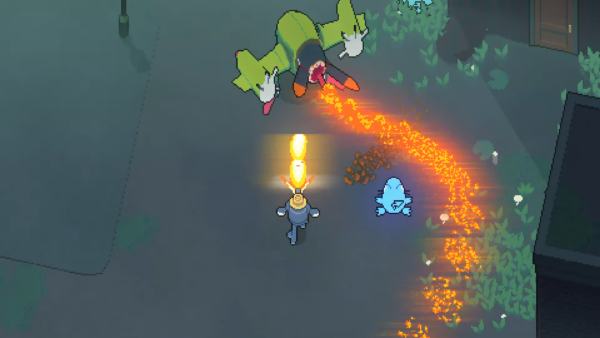2024年3月に新曜社から『日中韓のゲーム文化論 なぜ、いま〈東アジア・ゲーム批評〉なのか』が刊行された。この書籍では、1980年代から40年間に渡って発表されてきた日本のゲーム批評を集成しているのに加えて、中国や韓国の最新ゲーム研究論文も収録されている。
副題にもあるように〈東アジア・ゲーム批評〉という概念が打ち出されている本書の内容を見ていくことで、日本のゲーム研究と中国や韓国のゲーム批評の何が共通し、何が異なるのかを考えてみたい。ゲームにおいて「東アジア」という枠組みは、いったいどのような意味を持つのだろうか。
文/伊藤誠之介
日本のゲーム批評を集成した「ゲーム批評アンソロジー」でもある一冊
新曜社から刊行された『日中韓のゲーム文化論』は、副題に〈東アジア・ゲーム批評〉とあるように、日本、中国、韓国の研究者によるゲーム批評18本を収録した論文集だ。
本書のタイトルを目にした際に、「日中韓」という括りにまず目が向くのは当然だろう。だが本書はそれだけでなく、1980年代から現在(2020年代)までの日本のゲーム批評を集成した「ゲーム批評アンソロジー」である点も大きな特徴だ。この2つの特徴は、本書の成り立ちが深く関係している。
まえがきによると、本書は中国で2020年に出版された日本のゲーム批評アンソロジー『探寻游戏王国里的宝藏──日本游戏批评文』を基盤として、そこに韓国と中国の最新ゲーム研究論文を追加したものだという。具体的には、本書第1部の日本パートに10本、第II部の中国パートに5本、第III部の韓国パートに3本の論文がそれぞれ収録されている。
ちなみに本書の成り立ちや構成を記したまえがきは、新曜社の公式ページで試し読みできるので、気になる方はぜひ目を通してみてほしい。
そのため「日中韓」の括りをいったん脇に置いて「日本のゲーム批評」だけに注目しても、本書の第I部はもともと海外に日本のゲーム批評を紹介する役割を担っていただけに、1980年代から約40年に渡る日本ゲーム批評の流れを概観できるようになっている。ここにまず本書の第一の価値がある。
日本ゲーム批評40年の積み重ねを概観できるアーカイブとしての価値
「日中韓」という部分については後で改めて語るとして、「日本のゲーム批評アンソロジー」である第I部の内容をもう少し詳しく見てみよう。
中川大地氏による第1章「日本ゲームはいかに語られてきたか──ゲームの批評/研究がめざすもの」は、1980年代からの日本ゲーム批評史を整理した内容で、本書の導入には非常に適した論文だ。
初期のアーケードゲームやPCゲームから、家庭用ゲーム機の普及と物語性の強いゲームの登場、そしてオンラインなどを介したコミュニケーション要素の強いゲームと、ゲームそのものの変化に合わせてそれを語る言葉もよりふさわしい形に変化してきたことがまとめられている。
ちなみに本論は、中川氏の著書『現代ゲーム全史──文明の遊戯史観から』が刊行された際に電ファミニコゲーマーが行ったインタビュー記事を、中川氏自身が全面的に加筆修正したものである。
そういった経緯で本書にも、元記事の聞き手である電ファミ編集長のTAITAI氏や当時の副編集長だった斉藤大地氏、元記事で構成を担当した筆者の名前が掲載されているが、本論はあくまで中川氏の論であることを付記しておく。
さて、「日本のゲーム批評アンソロジー」としての本書の価値はまずなによりも、第2章に中沢新一氏の歴史的な論文「ゲームフリークはバグと戯れる」が収録されている点だ。
ファミコンが登場する以前の1980年代前半、中沢氏はアーケードゲームの『ゼビウス』にいち早く注目して、ビデオゲームに物語性を喚起する力があることを見出しただけでなく、のちに『ポケットモンスター』を生み出すゲームフリークの登場をも見据えていた。そうしたこの論文の意義については、本書の第1章でも解説されているとおりだ。
本論を2020年代の現在に再読すると、ビデオゲームがまだ誕生したばかりの時代にゲームやそれを取り巻く事象への驚きをストレートに語っているがゆえに、その言葉は今なお古びていない。さらに、ピンボールマシンの『シャングリラ』からチベットのシャンバラ幻想を読み取るといった中沢氏の文章そのものに、受け手の想像力を刺激する力がみなぎっており、一時代を築いた批評家の凄味を改めて思い知らされる。
ところで、筆者が今述べた第2章への評からも逆説的に分かるように、第I部はあくまで約40年に渡る日本のゲーム批評の流れを示すアンソロジーであり、掲載された論文すべてが必ずしも最新のゲーム研究というわけではないことは、ここで強調しておくべきだろう。
たとえば、第3章「オタク論──カルト・他者・アイデンティティ」の初出は1992年であり、論文中で例として挙げられている「幼女連続殺人事件」や『カルトQ』といったトピックは、いずれも1980年代後半の社会事象だ。
「オタクは仕事と趣味の価値付けが逆転している」といった、本論で提示されているオタクに対する見方が初出の当時に確かに存在していたことは、筆者自身も当時のオタクのひとりだっただけに懐かしく思い出される。だが、そこから日本社会そのものが大きく変化した現在でもそうした見方が通用するかというと、さすがに厳しいと言わざるを得ない。前述したようなかつての“正論”が空々しく聞こえてしまうぐらい、すでに一億総オタク化が進んでいるのだから。
また、東浩紀氏による第5章「萌えの手前、不能性に止まること──『AIR』について」の初出も2004年である。本論はKeyのアドベンチャーゲーム『AIR』において、シナリオレベルで強調される「父の不在」とゲームシステム上での「プレイヤーの不在」が重ね合わせられていることを指摘する、じつに切れ味の鋭い内容で、発表当時はかなりのインパクトがあったと記憶している。
とはいえ本論の結論部では、『AIR』が「批評的」な作品であることにどこまで自覚的なのか、この時点ではまだ判断が保留されている。これはあくまで年月を経た後付けの理屈だが、『AIR』のクリエイターである麻枝准氏がその後に発表した作品を見れば、そうしたことに自覚的であったのは明白だ。ゆえに2020年代現在の視点からすれば、本論の結論部はまた違ったものとなり得るはずだ。
以上の例からも分かるように、本書の第I部は約40年間に渡る日本ゲーム批評の流れを示すことに主眼が置かれており、収録された論文はその発表時点における論考を記録したアーカイブである。今を生きる読者としてはこのアーカイブを通じて、日本のゲーム批評がこれまでにどのような考察や議論を積み上げて2020年代の現在にまで至っているのか、という点を第一に読み取るべきだろう。
『ポケモンGO』の登場から、さらにその先へと踏み出す最新のゲーム批評
その意味で、ゲームをどのように読み解くかという方法論のガイダンス的な側面を持つ第7章「様式化されたシミュレーション──JRPGの「不自然さ」を考える」を経た先にある、本書の第8章から第10章は、これまでの日本ゲーム批評を踏まえた現時点での最新のゲーム研究だと言える。
第8章「メタゲーム的リアリズム──批評的プラットフォームとしてのデジタルゲーム」では、メタゲームやノットゲームといった概念を用いることで、「ゲームのような現実」が日常化した先にある「ゲームではない何か」の存在を指摘している。
続く第9章「戦いをつくりかえるゲーム」では第8章での論考をさらに先へと進めて、ゲームと現実の戦争との対比を通じてゲームの「前提」自体に目を向けることで、「ゲームとは何か」を改めて問い直している。
しかもこの2つの論文は、第1章において中川大地氏が2016年の時点で記した結論から、さらに次のステップへと踏み出すものでもある。
第1章では、現実世界そのものを巨大なゲームフィールドとする『ポケモンGO』が登場したことを受けて、「ゲームを語ることが社会を語ることと同義になる」としていた。それに対して第9章では、現実をモデルとするゲームの「前提」を疑うことで、「ゲームを語ることは現実をつくりかえる契機になり得る」としているのだから。
そして第I部の締めくくりとなる第10章「あなたは今、私を操っている。──「選択分岐型」フィクションの新たな展開」では、第9章で語られた「ゲームの前提を疑う」思考が、ルート分岐による選択分岐型のフィクションに対して向けられている。
ここでは、いわゆるゼロ年代的な選択分岐型のフィクションが「トゥルーエンド」という形で単一的な現実の肯定へと向かっていたのに対して、近年(2010年代後半)は『Detroit: Become Human』やNetflixの『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』のように、操作する者と操作される者の関係性を前景化することでプレイヤーに実存的な問いを突きつける作品が登場している……と指摘している。ゲームを操作する我々自身の立場をも疑う本論は、本書の第8章から積み上げられてきた議論のひとまずの到達点と呼べるものであり、非常に刺激的な内容だ。
加えて、第10章の中で「操作する者と操作される者の関係性を前景化する」作品のひとつとして採り上げられているのが、中国のインディーゲーム『WILL −素晴らしき世界−』だというのも、本書のもうひとつの特徴である〈東アジア・ゲーム批評〉を考える上で、興味深いポイントと言えるだろう。