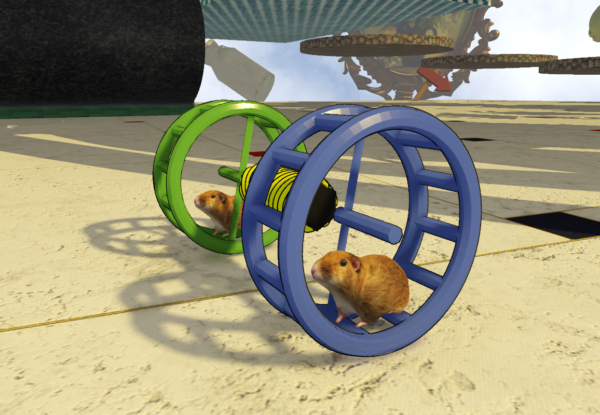「遊び」論の哲学書を本当に読んでいた!
――お二人の話を聞いていると、ゲームフリークの血筋ってあるなと思うのですが、どんな薫陶を受けてきたのですか? 以前、増田さん【※1】に取材した際に、『遊びと人間』【※2】と『ホモ・ルーデンス』【※3】はゲームクリエイターの必読書だ、と言われて「ホンマかいな」と(笑)。

オランダの歴史家、ヨハン・ホイジンガによる1938年の著作。語義は「遊ぶ人」というもので、「遊び」こそが人間の本質であり、その活動を支え、文化を生み出すものと規定。この視座から、ヨーロッパ文明の歴史を考察している。
※2 遊びと人間(講談社・1990、画像右)
フランスの社会学者ロジェ・カイヨワによる1958年の著作。前述したホイジンガの『ホモ・ルーデンス』の影響を受け、「遊び」を定義し、その分析を起点に文化全体を考察する名著。「遊び」について、競争(agon)、運(alea)、模擬(mimicry)、めまい(ilinx)という有名な4分類をしている。
※1 増田さん
増田順一。1968年生まれ。日本のゲームクリエイター、作曲家。株式会社ゲームフリーク取締役開発部長。株式会社ポケモン取締役。『ルビー・サファイア』以降のディレクター・プロデューサーを務めるほか、『クインティ』や『ヨッシーのたまご』、『マリオとワリオ』などの多くのゲームフリーク作品の楽曲を手がけた。
大森氏:
ああ、読まされましたよ。
――え、ホントにゲームフリーク社内では必読書なんですか(笑)?
いや、増田さんに取材したときに、もう「そもそもテレビゲームでさえも、テレビを使った遊びでしかない」なんて言われながら、延々と「遊び」論【※】を語っていただいたことがあるのですが……そんな議論を本当に社内でやってるのかと、さすがに疑ってまして。
※「遊び」論
人間の「遊び」を主題に研究する学問。Ludology(ルドロジー)。学際性が強く、その知見は児童心理学、文化人類学など様々な学問分野にまたがる。ヨハン・ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』(1938年)とロジェ・カイヨワの『遊びと人間』(1958年)は、この分野に多大な影響を与えた古典的な著作。実際にゲーム開発に携わるゲームクリエイターから、しばしば名前が挙がる本でもある。
大森氏:
あの二冊は、プランナーは読みます。
議論も、もちろんやってますよ。「遊びとはなんなのか」や「これは遊びなのか」は、普段から話し合います。
尾上氏:
プログラマーの本棚にも、普通にありますよ。
――社内で「これは遊びなのか」という議論が交わされるのは、なんかヤバいですね。どういうとき、そういう議論になるんですか?
大森氏:
例えば、子供に対して「いないいない、ばあ」をやったら喜びますよね。これは、一体なんなのかということです。
――な……なるほど。
大森氏:
一体、どこまでが「いないいない、ばあ」なのか。例えば、子供が産まれた人は観察してみるといいのですが、実は横顔で「いないいない、ばあ」をすると、ダメなんです。笑ってくれない。どうも正面から顔を向けていないと、赤ん坊は喜ばないんです。
――えー、そうなんですか!
大森氏:
「想像したものに対して、出てきたものが一致するか」に、赤ん坊は喜びを覚えているようなんです。つまり、期待していたものが登場した喜びは、凄く根源的なものなんですね。だから、『ポケモン』でいえば、草むらから何かが出てくるとき、自分が想像したものが出てくるか否かは、人類が共通して面白いものなんですよ。
 |
そうすると、エンカウントしたときに、パッと真っ黒いシルエットを出して、スッてちょっとタメを入れる演出も、まさに「いないいない、ばあ」の期待を起こさせる機能があると理解できるじゃないですか。
――なるほど! 色が違うと嬉しかったりしますしね。
大森氏:
あのエンカウントは、まさに「いないいない、ばあ」の遊びそのものです。実は、「何をもって人は喜ぶのか」は、意外と子供と会話していると、わかるものなんですよ。
上司の心の中に、ポケモンが“住んでいた”?
――あの、一つお聞きしたいのですが、大森さんはそういうことを考える人だからゲームフリークに来たのか、それともゲームフリークで教わったのか……ちょっと気になります。
大森氏:
僕は専門学校でプログラムやっていて、学生時代に『焼肉奉行』というゲームを出しました。

(画像はPlayStation®Storeより)
この会社の面接でも、それを挙げ「市販されているゲームを作っている」と言い採用されています。ただ、当時ゲームを作りながら、プログラムを組むよりもゲームを考えるほうが、自分は楽しいことに気づいたんです。そんなときに、プランナーを募集しているのを見つけて、早速応募しました。
中に入ってマップ作成時に多く関わったのが、西野【※】という人です。彼からは本当に色々なことを教わりました。
※西野
西野弘二。プランナーとして、企画、データ管理を担当。ポケモンの出現率や、世界観の設定を行っている。
――西野さんって、ファンにはカビゴンのモデルになったことで有名な方ですが、『ポケモン』のバトルデザインを森本さんと一緒に行われている方ですよね。
大森氏:
ええ、森本がバトルの強さの「戦略性」を調整するのなら、西野は世界観を踏まえて「キャラクター性」を調整するんです。この「戦略性」と「キャラクター性」のバランスが、『ポケモン』は絶妙なんですね。
尾上氏:
あの二人は、本当に彼らにしか作れないような凄いデータを産みだしていると思います。本当にデータの一つ一つに「なぜそうなっているのか」が考え抜かれて、徹底的に調整されているんですよ。
 |
簡単なところでは、バージョンごとに登場するポケモンの違いは意図的だし、確率なんかも凄く考えられています。あるいは、もっとわかりにくいところでは、色違いのポケモンのような、ユーザーがそこに向かって頑張る要素を入れるときでも、「難易度をこういう曲線で上げれば、この辺りで全員が手に入るようなバランスになるな……」みたいなことを真剣に考える。データとは、ここまで考え抜くものなのかと、ゲームフリークに入って知りました。
大森氏:
まさにそういう戦略性の観点から、データを作り込んでいくのが森本ですね。そして、西野は、それを理解した上で、キャラクター性を徹底的に作っていくんですよ。西野の中には、ポケモンが本当に生きているんです。
――心の中で、ポケモンの姿がありありと想像できていると言うことですか?
大森氏:
森本が「こいつはこの技を覚えていないとダメだ」と戦略の観点から言っても、西野は「この外見で、ここに住んでいたら、その技ではない」とポケモンの観点で徹底的にこだわる。それは、バトルのデータだけではありません。「魚であっても淡水魚なので、この近くには絶対きれいな池がある」みたいなマップ構造までこだわってくる。
それは、彼の中にポケモンが住んでいるからです。だから、そこがどんな場所で、どんな生き物が住んでいて、どういうふうに描かれるべきなのかを最終的に決められるんです。

(画像は『ポケットモンスター サン・ムーン』公式サイトより)
僕なんかは最初、西野の下で、自宅の周囲のマップに「キレイじゃないかな」と思って池と滝を作ったら、「君の家の近くに滝はあるのか?」と言われてしまって……(笑)。
西野は「そんな場所を、ほとんどのプレイヤーは自分の家の近くだと思うはずがない」と言うんです。「滝があるならば、きっと冒険が進んだ先の奥だろう」と。そういう言葉に、当時の僕は「ああ、なるほど」と納得していました。
――西野さんは、おそらく『ポケモン』の雰囲気の凄く大事なところを統括されている方なのでしょうね。実際、『ポケモン』のマップって評価が高くて、道路の番号が遠くに行くほど増えていくギミックとかも、凄く有名じゃないですか。距離を感覚的にわかるように表現してきたのは凄いと思います。他のゲームでも、あまり見たことがない。
大森氏:
あれは子供が遊んでいても、1ステージ進んだような感覚がありますね。あれ自体がステージっぽい概念で認識されてることも意識しながら作っています。
というのも、僕としては聞いただけでは納得できなくて、実際に子供が遊んでいるところを観察したんです(笑)。そうしたら、2番道路のことを「2ステージクリアした」と言っている子供がいて、「そうか、アクションゲームのステージと同等の概念として捉えられているんだな」と理解できました。おそらく、彼らにとって街はアクションゲームで言うところのゴールで、回復して次のステージに進むイメージなのだと思います。以降は、そういう自分なりの理解を、スタッフに伝えるようにしています。
 |
「トンチを使え!」
――なるほど……しかし、ちょっと話を戻すと、森本さんと西野さんのパラメーターの二つの捉え方って、僕らも取材の中でゲームクリエイターからしばしば聞くんです。ただ、そのたびに思うのは、ある種の「数理的問題」としてのパラメーター調整と、物語における「キャラ立て」のためのパラメーター調整は結構噛み合わないんじゃないかということでして……どうすり合わせるのかな、と。
大森氏:
例えば、デザイナーに「爪をつけてくれ」と頼んで解決することもありますよ。つまり、ゲームバランスの要請から、むしろポケモンのデザインを変えるわけです。

(画像は『ポケットモンスター サン・ムーン』公式サイトより)
ゲーム初心者の人でも、外見一発で「爪で攻撃してくるんだな」とわかるビジュアルになるだけで、一気に解決することはあります。逆に「この外見では全てイケてしまうな」となれば、のうりょくを全体的に下げたりする。そういうバランス調整は大事にしていて、この辺はまさにゲームならではのキャラクター性ですね。
――ゲームフリークって、「絵」もすごく大事にしているイメージがありますが、ゲームデザインの調整過程でも絵が大きな役割を果たすんですね。ゲームのビジュアル一発で納得感が生まれるということは、キャラクターやマップの絵もまた、ゲームデザインの欠かせない一部なのかな……と。
大森氏:
そうですよ。僕は、よく「ストレートに作ろうとするな。トンチを使え」と言います。なんなら、ダジャレで笑わせて「ごまかして」解決したっていいんです。普通にやるのが、何よりも一番面白くない。僕自身、ディレクターとして、そういうダジャレを言い合いながら「面白いじゃん」となれるくらいの環境を作るように努力しています。

(画像は『ポケットモンスター サン・ムーン』公式サイトより)
例えば「カキの試練」は、ちょうどリソースが足りなかった時期で、メッセージとキメポーズを作るくらいしかできなかったんです。そこで考えたのが、踊りを当てるゲームです。こういう解決の仕方が、ゲームフリークのやり方なんです。
——あれはリソースが明らかに安く上がってるのに、すごく面白いですよね。
大森氏:
そうです。シンプルですが、キメポーズの種類を増やせば沢山面白いものが作れます。これは容量が限られたリソースの中で面白さを広げるとても良いアイディアだったと思います。
 |
僕らの場合は、『ポケモン』シリーズのゲームを取り巻く多くのメディアでの展開などに合わせて、細かにスケジュールを組んでゲームを作るような厳しい条件があることも多い。だから、どうしたら解決できるかは、もうあらゆる手法でやればいいと思ってます。
それは設定を変えることかもしれないし、キャラクターを変えることかもしれない。僕はその時々で、担当する人材が得意なことに合わせた解決法を考えます。ですので、担当者にあわせてその場で企画内容を変更することもあります。
――ジャズのアドリブ演奏みたいですけど、逆に総合的なゲーム力が問われるやり方でもあるし、日本人らしいツーカーでのコミュニケーションも求められる気はしますね。
大森氏:
そこはゲームフリークなんで、ゲーム好きが集まってきますから(笑)。議論もしますが、ある程度は共通認識としてツーカーでコミュニケーションできるところはあります。
――そういう意味では、最近『ゼルダ』新作の取材をしまして、開発者全員で遊ぶことでコミュニケーションロスを減らしたという話があって、凄く日本的な解決策だなあと思ったんですよ。ゲームフリークはどうですか?
尾上氏:
働く中で培われる共通認識のようなものがあって、それがあるおかげでコミュニケーションのロスは少ない気がしますね。逆に、開発者同士に共通認識がない状態だと、色々と大変です。
 |
実際、『ギガレッカー』では、最初プロジェクトに自分と伊藤しかゲームフリークの人間がいなかったので、二週間に一回みんなで集まって、お菓子を食べながらみんなでプレイして、「ここの色は背景と分かれてないね」とか指摘し合いながら、チーム内で共通言語を作っていきました。
大森氏:
実際のところを言えば、ゲーム開発は複雑化しているので、分業化は進めざるをえない部分はあります。でも、議論に議論を重ねて作ることこそが、ゲームフリークらしさだと思うんです。
ここのスタッフって個性的な人が多くて、あまり管理された集団ではないです。その個性ある人たちが「面白さ」という共通価値観で話し合ったときに、「じゃあ、こうしたらどう?」が積み重なって、とてつもない連鎖が生まれる。そういう、もの凄い面白いものが生まれる瞬間があるんですね。
 |