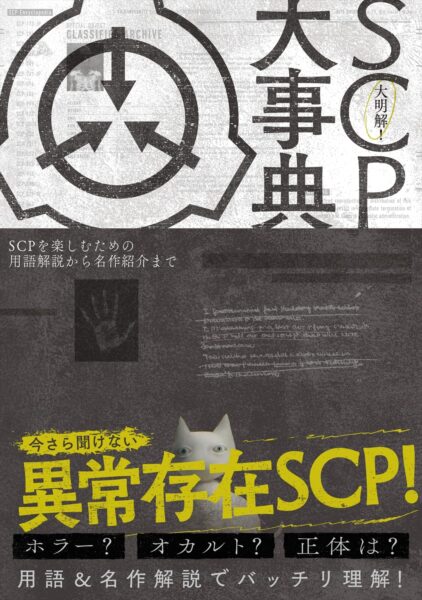電ファミでは、かねてから「日本のゲームAIの歴史」に迫る記事をお届けしてきた。
たとえば、ゲームAIの起源と言われる『パックマン』の生みの親・岩谷徹氏や、麻雀にAIを持ち込んだ『ぎゅわんぶらあ自己中心派』の開発者・宮路洋一氏にご登場いただき、彼らの歴史的証言をインタビューの形でまとめている。
“世界最古”にして現代ゲームAIの先駆。21世紀に『パックマン』が再評価される理由を、作者・岩谷徹氏×AI開発者・三宅陽一郎氏が解説【仕様書も一部公開!】
面白さの評価関数は作れるか? 麻雀対局中の思考を真面目に再現したらゲームAIになっていた──ゲームアーツ創業者宮路洋一氏が説く試行錯誤の大切さ、そして80年代【聞き手:三宅陽一郎】
そもそも、なぜ日本のゲームAIの歴史を電ファミは取り上げ続けているのか──このテーマに心惹かれない方に向け、あらためてその理由をお伝えさせていただきたい。
発端は、最先端のゲームAI研究者として知られ、数々のAI関連のインタビューの聞き手も務めていただいている・三宅陽一郎氏への以下のインタビューだった。
21世紀に“洋ゲー”でゲームAIが遂げた驚異の進化史。その「敗戦」から日本のゲーム業界が再び立ち上がるには?【AI開発者・三宅陽一郎氏インタビュー】
かなり大雑把に要約すると、この記事では、それまで世界的に存在感を示していた日本のゲーム産業が、21世紀に入ってからシビアな状況に追いやられたのは、じつは「AI技術の軽視」という問題が側面のひとつとしてあったのではないかということが語られている。
ゲームの3D化が進むと、2D時代には当たり前だった「すべてスクリプトで動かす」開発手法の前に技術的な限界が立ち塞がったのだ。そこで日本が手をこまねいているあいだに、AIをはじめとする3D時代のための技術や手法が海外で著しい発展を遂げていった経緯がある。
電ファミが三宅氏とともに「ゲームAI」を取り上げ続けているのは、そうした日本のゲームをめぐるひとつの問題意識による。
実際、知見の共有が盛んだった海外に比べ、当時の日本のゲームAI界隈はまさに“暗黒大陸”のように閉ざされており、個々の実績がバラバラと点在しているだけだった。
そのひとつひとつを掘り起こして一本の線で繋げていく作業の果てに、今後の国産ゲームを考えるうえで必要なひとつの道筋が描けるのではないか──大仰に言うなら、そうした意図のもとでコツコツと話を伺って回っているわけだ。
……さて、今回取り上げる人物は、このテーマの本丸とも言うべき相手だろう。なぜならその人物は、言わば「AIそのものをゲームに落とし込む」という歴史的にも稀有なゲームを作り、さらに現在は世界で唯一のゲームAIを専門とする会社を立ち上げているからだ。
その人物の名は、モリカトロン代表・森川幸人氏。

森川氏は、株式会社ポケモン代表取締役社長の石原恒和氏にコンピューターを教えられたことをきっかけに当時の最先端だったCG技術の道を歩み、伝説のテレビ番組『ウゴウゴルーガ』などで活躍したあと一転して、プレイステーション黎明期の熱気漂うソニー・コンピュータエンタテインメント(当時)から、『がんばれ森川君2号』、『アストロノーカ』などのAIゲームを送り出している。
- 『がんばれ森川君2号』 (画像はがんばれ森川君2号 | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイトより)
- 『アストロノーカ』(画像はアストロノーカ | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイトより)
2004年にAI研究者を志してゲーム業界に入った三宅氏によれば、21世紀に入るまでに国内のゲーム史に表立って刻まれたAIに関するテキストと言えば、森川氏が執筆して人工知能学会に掲載されたふたつの論文と、当時「釣り仲間」であったという糸井重里氏主宰のサイト「ほぼ日」に掲載された森川氏の記事程度という。
そのほぼすべてが森川氏によるのものであったことからも、森川氏の業績がどれほどの凄さか判るだろう。実際、「当時はそれだけが国内ゲームAIの手がかりだった」と三宅氏は言う。
本稿では、おもに森川氏の手掛けた『がんばれ森川君2号』、『アストロノーカ』、『くまうた』のゲーム開発の様子を伺いながら、その功績にできる限り迫った。前人未踏の領域で氏は何を思い、何を進めていたのか。
じっくりとご覧いただきたい。
※電ファミでは、「ゲームAI用語辞典」というwikiを開設している。これはゲームAIを理解するうえで重要となる用語の意味や歴史、用例などを解説するもので、ぜひ本記事を理解する一助にしていただければ幸いだ。
聞き手:三宅陽一郎、電ファミニコゲーマー編集部
カメラ:佐々木秀二

「森川さんの仕事はいまだに世界の頂点です」
──今日の取材は、以前行った三宅さんへのインタビューが発端となっています。
それは21世紀の洋ゲー史を「AI」という観点で追うことで、「日本のゲーム産業がなぜ苦戦を強いられていったのか」という命題に対するひとつの回答を浮かび上がらせるものでした。
三宅陽一郎(以下、三宅)氏:
あのインタビューは、予想以上に凄まじい反響をいただきました。それこそゲーム業界に限らず読まれ、読んでくださった皆さまのAIに対する関心を感じ取れたいい機会となりました。ありがとうございます。
──あのときはおもに海外の状況について語っていただきましたが、そこで唯一、日本国内に残された業績としてピックアップされた論文がありましたね。それが、今日お招きした森川幸人さんが手がけたゲーム、『がんばれ森川君2号』と『アストロノーカ』について、森川さんご自身で書かれた論文でした。
三宅氏:
『がんばれ森川君2号』や『アストロノーカ』、そして『くまうた』などの森川さんが当時残された仕事は、いまだに世界のゲームAIの頂点なんですよ。もし当時の海外の開発者が森川さんの仕事を見ていたら、それはもう、めちゃくちゃびっくりしたはずなんです。
ただそのAI技術の情報は、残念なことに英語でも読める形としては、表立って残らなかったので、その後、歴史的には、森川さんの業績は海外のゲームAI技術の文脈とリンクしていかなかった。
先のインタビューでは洋ゲー史を支えたAIの凄さを語りましたが、僕としては語りながらも「国内にすでにこんな偉業があるのに」という思いで、正直に言って悔しかったんですよ。
──それほどまで。
三宅氏:
自分はもともと「AIをやる」ために2004年にゲーム業界に入ったのですが、そのときに過去の国内のゲームAIの業績をいろいろと調べても、まるで歴史が見えてこなかったんです。
当時はいまほど資料も開発者によるコミュニティもなく、基本的にそれぞれの会社の中だけに知見が積もる、閉じていた時代だったので。
そんな国内の状況に対し、海外では毎年知見がアップデートされ、ネット上でも発言がなされるので、大きな流れがよく見えたんです。ですから僕自身の仕事も、そうした海外の文脈に沿うことになりました。
そこから見える2004年から2010〜11年ごろまでのゲームAIの歴史というのは、おもにFPSを通して語られてきており、その後になってさまざまな分野にスピンオフしていくんです。でも日本ではFPSがほとんど作られなかったので、そのゲームAIの歴史の流れの中に日本はほとんど見当たらないんです。
その善し悪しはさておき、海外は基本的にひとつのスタジオでずっと同じゲームを作っています。バンジースタジオだったら『HALO』を作っているし、ユービーアイソフトだったら『2』以降の『Far Cry』を作るというように。
だからこそゲームエンジンの形がちゃんと固まるし、AIもどんどん発展するんです。
──それに対して、日本はどうなのでしょう?
三宅氏:
日本はゲームごとに新しいゲームデザインを切り拓いていく。すると、そのゲームごとにAIを構築することになるから、なかなか知見が積み上がっていかないんですね。
 |
そうした事情もあって、海外のFPSを主体とするゲームAIの文脈と日本の多様なゲームデザインの文脈は二分され、いまだに交わっていないと言えます。僕は西洋のゲームAIの流れを受けていまの仕事をしていますが、もうひとつのアイデンティティとして「日本のゲームデザインを主体とするゲームAIの流れ」を打ち立てたいんですね。
それをしないことには、日本らしさの上に成立するAIの開発というのはできないと思うからです。
なぜそうした日本のゲームデザインに即したAIを求めるのか。これは僕がゲーム業界に入ったときもまさにそうだったんですが、そうしたものがないと、若い人が何をやっていいのかが全然判らないんですね。
たとえば、CGの技術だったら、CG技術の最先端までの流れというのは、SIGGRAPHやゲームカンファレンスで可視化されていますので、社会人1年目でも解るようになっていたり、それこそその彼らが最先端に突っ込まれたりしています。
それに比べてAIは、流れのない状態で「ぽつん」と取り残されている状態。AI研究の全体像を追っても、日本のゲームデザインとはまた違った海外の話ばかりで。FPSを作るというのなら、それでいいんですが。
──だからそこで、日本的なゲームAIを考えるうえで欠かせない足跡を残された森川さんに、今日はお話を伺おうということですね。
三宅氏:
ええ。森川さんは国内ゲームAI史の出発点のような存在なんです。というのも『がんばれ森川君2号』や『アストロノーカ』って、言ってしまえばAIそのものをゲームにしたもの。
ゲーム内のAIに学習を与えるプレイヤーですら、ある意味大きなAIの一部として組み込まれている。そんなゲームはそれまでも、そしていまなお、ほとんどありません。
森川さんの仕事の凄さはそれだけじゃありません。たとえばAIのひとつである「ニューラルネットワーク」【※】って、歴史的にはそもそも「分類器」として発展していったものなんです。
「身長や体重などのデータを入れると健康かそうでないかが判る」というようなイメージですね。
ただそれをリアルタイムに動作する「知能」として扱う発想自体は、いまとなっては当然なんですが──『がんばれ森川君2号』以前にはそこまでのものがなかったことだったんです。少なくともゲームタイトルの実装例は見当たらなかった。
──『がんばれ森川君2号』は普遍的なAIの歴史の中でも異質なゲームだったわけですね。
今日はそれらを手掛けた森川さんという人物を知る場であると同時に、日本のゲームAIそのものを知る場でもありますので、記録として残す取材にできればと思っております。
※ニューラルネットワーク
ニューロン(神経細胞)の伝達構造をコンピューター上のシミュレーションによって表現することを目指した数学モデル。人や動物のニューロンは、ほかのニューロンから一定以上の刺激を受けると興奮し、つながったニューロンに電気信号を送ることで情報を伝達する。
ニューラルネットワークはこの仕組みを数値モデル化したもので、生物学や神経科学での同一ワードの使われかたと区別するため、人工ニューラルネットワーク(人工神経回路網、英: artificial neural network, ANN)とも呼ばれる。詳しくはこちらを参照。
世界で初めてゲームAIを専門に扱う会社・モリカトロン
──森川さん、お待たせしました。
森川幸人(以下、森川)氏:
よろしくお願いいたします。
 |
いきなり話がズレちゃうんですけどいいですか?(笑)
いま三宅さんの話を聞いて思い出したんですが、その昔、プレイステーションのブレイクのおこぼれで、僕の作ったゲームについてたくさん取材を受けていた時期があったんですね。でも当時って、AIについてどれだけ熱心に語っても、その部分だけ必ず全部カットされちゃっていて。
だからじつを言うと、誰も話を聞いてくれないものだから、ふてくされちゃって、AI関係の仕事はずっとほっぽらかしていたんですよ。
──今日は存分に語っていただければと思います(笑)。ただ、森川さんの仕事は、ゲーム業界よりもむしろアカデミズム方面で評価を受けている印象があります。
森川氏:
そうそう。AI学会や人工生命学会などからは、結構声をかけていただいていて。あとは、僕のところまでわざわざ話を聞きに来ていただいた熱心な方がいて。……それが三宅さんだった(笑)。本当に誰も話を聞いてくれなかったので、あのときは嬉しかったですよ。
三宅氏:
いやいや……そもそも森川さんの作ったAIに関する読みものって、当時は「ほぼ日」のコンテンツや、CEDECの短いインタビューがあるだけで、あとはすべて論文【※】なんですよね。
※論文
森川氏の論文や講演資料の多くは、株式会社ムームーのホームページ内、こちらの論文・講演の項からダウンロードできる。
でも当時はそうした論文がゲーム業界から現れたこと自体がセンセーショナルでした。僕はAIをゲームに応用しようとして2004年にゲーム業界に入ったのですが、森川さんのゲームだけがずっとお手本だったんです。
いまも「ゲームAIの開発をした経験を論文にしていく」ということを繰り返しているんですが、それは完全に森川さんの影響なんです。
「森川さんのように、自分の仕事を論文にすることで日本のゲームAIの歴史を作っていくんだ」という思いからなんですね。ゲームAI研究者の僕にとって、森川さんはヒーローなんです。だからお話を聞きに行ったのは極めて自然なことで。
──なるほど。そして、その森川さんご自身も研究をずっと続けており、現在は世界で初めてゲームAIを専門に扱う会社・モリカトロンを立ち上げられています。今日はそんなモリカトロンの中核メンバーにもお越しいただいているので、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか?
成沢理恵(以下、成沢)氏:
では私から。モリカトロンでは取締役を務めている成沢です。

もともとはスクウェア・エニックスに15年いて、『ドラゴンクエスト』や『ニーア』シリーズなどのプロデュースで有名な齊藤陽介さんの直属の部下としてプロデューサーをしていました。たとえば『ファイナルファンタジーIV』、『V』、『VI』のスマートフォン版や、『ドラゴンクエストの不思議のダンジョン』のモバイル版を始め、オリジナルタイトルなども作ったり。
いまはモリカトロンを始めとした、12社ほどのゲーム会社の役員や顧問をしています。
森川さんとの関わりは、入社後すぐの、齊藤さんがプロデュースしていた『アストロノーカ』の制作から始まり、その後継作である『コスモぐらし ~オンライン的野菜生活~』(2003年・PC)で齊藤さんから『アストロノーカ』の魂を引き継いでプロデューサーを務めたところからです。ですからもう何十年ものお付き合いですね。
──本城さんはどういったご経歴なのでしょう?
本城嘉太郎(以下、本城)氏:
もともと僕はゲーセン少年で、19歳のころに『ウルティマオンライン』や『ディアブロ』に出会ってしまってからはずっと「オンラインゲームを作りたい」と思い続けた人生で。

最初はフリーのプログラマーとしてサーバー構築をしたり、開発会社で5年ほど『バイオハザード0』などのコンソールゲームを作ったり、コナミの『S.L.A.I.』などのオンライン対戦部分のコーティングをしていました。
それからオンラインゲームを作るために起業して、大手メーカーさんのゲームタイトルを受託で作りつつ、自分たちでもガラケー初のフルボイス乙女ゲームを作ったり、mixiアプリやモバゲーのオープン化のタイミングで自社タイトルをリリースしたり、その後のスマホ時代はリアルタイム通信エンジンなどを提供したりしています。
……とまあ、そんなふうにプログラマーをかれこれ10年以上やっていたんですけど、気がつけば会社の経営のほうがプログラマ歴より長くなりまして。何より森川さんのファンだったこともあり、いまはお手伝いさせていただいています。
──なかなかにディープな経歴ですね。本城さんには森川さんから声をかけたのですか?
成沢氏:
ある晩、森川さんと私で話しているとき、ゲームAIの専門会社を作るにあたって「森川さんが研究をし、私がプロデューサーや営業、交渉をやるとしたら、あとはプログラムが解って、かつ信頼できる経営者がいないとダメだね」という話になり、その条件を満たす人で最初に思いついたのがこちらの本城さんでした。
夜中の1時ごろに「話があるんだけど」と本城さんを呼び出し、3人で集まって、その場でモリカトロンの立ち上げがパッと決まったんです。
本城氏:
最初、僕はアルバイト社長で「経営だけ見ます」みたいな感じだったんですけれど……(笑)。
成沢氏:
プロデューサーとしては、最初からどっぷり入ってもらう気満々でした(笑)。
 |
──(笑)。皆さんで立ち上げられたモリカトロンの話は、後半でじっくり伺えればと思います。
ゲームは「ほとんどやっていない」
──さて、ここから本題に入ります。
まずお伺いしたいのは、森川さんがあの伝説的なテレビ番組『ウゴウゴルーガ』【※】にCG担当として関わられていたことです。『ウゴウゴルーガ』って、3DCGのバーチャルスタジオを使ったりCGキャラクターの動きが会話と同期していたりなど、当時のCG表現の実験場としても機能していた、かなり尖った子ども向け番組ですよね。
※ウゴウゴルーガ
1992~1994年にかけてフジテレビ系列で放映された、子ども向けバラエティ番組。当時はまだめずらしかったCGで描かれたキャラクターたちが、ナビゲーターの子役たちとやりとりをする構成。
バラエティ豊かなCGはもとより、畳みかけるようなテンポの速さや、内容のシュールさなどで注目を集めた。森川氏はじめ、番組で使われたCGはAmigaで制作されたというエピソードは有名。
森川氏:
きっかけは、株式会社ポケモンの社長、石原恒和さんだったんですよ。
石原さんは大学時代のふたつ先輩で、すごくお世話になっていたんです。僕は彼の影響でコンピューターを知り、CGを始めた。とはいえコンピューターといっても、当時美大生だった僕にとっては「絵が描ける機械」でしたが(笑)。
 |
そういう経緯からコンピューターに触れていたので、『ウゴウゴルーガ』に至るまでずっとCGを描いていたんです。
その後ゲーム業界に関わったのも、1994年の35歳になってから。それもとくにゲームが作りたくてゲーム業界に入ったわけじゃなかった。それまでに遊んでいたゲームも『ゼビウス』と、あと『ドラゴンクエスト』ぐらい……という感じでほとんどやっていませんでしたから(笑)。
──ビデオゲームにはそこまで関心がなかったんですね。なぜそんな「ゲームに興味のない」森川さんが、ゲームを作ることになったのでしょう?
森川氏:
当時はプレイステーションの立ち上げの時期で、そのどさくさに紛れ込んだんですよね。
というのも、あのときはその少し前に登場した3DO【※1】の影響で「家電メーカーが出すゲーム機は……」という空気があり、PSは「ゲーム業界の人以外」に声をかけざるを得なかったみたいなんです。そういうわけでか声がかかり、ゲームを作りたいわけじゃなくても、業界にひょこっと入れちゃった。
実際に『せがれいじり』の故・秋元きつねさん【※2】、『バスト ア ムーブ』の田中秀幸さん【※3】、『びっくりマウス』のうるまでるびさん【※4】など、当時の『ウゴウゴルーガ』のメンバーもその後、ゲーム業界に流れて来たり関わったりしましたからね。
※1 3DO
1993年に発表された、32bitマルチメディア機の規格。同名の3DO社からのライセンス提供により、松下電器、三洋電機、金星電子(韓国)の3社がハードウェアを発売した。
もっとも早い1994年に発売された松下電器の3DO REALが有名。だがその約半年後にはセガサターンやプレイステーションが登場し、大きく普及しないまま終息している。
※2 秋元きつね
1968年生まれのCG作家。有限会社件(くだん)代表取締役。
1980年代後半にアーティスト平沢進のもとで学んだAmigaによるCGが、深夜の科学情報番組『アインシュタイン』(1990年・フジテレビ)に採用されたことをきっかけに映像業界へ転身。1992年の『ウゴウゴルーガ』を経て、1999年にエニックス(現スクウェア・エニックス)よりプレイステーション用ゲーム『せがれいじり』を発売。2014年に逝去。
※3 田中秀幸
1962年生まれのアートディレクター。株式会社フレイムグラフィックス代表。
多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業後、1992年の『ウゴウゴルーガ』や深夜番組『Flyer TV』(1998年・フジテレビ)内で放映されたアニメ『スーパーミルクちゃん』の監督・デザイン・原案などを手がけた。
※4 うるまでるび
夫婦(「うるま」と「でるび」)によるアーティストユニット。1992年の『ウゴウゴルーガ』を経て、2000年にソニー・コンピュータエンタテインメント(当時)から発売されたプレイステーション2用ソフト『びっくりマウス』では、企画・キャラクターデザインを担当。
また、2007年には『おしりかじり虫』を発表し、話題を呼んだ。
──PS黎明期の、ある種の猥雑な状況の中に紛れ込んだわけですね。ゲームを作っている最中に、そうした「ゲーム畑じゃない」というギャップは気にならなかったのでしょうか?
森川氏:
まったくありませんでしたね。
というのも当時の僕らは、プロデューサーがとにかくおだてて「アーティスト」として扱ってくださって、木に登らせてくれたんですよ(笑)。
ソニー・コンピュータエンタテインメント(当時)は、もともと音楽のソニー・ミュージックエンタテインメントが母体の会社だったから、完全に「アーティスト」と「プロデューサー」のような関係性でゲームを作っていたんです。
──そうした音楽業界の血筋から、現在に繋がる音ゲーの祖と言われる『パラッパラッパー』も生まれたわけですしね。まさに森川さんの作られたゲームがそうですが、あのころは従来のゲームの文脈に依らない異質なゲームが多かったように思います。
森川氏:
ただ、そうしたものづくりの雰囲気って、僕がフジテレビの深夜番組で『IQエンジン』【※】なんかに参加していた時代もまったく同じなんですよ。
それまでテレビは24時で放送が終わっていたものだったんですが、「景気が良くてもっと広告が取れるから」という理由で、当時は各局がちょうど放送時間を深夜まで伸ばしていった時代だったんです。
すると、いままで枠のなかった時間帯ですから、「誰が観るのか」、「何をするのか」、「どういう番組を作ればいいのか」……そういうことがまったく判らないわけです。
「だったらもう、みんなで楽しいことをやっちゃえ」というようなノリが、当時の深夜番組にはありましたね。それが最後には『ウゴウゴルーガ』のような子ども向け番組にまで波及していくわけですが(笑)。
※IQエンジン
1989年のフジテレビの深夜番組放送枠『JOCX-TV+』で放送されたクイズ番組。スタジオや司会はおろか、回答者もなく、ひたすら出題と正解発表をくり返すのが特徴。
とくに番組放送時期の前半は、のちの『レイトン教授』シリーズと同根となる『頭の体操』シリーズから多く出題された。
PSの立ち上げもまったく同じ雰囲気で、ソニーさん自体がゲームを作ったことがないし、寄せ集めたメンバーもゲーム経験がないから、みんなでなんとなく未経験のまま勢いだけでやっちゃえた。
深夜番組とまったく同じノリで、僕らの仲間はあのときゲーム作りに向かっていったんだよね。
──その猥雑さが当時は本当に目新しく、CD-ROMという新しいメディアとあいまって、「ああ、ゲームに新しい時代が来た」という実感に繋がっていたと思います。
マリオに「自力でクリアしてよ」と思っていた
──そうした経緯で、最初に手がけられたゲームが『がんばれ森川君2号』だったと。そもそも何がきっかけで「AIのゲーム」を作ろうと思ったんですか?
森川氏:
まず、「やらなくていいゲームを作りたい」と思ったんですよ。いまで言う「放置ゲー」みたいなものなんですが……当時は誰もそのコンセプトを解ってくれなかったんです。
20年前に「こういうのがやりたい」と言ったときは、会議室が凍りつきましたね。「何を言っているんだ、この男は」と(笑)。
──(笑)。さすがに「やらないゲーム」というのはいまでも衝撃的な発言だと思いますが、なぜそうしたものを作りたいと思ったんですか?
森川氏:
僕がそんなにゲームをやらないタイプだったから(苦笑)。
そういう意味で、僕がひとつだけずいぶん感心したゲームがあるんです。それは石原さんに勧められた『Little Computer People』【※】。
おっさんが画面の中に建てられた家で、ただ寝ていたり音楽をかけたりお風呂に入ったりトイレに行ったりするのを眺めているだけのゲームなんですよ。そうやって24時間、コンピューターの中の人がまるで生きているかのようにずっと動いているというのが、当時の僕には凄まじく衝撃的で。いま思うとまさに「やらなくていいゲーム」だったんですよ。

(By Scanned image from Little Computer People cover art, Fair use, Link)
三宅氏:
『がんばれ森川君2号』は『Little Computer People』の影響下にあった……腑に落ちるものがありますね。
※Little Computer People
1985年に米国・アクティビジョン社から発売されたゲーム。日本では、1987年にスクウェア・DOGブランドからファミリーコンピュータ ディスクシステム用シミュレーションゲーム『アップルタウン物語』として発売されている。移植に際し、元はおじさんだったキャラクターが女の子になるなどの変化はみられるが、基本的にはプレイヤーは何もせず、ただ生活する様子を眺めるゲームであるという本作の最大の特徴は共通している。
森川氏:
あと、僕は『スーパーマリオブラザーズ』をやりながら、「なんでいちいち最後のステージまで操作してやらなきゃいけないの? こっちはお金を払っているのに」と思っていたクチなんですよ(笑)。
 |
というのも、「World 1−1から1-3まで動かしながら、土管とは何か、亀とは何かということをずいぶんキミ(マリオ)に教えたはずだ。だから、後のステージぐらい自分でやってくれよ」という不満を持っていたからで。
そんなことを思っていた矢先に、何かの折に第二次AIブーム【※】の残り火のような記事を読み、「これだ!」と思って「AIを使ってキャラがパズルを解くゲーム」の企画書を出したら、あっさり通っちゃって(笑)。
※第二次AIブーム
1980年代に起きた世界的なAIのブーム。記号主義寄りになっていた当時のAIの潮流の中で、脳をモデルにしたコネクショニズムが復活を果たし、世界中の企業で「エキスパートシステム」(後述)が採用されるなどし、この時期のAI研究の中心は知識表現となっていった。
当時、日本政府が「第五世代コンピュータプロジェクト」という名目のもと、研究の場に積極的な資金提供を行ったことでも知られている。
──ゲームもAIも、そのときはまだ作ったこともないわけですよね?
森川氏:
それどころか、知識すらろくにないわけです(笑)。だからそこからの半年間は、ずっと数学の勉強をしていたんです。
まずは新宿の紀伊國屋書店で、当時まだひと棚の3段ぶん程度しかなかったAI関係の本をとにかく全部読んで。
ですからミーティングをするたびに「今週もAIのことを勉強しました」というような報告をずっと続けていましたね。
いまとなってはどうやって上を納得させていたのか謎ですが、僕に付き合わされたプロデューサーはたまらなかったでしょうね(笑)。
──(笑)。森川さんは芸術専門学群のご出身ですよね。すると数学を学んでいたのは高校までですよね?
森川氏:
ですから大変でしたね。AIは工学系の分野なので、高校とは数学の質が違うんですよ。
大学1〜2年あたりの多変量解析【※1】までやっていれば、ニューラルネットや遺伝的アルゴリズム【※2】など第二次ブームのAIまでは理解できるんですけどね。ちなみに、いまの第三次ブームのディープラーニングなどになると、大学4年の変分法【※3】が解らないと本質的には理解できなかったりします。
じつは、その後の『アストロノーカ』や『くまうた』も含め、アイデア自体はその半年のAIの勉強をしているあいだにすべて出ていたものなんです。結果的に作る順番があっただけの話で、着想はすべてほぼ同時なんですよね。
※1 多変量解析
ふたつ以上の変数からなる「多変量データ」を統計的に扱う手法。ニューラルネットは、多変量解析のひとつである、統計学で言う「重回帰分析」の発展形でもある。統計解析、ビックデータ解析では、基本的に多変量解析が中心的な役割を果たす。
※2 遺伝的アルゴリズム
1975年にミシガン大学のジョン・H・ホランドによって提案された、複雑な問題に対する近似解を探索するアルゴリズム。生物界の進化における遺伝と適者生存による自然淘汰の仕組みを模倣。多変量の解を求めるときに、多変数配列を染色体とみなし、遺伝の仕組みを使って解の空間を探索して行くもの。解へ至る関数が見つけにくい場合でも、純粋にアルゴリズムのみで解へと近付くことができる。
※3 変分法
解析学の一種で、値を最小あるいは最大とする最適な関数を求める方法。未知の関数であるが、条件を満たす関数を求めたいときに用いる。ヨハン・ベルヌーイが提示した最速降下曲線問題の解法として発展。 物理学の原理は変分の形で与えられる。
──つまり、AIというものを勉強しながら「これをどうゲームにしよう?」と考えて産み落とされたのが、『がんばれ森川君2号』、『アストロノーカ』、『くまうた』の3作品だったということですね。
森川氏:
そうですね。僕にとって「ゲームを作る」のは、「AIを使って何かしたい」ことに対する口実だったわけです(笑)。
──なるほど。